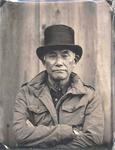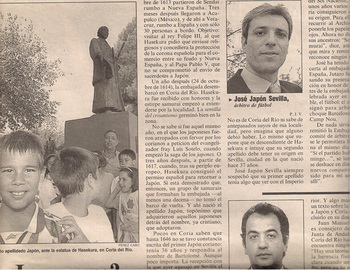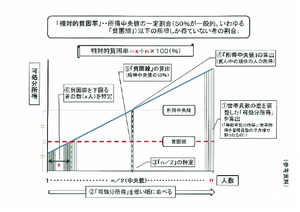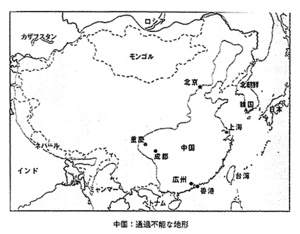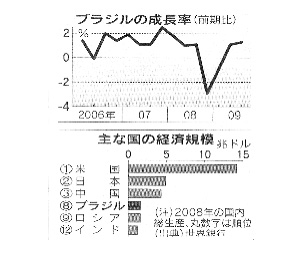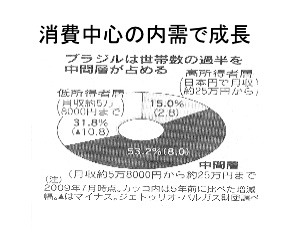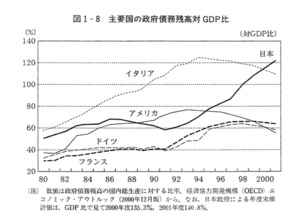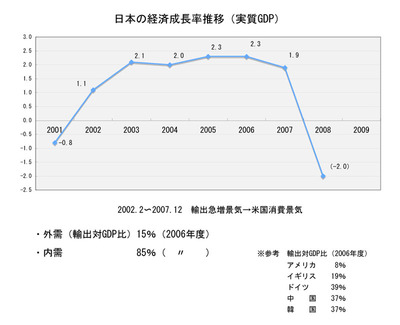2020年04月18日
シアトルのIT経営者から
Pacific Software Publishing, Inc.(シアトル)代表取締役社長 内倉憲一氏から次のアドバイスをいただきました。
危機
つい最近まで、誰もがこの数年間の経済成長を実感し、活気に満ち溢れていたと思います(トランプ政権への賛否は別として)。しかしながら、コロナウイルスパンデミックの影響を受け、今では未曾有の株価暴落の真っ只中にいます。レストランは閉まり、飛行機はキャンセルが相次ぎ、ホテルは空です。言うまでもなく、多くの人が職を失っています。職を失っても、命を守る方が重要だということでしょう。
私は、1987年に起業して以来、インターネット・バブル、サブプライム住宅ローン危機、9.11 を経験してきました。身近なところでは、シアトルのWTO抗議活動、データセンターの洪水、フィッシャープラザの電気火災などがありました。さらに言うと、ハッキング、DoS攻撃、ウイルスアタック、サーバーの故障などは常に起こり得ることで、我々は様々な危機に直面しては、その都度乗り越えてきたのです。
これらの危機から私が学び、心に留めていることを下記のリストにまとめました。
1. 危機が訪れた時、焦って決断をするのではなく、まず準備をします。私は、コロナウイルスパンデミックは予期しておりませんでした。
2. 現金を準備します。万が一の場合に備えた資金を準備しておくことで、パニックにならずに済みます。
3. 社員と密にコミュニケーションを取ります。社員と意見が合わないこともあるかもしれませんが、みんなから良い意見を引き出せるよう、話を聞き理解するよう努めます。
4. 冷静になります。リーダーがパニックになれば会社全体がパニックになってしまいます。あなたは舵を握る船長なのです。社員に焦っている姿は見せないでください。
5. 危機には終わりがあることを思い出します。意識を高く持ち、嵐が過ぎたあとの準備を始めます。
危機的状況にいるかどうかに関わらず、これらのことを常に意識するよう心がけています。「マーフィーの法則」や「ハインリッヒの法則」もその一つです。これらの法則について知らない場合は是非調べてみてください。
コロナウイルスの危機にも必ず終わりが来ます。その時の準備はできていますか?
2014年03月06日
2014年3月5日 山岡鉄舟が道徳教科書に
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2014年3月5日 山岡鉄舟が道徳教科書に
文部科学省「私たちの道徳」
2月は山岡鉄舟にとって素晴らしい出来事が続いた。
最初は文部科学省。2月14日に新年度から全国の国公私立小中学校に無償配布する道徳用の新教材「私たちの道徳」を公表したが、その中学二年生教科書の中で山岡鉄舟が取り上げられたことである。
今回の道徳教科書の配布は、従来の「心のノート」を全面改訂したもので、国内外の偉人伝などの読み物を盛り込み、ページ数を約1.5倍に増やし、いじめ問題への対応などのほか、「日本人としての自覚」を深める記述も数多く盛り込ませ、日本人が昔から大切にしてきた「美しい心」とは何かを考えさせる内容となっている。
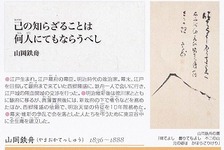
(1ページ全部鉄舟掲載の下段部分)
鉄舟は「2.人と支え合って」項目の「(5)認め合い学び合う心を」の中で「この人に学ぶ・人物探訪」として登場している。
更にうれしいことは、鉄舟の業績は江戸無血開城と明治天皇の扶育であるが、上記のようにほぼ妥当に記していることである。
江戸無血開城は西郷隆盛と勝海舟の二人で決めた?
実は、世上、江戸無血開城は西郷隆盛と勝海舟の二人で決めたと、流布されているのが一般的である。
その一例が、某教科書出版社から発行されている中学一年の道徳教科書である。西郷を「はかりしれない人間の大きさ」の人物として紹介しているが、その中で次のように記している。
「勝は幕府を代表して、総攻撃の中止を求めるため西郷に会見を申し入れ、両雄は、江戸城明け渡しという難局で再開しました。当時の思い出を勝海舟は『氷川清話』の中で次のように述べています。
当日のおれは、羽織袴で馬に乗り、従者一人連れたばかりで、江戸にある薩摩屋敷に出かけた。(中略) さて、いよいよ談判になると、西郷は、おれの言うことをいちいち信用してくれて、その間、一点の疑念もはさまなかった。
『いろいろ、むずかしい議論もありましょうが、私が一身にかけてお引き受けします』
西郷のこの一言で、江戸百万の人々の生命と財産とを保つことができ、また徳川家も滅亡を免れたのだ」
JR田町駅近く、都営浅草線三田駅を上がったところ、第一京浜と日比谷通り交差点近くのビルの前に「江戸開城 西郷南洲 勝海舟 会見の地 西郷吉之助書」と書かれた石碑が立っている。その石碑の下前面、向かって左側に「西郷と勝の会見画銅板」、真ん中に「この敷地は、明治維新前夜慶応4年(1868)3月14日幕府の陸軍参謀勝海舟が江戸100万市民を悲惨な火から守るため、西郷隆盛と会見し江戸無血開城を取り決めた『勝・西郷会談』の行われた薩摩藩屋敷跡の由緒ある場所である・・・。」と書かれ、向かって右側に高輪邉繒圖が描かれている。
実は、この銅板が問題なのである。画に西郷と勝しかいない。当日は鉄舟も同席していたのに、二人だけのシチュエーションとなっている。
さらに、神宮外苑の聖徳記念絵画館に掲示されている壁画「江戸開城談判」(結城素明画)の影響が大きい。

聖徳記念絵画館は、明治天皇・昭憲皇太后の御聖徳を永く後世に伝えるために造営されたもので、明治天皇のご生誕から崩御までの出来事を壁画として年代順に展示していて、その一つが左の壁画であるが、これによって二人の会見で江戸無血開城が行われたというイメージを醸成付加させた。
出版社に出向く
二つ目の素晴らしいことは、教科書出版社に出向き、以下のように説明したところ、修正印刷してくれることになったことである。
「貴社は、勝海舟『氷川清話』の『西郷と江戸開城談判』を引用され記述されていますが、これは明治28年8月15日の『国民新聞』の『氷川伯の談話(二)』に掲載されたもので、この時、海舟72歳。
海舟は、氷川神社のそばに寓居し77歳で亡くなりましたが、幕末維新のすべてを見聞き、かつ自由な隠居の身で好きなことを話せる男は海舟しかいなかったので、氷川の寓居に、東京朝日の池辺三山、国民新聞の人見一太郎、東京毎日の島田三郎らがしょっちゅう訪れて、海舟の談話を聞き書きした。それを人よんで『氷川清話』といいます。
吉本襄が大正3年に新聞連載を編集し直し、日進堂から刊行した『氷川清話』が有名ですが、吉本襄があやしげな換骨奪胎をしているので、江藤淳と松浦玲が編集し直し、さらに相当の補充をして、講談社から決定版ともいうべき『勝海舟全集』全22巻が出版(昭和48年)されています。
しかし、『氷川清話』の『西郷と江戸開城談判』は、『江戸無血開城』に至るまでの史実経緯をかなり省いておりますので、その史実について以下ご説明させていただきたい」
と述べ、次のような説明を行った。
「鳥羽伏見の戦いに敗れた徳川慶喜は、上野・寛永寺に謹慎し、和平の意を伝えるべく朝廷と縁故ある使者を何人も派遣したが、いずれも失敗。最後の手段として慶喜護衛役の旗本・山岡鉄舟に使者を命じた。
命を受け鉄舟は、軍事総裁の勝と初めて面談、慶喜の命令を伝え、直ちに新政府軍が充満している東海道筋に向かい、多くの危難を切り抜け、駿府(現・静岡市)で新政府軍参謀の西郷と会談を持った。
西郷からは和平5条件を示され、4条件は受け入れたが『慶喜公を備前藩(新政府軍)に引き渡す条件は絶対に受け入れられない。もし立場が逆であったとしたら、あなたは自分の主君を敵に引き渡せるか』と君臣の情からの鋭い論理と、決死の気合いによって反論、西郷を説得・約諾させ、ここに事実上の江戸無血開城が決まった。
江戸に戻った鉄舟は、直ちに慶喜と勝に報告、江戸市中に高札で和平成立を布告した。勝は日記で『山岡氏帰東。駿府にて西郷氏に面談。其識高く、敬服するに堪たり』と鉄舟を称賛した。鉄舟による駿府での西郷説得の前提があって『西郷と勝による江戸城無血開城会談』が成立したのである」
また、この歴史史実で使用した史料「海舟日記」と鉄舟直筆の「西郷隆盛氏と談判筆記」を示したことで、出版社はこの申し出を受け入れ、次回印刷文から修正するとの発言を得ることができた。
なお、「氷川清話」の取り扱いは慎重にすることが望ましいとも加えてお伝えしたところ、頷いてくれた。

ところで、写真の石碑は静岡駅近くの「西郷・山岡会見之史蹟」である。刻字されている文言は「ここは慶応四年三月九日東征軍参謀西郷隆盛と、幕臣山岡鐡太郎の会見した松崎屋源兵衛宅跡で、これによって江戸が無血開城されたので明治維新史上最も重要な史蹟であります」と、高さ1.5メートル、横幅は1メートルの御影石で、向かって右に鉄舟、左が西郷の顔が銅板ではめ込まれている。
歴史が、あるつくられたストーリーで語られ、そのストーリーが素晴らしいと、その方向へイメージが重なっていき、事実として巷間誤認されていく。
特に、教科書は子供にとって絶対的なものであるから、ここでの記述は慎重にしたい。
その意味で、鉄舟の文部科学省記述と、某教科書出版社の修正に満足しているところ。以上。
2014年02月22日
2014年2月20日 タイへの関心事・・・その三
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2014年2月20日 タイへの関心事・・・その三
東南アジアは足で売るのが成功の基
日経新聞記事(2013/12/3)を紹介したい。タイトルは「東南アジア、足で売る 味の素、自社社員5000人」で、この記事で分かるのは東南アジア地区における小売市場の全体網であって、この実態を日本人はあまり理解していないように思う。
近代的な大型店が急増する東南アジアだが、食品などでは零細店の比重は依然高く“足で売る”味の素の販売戦略は徹底していて、これが実に参考になる。
味の素は、東南アジアに約5000人の自社営業マンを抱え、庶民的な市場や零細店で1個十数円の調味料をコツコツと販売し、売り上げは年1500億円に伸びたという。
●野菜や
肉がずらりと並ぶ熱気あふれる売り場の一角、木材で手作りした店で味の素の現地法人社員、ナノ・スハルノさん(37)の営業が始まった。
●マサコの方がおいしいし、きれいだろ。ほら売ってみせるから。英蘭ユニリーバなどの競合商品をひょいとつまんで、目立たぬ場所に押しやった。
●店先に並べ始めたのはスハルノさんの営業の三種の神器。「マサコ(粉末)」「サオリ(液体)」「マユミ(マヨネーズ風)の調味料3姉妹だ。マサコは現地語で「料理する」の語感に、好感度の高い日本人女性のイメージを重ねたヒット商品。
●「さっさと売るのがコツだよ」と言う通り、スハルノさんは10分ほどの間に4人のお客をさばく。商店主も満足げで、次の発注を決めた。1日の注文件数で評価が上下するが、スハルノさんの給与は同年代の一般的な大卒ホワイトカラーを上回る。
インドネシアだけで、スハルノさんのような味の素社員の営業マンは1800人もいて、人が集まる市場で8万店を取り込み、郊外に散らばる零細店もローラー方式で取り込む。「ちりも積もれば」の作戦といえる。
食品などの業界では、こうしたルートセールスは卸業者や販売代理店に任せるのが一般的だが、味の素は違う。フィリピンで800人、タイで1200人といった規模の営業員が動く。同社は東南アジア地域で「新興国に最適の営業スタイルを武器に」2020年に4500億円の達成を狙うという。
タイ・バンコクの香水販売実態を見る
前号で紹介した「J.J Market」、犬売場の次に向かったのは香水店である。
ところでタイ人は首都をバンコクとは言わず「クルンテープ」と呼ぶ。正式な首都名は以下の通り超長く、タイ人でも全部言える人は少ないから、日本人がスラスラいうと尊敬されること間違いない。「クルンテープマハナコーン・アモーンラッタナコーシン・マヒンタラアユッタヤー・マハーディロッカポップ・ノッパラッタナラーチャニーブリーロム・ウドンラーチャニウエットマハーサターン・アモーンラピーンサティット・サッカタットタィヤウィサヌカムプラシット」
さて、「J.J Market」内の「Butterfly Thai Perfume香水店」は、屋台が密集している細道小路の奥にあり、間口一間程度の香水ショップで、ここが店だと紹介受ける。ビックリする。今まで世界各地の香水店を訪問したが一番小さい。
ここで社長と会う。まだ若い。六年前に創業。以前は洋服を取り扱っていたという。いろいろ聞いてみるとなかなかである。
●店舗は13店。全てオリジナル香水、自分で処方している。現在16品。来年新製品を出す。現行品の価格は859バーツ2750円。新製品は959バーツ3070円。ボトルを見せてくれる。ボトルの購入先は明らかにしないが中国製とのこと。なかなかデザインがよく、格調あるとほめる。
●匂いのティスティングしてみるが上品な香りで果物系が多い。そうしていると中年女性が来て、香水を5個買う。
●驚いて「ずいぶんたくさん買いますね」と日本語で聞くと、上手な日本語で回答が返ってくる。全然訛りなく日本人と同じ発音。これにも驚く。香水をどうするのかと聞くと「Xmasプレゼント用に買う」との答え。どこでこの香水を知ったのかと聞くと「友人からもらったので買いに来た」という。
この2750円や3070円という価格帯は高い。それなのにわざわざ「J.J Market」内に指名買いに来る実態を見て、ここの香水のレベルが分かったが、パンフレットはなく口コミとインターネット展開という零細店が、タイの香水販売では主流だと理解しないといけない。
日本企業は出張を取りやめている
日本で報道されているタイの政治デモ内容を見聞きしていると、治安が心配で危険と判断し、日本企業はタイへの出張を取りやめるケースが続出している。
ところで、タイの政治デモ報道は、バンコク中心街で行われているので、中心街に位置する大型商業施設の客が減ったことを伝えるが、一方、今回訪れた「J.J Market」にはデモが関係なしとは報道しない。また、政治混乱の影響を受けにくいリゾート地では、バンコクに代わって観光客が殺到し、ホテルの稼働率が大幅に上昇しているのが実態である。
トランジット・ポイント
人は変化することで成長するものである、といつも思っている。だから、何かの機会に「変化」に気づいたとき「楽しい」と感じることが多いが、この「トランジット・ポイント」を体験することが大事だと思っているし、その体験を記録化し、体におぼえさせ、必要なタイミングで発揮させるようにすることが、さらに重要ではないかとも思っている。
では「トランジット・ポイント」とは何か。それは「閾値(いきち)・スレッシュホールド」ともいうが、ある一定の感覚・知覚から反応が変わってしまうポイントのこと。
例えば、痒いとところがあるからといって、そこを掻きすぎると気持ちが悪くなり、刺激されすぎて「やめてくれ」という気持ちに逆転してしまうような変化点をいう。
又は、軽い冗談でも何度も聞かされると、逆に腹がたったりするのと同じだが、この「閾値・スレッシュホールド」をタイミングにうまく合わせ、コントロールしていけるようにすれば生活や仕事で結構役立つ。というより成功・不成功を分けるポイントになると思う。
情報とは何か
次に、マスコミ報道とは何かについて時折考えてみる必要があるだろう。マスコミ報道とは、本来、目立つもの、珍しいものを中心に報道するのを仕事としている。
今回のソチオリンピックで羽生結弦選手のフィギュアスケート金メダル、スキージャンプ男子個人ラージヒルの葛西紀明選手が銀メダルを獲得したが、これは一面で大きく取り上げられた。だが、他にも多くの選手がいるわけだが、成績が振るわないと片隅に小さく報道されるだけ。これがマスコミ報道の本質。つまり、金銀メダルを獲得したごく少数の人について大きく目立つように報道し、その他大多数の選手は無視される。
また、一般人が「朝起きて、朝食して、会社に向かった」という日頃の行動は報道しなく、それが今回の二週にわたる大雪で「できない・不可能」という状況下に陥った時、大きく・詳しく報道する。
火事の場合、例えば恵比寿駅前が火事で、消防車が出て消火活動をする時は、その事実を報道するが、これは当たり前のこと。しかし、報道されない一方の事実は「恵比寿駅前以外は火事ではない」ということで、恵比寿駅前以外は安全という主流の実態は何も伝えない。
これをタイの政治デモに当てはめれば、バンコク中心地帯、官庁があるところとか、伊勢丹があるような地区には行かない方がよいが、今回行ってみた「J.J Market」はデモと全く関係ない、とういう考え方ができるかどうか。それがビジネスでは必要で重要だと思う。
政治デモが発生しているバンコクへ社員を出張させようと思うならば、その前提として「考え方をチェンジ」しないといけない。さらに「考え方をチェンジ」するには、何かの「トランジット・ポイント」体験が必要で、加えて、この「トランジット・ポイント」体験・記録・体得化がなされていないと、マスコミ報道という一般的ではあるが限定された情報によって、自らの行動を抑制してしまうことになる。
なかなか難しいことではあるが、「トランジット・ポイント」体験を重ねて、それをセオリー化していくしかないのではないか。味の素が、東南アジアの実態をつかんで、足で売る商売をしているのは、どこかの国で味の素が失敗体験をして、それを記録化し、実際の営業に役立つよう変化させたからだと思う。行動する背景に考え方基準を持ちたいものだ。以上。
2014年02月07日
タイへの関心事・・・その二
大学教授にパリ情報を話す
先日、突然、ある大学の英文学教授から電話がありました。
「初めてお電話します。何々さんから紹介受けた者です。この度、パリの大学で一年間教鞭をとることになり、パリについていろいろ教えてほしいのですが」
「そうですか。雑談程度の内容でしたら、お話しできると思います」
ということで、さいたま新都心のレストランで昼食をとりながらお話ししましたが、ちょうど日仏合弁企業時代に秘書兼通訳をしてくれた女性が定年になり、一度、会いたいとと思っていたので一緒にどうかと声かけると、都合をつけて参加してくれました。
この女性はリオン大学卒で、パリで結構長く生活されたので、大学教授に実務的なアドバイスをしてくれました。
その中で参考になったのは「仕来りの違い」を受け入れるということでした。
① ドアを開け入る際、必ず女性を先にする
② フランス料理を一緒にしたら、最後にデザートをいかがですかと必ず声かける
③ 食事相手が女性ならば、水・ワインは必ず男性が注ぐこと
④ 洗濯物は必ず家の中に干す。外で干してはいけない
⑤ アパルトマンのエレベーター内で同乗者がいたら必ず挨拶する。しないと危ない人物だと警戒される
⑥ 商店に入ったらボンジュール Bonjourと挨拶した方がよい。しないとお金を払った後で嫌味たっぷりの発音で「ボンジュール」と返され、サービスに影響する
この他で強調したのは「家の内部の修理・修繕」は日本みたいにすぐに業者は来ないことと、各地というより全国的なストライキが年に何回か勃発すると伝えました。私は何度もストライキを経験していますが、フランス人に言わせると「リーダーが朝起きて『今日はストライキだ』叫ぶと、組織が一斉にストライキに突入する」という冗談が事実に近いという話ですから大変です。
全く、一般人の迷惑を考えない、というより迷惑をかけるためにストライキをするわけで、基本的な考え方が違っていることも「仕来りの違い」に入ります。
ストライキの体験話では、パリからニースに飛行機で移動したとき、ニース空港で乗車したタクシードライバーが、先ほどまで農民が道路封鎖していて、飛行機は飛ばなかったのだといい、明日も同じことが起きるから飛行機便は避けた方がよいとアドバイス受けたことがありました。
そこでその日のうちにニースでレンタカーを予約し、翌日の移動先のトゥルーズまで約500kmを走りましたが、このようにフランスではストとデモは常識といってもよいのです。
タイのデモ
前号でお伝えしたタイの政治デモに戻ります。
その後も続いていて、2月2日の総選挙は(下院選・定数500)は反政府派の妨害で投票が中止になる選挙区が相次ぎ、結果が確定できませんでした。インラック政権は選挙管理内閣として再投票などの手続きを進める構えですが、反政府派は続いてデモを行っており、政治空白が避けられそうもない状況で、タイ政局がどう展開するのか難しい局面となっています。
バンコクには昨年デモが発生し始めた頃の、11月14日(木)~17日(日)に行きまして、ホテルが市内中心地であったことから遠目でデモは見ましたが、特別の危険も感じませんでした。というより、デモはタイ人同士の争いで、外国人には関係ないわけですから、それを承知していれば、デモ隊の近くに行かない限り問題は発生しません。
だが、毎日マスコミ報道されるタイ政局の動きとデモ状況を読み見ていると、ちょっとタイには行く気がしなくなって、結果としてGDPの1割弱を担う主要産業の観光への影響は大きいでしょう。
その通りであって、タイ財務省は12月26日に2013年のGDP成長率予想は3.7%から2.8%へ引き下げ、2014年のGDP成長率も5.1%から4.0%に下方修正しました。また、総選挙が実施されない場合、来年の経済成長率は3.0%にとどまる見込みだとも発表しました。
JJマーケット
11月のバンコクで訪問したのは市内中心地区から、BTSまたは地下鉄で30分弱、北へ行ったところに位置しているJJマーケットです。
ここは地元タイ人のみならず世界中から観光客やバイヤーたちが押し寄せるウィークエンドマーケットで、タイ語で「チャトゥチャックJatujak」といいますが、これを省略して「J.J Market」とも呼ばれているところ。
ここでは全くデモの影響がなく1万以上もの店が軒を連ねるバンコク最大級ゾーン。ここでの買い物の魅力は、ほかでは売られていないオリジナルアイテムが多いので、そのセンスがバイヤーたちの目に留まり、お店が繁盛してくるとバンコクの中心部に品物へ卸をしたり、支店を構えるようになるという。
もちろんオリジナル以外にも、定番のお土産(象の置物やエスニック小物やバッグなど)を扱うお店もたくさんあり、バンコク市内のお土産屋やデパートよりも2~3割は安く買うことができる。つまり、タイ最大級マーケットであり、一大アミューズメントパーク並みに楽しい地区で、ここの銀行は土日営業です。
しかし、このマーケットは陽射しが熱い。日本の寒さが懐かしいが、そんな事を言っていられないなぁと思っていると、一人の若い男性が迎えに来てくれた。
迎えがないと込み入ったJ.J Market内は歩けないのです。彼は少し日本語ができる。彼の案内で屋台が密集している細道の奥に入っていくと、突然、可愛い犬の売り場があるではありませんか。
犬からわかる階級社会
その犬売場に行くと、昨年春に死んだ我が家の愛犬ビーグルが可愛い女性に抱かれているので、思わず写真に撮ってしまいましたが、実は、この犬売場がタイの階級社会を示唆しています。
タイの犬は三種類に分類されます。①家の犬、②お寺の犬、③道ばたの犬。いずれも放し飼いです。ということは勝手に交尾しどんどん子供を産むことになって、飼い主は面倒が見きれなくなると、日本のように市役所には連絡しません。どこへ持ち込むのか。それはお寺であって、お寺に犬を置いてくる。
その寺の犬は、お坊さんが托鉢で貰ってきたおこぼれを頂戴することになる以外は、暑いので一日中ごろごろ寝転んでいる。
ところが、お寺でも犬が増えすぎると厄介なので、時々、どこに捨てることもあるらしい。それらの相互作用で、③の道ばたの犬が多くなるが、大の愛犬家としても知られるプミポン国王の指示により、道ばたの犬も手厚く保護され、ワクチン接種や避妊手術などが行われているので、タイの犬は他国に比べると幸せ度が高いといえます。
ところで、J.J Marketの犬売場はこの三種類とは別世界に所属します。写真で分かるように日本のペットショップと同じく、世界の名犬純血種が並んでいます。本物かどうかは不明ですが・・・。これらの犬を買うのは大金持ちや特権階級の人たちであって、外へ散歩に行く場合はちゃんとリードで繋がれていくが、それは飼い主ではなくお手伝いさんの仕事になるという生活です。
これはタイの社会を示しているのです。タイは典型的な階級社会であって、頂点に大金持ちや特権階級がいて、次に経済発展に伴う中産階級がいて、それと長年政治から無視されてきた農民たちがいるわけで、犬もその階級社会通りの種類分けとなっているのです。
さて、政治デモはまだ続き、何らかの解決策をタイ人は自ら見出すまでには時間がかかります。ということは日本のタイとのビジネスも停滞するということになります。知人の企業もタイへの出張を取りやめました。社員安全を考えたのだと思います。
しかし、そのような対応でよいのでしょうか。次号でそのあたりを分析します。以上。
2014年01月21日
2014年1月20日 タイへの関心事・・・その一
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2014年1月20日 タイへの関心事・・・その一
昨年12月から今年の1月5日まで、3回のレターでお伝えしたウラジオストク状況、何人の方から関心を持たれた。ちょうど2月にはソチ冬季五輪が開催され、ソチ開催ではテロと人権問題が話題となっている。だが、隠れた大問題としてロシア人の無愛想、笑顔のなさ、おもてなしが欠けていることを指摘したことが、関心を持たれた理由と思っている。
今号と次号ではタイを取り上げたい。今のタイ、政治対立が新聞に出ない日はないほど毎日報道されている。今までに何回もタイに行った経験と、この対立が始まった昨年11月にもタイを訪問した体験を加え分析したいが、それにはタイという国を「見る眼」、それをタイの立場に置き換えなければならないと思う。
タイの政治対立

タイの政治が混迷のきっかけは、2013年10月31日にインラック首相(タクシン元首相の妹)率いる与党のタイ貢献党が、恩赦法の対象に急遽政治指導者を追加し、翌日11月1日に下院で強行採決したことからであった。
この法律の対象に国外追放されたタクシン元首相が含まれていたことから、反タクシン派はデモや大規模集会を開催した。結局、法案は上院で否決されて廃案となったがデモは収まらなかった。反政府のデモ隊はタクシン体制を打倒するまでデモを継続する姿勢を示し、財務省や外務省などの政府機関や国営タイ放送などの放送局を占拠した。そして反タクシン派のリーダーであるステープ前副首相が最終決戦とした12月9日、インラック首相は下院を解散することを表明した。総選挙は2014年2月2日に実施される予定。
民主主義は選挙で決まるのではないのか?
多数派であるタクシン派は選挙を通じた民主主義を重要視している。タクシン派の主な支持層は長年政治からほとんど無視されてきた農民である。タクシン元首相は2001年の選挙の時に農村支援を掲げて勝利し、首相に就任した後は農民債務モラトリアム、30バーツ健康保険制度などの積極的な農村振興策を次々に実施した。これらの政策の結果、農民の生活環境は劇的に改善した。こうして、農民は自らが政治に大きな影響を与え、それが自らの生活水準の向上に繋がることを自覚するようになった。
一方、都市部の中間層が多くを占め、少数派である反タクシン派は選挙をあまり重視していない。彼らに言わせれば、選挙をいくら行ってもタクシン派が貧しい農村部の住民を買収することで勝利するため、汚職と腐敗にまみれた政治家が誕生するだけであるという。
そのため彼らは議席の多くを医者、教員、弁護士、労働者等の協会の代表者から選出すべきであると主張している。
総選挙ではタクシン派が勝利するだろう
予定通り総選挙が行われれば、人口の半数以上を占める農村を支持基盤としているタクシン派が勝利する公算が大きく、タイ貢献党は総選挙の比例代表名簿第一位をインラック首相としていることから、このまま行けばインラック体制は継続する可能性が高い。
一方、反タクシン派は選挙ではタクシン派に勝てないと認識しており、選挙自体をボイコットしようとしている。また、ステープ前副首相は軍主催のフォーラムに出席するなど、選挙以外の手段で政権に揺さぶりをかけようとしている。
このように、両派の民主主義に対する考え方の溝は極めて深い。これまでも片方が政権を奪取すればもう片方がデモを行い、時には軍が出動して流血沙汰となることもあった。
今後も民主主義のあり方に対して両派が同じ認識を共有できなければ、タイの政治的混乱は終わらないのでないか、という指摘が多くタイの未来を悲観視する見方も多い。
だが、タイ人を分析していくと、今回の政治対立も何らかの解決策を、タイ人は自ら見出すと推察する。その推察根拠も含め、タイ人をいろいろな角度から検討してみたい。
タイの概要
最初は全般的なタイ概要である。
①国土面積 51.4万平方㎞、日本の1.4倍、フランスとほぼ同じ。
②人口6600万人(2009年)。
③タイ王国、現国王ラーマ9世(プミポン国王)王は圧倒的信頼あり。
④民族はタイ族が最大多数、中国系等で民族間の争いはない。
⑤9割が仏教徒・上部座仏教・・・輪廻の思想で前世からの業カルマによって今ここに生きていて、今の境遇を受け入れ、善く生きることで来世にはよく生まれ変わりたい。⑥タイ人が日本と聞いて浮かべるもの・・・ 富士山がトップ
タイのしたたかな外交力
日本とタイは長い外交関係があり、アジア諸国が欧米国の植民地化した地域の中で、お互い独立国としての地位を築いている。
日本は第二次世界大戦で無条件降伏、連合国の占領体制下に一時陥ったが、タイは日本の同盟国として、日本と同様に英米に宣戦布告したのに、敗戦国とはならなかった。
日本が開戦した1941年12月8日、日本軍はマレーへの侵攻を目指して、タイ・ビブン首相から駐留の承認を得てタイに上陸、この結果タイも、日タイ同盟から米英に宣戦布告した。
ところが、日本軍の旗色が悪くなったころには、対米公使を通じ米英とひそかに通じ合う関係を築きはじめ、終戦になるとタイは、米英に宣戦布告したのは、国民の意志に反して行われたもので、手続き的にも瑕疵があり、あの宣戦布告は無効だと主張し、これを連合国側が受け入れ、日本と道ずれの敗戦国にならずに済んだという経緯がある。また、現在も親米であるのに、北朝鮮とも外交関係を保持している、というしたたかな外交力を持っている。
頑張るという言葉はないが頑張れる
タイ人は日本人よりも明確な意志を持たないし、明確な意志を持って仕事や勉学に励まない。例えば、日本の来ているタイ人に来た目的を聞くと、留学生なら「たまたま奨学金がもらえたから」「日本語ができると仕事が探しやすいから」、働きに来ている人なら「お金が稼げるならどこの国でもよかった」「バンコクは暑いから日本の方がよい」「親戚がいたから」
つまり、具体的な目標や明確に意志をもって、日本に来ている人はめったにいない。
したがって、インタビューしても相手が具体的でないので、引き出しができないから内容がそろわないということになる。例えば、ムエタイ選手にどうして選手になったのかと聞くと「楽しいから」「友達がたくさんいるから」「バンコクに住めるから」「親から離れて暮らせるから」というもの。目標とはという問いには「お金を稼ぎたい」「有名になりたい」がほとんどで「チャンピオンになりたい」という選手は一人もいない。しかし、明確な意志や目標がないのに、頑張るのがタイ人。ムエタイの選手は毎日厳しいトレーニングを自ら進んで積むし、試合では信じがたいほどの闘志で相手に立ち向かう。パンチやキックを受けても苦しそうな表情を見せないでファイトする。タイ人は意志なぞわざわざ立てなくても、成りゆきまかせで、やるときはやるのである。これがタイ人の真骨頂で、タイ語に「頑張る」に相当する言葉はないが「頑張れる」のである。(参照「極楽タイ暮らし」高野秀行著)
微笑みが武器
タイは「微笑みの国」といわれる。顔の造作からいえば、さして美人でない女性でも、笑顔は素晴らしく、日本ではお目にかかれない笑顔がタイ女性の魅力であるが、その笑顔にもいくつかのパターンが隠されている。
つまり、ニュートラルな微笑みなのだが、そこに「タイの微笑み」の真実があって、微笑みはタイ人の表情の基本となっている。どういう反応をしたらいいのかわからない時、日本人はとりあえずシリアスな顔をするが、タイ人はその場合、とりあえず「にっこり」とする。別におかしなことがなくても、笑みを浮かべるのが、タイ人の常態であり、処世術でもある。これが外国人への武器となる。
タイを検討すると、面白くてやめられなくなる。次号でもタイ人を検討したい。以上。
2014年01月06日
2014年1月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その三
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2014年1月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その三
ウラジオストクの三回目・最終回です。今号の最後に2月7日から始まるソチ冬季五輪に向けて、昨年12月5日にお伝えした「微笑みのないロシア」、これに対する対策が必死に行われている状況が、NYタイムスに掲載されましたので、その内容もご参考にお届けいたします。
3.ウラジオストクの未来と日本
① ウラジオストクの歴史
ウラジオストクのある沿海州は、かつては中国の領土で、渤海や契丹、 金などがここを支配していた。
1858年、 アレクサンドル二世と清の文宗との間でアイグン条約(ウスリー江の東をロシアと清の共同管理地とする)が締結され、また、1860年には北京条約(沿海州をロシア領とする)が締結されて、ロシアの領土となった。
ロシアがウラジオストクの街建設を始めた頃、 日本は幕末から明治への移行期であり、中国では英仏連合軍が北京を占領という動乱の時代の始まりであった。
ウラジオストクというのはロシア語では「東方を征服せよ」という意味である。 ロシアは文字通りここにロシア海軍の軍港を築いた。
1891年訪日後の皇太子ニコライが帰途ウラジオストクに立ち寄り、シベリア鉄道の起工式が行われる。その後、 ロシア革命など、激動の時代を経て、1932年には、ソ連太平洋艦隊の基地となり、第二次大戦後は、 軍港であると同時に工業都市としても規模を拡大し、現在のウラジオストク市内の姿が形作られた。
ソ連時代は軍港として立入りを制限されていたが、1990年代に再び自由に訪問できる都市となり 海外からの大型客船も寄航する国際港になり、日本からは飛行機で約2時間という距離であるから観光客も増えている。
② 日本との関係
日本との関係について、ウラジオストクの極東連邦大学のモルグン・ゾーヤ教授の発表で紹介したい。(2012年4月13日 日本ウラジオ協会)
「最初にウラジオストクに来た日本人は1860年代に長崎から来た人たちです。大工(土木請負業者)やからゆきさんが多かったです。当時、ウラジオストクには建築が足りなかったし、ロシア女性も少なかったからです。からゆきさんと一緒に洋品店や理髪師も来ました。
1876年、日本貿易事務館が開設されました。そのとき日本の領事はロシアの軍艦に乗って来ました。1880年代に入ると、日本人の数は増え、約400名と記録に残っています。
1890年代に入ると、都市のインフラが飛躍的に発展します(91年にシベリア鉄道の沿海州地域が着工、93年に完成。モスクワとつながる)。街には日用品や装飾品などの商店が増えましたが、ウラジオストクは物不足のため、日本から多くの商店経営者が渡ってきました。日露戦争前の1903年には、3000人以上の日本人がいました。
日本との航路は、幕末から長崎、函館などにロシア船の入港があったが、明治政府になってから長崎港を拠点として、極東ロシア、中国、朝鮮への航路が整備された。
しかし定期航路が開かれたのは比較的遅い。ロシア義勇隊艦隊が1877年にオデッサから長崎経由でウラジオストクへの定期航路を開設したが、便数が少なく、神戸~ウラジオストク間は1899年(日本郵船)、ウラジオストクへの最短距離である敦賀からは1902年(大家汽船)に開通した。
日露戦争開戦後、日本人の多くは帰国します。貿易事務館も閉鎖されました。しかし、1906年には多くの日本人が戻ってきました。その一部は中国のハルビンへ行きました。当時、ウラジオストクには杉浦商店や徳永商店などに加え、銭湯や写真館ができ、日本人が経営していました。09年頃には日本人経営の精米工場やミネラルウォーター工場などもありました。
1914年、第一次世界大戦が始まりましたが、日露は友好関係にあり、この時期も日本人が増えました。17年にロシア革命が起こり、18年に日本のシベリア出兵が始まると、日本の軍人相手に商売する日本人も増え、5000人を超えるほどになりました。
1922年、シベリア出兵が終わり、多くの日本人が帰国しました。
1930年代に入ると、満州事変が起こり、以後、ウラジオストクは軍事基地にすることがモスクワ政府により決定されました。外国人は、日本人に限らず、中国人、朝鮮人も退去を命じられました。日本総領事館も1936年5月に閉鎖。
その後、日本人がウラジオストクに姿を見せたのは、1945年から53年頃まで、シベリア抑留者の労働キャンプが2つ置かれた時期です。彼らはスタジアムやビル建築、道路の改修工事の現場で働かされました。それから1992年までウラジオストクは対外的に閉じられた都市で、外国人は来ることができませんでした。
1992年に対外開放されて、93年に日本総領事館がナホトカからウラジオストクに移転し、開設されました。現在は、三菱商事や住友商事、三井物産などの商社やNHKの支局など、在留日本人の数は80名くらいです。まだ少ないですね」
③ 最近のロシア経済
今から10年前の世界経済を振り返ってみたい。2003年から06年までの4年間、世界経済の実質成長率は年5.1%と高率だった。常識的な考えでは3%台の成長率でまず順調という見方であるから大変な成長率であった。
世界の消費の中心は米国、加えて、中国、インドが10%を超える成長をし、ロシアも2006年実質成長率6%台を達成し、世界経済全体に大きく貢献した。
つまり、当時はBRICsの成長率が、世界経済全体に大きく寄与していたわけで、ロシアも石油や天然ガスの輸出収入で国内を潤し、資金力を拡大した企業が積極的な拡大戦略をとり、中産階級にも浸透し、個人消費が旺盛となっていた。
だが、今は変わった。2013年のロシア経済のGDP実質成長率は4月~6月が1.9%、7月~9月は1.2%となっているように、10前とは大違いの低迷状態である。
その理由は明らかで、北米発のシェールガス革命等によって、最大の石油などの輸出が落ち込んでいる上に、効率の低い古い企業が競争の少ない分野で優位に立っているので、労働生産性は日本大企業の3~4分の1といわれているほど低く、経済の構造改革・技術革新が進んでいないからである。

④ 地政学から考える
ウラジオストクは日本から近い。この地理的観点から考えると、日本はウラジオストクに進出することが有利であろう。
事実、過去に日本は何回もウラジオストクに足を踏み入れている。だが、それも政治的理由から日本は遠のき、現在もモルグン・ゾーヤ教授が語るように進出企業は少ない。
地理的に魅力溢れるウラジオストク、しかし、地政学的に見ると問題が浮かぶ。地政学とは二つの前提で成り立つといわれている。
⑴「人間は自分の生まれついた環境、つまり、周囲の人々や土地に対して、自然な忠誠心を持っている」という前提。
⑵「国家の性格や国家間の関係が、地理に大きく左右されると想定する」という前提。
再び、ここでガイドが述べた言葉を紹介したい。彼は無愛想で口数は少ないが、時折、鋭く指摘する。さすがに伝統と歴史ある優秀な極東連邦大学出身である
バスの中で「ロシア人と日本人とは異なる特徴を持つ。列挙すると以下の4点になる」と述べた。
A 個人主義であり、且つ、その個人主義のレベル内容も人それぞれ皆違う。
B 行動判断の基準はお金である。義理や義務意識は全くない。
C 今日は今日。明日はこうなるからという思考を持たない。
D 文化を失っている。ここが中国人と似ている。
このロシア人の特徴、地政学前提⑴から生じているし、日本人の特徴も同様であるから、必然的に人間としての違いが発生する。だから、お互いの共同作業は難しい。
それに⑵が加わる。それはウラジオストクの歴史からも明らかである。清から割譲された時は帝政ロシア、その後ソビエト連邦構成共和国体制となり、1991年崩壊しロシアに戻ったように、政治体制を激変させ、中心産業も変化し続けている。農業国家の帝政ロシア、工業国家を目指したソ連、一時成功し低迷しだした今の資源国家ロシア。
つまり、相手方が時代とともに変わっていくのであるから、日本側の対応は難しい。相手の変化はチャンスだという考え方もあるが、地政学観点から予測すると、日本がウラジオストクでビジネスを成功させ、それを長期的に維持するのは苦しいと予測する。
しかし、地理的には最も近い外国で、現地情報は集めやすいという利点はある。現地情報が的確に集められれば、短期的なビジネスの成功はあり得るし、ロシア政治体制が激変しなければ継続的ビジネスも可能であるが、そのためには定期的な訪問を行い、現地と情報ネットワークを構築することが前提要件だろう。
清話会がそのような仕組みを構築し、会員に情報発信できるかにかかっている。
⑤ ソチ冬季五輪対策は笑顔の特訓から
昨年12月5日号で紹介した北斗画像診断センターの美女、あの笑顔は特別であって、ロシア全体に笑顔がないのが一般的。ここで困ったのが2月7日開催のソチ冬季五輪である。
笑顔の特訓に入る前に、北斗画像診断センターの北斗病院が日経新聞(2014.1.1)で最先端病院として紹介された。
さて、話はソチに戻るが、世界中から人がソチに集まってくる。ところが、ロシア人の誰もが笑顔で迎えないとしたら、ロシアの評判は一気に悪化する。加えて、爆弾テロ事件や、人権問題で欧米首脳の欠席表明が相次いでいて、ロシア人気はそれほど高くない。だから、オリンピック開催では、何としても無愛想評価を改善したいだろう。
そこで現在、ロシアでは「おもてなし」特訓中とのことで、その記事がNYタイムスに掲載された。
「ロシアのサービスと言えば、社会主義時代の名残で、ぶっきらぼうで無愛想というイメージを抱く人が多いかもしれない。だが、それも過去のことになりつつあるようだ。
『アンナ、いまお客様に無言でシャンパンをお出ししたわよね』
教官の声が飛ぶ。ここはアエロフロート・ロシア航空乗務員訓練センターだ。
『それはソ連流の接客よ。言葉をかけて、笑顔を忘れないで!』
アエロフロートには美男美女の客室乗務員はいくらでもいるが、愛想のいい乗務員にはまずお目にかかれない------そんな定評を、同社は接客教育を徹底することで覆そうとしている。
こうした取り組みは、外食企業や販売業などロシアのサービス業界全体に広がっている。米コンサルティング会社マッキンゼー・アンド・カンパニーのロシア支社幹部はこう話す。
『顧客第一主義はロシアの文化に馴染まないと思われてきましたが、最近はどの企業も接客指導に熱心ですよ』
かつてロシアでは『意味なく笑うのはバカな証拠』と言われたものだ。それがいまや、スターバックスのバリスタは他国のバリスタ同様に眩しい笑顔を振りまき、マクドナルドの店員は完璧なスマイルで『ご一緒にポテトはいかがですか』と勧めてくる。中間層が増加して個人消費が活発化したことにより、ロシアでも顧客サービスの質が問われるようになったのだ。
2月のソチ五輪はその試金石となる。案内係を務めるボランティアスタッフは接客マナーの特訓を受けて本番に臨むという。合い言葉は『笑顔で親切に』。
ロシア流『おもてなし』、まずはお手並み拝見といこう」
プーチン大統領もいろいろ心配事多く、大変だろうと同情する。
以上
2013年12月21日
2013年12月20日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その二
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年12月20日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その二
1.ウラジオストク三つの見所
ウラジオストクは坂の多い街だ。 起伏の多い街のあちこちから海を望むことができ、街の中心部には19世紀末から20世紀初頭にかけて外国商人によって建設されたアールデコ調の洋館が多く残され、ヨーロッパの雰囲気を持っている。
街の散策はウラジオストク駅前広場からメインストリートのスヴェトランスカヤ通りを歩き、アルセーニエフ博物館、要塞博物館、 潜水艦C-56博物館、ニコライ二世凱旋門などが主な見所だとガイドブックにあるが、今回はバスで回ったので、筆者の見所はガイドブックと異なる。
我々のバスは、APEC開催を機会にインフラ整備が進んだ高速道路を走り、ルースキー島と結ぶ自慢の2本の橋を通り過ぎる。
1本目の金角湾大橋は海に面してコの字型に広がるウラジオストク市の内湾を、街の上にのしかかるように跨いで架けられたGolden Horn Bridge。2本目の東ボスポラス海峡大橋は2本の主塔から張ったケーブルで橋桁を支えるユニークな斜張橋で、世界最長の斜張橋といわれている。
。
だが、日本人として関心を呼ぶ見所は、この自慢の橋ではなく、以下の三か所と感じるので紹介したい。
日本人の心を打つ最初の見所は、シベリア鉄道の始発駅だろう。先の大戦でシベリアに抑留された日本兵士達が鉄道やビル建設に動員された。我々の先輩たちの汗と涙で造られたのであり考え深い。
駅はウラジオストクの街の中心に位置し、ネオロシア建築がすばらしい建物で、駅の向こうには社会主義革命を導いたレーニン像が建っている。
駅の中に入ると、天井画がすばらしく、大きな荷物を持った乗客が列車を待っている。ここからモスクワまでつながっていて、ホームの中央には「モスクワより9288㎞」と刻まれた石造りのキロポストが立っていて、ロシアの象徴である双頭の鷲が付いていて「まさにロシアに来た!という感じがする。
② 与謝野晶子の記念碑
次の見所は、極東総合大学東洋大学の入り口にある与謝野晶子記念碑だろう。
1912年(明治45年)5月、与謝野晶子が夫鉄幹を追ってパリに向った。500人もの友人達に新橋駅で見送られて東海道経由で敦賀に向かい、敦賀からロシア船でウラジオストクに渡り、シベリア鉄道に乗ってパリへ向かった。4ヶ月の欧州滞在の後、晶子はマルセイユから船で40日をかけて帰国したが、その与謝野晶子記念碑がウラジオストクにある。
この碑の前で、晶子が詠った激しい恋心に驚く人は多いが、実は、この碑にウラジオストクの現実が遺されていることを知る人は少ない。
それは、この晶子の日本語原文と解説が刻まれた二枚の銅版が盗まれていたことだ。1998年9月のことである。
この事実は何を意味するか。当時のロシア経済は厳しく、貧しい人は金になるものなら何でも得ようとしたわけで、無防備な石に貼られた銅は、格好の獲物であったことを示した事件で、また、この当時は下水道マンホールのふたも盗まれているように、ウラジオストクは問題多き街であった。
現在の晶子記念碑は2004年8月に修復されたものである。手がけたのは山梨学院大の我部政男教授。今度は盗まれないように、詩の原文などは碑に直接刻み、複製した銅板は極東大学の施設で保存してあるが、ここにウラジオストクの治安状態が現れている。
ウラジオストクの治安について、在住日本人がいろいろブログで述べている。一例を紹介する。
A 夜暗くなっての帰宅で、自宅の玄関先で殴られる⇒暗くなくても自宅の鍵を開けるときは、周りに要注意。
B 中央郵便局前のキオスクで買い物をした時から後をつけられる。
C 一時帰国中にアパートの電気製品などがごっそり盗まれた⇒玄関のドアは2重(1枚は鉄製のドア)になっていても、窓際の木をよじ登って窓から進入する。留守だということが知られると、狙われる。
ブログでの警戒警報はまだたくさんあるので、これから訪れる方は参考にされることをお勧めする。
③ 溢れる日本車
もうひとつの見所は「溢れる日本車」である。走っている車と駐車場の車の8割が日本車ということだが、そのほとんどは日本海側の港湾から積み出された中古車である。
複雑なのは、日本のメーカー企業が正規のルートを確立しているわけではなく、主としてパキスタン系の企業が日本国内の中古車を確保し、極東ロシアの受け皿企業を介して輸出しているという変則ビジネスモデルが肥大化したのである。
日本車の性能に対する極東ロシア市場の評価は極めて高く、特に厳寒の冬季に対応できる4WD型のランドクルーザーやプラドなどの車種への需要は強いという。一時、韓国車が攻勢をかけたこともあったが、市場の評価が日本車の優勢を決定づけた。
バスの中でガイドが補足する。市内を走る車の98%は日本車である。また、日本製そのままで右ハンドルのままの状態も多い。
いわれてウオッチングするとその通りで、メーカー別ではトヨタが多いが、ここでガイドが強調する。
それは、ソニーがサムソンに負けた要因についてである。
「日本車は、日本国内製と、サウジアラビア製では、明らかに性能が異なることをロシア人はよく知っている。ここが日本企業の問題点だ。サムスンはどこの国でも性能基準は同じだ。それがソニーの負けた理由。日本企業は日本人のためにつくる。サムソンは世界の人のためにつくる」
このガイドの指摘は鋭い。日本国内では聞けない貴重な見解と思う。
2013年12月11日
2013年12月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その一
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年12月5日 ウラジオストク視察旅行会に参加して・・・その一
今回のYAMAMOTOレターは、経営者勉強会・清話会主催のロシア・ウラジオストク視察旅行会(2013年10月23日(水)から26日(土)三泊四日)に参加し、様々な体験を通じ、以下の三項目について考えさせられましたので、三回にわたって送りいたします。なお、三回とも従来の三ページスタイルではないことをご了解のほどお願いいたします。
1. ロシア人には微笑みがないのか・・・12月5日号
2. ウラジオストク三つの見所・・・・・12月20日号
3. ウラジオストクの未来考察・・・・・新年5日号
1. ロシア人には微笑みがないのか
① ウラジオストクに着いて

事前に配布された資料に「ロシア人は笑わない」と書いてある。日本人はどちらかというと笑みを見せる顔かたちが多く、オリンピック招致で滝川クリステルの「おもてなし」プレゼンがその証明だ。
しかし、ロシアのスチュワーデスや入国係官は、絶対に笑わない。だが、それはサービス精神の欠如ではなく、仕事中は笑ってはいけない、と教えられているからだという。だから、仕事中のロシア人が笑わなくとも、無愛想だと思わないで下さいとも書かれている。
到着したウラジオストク空港、1999年開港、2012年APEC開催にあわせ改修し、なかなか機能的と思える中規模の空港である。日本でいえば広島か岡山空港といったところ。
出迎えの日本語ガイドの案内で、出口前に駐車しているバスに乗る。
早速に同乗した経営者の一人がガイドに質問する。「日本人はロシア人に好かれていますか」「好かれています」「中国人はどうですか」「それほどでもありません」
15分程で夕食レストランに着く。街道わきのハブみたいなところ。奥にパーティ用なののか、岩窟部屋みたいな個室があって、そこに座るとガイドが「飲み物は」と聞くので「ビール」と多くの人が手を挙げる。
ウェイトレスがサラダ、スープ、メインがオヒョウの蒸し料理とバターライスを次々と手早く運んでくる。結構うまい。この間行ってきたドイツよりもうまい。しかし、期待のビールがなかなか出てこない。ガイドが説明する。注文してからジョッキに注ぐので、時間がかかります。食事中盤には出で来るでしょうと。
ようやく現れたビール、グラスが様々な形をしている。そういえばスープ皿もそろっていない。総勢16名に対応できる容器が備わっていないのだ。
ところで、ここのウェイトレスは全員若く美人で、体の線が崩れていなく魅力的ラインであるが、全員口をしっかり結んで笑顔は皆無。ガイドが「テーブルで粗相してはいけないと緊張しているせいです」という。これは、その後入ったどこのレストランも同様で、笑顔のない、若い美人女性ばかりだった。
② 笑顔のない歴史的背景
笑顔がないのは以前モスクワに行った時も同じだった。美人が多いのに笑顔はない。この笑顔がないという背景、事前資料やガイドの説明通りだろうか。違うように思う。
かつてのソ連時代、グロムイコという外務大臣がいた。あだ名は「Mr ニェット(ノー)」であった。いつも表情を変えず、とりつくしまもなく、これがロシア人の代表的イメージとなっているように、ロシア人の無愛想顔は共通している。いわばロシア人の母型感覚、マザータイプといえるのではないか。少し長くなるがロシアという国の歴史から、その背景を検討してみたい。
ロシアにおける最初の国家は、ノルマン人(スェーデン人)の族長リューリクが862年に建国した時、それがキエフ公国となって、ビザンチン(コンスタンチノーブル)文化を導入し、農民達をロシア正教(ギリシャ正教)に帰依させ、教会に属させたが、ここで大事件が勃発した。
13世紀の始めにチンギス汗(君主)・モンゴル軍がやってきたのである。その勢力は西方に伸び、チンギス汗の孫バトゥ大汗の征服軍は、在来のモンゴル式騎兵のほかに、攻城に対しては、工学的方法による投石機その他城破壊機を用い、キエフのモスクワも破壊され瓦礫の山になり、さらに、西ヨーロッパまで侵攻したが、内部事情により軍勢を後方にひきあげ、ロシア平原に居座って、キプチャク汗(はん)国(こく)(1243~1502)を立国する。
ここからキプチャク汗国による「タタールのくびき」といわれる暴力支配が259年間続き、ロシア農民に対する搾りは凄まじかった。いくつもの貢税がかけられ、ロシア農民は半死半生にさせられた。反対すると軍事力で徹底的な抹殺を行うというやり方に従うしかなく、この当時、育ちつつあった都市文化や石工、鋳金、彫金、絵画、鍛冶職も連れ去られ、文化が根こそぎ絶やされるというひどい実態であった。
一方、この時期の西欧は華やか文化への幕開き時期だった。花のルネサンスが進行しつつあったこの時、ロシアでは「タタールのくびき」によって文化が閉ざされていた。
このことがロシアというものの原風景にある、という事実を見逃してはならないと思う。外敵を異常に恐れるだけでなく、病的な外国への猜疑心と潜在的な征服欲、軍事力への高い関心、これらはキプチャク汗国の支配と、その被支配を経験した結果であって、他人に笑顔を簡単に見せない、特に外国人には見せないというところにつながっていると推測する。
二日目の24日はルースキー島の極東連邦大学へ向かった。ここで日本語を学ぶ学生と懇談するためである。
極東連邦大学は、1899年にロシア極東最初の高等教育機関として前身が誕生、1920年に極東国立大学に再編され、ウラジオストク随一の総合大学となった。2010年には、 ロシアの8つの連邦管区に設置する連邦的意義をもつ国立大学「連邦大学」として、ウラジオストクの3つの大学、国立極東技術大学、 国立太平洋経済大学、国立ウスリー教育大学を吸収して極東連邦大学として生まれ変わった。
現在の学生総数は6万3000人。エンジニア、生物医学、人文、自然科学、 芸術文化体育、教育学、地域国際研究、経済経営、法学の9つの学部のほかに、ナホトカやユージノサハリンスクそのほかの極東都市、 そして日本の「ロシア極東連邦総合大学函館校」を含む10支部を含んでいる。
この大学で2012年9月のAPEC開催が行われたが、総敷地面積は80万平方メートル。キャンパスはアヤクス湾に沿って11の校舎が弓形に広がり、どの校舎の前面には海が広がり、一か所に集中したロシアの大学キャンパスとしては最大規模で、 ウラジオストクを極東の学術と教育の中心にしようとするロシアの意気込みが感じられる。
さて、この極東連邦大学のD建物、ここの日本語学科五年生の教室に行く。ここはエリート校で入学が難しいとのこと。入り口でガードマンが生徒一人一人カードを確認する。
日本語教室には五年生の学生が4人。先生は森さんという女性。いつも10人いるというが風邪とかで休みで少ない。
佐伯優税理士事務所長が生徒たちに「求められる人材」五項目を話し、学生に日本語を学ぶきっかけを尋ねる。答えは以下の通り。
A アニメから。セーラームーン、ワンピースなど。
B アニメとマンガから入って日本が好きになったため。
C 合気道六年経験し日本文化に興味あり。
D 日本の歴史に興味あり。
学生から質問が出る「日本では若い人の就職が難しいと聞いているが本当か」「そういうことはない。仕事はたくさんある。自分に合うものを探しているが、それを頭だけで考えているのでチャレンジしないのだ。二週間くらいで自分に合わない仕事だとやめてしまう傾向がつよいのだ」と佐伯所長。
4人がこれからの希望を述べる。
A 今、自分の夢を探しているところ。
B 日本語を使ってロシアで仕事したい。
C 日本に行って仕事したい。
D 性格が緊張しやすいので人と十分コミュニケーションがとれるか心配。
四人とも日本で三週間程度のホームスティ経験がある。
ここで、関西経営管理協会の鳥越理事長が「一年間はホームスティし体験してほしい。それがキャリアへのスタートだ」「ホームスティ先を探す組織としてロータリーとかライオンズクラブ等がある」と補足する。
日本語教師の森先生も発言「ここは伝統と歴史ある大学。卒業生は通訳等で活躍している」とガイドを指差す。
しかし、今のところ、ウラジオストクで日本語を活かした就職先がないのが現状らしい。
④ 笑顔はあった
午後は北斗画像診断センターを訪問。2013年5月開設。ここは北海道の社会医療法人北斗病院が、ウラジオストクの機関と提携して開設したところ。
北斗病院は、医療・福祉・介護サービスを事業としている全体人数881名(2013年4月)である。
この北斗画像診断センターは予防医療に位置づけられる。「健常者対象の脳ドックや心臓ドックを中心とした検診事業」「連携関係にある周辺医療機関から依頼を受けた患者の画像診断」という診療科目で、主要機器としては、血液検査器、心電図器、超音波診断装置、ABI動脈硬化測定、64列CT、MRI(1.5T)、遠隔画像診断システム 等。全て新品で機器が輝いている。敷地面積は638.93 平方メートル。
ところで、このセンター入り口から駐車場にバスが入ると、若い美人女性が立っている。ウラジオストクの若い女性は美人だらけである。
ところが、この北斗画像診断センターの美人、何と「満面の笑顔」である!!。絶対に笑わないというロシア女性がにこやかに迎えてくれたのだ。ロシア人でも日本人並みの笑顔ができるのだと感じる。
この笑顔美人女性、日本語が上手い。聞くと極東連邦大学出身。午前に聞いた学生の希望Bの「 日本語を使ってロシアで仕事したい」がここで実現しているのだ。
ということは、日本語を活かして就職すると、笑顔ができないロシア人も、滝川クリステルの「おもてなし」へ変身することができるということになる。
ウラジオストクの美人女性に笑顔をつくるためにも、今は少ない日本企業の進出を期待したいと思うが、経営者の皆さん、いかがでしょうか。
以上
2013年11月21日
2013年11月20日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(下)
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年11月20日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(下)
コペンハーゲンという街
前号に続いて世界一暮らしやすいコペンハーゲンを検討する。人口は52万人。名前はデンマーク語の"Kjøbmandehavn"(商人たちの港)に由来し、日本語では「コペンハーゲン」というが、これはドイツ語名をカタカナ表記したものであり、デンマーク語では「ケブンハウン」に近い。
コペンハーゲンには、城、公共建物、美術館など歴史的な建造物がたくさんあるし、市役所前広場からストロイエ通り、この通りは市庁舎前広場とコンゲンス・ニュートーゥ広場を結ぶ通りであるが、フレデリクスバーウギャーゼ、ニューギャーゼ、ヴィメルスカフテ、エスターギャーゼの4つの通りで構成されている。
ストロイエとはデンマーク語で歩くこと。市民や観光客の目を楽しませてくれるこの通りは、その名にふさわしい歩行者天国。道の両側にはさまざまなショップやレストラン、カフェが並び、路地裏には、中世の香り漂う重厚な教会や色鮮やかな家屋が並んでおり、そぞろ歩きが楽しい。
通りの中ほどにギネス・ワールド・オブ・レコーズ博物館 がある。入口に世界一の背高のっぽの人の像が目印だからすぐわかる。中に入らなかったが、ギネスブックに載っているさまざまな記録がひとめでわかる博物館である。ストロイエ通りの終点はコンゲンス・ニュートーゥで、ここに入ると自然にニューハンに足が向く。
ここはいつも大勢の男女が屯っていて、天気の良い日は足元にビール瓶を置いて会話に興じている。その傍らを、そのビール瓶目当ての男女が袋を持って歩いている。結構の人数が徘徊していて、気をつけないとまだ飲み残しがあるビール瓶が浚われる恐れがある。空きビール瓶を売ってお金に替える仕事であるが、何となく侘しく見え、これだけはコペンハーゲンの街並みのよさを傷つけていると感じる。
次の日の日曜日は朝から雨。昨日より12度低い14度。コートがいる。その雨の中、ホテルから歩いて地下鉄駅へ。乗車券はセブンイレブンで買う。一人24デンマーク・クローネDkk、1 Dkk =18円換算で1430円。結構高い。人魚姫の像の駅、エスターボートにすぐに着く。
駅から歩いて20分くらいかと、地図を広げていると親切にデンマーク人が教えてくれる。言われたように歩いて行き、公園内の道になったあたりから人が徐々に多くなっていき、その人々の回りをマラソンランナーが走っていく。今日はコペンハーゲンマラソンの日なのだ。モロッコの選手が2時間17分台で優勝したらしいが、一日中街中はマラソンで大賑わいであった。
さて、期待の人魚姫は公園を過ぎて、少し下る坂道の突端埠頭近くの岩の上に楚々として腰かけている。今までに何回も首が切断されたりする事件が話題なっているが、「世界三大がっかり」と言われながらも、コペンハーゲンの人気観光スポットである。
この人魚姫、足の先だけが魚らしくなっているだけで、ほとんど裸婦像と言ってもよいだろう。象をつくる際のモデルの足があまりにも綺麗だったので、作者が足をつくりたくなったのだというエピソードがうなずける。
人魚姫の撮影は結構難しい。理由の一つは、あまりにも観光客が多いことで、自分と人魚姫だけの写真を撮るには、タイミングが必要である。人がカメラを構えていても、お構いなしに人魚姫の前に立ってしまう男女もいるし、特に激しいのは団体客である。バスで来て、時間が限られるためか、一斉にやってきて、争うように撮影しまくるので、その間は茫然と見ているだけ。
もうひとつの理由は、後ろは海、手前は岩場で足元が悪いうえに狭いので、うっかりすると足を踏み外す危険性もあるからだ。ここで怪我すると厄介だ。救急車を呼ぶにも、コペンハーゲンでの手続きが分からないだろうから、とにかく、人魚姫では慎重な行動が望ましい。
ここで日本人女性一人旅に出会って、シヤッターを押してくれといわれた。ヨーロッパを歩いていると、時折、このような若き女性の一人旅に会うことがある。現在の境遇に飽き足らず、人生の転機を求めて結構長期の旅をしている女性が多い。場所を変えればある意味で転機になるだろうと思っているらしいが、結局、日本が一番住みやすいと気づき、戻っていく例が多いと思う。
nomaというレストランの存在
ロンドンのライフスタイル誌「モノクル」が毎年、世界の都市のどこがもっとも暮らししやすいかをランキングした内容は前号で紹介した。編集長のタイラー・ブリュレが選定基準を次のように語る。
「『本当に良い街』とは、一日の間にできる限り多くのことを気持ちよく体験させてくれる街のことだと、私は考えています。朝、子どもを学校に送り届け、買い物をし、仕事に出かける。そうしたことをスムーズにストレスなくできる街です」
これに異論はないが、私はもう一つ加えたい。それは食である。素晴らしいレストランがあることが「よい街」の重要要件であると思う。
その素晴らしいレストランがコペンハーゲンに存在している。それがクリスチャンハウン地区の「ノーマnoma」レストランである。途中マラソンのため渋滞で、世界中で都市マラソンの人気が高いと再認識しつつようやく「ノーマ」店の前にたどり着いたそこは、予想通り静かな寂れた海岸倉庫街にあった。
ここが、ここが世界でもっとも予約が取れないレストランといわれているところだ。
だが、今年の4月29日にロンドンで発表された「サンペレグリノ世界のベストレストラン50」、これは料理人や評論家ら900人の投票で選ぶものであるが、2013年はスペイン・カタルーニャのミシュラン3つ星「エル・セジェール・デ・カン・ロカ」が、3年連続で首位だった「ノーマ」を抑えて世界最高の栄冠を獲得したが、「ノーマ」の価値は下がっていない。
nomaとはnordic(北欧)と、食材を意味するmadを組み合わせているように、北欧の食材をテーマにしており、地元出身のシェフ、レネ・レゼッピは、まだ36歳という若さ。
予約が取れないのであるから、店に入れない、したがって、折角コペンハーゲンに行っても「ノーマ」を語れない。そこでデンマーク大使であった岡田眞樹氏の体験内容で補いたい。(魅惑のデンマーク 新評論2012年)
「これまでに行ったレストランのなかでダントツに素晴らしかった店がここ。周りは察風景なところだ。
夜のメニューは7皿のコース料理が標準だが、昼はその中から魚と肉とデザートの3品が選択できる。2品だと220クローナ、3品だと290クローナとちょっと高めだがワインをグラス程度にしておけば3品注文しても400クローナ(約一万円)ぐらいでどうにかなる。
座った途端に出てきた奇怪な料理に、まず驚かされた。ウェイターに聞いてみると、手前のものは干したタラの皮、右は揚げ物だが、飴色っぽい何かの魚を干したものでピリッと辛いスパイスがまぶしてある。ポテトチップ以外はすべて海産物、それも店の売り言葉のように『北欧の産品だ』と言う。この揚げ物、結構こくがあっておいしい。
次に出てきたのは、コース料理には含まれてはいない付き出し。これがまた奇妙というか、食べたことのないものだった。ライ麦パンと真ん中がクリーミーなチーズ、そしてライ麦の粉でつくった『スノー』だ。これが単なる粉ではなく、それこそサラサラした新鮮な雪を食べるような感触で、口の中でさくっと崩れて融ける感じともに冷たさがあった。クリーミーなチーズと一緒に食べると、口の中で融ける味わいは絶妙であった。
さて、ここからがようやくコースメニューとなる。・・・以下省略・・・『美味しい、美味しい』の連続で料理レポートとしては芸がないが、デンマークでこれまで食べた食事のなかではダントツに美味しかった。あくまでも軽く、淡泊で繊細なところに強い自己主張があり、日本人好み味と言える。店は『ノルディック・グルメ料理』を目指しているそうだが、その結果は、伝統的なデンマーク料理とは似ても似つかないものとなっている。何かの料理に似ているというよりは、まったく新しい方向を進んでいると思えるような品々であった」
この岡田大使の記述を読んで感じるのは、レネ・レゼッピが目指しているのは「美食」というよりは、もっとほかの方向を目指しているように思う。単純な「美味しい」を超えて、哲学的要素を含んだ最先端料理を作り上げようとしているのだと判断するのがよいと思う。
「サンペレグリノ世界のベストレストラン50」で日本勢は、東京南青山のフランス料理店「レ・クレアシヨン・ド・ナリサワ」が12位、東京・六本木の「日本料理龍吟」が20位に選出された。いずれも去年の順位より上昇し躍進しているが「ノーマ」との違いは何か。
その差を掴むためには日本の二店に行き食べ、それから再びコペンハーゲンを訪れ、何とか「ノーマ」を予約し食べることで、暮らしやすさ世界一の要因を理解したいと思う。以上。
2013年11月05日
2013年11月5日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(上
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年11月5日 世界で最も幸せな国、暮らしやすい都市(上)
第10回 日経・CSIS(米戦略国際問題研究所)シンポに参加して
10月29日(火)帝国ホテルで日経・CSIS(米戦略国際問題研究所)シンポジウムが開催され、1800名の参加者の一人として出席した。
テーマは「新時代の日米同盟・未来への助走」で、さまざまな見解が討議された中で、日米の同盟関係の強化策に関する討論では、参加者から事前にアンケートされた内容(下図)と、会場でも意見に賛成・反対への投票を含めた討論が大変参考になった。
ジョセフ・ナイ・ハーバード大学特別功労教授が「基地の共同利用をもっと増やすべきだ」と提言し、領土対立問題では、ナイ氏とアーミテージ元国務副長官が昨年9月の沖縄県・尖閣諸島の国有化について、東京都が購入するよりも賢明な判断だったとの意見で一致した。
また、ナイ氏は「日本が尖閣諸島を環境保護区と決めて、居住や軍事利用をしないと宣言する」アイデアを披露し「主権と倫理の両面で中国より優位な立場に立つべきだ」と語ると、多くの参加者から拍手が起きたのが印象的だった。
北方領土問題では、事前の参加者へのアンケートで約8割が「四島一括返還でなくても支持する」と答えに対し、アーミテージ氏は「米国は日本の立場を一貫して支持してきた。ロシアとの返還交渉で、日本が満足する結果になれば、米国も満足するだろう」と語った。
なお、ナイ氏が「日本は中韓以外の世界から最も人気の高い国だ」と「ソフトパワーに優れた国であるから国際関係で自信を持って行動すべき」との主張に改めて共感した。
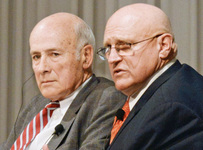
(左 ナイ氏 右 アーミテージ氏)
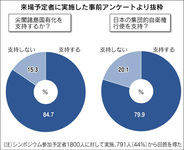
世界で「最も幸せな国」はどこか
現在の世界で「最も幸せな国」はどこだろうか。それはデンマークであり、米コロンビア大学地球研究所が調査し発表した世界各国「幸せな国」ランキングでトップを占めている(2013年9月CNN)
上位10カ国は以下の通り。
1.デンマーク 2.ノルウェー 3.スイス 4.オランダ 5.スウェーデン
6.カナダ 7.フィンランド 8.オーストリア 9.アイスランド 10.オーストラリア
この他の主要国では、米国17位、英国22位、ドイツ26位、日本43位と好感度ではトップクラスでも、幸せ度では中間となっている。
幸福度が最も低い5カ国はルワンダ、ブルンジ、中央アフリカ、ベナン、トーゴと、アフリカのサハラ砂漠以南に集中している。
デンマークという国
そこでデンマークという国の全体概要を見てみる。
① 面積は約4.3万平方キロメートル(九州とほぼ同じ・除フェロー諸島及びグリーンランド)
② 人口は約560万人(2013年デンマーク統計局)
③ 首都はコペンハーゲン(人口は約70万人、首都圏の人口は約120万人)(2012年末)
④ 言語はデンマーク語
⑤ 宗教は福音ルーテル派(国教)
このデンマーク、今でこそ世界有数の豊かな国家となったが、これは一朝一夕でできたわけではない。19世紀初頭のデンマークは、経済的に破綻し、領土も喪失して、実際に「貧しく、小さな国」であった。
そこからデンマークの人々は立ち上がり、土地改良ほか、さまざまな改革と努力によって、今日の恵まれた国を築き上げてきたのである。
現在の政治は、2011年9月の総選挙によって、10年に亘り政権を担当してきた自由党及び保守党による右派連立政権が敗北し、社会民主党を中心とする左派が勝利を収め、トーニング=シュミット社会民主党党首を首班(デンマーク初の女性首相)とする中道左派三党連立内閣が発足している。この政権は、移民には厳しく、仮に夫か妻がデンマーク人であっても、手続きが大変な上に、政権交代のたびに移民制度の内容が変わり、EU以外の国からの移民は特に難しい。消費税は25%。同性婚は昨年認められている。
有名な文学者はアンデルセン、哲学者はキルケゴール、スポーツでは自転車競技、ヨット、カヌー、ハンドボールが強いという。
世界で最も「暮らしやすい都市」はどこか
次に、世界で最も「暮らしやすい国」はどこだろうか。それはデンマークの首都コペンハーゲンである。ロンドンのライフスタイル誌「モノクル」が毎年、世界の都市のどこがもっとも暮らししやすいかをランキングしているのでみてみよう。
編集長のタイラー・ブリュレが選定基準を次のように語る。
「『本当に良い街』とは、一日の間にできる限り多くのことを気持ちよく体験させてくれる街のことだと、私は考えています。朝、子どもを学校に送り届け、買い物をし、仕事に出かける。そうしたことをスムーズにストレスなくできる街です。
犯罪の多いエリアを迂回すべきだろうかとか、自宅に泥棒が入っていないだろうかとか、そんな心配は誰もしたくないはずです。また、交通渋滞にはまって一日を無駄に過ごしたくもないですよね。そうした考えに基づきランキングするには、まず治安や交通の便、それに基本的なインフラや自然環境の豊かさといったポイントを重視しています」
コペンハーゲンを歩いてみて
コペンハーゲンには、2013年5月18日(土)にベルギー・ブリュッセル空港からスカンジナビア航空で入った。
ブリュッセルでは雨が降り、寒くて震えたので、ここより緯度が高いコペンハーゲンだから、もっと寒いだろうと予測し国際空港のカストロップ空港に着き、窓から外を見ると日光が燦々として26度もあるという。
ホテルでコペンハーゲンの地図をもらい、早速、街中を歩いてみた。日差しが熱い。ホテルで聞くと、今日は特別だといい、明日は雨だよとつけ加える。
コペンハーゲンには23年前の1990年11月に訪れている。当時の思い出を辿って、市庁舎の前に立つと何か騒々しくなっているような感じがする。
この市庁舎は1905年に完成した6代目にあたるもので、中世デンマーク様式と北イタリアのルネッサンス様式を取り入れた堂々たるたたずまいの建物。コペンハーゲンで最も高い105.6mの塔をもっており、コペンハーゲン市街を見渡すことのできる絶景スポットしても知られている。
だが、この街を一日半、歩いてみて感じたのは「やはり変わっていない」ということ。最初に騒々しいと感じた理由は分かった。市庁舎前の広場がイベントを開催するらしく、多くの関係者が慌ただしく動いており、そのための資材がおかれていたことから、そのように感じたのである。
23年前、この街は、歩いて観光するにちょうどよい大きさだと思ったが、今回も同じ感覚を持つ。
パリやニューヨークを歩いて動き回るのは厳しい。地下鉄やタクシーを使うことになるが、コペンハーゲンは地図を見ながらブラブラ歩くには絶好の街だと思う。
しかし、これだけでは世界一という評価は得られない。
もっとコペンハーゲンには何かがあるはず。それを次号でも検討を続けてみたい。以上。
2013年10月23日
2013年10月20日 計画された偶発性(2020への戦略)・・・その二
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年10月20日 計画された偶発性(2020への戦略)・・・その二
スポーツジムで
毎日、スポーツジムに行くようにしている。顔馴染みができ、自然に会話が進むことになって、お互いの生き方環境が分かってくる。
その中の一人、85歳の男性、白髪と見事な白ひげをたくわえた穏やかな人物。このジムでは最高年齢で、ジム開設時からの会員だという。いろいろ物事に詳しく、教えてもらうこと多く、次第に親しさが増していく。
ある日、何となく元気がないようなので「どうかしましたか」と尋ねると「家内が明日ガンの手術です」という。
「奥さんは何歳ですか」「もう80歳を超えていますよ」「どこを手術するのですか」「腹部です。大腸ガンの手術を既に二回受けていますが、それが転移したらしいのです」
一週間ほど経って「奥さんいかがですか」と尋ねると「退院して自宅で静かにしています」「手術は成功したんですね」「お陰さまで」「よかったですね」「手術はよかったのですが、このところの暑さで参っていますよ」「クーラーで調整するしかないですね」「それが問題で、クーラーが壊れてしまったのです」「奥さんのためにも新しいクーラーを買った方がよいのでは」「そうなんですが、もう少しで涼しくなるし、それと・・・もう歳だから・・・あと何年生きるのか・・・考えているのですよ」「うーん・・・」
お向かいのご夫婦
広い敷地に住むお向かいのご夫婦、ご主人は99歳、奥さんは95歳。ご主人を亡くされた長女が関西から戻って来て、一緒に住んでいるので生活は心配ない、と言いたいが、実は、ご主人は娘さんと一緒に自転車で買い物に行くほど元気。
奥さんもいたってしっかりしていて、インターホンを鳴らすと「ハーイ」と明るい笑顔で出て、記憶力もよく「先日はご馳走様」と旅行のお土産に対する配慮も忘れない。
この高齢ご夫婦、わが町の有名人で、目標とすべきご夫婦として、町民の憧れのもとであり、娘さんの同居が必要ないのではないかと思われるほどの健在ぶり。
先日、庭の茗荷を採りに来たら、という電話があったので伺うと、暑い中、奥さんと娘さん二人で新しい大きな物置前で汗掻いている。
「物置を買ったのですね」「そうなのよ。物が増えて必要になって」という隣には、もうひとつ以前からの物置がある。つまり、物置が二つ並んでいるのである。
このお宅、20年ほど前に建て替えし、その時の奥さんが挨拶に来た会話をよく覚えている。
「今度、家を建て替えすることにしました。いろいろご迷惑をおかけしますが、よろしくお願いします」「そうですか。ご立派なお宅を立てるのでしょうね」「いやいや、今より小さい家にするのよ」「どうしてですか。家財や荷物もたくさんあるでしょう」「全部、整理して少なくする予定なの」「へえー」「もう歳だし、あと何年生きられるか分からないから、そんなに大きな家は建てないようにします」「うーん・・・」
20年後の今、娘さんが同居し、孫が曾孫を連れて泊りに来るという状態になって「狭くて困るわ」が奥さんの常套語になって、新しい物置を買うことになったのです。
友人の経営者
友人の経営者、現在76歳。至って元気である。サラリーマンを60歳で定年となり、新橋に事務所を設置したという挨拶ハガキが届いたので、電話してみると「事務所を見に来てくれ」とのこと。
当方は、この友人より年齢的に後輩だが、定年前に独立したから、事務所経営としては先輩に当たるので、声がかかったのである。
早速、行ってみると「毎月一回事務所に来てくれないか。いろいろ相談したいから」という申し出で、昼頃に行き、昼食をご馳走になりながら、経営の状況を聞き、アドバイスという程でもないが雑談を長年過ごしている。
事務所独立当初の昼食は、近くのうどん屋。まずくはないが、それほど高くない普通の価格。このうどんがしばらく続いて、いつの間にか、今度はすし屋に昇格した。すし屋でも当初は「並み握り」そのうち「上握り」となり「特上握り」となった。
業容拡大したのか、新橋から愛宕山下の元焼肉屋ビル一階に移転したところ、このビルが東京都の再開発に引っかかり、立ち退きとなって、多額の補償金を受け取り、一気に財政は好転し、昼食はホテルのレストランへ格上げとなった
現在の取引先に、世界ナンバーワンブランド企業があって、そこへ部品を納入しているのだが、相手の大企業、頻繁に人事異動があり、その度に担当者が代わる。
世界各地に工場を持っているので、そこへ転勤するらしいのだが、その度に、不慣れな新担当者へ部品取り扱いノウハウを教えに九州まで出張している。
さらに、孫がオーストラリア・シドニーにいて、運動会だから「カム・ヒァー」と孫から電話があったので、成田から三泊四日で行って来て、孫がとても喜んでくれたと話す。
つまり、年齢を感じさせない元気人間なのである。
ところが、独立した当初は「70歳になったら、この会社を誰かに譲って引退する」と何度も公言していた。年齢をひとつの区切りとして考えていたのだ。
目的・目標を立てること
物事を進めるには目的・目標としての基準・物差しが必要である。基準・物差しを明確にしないま、何かを成し遂げようとして行動していると、いつの間にか時間軸の経過とともに、今、自分は、何のために「このようなことをしているか」という矛盾にぶつかり「そうだ、こんなことより別のことの方がよいのでは」と、全く新しい方向へ走っていくという事例が多いのではないかと思う。
ものすごく簡単な事例で恐縮だが、新幹線で大阪に行こうと思って、東京駅に来たら、この日は大阪行きの新幹線が全て満員となっている。そこで、大阪へ行くのをやめて仙台に行くことにした。要するに、目的・目標をお大阪から仙台に変化させたのである。新幹線に乗るという手段は変わらないが、目的・目標を変えてしまったのである。
そんなバカなことはしない。と殆どの方は思うでしょうが、ある会議で重要な議題があって、そこに参加しないと後に問題が生じる恐れがあるのに、会議メンバーに気が合わない、嫌いな人物がいるので出席しない、又は、代理を立てる、というようなことは日常割合あるのではないでしょうか。
この場合も、会議の目的・目標を基準にするのでなく、同席するメンバーの好き嫌いから判断する。つまり、条件から目的・目標を変化させてしまうという事例である。
年齢を目的・目標にしない
年齢を目的・目標にしないことが重要だと思う。
スポーツジムの85歳の男性の場合、年齢面から躊躇しているが、手術後の奥さんと自分の健康を目的・目標にするならば、クーラーを新たに設置したほうがよく、年齢を基準にしないようアドバイスしたところ。
お向かいのご夫婦、もう歳だからという理由で自宅建て替え規模を決めた結果、長寿で喜ばしいが、今度は「家が狭くて、孫と曾孫が可愛そう」という状態になっている。これも年齢を基準として物事を判断した事例。
友人の経営者の「70歳に引退」発言の都度「年齢で物事を決めない方がよい。目的・目標の達成で区切りを決めるべきだ」とアドバイスしてきて、今は年齢のことは一切言わなくなって、さらに、業容拡大に邁進しているので、今は、どのような企業スタイルにするのかを明確化、つまり、目的・目標を紙に書いたほうがよいとアドバイスしている。
オリンピックの招致成功
今回の東京オリンピック招致成功、様々な要因が語られている。
最も高く評価されているのは、9月8日のブエノスアイレスIOC総会における、日本側プレゼンター素晴らしい内容である。
その通りであるが、我々がオリンピック招致成功で学ばなければいけないものがあると思う。それは、このIOC総会のプレゼンまで持ってきた全体計画作りである。
前回のコペンハーゲンでの失敗、そこから客観的に冷静に問題点を追及し、その上で4年後の招致を成功させようと作り上げた計画作業を評価したい。
この計画作業が、ライバルのマドリードとイスタンブールとの差となって、9月8日のブエノスアイレスIOC総会に表現されたのである。
我々も東京オリンピック招致の成功に学ぼうではありませんか。
年齢を基準・物差しにしないと、三つの事例でお伝えしましたが、世界中が注目する東京オリンピック、そのビックチャンスを活用して、今回だけは2020年という時間軸に基づく年齢を考えた上で、自分はそのとき「何を目的とし、目標にしているか」を、アバウトでもよいから作ろうではありませんか。それが「計画された偶発性」を生むと思います。以上。
2013年10月06日
2013年10月5日計画された偶発性(2020年への戦略)・・・その一
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年10月5日 計画された偶発性(2020年への戦略)・・・その一
「2020」twenty-twenty
東京オリンピック開催「2020」の英語はtwenty-twentyとなり「正常視力の」という形容詞になる。視力1.0の人が20フィート離れて識別できる文字が、検査で実際に20フィート地点から見えるということで、よく見通せるという意味に捉えるとよいと思う。
だが、今からオリンピック開催年の2020年を見通すことは難しいだろう。先々、消費税をはじめとして予定された政策課題の推移と、想定できない出来事も多発するので2020年の戦略など出来るはずがないという意見になると思う。
しかし、時間の経過は正しく、時間軸通りに2020年は訪れる。そこで、そこまでの7年間、計画・目標をつくり過ごすのか、それとも出たとこ勝負で毎日を過ごしていくのか。その判断は自由であるが、我々の行動は気分・気持で決まっていくのであるから、先々の2020年には「こうなりたい。こういう状態にしたい」というイメージを持つか持たないかで、日々の日常行動が変わっていく。
折角オリンピック招致が決まったチャンスに、人生の価値を改めて捉えなおし、気分・気持ち再整理し、基準をつくり直し、積極的なたくましい方向へ転換させて行った方がよいのではないかと考える。さらに、計画をつくって行動していると、当初予想もしていなかった成功や幸運が訪れるという偶発性にめぐまれることが多いことは知られている事実である。
今号と次号では、2020年への戦略構築について触れてみたいが、まずは前回オリンピック開催都市ロンドンの変化を確認したい。
ロンドンは変わった
2013年7月、ヒースロー空港「ターミナル5」に着いた。ここは2008年3月開設のBA専用で新しく気持がよい。さて、入国審査に向かったが、ここヒースロー空港の入国審査はかなり厳しいことを思い出す。今まで何回もここで入国審査を受けたが、不法入国ではないかと、最初から疑ってかかる目つきでの対応で、気分が悪くなる空港の代表であった。
ところが、今回は違った。妙に愛想がいい。カウンター内の中東系と見られる若い男性がニコニコ笑顔で尋ねてくる。職業を聞かれ、答えると、パンと判を押しパスポートをこちらに返してくれる。これだけで終わった。
随分、変わったものだと思い、ロンドンに長く住む人に聞いてみたら、2012年のオリンピックを機会に、入国手続き業務を民間企業に委託してから、全くよくなったのだと笑う。
ヒースロー・エクスプレス
バックを持ってロビーに出ると、少し先の何となく品がよい表示が眼についた。近くに行ってみるとヒースロー・エクスプレスである。
ああ、これがあの便利な列車かと思いつつ、乗車券代20£をカードで払う。ヒースロー・エクスプレスは、ヒースロー空港とロンドンヒの主要ターミナル駅のひとつであるパティンドン駅との間を、日中15分間隔、所要時間21分でダイレクトに結んでいる。 2009年11月時点での定時運行率は99.9%とロンドンの地下鉄と比べて高い。最高時速160km、車内は十分な座席と荷物置き場が確保されていて快適で、最も速くロンドン市内へアクセスできる。
パディントン駅に着き、右手側のなだらかな坂を上がると、宿泊するヒルトンホテルである。パディントン駅とヒルトンホテルを利用すると、ヒースロー空港から25分でホテルの部屋に入れくつろげるのだ。大変身である。
今や世界一という評価
それを証明するのが「2012年・都市総合ランキング」(森記念財団調査・日経新聞2013.9.14)で紹介されたにロンドンの第一位というランクである。オリンピックをチャンスに都市整備を進めた結果である。
東京は第四位、2020年には一位になっていることを期待したいが、ロンドンが評価された背景に日本の鉄道技術が存在することを認識したい。

日立製列車の貢献
今回、イギリス国教会の総本山であるカンタベリー大聖堂があるカンタベリー駅から、サウスイースタン鉄道でセントパンクラス駅まで乗ってみた。このサウスイースタン鉄道の車両が日立製なのである。

日立は2009年から「ジャベリンJavelin」の名で知られる高速列車Class395を製造、冬季に他の列車が全てストップした際も、運行を続けるなど高い信頼性が評価されて、2012年8月には英国の鉄道インフラを管理するNetwork Railから、英全土への導入に向けた運行管理システムのプロトタイプを受注し、日立が英国で受注した車両は計866両となり、受注総額は58億ポンド(8800億円)にのぼり、日本企業が海外で受注した車両数としては最大である。
さらに、日立は車両の製造と併せて27年半の保守を行うのであるが、これには日本の鉄道が誇る「時間通り」「事故を起こさない」「プラットホームの指定位置に停車」「環境に優しい」などで高い評価を受けたという背景がある。
昨年のロンドンオリンピック、セントパンクラス駅からメーンスタジアの最寄り駅のストラトフォードまで7分で直通運転したのも日立製ジャベリンで、マスコミ陣から渋滞によるロスもなく、時間通りの取材が出来たと高い評価を受けた。
この日立製列車のイギリスへの導入、長期戦略・目標の最適例ではないだろうか。
失敗から学ぶ
2020年東京オリンピック開催が決まって、猪瀬東京都知事は次のように語っている。
「東京に五輪を招致できて、心が晴れ晴れしている。スポーツの力で何年も失われてきた日本の活力を取り戻し、心のデフレを払拭できる。だが、僕自身が考えてきた真の招致成功の意味は、世界最高のスポーツの祭典を東京で開く栄誉や、東京、日本の力を世界に示す好機という以上に、日本の構造改革をスタートさせられることだ。
五輪は開催そのものが一つの目的ではあったけれど、それがすべてではない。五輪を一里塚にして、日本全体を変えていく、というのが僕の発想だ。最も大きいのが縦割り行政の解消、省益至上の官僚主義の解消だと思っている。
今回の招致成功で僕は何度も『オールジャパンの勝利だ』と言ってきた。経済界、スポーツ界のほか、五輪を担当する文部科学省、パラリンピックの厚生労働省、外交交渉を担う外務省、それに宮内庁、内閣。特に役所では、それぞれが管轄するピラミッド型の行政システムが、過剰な縄張り意識を生み、互いに情報を隠し、国家戦略として『何をしたいのか』がさっぱり分からない状態が続いてきた。
復興庁が有効に機能していないのは縦割りの弊害そのものだし、さかのぼれば太平洋戦争突入の決断だって、その最たるものだ。
僕は著書『昭和16年夏の敗戦』(中公文庫)で東條英機内閣が開戦直前、ひそかに省庁や陸海軍、民間の若手エリートを横断的に集めて日米開戦のシミュレーションをさせた総力戦研究所の姿を描いた。それぞれが組織の資料を持ち寄って分析し『必敗』と結論づけた。だが、報告は握りつぶされて戦争回避につながらず、戦況はほぼ分析した通りに推移した。縦割り官僚国家の中枢がまったく機能しなかったわけだ。
それが今回、五輪招致で、できた。情報を共有し、一つの目標のために力を合わせた。日本の中枢が機能を取り戻し、国家として勝った。
僕が言ったオールジャパンとはそういう意味だ。大げさでなく、近代日本史上、まれにみる快挙だった。中枢が機能すれば物事は前に進む。被災地で、福島原発で何をすべきで、どう動けばよいか。招致成功は意思実現のモデルになったはずだ。あとは成功の経験を、官僚がどう生かすか、だ」
(中日スポーツ2013年9月21日付の連載コラム「月刊猪瀬直樹」より)
その通りだが、見過ごしてはならないことがある。オリンピックの招致成功から学ぶべき、全ての組織・個人が参考にすべきセオリーのことである。次号でお伝えしたい。以上。
2013年09月20日
2013年9月20日 日本は「つなぎ・絆」大国(下)
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年9月20日 日本は「つなぎ・絆」大国(下)
サッチャーイズムでの祭り開催
前号でお伝えしたウィスタブル牡蠣祭りの始まりは1985年、マーガレット・サッチャー政権下。第二次世界大戦後のスローガン「ゆりかごから墓場まで」によって「英国病」となり、マーガレット・サッチャー政権下で経済立て直しへ大転換、以後、今のイギリスがあり、ウィスタブル牡蠣祭りも存在する。
そのサッチャー氏、7月8日に87歳で死去し葬儀が7月17日、ロンドン中心部のセントポール大聖堂で、1965年のチャーチル氏の国葬以来の、エリザベス英女王の出席と、国内外の要人ら約2300人が参列、1千万ポンド(約15億円)という葬儀費用を要して国葬が営まれた。
サッチャー氏は、国を開いて海外マネーを呼び込む金融立国で成長を実現し、貧富の格差は開いたが、経済優先という国造りでの貢献をイギリス政府が国葬という形で認めたのである。これと同じくウィスタブル牡蠣祭りも地元経済の発展に開催されている。
洲崎神社祭り
一方、日本の祭はどういう実態なのか。日本には各地に多くの様々な祭りがある。町おこし、地元経済対策を目的とした祭りも多いだろうが、これらとは一線を画す祭りもある。
そのひとつが千葉県館山市の洲崎神社祭りで、2013年8月21日(水)に訪問してみた。
館山市は、千葉県房総半島の突端南部に位置し、歴史的には房総半島の戦国大名"里見氏"の本拠地であり、神社仏閣が多く、市内各地において催される祭りが数多く、内容も多彩であることで知られている。この館山市、通常の日本地図ではなく南北逆さにしてみると、弧を描く日本列島の頂点に位置していることが分かる。見方を変えれば館山は日本の中心ともいえるだろう。

館山駅に行くには東京駅からJRと高速バスがある。洲崎神社は、館山市の最西部、海にせり出した岬の突端に位置している。東京湾を航行すると、この岬を境に海の姿は一変し、広大な太平洋へと視界が開け、沖合は潮の流れが速い海上交通の危険個所で、沖を通る船は海上安全を祈願して洲崎神社を篤く信仰、その信心は東京湾内に広がった。
洲崎神社本殿・拝殿へは、勾配30度急坂147段の石階を上る必要がある。一気に上るのは息が切れ、途中で一休みが必要となるほどである。15時、拝殿前には白丁(はくちょう)姿の若衆と、見物の客が集まる。
神社は御手洗(みたらし)山の中腹にある。中腹の神社拝殿から見渡す海の景観は絶景で、その境内に白丁姿の神輿担ぎ手が集まり、宮司からお祓いを受け、いよいよ神輿担ぎを始めた。
まず、拝殿前の境内を何回も神輿が勢いよく揉み回る。見物客も神輿の勢いに押され隅の方に追いやられるほどである。
ここで疑問を持ったのは白丁姿である。今まで各地のお祭りで見た神輿担ぎ手の衣装は半纏、腹巻、股引、足袋であった。ここは全員白丁姿。
この白丁とは何か。ハクテイともいうが、古代律令制のもとで、公の資格を一切持たない無位無官の一般男子が着用したものであり、神事や神葬などに物を持ち運ぶ人夫をいう(広辞苑) とあり、祭りでの衣装として館山の祭りで定着している。
さて、拝殿前の境内を何回も勢いよく揉み回った神輿は、いよいよ勾配30度の147石階段を降り出す。普通に降りても危ない急勾配、そこを重い神輿を担ぎながら、それも左右に揉みだして、下がるのであるから、白丁の担ぎ手は必死の形相、見ている方もハラハラ、洲崎神社祭りのハイライトである。
神輿は拝殿前での揉み時間を含め、約30分かけて石段を降り、随身門をくぐり、そこで一旦休憩する。今日の気温は34度。白丁姿から汗が滴り落ち白衣が皮膚にまとわりつく。
再び、リーダーのかけ声で、今度は浜辺へ神輿が渡御するため動き出す。浜辺の鳥居をくぐったところで、再び、神輿を休め、全員お神酒で乾杯。無事に渡御できたことを祝い、海に対する感謝の神事を行うための準備でもあり、宮司がいよいよ米とお神酒をお払いしながら海に向かう。この一瞬のために大勢の白丁姿が大汗を掻いて神様を神輿に乗せてお運びして来たのである。時刻は16時を過ぎ、夕陽が沈み始めた。ここまで約1時間10分要している。
厳かな儀式を終えると、再び、147段上の神社に神輿を奉納するため、大勢の白丁姿が担ぎ始める。見ていると海に面した鳥居に入る前の道路、そこで揉みだした。なかなか鳥居をくぐらない。もうくぐるかと思うと引き返し、左右に動き揉み回す。 見ている方が焦れるほどの時間を要している。ようやくリーダーのかけ声で鳥居をくぐり、随身門を通って147段の石段を上っていき、無事、神社本殿前に到着した。17時半である。
怪我人もなく洲崎神社祭りは終了し、白丁姿のまま、ということは汗をかいたままであるが、社務所の広間で直会(なおらい)である。寿司や鶏のから揚げ、サラダなどが大盛りで出され、リーダーから「お疲れ様」の挨拶とともにビールで乾杯。
その輪の中に入れていだいて「大変だったでしょう」と声掛けると、すきっとした笑顔が頷き「でも、楽しかったですよ」と語る。これが本音だろう。その証拠に全員の眼が澄んで、眼差しに満足感が漂っている。 あの鳥居の前で随分時間をかけて揉んでいましたね、と一人に尋ねると「あぁ、あれは神様と一体化する儀式で、憑依(ひょうい)ですよ」とさりげなく語る。 これにはビックリした。思わぬ言葉が出てきたと思う。憑依とは、霊などが乗り移ることを意味し、一種のトランス状態ともいえるが、洲崎神社祭りの白丁姿の若衆から憑依ですよと聞くとは思わなかった。
神輿を担ぐことで、神を意識しているのだ。日本人しか分からない感覚だと思うが、そのような純粋な気持・心理が一人ひとりの白丁姿に横たわっているのだ。
穏やかに直会が続く中、数人の白丁姿が「今日はありがとうございました。これで失礼します」と席を立つ。聞いてみると東京の品川から来ていて、これから帰るのだという。今日は会社を休み参加した。洲崎の方も品川の祭に来てくれるので、そのお返しで来たと、当然のごとくに語る。
リーダーが話してくれる。この洲崎神社祭りも地域人口減で、地元民だけでは開催できなくなっている。隣の坂東地区からも手伝いの担ぎ手が来てくれているように、各地との神輿つなぎネットワークがこの祭りを支えてくれているのだという。
そうなのか。洲崎神社の祭りは各方面からのつながり、それは祭り神輿を通じた関係ネットワークによって今でも昔通りの祭が催すことが出来ているのだ。
そういえば、この洲崎祭りにはビジネスの匂いのかけらもない。この祭りで町おこしをしようとするのではなく、昔からの伝統をそのまま守っていくという意識だけが祭りを支え、それを手助けしようと各地から駆けつける。純粋・無垢だと思う。
この状況をどのように理解したらよいのか。南浦和駅事件や東北大震災時に発揮された日本人の助け合い、その行動を「精神」という言い方でまとめるのは、的を外しているとはいわないが適切ではないと思う。精神というより、もっと日本人が持つ内面・奥底にある気持ち、それは「つながり・絆」がそうさせたのではないかと思う。
もともと昔から日本人は祭りと共に生きてきた。それはとりもなおさず神仏と共に生きてきたことになる。つまり、神仏との「つながり・絆」で生きているのが日本人で、それがいざという時、咄嗟に顕現し発現するのでなかろうか。
ウィスタブル牡蠣祭りにはイギリス人が、洲崎神社祭りには日本人が現れている。以上。
2013年09月06日
2013年9月5日 日本は「つなぎ・絆」大国(上)
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年9月5日 日本は「つなぎ・絆」大国(上)
南浦和駅事件
さいたま市のJR南浦和駅で2013年7月22日(月)、乗客の30代女性が電車から降りようとした際、足を踏み外し、右足が電車とホームの間の約10センチの隙間に入ってしまった。ホームにはい上がろうとしたが、左足も落ち、へその辺りまで隙間に入ってしまった。
転落に気づいた客がホームに設置された「列車非常停止ボタン」を押し、駅事務所から駅員が駆けつけ、2人の駅員が女性を引っ張り出そうとしたが、うまくいかず、別の駅員がとっさに車両を両手で押したところ、周囲の乗客や別の駅員も押し始め、その数は約40人に達した。「押しますよ! せーの! 」という駅員のかけ声に合わせて押すと、重さ約32トンの車両が傾き、ホームとの隙間が広がった。2人の駅員が女性を引っ張り上げると、乗客から拍手や歓声がわき起こり、万歳をして喜ぶ人もいた。女性に目立ったけがはなく、駅員や周囲の乗客に「自分の不注意で落ちてしまい、ご迷惑をおかけしました。助けていただきありがとうございました」と深々と頭を下げたという。
昭和電工相談役・大橋光夫氏の見解
南浦和駅事件へのコメントが2013年8月6日(火)日経新聞夕刊に次のように寄せられた。
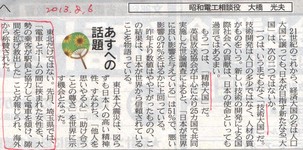
大橋氏の「精神大国」という表現は、何となく大掴みの感がする。もう少し範囲を絞ったワードで定義した方がよいと思うので、イギリスと日本の祭りから検討してみたい。
ウィスタブル牡蠣祭り
2013年7月26日(金)、ロンドン・ヒースロー空港から約160km離れたケント州、ロンドンの南東に位置するウィスタブルWhitstableへ車で向かった。約2時間で到着。この街で牡蠣祭りが27日(土)から一週間にわたって開催される。
ウィスタブルはカンタベリー司教区に属している。カンタベリー大聖堂は、イギリス国教会の総本山であり、カンタベリー大聖堂の身廊は素晴らしい。身廊とはキリスト教聖堂内部の、中央の細長い広間の部分で、入口から祭壇(内陣)までの間を意味し、天空に向けて伸びるが如く柱が林立している。14世紀の垂直式ゴシック様式建築である。
このカンタベリーから約8キロ北に位置しているウィスタブルは、「ケントの真珠」とも称されるように、潮風が香る風光明媚な牡蠣の町。
ウィスタブル牡蠣の歴史はローマ時代にまで遡り、ローマ帝国でもネイティブ・オイスター(ヒラガキ)が大人気で、当時はウィスタブルに専用の牡蠣採集施設が作られ、何千というネイティブ・オイスターが、ローマにはるばる運ばれていたと伝えられる。
このウィスタブルの牡蠣祭り、いつから始まったのか。それを語ってくれたのはDr Clive Askerで、Asker夫妻とロイアル・ネイティブ・オイスターROYAL NATIVE OYSTER STORESと表示された格式ある建物とつながっているWhistable Oyster Fishery Company
のレストランで夕食をとった。Dr Clive Askerは、ウィスタブル牡蠣祭りを企画した人物なのである。
この祭り開始は1985年だが、そのはじまりのきっかけは、ウィスタブルの海では、元々ネイティブ・オイスターを採るだけで、マガキ牡蠣養殖は殆ど行われていなく、マガキの稚貝をフランスに売るのが中心であった。
ところが1982年のこと、この年は大量の稚貝が採れたが、フランスでも同様で輸出が激減、やむを得ず地元で牡蠣養殖する必要が出てきて、祭り企画につながったのだが、その前にイギリスの牡蠣に対する意識変化を話したいという。
18世紀・19世紀のイギリスでは、牡蠣に対する人々の評価は低かった。それにはロンドンにおける水状況が影響している。当時の水はとても汚かった。なぜかというと、18世紀のロンドンでは、下水設備と、井戸水や圧水による上水設備が入り混じっていたので、人口過密地区に住み、公共上水道を頼りにしている貧しい人々は、汚染された水を飲むことになり、下痢・赤痢・腸チフス・コレラなど、口から入るもの、とりわけ飲料水から伝染する病気が多発していた。人々の意識には、水によって健康を害されたという、水へのイメージ悪化、結果として水で育つ牡蠣はよからぬものと評価された。その後の水の改善とともに、ようやく1920年頃から牡蠣に対する認識が正常化して来たという経緯がある。
1982年当時のウィスタブルでは、レストランが一軒しかなく、一般店舗も少なかった。その状況下で開催時期を、夏場の7月にした理由は、セント・ジェームズの日St James's Dayがあり、カンタベリー大聖堂が牡蠣シーズンの終わりに、漁師たちに感謝の意を述べ、子供たちが提灯行列するなどの催しが昔からあったので、それに合わせたのである。
はじめて開催した1985年、商工会議所が頑張ってくれ順調なスタートを切り、翌年はもっとうまく行った。その背景に商工会議所が店に働きかけ、店頭を祭りらしく華やかに飾り、店内も奇麗にした結果、大勢の人が来てくれ、現在のような盛大な催しになった。
この日の14時45分から開催されたロング・ビーチLong Beachでの開始セレモニーの様子を紹介したい。カンタベリー大聖堂の司祭によるお祈り、市長の挨拶があり、挨拶の内容は牡蠣に感謝するというもので、次に主催者の商工会議所の挨拶、その合間合間に地元の楽団が演奏し、30人くらいの男女、海辺にふさわしいダンスを踊る。何となくアフリカっぽく感じるが、全員常にニコニコ顔で愛嬌をふりまく。
さて、司祭の祈り、市長の挨拶が終ると、沖合から茶色の帆をつけた船が浜辺に到着し、両手の駕籠に牡蠣をいれた三人の漁師が船を降りて、司祭の前まで進み、司祭からから祝福を受ける。開催セレモニーはこれで終わりである。
その後は、ロング・ビーチから一般道路に出て、仮装行列パレード行進で、様々な企画によって期間中、街は人で溢れかえるが、実は祭りが始まった1985年は、マーガレット・サッチャー政権下であった。「ゆりかごから墓場まで」によって「英国病」となり、サッチャー政権下で経済立て直しへ大転換、以後、今のイギリスがある。ウィスタブル牡蠣祭りも、このサッチャーイズムを受け入れ、町の繁栄対策として行われた。次号に続く。以上。
2013年08月21日
2013年8月20日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(下)
YAMAMOTOレター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2013年8月20日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(下)
前号(2013年8月5日)の米国NYウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン支局のエネルギー・司法担当のエディターによる自宅への取材についての続きである。この人物の日本語は日本人並み。さすがにアメリカの新聞記者の人材層は厚いと感じる。
本当の取材意図は別だろう
エディターと話をしていて感じたのは、前号で紹介した内容で取材に来たのではない。という疑問を持ったので、率直に尋ねてみた。
その通りで、実は、記事を書こうと考えた背景には、アメリカの実情が隠されていた。
アメリカでは電力自由化となっている。これは電気料金の引き下げや電気事業における資源配分の効率化を進めることを目的としているが、具体的には
• 誰でも電力供給事業者になることができる(発電の自由化)
• どの供給事業者からでも電力を買えるようにする(小売の自由化)
• 誰でもどこへでも既設の送・配電網を使って電気を送・配電できるようにする(送・配電の自由化)
• 既存の電力会社の発電部門と送電部門を切り離すことで競争的環境を整える(発送電送分離)
• 電力卸売市場の整備
などである。
これらの自由化は電気料金を引き下げ競争となるが、それには二つの方法を採る。
• 従来の独占体制下で行われていた総括原価主義によって、無駄なコストを料金に上乗せすることはできなくなる反面、コストを引き下げた企業はその分利潤を増大することができる。このため発電コストを下げる努力を鋭意することになる。
• 電力料金が需給のバランスで決めるので、夏のピーク時間帯の電力料金は高くなる。今まではピーク時間帯の需要に備えて、過大な送電や発電の設備がつくられてきたが、ピーク時を高い電力料金にすることによって、この時間帯の需要量が抑えられると、これまでのような過大な施設は不用になり、結果として設備投資減から、コストが下がり、返ってピーク時以外の時間帯の電力料金は大幅に引き下げられことから、この電力供給企業は需要増になり利益増となる。
このように個々の電力企業の行動で利益額が変化していくが、ここに今後急増していく太陽光発電での買い取りがどのような影響を与えるのか。
この検討には、日本と違うアメリカ企業の実情がある。アメリカの企業は、常に格付け機関によって企業評価を受け、それによって銀行からの借り入れコストが変わる。また、アメリカでは株主の発言力が強く、常に株主の意向を忖度する必要がある。
つまり、急増する太陽光発電を、電力企業が買い取りすると、格付け機関と株主がそれをどのように評価し判断をするのか、そこを論点として記事を書いてみたいと思っているのだと発言する。
一例を挙げると、規模が小さい電力企業の場合、供給量の買い取り増加で、配電量と配電先が増加すると、送電線のなどの設備投資を増やさざるを得ない。
加えて、アメリカでは結構停電が多い。その理由は強風で樹木が電線に倒れ、それによって通電ができなくなるという事態で、これを改善しようとすると、更に設備投資がかさむ。
つまり、送電線の強化を図ると投資が増え利益が減り、企業格付けランクが下がり、株主から追及される可能性もある上に、ドイツのように環境破壊という理由で設置地区から反発を受けることも予測される。
という様々な背景があるので、そのところと日本実態を勘案して記事を書き、次にデスクと相談し、どのような編集にするか。そのところを今考えているとの発言。
これにはウォール・ストリート・ジャーナル社が、ルパート・マードックによって買収されたことが絡んでいる。自分は署名記事を書くのだから自己主張をしたいが、経営トップが共和党であり、保守主義的であるから、なかなか自分の主張や筋を通すのが難しい面があるという発言もあって、アメリカの新聞の背面実態を知るよい機会であり、これらを分かった上で、今後、NYタイムスやウォール・ストリート・ジャーナルの記事を読み解くことが必要だと思った次第。
なお、従軍慰安婦問題は、アメリカでは特定の人しか関心を示していないので、日本側は正面から立ち向かわない方がよいのではないかと、先日の昼食会で佐々江大使に申し上げたとも発言。
さらに、原発の再稼働について、当方の見解を求められ、家内にも直接問いかけていたが、これについては主題でないので割愛する。
最後に
東日本大震災後、電力各社は行政の認可が必要な家庭向けに加え、企業向けや燃料費の上昇を自動的に反映する制度で、料金を順次上げている。
-thumb.jpg)
その家庭用電気代は、8月1日に北海道、東北、四国の3電力の値上げ幅が決定され、標準家庭の月額で見た利用金は2013年9月から次のように値上げされる。
この値上げによる負担増は全体で2兆円(日本経済新聞社試算)を超すという。消費税に先駆けて、既に国民は負担が増えているのであって、この解決策は自ら発電するしかない。
勿論、太陽光+エネフアーム=ダブル発電のシステムを自宅に導入するには、それなりの設備とお金がかかるが、太陽光発電による売電で、毎月、結構な金額が入金になる実態を経験してみると、値上げに対する反発気分はあるものの、助かったという気持ちも正直ある。
それと、火力や原子力発電の場合、一次エネルギーの63%が利用されずに排熱されるということで、家庭に届くのは結果的に37%にしか過ぎなくロスが大きい。
これに対し、エネファームは家庭に設置するので、送電ロスはゼロとなって、エネルギー利用効率は81%と高いので、国家全体の効率化に寄与していることになる。 これらを考えるとエネファームを導入してよかったと思っている次第である。
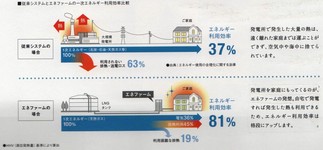
だが、「再生可能エネルギーの電源構成が20%に近づくと様々な問題が表面化する」(日経新聞2013.7.29)という指摘もあるので、続けて関心を持って行きたい。以上。
2013年08月05日
2013年8月5日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(上)
YAMAMOTOレター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2013年8月5日 ウォール・ストリート・ジャーナルの関心事(上)
ウォール・ストリート・ジャーナルから取材
7月21日(日)、米国NYウォール・ストリート・ジャーナル、ワシントン支局のエネルギー・司法担当のエディターが自宅に取材に来た。彼の日本語は日本人並みである。
ウォール・ストリート・ジャーナルとは、NYで発行される国際的な影響力を持つ日刊新聞で1889年創刊。その間にピューリッツァー賞を26回受賞し、創業者による編集不干渉の方針が1世紀貫かれてきたが、ルパート・マードックによる2007年の買収により、それまでの分析記事基調の誌面から大衆誌へと変化してきて、2009年から発行部数が米国首位に返り咲いている。保守系・共和党系寄り。
取材までの経緯
エディターとは、事前にメールで日程調整はしたが、どうして日本の個人家庭へ取材をするのかについては、詳しく連絡がなかったので、実際に会い、その背景を聞き、更にビックリした。
それは自宅北道路側に設置した下写真のエネフアーム、この高さ1.8m、幅1.1m、奥行き0.5mの物体が世界にはなく、日本だけに存在しているという事実を、ワシントンから来たエディターから聞くまで知らず、それほどの価値があるものとも認識していなかったから。
では何故に、ウォール・ストリート・ジャーナル紙ワシントン支局のエディターが自宅に取材に来たのか。他にもっと著名な家もあるし、立派な高級住宅もあるだろうから、当家に来るのは何か理由があるのだと、これを読まれている方は疑問を持たれずはず。
その通りで、お話すれば簡単なこと。実は知人のウォール・ストリート・ジャーナル紙東京支局長夫妻が、先般、娘さんを連れて、建て替え後の当家を見たいと来た際、家の中を案内し、当然に屋根上の太陽光+エネフアーム=ダブル発電、このシステムを説明済みであったので、東京支局長がワシントン支局に当家を推薦したのである。
だが、その時の東京支局長は「ああ、そういうシステムですか」という程度の反応しかなかったので、ワシントン支局から取材依頼のメールがあった時は大変驚いたわけ。
しかし、こちらはエネフアームの仕組みには詳しくない。というのも当家を工事した住宅メーカー、日本で一流といわれている会社であるが、詳しい実践的解説が少なく、概念的な説明を受け設置したので、取材で質問されても答えられない。
そこで、東京ガスの「エネフアーム使用説明担当」に来宅を依頼し、改めて懇切丁寧で分かりやすい説明を受け、ようやく「なるほど」と理解したのである。
次に必要なものは、多分、省エネの実態だろうと考え、昨年と今年の電気とガス料金を比較し、東京電力から入金になっている太陽光発電額も調べウォール・ストリート・ジャーナルを迎えたわけである。
日本でのエネファーム導入経緯
エネファームの日本での導入経緯を調べてみた。
現在、「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池車の量産時代に向かって、日米独自動車メーカーが鎬を削る競争をしているが、この燃料電池原理は1801年に英国で発見されたもの。
エネファームはこの燃料電池原理に基づき、自動車に先駆け、日本が世界で最初に一般商品化したもの。2002年小泉首相(当時)が「燃料電池は水素利用の時代を開く鍵」と施政方針演説を行い、2005年に首相新公邸にエネフアーム一号機が設置され、2009年から「民生用燃料電池導入支援事業」がスタートし、市場導入が開始。
既に43,000台(昨年12月現在)が稼働しており順調に拡大していて、東京ガスは2013年6月11日発表で、累計販売台数2万台を達成したという。エネファームの累計販売台数が2万台に達したのは東京ガスが初めて。
取材の意図
都内のホテルに宿泊しているというので、昼食を招待するから12時に最寄りの駅まで来るよう伝え、車で出迎え、家内がつくったサラダとから揚げ、天ざるそばを食べながら取材を受けた。
① 取材目的の第一
アメリカでの太陽光発電は、2011年の新規導入量は前年比76%増、2012年の新規導入量は世界全体の11%を占め、ここ数年で初めて10%を超えているように盛んである。
ところが、世界全体では2012年は前年比でわずか2%増にとどまっている。その最大の理由は欧州が23%減となったこと。アメリカや中国、日本が伸びる以上に欧州が沈み、このまま推移すれば、2013年の世界全体では11%減ると見込まれているという。
この背景には、欧州が高い買い取り価格を、電気料金に含まれる賦課金などの形で利用者に負担させるので、産業界からは「国際競争力を脅かす」と批判が相次ぎ、一般家庭からも料金値上げに不満の声が出ている。
アメリカではまだ欧州のようにはなっていないが、潜在的な問題としていずれ発生するのではないか。その点、日本ではどういう状況なのかを調べたい。これが第一の取材目的である。
② 取材目的の第二
これは2013年6月7日の日経新聞記事にエディターが関心を持ったこと。
記事は次のように、積水ハウスがゼロエネルギー住宅「グリーンファーストゼロ」の売上が好調で利益増というもの。

この記事の中の「ゼロエネルギー住宅」とは何か、ということに関心を持ち、積水ハウスの本社がある大阪へ行き、取締役本部長と面談しているうちに、初めてエネフアームの存在を知り、大阪ガス作成のパンフレットを入手、本社から紹介された川崎の積水ハウス住宅に訪問した。
この訪問時には神奈川支社の支店長と部長・担当者が同席していた。その翌日に当家に来て、家族だけの取材対応であったので、少し意外な顔していたが、帰りには「その方がいろいろザックバランな話でよかった」とのこと。
このエディター、ワシントン支局であるから、オバマ大統領を訪ねる各国首脳と接する機会もあり、安倍首相がワシントンに来た際に質問したことがあるように、世界の情報を一応持っていると自負している人物であって、日本の外交官などにも会う機会があり、先日も佐々江日本大使と昼食を一緒にしたが、エネフアームが話題なったことはないという。
燃料電池車と同じ原理を活用したエネフアームが、既に一般化商品として日本で普及している事実をエディターは知らなかったわけで、日本人は何故にこのようなシステムを世界にPRしないのか。そこが分からないと何回も発言する。
この発言に同意したい。世界に先駆けて日本が開発普及させたものを、世界に売り込み普及させていくことが必要だと思う。
安倍首相の外国訪問に多くの住宅メーカー社長が同行しているので、海外で売り込み機会は多々あるはず。住宅メーカー・関係業界の問題だ。次号に続く。以上。
2013年07月21日
2013年7月20日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(下)
YAMAMOTO・レター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2013年7月20日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(下)
ユングフラウヨッホ
パリに入る前はスイスのユングフラウヨッホ観光であった。
ユングフラウ(独:Jungfrau)とは 「乙女」「処女」の意で4,158 mの山。スイス・ベルン州のベルナー・オーバーラント地方にあるアルプス山脈のユングフラウ山地の最高峰である。
この山の3,454m地帯にユングフラウヨッホ駅が造られている。ヨッホとは山のピークとピークの間の鞍部を意味するが、ヨーロッパで最も高い位置にある鉄道駅で、ユングフラウ鉄道のラック式鉄道(Rack Railway歯軌条鉄道)、2本のレールの中央に歯型のレールを敷設し、車両の床下に設置された歯車とかみ合わせることで、急勾配を登り下りするための推進力と制動力の補助する鉄道であるが、これで三大北壁のひとつアイガー北壁の中をくり抜いたトンネル内を走り、途中、二度停車する。
最初はアイガー北壁の裏にある高さ1m幅8mほどの展望用の窓のところで停車。次は、西に向きを変えユングフラウヨッホに着く前に停車する。
二度停車時間を含めてユングフラウヨッホに50分ほどで着く。全長は9.3km、勾配は最大で250‰、1896年(明治29年)着工、1912年(大正元年)完成。16年間かかっている。完成はちょうど今から100年前に当り、それを記念して訪問者に「乗車記念パスポート」を各国語でつくり配布している。矢印がユングフラウヨッホ。
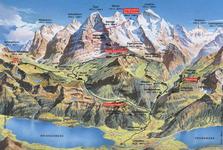

その中に詳しく開発までの経緯が書かれている。着工の明治29年当時の日本は、前年に日清戦争に勝利し、京都に初の市街電車が開通した年であったが、果たしてこの当時の日本で、外国人観光客を誘致しようという政策が存在したか。疑問である。
日本で外国人が旅行免許状なしで国内旅行ができるようになったのは、不平等条約の撤廃実施が施行された1899年(明治32年)であるから、明治政府にとっては今の観光立国などというネーミングは毛頭考えられないものだったろう。
(ユングフラウ山)
(ユングフラウヨッホの観光客)
だがしかし、同時代に、ここスイスでは観光政策としてアルプスにトンネル工事を始めているのである。近代国家建設途次の日本と、既に文明国としてのスイスとの差は大きい。
当時、産業界で名を知られていたアドルフ・グイヤー・ツェラーが、ユングフラウ山の麓でハイキングをしていた時、アイガーの山中にトンネルを掘り、ユングフラウの頂上まで登山鉄道を走らせるという斬新な、正にイノベーション的発想を持ち、その構想を地元住民に発表すると、将来の観光需要に夢ふくらませ、こぞってこの計画に賛成したのである。
工事は当然に難航を極め、爆発事故で6名の犠牲者、工夫の賃上げ要求ストライキ、資金難のため2年間の工事中断、建設費用が計画比二倍になる等、様々な困難を乗り越えて完成させた結果、今では世界各国から毎年70万人を超える観光客が訪れ、山頂への訪問者の数を毎日最高5000人に制限するというスイス観光のハイライトになっている。
スイスには2008年に840万人の観光客が訪れている。この人数を少ないと感じる人が多いと思うが、実は、スイスは昔から物価高であり、その上、ユーロ経済不振でスイスフランが強くなりすぎ、近隣のヨーロッパからの観光客が激減している中で、ユングフラウヨッホには、鉄道への乗車制限をするほど押し寄せている。
その源となるダイナミックな構想を抱き立ちあげたのは、日本では観光立国なんて考えられなかった時代であるという事実を考えると、やはり、日本人はイノベーション力では敵わないと思わざるを得なく、この面で欧米諸国と対抗するのは得策でないだろう。
日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること
ルーブル美術館、ユングフラウヨッホの事例から考え、規模とダイナミックという視点で振り返り、日本の魅力・特長を顧みれば、やはり「一般社会システム」が優れていることだと感じる。
そのことを東京都の猪瀬知事が表明している。2020年夏季五輪開催会議、5月30日のロシア・サンクトペテルブルグでの招致プレゼンテーションで、東京の治安の良さについて、「財布を落としても現金が入ったまま戻ってくる」と話すと、会議場内から笑いが起きたと報道されている。
この「会議場内からの笑い」、それは「おかしい」とか「面白い」というような笑いでなく、多分、「驚きのざわめき・どよめき」であったと推察する。
世界中のどの国で、財布を落として現金が戻ってくるだろうか。皆無でないかと思う。パリに入る前、同行した添乗員女性が懇懇と繰り返し注意を続けたのは、「スリに用心しろ」「バックは身体の前に」「大事なものは肌身に」「特に人混みで写真撮るときが危ない」とルーブル美術館を例えにしつこく何回も言う。
確かに華の都パリは、プロのスリのたまり場であり、稼ぎ場であるのは間違いなく、スリに出あい、スリから身を守るのも、観光の一部だと割り切らねばならないほど。
それに対し日本は全く異なる治安状態を維持している。列車は正確なダイヤであり、車内でのスリの発生は稀、交通事故死(2012年)は4411人で、前年より201人(4.4%)減り、12年連続減少、過去最悪だった1970年の16,765人に比べ、4分の1近くまで減っている。
日本の四輪車台数(2011年)は75,512,887台であり、人口は12,700万人という実態から考え、交通事故死数は信じられない安全さを示している。以下の図からも明らかである。
やはり、日本の魅力は「一般社会システム」が優れている事。このPRが重要。以上。
2013年07月06日
2013年7月5日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(上)
YAMAMOTO・レター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2013年7月5日 やはり日本は日本的で行くべきだろう(上)
今月もTGVに乗って
パリからブリッセルへTGVで行った経緯は、既にお伝えした通り混乱して大問題だったが、今月もジュネーブからパリまで直通のTGVを利用した。
今度はどうなるか。何かトラブルが発生するのではないか。というような期待ともいえる問題意識がもたげてくるのは、ブリッセル線での体験からやむを得ない。
ところで、ジュネーブはスイス。スイスはEUに加盟していないので、TGVに乗車するにはスイスから出国するための検査を受けなければならない。
ところで、ジュネーブはスイス。スイスはEUに加盟していないので、TGVに乗車するにはスイスから出国するための検査を受けなければならない。
ジュネーブ駅の狭い通路、ここが出国検査ルート。ここに乗客が大勢立ち並び、出発時間15分前になるとぞろぞろとホームに向かった。
ここまでは問題なし。今回は二等の座席指定に座った。発車前にトイレに行こうと思い、入口右側にあるトイレ方向を見ると「使用中」という赤表示となっている。
発車したあと、何回か振り向くが、一向に赤表示は消えない。仕方ないので隣の車両に行くが、ここも赤表示、次の車両はどうかと行ってみると、ここも赤表示、とうとう4両先の軽食販売車両のトイレを利用することになった。
戻る途中に自席車両のトイレを見ると、依然として赤表示である。ちょうどそこへ女性車掌が乗車券検査に来たので、指さして「あのトイレは使用不能か」と尋ねると、ウィと頷く。車掌は分かっている。だが、修理をしないのだ。全く困ったシステムだと思う。TGVの恥ではないかと思うが、車掌の顔からは「何も問題なし」という表情が窺える。
なお、TGVの名誉のために補足するが、車掌が頷いた以外の車両トイレについては確認していないので、使用不能ではなく、間違いなく「使用中」であると推測している。
パリに着き、時計を見ると17分遅れ。この程度の遅れはフランスでは問題ないのだろう。さて、重いバックを持ち、車両から出ようと扉方向に歩いて行くと、何と、扉の前に二段の段差があるではないか。入るときは気づかなかったほどの高さであるが、バックを持っている身としては結構厳しい段差である。それと扉の前に段差があるのは危険ではないかと思うが、これが文化・芸術を愛するフランス式かもしれないと諦めて、よいしょ、とバックを持ちあげてホームに出た。
フランス料理の凋落
この日の夕食はフランス料理で、久し振りに前菜でエスカルゴを食べたが、このところのフランス料理は、かつての栄光を失っているような気がしてならない。

毎年5月に「サンペレグリノ世界ベストレストラン50」のランキングが発表される。ランキングは世界の26地区、36人の委員(料理評論家・料理人等で構成)による投票で決定される。
2013年の一位はエル・セジュール・カン・ロカ(スペイン)で、二位は3年連続トップを確保していたノマ(デンマーク)、このNOMAについては先般行ってきたのでいずれお伝えしたいと思っているが、三位はオステリア・フランチェスカーナ(イタリア)。フランス勢は辛うじて十六位にラルページュと、十八位にル・シャトーブリアンが入ったのみ。
因みに、日本のNARISAWA(南青山)が二十位で、アジア勢としては一位である。
このランキングのみでフランス料理が凋落したとは言いきれないが、20年以上前なら確実にこのランキングの過半数はフランス勢で占められていたと思う。当時は今よりフランスへ足繁く通っていたので、20年前の実態は熟知しているが、当時はフランスが料理業界で絶対的なステイタスを持っていた。
しかし、今の現実は上述のランキングが示す通りなのである。何がそうさせたのか。いずれ分析してみたいが、様々なフランスの指標実態を見る限り、これは料理だけの問題でないように感じる。
フランス経済
例えばフランス経済、アメリカ調査機関ピュー・リサーチ・センターが今春実施した欧州世論調査、この中で「向こう12カ月間に自国の経済はどうなるか」という問いにフランス人は、
改善する⇒11% 変わらない⇒28% 悪化する⇒61%
と自国を悪く見ている国民が多い。先日、支持率低迷のオランド首相が来日し「ユーロ圏の経済危機は過去のもの」と強調したが、フランス国民の多くは経済の先行きに悲観的なのである。
その上、富裕層に対する高額課税と雇用や税金にまつわる手続きが煩雑で、この行政の煩わしさは金持ちならずとも多くのフランス人から聞いているが、大問題は企業経営者の国外流出が続いていることだろう。フランスといえば、ひと昔は世界中から憧れの的の国だったのに、随分イメージが変わったと、このところつくづく感じている。
ルーブル美術館
今回のヨーロッパは、いつも留守番させているお詫びを兼ねた家族観光旅行で、パリには詳しいので、市内を散策し、ルーブル美術館にも久し振りに訪れてみた。
ご存じのとおり、ルーブル美術館は、かつての王宮が市民に開放され、今や世界最大の美の殿堂に生まれ変わって、中世から近代の目を見張るヨーロッパ絵画のコレクションが一堂に見られるので、いつも大人気の美術館である。だが、今日は異常ではないかと思われ程、世界中からの観光客が溢れ、館内は通勤時間帯の新宿駅ホーム並みであり、入場制限をしないといけないのではと思うほど。
あまりに混んでいるので、最初からつぶさに見ようとしたら一日では終わらず、一週間は要するので、とにかく超有名な絵画彫刻「ミロのヴィーナス」「モナ・リザ」「ナポレオンの戴冠式」を見て出ることにした。
「モナ・リザ」「ナポレオンの戴冠式」は、人が溢れかえっていて、とにかく至近距離にはどうしても行けない。やむを得ず、大勢の頭越しにズームインで撮影したが、当然にピンボケしやすくなる。これが観光客の頭と手が写っている下の見苦しい写真である。


しかし、「ミロのヴィーナス」については、階段の上方に位置展示されているので、辛うじて通常の写真が撮れると思ったが、ここも真正面には大勢の人で写真撮れず、やむを得ないので背後から撮影したら、左肩が欠けていることが判明した。
だが、この写真を撮り終えて、はたと納得・得心した次第。
フランスはすごい。これはすごいことだと。
先ほど来、フランスが落ちぶれたと貶してきたが、とんでもないことだ。
ルーブル美術館に匹敵する存在が日本にあるのか。絶無だ。ルーブル美術館所蔵の一点でもあれば、それだけで大変な人気となるレベルが日本だろう。それに対し、ここルーブルは逸品ぞろいで、想像できない程の美術品を所蔵しているのだ。
フランスの観光底力
フランスには年間8,300万人もの観光客が訪れ、ある機関の推定によると、ルーブル美術館には観光客全体の約8%が入館するという。この推定で計算すると8,300万人×8%=660万人となる。一方、日本には年間840万人、十分の一である上に、ルーブルの660万人は日本全体観光客の八割にも及び、ひとつの美術館で占めている。
いかに大勢の人がルーブルに入館するのかが分かり、これではラッシュアワー状態になるはずと思い、フランスの観光底力にとても敵わないと思う。次号でスイスについても検討する。以上。
2013年06月19日
日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(下)
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年6月20日 日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(下)
フランスTGVに乗車して
5月の半ば、羽田からシャルル・ド・ゴール空港に朝着き、そこから列車でベルギーのブリュッセル南駅Gare de Bruxelles-MidiまでTGVで行くことにした。
バックを持って高速列車はこちらへという表示に従ってエスカレーターを上り、下がり、ようやく大きな列車表示板の見えるところに着き、その裏側が出発案内となっているので、ブリュッセル南駅行き8:07発を探すが表示されていない。
そこでさらにホーム側のフロアに行くと、そこでようやくTGV専用の電光掲示板に出合い、ここにブリッセル南駅行きと書いてあり、ホーム表示は発車15分前に出すとも書いてある。大分待ってようやく5番ホームと分かる。
ホームに降りるにはエスカレーターの前に立つと、一人の黒人が大型バックを二つ持ち、肩にカバンを掛けている。見ているとひとつのバックをエスカレーターの足元に乗せ、もうひとつを手に持ち、スタートした途端、先のバックが倒れ、急速に音を立て滑り落ちていく。
危ない。ホームにいる人にぶつかってしまうと思ったら、ずり落ちていく激しい音が大きかったので、ホーム上に立っていた人々が一斉に逃げ、避けることができたが、危険なことで、日本では考えられないバックに対する扱い方だ。
ホームに着いて、羽田空港JALカウンターで発行されたAF7181と表示された列車乗車券、それをエアフランスAFの看板表示板をもって立っている若い男に見せると、そこにいるTGV係員に尋ねろと言うので聞くと、TGV係員はAFの係員に聞けと言う。
どうなっているのか、と困っていると、向こうから女性二人、AFの制服姿が歩いてきたので列車乗車券を見せると、手元のリストで筆者の名前を確認し、TGVの一等指定乗車券を渡してくれる。この乗車券に列車番号はどこに書いてあるかと見ていると、再び先ほどのAF制服女性が走ってきて、これと交換だと別の乗車券を差出し、先ほどの乗車券をスリのようにサッと持ち去る。差し替えられた乗車券は3号車で26シートである。
しばらく待つとようやく列車が入って来たが、乗車券に搭乗時刻は7;47と表示されているのに、既に10分遅れている。その時、ホームと列車入り口が平行だと気付く。ヨーロッパでは初めてだ。改善したなと思いつつ、大勢が大きな荷物持って争って乗車するなか、専用置き場にバックを置くことができ、ようやく指定席に座る。
ホッとした途端、列車到着が遅れたのに8:07の定刻に走りだす。郊外は黄色い花が一面に咲く田園風景。奇麗だなぁと見とれていると、突然、途中の駅に止まる。これはブリュッセル南駅まで直通のはずだ。途中駅で乗り換えするはずがない。
何かアナウンスがあり、こういう場合全てフランス語で行われるが、乗客全員がざわざわと立ち、バック持って降り出す。そこで前座席の黒人に聞くとチェンジだという。えっ・・・。終点のブリッセルまでこのTGVは行かないのかと聞くと「そうだ」と頷く。
訳が分からないが全員が降りるので、一緒に降りて、降りた44ホームに立つと、表示板に発車時間が表示される。見ると9:07ブリッセル南駅Bruxlles Midi行きとある。既に時間は9:20である。隣にいるベルギー人夫婦に聞くと「フランスに10日間バカンスに行って帰るところだが、行きのTGVでブリッセルからパリに入るのに、ずっと遠くを大回りしてようやくたどり着いたように、このような事例は普通に起きることだ」という。間違いなくブリッセルに着くのかと聞くと「大丈夫だ」とウィンクする。
しばらく待っていると44ホームに停まっていたパリ北駅行きがスタートした後、空車の列車が入って来た。突然、ベルギー人夫婦が向こうに走り出す。自分も慌ててついていく。到着した車両の前で争って乗客が荷物をもって入るが、この列車の入り口はいつものヨーロッパスタイルで、ホームより二段ほど高くなっているからバックを持ちあげるのが大変。ようやく引き上げて車内に入るとバック置き場は既に一杯。そこで空いている座席に座り、バックは通路におくと、すぐに発車である。心配なので隣席の男性に尋ねると「問題なくブリッセルに着く」という。郊外を見ていると少し眠くなる。ここで寝てしまうと危ない。我慢していると10:02にブリッセルに到着した。9:42到着予定が20分遅れであるが、ようやく何とか着いたという感じになる。
こういう経験をすると、当然ながらフランスTGVへの信頼感はなくなる。それもしばしばあるということであるから、列車管理はどうなっているのか。事故へ結びつくような気がしてならない。安全対策が不十分で心配だ。
宇野常寛氏が「この街のファンづくりに徹すれば、人口が少なくても生き残れる街になる」という主張、その通りと思うが、フランスで経験したTGVの実態は宇野常寛氏の提案とは逆事例で、フランスでTGVを利用しようとする観光客は少なくなっていくだろう。
その点、日本はTGVのような事例が発生することはまずない。素晴らしい列車システムを持っているので、とにかく一回でも日本に来させて新幹線を体験してもらえば、日本のファン化につながり観光客が増え、日本の「人口減対策」として有効な対策になる。
ドイツの実態
ブリッセルから各地を回ってドイツに入ったが、ここで昨年日本に旅行したという若い女性と話す機会があった。
日本の何が一番よかったか、と尋ねると「新幹線の列車が決められたところに停まるのでビックリした」という。日本では当たり前だが、これはドイツでは考えられないことなのである。
フランクフルト国際空港駅からICEインターシティエクスプレスに何回も乗車しているが、毎回、ホームに表示されている停車位置には困惑させられる。指定席の列車番号がホーム上の表示板にアルファベットで掲載されているので、その指定された停車表示のところで待つが、大体違うところに停車する。それも結構離れて停まる。したがって、大型パックを持ってホーム上を走ることになる。
これがドイツの工業技術を結集して、東西ドイツ統合後の1991年に颯爽とデビューした高速列車ICEの運行実態である。
しかし、ドイツ人はこれをあまり気にしない。列車が到着すると、ホーム上を客が右左走り回るのが常識である。停車位置なぞ関係ないように思っているのかもしれないし、この状況が世界で普通だと考えているのかもしれない。
だから、日本に旅行して新幹線ホームで指定券に示された車両位置扉の前に立っていると、誤差が殆どなくピタッと停まるので眼を丸くすることになる。
日本ではピタッと指定場所に停車でき、EU世界で経済の一人勝ちのドイツでも出来ていない。この要因を語り出すと長くなるので止めるが、この事実は日本に来ないとわからないから、日本では普通のことが、ドイツでは実現していないことの不可解さに気づかず、結果として日本の素晴らしさが日常の社会システムに存在することにつながらない。
このような交通システムに関わる日本と世界の常識違いは、日本以外の殆どの国でいえることだろう。それだけ日本は素晴らしい交通システムを保持しているのだ。
アベノミクスを機会に日本の社会システムをPRすることだ
世界がアベノミクスに関心を持ち、為替が円高修正というタイミングに、日本の社会システムが素晴らしいことをPRしたい。特に新幹線の素晴らしさ、それを実態通り正しく伝えることができれば、それを体験したいという観光客も増えるだろうし、世界各国が計画している鉄道市場への強力な輸出武器にもなるだろう。
経済産業省によれば、2007年に約16兆円だった世界の鉄道市場は、2020年には22兆円まで拡大する見通しであるから、ハードとしての車両だけでなく、運行管理や保守を含めたシステム提案を行っていけば、日本の輸出への貢献度は大きい。
特に、新幹線は素晴らしいシステムなので、とにかく一回でも東京発の新幹線を体験させれば、日本へのファン化につながり、東京以外の場所である「地方の活性化」に結びつき、観光客増加は日本全体の「人口減」につながる。今は円安状態が続いているから絶好のチャンス到来である。アベノミクスによって20年間のデフレから脱却し、世界から「日本化」と揶揄されている実態から抜け出し、加えて、日本へのファン化を図って「地方の活性化」と「人口減」対策へとつなげたい。
2013年を日本が過去から脱却し未来に向かうチャンスの年にしたく願っている。以上。
2013年06月06日
日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(上)
YAMAMOTOレター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年6月5日 日本の魅力は「一般社会システム」が優れていること(上)
白から黒へ
「白から黒へ」とは、勿論、日本銀行が白川方明元総裁から黒田東彦現総裁に代わったことを意味しているが、その結果、日本経済の変化は著しい。
今までの日本は20年間デフレに喘ぎ、低成長に甘んじていたが、インフレ目標を2%と掲げ、異次元の金融政策を黒田総裁率いる日銀が実施し、安倍政権によって機動的な財政政策を開始し始め、さらに、これからの成長政策への期待もあって、為替は円高修正、株価も回復してきて、企業も個人投資家も息を吹き返しつつある。
だが、この変化、まだ社会一般につながっていはいない。それはそうだろう。安倍首相が就任してまだ7カ月、20年も喘いで、世界から「日本化」と揶揄されていた状態から一気には変わらないのは当然であろう。時間が必要であることを我々は理解し受け入れないといけない。
と同時に、アベノミクスを継続強化・成功させたとしても、まだ残るだろう「地方の活性化」と日本全体の「人口減」問題、それへの対策を考えなければいけない。
観光客は東京に集中
5月22日、東京スカイツリーが一周年を迎えた。展望台への入場者数は638万人で、商業施設を含めたスカイツリータウンの来場者は5080万人に達したという。
当初、事業主の東武鉄道が公表した年間来場者数見込みは3200万人で、これは東京ディズニーリゾートの年間来場者数2500万人を上回って、大阪万博(6カ月間開催)の総入場者数6421万人には及ばないが、2005年の名古屋万博(6カ月間開催)の2204万人を超えていたが、この当初見込みを1.6倍も上回っている。
ということは日本人観光客だけでなく、634メートルという高さとともに、海外でも話題になって、円高修正とともにスカイツリーに観光客が押し寄せ、その影響で東京各地の観光地にも客が増え、結果として東京地区の一人勝ちといえる現状となっている。
地方の立場から考えれば、東京の一人勝ちに対して何らかの対策を講じないと、この東京集中傾向はさらに進むことになるだろう。
そのひとつはソラマチに進出することだ
ソラマチの4階に行くと、ソフトクリーム専門店がある。店の名は「東毛酪農63℃」。東毛とは群馬県の東部を表すが、東毛の太田市を中心にした酪農家約30軒が加盟する東毛酪農業協同組合が、広告企業と組んで東京に初めて出した店である。スカイツリーのある墨田区と東毛は、東武伊勢崎線でつながっている縁もある。
店の名前についている63℃とは、牛乳をセ氏63度で30分間殺菌する手法を意味している。この方法は欧米では普通だが、日本では高温殺菌が主流のため少ない。だが「たんぱく質の熱変性が少ないため、臭みが少なく、自然な味がする」と普及活動をしていて、ソフトクリームだけでなく「牛乳も知ってもらいたい」と名づけた。そのソフトクリームの売り上げは予測よりも25%多い50万本と上上である。
ソラマチには他にも今治タオルなど地方を売り物にする店があるように、東京に続々できる商業施設が個性を出すため地方企業を誘致している。地方企業にとっては、東京で「地方ブランド」を磨く好機ととらえ、東京と張り合うのではなく、東京を利用・活用する戦略が大事だといえ、その一例がソラマチの「東毛酪農63℃」である。
もうひとつはマスコミの力を借りて集客を増やすことだ
昨年9月、兵庫県朝来市和田山のホテルに宿泊しようと、チェックインすると本日は満室で、このところ連日団体客が入り満室が続いているとフロント女性が発言した。
どうして観光客が来て満室なのか。それは直ぐに分かった。JR山陰本線和田山駅にも、ホテルロビーにも竹田城址のポスターが貼ってあるからである。竹田城址への観光客が急増しているのである。
急増化した背景は、高倉健主演の映画「あなたへ」で竹田城址が登場した結果である。亡くなった妻から「故郷の長崎県平戸の海へ散骨して下さい」という絵葉書での遺言と、その妻の真意を知るため、旅に出る男の話だが、その旅の途中で竹田城址に立ち寄るのである。
竹田城址は、標高353.7メートルの山頂に位置し、豪壮な石積みの城郭で、南北400メートル、東西100メートルにおよび、完存する石垣遺構としては全国屈指のもの。
この竹田城址周辺では秋から冬にかけてのよく晴れた早朝に朝霧が発生し、雲海に包まれた竹田城跡は、まさに天空に浮かぶ城を思わせ、この幻想的な風景が「あなたへ」で巧みな映像と共に紹介され、それを一目見ようとたくさんの人々が訪れるようになったのである。
実は、この城址は以前から但馬地方では知られていたところだが、全国的にはそれほど有名でなく「あなたへ」のヒットで脚光を浴び、ホテルが満室状態という結果にしたのであるが、これはNHK大河ドラマや朝ドラ舞台として取り上げられたところは、同様に観光客急増となるから、マスコミ対策も必要であろう。
本命は自分らしさを追求することだ
しかし、以上の対策をできない地方の方が絶対的に多いのが現実だ。
これに参考になるのが、宇野常寛氏「新時代を読む」(毎日新聞5月15日)で、宮崎県高千穂町の町おこしについて面白い提案をしている。
「僕が提案したのは一言で言うと『街が栄える』とは何か、を問い直すべきだということだ。他の多くの地方都市がそうであるように、高千穂町は産業の衰退と人口減少に直面している。しかし、高千穂町『らしさ』を確保し、発展させていくために必要な人口はいったい何人だろうか。私見では、それは数千人以内に収まるはずだ。棚田と森林を維持し、神社と伝統芸術を守り、観光客にサービスを提供する人間さえいれば、高千穂は高千穂でいられるのだ」
「僕の考えでは、これから高千穂に住むのは、こうした高千穂らしさを保持していくために必要な人と、高千穂でなければ生きていけない人々だけでいい。そしてたとえ人口が1000人でも、街の外に、世界中に10万人ファンがいればそれでこの街はたぶん成り立っていくはずなのだ。それが、ほんとうの意味で『街が栄える』ということだと僕は思う」
「地方が生き残るとはその街の個性、つまり自然や文化が生き残ることであって、決して不相応な人口を養うことでない。たとえば高千穂のような観光の街の場合は、1万人の人口を維持することよりも、人口1000人で10万人のファンがいる街を目指すことのほうが、ほんとうの意味で地方の町が『生き残る』ことなのではないだろうか」
街に来た人をファン化し続ければ、その街に住む人が減って行っても、街そのものは生き続けるというのである。その通りと思うとともに、これは日本の「人口減」への打開策に通じるものだろう。
世界に冠たる日本の列車システム
日本の新幹線が素晴らしいことは日本国民なら全員認識しているが、世界中の人々が認識しているかとなると、まだ十分でない。何故、伝わっていないのかという要因の一つに、世界の実態を日本人は認識していないので、比較して日本の素晴らしさがわからないから、日本人が日本の良さを十分にPRできない。したがって、日本のファン化につなげられない。
風景や食やアニメ・キャラクター人気だけでなく、列車システムが代表する日本の一般社会システムは世界に冠たる存在であることを認識するためには、外国の列車システムの実態を知ることが必要であろう。次号でフランスとドイツの事例を紹介検討したい。以上。
2013年05月25日
2013年5月20日 村上春樹の正体(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年5月20日 村上春樹の正体(下)
村上の新作も自分探しの旅がストーリー
村上春樹の新作長編小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」をここで解説することは簡単にはできない。
だが、主人公は「『大事なもの』を守るため、つらい過去の真相を知る旅に出る」、つまり、自分探しの旅にでるストーリーで小説が展開されていく。
また、日経新聞「春秋」(2013.4.13)は
「人間は生涯に何かひとつ大事なものを探し求めるが、見つけられる人は少ない。もし見つかったとしても致命的に損なわれている。にもかかわらず我々は探し続けなくてはならない。そうしなければ、生きていく意味がなくなるから」と述べている。
村上作品の特徴は、この探し求める人物の内面心理状態を、鋭く、美しく、比喩的でありながら分かりやすく、考え込ませられる文言で表現されていく。
よくぞこのような書き方が出来ると感嘆するばかり。これが村上春樹の正体ではないかとも感じるが、どうしてそのような書き方ができるのかが疑問である。
前作の「1Q84」
2009年5月発売の「1Q84」も大ベストセラーになった。
「1Q84」は、
●「現実」=月がひとつの世界と、
●「もうひとつの現実」=月が二つ並んでいる世界、
この間を行き来するという設定で物語が進んでいく。
今回の「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」も、夢の中で、現実にあり得ない物事が語られていくというストーリー展開であって「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互しつつ、次第に本当の自分を見つけ出していく物語になっている。
ところで、実際の村上春樹はどういう生活態度なのだろうか。
「村上の生活は規則正しい。夜9時ごろに就寝し(彼は夢を見ることがない)、目覚まし時計なしに午前4時ごろ起きる。起床したらすぐに、マッキントッシュに向かって午前11時まで執筆する。一日の執筆量は400字詰め原稿用紙10枚ほど」(2005年1月ニューヨーク・タイムズ)
このようにまことに規則正しい生活スタイルを、一日も休まずに続けているという。ということは、夢も見なく、オカルト的な体験もしていないのに、「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互する世界を描けるということになる。つまり、体験していないことを文章にできるのである。何故、村上はできるのだろうか?
村上春樹は特殊な技術を身につけている
それについて村上は次のように語る。(亜州週刊2003年3月31日~4月6日号 中国)
「想像力は誰でも、たぶん同じように持っているものです。人によってそれほど差があるとは思えません。ただ難しいのは、それに近づいていく場所です。誰でもきっと自分の想像世界を魂の中に持っているはずです。しかしその世界へ行き、特別な入口を見つけ、中に入って行って、それからまたこちらにもどってくるのは、決して簡単なことではありません。僕にはたまたまそれができた。もし読者が僕の本を読んで、その過程で同感したり共感したりすることができたとしたら、それは我々が同じ世界を共有できたということです。
僕は決して選ばれた人間でもないし、また特別な天才でもありません。ごらんのように普通の人間です。ただある種のドアを開けることができ、その中に入って、暗闇の中に身を置いて、また帰ってこられるという特殊な技術がたまたま具わっていたということだと思います。そしてもちろんその技術を、歳月をかけて大事に磨いてきたのです」
いくつかのインタビューでも同様見解を述べているので、これが村上の実体だろう。
武道の境地に通じる
思想家で村上論を書き継いできた内田樹神戸女学院大学教授は、次のように村上春樹を語っている。(「村上春樹にご用心」ARTES)
「『死ぬ』ということが『隣の家に行く』ような感じになること、それが武道においてはとても大切なことだ。それは必死に武道の稽古をして胆力を練ったから死をも恐れぬ精神に鍛え上がったということではない(そんなことは残念ながら起こらない)。話は逆で、『生死のあわい』におけるふるまい方について集中的に探究する人間は、自分がどれくらいその『ふるまい方』に習熟したのかを武道を通じて『チェック』することができる、ということなのだ。
『死ぬ』というのが『ちょっと、隣の家に行くような』感じになることは子供にも起こる。そういう子供はすごく危険な存在だ。だから、子供にはまず死を怖れさせる必要がある。
その教育の甲斐あって、私たちはみんな死を怖れるようになる。でも、成熟のある段階に来たら、死とのかかわり方を『元に』戻さないといけない。『元』というのは、死者は『すぐそばにいる』という感覚を取り戻すことだ。ある種のコミュニケーション・マナーをていねいに践(ふ)むならば死者と交感することは可能だという、人類の黎明期における「常識」を回復することだ。
別にオカルトの話をしているわけではない。これが本来人類の「常識」なのだ。ただ、その「常識」を子供たちに段階的に教える教育制度がもう存在しなくなってしまったというだけのことである。
武道と文学と哲学はそのための回路なのだけれど、「そういうふうに」武道の稽古をしたり哲学書を訳したり小説を読んだりしている人は、もうあまりいない。
社会学者の書いたものがあまり面白くないのは、あの人たちは「生きている人間」の世界にしか興味がないからである。霊能者の書いたものがあまり面白くないのは、あの人たちは平気で「あっち側」のことを実体めかして語るからだ。「こっち」と「あっち」の「あわい」(注 間のこと)でどうふるまうのが適切なのか、ということを正しく主題化する人はほんとうに少ない。
村上春樹は(エマニュエル・レヴィナスとともに)その数少ない一人である」
内田樹は、村上が自分の魂の中に入っていくことができ、そこからまた帰ってくることができると述べているが、そうすると村上は「あの世」と「現世」を行き来できるということになる。村上が「二つの世界を行き来できる」技術をどのように体得したかは分からないが、前述した亜州週刊やいくつかのインタビューで、そのことを自ら述べているから事実なのだろう。
人は自分を探すために生きているのでは?
人は何のために生きているのだろうか? 家族のためなのか? 会社のためなのか? 社会のためなのか? 国のためか? あるいはお金のためか? それとも何も考えないで生きているのか?
村上春樹の新作は、自分探しの旅にでるストーリーで小説が展開されていくと述べた。
また、「現実世界」と「もうひとつの現実」が交互しつつ、次第に本当の自分を見つけ出していく物語になっているとも述べた。
現代人の多くは「あなたは何のために生きているのか」と問われると困惑し、答えに窮することが多いのではないだろうか。
そんなことより、自分は他者の眼にどのように映っているのか、ということの方に興味と関心を持ち、その他者によって自分が影響されやすいのではないだろうか。
また、分からないことがあると、新聞、雑誌、書籍、ネット等から解答を見つけようとして、そこに解答が見つかれば「視野が広がった」「教養が深まった」と思い、そこにひとつの安堵感をもって生きるという癖がついているのではないか。
しかし、時に、そのような安心・安堵感は気休めにすぎず、自分の魂に安らぎを与えるものでないことも知っていて、今ここにある不安を鎮めるものでないことを分かっているのではないか。もっと別なものが、今とは異なる世界から来ることによって、自らの魂を納得させられると思っているのではないか。
実は、これが人間の普遍性であって、それを村上春樹が小説化しているのではないか。村上春樹の正体とは二つの世界観を持っていることだと思うが、どうだろうか? 以上。
2013年5月5日 村上春樹の正体(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年5月5日 村上春樹の正体(上)
村上春樹新作の評判
村上春樹の新作長編小説「色彩を持たない多崎つくると、彼の巡礼の年」の発行部数が4月18日に100万部に達したという。12日発売であるから一週間も経たない。すごい売れ行きである。
発売当日夕方、渋谷で最初の書店に行くと「売れ切れです」。次にヒカリエ斜め向かいの大型書店に入ると、まだ少し残っていたのでホッと買う。
新作に出てくる音楽も人気に
新作では「巡礼の年」の中の「ル・マル・デュ・ペイ」という曲が繰り返し登場する。主人公・多崎つくるは高校時代、五人組のグループの一員で、そのうち一人の女性「シロ」がよく弾いた曲である。
「ル・マル・デュ・ペイ」はフランス語で、作中では「田園が人の心に呼び起こす理由のない哀しみ」を意味すると表現され、主人公が深い「哀しみ」を癒す「巡礼」の旅に出ることを暗示する曲として選ばれているが、このCDも異例の売れ行きである。
何故村上作品は売れるのだろうか?
新作を、早速読んでみる。いつものように村上作品は読み手を惹き込む。だが、一気に読むと「棒読み」になるので、敢えてジックリ「辿り読み」にしようと、途中でやめて考える。
村上作品は「面白い」「エンターティメント性」「わくわく感」という分野の小説ではない。読み手によっては「難しい」「心理描写が長すぎる」「ストーリー時間軸が行ったり来たりで分かりにくい」という評価を受けるかもしれない。
だが、世界中から受け入れられていることはご承知のとおりで、文字通り発売日に飛ぶように売れた。何故か?
世界での評価
村上春樹は世界中、どの国に行っても知られているし、各国語に翻訳されて書店に並んでいる。実際に村上ファンという人物に何人にも会っている。
その一人、イタリア・プーリア州フォッジャ県マンフレドニア市、南イタリアの地方都市で人口は約6万人の町、ここで会った39歳のフィレンツェ大学出身で水中生物の繁殖技術コンサルタント、彼が語る村上春樹論は面白かった。2010年のことである。
殆ど掃除しない汚すぎるマツダ車を運転しながら、村上小説は、ノルウェーの森を友人からもらって読んでハマったのだと語りだす。料理の場面が多いのも関心あった。イタリア語で「素晴らしい国の終わり」というのが大好きで、カフカの海辺も読んだ。
一般に西洋の作家は売るために書いているが、村上は日本ならではというものを書いていて、どこの国でも起きていることではなく、日本のことを書いているので外国人にとって学ぶこと多いという。
彼のこの評価は、他国で聞く村上作品の評価と少し異なる。他国では村上小説が場面は日本で、日本人だけが登場するのに、外国に住む自分の身近なところを描き、自分のことを書いているのではないかと思い、その点から村上作品を受け入れている、というのが多い。だが、彼は視点を違えてはいるが、村上を高く評価している。
ところで、イタリアでは四種類のノルウェーの森が出版されていてそれぞれ中身が異なるという。日本語から英語に訳し、それからイタリア語に翻訳する場合と、日本語から直接イタリア語に訳した場合でニュアンスが異なるのと、訳者が違うと本の中身が異なるという意味である。日本でも同様な事があるのだろうと思うが、マンフレドニア市の彼の話は強く記憶に残っている。
司馬遼太郎との違い
日本人で司馬遼太郎を知らない人はいなく、殆どの人たちは司馬の本を一冊は読んでいるだろうし、司馬が語る日本歴史観に納得している場合が多い。
だが、日本でこれほど有名な司馬も、外国では無名である。知人で仏ジャーナリストのリオネル・クローゾン氏、彼と昨年夏、播磨灘を旅して、兵庫県赤穂市坂越にある大避神社を訪れ「ここは司馬遼太郎が書いた『兜率天(そとつてん)の巡礼』の舞台の神社だ」と伝えると、司馬とは何者か、という疑問を呈された。という意味は司馬を仏ジャーナリストは知らないのだ。さらに、今年3月、和紙の本を書くために来日し、各地を案内した米作家マーク・カーランスキー氏、米国では知られた作家であり、ニューヨーク・タイムズ寄稿記者であるが、マーク氏も司馬について知らないという。
司馬について、同様な質問を多くの外国人に尋ねればすぐ分かるが、日本では超有名で、外国では全く無名というのが実態である。
司馬と村上との違いは世界の普遍性
司馬が世界で知られていない理由を分析すればいくつも挙げられるだろうが、一番の背景は日本歴史上の人物をテーマにしていることだろう。
日本では最も著名な坂本龍馬であっても、世界では無名であるから、いくら司馬が坂本龍馬をロマン人物として描いても、それを翻訳しようとする外国人はいない。
したがって、司馬の著書は翻訳されていないのだから、外国人は司馬のことを知らないのが当たり前であるが、村上本は世界中の言語に翻訳されているので、十分に知られているし、今やノーベル賞受賞の最有力候補者であるという意味は、世界の普遍性をもっていることになる。そのことを語る二氏を紹介したい。
●四方田犬彦氏(「世界は村上春樹をどう読むか」文春文庫)
「村上春樹の読者は伝統的と考えている日本文学や日本のイメージとは関係なく、単に一人の作家を体験しそれに満足しているのです。つまり、彼の『無臭性』が現代のグローバリズムにおいて、世界の人々に大きくアピールしたという事実があるわけです。
谷崎や三島、川端はある意味では意図的にそういった日本の匂い・香りというものを演出して、『美しい日本の私』として国際舞台に出ていったと言えます。逆に、春樹はそういう日本の伝統的なものへのまったくの無関心から出発して、そして世界に受け入れられていったわけです」
●元ハーバート大教授で翻訳家のジェイ・ルービン氏(文芸春秋2010年5月号)
「非常に多くの作家が日本人としてのアイデンティティを追及しているが、村上にとってそういうことは文学の中心になっていない。村上は『あなたが今持っている物語は本当にあなたの物語なのだろうか? それはいつかとんでもない悪夢に転換していくかもしれない誰か別の人間の夢ではないか?』(アンダーグラウンド)と語っているが、これが世界文学として普遍性の底流にあるものかもしれない」
この二人の見解、いずれも村上の作品は世界から受け入れられる普遍性があると判断している。
日本を舞台に、日本人のみが登場するのに、世界中の人たちが「自分のことではないか」と考えさせられるもの、言葉を変えれば、世界中の人たちが持ちつつ、実は、それが自分の内部に隠され、表に現れてこない何かを探るためのヒントが村上の中にある。
ところが、一般的に人は意外に自分を知らないし、知る努力をしていないが、村上を読むとそのこと、つまり「生きるための解答のあり方が物語的に示唆されている」と察知し感知するから世界中で読まれているのではないか。村上の正体解明は次号で。以上。
2013年04月22日
2013年4月20日 分かったこと(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年4月20日 分かったこと(下)
安倍首相
安倍晋三首相が2013年4月18日朝放送の「スッキリ!!」に出演し、いわゆる「アベノミクス」をめぐり、「間違いなく、多くの方々の収入も増えていく。夏を越えていけば、だんだんそういうことになっていく」と具体的な見通しを示した。
現職の首相が情報番組に出演するのは異例で、40分にわたる出演では、「この番組に出るとね、この後色々いいことがあるのかなぁと…」と、終始上機嫌だった、と報道された。
就任から4か月が経つ安倍首相のメディア対応は、記者会見以外の個別取材を多く受けていることが特徴で、すでに在京キー局や主要新聞・通信各社のインタビューは一巡している上、民主党政権時代と比べて、週刊誌やバラエティー番組など、出演するメディアの幅が大幅に広がっている。
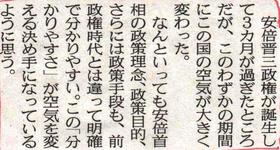
この背景には、上の記事(日経新聞「大機・小機」2013.4.2)のように安倍首相の「分かりやすさ」がある。人々はモノゴトを無意識のうちに簡便に理解しようとする傾向がある。だから「分かりやすさ」が「説得力」を生みだすことになる。
第一次安倍内閣は2006年9月から2007年9月まで、ちょうど一年間で幕を閉じた。最後の辞任会見は安倍首相にとって「誇りや自信が粉々に砕け散った」もので、みじめな状態というべきものだった。
それが今回は「デフレ脱却」や「決められる政治」への期待を背景に、内閣支持率は高い水準を維持している。
どのように変わったのか。それを示しているのが左である。「優先する政策テーマ」「人事」「メディア対策」すべてを変えている。
識者も驚く安倍首相の変身
安倍首相の大変化については識者も驚いている。先日、評論家の大宅映子氏と東京大学名誉教授の御厨貴氏から話を聞く機会があったが、両氏とも安倍首相の一大変身について、その要因は分からないが、確かに変身したという発言が印象的であった。
特に、御厨氏は政治学者として歴代の首相を見続けて来ていて、一度退陣した首相が再登板するのは戦後二人目で、吉田茂以来64年ぶりだとのことであったが、吉田茂の一回目は旧憲法下であり、新憲法になってからの再登板は安倍首相しかいないというところが重要だと強調された。
さらに、安倍首相は本来、経済・金融は詳しくないはずで、元々は保守本流で情の人物であるから、今の変化には驚くばかりで、今では五年半前退陣の負の遺産を消去しつつ、官邸主導政治を実現し、メディアをもコントロールしている状況であるという。
また、外からの緊張、それは竹島であり、尖閣諸島であり、北方領土であるが、それと内からの緩和、これは日銀の脱デフレ作戦であるが、この両面作戦を上手に使い分け、夏の参院選まで乗り切る作戦であるとの解説に、正にその通りだと納得した次第。
安倍首相の変身背景
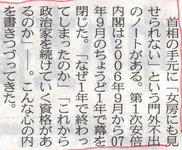
すべての人が認める安倍首相の変身、ではそこにはどのような背景・要因があるのか。
安倍首相に直接聞くのが一番でしょうが、それは難しい。したがって、発表される資料を分析するしかない。仮説として、多分、失敗から生え出づるためには、人生の生き方セオリーを踏んでいると想定し、それを新聞記事からひろってみたい。
左の記事から分かるのは「ノート」である。失敗の背景・要因と考えられる内容を記録化していることである。これは大事な作業であって、失敗から学ぶためには必須条件であろう。
奥さんの安倍昭恵さんも、次のように分析し語っている。
-thumb.jpg)
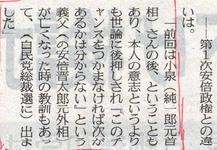
人生に失敗はない。諦めた時、失敗という
このような人生訓、そば屋や居酒屋で見ることがある。一瞬、成程と思って頷きやすい。だが、少し深く考えてみると違うのではないかと気づく。
人は失敗が常である。そこで失敗しないように再挑戦する気持ちを持つこと、これが大事で必要なことはすべての人が熟知している。だから「人生に失敗はない。諦めた時、失敗という」という格言が成り立つので、その通りと思うのが普通だが、ここで見落としてならないことがある。
それは、失敗の要因を分析し、十分に解明しているかである。失敗したことを反省するだけで、失敗の要因を追及し究明しておかないと、再度のトライも前回と同様の手段・方法で行うことになっていくから、成功よりは失敗の確率の方が高いということになる。
失敗が続く多くの事例を見ていると、この失敗からの解き明かしが不十分の場合が多い。折角、失敗したという情報を体験したのであるから、その経験を活かして、次の行動につなげていけばよいのに、もう一度、さらにもう一度と、同じパターンで続けていき、やはりダメかと落ちこみ、結果として、その行動をとることを諦めてしまうのである。
失敗したら、その要因・背景をしっかりと分析しておくことが重要であるが、その際に不可欠前提条件は「文書化・メモ化しておくこと」である。つまり、記録が必要条件なのに、これが案外なされていない。したがって、失敗要因の分析をしようにも情緒的に流れて不十分になりやすく、失敗の継続化という実態になっていく。
人生の勝ち負けを決めるのは、失敗した後の「作法」である
この格言は米ジャーナリストで外科医のアトゥール・ガワンデの言葉である。
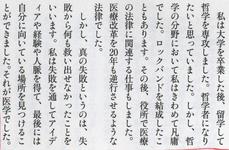
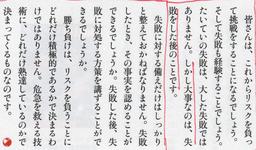
安倍首相から学ぶこと
安倍首相が第一次内閣の失敗から学んだことが「アベノミクス」につながったのであるが、ここで我々が「分かったこと」は「失敗した際の分析力」で、徹底して失敗の要因・背景を分析し、その結果として次の行動への計画をつくりあげていく、という誠にオーソドックスな手法と、そのために必要不可欠なノートづくりだということであろう。以上。
2013年04月06日
2013年4月5日 分かったこと(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年4月5日 分かったこと(上)
浦和学院・春の甲子園優勝
選
抜高校野球、決勝戦で埼玉県代表の浦和学院が、愛媛県代表の済美高校を破り優勝しました。得点差は17-1という大差でした。
旧浦和市民は大喜びですが、しかし、この得点差には驚きました。実力以上の点数でしょう。済美高校の上甲監督は、浦和学院打線の「安楽投手対策」、それは「速球に詰まるのを承知の上で、内角球を投げづらくするように仕向けた」作戦だと褒めましたが、これにちょっと疑問を持ちます。
投手の投げ過ぎ
浦和学院の猛打もあったでしょうが、それより安楽投手の投げ過ぎが影響していたと誰もが感じるのではないでしょうか。
初戦か
ら4試合で663球を投げきってたどりついた決勝。5回に打者一巡の猛攻で7点を失って、6回も続投したがさらに2失点。ここで109球を投げ終え、初戦から数えると772球のところでマウンドを降りました。
アメリカからも疑問の声が届いており、上甲監督の「十分にケアさせる」という発言からも「投げさせ過ぎた」と思っていることが分かります。何事も「やりすぎ」はよくないと「分かった」春の甲子園でした。
3月レターに対する反応
3月は二回に分けて「隣の国・韓国」をご案内いたしましたところ、多くの方から反応をいただきました。その主なものは「今まで知らなかった」というもので、隣の国であり、且つ一度は韓国を訪問旅行している人が多いのに、意外に韓国人の内面についてご存じないということが「分かった」レターへの反響でした。
当方も韓国には何回も行き、牡蠣養殖の取材で企業を訪れ、その他多くの業務で韓国人の自宅まで何度か訪問しているのに、呉 善花(オ・ソンファ)拓殖大学国際学部教授から直接お話をお伺いするまで、韓国人の内面について認識しておらず、隣の国民について「分かっていなかった」ことが「分かった」のです。
東日本大震災追悼式の欠席と朴槿恵大統領の発言
東日本大震災追悼式に中国と韓国が欠席しました。中国の欠席理由は台湾が出席したという明快なものですが、韓国は左の新聞記事にある駐日大使の発言が示すように、欠席理由が明快ではありません。
欠席理由を大使が明快に述べられない、というところこそが、呉 善花氏の指摘する韓国人の日本に対する内面 意識であると「分かった」ように感じます。
また、朴槿恵大統領が2012年12月の選挙戦で訴え、当選後の第一声で国民に約束したのは「幸せに国にします!!」でしたが、これに驚いた方が多いのではないかと思います。サムスンが日本企業を撃破し、日本経済界から「成長モデル」に高い関心を持たれているように、このところの韓国経済は成長軌道であると思っていたのに、新大統領の第一声は韓国民の多くは「生活が荒廃している」というのが実態なのです。
何故なのでしょうか。よく「分からない」ので「分かった」と思えるよう少し補足してみます。
企業の株主
このところ話題なっている西武ホールディングス(HD)に対する米投資会社サーベラスによる敵対的な株式公開買い付けTOB、現在保有する約32%と合わせて4割を超える株式の取得を目指すとのことです。その理由は、株式上場を巡り対立する西武HD経営陣へ圧力を高めるためで、そのためにサーベラス幹部のダン・クエール元米副大統領らを取締役として推薦する見通しだと報道されています。
だが、外資系投資企業の目的は何かを最終的に考えれば、配当収益の向上獲得ですから、TOBによる株式支配シェアを高めた後は、より一層の効率経営を目指し、そのためには不採算路線のカットなどを提案し経営を改善させ、結果として高配当を要求してくるでしょう。
左のグラフは韓国の所得収支です。所得収支というのは、国の経常収支の柱の1つで、外国へ投資した利子・配当収入と、外国へ支払ったそれらなどの差額を指します。
韓国はグラフで分かるように、毎年4月前後だけ、極端な赤字になっています。ということはこの時期に韓国からお金が外国に出ていくのです。どうしてこのようにある時期だけ極端なマイナスになるのか。
それは韓国を支える大手輸出企業の大半の株主が外国人であることから、高配当額が外国へ流出していることを意味しています。
日本の所得収支
一方、日本
の所得収支は上のグラフの橙色で黒字基調を続けています。月別に見ても極端に海外流出はありません。海外株主も多いのですが、海外投資残高が多いからです。
韓国人の生活へ大手輸出企業の業績が結びつかない
日本経済界から高い関心を持たれている韓国大手輸出企業、実は、これらの株主は外国人が半数近くかそれ以上を占めており、いくら法人税を安くして巨額の利益を上げさせても、外国人株主から高配当を要求され、韓国内にはあまりお金が残らないのです。これが新大統領の「幸せに国にします!!」発言背景実態だと「分かった」のです。以上。
2013年03月22日
2013年3月20日 隣の国・韓国・・・(下)
AMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年3月20日 隣の国・韓国・・・(下)
犬の躾
昨年12月20日号でお伝えした内容ですが、毎朝夕、リード(紐)を持ってビーグル犬の散歩をさせている。ところが、この犬、あちこち勝手に動き回り、飼い主の思うようには動かない。犬に引かれて善光寺参りである。犬の散歩をしている同類の方々、殆どが同様で、日本の犬は躾と礼儀が欠けている。ところが、欧米の犬はとてもよく躾されている。
この写真は昨年11月に乗ったドイツのICE特急列車内で見た実際の犬の姿である。若い女性が、車内でパソコンを操作している足元に、犬がリードなしで、静かに吠えもせず座って、こちらを見ている。自宅のビーグル犬とは大違いのお利口さんで、感動ものなので、許可を得て写真を撮らせて頂いたが、日本ではリードによる手綱さばきが必要で重要条件である。
これと同じ体験を再びした。3月11日、ボストンからサンフランシスコに移動するUNITED AIRLINES機内のこと。三人座席が並ぶ窓側と中央席に若い中国系男女が座り、当方は通路側である。6時間という長時間フライトなので通路側に座った。ボストン空港を出発して一時間程度経ったとき、突然、窓側の男性膝の間から白いモノが出てきて、それが動く。アレっと思い見つめると、ブルッと頭を振ってあくびする。犬だ、とびっくりする。吠えもせず、鳴きもせず、水も飲まず、ずっと大人しく6時間過ごしている。これにも感動し世界標準の犬の躾はこうなのかと、再び思った次第。
韓国人と日本人、躾の違い
日本人と韓国人とでは、顔かたち、体つき、同じく東南アジア人であるから概ね90%部分で似ている。しかし、残り10%は全く異なり、その中でも「考え方」としての躾は大きく違っているので、意見は合わない。その実態を語るのが呉 善花教授である。
呉 善花(オ・ソンファ)拓殖大学国際学部教授の見解
呉 善花教授は流暢な日本語を操るが、時に「濁音」表現で誤ることがあるので、「呉・ゴ」「善花・ゼンカ」とは称さずに、日頃は「オ・ソンファ」という名前で通していると最初に紹介された。
呉 善花教授は元韓国籍で日本に帰化、日本では知日派でとおり、韓国では親日派=「売国奴」として扱われていて、韓国へは入国禁止措置を受けたりしている。韓国漢字復活論支持者でもある。
その呉 善花教授が述べられた内容は以下の通り。
①朴槿恵大統領は親日ではない。父が日本との親密な関係があった朴正煕元大統領の娘なので親日派と、日本でいわれているようだが、全くの誤解。
②朴正煕元大統領は元日本陸軍中尉で日本名は高木正雄で、現在の韓国軍隊を日本式でつくった人物。
②だが、反日教育はこの朴正煕元大統領から始まった。
③反日教育の中味は、日本人=野蛮人=未開人
⑤新大統領の補佐役でナンバー2の女性は、日本に二年間留学し、韓国で本を書いた。タイトルは「日本は無い」。300万部という大ベストセラーになった。
⑥この本の内容は、日本と韓国の違いを述べ、日本人の野蛮性を追求している。
⑦例えば、靴の脱ぎ方。日本人は靴を脱いで、出口の方に揃える。したがって揃えるときに体を曲げる。これをねじると表現し、だから、日本人の「心はねじれている」と証言する。韓国では出口に向かって揃えるのは「早く帰れ」という意味になる。
⑧食事で日本人は左手でお椀を持って食べる。韓国では左手は使わない。右手のみ。また、お椀を直接口に持っていく。これは犬食いであり野蛮人。
⑨初対面で親しくなると、すぐに腕を組み、親しさを強調するのが韓国流。親しい中に礼儀なし。それをしない日本人は冷たい人種だ。
⑩親しくなった人の持ち物は自分が使ってもよい。お金でも食べ物でも何でも。日本人はその習慣がない。親切心がない。一方、韓国人は人からお金を借りる、盗るとの区別がつかず世界で一番詐欺事件が多い国。
⑪韓国女性は、冬のソナタのヨン様のような、なよなよした俳優は好まない。強い男性に憧れる。ヨン様を好きな日本人は弱い人種だ。
⑫韓国人が鍋料理を食べる際、右手でスプーンを持って直接鍋の中に入れてとり、そのまま食べる。また、鍋の中でスプーンをかき混ぜる。これは鍋を囲む全員が行う。日本人から見ると異常風景だが、韓国人から見ると、日本の鍋料理で取り皿が使われるのは異常風景となる。
⑬また、口の中で食べ物を噛む際、なるべく音を立てることが流儀。美味くなる。日本人は取り皿を使い、音をたてない。
呉 善花教授の結論的見解
いかがですか。今まで韓国に旅行された方もたくさんおられるし、韓国籍の人と友人関係方も大勢いると思われるが、以上の呉 善花教授が述べた内容をご存知でしたか。
呉 善花教授は結論的見解として次のようにまとめられた。
①韓国は儒教の国である。そこから考えると、中国は「お父さん」韓国は「長男」日本は「弟」となる。したがって、この序列を守るべきというのが韓国人の心象風景であって、心のなかに強くもっている。儒教的価値観から考えるとこれが当然の結論となる。
②したがって、竹島なぞの小さい島なぞは、当然に弟なのだから兄に渡すべき。それよりもっと寄こせと実は言いたいと思っている。日本は島がたくさんあるのだから。
③それなのにしつこく竹島を返せと主張する。大体、日本人はやることが細かすぎる。だから小日本人といわれるのだ
④韓国人は、竹島だけでなく、当然、対馬も韓国のものと思っていて、今は土地を買いあさっている
⑤結局、兄として弟に求める行為は当然であるという思考であり、この考え方を逆にみれば日本に甘えている思考ともいえる。
⑥韓国人の理想は、働かないでお金が入ってくること。豊かな親戚、友人を多く持って、その人達からお金を借り集めて暮らす。いかに多くのお金を借りられるかがステータスになっている。
⑦だから、中国、韓国との話し合いでの解決は不可能。距離をおくことだ。
⑧日本は過去に侵略されたことのない世界でも極めて恵まれた国。だから「話し合いで解決できる」と考えるが、世界の他国は違うのだ、ということを日本人は理解しないといけない。
比較の基準を変えれば判断が異なる
ある事実・現象を判断しようとする場合、立場の違いで判断結果が異なっていく。つまり、判断とは、ある立場を基準にとして、物事を評価することであるといえる。
算式でいえば次のようになる。(事実・現象) ÷ (立場=基準) = 判断結果
呉 善花教授の韓国分析・説明を聞いていると、韓国人は日本人を侮国化している。しかも、その侮国しようとする基準の中味が、儒教的思想から発しており、日本人の発想法とは異なるので、お互いの批判内容を話し合いでは理解し得ない。したがって、呉 善花教授の提言通り「話し合いでの解決は不可能」と判断した方がよいことになる。
3月11日の東日本大震災二周年追悼式に、140カ国もの諸外国代表出席の中、中国と韓国が欠席した。中国欠席の理由は明確で「台湾が出席するから」である。
だが韓国欠席理由は「事務的なミス」という不可解なもので明確でない。だが、呉 善花教授が述べることが、間違いなく韓国人の底流意識にあり、それらが心中の壁となって出席できなかったのではないか。そうならば韓国との国際交流は今後も難しいだろう。以上。
2013年03月06日
2013年3月5日隣の国・韓国・・・上
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年3月5日 隣の国・韓国・・・上
3月レターは、隣国である韓国について、日本人の立場から分析してみたい。
安倍政権好調なスタート
英フィナンシャル・タイムス(2013.3.3)は安倍政権を次のように評価した。
「安倍晋三首相は在任60日でまだ失敗がない。60日というのは日本の首相としては立派だろう。不器用さが目立った2006~07年の第一次安倍内閣やそれに続く5人の首相と比べれば、なかなかの偉業といえる。
安倍氏の出発は自信に満ちていた。経済活性化のために打ち出した『リフレ』路線は、政策期待で市場が反応したという点で一定の成果を上げた。日中間の問題では主張を曲げていないが、必要以上に国家主義的態度を取って事態を悪化させることは避けている。
米国訪問も無事にこなした。自民党の支持基盤である国内農業団体を離反させることなく、環太平洋経済連携協定(TPP)交渉参加へ前進した」
黒田日銀総裁への海外論調
黒田東彦アジア開発銀行(ADB)総裁の日銀総裁への起用についても、海外のメディアがそろって詳報した。積極的な金融緩和を推し進める米欧諸国の間では、大胆な金融緩和と積極的な財政出動を組み合わせる「アベノミクス」に好意的で、日本が長引く経済低迷から脱却するきっかけになるという受けとめ方が目立つ。
一方、アジアでは円安への懸念が一段と広がっていて、台湾・韓国で強い警戒の声が強いが、影響が最も大きいのは韓国であろうと次の見解が述べられている。
「日本が経済の復活に取り組むことは(工業製品の輸出で競合する)韓国を除くアジアにとっていいことだ」(スイス・プライベートバンク、ジュリアス・ベア)
朴槿恵(パク・クネ)新大統領就任
その韓国の朴槿恵新大統領は、2月25日の就任演説で「もう一度、漢江(ハンガン)の奇跡を起こす」と宣言した。
この漢江の奇跡とは、1970年代のことで、当時の韓国は年々輸出を伸ばし、年平均の成長率は10%を超えた高度成長時代で、当時の大統領は朴正煕、朴槿恵新大統領の父であるが、この高度成長にあやかる狙いをこめて改めて宣言したものだが、ここで疑問が湧いてくる。
韓国はサムスン電子、現代自動車等の躍進で、日本企業も韓国に学べということが喧伝され、私もサムスン電子経営実態セミナーに出席し、その海外開拓手法のシステム化に成程と思った経験がある。
ということは、韓国は今さら新大統領が「もう一度、漢江の奇跡を起こす」と宣言する必要がない経済実態ではないかと思うが、この認識は間違いなのか。
さらに2009年、UAEから原発受注というニュースが世界を走り回り「さすがに飛ぶ鳥落とす勢いの韓国」という賞賛の声が盛んに上がったことは、今でも記憶に生々しい。
韓国経済は巨大財閥企業との格差が厳しい
実は今の韓国経済、2012年成長率は2%と低迷化していて、かつての高度成長とは程遠い実績となっている上に、韓国には「三大輸出企業」といわれる「サムスン電子」「現代自動車」「ポスコ(製鉄)」があり、この三企業の売り上げ規模を合計すると韓国GDPの30%になるほどの寡占化が進んでいる。
つまり、ごく一部の巨大財閥企業が韓国経済を支えているというのが実態であり、これら企業は全て輸出企業として存在している。
また、この巨大財閥企業は業績が向上しても、国内の雇用を増やさない経営をしているので、国民には輸出主導の経済成長による恩恵が及ばなく、国内に多くの格差が発生している。
例えば、財閥企業の給与は国内常用勤労者の平均の二倍に達している上に、子女が大学を卒業するまで授業料を全額負担するなど福利厚生も手厚くなっているが、当然のごとく他の企業はそのようなことはなく、一段と格差を大きくする要因となっている。
これ等の実態から、朴槿恵新大統領は財閥による輸出依存の従来型の成長モデルを、財閥と中小、輸出と内需という両輪による成長に切り替えたいというのが25日の演説で述べた「創造経済と経済民主化」方針で、情報通信技術を使った新産業を創出し、その一方で中小企業の育成を通じて所得底上げを目指すことを掲げたのであって、方向性としては妥当な戦略だろうと思う。
ウォン安の修正
このところ日本は円高の修正が進んで、株価時価が一兆円を超す企業が増えたが、一方、韓国はウォン安の修正が進み、輸出産業の競争力に影を落としている。
輸出の伸び悩みは成長鈍化だけでなく、税収の減少にもつながる。そうなれば新政権が掲げる格差是正に向けた福祉政策も頓挫しかねない。
その兆候が2月の米国新車販売の実績に表れだしている。2月販売は米国三社、GM、フォード、クライスラーが好調で、トヨタも4.3%増だったが、現代自動車は傘下の起亜自動車を含め▲2.5%減となった。現代自動車の販売が減少したのは2年半ぶりである。
勿論、現代自動車は米環境保護局(EPA)による調査で、傘下の起亜自動車と合わせ、米国で近年販売していた主力の中型セダン「ソナタ」や「エラントラ」など全体で13車種、合計90万台について燃費性能を誇大表示していたことが発覚したことも、消費者の購買心理にマイナスを与えていることは確かだが、その他の輸出財閥企業にもウォン安の修正によって影響が出始めるだろう。
親日には絶対なれない韓国
日本の植民地時代の1919年に起きた「三・一独立運動」の記念日にあたる3月1日、朴槿恵新大統領は演説を行い、歴史問題で日本に「積極的な変化と責任ある行動」を取るよう求めた。
また、韓国の約600万人の自営業者らが加盟する民間団体「路地裏商圏生存消費者連盟」が、島根県が22日に「竹島の日」式典を開催したことへの対抗措置として、3月1日から日本製品の不買運動を実施すると発表したように、相変わらず韓国の反日運動は根強く行われている。
日本の一部で、朴新大統領の父は朴正煕元大統領で元日本陸軍中尉、日本名は高木正雄で、現在の韓国軍隊を日本式でつくった人物であるから、朴新大統領は親日派であるといわれているが、これは全くの誤解であろう。
現在の反日教育は、実のところこの朴正煕元大統領から始まっているし、韓国には「親日法」と呼ばれる法律がある。
それは2005年に公布された「親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法」で、読んで字のごとく「親日的で韓民族の利益に反するような行為をした者の財産を没収する」という法律である。しかも現在だけでなく、過去にまで遡って処罰する「遡及法」で、たとえば、過去に祖父が親日的な行為をしていたら、その孫が持っている財産まですべて没収されるという悪法が韓国で実際に適用されている。
このように国の方針・法律が反日であるのだから、仮に、新大統領が親日になろうとしても、それは国家の法律上出来ないことになる。
ここで少し深く、韓国人の心情を推測するならば、何か日本に対して問題事例が発生した時「愛国者として怒らねば」という強迫観念から行動をとるのではないかと想像できる。本気で問題意識は持っていなくても、または薄い問題意識でも、愛国者として振る舞わねば、「親日法」が現に国家法としてある限り、自分が叩かれてしまう、という結果を恐れて、日本叩きに参加することになるのでないか。そうしないと「親日」のレッテルを貼られて断罪を受けることにつながる可能性が高いのである。
さらに、韓国の義務教育では、いわゆる日本人が学ぶ「世界史」はなく、韓国史、韓国文化史、東アジア史といった民族史学のみを教えこまれ、その視点から「日本人は正しい歴史を勉強して反省しろ!」と主張してくるが、その背景に存在する「世界史」が日本人と異なるので、多分、いくら議論をしても理解し合えず平行線が続くだろう。
いろいろ日本人の立場から検討すると、隣国韓国とは相容れないことが多い。次号では韓国から日本人に帰化した呉善花拓殖大学国際学部教授の見解をお伝えしたい。以上。
2013年02月20日
2013年2月20日 判断とは基準の持ち方で決まる(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年2月20日 判断とは基準の持ち方で決まる(下)
仏雑誌の「JAPON」特集
フランスのジャーナリスト、リオネル・クローゾン氏から「カイエ・ド・サイエンス& ヴィ(科学と生命ノートCahiers de Science & Vie)」 2013年2月「JAPON特集」号が送られてきて、そこに次のメッセージが書かれていた。
「私は長年カイエ・ド・サイエンス& ヴィ 誌に寄稿しています。この雑誌は文明の歴史や科学的な見地から見た考古学の専門誌です。毎回教養のある読者を対象に、深く掘り下げた一つの話題が取り組まれます。
通常、ベルサイユ、ベニス、ローマ、ギリシャ、古代エジプト等のような西洋文明や古代地中海文明が好まれ取り扱われます。しかしながら、文字、言語、数え方の由来のような、より世界的な話題を扱うこともあります。過去には私が日本の言語、文字の起源、更にはそろばんでの数え方に関する記事を書いたことがあります。
2011年3月以来、仏メディアが日本について語る時、未だに深刻な問題となっている津波や原子力問題についてのみ常に集中しています。というのは、日本専門の仏ジャーナリストはこのような問題以外について書くことがほぼ不可能なのです。もちろん、観光について書くこともできません。
2年が経ち、フランス人は日本文化に関する全てのことに益々興味を持つようになりました。従って、今年ようやくこの雑誌は私のアイデアである日本特集を受け入れてくれました。私が何年も主張して来た考えでした。雑誌の編集者であるIsabelle Bourdial氏は私を信用し、この雑誌の全てを任せてくれました。私は18記事のうち、7つを自分でサインしました。私はこの雑誌によってフランス人が日本にもっと興味を持ってくれればいいと思っています。また、より多くのフランス人が日本に旅行に行きたいと思うようになってほしいと期待しています」
仏の知識層が持っている基準で判断すると、日本文化への評価は高い。
マーク・カーランスキー氏
NYのメトロポリタン美術館アメリカウィングは、10年にわたる大拡張プロジェクトを終え、2012年1月から一般公開されているが、ここに宝石店として有名なティファニーの創始者の長男、ルイス・C・ティファニー(1848-1933)のステンドグラスの作品があり、そのひとつに「オイスターベイからの景色」というタイトルの作品がある。
NYの海には昔、牡蠣が溢れていたことを知る人は僅かであるが、その事実を詳細に記述した本がマーク・カーランスキー著「牡蠣と紐育」、原著はThe Big Oysterで、同書の冒頭に「かつてNYは自然の宝庫であり、海には牡蠣が豊潤に育っていて『オイスターベイ』と称された」とあり、ルイス・C・ティファニーもその事実からステンドグラス作品を描いたのである。
そのマーク・カーランスキー氏から、突然連絡メールが届いた。日本の和紙の本を書きたいので協力してほしいという内容。和紙は世界中の文化財の修復に使われる一方、1000年以上もの優れた保存性と、強靱で柔らかな特性を利用して、独特の用途を確立していることは、世界の知識層では知る人ぞ知るで、その事実を詳細に書きたいというのである。
また、彼はNYタイムズの寄稿記者でもあるので、協力すると日本文化を伝える際に何かと役立つ可能性が高いので、早速にOK連絡したところ、どういうところを取材したらよいのかという相談も来たので、和紙製造業者、紙博物館、皇居御用達店、茶の湯家元、旧家、障子のある家庭等を探し紹介し、今月末に来日することになった。
いずれにしても、アメリカの著名ジャーナリストが和紙に関心を持って、それを出版したいというのであるから、やはり、日本文化への認識基準は高いと判断できる。
街並みと住宅景観は絶望的だ
日本の街並みと住宅景観は絶望的だ、というのは私と一緒に仕事しているアメリカ人女性の発言である。各地方を訪れる度に、彼女の発言を思い出し、改めて、その地の家並みを見ると、明治時代から昭和前期までの、一定感のある落ち着いた宿場町・街道筋であったところが、今は新しい建築様式で、それも様々な家並み、個性というよりはばらばらの街づくりとなって、過去とは比較にならない猥雑な状況となっている。
つまり、かつて存在していた地方独自の建築様式による住宅が見られないのである。オイスターベイであったNYの海と同じように、すっかり変わっている。
欧米諸国では古い町並みが観光資源として成り立つが、日本では無理であり、別の角度から欧米人対策を講じなければならない。
和食の魅力
その第一候補は食文化である。マーク・カーランスキー氏が和紙に目をつけたが、食は地方ごとに独自の魅力づくりをしていて、観光資源として魅力的である。
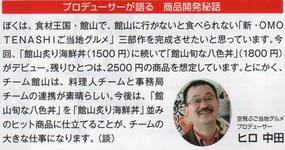
まず、最近、体験した事例を紹介したい。千葉県館山市では、食について昨年から新たなる企画を展開している。その意図を左のようにプロデューサーが語っているが、その「館山旬な八色丼」を食べた際の写真が下記のとおりで、これは「すごい」というのが率直な感想である。
祭も魅力である
食の次は祭りではないだろうか。日本全国いたるところで毎日のように祭りがある。日本人は祭り好きであり、その祭りを訪ねて観光客が集まってくる。京都「祇園祭」、大阪「天神祭」、東京「神田祭」、東北の「ねぶた祭」、九州の「博多どんたく」、「長崎くんち」のように人気の祭りには大勢の観光客が集まる。
しかし、各地方にも独自の趣向をもった素晴らしい祭りがたくさんあって、それらを欧米人に的確に紹介できれば、その地に観光客は訪れることになるだろう という目標をもって、房総半島最南端の小さな漁村・布良﨑神社で地元の人からいろいろ説明を受けて分かったことがある。
それは、地元の人々は祭を、自分たちの民俗文化として、自分たちが守り、育て、維持しているだけだということ。さらに、祭が大好きな人の肩には、神輿を担ぐための盛り上がった筋肉があり、これが祭好きの証明だと言い、それ以上は何も求めていないという。
なるほどと思うが、これだけの伝統と仕掛けがある日本民俗文化の祭を、世界の人達に伝えることも必要ではないかと思った次第で、
そのための基準を提案したいと思っている。
日本人の基準を変えたい
リオネル・クローゾン氏、マーク・カーランスキー氏等の著名外国人は、日本文化を優れていると判断している。日本人も「日本文化は世界に発信できる」という確信を持ち、それを基準にして「世界に伝えよう」という判断をするならば、国内各地に埋もれているはずの素晴らしい日本民俗文化を観光資源へ止揚出来る。期待を持って協力したい。以上。
2013年02月07日
2013年2月5日 判断とは基準の持ち方で決まる(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年2月5日 判断とは基準の持ち方で決まる(上)
アズビルazbil㈱藤沢テクノセンター
家の建て替えの省エネ対策として、「屋根据置型太陽光発電」「エネファーム」「LED照明」等を採りいれたので、最近、特に省エネに関心を持っている。
そこで、企業についても検討してみようと、アズビルazbilグループの藤沢テクノセンターを訪問してみた。
ここは昨年、「㈱山武」から「アズビル㈱」に社名変更している。そのAzbilとは、automation・zone・builderの略。意味はオートメーション(automation)の技術によって、グループ理念のキーワードである安心・快適・達成感のある場(zone)を実現(build)することを表しているという。
訪問したアズビル藤沢テクノセンターは、アズビル㈱グループの中で「省エネモデル事業所」と位置付け、身近なアイデアを駆使したユニークな省エネ対策から、先端技術を駆使した省エネ対策まで幅広く対策を展開していて、そこで得られた「省エネ」に関する技術・ノウハウを公開し、併せて、希望者に省エネ工場見学会を開催している。
見学会によって自社の省エネレベルの判断が出来る
アズビル藤沢テクノセンターの説明と工場見学は、次のように開催される。
まず、省エネに関するプレゼンテーションとして「.藤沢テクノセンターにおける省エネ取組みと事例紹介」「オフィス空調の省エネとエネルギーの把握」「空気で省エネの実例と制御方法」を説明受け、その後工場見学(実際の省エネ現場)して、その事例を見る。
約二時間、いずれも要領よい説明と見学、とても参考になり、成程と思った次第。省エネは時代の方向であり、身近な課題であり、家庭でも採りいれる必要があり、皆さんに見学されることをお薦めしたい。
特に、企業には最先端事例に加えて管理システムが参考になり、これを基準にすると自社の現状省エネレベルが判断できる。まだ、見学していない企業は行かれるよう推薦する。
藤沢駅にはエスカレーターがない
アズビル藤沢テクノセンターの最寄り駅は藤沢である。JRさいたま新都心駅から赤羽乗り換え、赤羽からは湘南新宿ライン、横須賀線、東海道線を通るが、乗り換えなし一本で行ける。所要時間1時間30分。随分便利になったものだと実感する。
藤沢駅には今まで何回か行っているが、久し振りに降りてタクシー乗り場に行くと、ハイブリットのプリウスが待っていて、運転手さんに聞くと一昨日入庫したばかりというので「そうですか。新車ですか」と乗車し、気持ちよくスタートしたが、駅前から左道に入って、すぐに止まってしまう。
渋滞というより、前にバスがいて、向こうから乗用車もバスも来るので、お互いにすれ違うのが苦しいほどの道幅、当然に歩道はなく、歩く人にも気をつけないといけない。したがってスピードは出せない。結構時間がかかる。
アズビル藤沢テクノセンターの見学を終えて、帰りも藤沢駅までタクシーを利用した。途中の窓から見えるマンションは立派で、ショーイングが上手なショップ等、多分、所得の高い層が住んでいるだろうと運転手さんに聞くと、頷く。
にぎやかな駅前で車から降り、JRの改札口は二階であるので、さて、エスカレーターはどこかと探すが見当たらない。では、エレベーターがあるだろうと見るが分からない。
湘南と呼ばれる地域の中で、最大の人口(約42万人)を有する藤沢市であり、JR、小田急、江の島電鉄が乗り入れている駅であるから、機能面で進んだ駅づくりをしているのではないかと思ったが、高齢者には厳しい階段だけがやたら眼につく。
あちこち歩き回ってみて、エレベーターは階段途中から設置されていることを確認したが、やはりエスカレーターはない。
みどりの窓口のお嬢さんに確認すると「エスカレーターはありません」と明解。
さいたま新都心駅と藤沢駅の比較
仮住いの最寄り駅「さいたま新都心駅」に戻って、ホームから二階改札口までエスカレーターで上がる。エレベーターもある。
改札口から仮住まいマンションまでは、傘が要らない屋上屋根付き歩道橋がつながっているし、階下の道路まではエレベーターとエスカレーターが各所に配置済みで、 先ほど利用した藤沢駅とは随分異なる。
毎日のように利用していると、この実態が当たり前となって、別に特別な感覚は持たなかったが、さいたま新都心駅を基準にして、藤沢駅と比較すると、その便利性が優れていて、高齢者にやさしい駅ということが判断できる。
海浜幕張の公民館での講演
先日、NPO法人フォーラムパートナーズ主催の会合で講演を行った。会場は海浜幕張の公民館である。NPO法人フォーラムパートナーズは以下の目的で設立されている。
「『国際化って何?』を議論する場として、JICA から世界の途上国に派遣された専門家集団を母体に、海外で又国内で国際交流・国際協力活動を行うNPOとして平成14年に結成、一般の人の参加を促し、平成16年2月に特定非営利活動法人の認可を受けました」。
ここの主催者の方が、YAMAMOTOレターを見られて、講演につながったわけで、内容については、国際化の事例中心に約二時間というご依頼であった。終了後、数日して、講演記録としてホームページに次のように掲載されると連絡をいただいた。
●山本紀久雄氏(経営コンサルタント・ライター)による講演会「話して分かる時も分からない事もある。そこから方向性を導き出すことが国際化」を開催した。
●山本さんは毎月「山本レター」発信しており、外国と日本の習慣、価値観、倫理観などの違いを分析したレポートを配信している。その為今回の講演には千葉県下のみならず東京から、また、他の機関からも大勢参加した。
●今回はそのレポートの延長として、日仏企業合弁でのやりとり、日本と外国の観光ガイドの違い、カキ養殖と牡蠣料理の違い、香水に関する日本と外国の背景と価値観の違いなどを分析、市場における国際化を解析して、日本は世界で最も豊かであるという結論を述べている。
●当NPOは途上国の事象には精通している専門家もいるが、山本さんは主として欧州の体験から説明がなされているので、新鮮であり、価値観の違い等比較でき、今後の国際交流、国際協力、技術協力の活動にヒントをもらい参考となった。
●今後出来たら日本で考える豊かさ、欧州で考える豊かさ、物質に頼らない例えばブータンなどの豊かさの比較検討をして頂き次回に繋げたい。
講演して反省したこと
NPO法人フォーラムパートナーズでは、講演前に例会が開催されていて、その記録を拝見すると、以下が論議されていた。
●キルギス共和国との20周年を記念した催し。
●ホームビジットとして、中国人、バングラデシュ人、パキスタン人と懇談。
●ナイジェリア、マリ、セネガル、リベリア、トーゴ、ガーナ、ペナン、コートジボワール、ブルキナファソ、ギニアの催し。
●トーゴ大使館表敬とイベント申し入れ。
事前にJICA組織が関係していると分かっていたので、一応の理解をしてお伺いしたのだが、例会記録を見るといずれも訪問したことのない国々である。ビックリすると同時に反省した次第。
つまり、聞く側は途上国滞在経験関係者であるから、話す方は「欧米プラス途上国」という判断基準で講演ストーリーをつくるべきだった。主催者から「新鮮だった」という評価をいただいてはいるが、全ての判断は基準の持ち方で変わるというのがセオリーである。このセオリー実践が今回の講演では不十分と、海浜幕張の公民館で反省した次第。以上。
2013年01月21日
2013年1月20日 2013年は脳力を絞る(下)
新成人に対するアンケート結果
昨年12月、2013年に成人式を迎える新成人、男女250人ずつ計500人の回答結果から見られる新成人の政治に対する認識は酷い。(調査会社マクロミル)
これからの日本の政治に対して「期待できない」と回答した人は21.2%、「どちらかといえば期待できない」も54.4%を占めた。その理由として「政権がまた交代したからといって、すぐに良いことがあると思えない」「公約を実現できないから」といった声が目立つ。日本の未来については「暗い」が13.4%で、「どちらかといえば暗い」の64.0%を合わせると77.4%に上った。「不景気だから」「政治の先行きが見えない」などの意見があったが、この質問には09年以降、8割前後が暗いと回答している。
暗いという認識を煽る新聞
若者が日本について「暗い」と評価する一つの理由としては、以下の日経新聞記事を読むと分かるだろう。明るい未来を見通し、元気づける文体構成ではなく、晴れやかな材料があっても、それを否定する書き方で、日本は安心できない社会だと結論付けしている。
だが、時代とは、常に新しい状況変化に直面し、過去とは異なる問題が様々な形で現出するものである。だから、絶えず新しい事態が発生するわけで、それに果敢に取り組むことを通じて、その時代を前向きに生きることが必要だと思う。したがって、その新しい問題を解決させることに邁進しよう、というように新聞の論説は人々に呼び掛けないといけないと思うが、この日経「春秋」は不安を煽っている。成人式の日に、これを読んだ新成人は、やはり日本は問題多き国で、先行き暗いと思ってしまうだろう。

日本が向かうべき目標像
今の日本が、今後、近未来に向かって行くべき目標を挙げるとすれば次の三つであろう。
① アベノミクスでデフレを解決し、名目成長率を高めた国にもう一度戻す。
② 今のままのデフレ状況を続け、じわじわと国力ランクを下げ続ける。
③ 国家像を新しい価値観でつくり直し、国民みんながそれを納得して行動する国にする。
②は採れない目標であると考えると、①か③しかないことになる。とすれば、①はまだ始まったところで、その成果を得るには、首相を代えないという条件が必要だ。06年以降、7年連続で毎年、首相が交代している政治指導者の大量消費時代と決別しなければ、デフレは解決できず、日本の世界での位置づけは、さらに軽んじられる国になってしまう。
国家像を新しい価値観でつくり直す
国家像の新しい価値観について、月尾嘉男東京大学名誉教授(日経2013.1.12)は以下の提案をしている。成程と思い、そうしたいとも思うが、これを日本国民全員に「その通り」と納得させるには、相当の時間が要するだろう。

日本人の特性から考える
日本人サッカー選手が30カ国で140人も活躍している。選手個人の力量があって活躍しているのは当然としても、日本人ならではの行動も高く評価されていることは間違いない。プロ野球の松井秀樹選手は、常にチーム優先の人で、個人記録は二の次でヤンキースの勝利に貢献してきた。このところが日本人らしいと思う。日本人は組織的プレーに強いのである。だから、ロンドンオリンピックの団体競技で力を発揮したのだ。
ところで、組織として行動するには、必ずリーダーが必要であって、そのリードによる手綱さばきが必要で重要条件である。その日本国のリーダーたる首相がコロコロ変わるようでは、日本人が得意とする組織力は発揮できないのは当然であろう。
明治時代、日本が日清・日露戦争に勝利し、国際社会の一員として認識されたのは、明治天皇の45年に渡る巧みな指導力が影響していることを再認識したい。
明治天皇の素晴らしさ
「江戸時代の天皇の存在感は非常に希薄なものでした。しかし、明治時代になると事情が変わりました。天皇は大きな存在となり、常識があり、公平で、信頼できる人間的美徳の持ち主として、たとえば拮抗する二大派閥間で争いが生じたとき、天皇にご聖断を仰げば、公平なご裁断をいただけるのではないかと期待する雰囲気が自然にできあがっていったのです」とナルド・キーン氏が語っている。(NHKラジオ深夜便2002年10月17日)
さらに、京都大学教授の伊藤之雄氏は「明治22年代以降に絶妙の政治関与を行っていた明治天皇の資質や人間性に、それまで以上に魅力を感じるようになった」という理由で、著書「明治天皇」を書いた動機を語っている。いずれも明治天皇という長期間に及んだリーダーシップによって、日本は素晴らしい躍進を明治時代にとげたのである。
今の日本が当面する人口問題
素晴らしい発展を遂げた明治時代、長期にわたる明治天皇のリーダーシップに加えて、実は人口増が国力増強・経済成長に大きく寄与していた。
だが、今は逆の人口減という時代、移民受け入れに我々は懐疑的なので、残る対策は「女性の労働参加率」を北欧並みにすることが必須要件である。国際通貨基金(IMF)は女性労働参加率向上で、経済成長率で0.4%アップすると提案している。ここに日本の活路があると考えているが、そのためには絶対必要条件がある。それは一人ひとりの意識、つまり、脳の開発である。今まで違う人間=脳細胞をつくらないといけない。
人間の脳力発揮は「前頭前野」で決まる
今の日本人に求められているのは、脳力の再開発である。脳の新築は不可能だから、新しい脳を建て替えるしかない。そのためには、漠然と約1000億個もの脳神経細胞(ニューロン)を開拓するという考え方ではいけない。
長期的な目的を持ち、未来に向かって努力するための脳、これは、大脳の一部である前頭葉(おでこの内側の部分)の「前頭前野」であると、人間性脳科学研究所長の澤口俊之氏が断定していることは前号で述べた。
その理論をくどくど述べるよりは、わが身の脳力認識テストを、自らが行ってみることを推薦したい。今年に入って数カ所での講演で、このテストを行っていただいたが、自分を含めてほぼ妥当な脳力の実態が判明した。「夢をかなえる脳」(澤口俊之著・WAVE出版)30ページから68ページである。簡単な内容であるので重ねて皆さんに推薦したい。以上。
2013年01月06日
2013年は脳力を絞る(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2013年1月5日 2013年は脳力を絞る(上)
新年明けましておめでとうございます。
元旦の日経新聞社説
日経新聞元旦の口切りは厳しいものでした。
「日本の国の力がどんどん落ちている。GDPはすでに中国に抜かれた。強みを発揮してきた産業も崩れた。巨額の赤字を抱える財政は身動きが取れない。政治は衆院選で自民党が大勝したものの、夏の参院選まで衆参ねじれの状況は変わらない。
手をこまぬいていては、この国に明日はない。閉塞状況を打ち破り、国力を高めていくための手がかりをつかまなければならない。
まず大事なことは目標を定めることだ。どんな国家にしようとするのか、どのように経済を立て直していくのか、どんな社会をつくっていこうとするのか----という思いの共有が求められている」
最も主張で、反論する余地はない。
目標を持つことは大事だが、問題解決と同一視してはならない
目標を持つことが大事なことは誰でも知っている。また、人によって目標が異なるのは当然である。
だが、国家がどのような目標を持つか、という選択肢になると、個々人の目標とは異なる。国家目標は政治によって共有化をはかり、それに向かって政治力を発揮させ、国民を引っ張っていくしかない。
そうしないとそれぞれ国民各自が国家目標を述べあい、その異なる目標ごと達成への方法論が異なって、結果的にまとまらず、国家として統合的な成果は得られなくなる。
さらに、もうひとつ大事な視点は、目標と問題を同一視してはならないことである。いつの時代にも問題は多々あって、その時々の問題解決を第一目標にした場合、問題解決がひとつ片付いたとしても、世の中は複合的に絡み合っているから、必ず新たなる問題が次の目標として現れるのが世の常であり、結局、問題のモグラたたきに終始することになる。
そうではなく、諸問題の上部に位置している上位概念を目標とすべきであって、その目標が達成されれば細部の微妙な問題は多々のこるとしても、国家としての大きな成果が得られる結果、諸外国との比較で国民の満足度が向上し、国民マインドは今より満たされることにつながる。
政治力
もう少し日経新聞の元旦社説を続けてみたい。
「目標を達成していくためには政治の安定が欠かせない。何よりも、06年以降、7年連続で毎年、首相が交代している政治指導者の大量消費時代と決別しなければ世界に相手にされない」と述べている。これにも反論の余地はない。
同様なことは、タイのバンコクポスト編集長も述べる。(日経新聞2013.1.4)
「近隣諸国は政権交代のたびに一歩下がって様子見を繰り返してきた。今の日本を一言で言い表せば「quiet(物静か)でpassive(消極的)」。批判的な意味ではないが、積極的な中韓とは対照的だ」と。
日本人は元来、荒々しい粗暴な人種ではない。穏やかで、物柔らかで、しなやかな民族である。だから、危機に対して冷静な行動がとれる。
新渡戸稲造「武士道」第二章は、「仏教は武士道に、運命に対する安らかな信頼の感覚、不可避なものへの静かな服従、危険や災難を目前にしたときの禁欲的な平静さ、生への侮蔑、死への親近感などをもたらした」と述べ、これがその通りに東日本大震災時の行動に顕現され、世界から称賛された。
したがって、バンコクポスト編集長によって、日本人が静かで受け身的であるという指摘を受け入るとしても、それが首相の交代と関係づけられ、論じられることは筋合いのものではない。
タイ編集長が言いたいことは、首相が毎年代わるような事態では、目標もコロコロ変わる上に、その目標達成へ向かう日本の「やる気」が疑わしいという意味と理解したい。
やる気、脳の働き解明へ・・・Sunday Nikkei
では、一体「やる気」とは科学的にはどのように整理されているのだろうか。
「やる気」についても、タイミング良く日経新聞のSunday Nikkei(2012.12.16)が紹介している。タイトルは「やる気 脳の働き解明へ」である。
「仕事や勉強、スポーツで、やる気や効率にかかわる脳の働きが少しずつ分かってきた。これまでなら気持ちの問題と片付けられそうだが、最新の科学で脳の巧みな振る舞いをとらえようと仕組みの解明が動物実験で進んでいる。脳は、頑張るためにどんな手を使うのだろう」という前置きがあり、長文で展開しているのでその内容を整理してみた。
1. 産業技術総合研究所が動物実験で、気が進まないとか、憂鬱という感情は、大脳の扁(へん)桃(とう)体という部分の活動が変化することから生ずると突き止めた。
2. 沖縄科学技術大学院大学の研究グループは、ネズミ実験結果から、辛抱強さとはセロトニン神経の活動にあると解明。
3. 自然科学研究機構・生理学研究所は、サルにリハビリテーションさせて、運動機能の回復促進に、大脳辺縁系の側坐核と強い関連があったと発表。
4. 理化学研究所・脳科学総合研究センターは、ネズミの実験で短期記憶は小脳皮質にでき、休憩があると近くの小脳核に長期記憶が形成されると推測指摘。
5. 最後にコラム的記事で、脳は約1000億個もの脳神経細胞(ニューロン)からなり、それらが複雑なネットワークを形成していると説明。
如何でしょうか。この記事で「やる気」の要因が解明されたでしょうか。全くタイトルの「やる気 脳の働き解明」になっていなく、ただ単に各研究機関の解明・指摘・主張を書きならべているだけで、読むだけ時間の無駄であり、私が日経新聞編集長ならこの記事はボツにしたでしょう。これほどお粗末な紙面はないと深く感じた次第。
澤口俊之氏の講演を聞く
このどうしようもない日経記事の四日前、昨年12月12日ですが、人間性脳科学研究所長の澤口俊之氏の講演を聞く機会があった。
フジテレビの「ホンマでっか!?TV」に出演している澤口氏、その言動に一部から批判的コメントもあるようだが、一時間半の講演、パワーポイントのつくり方が工夫され、話し方も楽しく、新鮮な情報が多い上に、面白く編集されていて、とても興味深く聞くことが出来た。
講演で最も驚いたのはその内容である。日経記事とは全然違っている上に、今まで様々な学者の講演や資料などで知っていた内容とも大きく異なっている。
従来から主張されている脳科学は、約1000億個もの脳神経細胞が人間の思考・行動を支えているという全般的な視点から説明されていて、これはSunday Nikkeiでも同様であるが、澤口氏は異なる。
勿論、脳細胞の話であり、脳についての研究成果であるので、脳が関係していないのではなく、大いにかかわっているのであるが、今までの諸研究者と全く異なる主張、それは脳の一部に対象を絞っていることである。
念のため、著書を数冊読み、成程と思うところを確認したので、目標達成に活用すべきではないかと考えている。
澤口氏の脳理論は、どこが従来理論と異なるのか
まず、長期的な目的を持ち、未来に向かって努力するための脳、これは、大脳の一部である前頭葉(おでこの内側の部分)の「前頭前野」であると断定していることである。
「前頭前野」は大脳皮質の15%ほどの面積を占め、人間は他の動物と比較にならないほど「前頭前野」が発達しているので、ここが「人間性知能HQ(humanity quotient)」を掌る。つまり、HQが賢者の役目を担い、総合コントロール機能を担当していると説く。
したがって、自分の脳をうまく操作し、他者の脳も適切に操作し、目標を達成したいなら「前頭前野」を活用することが一番だ、という理論なのである。
どんな国家にしようとするのか、どのように経済を立て直していくのか、どんな社会をつくっていこうとするのか----という思いの共有が求められているのが、2013年の時流としたら、「前頭前野」のHQ活用が重要なキーワードであろう。次号でも検討したい。以上。
2012年12月23日
2012年12月20日 モチベーション(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年12月20日 モチベーション(下)
日本の発言力低下の最大要因
米コロンビア大学教授のジェラルド・カーチス氏は以下のような見解を述べている。 (2012年12月3日 日経新聞) この指摘はその通りと思う。
豊かな日本の実態
日本は豊かである。というのが日本を訪れた外国人の評価であり、その声を実際に何人もから聞いている。また、自分が海外に行き、その国の実態と日本を比較すると、この事実がよくわかる。
①11月のロンドン、次の本の取材で図書館に行こうと、City Of Westminster(ウェストミンスター市役所)内にある図書館に向かった。ところが、行ってみると図書館は移転したという。ちょうどトイレに行きたくなったので、洗面所を借りようとしたが、市役所内に用事がない人、アポイントをしていない人は、入口の遮断機のところで断られ、自由に入れない仕組みになっている。
仕方ないので、近くの図書館に行き、まずは、トイレと探したがない。そこで係に尋ねると「この図書館にはトイレはありません」という。館内には大勢読書したり調べたりしているが、この人達はトイレに行く場合どうするのか、それが心配になるほどであったが、街中で簡単にトイレ利用は出来ない。カフェかレストランに行くしかない。
日本では駅でも市役所でも、勿論、図書館でもトイレは自由に使え清潔である。
②現在、自宅の建て替え工事で、仮住まいなので何かと不便をしているが、この建て替えということ、
欧米ではどのような実態なのか。それをロンドンに住む人に聞いてみると「個人住宅の建て替えする人は皆無でしょう」といい、ドイツの不動産会社で聞くと「まず、ないでしょう。古い家は価値があるのでのこします」との答えで、日本は地震があるからではないか、というのが補足回答である。フランスのトゥルーズに住む富裕層に属する女性に聞くと「自宅は有名な建築士に依頼して建てた」という例外はあるものの、一般的に建て替えは稀だという。
今ドイツでは空前の不動産ブームが起きているが、それは賃貸住宅の転売が主流で、ドイツ人の不動産所有率は約40%にすぎない。世界で持ち家の割合が最も高いのは日本で89%、韓国78%、アメリカ67%、スウェーデン55%である。
③外国人が最も驚くのは交通機関である。特に新幹線。東京駅発の新幹線15分おきに発着して、それが殆ど時間正確、時刻表通りに動いていく。他の国では列車の時刻表通りにはなかなか動かず、さらに、時刻表がない国が多いのである。
ただし、犬だけは問題
毎朝夕、リード(紐)を持ってビーグル犬の散歩をさせるが、この犬、あちこち勝手に動き回り、飼い主の思うようには動かない。犬に引かれて善光寺参りである。犬の散歩をしている同類の方々、殆どが同様で、日本の犬は躾と礼儀が欠けている。
ところが、欧米の犬はとてもよく躾されている。この写真は11月に乗ったドイツのICE特急列車内で見た実際の犬の姿である。若い女性が、車内でパソコンを操作している足元に、犬がリードなしで、静かに吠えもせず座って、こちらを見ている。自宅のビーグル犬とは大違いのお利口さんで、感動ものなので、許可を得て写真を撮らせていただいたが、日本ではリードによる手綱さばきが必要で重要条件である。
問題多き民主党政権
今回の衆議院選挙、見事に民主党が負けた。2009年8月の総選挙で民主党が第一党になり、鳩山内閣が成立し、その後菅内閣、野田内閣と続いてきたが、その評価が今回の総選挙で決まった。
民主党政権はこれまで、ことごとくやったふりを続けてきた。子ども手当、事業仕分け、成長戦略、新年金制度、社会保障改革、東日本大震災の復興・・・。どれも食い散らかしただけであった。
加えて、外交面での脆弱さ、中国、韓国、ロシアから領土問題で、民主党政権の弱体化をチャンスとみて攻勢をかけてきて、国民の歯ぎしりが続いている。
その中で、ただひとつ財務省シナリオ通どおり、消費税増税だけは決めたが、全く問題多き民主党政権であった。
問題解決とは手順づくり
民主党から自民党政権に、多くの課題と問題が引き継がれた。「復興」「グローバル」「TPP」「国の仕組み」「領土」「年金」「少子化」等、数え上げればきりがない。
これらの解決を新政権に期待するわけだが、その前に「問題解決手順」を考えなければいけない。全ての問題を一気、一網打尽、一目散にできるはずがない。原理的に無理である。何故なら、問題とは、今の日本で異常であり、損害が発生して、困っていることであり、悩んでいることである。また、それらは必ず複合的に重なり合って、その結果の問題としての事象が表面化しているからである。
そうであるからこそ、新政権に要望として、こうなりたい、このような状態になりたい、あそこまで行きたい、というように数多く並べ立てるのはやめたいと思う。
ここは慎重になりたい。問題解決の手順を誤ると、労多くして功少なしで終るからで、ひとつ一つ、問題と課題の糸口、根源を解きほぐして行くしか方法がない。そのために最も大事なことは「問題解決への手順」を決めることである。
今の日本はデフレ解決が先決
日本を海外から客観的に見れば豊かな国である。なのに、国民は何となく閉塞感を持ち、元気が欠けているように感じるのは何故か。
その理由を考えるには、以前の元気であった時の日本はどうであったのかを思い返してみれば、今の状態がわかる。
経済が順調であった頃は、企業業績が向上し、勤め人の給料も上がり、物価もある程度上り、消費も増えて、結果的に税収が上がっていた。つまり、インフレ経済下にあったわけである。
それが一転、デフレ経済になってみると、諸問題が一気に噴き出し、その要因が政治というところにあるのでは、というので民主党政権に替えてみたら、それがとんでもない実態政権だったと気づき、慌てて、再び自民党に戻したというのが、今の日本人の多くの気持ちであろうが、今度は我々国民が問題解決の糸口、根源に気づかなければならないと思う。
立場によって問題への認識は異なるが、日本経済を順調にしたいという立場に立つならば、その糸口と解決への手順第一歩は、デフレからの脱却ということしかない。
首相を替えないというモチベーションへ
日本の首相が毎年コロコロ変わるという状態では、問題解決は出来得ない。新しい自民党政権によるリーダシップによってデフレ脱却を望むならば、そのリードによる政治手綱さばきを巧みに発揮させるしかない。そのためには我々のモチベーションを、新政権の長期化=首相の在任期間の長期継続化というところにおく必要があるだろう。以上。
2012年12月06日
2012年12月5日 モチベーション(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年12月5日 モチベーション(上)
2012年も今月で終わります。そこで、今回の衆議院選挙と来る2013年へ、どのようにモチベーションを持ったらよいのか。それを今号と次号で検討したいと思います。
モチベーションとは
最初は定義。三省堂辞書サイトによると「モチベーション(motivation)とは、意欲の源になる『動機』を意味します。例えば、ある人が『仕事を頑張りたい』という意欲を持っているとすると、その意欲の源になる『彼女にモテるから』『お金がもらえるから』などの動機付けこそが、まさにモチベーションということになります。もっとも一般には、動機の結果として現れる意欲(=仕事を頑張りたいという気持ち)の方を、モチベーションと表現しているようです」とある。
ザッケローニ監督
日本サッカー代表チームのアルベルト・ザッケローニ監督(59)が24日、在日イタリア大使館で母国の「イタリア連帯の星勲章・コメンダトーレ章」を受章した。
日本との友好関係を深めたことなどが授賞理由で、ザッケローニ監督は「サッカーの世界は1日で大きく状況が変わるので、話を聞いた時できるだけ早くしてくれとお願いした」と笑わせ「代表の活躍は協会、スタッフ、選手、サポーターのおかげ。自分の仕事が認められて誇りに思う。これからもいい結果を目指してまい進する」と述べた。
ザッケローニ監督を選任したのは日本サッカー協会。ワールドサッカーに出場したいというモチベーションによって、2010年8月、難航のうえザッケローニ監督を決めたが、今ではその選考結果に日本人の多くが満足している。
では、ザッケローニ監督の手腕はどういうものか。それは選手(チーム)をひとつにまとめることが上手いという、チームマネジメント(チーム作り)につきる。
つまり、選手(チーム)に目的達成に向かっていこうとする明確なモチベーションを持たせることで、一人ひとりの力量を発揮させていることに優れているのである。
トルシエ元監督の評価
11月22日、元日本代表監督のフィリップ・トルシエ氏が、日本サッカーの現状について自身の考え次のように語った。(FIFA.com)
「トルシエ氏は、日本が10月の親善試合で母国であるフランスにアウェーで勝利したことについて、『驚きがあったか』と問われた際、『フランスはまず実験的なメンバーだったし、スペインとの大事な一戦を控えていたことは事実だね』とコメント。
しかし、『日本は草の根でサッカーを普及させている。ユース世代の育成は日本にとって必要で、効果的であり、安定をもたらす。日本の今の成績に関しては驚かないよ。育成に関しては世界トップ3に入ると思う』と語り、現在の日本代表が残している好成績の要因は、日本サッカー協会の育成方針にあると述べた。
ボルドーのタクシードライバー
11月20日、フランスのボルドーのサント・クロア・デュ・モン地区へ向かった。いつも頼んでいる顔見知りのタクシードライバーで、とてもお喋りで何かと話したがる。
ボルドーの「城壁街道」と称される、サント・クロア・デュ・モン地区に行くには、ボルドー市内から車で約一時間かかるが、その間、ドライバーはずっと話を続ける。
その話の中で「日本がフランスに勝っただろう」というので「サッカーか」と聞くと「そうだ」という。そこで「フランスは残念に思っているだろう」と尋ねると「全然、気にしていないよ」「どうしてだ」「簡単さ。フランス人はモチベーションがないと気合が入らないのさ」「へえー」「俺たちはラテンだからね」という。
この発言背景には、格下の日本との試合ではモチベーションが出ない。香川選手のゴールによって1対0で負けたが、あまり重要ではないと判断しているのだ。
その通りで、日本との試合が10月12日、そのすぐ後の16日には、ワールドカップ欧州予選グループI第4節で、前回の世界チャンピオンのスペインと、アウェーのビセンテ・カルデロンで戦い1-1のドロー、スペインが2006年11月から継続していたホーム連勝記録を25でストップさせた試合は、日本戦とは別人のようなフランス人であって、さすがと思わざるを得ない。
日本人への評価
このボルドーのタクシードライバー、日本人は真面目だからなぁと、誉め言葉か、けなしなのか分からない発言をした後、この前、日本人のボルドーワイナリー巡りで運転した際、日程表を見たらこう書いてあったと言う。
月曜日 ワイナリー視察 火曜日 ワイナリー視察 水曜日 ストライキ
木曜日 ワイナリー視察 金曜日 パリに戻る
この中で「ストライキ」とは何だろうか。多分、休みを取るのだろうと想像していたが、そうではなく「ストライキ見物」というのでびっくりしたと言う。
最近、日本ではストライキがないからだと説明受けたが、スト見物まで計画表に書き入れるという日程表つくり、全くフランス人には考えられない。何でも計画的に真面目に行動するのが日本人だと思うが、堅苦し過ぎないか。と運転中なのに前方を見ないで、大きく後部席の当方を振り返り「フランスも日本みたいに真面目にしたら、世界中のどの国と試合しても全勝だろうが、俺たちはラテンだから、そうはいかないよ」「やはり、モチベーションがないとダメなんだ」と大きくウィンクする。
ドイツの友人が介護専門に
フランスの次はドイツ・カールスルーエに向かった。このカールスルーエは今年9月のレターでお伝えした日独交歓音楽祭で来日した、独日協会合唱団「デァ・フリューゲル」(注 翼という意味)のある都市である。
その合唱団の一員であったドイツ人男性、今年の合唱団来日メンバーに入っていなかったので、どうしたのかと尋ねると「長女の介護を24時間している」と発言する。
この男性、なかなかアイディアマンで、いつも新しい企画に基づく事業計画を熱っぽく語っていた。
だが、今回は何も事業計画は語らない。長女がどのように状況なのか、住んでいたボンで交通事故に遭い、最初は命も危ないという大事故だったが、ようやく病院は退院でき、今はリハビリ施設でトレーニング中なので、そのリハビリ施設の一室に長女と一緒に暮らし、介護に全力だという状況のみを語る。
だが、以前の事業計画を語る当時よりは一段と輝いているように感じる。
思い出してみると、このドイツ人、何回も転職し、その合間に次の事業を企画し、各方面に提案していたが、どこからも採用されない状況だった。しかし、彼は常に元気で前向きな発言を繰り返すので、よく堪えないなぁと、その精神力に感心しつつも、どうして提案計画が採り上げられないのか、ということに相談に乗ったこともあったが、その当時と比べて明らかにモチベーションが向上している。
そこで以前のように事業計画はつくらないのかと聞くと「やめた」「もうしない」「娘の介護に命をかけている」と、お節介なことは言うなという厳しい目つきになる。今や、彼のモチベーションは介護一筋なのである。
肉親は「情」で、論理ではない
このドイツ人男性の発言はよくわかる。というのも自分も義母の介護で勤め人を辞め、その結果として今の仕事につながったのだが、その時の気持ちは、家族が病気等で倒れたときは、論理的に考えてはいけないというものであった。
「情」で対応するのが家族愛であり、その「情」から出る介護にモチベーションを持つのが人間の務めだ、と判断した体験があるからである。
首相を選ぶ選挙
日本サッカー協会のモチベーションでザッケローニ監督を決めた。来年3月のヨルダン戦に勝てば、世界最速でワールドカップ出場が決まる。結果として日本人は満足する。
日本国民のモチベーションによって12月16日衆議院選挙で首相が決まる。果たして、国民が納得し、コロコロ変わらない首相を選べるか。一人ひとりにかかっている。以上。
2012年11月30日
2012年11月20日 安定した日本が一番だ
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年11月20日 安定した日本が一番だ
富士のお山は日本の誇り
富士山は、その姿の崇高さ、優美さ、安定感によって日本の象徴であり、日本人の心のふるさとです。また、富士信仰ともいわれるように、悩んだ時に富士山を仰ぎみると、背筋を真っ直ぐ伸ばさねば、という想いにさせてくれる日本人の基盤的存在です。
子供のころ、近くの銭湯に行くと、浴槽の壁に富士山と羽衣の松と天女が描かれていました。その当時は何も分からずボーと見ていただけでしたが、あの絵の意味は、富士山が日本人のシンボルであるという証明であったのかと、今頃になって感慨に浸っています。
仮住まいに移って、朝夕に見る富士の安定感ある姿に、改めて見入っています。
今は東京が一番人気
今、日本の観光地で一人勝ちは東京でしょう。勿論、その理由は東京スカイツリーと、大正3年(1914)開業当初の姿に復元された東京駅によります。
スカイツリーはXmas装飾でシャンパンカラーに彩られ、東京駅はルネサンス様式の伝統的な装飾で蘇り、皇居までの御幸通りとマッチし、東京丸の内駅前地区は、世界でも指折りの落ち着いたシックな景観になりました。
また、東京駅は外見だけでなく、南北入口内のドームは、八角形の天井に巨大な鷲の彫刻が見据え、折り上げ天井となっていて一見の価値ありです。10月上旬に開催された国際通貨基金IMF総会時、東京国際フォーラムと帝国ホテルが主会場となった関係上、多くの外国人が東京駅を利用したので、世界中にこの安定感のある美しい景観が伝わったと思います。
世界は常に変化している
アメリカはオバマ大統領が再選しました。だが、経済政策運営への不安が消えず、ダウ工業30種平均が一時下げ、半面、安全とされるアメリカ国債は買われ、利回りが下がり、ドル高となっています。
中国は新体制、習近平総書記の就任で、新指導部の顔触れににじむ経済政策の停滞への不安か、香港と上海の株式相場は値を下げました。
一方、衆議院解散総選挙後の次期首相候補といわれる、自民党の安倍晋三総裁の発言、2~3%のインフレ目標、無制限の金融緩和、マイナス金利政策……。株価が上昇、日経平均株価は9000円を超えました。
我々が関知できない要因で、世界の経済指標が日ごとに変化し、これを的確に把握することは至難です。それより我々の生活面から見て、世界を評価した方がよろしいと思います。
中国について
習近平体制について多くの解説が各マスコミでなされています。これは中国の世界に対する存在意味が高まっている証明です。一方、日本の動向に対する報道量は、以前から比較すると格段に減り、やはり経済的に躍進していないと世界からの関心が遠のいていきます。
その通りですが、ここで少し中国経済・社会実態について分析してみると、先日の共産党大会で、退陣した胡錦濤総書記が2020年までに「国民の平均収入額とGDPを10年比で2倍にする」と発表しました。かつての日本の所得倍増論と同じです。
中国のGDPは2011年でドル換算しますと7兆4000億ドル、これを計画通り7%成長させ、そこに中国元の切り上げとインフレ率をそれぞれ2%と予測して計算すれば、2020年には20兆ドルを超え、アメリカを抜いて世界一の経済規模に計算上なります。
中国が世界一の経済国家になると、その経済力を背景に、世界に対する発言力を高め、特に、反日教育を日頃熱心に行っている日本に対しては、尖閣諸島問題を含めて干渉圧力を強化してくると予測されると、多くの識者が述べています。
確かに、日本が高度成長した時代、日本の経済力をバックに日本は世界での発言を強め、ビジネス交渉でも各国に対し有利に進めることができましたから、中国の躍進と中国人の強引な性格を考えると、世界中が中国によって大きな影響を受ける懸念が高いでしょう。
問題が多い中国社会
しかし、このGDPというもの、経済力を数字で表したものですが、その算出方法というより、経済をつくる手段に各国の違いがあるので、GDPといってもそれぞれ異なる実態で、それを平等に評価することには問題があります。
例えば、2012年1月のNYタイムズ紙に、アイルランド人で「フォーブス」誌、「フィナンシャル・タイムズ」紙の元編集者である「エーモン・フィングルトン」氏が寄稿して大反響を呼んだ「日本の失敗という神話」The Myth of Japan’s Failureのなかで、アメリカのGDP計算について次のように指摘しています。
「80年代から米国の統計学者はGDPに対してインフレ率を調整するヘドニック法を積極的に採用するようになった。これは多くの専門家に言わせると、見かけ上の成長率を意図的にかさ上げする手法だ」と。
アメリカのGDPに対しても批判があるわけで、まして中国には疑問が多くあります。先日、中国のGDP倍増計画について親しい経済アナリストにお聞きしたら「それは簡単に達成できる。中国全土が国有地なので、原価ゼロの上に建物を建てるとGDP向上となる」という見解で、計算上の経済はドンドン増えていくとの回答です。
言われてみればその通りですが、いずれにしても中国の経済指標には疑問点が多く、実際のところどうなっているのか不明なところが多々あります。
そのような不確実な中国ですが、確実に言えることは所得格差が酷く、反日デモの背景にはこの格差への不満があるというのが妥当な見解です。
裸官
これは「裸体官員」の略ですが、配偶者や子女が仕事以外の理由によって海外で暮らす、あるいは外国国籍や永住権を取得している中国政府の公務員のことを意味します。文字通りハダカの王様ならぬ「ハダカの官僚」ですが、別に服を着ていない訳でも、役職なしの平役人という意味でもなく、配偶者と子女が外国籍を取得して、国外に定住している官僚のことをいい、配偶者と子女を海外に送り出す理由は、勿論、職権を利用して蓄財し、頃合を見て海外に逃亡するためで、既に海外逃亡した汚職官僚数は四千名強、流失額は総計50億ドルに上るとも言われ、逃亡先は世界各地に広がっており、中でもカナダが人気らしいのです。
また、習近平総書記一族の資産は300億円ともいわれています。日経新聞(2012.11.16)に報道されるくらいですから、多分、事実だと思いますが、共産党の幹部がどうやって資産を作り上げたのか不明です。いずれにしても一般国民は、幹部との所得格差を熟知しているので、反日教育による尖閣諸島の官制デモという「火遊び」に失敗すると、共産党王朝は過去の中国王朝の歴史が示す結果となる恐れがあると思っています。
91歳のアメリカ人の九州旅行
友人のアメリカ人女性が91歳になるカリフォルニア在住の母親と二人で九州旅行をして、その結果を報告してくれました。一言で「何も心配いらなかった」というものです。
来日前は母親の年齢を考えて心配していたようですが、日本に着いて1日で全く心配は杞憂で、どこに行っても親切、車椅子はどこの駅でもホテルでも事前に用意され、薬を飲もうとすると親切な女性が水まで持ってきてくれるという、大変満足した旅ができたとの報告で、日本は世界の富裕層高齢者にとって最高の旅行先ではないかと絶賛です。
実は、ここに日本のよさがあるのです。見かけの経済力であるGDPはデフレで20年間増えていないが、その間に国内整備は進み、とうとう東京駅まで素晴らしい復活を遂げ、「エーモン・フィングルトン」氏が実際に日本に来てみると、世界の評判とは大きく異なり「充実した生活を送っているのが日本人だ」というNYタイムズ紙記事が本当の姿です。
経済成長という変化は少なく、所得格差は増えたと言っても他国と比較し少なく、大地震を除けば安心・安全で安定した生活の日本、誇りとプライドを持つべきと思います。 以上。
2012年11月12日
2012年11月5日 尖閣諸島問題
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年11月5日 尖閣諸島問題
富士山は日本人の心の象徴
家の建て替えのため高層マンションに仮住まいしていますが、このところ毎日ベランダ越しに富士山が見えます。
今日の富士山は雪化粧で、そろそろ冬が訪れたと感じます。
ところで、富士山といえば、世界各地で富士山に似た山が、その地に住む日本人や日系人から「●●富士」と呼ばれているところがあります。

(チリの富士山オソルソ山)
10月はアメリカ・シアトルに行きましたが、ここでは標高4392mの火山レーニア山が、日本人・日系人からは「タコマ富士」と呼ばれていました。
同様に富士山そっくりの山は、チリ・サンティアゴから約1000キロ南に下ったプエルト・モンでも見ました。オソルソ山2652mですが、地元の日本人・日系人から「フジ」と慕われています。富士山は日本に生まれ育った、日本人の心の象徴で誇りです。
ジャイアンツが優勝
プロ野球の日本シリーズは、読売巨人軍ジャイアンツが優勝しました。3年ぶりの22度目の日本一になったこと、原監督におめでとうと述べたいと思います。
ところで、アメリカ大リーグのワールドシリーズでも、タイガースに4連勝し、2年ぶり7度目の優勝を果たしたのはサンフランシスコSF・ジャイアンツです。
その優勝パレードが10月31日、SF市内で行われ、この日はハロウィーンとパレードが重なり、街はどこへ行ってもオレンジと黒でしたが、雨だったのでキャンディをもらいに来た子供達にはあいにくでした、とSFの友人から連絡がありました。
このSF、アメリカ大統領選挙では街中オバマという感じです。元々民主党の地盤ですから、誰に聞いてもオバマに投票するという声ばかりです。アメリカの大統領選挙では、共和党が強い州は「赤」、民主党が強い州は「青」で表すと、フリージャーナリストの牛田誠氏が述べ、それを州別に表したのが下図です。
これを見るとよくわかるように、西海岸は青の民主党、大陸の真ん中あたりは赤の共和党となっています。ですから、SF市内で大統領選の話をすると、圧倒的に民主党であるばかりでなく、中西部の人々を「あの人達は田舎者だ」という発言を聞きます。
なお、大統領選挙を行う投票所、日本では小中学校等の校舎が多いのですが、4年前の大統領選で見たSFの投票所、これは民間の普通の家の物置とかガレージで行われていまして、日本とは違う身近な感じをした体験がありますが、ここで注目したいのは投票所POLLING PLACEに、漢字で「在此投票」と書かれていることです。
漢字で書かれている背景を理解する、つまり、SFのベイエリアでは、アメリカ合衆国のどこよりも広東語を話す中国人が集中していることを示しています。また、その事実を証明するものとして、公立の高等学校、それも成績が良い生徒が集まる学校では、圧倒的に中国人が多く、知人の長男が通っている高校では70%が中国系になっているというのが実態です。実は、中国の怖さはここにあります。いつの間にか人の数で圧倒していくという戦略を採ってきます。
尖閣問題
尖閣問題、中国の報道を見ていると、中国国内向けの成果アピールに躍起ということがわかります。
中国の国家海洋局は10月30日、海洋監視船4隻を尖閣諸島周辺の日本の領海に侵入させた後、ウェブサイトで 「中国領海で不法な活動をしていた日本の船を領海から駆逐させた」と強調する報道がなされています。(日経新聞2012年11月3日)
勿論、日本の海上保安庁は「駆逐された事実はない」と否定しますが、中国は「日本に尖閣諸島の国有化を撤回するよう求めて」一方的で勝手な広報PR工作を行っているわけです。

しかし、上の報道のように「海洋監視船員応募者ゼロ」ということを考えますと、中国人の本質はそれなりだと思わざるを得ません。
この件に関して、共産党機関紙の人民日報は2日、紙面の半ページ分のスペースを使い、「該当ポストは採用条件のハードルが高かったので志望者がいなかっただけだ」などの苦しい言いわけをしていますが、中国人の実際の気持ちを正直に顕していると推察する方が妥当ではないでしょうか。
一方、日本では海上保安庁に目指す若者が急増していることを考えますと、ここに日中両国民性が顕れていると考えられます。
だが、我々が最も注意し警戒しなければならないのは、SFの高校が中国人に占拠されたように、中国の最大の武器である国民の数を使った尖閣対処法で来た場合です。
それは、中国が明確な武力攻撃でなく、尖閣諸島を占拠しようと画策する「飽和攻撃」を採った場合のことです。中国の国家海洋局をはじめとする様々な機関が保有する船舶、その数は1470隻とみられ、それに地方政府の船舶を加えて、尖閣諸島に上陸を図るというケースが採られた場合、日本の海上保安庁船舶数は450隻ですから、完全阻難しいかも知れない可能性があります。
日本の誇りである美しい富士山を見つつも、我々は対中国対策を考えなければならない事態になっています。以上。
2012年10月06日
2012年10月5日 一極集中、全体システム、または新工夫か(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×環境 山本紀久雄
2012年10月5日 一極集中、全体システム、または新工夫か(上)
地方の家並み景観
9月下旬、羽田から伊丹乗り換えで但馬空港に着陸し、豊岡市を経由し朝来市と養父市を回った。利用したJR、タクシーから外を見、特にバスは片道30分の山深き目的地に行き、道端を歩く人も殆どいなく、乗客も往復とも二人のみという状態のなか、その間ずっと窓外をウオッチングし続けたが、家並みには何ら違和感がなく、景観に珍しさが感じられない。どこの家も、新しい建材で建てられており、庭の片隅にプレハブ物置小屋がたたずんでいて、筆者の自宅あたり首都圏と似ている。
勿論、自然環境の山川と木々は地方の素朴さを示し、道路端には田畑があり、農業が行われているので、家と家との間隔は広く、全体的景観は違っているのであるが、家は今時の建築で建てられているので、住居としての木造家屋には何ら違和感をおぼえない。つまり、かつて存在していた地方独自の建築様式による住宅が見られないのである。
そこでこの地に観光に訪れたとしても、家屋とそれが続く家並みそのものは観光資源として存在し得ないと感じる。首都圏と同じように建物と物置小屋が並ぶ光景では、何ら地域としての特殊性がないからである。では、何故にこのようになったのか。その理由の第一は、全国統一基準の建築基準法により建築されるからであろうと推測している。
しかし、仮に日本に建築基準法がなければ、昔の家並みが維持されたか。それも疑わしい。日本人の家は、その家族の状況によって建てられるケースが多い。したがって、家族構成の変化や、今時の生活スタイルと異なった昔のままの間取りでは快適さが損なわれる。
さらに、元々冬寒く夏暑い構造建築であることや、萱葺きの屋根の場合、葺き替えにコストがかかり過ぎるように、メンテナンス費用が膨大になってしまい、それなら建て替えした方が安いし快適な生活が出来る。加えて、高度成長時代の道路等公共設備関係の整備も影響し、そこに日本人の何でも新しいものを好む感覚が加わって、家の建て替えに至るのだろう。
竹田城跡
家並みに景観に珍しさが感じない、朝来市和田山のホテルに宿泊しようと、チェックインすると本日は満室で、このところ連日団体客が入り満室が続いているとのこと。
どうして観光客が来て満室なのか。それは直ぐに分かった。JR山陰本線和田山駅にも、ホテルロビーにも竹田城跡のポスターが貼ってあるからである。竹田城跡への観光客が急増しているのである。
急増化した背景は、高倉健主演の映画「あなたへ」で竹田城跡が登場した結果である。亡くなった妻から「故郷の長崎県平戸の海へ散骨して下さい」という絵葉書での遺言と、その妻の真意を知るため、旅に出る男の話だが、その旅の途中で竹田城跡に立ち寄るのである。

竹田城跡は、標高353.7メートルの山頂に位置し、豪壮な石積みの城郭で、南北400メートル、東西100メートルにおよび、完存する石垣遺構としては全国屈指のもの。
この竹田城跡周辺では秋から冬にかけてのよく晴れた早朝に朝霧が発生し、雲海に包まれた竹田城跡は、まさに天空に浮かぶ城を思わせ、この幻想的な風景が「あなたへ」で巧みな映像と共に紹介され、それを一目見ようとたくさんの人々が訪れるようになったのである。実は、この城跡は以前から但馬地方では知られていたところだが、全国的にはそれほど有名でなく「あなたへ」のヒットで脚光を浴び、ホテルが満室状態という結果にしたのである。一つの観光資源が大勢の人々をひきつけるという好例である。
だが、この竹田城跡には欧米人観光客は少ない。
ところで、今、日本で欧米人が多いのはどこか。その第一は東京である。東京駅に行けばすぐにわかる。タクシー乗り場には大きなバックを持った欧米人が大勢並んでいるし、八重洲口のスカイツリー行きバス乗り場にも大勢いる。
訪日外国人は2012年7月、前年同月比50.5%増の845,300人。7月としては過去最高の2010年に次ぐ。それも都心ホテルに宿泊し「ビジネス客の戻りが顕著」という。
尖閣諸島を巡る日中関係の悪化を受けて、地方のホテルや旅館では、中国人団体客の予約キャンセルが出ているが、都内の大手ホテルは欧米からの利用者が中心。中国人の利用者が少ないこともあり、キャンセルは殆ど出ていないという。(日経新聞2012年9月21日)
2012年10月にはIMF総会が開かれるので、一段と外国人が訪れる。
高山市
さて、この東京のように欧米人が多いところが地方に存在していることをご存じだろうか。それは岐阜県高山市である。名古屋から高山本線で二時間以上かかり、その列車も昭和9年10月に開通した単線上を走るので、特急列車は左右揺れが酷く、トイレに行くのにも容易でないほどで、交通が決して便利とはいえない。また、到着した高山駅には、エレベーターもエスカレーターもない。重い大きいバックを抱えた観光客は、階段を上り下りすることになる。日本の主要な交通駅はすべてエレベーターやエスカレーターがあると言っても過言でないほど便利になっている。だが、高山は違う。それでも欧米人は訪れる。
この高山を有名にしている大きな要因は高山祭りである。春の山王祭りと秋の八幡祭りを言う。春祭りは、高山市城山に鎮座する日枝神社の例祭で、安川通りを境にして南側が祭礼の区域、現在屋台は十二基ある。
秋祭りは、高山市桜町に鎮座する桜山八幡宮の例祭で、安川通りを境にして北側が祭礼の区域、屋台は十一基ある。
江戸時代からのこる屋台は、当時の材木商・金貸し業・酒造業・流通関係等、富を蓄えた豪商に支えられ、東西文化をふんだんに吸収して華麗に造られた。そこに屋台大工、漆塗職人、彫刻師が見事な技術で芸術品に育てている。
屋台は各町の通りに面した各々の保管庫に格納され、祭りの際に引き出されるのであるが、各屋台組には、屋台ごと非常に熱心な人が何人か必ずいる。これは一年の生活の中で「屋台が第一」という公言する人たちであり、祭りの時に、ほかの組の屋台に少しでもケチをつけられたり、差し出がましいことを言われたりすると、屋台好き同士でけんかになるほど屋台にひたむきの人である。屋台組では、自分の組の屋台が一番いいと自慢しあい、「オゾクタイ(立派でない、だめな意)屋台」と笑われることが何よりも腹立たしく、高いプライドを持っている。
屋台が定住要因
なお、この屋台組というのは、区域が決まっていて、その組内に入れば屋台組の権利が得られるが、いったん組の外へ出る、つまり、移住すると、どんな功労者でも屋台に乗ったり、曳いたりする権利を失うころになるので、この屋台組を離れない。
ということは、後に述べる屋台組が位置している「重要伝統的建造物群保存地区」から引っ越しをしないということ、つまり、現代的な快適性を捨てても、ここで生活していくことになり、屋台のお陰で昔ながらの保存建物が維持されていくのである。日本各地に祭りはいくつあるだろう。いったいどのくらいあるのか。10万とも30万あるとも言われるが、生活システムとして屋台を中心に置く祭りは他では見られない。これが高山祭りの特徴である。
日韓の団体観光客は領土問題で厳しい状況が続く。一方、欧米人観光客は個人が多く、文化的価値を求める傾向が強い。欧米人観光客増加対策について次号で検討する。以上。
2012年09月20日
2012年9月20日 日独交歓音楽祭(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年9月20日 日独交歓音楽祭(下)
ドイツとの関係づくり
前号に続く「日独交歓音楽祭」についてお伝えしたい。
日本童謡歌唱コンクールで宮内麻里さんが歌った「大きな木はいいな」が金賞を受賞したが、その作詞は高橋育郎氏である。高橋氏は元国鉄マン、JRに移管する際に退職し、以後は童謡作家として活躍しているが、国鉄時代も歌で貢献している。
例えば、千葉管理局で昭和55年、団体旅行に力を注ぎレコード化第一号「シャンシャンいい旅夢の旅」を、次に「お座敷電車なのはな号音頭」を出し振付してもらい歌手と組んでカラオケ列車や落語列車を走らせ、町内からの新人歌手には「房総半島ひとめぐり」「ハッピーランド房総」をレコード化して歌ってもらい団体列車の勧誘につとめ、街の祭りや運動会などにもアイデアを発揮し、増収に貢献した。今は平成4年に始めた「心のふるさとを歌う会」を、日本橋社会教育会館で主催している。
しかし、肝心の童謡の世界は、高橋氏も、同氏が所属する日本童謡協会も、童謡歌唱コンクールのような素晴らしい企画を持ちながら、日本の子供たちが以前よりは童謡を口ずさまなくなっている。少しずつ子供の世界で童謡が下火化しているのが実態である。
この問題について、時折、高橋氏と話し合うことがあって、簡単に解決策が見つかるものではないが、方向性としては「国際化」の流れを取り入れることが必要であると提言している。そのようなタイミングに、カールスルーエの有馬氏が指導する独日協会合唱団が、東京で公演することを希望していることを知り、高橋氏は日本橋に拠点を持っているのであるから、お互いが交流することで、両者の希望が適えられるはず。
つまり、有馬氏は東京の中心である日本橋で公演開催が出来、高橋氏はドイツとの交流で童謡の国際化へのキッカケづくりになる、という両者のメリットをつなげるべく、カールスルーエ合唱団一員で筆者の通訳をしてくれている三樹子さんを紹介したわけである。
三樹子さんは日本人であるから言葉の問題はなく、高橋氏は早速にメール連絡し、有馬氏とも関係づくりし、日本橋社会教育会館事務局とも連携し、独日協会合唱団「デァ・フリューゲル」(注 翼という意味)の来日公演計画づくりに入っていったのである。
館山市でも開催
高橋氏がカールスルーエと交信を始めてすぐに、千葉県館山市の踊りの師匠、里見香華さんを高橋氏から紹介された。里見さんは滝沢馬琴作の南総里見八犬伝に書かれた里見家の末裔で、「里見氏正史物語をNHK大河ドラマに」と活動されていて、今年の五月にはNHK放送センターで、NHK幹部に署名活動の束と一緒に提案したという南房州をこよなく愛する素敵な女性である。さらに、国際的な行動派でもあり、一昨年はブラジル千葉県人会会館落成式に森田千葉県知事と共に出席し、祝舞として自ら振り付けをされた高橋氏の作詞「ああ、武士道」を踊り、大好評を得たという。
この里見さんと高橋氏と三人で会ったのは、千葉市駅近くの館山寿司の店であった。それまで知らなかったが、館山は魚の種類が多く、寿司店数が人口比で日本一ではないかと言われているほど寿司が有名で、確かに、その後何度か館山で寿司を食べたがうまい。
寿司はご存じのように世界の食べ物になっている。世界中の大都市には必ず美味い寿司店があるようだが、やはり、世界の観光客に聞くと、日本で食べると一味異なり、別格の本もの美味さだと称賛する。
上海で日本ツアーの添乗員を務める中国人女性から聞いたが、日本に行って最大の楽しみは寿司だという。上海とは比べ物にならない美味さだという。その通りだろう。
その日本でも美味いと言われている館山の寿司、それを食べながら里見さんと話していると、館山は関東地区では観光地として有名であるが、果たして世界レベルで論じた場合どうなのかという話題になった。
そこで、世界の観光地にはランク付けがあり、その結果で観光客が増減することを里見さんに伝えると、突然、眼を光らせて、もっとその仕組みを詳しく話してほしいという。
では、とお伝えしたのはシュラン旅行ガイドである。このガイドに掲載されている東京周辺地図を見ると「東京」「日光」「高尾山」「富士山」の四カ所が三ツ星で、オレンジ枠で大きく表示されていて、高尾山に欧米人が多く訪れるようになった理由は、この三ツ星が要因。イエローで囲まれた二つ星は「鎌倉」「伊豆半島」「修善寺」「下田」の四カ所、黒字に赤線が引かれている一つ星は「横浜」「箱根」「中禅寺湖」「河口湖」の四カ所となっていて、残念ながら館山は選ばれていなく、当然に掲載されていない。
どうして掲載され、何故に表示されないのか、その疑問を解く鍵は簡単明瞭で、このガイドブック作成のライターが訪問していないからで、訪問しないのはライターの手許にその観光地の情報が届いていないのである。
という意味は、訪問させるような情報を観光地が発信していないということで、具体的に言えば英語か仏語による観光資料が作成されていないからだと解説したところ、里見さんの眼はワールドカップのアメリカ戦決勝でシュートを決めた澤選手のように、新たなる好機を捉えたというような鋭い輝きに急変化する。
里見さんと別れて二三日後、里見さんから電話があり、館山で観光協会と市の観光課長へ「外国人観光客誘致」について解説をするよう要望された。さすがに行動派の面目躍如で、あの時の輝く鋭い眼が市役所と観光協会を動かしたのである。
その後、いろいろ打ち合わせや調整があったが、今年の4月に館山市で「外国人誘致セミナー」を開催することが出来た。講師に筆者の友人でフランス人のガイドブックライターであるリオネル・クローゾン氏を迎え、併せて房総半島の取材を行ってもらい、クローゾン氏講演会とパネルディスカッションを開いたのである。
これ等一連の動きから、高橋氏が有馬氏と連携して計画化してきた独日協会合唱団「デァ・フリューゲル」の来日公演企画も、当然に里見さんの耳に入って、再び、国際派の里見さんは館山国際交流協会に働きかけ、8月末に館山と日本橋で「日独交歓音楽祭」が開催されたわけである。
館山は千葉県南総文化ホールにて、日本橋は日本橋社会教育会館にて開催されたが、様々な方面からの出演プログラムが組まれ、二会場とも満員、大盛況であった。
当日はいくつかの市の市会議員も来ていて、所属する市もドイツと文化交流したいと高橋氏に申し入れがあったとのことで、外国との関係づくりに少しでも貢献できたとすれば、大成功の「日独交歓音楽祭」であったと思う。
また、今回の「日独交歓音楽祭」が開催されたことは、外国との取っ掛りが難しいと思って、海外との民間交流を逡巡し、海外進出を躊躇している経営者に参考になったのではないかと思う。
外国との関係づくりは一般的には難しいと思いやすいが、いろいろ考えれば方法はあるわけで、その重要な一つとして外国との接点キーワードを挙げれば「日本語教室」の活用であろうと思う。日本に興味持つ外国人の多くは、日本語を学びたいと思い、当然のごとく「日本語教室」を訪れる。
また、教師は日本語が出来るし、現地在留日本人が教師をしている場合が多いので、外国語が苦手という言葉の問題はクリア可能である。カールスルーエの有馬氏が合唱団の会員を増やしたのは、日本語教室にアプローチしたからだと有馬氏は述べており、さらに、東京での公演を希望していることを筆者に伝えたのは、合唱団所属で通訳の三樹子さんである。
今回のように外国の地に住む日本人と、その方が所属している日本語教室や趣味の会を通じれば、割合簡単スムースに外国人とつながりを持てる。
経営者として、未知の海外リスクを勘案し、海外展開を躊躇するという気持ちは当然だとしても、日本国内でのシェア争いで「外部からみてあまり違いの分からない、ちょっとした内容」という差異化に、凄まじいまでの意欲と、工夫努力を続けている現状を見ると、随分無駄なコストと体力を消耗しているわけで、それよりも日本の素晴らしい品質・技術を持っていけば、かなり高い成功率となると思っている。
そのためには狙うべき外国の地情報を「集める」作業を行い、日本国内情報も「集め」、それらを狙い定めた外国へ発信すべく編集し、外国の地と何かのキッカケづくりに努力する事だろうと思うが、その成功例が今回の「日独交歓音楽祭」である。企業の外国進出へ参考にお伝えした次第。以上。
2012年09月07日
日独交歓音楽祭(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年9月5日 日独交歓音楽祭(上)
異業種交流会にて
先日、異業種交流会で講演する機会があった。中小企業経営者などが多く、熱心に聞いていただいた。講演後、参加者と名刺交換し、質問を受けて気づいたことがあった。
それは、当然とはいえ、改めて確認したことであるが、「日本から日本を見る」という思考になっているということである。
当方は、毎月海外に出かけているので、必然的に「世界から日本を見る」という思考を展開すべく心掛けているが、やはり「そうか」と感じた次第である。例えば、世界的に有名なバラの花をテーマに起業したベンチャー経営者と名刺交換し、その事業概要をお聞きしたので、「その花はパリのブローニュの森のバガテル公園が著名ですね」と伝えると、怪訝な顔をする。初めて知ったらしいのである。
外国とつながりをつける
新しい事業を始めるに当って、まず必要なのは「集める」作業、つまり、自らが狙う市場の情報を集めておくことだろう。
また、その情報は世界中にあるわけで、日本国内にとどめておくことは、狭い範囲での「集める」作業になってしまうから、発想に広がりを欠く傾向になりやすい。
だが、それらを補って余りあるのが、起業家の凄まじいまでの意欲と、工夫努力であり、これを武器に強力に国内で事業を展開している事例を多く見る。
しかし、その工夫と努力によって、他企業に差をつけようとしている内容を少し深く分析してみると、その差異は「外部からみてあまり違いの分からない、ちょっとした内容」になっているように感じる。
その上、日本国内の流通サービス業における客対応力は、世界的にみて高く評価されているように、細やかな気配りがきいた上質レベルであって、この対応に慣れ切った日本の消費者を相手にするのであるから、差異化へ投入するエネルギーと、そこから得られるアウトプット果実を比較すると、あまり効率的ではない。
ということで、情報を「集める」作業は、国内だけでなく、外国の情報も集め、その過程で外国人とつながりをつくり、それをきっかけとして外国進出も検討した方がよいのではと、名刺交換したベンチャー起業経営者に話したのであるが、「話は分かるが外国とのとっかかりがない」ので無理だという顔をする。
多分、このような起業家が多いのではないかと推察する。そこで、今号では、先日開催した「日独交歓音楽祭」、これは民間外交として展開したのであるが、その経緯をお伝えすることで、外国人との接点はこのようにすると出来るという事例を紹介したい。
縮小していく国内市場対策として、外国進出が大事であることをすべての経営者は知っているが、そこへの道筋に悩んでいる方への一つの事例として参考にして頂きたい。
ドイツ・カールスルーエの合唱団
ドイツ南西部に位置するバーデン・ヴェルテンベルグ州の都市カールスルーエ(Karlsruhe)は、日本ではあまり知られていない。日本人には温泉保養地として著名なバーデン・バーデンの方が知られている。そのバーデン・バーデンから29キロメ-トル、急行列車でたったの15分のところにカールスルーエは位置している。
カールスルーエは城を中心に町がつくられており、街並みを歩いていくと、城の両側の側面から延びる道路が、城を基点として扇形に延び、その扇形の中に中心市街地が入っているので「扇の街」と呼ばれていることがよくわかる。
また、街の中心にはマルクト広場があるが、この広場を設計したのがヴァインブレンナ-で、バーデン・バーデンのクアハウスも設計したヨ-ロッパで屈指の設計家であり、市民はこの広場でくつろぎ、お祭りに興じるのである。
このカールスルーエには、ここ10年くらい毎年訪問しているが、カールスルーエには国際的に著名な国立音楽大学があり、世界中から留学生が集まっていて、その教授陣に二人の日本人がいることが分かってきた。
一人はドイツ・リート歌唱で国際的に高い評価を得ている、声楽科歌曲クラスの白井光子教授、もう一人はベルリン・フィルハーモニーホールをはじめとする世界の一流舞台で活動を重ねる打楽器奏者の中村功教授である。
白井教授とは、カールスルーエ市街の散策中や日本食レストラン、マルクト広場の合唱団コンサート会場などで何度もお会いしているが、この白井教授に師事した有馬牧太郎氏がカールスルーエ「独日協会」の合唱団を指揮・指導している。
有馬氏は東京芸術大学卒業後、カールスルーエ音楽大学に留学、卒業後、同大学の声楽科講師を兼ね、現在いくつかの合唱団の指導もしていて、カールスルーエの合唱団も有馬氏の指導下にある。
この合唱団は、マルクト広場でのお祭りには必ずゲストとして歌を披露、それも全員が着物姿で登場し、最後には必ずソーラン節で盛り上げるので、客席から盛大な拍手が鳴り響く実力派である。
実は、この合唱団の有力メンバーであるチズマジア・三樹子さんが、筆者の通訳を担当してくれている関係で、自然に合唱団のメンバーとも親しくなり、自宅へ訪問し、ビアホールでお会いしているうちに、メンバーが合唱団に入るキッカケの実態が分かってきた。
最初は、日本に対する興味からで、その興味と関心内容は人によって異なるが、結果として日本語を学びたくなり、どこへ行けば日本語を教えてもらえるかを調べているうちに、「独日協会」の日本語教室を見つけ、そこで日本語を勉強しているうちに、日本の童謡等が歌われている合唱団の存在を知ることになる。
「独日協会」とはドイツ国内各都市に存在し、日独友好関係に寄与している民間組織であって、日本ファンの集まりである。
さらに、合唱団は既に2007年に東北地方を中心に日本公演をしているように、合唱団に参加すると憧れの日本へ行けるチャンスもあるので、日本の歌を通じて熱心に日本語を勉強することになり、一段と日本に対する興味を強くもっていくのである。
この独日協会合唱団が、再び2012年の夏に日本公演を計画していると三樹子さんから二年前に聞き、加えて、東京でも公演したいという希望があると聞き、ふと東京・日本橋で合唱団を主催・指揮している高橋育郎氏を思い浮かべた。
日本童謡歌唱コンクール
高橋氏とは長い友人であって、童謡の世界では知られている作詞家である。童謡とは広義には子供向けの歌を指し、狭義には大正時代後期以降、子供に歌われることを目的に作られた創作歌曲を指すように、我々が幼年期からよく馴染み、歌ってきたものである。
しかし、高橋氏はこの古い歴史のある童謡範疇を超えた、新しい現代感覚の作詞を創作していて、代表作として「大きな木はいいな」がある。
その高橋氏から一昨年11月、第25回日本童謡歌唱コンクールで「大きな木はいいな」が歌われると聞き五反田の会場に出かけた。
童謡歌唱コンクールとは日本童謡協会主催で、「子供」「大人」「ファミリー」の三部門があり、まずテープによる審査を各ブロック単位で実施し、その上位者が8月から9月にかけて行われるブロック決勝大会を経て、金賞受賞者が11月のグランプリ大会に出場し、金賞・銀賞・銅賞が決定するシステムで、テレビ朝日系列で放映される。
一昨年のコンクール会場で一番前の席に座り、全国から勝ち抜いた童謡を聞いたが、さすがに皆さん上手いなぁと納得し続けていると、「大きな木はいいな」を歌う東海・北陸ブロック代表の宮内麻里さんが登場し、細身の体を少し傾け歌いだした。その瞬間、彼女のソプラノが、奥深き山の深淵から湧き出てくる清らかな澄んだ水の流れのように、ステージから会場の奥まで通り抜け、歌い終わったときには、これは「グランプリだ」と確信したわけだが、結果はその通りで、みごとに大人部門の金賞を受賞した。
また、彼女の歌い方で特に感銘したのは「みんなではくしゅを してあげよう」というフレーズであり、後日、彼女に確認すると「ここが最もこの歌で好きなところ」という。次号続く。以上。
2012年08月21日
2012年8月20日 小国大輝論(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年8月20日 小国大輝論(下)
パイ拡大思想
前号の上田篤著「小国大輝論」を続けて紹介する。『パイ拡大をよし』とする思想はいつ、どこでうまれたのか?
それを上田氏は明治四年から明治六年まで欧米派遣した岩倉使節団にあるとする。
「岩倉使節団が欧米各国を視察したとき、一行が、はじめアメリカ、イギリス、フランス、ドイツ、ロシア、オーストリアそれにイタリアといった七か国の大国のどれかを日本の将来モデルの候補としてかんがえていたかはうたがわしい。というのも使節団は、それら大国のほかにベルギー、オランダ、ザクセン、スイス、デンマークそれとスウェーデンといった小国六か国をも訪問しているからだ。むしろ使節団はこれら小国に大きな関心をよせ、かつ、期待感をにじませていた。それも、日本の国土の小ささや資源の少なさをかんがえれば、とうぜんのことだったろう。
ところが、使節団が日本を出発する前年に普仏戦争がおき、そのけっか小国プロイセンは大国フランスに勝利した。そして使節団がヨーロッパに到着したときには、プロイセンを中心とするドイツ帝国がうまれていたのである。
そうして一行はドイツ帝国で『鉄血宰相』の異名をとるオットー・ビスマルク(1815~98)の演説に魅せられた。『小国が生きていくためには国際法などおよそ役に立たず鉄と血によるしかない』。ナポレオンにおさえられていたがそれを跳ねかえした、というプロイセンの歩みは、片務的な『日米修好通商条約』を飲まされて苦々しいおもいで開国した日本人にものすごい共感をもってうけいれられた。 すると日本もまた『日米修好通商条約』をうちやぶるためには武闘路線をもって大国になるしかない。
こうして使節団一行は、ドイツにおいて『小国だったプロイセンが大国ドイツになった』というなまなましい現実をみせつけられたことが大きかった。ここに道徳どころか国際法までも無視するビスマルクの演説に共鳴して、大久保利通の『大国志向』がうまれていった、とおもわれる。『日米修好通商条約』を打破するための手段としての『富国強兵』が、こうして日本の国是になっていったのである」
小国路線選択もあった
日本が小国を見習うべきだったのに、大国化したドイツを模範にしたことから、今日の経済大国化に進んだという見解である。もし仮に、岩倉使節団の欧米視察結果を受けて小国を見習い、日本国の国是としたらどのような国家になっていたであろうか。
実は、この大国・小国路線の選択は、維新の元勲である大久保利通と木戸孝允の違いであった。木戸孝允は日本がスイスを目指せばと考えていたようである。それを「小国大輝論」が、イタリア統一運動をすすめたレフ・イリイッチ・メーチコフが見た見解として木戸孝允に対し、次のように述べている。
「日本議会の招集を夢み、ほどなくすばらしい炯眼をもってこう洞察した。すなわち長期にわたる共同体制をそなえたスイスこそ、領土の狭さにもかかわらず、多様な地域的、歴史的特性をもった日本のような国の為政者にとって格好の政治的教訓になる」
大久保とは大きく異なる見解で、この当時から大久保と木戸の対立があったが、結局、有司専制といわれた大久保への権力集中によって富国強兵路線に向かって今日に至っている。
改めてノルウェーを調べてみると
ここで国土面積が38.5万キロ㎡と日本とほぼ同じで、人口500万人のノルウェーを改めて見つめてみたい。
① ノルウェーはEU加盟を国民投票で拒否している。理由には様々な見解があるが、市場経済優先ではノルウェーの持つ特性、福祉の後退や女性の権利の後退することへのという不安があげられる。結果として、現在のユーロ危機には巻き込まれていない。
② ノーベル平和賞はノルウェーである。文学賞などの他のノーベル賞がスウェーデン・ストックホルムで授与されるが、平和賞はノルウェーのオスロで授与される。ノルウェーが「平和」という絶対的な全世界共通の社会価値について、その格付け機関として位置していることは、国家ブランドとして世界に輝く存在となっている。小国ゆえになり得る立場であろう。
③ ノルウェーの劇作家のヘンリック・イプセンは世界的に有名である。代表作は勿論「人形の家」であり、日本では婦人解放論者として受け入れられ、新しい社会思想家として受け入れられている。
④ ノルウェーを一般的な地図で見ないで、北極点から眺めてみるならば、その見方は大きく変化する。北極というとロシア、シベリアと思いがちだが、実は、極点近くに一番島嶼が広がっているのはカナダ、それから巨大なグリーンランドがデンマーク領。米国はアラスカを領有しているが、これらの国が面している北極海の大半は、永久流氷に閉ざされている。これに対して、メキシコ暖流が注ぐ北大西洋海流側は北緯80度過ぎまで海が凍結していない。「暖かい北極海」のど真ん中には、ノルウェー領のスヴァールバル諸島の存在が目を引き、よく見ると「暖かい北極海」海岸のすべてが、ノルウェーとロシアである。この「暖かい北極海」がそのまま巨大な油田と推測すると、この油田の恩恵に与っている国は、すべてノルウェーであることがわかる。
ここにノルウェーがEUに加盟しないひとつの重要な理由がある。ノルウェーは「OPEC(石油輸出国機構)非加盟の世界第3位の産油国」なのに、フィヨルド地形を利用した水力発電や潮位差発電などで国内需要を賄い、石油とガスは輸出に回しているのである。
また、海洋油田というのは開発とリグ建設や海底パイプ施設に莫大な投資をつぎ込むが、いったん生産が軌道にのるとやることは大部分コンピューター制御できるので、GDPの約20%を稼ぎだすにもかかわらず、石油生産に従事する労働者は人口のわずか2%。
とても効率がよいというところから、名目GDP一人当たりは97,254ドル。(2011年)と世界第三位の富裕国となっている。
ノルウェーの財政黒字
最後に最も大事なことにふれたい。野田政権が「まずは増税ありき」と消費税の増税をする目的は財政再建、国の借金経営を是正であるが、ノルウェーはノルウェーの2012年見込み財政黒字は4080億クローネ(6兆1200億円)であり、これとは別に石油輸出による収入は大部分「石油基金」にプールされ、2012年3月末時点の運用資産は3兆4960億クローネ(52兆4400億円)となっている。
人口が500万人であるから
(6兆1200億円+ 52兆4400億円)÷ 500万人=1172万円
という国民一人当たり黒字額となる。日本と正反対の良好財政である。それなのに所得税50%、消費税25%という高率となっているが、既にみたように国民は文句を言わないのである。
国民の税に対する考え方が違うのであるが、その背景には政治が国民に納得できる福祉や公共サービスが充実を示しているからであって、ここきが日本と大きく異なるところである。
日本はどうすべきか
日本は世界一の財政赤字国。政治の進め方でこのような実態になっているのであるが、ここからどう脱却するのか。様々な見解があると思うが、基本的には次の三点ではないかと思っている。
① 国家への納税額を増やす政策を採る。そのためには経済成長によって税収を増やすとともに、やはり消費税増税政策は受け入れないといけないだろう。
② 公務員人件費の削減が必要である。かつては民間給与を大きく下回っていた公務員人件費が、いつの間にか大きく上回っている。これも政治の問題であるから、政治で解決していかねばならない。
③ 日本は身の程を知った方がよいだろう。大国と思うから「ジリ貧大国」等と国民を暗い気持ちにさせる識者が大手を振って講演に歩くことになる。もともと国土は狭く、人口は少なかったのだから、人口減に向かうのは、人口適正化への道筋と考え直し、受け入れることで、大国意識を薄め、日本の特性条件を活かした国づくりが必要であろう。
つまり、資源小国なのだから「技術大国」へ。国土小国なのだから世界に稀なる四季を活かした「自然大国」へ。歴史と伝統に輝く文化を発信することで「文化大国」へ。
明治初年の岩倉使節団以降、パイの大きさを競う大国化を目指した日本を、東日本大震災を機会に、身の程を知るよう、別角度から考えなおして、小国であるが次元の異なる輝く大国にしたいと思う。
ノルウェーのフィヨルド景観を眺め国民に直接聞くと、日本国家運営へのヒントが多々ある。バカのひとつ覚えで経済成長のみを追うのでなく、生活重視への変化が必要であろう。以上。
2012年08月06日
2012年8月5日 小国大輝論(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年8月5日 小国大輝論(上)
消費税増税
消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案に対して、国民からは厳しい意見が多い。日本経済新聞社とテレビ東京が7月27日~29日に共同で実施した世論調査では、野田内閣の支持率は28%と急落し、消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案への賛成は41%、反対が49%である。
また、これを無党派層に限れば賛成が30%にとどまり、反対が57%になっている。この背景に「5%増という数字ばかり先に決まっていて、肝心の中味がない」という風評誤解があるという見解が多い。
確かに2015年10月に消費税が10%に引き上げられた場合、増税分5%の内訳は、国の年金国庫負担金を引き上げるための財源に1%、高齢者増加による社会給付財源が3%、消費税増税に伴う物価上昇に対応するための給付維持分が1%というように、基本的な大枠は決まっているので、増税だけを先に決めたという批判は的を得ていないという見解もあるが、一般的国民の気持ちは「まずは増税ありき」となっている。
ノルウェー・ベルゲン
7月上旬はノルウェー・ベルゲン、ハンザ同盟の商館がある世界遺産の旧市街と、フィヨルドの観光基地でもあるが、その一企業を訪問した。
社長に日本で消費税が話題となっているので、ノルウェーの25%という消費税について負担になっていないかまず聞くと「全く問題としてない」という明確なもの。ちょっと期待外れであったが、日本のインターネットで検索してみると以下の内容と同じであった。
(質問)なぜ、スウェーデンやノルウェー、デンマークは消費税の税率が25%と高いのですか?
(回答)福祉や公共サービスが充実しているからです。高福祉高負担といって高い税率が掛かるかわりに老後は貯金が無くても問題なく生活が送れる社会な為、国民からも不満がでません。日本はとにかく借金を返す為に消費税を上げようと福祉や公共サービスのプランが見えない増税を打ち出している為、国民からの反発も強くなかなか増税にはつながりません。日本の政治家も目先ではなく20年30年後のビジョンをしっかりもって政治をしてほしいものですね。
この回答からも、日本国民の野田政権に対する支持率下落の要因が分かるが、もうひとつ紹介したいのはアメリカの新聞記事である。(Inc・クーリエジャポン2012年7月号)
タイトルは「税金が高いノルウェーのほうが、なぜ米国より起業しやすいのか?」という記事で、その中で油田採掘現場に人材派遣する会社を起業した社長の言葉として次のように書かれている。
「いい税制ですよ。公平ですからね。税金を払うのは、商品を買うようなものです。だとすれば大切なのは商品に対する金の払い方でなく、商品の品質でしょう」と。
この社長は政府のサービスに満足していて、自分の払っている対価は妥当だと考えていることがわかる。もう少し紹介する。
「ノルウェー国民として、彼は連邦政府に所得の50%近くを納め、その他にも純資産のおよそ1%に相当するかなりの額を税金として払っている。さらに25%の消費税も払っているのだ。 2010年、この社長は所得と資産に対して個人として10万2970ドルの税を納めた。私がこんな細かい数字を知っているのは、納税申告書がウエブ上に公開されていて、誰でも、そしてどこからでも調べることができるからだ。納税者が有名なスポーツ選手であれ、お隣さんであれ、調べるのは難しくない」
つまり、ノルウェー人は税金の支払いを「購入」、つまり、サービスの対価と払うことだとみなしていることであで、明らかに日本人とは異なる。
日本に戻って何人かの経営者にノルウェーで経験したことを伝えると、皆一様にビックリする。日本では税金を「お上に取られるものだ」と認識しているのであって、考え方の違いは大きい。
小国大輝論を読んで
先日、上田篤著「小国大輝論」を読んでみた。なかなか深みのある内容で参考になったが、特に感じたのは以下の内容である。著者は元建設省技官であるから官僚であるが、その官僚が日本の官僚の問題点を三つあげている。
「かれらの政策決定において非所掌者である他の官僚たちの賛同をうるために、しばしば『経験主義』『物質主義』『鎖国主義』ともいうべき議論がおこなわれる。だがそのために、しばしばおもいがけない陥穽におちいることがある。
第一に、経験主義であるために経験しなかったことに弱い。未来もすべて過去の経験でしか推しはからないからだ。だから地震予測もすべて過去の経験による。したがって経験しなかったことについてはまったくお手上げである。こんどの大震災で『想定外』ということばが乱発されて国民の顰蹙をかったわけだ。
そういう経験主義だから直観ということは排される。しかしさきにのべたように現場にでれば津波は直観できるのだが、だが、誰もそれをやらないから官僚は『未来痴』である。
第二に物質主義であるから、孔子ではないが『快刀乱神』といったものは避ける。神や仏というものをまったくみとめない。したがって今回の大震災でも、貞観十一年(869年)に仙台平野でおきた大津波のことは考慮されなかった。
なぜなら、それをつたえる『日本紀略』そのものに神や怪異の話がおおいからだ。したがって貞観津波が無視されただけでなく、そのとき津波の到達時点につくられた波分神社の存在もみなかった。その波分神社から海側は『貞観津波がやってきた』目印だったのだが、それも無視して開発はすすめられた。すなわち『鬼神』を避ける『鬼神痴』とわたしはみる。

第三に鎖国主義である。日本は島国だから、だれでも国内のことなら知らない土地でもおおよその見当がつく。しかし外国となるとさっぱりということがおおい。
今回も、2004年12月にインドネシアのスマトラ沖でおきた『マグニチュード九・〇の地震、それによる高さ十メートルの津波、三十万人の死者』は日本にはおよそ関係ない、とみていた。それは調査の結果でなく、はじめから『別世界のこと』で『外国痴』である。
以上の『未来痴』『鬼神痴』『外国痴』つづめていえば『未痴』『鬼痴』『外痴』の三痴は、すぐれた近代官僚をもつ日本の役人の、いわば泣き所といってもいいものなのである」
パイの拡大方針
もう少し上田篤著「小国大輝論」の紹介を続けたい。
「そのけっか、原発の『経済性・効率性』を追求するあまり、今回、役人のこの『三痴』の欠陥をつかれて『想定外という未経験』『貞観津波の無視』『スマトラ沖津波の無知』という悲劇の結果になったのである。それら罹災状況の一部始終をみていた国民は、さきにものべたようにこれを『人災』とみ、これから長くつづくであろう結果の恐ろしさに当惑している。ために日本社会はふかい沈滞におちいっている。
ではこれからどうするのか? 問題は『人災』ということである。それについてはすでにいろいろのことがいわれているが、わたしはその元は『パイの拡大』にあるとおもう。
だれがかんがえてもわかることだが、なにごとも『パイの拡大』つまり単純な成長主義をつづけていけば、さいごは破局である。
『パイの拡大』つまり国内総生産を高めるのも結構だが、それは単純にどこまでもつづくものではないだろう。人間には欲望があるから『関係者はパイを拡大したい』とおもうだろうが、しかし『パイの拡大』の最後は破局に決まっている。
であるのに、なぜパイを拡大するのか? 問題は破局にみちびくような『パイ拡大をよし』とする思想にある。それあるかぎり、破局への道程はかぎりなくある」次号へ続く。以上。
2012年07月23日
2012年7月20日 考えるという脳作業・・・後半
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年7月20日 考えるという脳作業・・・後半
「考える」とはどういう脳作業を意味するのか
前号に続いて「考える」を具体的に検討してみたい。我々は幼少時に親から「考えろ」と言われ、学校でも「考えなさい」と言われ続け、社会生活でも同様の指摘を受けることが多い。しかし、この「考える」ということは、具体的にどういう脳作業なのか、それについては親も学校も会社の上司・先輩も教えてくれていない。特に、学校では知識を体系的に教えているが、自ら考えるためにはどうすることが必要だという、肝心要なことは教えてくれないのに、先生から「考えなさい」と言われ続けてきた。
我々は、ここでもう一度「考える」ということを、洗い直し、自らの日常生活に取り入れていくことで、日常習慣化していく、ということを検討したらどうだろうかと提案したい。つまり、「考えよう」と意識しなくても、自然に「常に学び考え続ける」状態にすることができれば、「考える」ことは生活習慣になって無理なくできる。
ということになれば、生活習慣病ではないが、思考することを生活習慣化するのであるから、無理なく、いつでも考えることができるはずで、そのような日本人が増えて、それらの人達が企業に入っていくと、延岡教授、遠藤教授、伊藤所長の指摘に適う人間になれ、その結果意味的価値を創りだせ、「際立つ存在」の経営体に変身出来るはずだ。
考えることとは
では一体、考えるとはどういう脳の作業なのだろうか。世の中には専門家を含め、様々な見解が披瀝されているが、当方は以下の五段階ステップが脳細胞の中で意識的に行われることで「考える」作業が進むと認識し、日常習慣化作業として実行している。
① 集める⇒知識や資料・情報は多くあった方がよく、この集めることが基本である。
② 分ける⇒集めた情報は、必要な項目ごとに分けてファイル化する。
③ 比べる⇒必要なテーマ・研究内容にしたがって分けたファイル・情報を比べる。つまり分析作業である。
④ 組合せる⇒分析した結果の情報を、目的・目標に基づいていろいろ組合せする。これが実はアイディアの源泉で、様々な組合せが行うほどアイディアは多く生まれる。
⑤ 選ぶ⇒組合せした中から選択する。決定作業である。この決定が最も大事で、この際に時代の方向性を掴んでいるか、つまり第一ステップの「集める」作業が時代方向性に合致していたかどうかというところが問われるわけで、時代性・時流の捉え方が狂うと大問題になる。日本のテレビ事業がこれに該当する。
最近体験したこと
今までに何回か「日本観光大国化」について具体的提案をし、各種セミナーや討論会を各地で開催してきた。その背景としては、日本が人口減に向かっている事実を考えれば、日本への観光客を増加させ、滞留人口を増やす戦略は重要であり、そこに微力ながら貢献していきたいと思って行動しているからである。
しかし、全てのプロジェクトが順調に進められるということはなく、全く関心を呼ばず、返って誤解を受け頓挫する事例も多々あるが、一番問題なのは「外国人観光客を増やしたい」というなすべき「戦略」は十分に分かっているが、何ら手段を講じない人達がいることである。
どうして様々な方法を駆使して外国人観光客を増やさないのか。それは過去に様々な方法でトライしたが、それが悉く失敗して、脳細胞の中に「もういい、したくない」と思ってしまっている場合である。
ここに至ると最悪であって、こういうケースでは、行政と住民との人間関係が複雑に絡み合って、憎悪とも言うべき対立が生じているので、そこに入るとこちらが火の粉を浴びる結果となるから、折角の世界的観光資源があっても立ち入らないようにすることになる。
先日も、フランスで著名なジャーナリスト男性と、ハーバート大学院卒博士のアメリカ人女性と一緒に、関東地区の海辺の市を訪問した。いろいろ観光ポイントを案内してもらっているうちに、二人の外国人が異口同音に述べたのは「あれはすごい。あれは外国人が最も関心持つ観光素材だろう」というポイントがあった。
そこで、市長、観光部門の関係者に伝え、勿論、直接同行外国人からも話をしてもらったのだが、全然動かない。そこで、その市出身の友人に動かない背景を調べてもらうと、過去に市の有力者がコンサルタントを導入し、様々な仕掛けを講じたのに、全くうまく行かなかったという事実が判明し、もう他からの観光政策の提言はコリゴリだというより、そういう提案には嫌悪感さえ抱いている、という事実が判明した。
したがって、今は誰も何も動かなく、昔栄えた旅館は倒産していくという自然淘汰状態のままになっている。残念だが仕方ない。
この状態を「考える」という視点で分析してみるならば、まず、提案を受け付けないのであるから情報を「集める」作業を拒否していることになり、第一ステップがスタートしないわけであるから、最初から「考える」という行為を諦めていることになる。
このような事例は各地で多いのではないかと推定しているが、これでは人間の脳細胞を使わず、ロスを続ける思考習慣化しているといわざるを得ない。
うまく行った事例もある
一方、非常にスムースに展開する場合も当然にある。
播磨灘に事業所を位置している企業から「世界遺産の姫路城までは外国人が大勢来るのに、すぐそこの播磨灘海岸には外国人観光客が少ない」という問題提言と、その解決策の相談を以前から受けていた。
いろいろ考えて、ふと、前述のフランス人ジャーナリストに話すと「そうならば播磨灘を海外にPRするために取材し、自分がレポート記事を書こう」ということになり、4月に当方も同行し一緒に播磨灘海岸各地を歩き回って、レポートは秋に完成することになっている。
この播磨灘レポートは、英文と仏文で「播磨灘文化・観光ホームページ」として世界に発信するのであるが、意欲的で前向きな経営者がいる場合は、行政とは関係なく日本観光大国化へ、ひとつの道筋貢献が進むことになる。
つまり、この企業にとっては自社の商品を、播磨灘産ブランドして世界に発信しているのであるから、当然そのPRになり、売上拡大につながり、また、播磨灘各地の観光地にとっては、外国人に知られる一助になって、いずれ時間軸の推移とともに、観光客が増えていくという結果が期待できるのである。
以上は、一企業の経営者判断が播磨灘の観光に貢献する事例であるが、ここで大事なことは「著名なフランス人ジャーナリスト」の投入ということである。
日本人ライターでも優れた文章は十分に書ける。だが、今回は外国人に読んでもらい、来日誘引したいわけであるから、ライターは外国人の方が適している。
そこで、書き手としてフランス人ジャーナリストと、NYタイムス寄稿ライターの二人を検討したが、結局フランス人が一番適していると考えたわけである。
フランス人が最も適しているという理由は、フランスが世界一の観光大国であり、文化ブランド国家であるから、そこのノウハウを肌身で持ち合わせているわけで、加えて、この人物が世界的大手の出版社が高く評価している人材で、ミシュラン社やアシェット社の観光ガイドブックのライターでもあるので、その方面にも働きかけてくれるという期待もあって今回選定したわけである。
外国に頻繁に出かける中で、時間軸とともに知り合いが増え、人脈ができていくが、これも「考える」作業の第一ステップの「集める」作業に該当して、今回はたまたまその中から必要な「戦略要素」によって人脈の「分ける作業」をし、次に「人物を比べる作業」をして、続いて「必要な人物と要求される内容を組合せプランつくり」して、「最後に選択し決定作業」をしたわけである。
これが「播磨灘文化・観光ホームページ」つくりで行った背景であるが、もうひとつ重要な要素として時代性がある。
フランス人が書くレポート、そこに当然に今の時代性が入ってくるだろうが、それと播磨灘が持ち合わせている観光ポイントとが合致していなければ、いくらホームページで紹介しても世界の人々は見ないし、来日しないだろう。そのところの確認作業は、人間の直感的な分野であって、理論的に説明が難しいのだが、フランス人から原稿が届いた時点で、今の時流に合致しているかどうか、検討しチェックする予定である。以上。
2012年07月10日
2012年7月5日 考えるという脳作業・・・前半
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年7月5日 考えるという脳作業・・・前半
日本人は「考える」ことについて具体的教育を受けていない
我々は幼少時に、親から「考えろ」と言われ続け、学校でも「考えなさい」と言われ続け、社会生活でも様々なタイミングで同様の指摘を受けることが多いのだが、この「考える」ということは、具体的にどういう脳作業なのか、それについては親も学校も会社の上司・先輩も教えてくれないままになっていると思う。
このあたりでもう一度「考える」ということを、洗い直し、自らの日常生活に取り入れていくことで、日常習慣化していく、というようなことを検討しないと、世界から「日本人は考える力が弱い」と指摘受ける結果となるだろうと懸念している。
伊藤穰一MITメディアラボ所長の指摘
伊藤穰一MITメディアラボ所長が、NYタイムスの社外役員に就任した。(日経新聞2012.6.23)

伊藤氏は1966年生れ46歳であり、日本におけるインターネット普及の第一人者で、MITメディアラボ所長には、2011年9月に約250名の候補者の中から抜擢された人物である。
その伊藤氏が次のように語っている。(クーリエ2012年1月号)
「従来のビジネスというのは、ある程度学んで効率を良くして、なるべく同じ作業を繰り返すことで生産性を高め、おカネを蓄積する。で、それを守る。だから、学びを止める。効率良く同じことを繰り返し、財産を蓄積するのが”オトナ“の世界なんですよね。
でも、変化の激しい現代の社会では、そのやりかたはもう通用しない。変化に応じて、効率は良くないかもしれないけれど常に学び続ける。偶然性だとか複雑性のなかで自分が生きるための学びの力とかネットワークの力を蓄積して、どうやって活動するかを考えることがすごく重要です。これは個人も組織もそうなんですが、それがいまの日本は弱いような気がしています」
と、今の日本人は「常に学び考え続ける」という段階が弱いと述べている。日本テレビ事業が世界競争で敗退した事実から考えると、この指摘は当たっているのではないかと思う。
日本のテレビ事業敗北要因
日本の大手家電メーカー三社、パナソニック、ソニー、シャープが巨額の赤字を出したが、その主因は薄型テレビ事業での敗北だと分析されている。
その背景として、急激な円高や、電力料金の高さなどのインフラコストに加え、海外メーカーは優遇税制の恩恵を受けているなど、一企業ではコントロールできない逆風要因があるのは事実だが、戦略的に考えてみると「テレビを戦う素材商品」と選択し、そこに巨額の投資をし続けたというところに、根本的な要因があるのではないか。
テレビ事業は世界的に見れば成長市場である。2011年の世界販売台数は22,229万台で前年比6%伸びていて、主に新興国で売れている。ところが、価格は年率30%を超える下落が続いているから、中国・韓国・台湾の安い製造コストに日本企業は敵わなくなる。
今のテレビは大型の製造設備さえ備えれば、比較的容易に製造でき、品質も均一化出来る存在であるから、付加価値も少なく、唯一の差別化要因は「価格」になってしまう。
そうなると相手を上回る巨額の設備投資をして、さらにコスト競争力をつけた「規模型事業化」した企業が生き残るということになり、結局、いずれは世界で一社か二社が圧倒的シェアをもつ寡占化業界になっていく商品である。
つまり、一台あたりわずかな利益しか計上出来ないのであるから、世界中の市場を相手に売って、膨大な販売台数を確保し、それで採算をとるという、極めてリスクの高い面白みのない業界がテレビ事業であって、そのような時流変化に気づかず、相変わらずテレビに投資し続けたという経営判断、そこが妥当ではなかったと思っている。
日本型モデルの敗北か
多くの日本企業は技術を重視しているが、その技術とは、全く新しい商品の開発よりは、既存製品の機能改善やコスト改善が得意という特性を持っている。また、その進め方も開発から製造まで自社で抱え、それらに横たわる各部門間で調整して仕上げる方法である。
ところが、今の世界的製造業は、部品がどの企業の製品であれ、標準規格の部品であれば、それを組み合わせて製品にするという「モジュール化」が進んで、メーカー間の差は薄れ、コストも下がるので、大量生産と低賃金というアジア勢に価格競争力で対抗できない。
一方、米欧はアップル社のiPhonに代表されるように、革新的な商品を開発してきて、とうとう日本は安いモノづくりでアジア勢に負け、斬新な商品開発では米欧の負けるという結果で、稼げるアイテムが狭くなっている。ということで「日本型モデルの敗北か」と、毎日のように識者が評論をしているのが現在の日本である。
意味的価値を開発することだ
この状況下をどう解決していくか。二人の識者が提案している方向性を紹介したい。
1. 延岡健太郎・一橋大学教授(日経新聞・経済教室2012.5.28)
昔も今も、ものづくりの目的は価値づくりである。以前は優れたものづくりが、そのまま価値づくりに結びついていたが、それが乖離したのには二つ理由がある。
① どんな優れた技術・商品でも独自性がなければ、同じような商品が他社から購入出来るので、その商品の存在価値は低く、過当競争から価格が下がる。
② 日本企業が創る新機能や高品質に、顧客が喜ばなくなった。高い価格を支払っても欲しいと思う真の顧客価値になっていない。
と指摘し、では、どう取り組むべきか。これにも二案の提案がされている。
① ものづくりよりは、真の顧客価値を創出できる技術経営への変革である。特に、単純機能を超えた意味的価値を持つ商品は下図のように過当競争になりにくいので、それを提案できる人材と、それを評価できる経営プロセスが必要。

② 各社が独自の戦略的視点から、特定の技術・商品分野に集中して取り組むことだ。日本企業はリスクを恐れて横並びになる傾向があるが、今はそれこそが最大のリスク要因である。
2. 遠藤功・早稲田大学教授(日経新聞・経済教室2012.5.30)
経営とは「際立つ」ことである。自社ならではの独自価値を生み出し、競争相手と一線を画す「際立つ存在」を目指すことが経営の主題であって、中途半端に「体格」を競うのではなく、「体質」で勝負する時代を迎えている。そのためには、高い技術力や独自の現場力を生かすことができる事業を、戦う土俵として選択することが必要である。
このように二人の識者が提案している内容、それは価値づくりであり、それによって「際立つ存在」になることであって、そのためには単純機能を超えた意味的価値を考えださねばならないわけだが、これは、日本人に「考える作業の見直し」が必要だと言っているのである。では、考えるとはどういうことなのか、それを具体的に次号で検討してみたい。以上。
2012年06月21日
2012年6月20日 Japan Rising Again(後)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年6月20日 Japan Rising Again(後)
インドネシアで成功している日本企業を訪問して
インドネシアは、人口と国土の優位性を未だ発揮していないが、20年間も続く人口ボーナスに成長がともなえば、迫力あるエンジンとして作動するわけで、先進国になるかどうかの鍵は、この人口ボーナスを活かした政策を採れるかにかかっている。
また、それはインドネシアに進出する日本企業にとっても同様で、巨大人口を活用する展開方法が採れるかどうかが成功の鍵である。
だが、もうひとつクリアしなければならない重要な問題がある。それは、インドネシアは多様性ある国家の宿命で、政府当局が経済成長のために選択する政策は、当然に多様性に富み、頻繁に変更していくので、これに対応することが出来るかどうかであるが、今回、ここをクリアしている日系現地企業を訪問したので紹介したい。
トヨタなどの日系企業が多くいるNORTH JAKARTA地区のあまり大きくないビル。ここがこの企業の事務所である。受付に入ると、二階からゼネラルマネージャーが駆け下りてくる。まだ若い。30代後半だろう。既に20年間インドネシアに在住し、バリ島ではスーパーの店長を5年間勤めたといい、インドネシア情勢に詳しく、携帯電話での応答は当然にインドネシア語である。
この企業は、本来は食品卸専門業だったが、資金回転が悪いという卸のマイナス点をカバーするため、日銭を稼ぐ目的で小売業に参入、今ではスーパー6店舗、コンビニ10店舗を展開している。同社が卸しているジャカルタ中心のPLAZA INDONCIAのフードホールに行ってみると、豆腐コーナーは広く、その他の日本食の品ぞろえも豊富で、岡山のパン屋や小樽のバームクーヘンも出店していて、美味しいと評判高く、照明も明るく、価格も日本並みであるが、金持ちのインドネシア人が買いに来るので売り上げは順調とのこと。
さて、この日系企業は大儲けしているらしい。勿論、具体的な数字は教えてくれないが、マネージャーのもの言いからも推測つくし、儲かっているという他社からの情報があって訪問したわけで、その背景には複雑なインドネシアの諸税法体系を巧みに活用していることがわかった。
実は、インドネシアには所得統計がなく、中央統計庁の家計支出統計「国民社会経済サーベイSUSENAS」でもなかなか実態は分からない。そこで手がかりになるのは個人所得税の納税額であるが、この徴税捕捉率も低く、個人所得税の納税者が85万人(2008)しかいないということから推測すると、各企業も納税率は低いのではないかと推測されるが、これは脱税とは違うらしいのである。
インドネシア政府当局が打ち出す政策と税体系を常に注視し、それを巧みに取り入れて行くと税金は
支払わないですむらしいのである。
リーマンショックの時にインドネシアは影響を受けなかったが、それは政府が輸入規制をかけて国内品で固めたためといわれているように、政府の方針が弾力的で、すぐに国民に伝わりやすい国である。
加えて、為替相場も激しく動くという環境下でビジネスを進めるには相当の変化対応力が問われ、この変化対応力に優れているとビジネスは成功するし、諸税法体系を熟知把握し駆使すると大儲けできるというのがインドネシアビジネスなのである。
静かな成熟大国日本
インドネシアから戻った日本は騒音が少なく、街中にはゴミがなく、渋滞は稀で、自宅駅でホームに降りるとエキナカで、そこでは高齢者が元気で大勢買い物を楽しんでいる。
明らかにインドネシアとは異なる。そこで、改めて日本の特徴を整理してみたい。
① 騒音が少なく、街中にはゴミがない
騒音が多い街とはどういう意味を持つだろうか。多分、犯罪の多い街であろう。犯罪者が多いところは、必然的にパトカーが唸り声を挙げ、人々は落ち着かず、そのような街はどうしてもゴミが多くなる。 ところが、日本は5月22日に発表された経済協力開発機構OECDの「より良い暮らし指標」で「安全」が一位、「教育」が二位と高い評価を受けている。治安に良さは、人々の教養に裏づけされているのだ。
② 酷い渋滞は稀だ
NYタイムスに今年一月、フォーブス誌・フィナンシャル・タイムズ紙の元編集者であるエイムン フィングルトン氏Eamonn Fingletonによる「失われた20年は真っ赤な嘘だ。日本社会は米国よりも豊かだ」という記事が掲載された。
その中で特に強調しているのは「日本は絶えずインフラを向上させている政策を採ってきた」と高く評価して、そのインフラの一例としてインターネット・インフラを挙げている。米アカマイ・テクノロジーズ社の最近の調査によると、世界最強のインターネット接続環境にある50都市のうち、日本の都市は38もあるが、米国の都市は3つだけだという。
さらに、「失われた20年」に東京に建てられた高さ150m以上のビルは81棟だが、同時期にNYでは64棟、シカゴでは48棟、ロサンゼルスでは7棟しか建設されていないという。
また、以下の実態を日本人の多くは認識していないが、欧米主要都市の鉄道駅と、日本の東京・大阪駅とシステム構造の違いである。
欧米主要都市の鉄道駅はターミナル駅、漢字にすれば「頭端駅」となって、駅舎は宮殿のように立派だが、この駅ですべて列車が行き止まりとなる終着駅となっている。
例えばパリには6つの駅があるが、それがすべて終着駅である。したがって、ボルドーからTGVでモンパルナス駅に着いて、リオンに行こうとしてリオン駅へ向かうためには、地下鉄・バスかタクシーを利用するしかない。大きなバックを持っている場合はタクシー利用になるだろう。
ところが日本の東京駅、仙台から大阪に行こうとするならば、東京駅で東北新幹線から東海道新幹線へと東京駅構内で乗り換えることが出来る。このような駅のことを「総合通過駅」という。
どちらの駅システムが便利で効率的か。比較にならないほどの明白さであり、移動にタクシーを使わないのだから道路上の車使用は、移動分だけ少なくなっていて、眼には見えないが渋滞発生を防いでいる。日本のインフラ整備は優れていると認識したい。
さらに、最近ではエキナカというショップがあって、そこにはデパチカにはないアイテムが並び、自宅へのお土産を買って帰ると家族に喜ばれる。世界中でこのような便利で快適な駅を見たことがない。
③ 高齢者が元気
厚生労働省は31日、日本人の平均寿命などをまとめた完全生命表を発表した。昨年7月に発表した簡易生命表の確定版で、2010年の平均寿命は女性が86.30歳、男性は79.55歳となった。前回調査の05年から、それぞれ0.78歳、0.99歳延びた。主要国・地域の直近の統計と比べると、女性は世界一、男性は4位である。
この報道を聞いて日本は改めてすごいと感じる。寿命が延びるという意味は、国民一人ひとりの生活状態がよく、医療制度が充実していることを示しているからであって、お目出度いことであるが、そう思わない人もいるらしいが、そのような人は変わった人物だろう。人間は元気で長生きし社会に貢献するのが一番だと思う。
インドネシアと日本は国の状況が異なるので比較は出来ない
インドネシアの道路上は渋滞で、クラクションが鳴り、鉄道は少なく、地下鉄はようやく工事をはじめたところである。つまり、基本的なインフラ整備がこれから行われる国である。さらに、人口状態が全く異なる。1950年時の人口は日本が8400万人、インドネシアは7700万人とほぼ拮抗していたが、2050年の人口予測では日本が8833万人から10360万人(国立社会保障・人口問題研究所「日本の将来推計人口」2006年)と推計されているが、インドネシアは29300万人(2010年国連人口推計・中位推計)とされているので、インドネシアは日本の三倍近い人口となる見込みである。
対する日本は「人口減」と「失われた20年」という認識から、多くの識者が日本に対して悲観的な言動をする場合が多いし、前号で紹介した観光庁作成のポスター「Japan Rising Again」、これには何がどうすれば「Again」になるのかが明確になっていない。
つまり、「Rising」できれば「Again」になるとしたら、「Rising」の定義をしなければいけないが、その定義を人口減という現実から構築しないといけないだろう。それが明確化しないままに標語化している。
チャールズ・ダーウィンが150年以上前に述べているのは、
「生き残る種というのは、最も強いものでもなければ、最も知能の高いものでもない。変わりゆく環境に最も適応できる種が生き残るのである」
これを基に「JAPAN Rising Again」に代わる標語を検討したらどうか。インドネシアから戻った感想である。以上。
2012年06月07日
Japan Rising Again(前)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年6月5日 Japan Rising Again(前)
Japan Rising Again
ジャカルタから成田空港第二旅客ターミナルに着き、第一旅客ターミナルへサテライトで移動しようとして、ふと上を見ると観光庁作成ポスターの「Japan Rising Again」という文字が目に入った。

観光庁はこの鯉のデザインを表に、裏に「Thank You」と印字した名刺サイズのカードをつくり、東京マラソン、京都マラソン、館山トライアスロンへの外国人参加者、全国の国際空港等において配布している。大変よいことだと思いつつ、何か引っかかるものが残った。
それは、このスローガンは東日本大震災からの復興を意味するのだろうから「Japan」ではなく、外務省の英文ウェブサイト「 the Great East Japan Earthquake」に準じて東日本を入れるべきではないか、そうしないと日本全体の復興と勘違いされてしまう。
しかし、もしかして敢えて「 East」を外して、日本全体の「Rising Again」を意図していると勘ぐって考えてみるならば、かつての高度成長時代思考が抜け切れていない認識で、日本の経済実態を捉えているのではないかという疑問をもつ。
東京スカイツリー
高さ634メートルの世界一高い電波塔「東京スカイツリー」が5月22日開業した。出足は好調で予測集客人数の1.5倍だともいわれている。
勿論、展望デッキに上がるのは予約制なので人数に制限があるが、商業施設の「東京ソラマチ」には大勢の観光客が押し寄せている。
オープン前日の前夜祭に出かけ312店舗が入っているソラマチを見て回り、スカイツリーを見上げながら食事した際、これは他の日本観光地は大変なことになると思った。
事業主の東武鉄道が公表した年間来場者数は3200万人で、これは東京ディズニーリゾートの年間来場者数2500万人を上回る。大阪万博(6カ月間開催)の総入場者数6421万人とは比較にならないが、2005年の名古屋万博(6カ月間開催)の2204万人を超える集客数であるから、多分、今年以降の国内各観光地は集客数減という甚大な影響を受けるだろうと予測され、各観光地はビジョン再構築を含めた観光政策の見直しが必要であろう。
日本とは比較が出来ないインドネシアという国
5月のゴールデンウィーク明けに訪問したインドネシアと日本と比較検討してみたい。
① 多様な国家
インドネシアという語は「インド」に、ギリシャ語の島の複数形「ネシア」をつけたもので「インド諸島」や「マレー諸島」に代わる地理学、民族学上の学術用語として、1850年に新たにつくられたものである。
したがって、インドネシアという語は一世紀半の歴史であり、国の一体性もせいぜい一世紀ほどの歴史だが、この地域にはそれぞれ島ごとに異なる2000年の豊かな歴史・文化があり、それを象徴するかのように、1128の民族集団と745の言語が確認できるという。
また、インドネシアは6000あまりの無人島を含む17504の島々からなる世界最大の群島国家である。
② 交通渋滞の酷さ
インドネシアの首都ジャカルタに着いての第一印象は、道路渋滞のすごさである。今まで訪れた都市での渋滞ワーストスリーは、一位がカイロ、二位がモスクワ、三位がサンパウロとランク付けしているが、ジャカルタはここに食い込むだろうと思うほどの酷さである。ジャカルタの人々は「一日の三分の一はベッドの上、三分の一は職場、残りの三分の一が道路上」と半ばあきらめ顔でいうが、車も二輪車も売れに売れている。
車は一種のステータス・シンボルなので「渋滞が酷いから」という理由で車を買い控えようという発想はなく、二輪車は車間をぬって効率よく動けるので、渋滞が酷いほどよく売れるということで、保有台数はますます増えている。
その結果、2011年度の新車販売数は前年対比17%増の89万台、二輪車は初めて800万台を超え、ともに過去最高を更新した。したがって、トヨタもスズキもインドネシアに新工場を建設し生産能力を高めている。
渋滞理由はインフラ整備遅れにあるが、どうしてインドネシアではそのような結果となっているのであろうか。
インフラ整備に必要な資金はあったはずである。というのも第二次世界大戦後、日本はインドネシアとサンフランシスコ平和条約に準じる平和条約を結んで、多額の賠償を支払っているのであるから、このお金でインフラ整備をしておけば今日のような渋滞は発生しなかったと思われるが、それがそうならなかったのには複雑な背景が存在している。
これらを説明しだすと紙数が足りなくなるのでやめるが、ご関心ある方は「経済大国インドネシア」(佐藤百合著)を参考にされたい。なお、現在でもジャカルタ市内地下鉄工事、新空港と国際港湾建設は、日本の支援で進めている。
③ インドネシアは人口ボーナス大国
インドネシアの人口は2.38億人(2010年)で世界4位。国土面積は191万㎢で世界16位であるが、海洋大国であるから領海が陸地の二倍近い320万㎢もあって、東西の長さは5100kmに及ぶ海域で、ちょうどアメリカの陸地部分がすっぽり入る大国である。
しかし、この人口と国土の大きさに比して、GDPは7070億ドル(2010年)で世界18位と少ないのであるが、今後は大いに期待できる要因がある。
それは、生産年齢人口という人口ボーナス、日本は既に減少期に入って、中国も韓国も近々減少期に突入するのに対し、インドネシアは1970年頃から2030年頃まで60年も続くから、今後20年間の国内需要増加が大いに期待される。
④ 旧日本軍への評価
ここで戦後賠償しなければならなくなった旧日本軍の評判を振り返ってみたい。
ネガティヴな面の多いといわれている旧日本軍政で、褒められるのは「言語統一」くらいである。というのもオランダ統治時代は、オランダ語を公用語としてインドネシア語を無視していたが、旧日本軍が今通用しているインドネシア語に改めている。この他にはあまり評判がよろしくない旧日本軍の進出背景思想には、いわゆる「南進論」があった。
●日本の生命線は南方にある。端的にいえば油の問題、蘭印からとるより仕方ない
●インドネシアは経済的には「未開発の厖大な資源が放置」されている
●政治的には「オランダの支配下で隷従」を強いられている
●文化的には「きわめて低い段階」と認識し
●それ故に「アジアの解放」を国家目標に掲げて
●「世界で優秀な民族」である日本人によって現状を打破する必要性がある
という論理構築で、この論理を一言でまとめれば「南方圏をただたんに資源の所在地と捉えて、そこの歴史も文化も民族も無視する」ものであった。世界のどの地域にも、豊かな歴史と文化があるというのが普遍的な事実で、日本だけに長く豊かな歴史に基づく文化があるという観念的思考をもつことは大問題である。
正しくは、日本の文化は豊かで優れている、同様に日本とは異なる豊かな優れた文化がどの地にも存在している。このように理解し認識すべきなのである。
⑤ 現在の日本への評価
一方、現在のインドネシア人の日本観はどういうものか。ここでインドネシア人の最新修士論文(2010年)から引用してみよう。(「経済大国インドネシア」佐藤百合著)この論文は旧日本軍の進出を起点として日本観変遷を6段階に分析している
1.占領者としての日本 2.従軍慰安婦を強いた日本 3.開発資金提供者としての日本
4.先進国としての日本 5.ハイテク国の日本 6.ポップ文化の日本
この中で1と2が区別されているのは、従軍慰安婦問題の責任と補償が今なお未解決の問題として認識されている事実を示している。インドネシアのすべての生徒たちは1と2について小学六年と中学二年で必ず学ぶようになっているという。
だが最近は5と6によって、世界中の多くの国と同様の「クールジャパン」現象で、日本の人気は高く、日本愛好家(プチンタ・ジュパン)が増えている。
次号ではインドネシアで成功している日本企業についてふれ日本の課題を検討する。以上。
2012年05月07日
YAMAMOTO・レター
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年5月5日 ビジョン構築力・・・前半
原節子
東京都写真美術館で、幕末から明治初年に来日し活躍した写真家フェリーチェ・ベアトの展示会が、2012年3月6日 ( 火 ) ~ 5月6日 ( 日 )で開催された。とても興味深い鶏卵写真と湿板写真の展示が多くされており、中でも「愛宕山から見た江戸のパノラマ」(1863-1864頃撮影作品)は、当時の江戸がいかに美しい都市景観であったかを示す貴重なものであった。
このベアト展を見てフロアに出ると、目の前に原節子の美しい写真ポスターが展示されていた。同美術館ホールで原節子16歳主演デビュー作の「新しき土」が、75年ぶりにスクリーン公開されているのだ。これは観ないといけないと早速に入ってみた。
「新しき土」は昭和12年(1937)公開の日独合作映画。新しき土とは満州のことを指していて、ドイツ語版のタイトルは「Die Tochter des Samurai」(侍の娘)である。
ドイツの山岳映画の巨匠アーノルド・ファンクと、日本の伊丹万作の共同監督で制作が計画されたが、文化的背景の違いから両監督の対立となり、同タイトルでファンク版と伊丹版の2本のフィルムが撮影された。
監督以外のキャスト・スタッフも豪華で、国民的人気のあった原節子や日本を代表する国際スター早川雪洲、スタッフでは撮影協力に円谷英二(この作品において日本で初めて本格的なスクリーン・プロセス撮影が行なわれた)、音楽に山田耕筰が名を連ねている。東京都写真美術館ホールで公開されたのは、ドイツ人監督ファンク版のほうで、山岳映画の監督らしく、日本の山々の美しい景色が映されている一方で、東京市街を阪神電車が走っていたり、光子の家の裏が厳島神社であるなど、日本人から見ると滑稽なシーンも多いが、原節子の息をのむ美しさに満足すると同時に、当時と今では人口に対する考え方が全く反対であることに気づいた。
人口過多か、人口減か
映画「新しき土」のなかで、何回か語られるのは「日本は土地が狭いのに人口が多すぎる」という問題指摘である。映画が公開された昭和12年の人口は7,063万人であって、この数字が日本にとっては多すぎるからこそ、その対策として「新しき土=満洲侵略」を国家政策としたのである。当時の国家政策判断として、他国に侵略してまで、日本の人口過大問題を解決しようとしたことは問題であるが、国民と政治家が人口対策を真剣に考えていたことは事実である。
一方、今の日本人は、平成22年国勢調査人口12,805万人と、75年前より5,742万人も多いのに、今度は「人口減」に向かうことを心配している。たったの75年で、日本人の人口数に対する考え方は全く正反対となっている。だが、この反対になった考え方というところ、そこに気づいている人はどのくらいいるのだろうか。
同じ国土面積で生活しているのであるから、昭和12年を基準に考えれば、今は全く多すぎる人口となっているが、このような認識を今の日本人はもっていないだろう。
だから、これから予測される「人口減」の「減少」というところのみを強調して考えてしまい、人口減を恐怖観念へ結びつけ、日本全体を重苦しい気持ちにさせているのではないか。今、必要とする検討は、このような悲観的な思考に陥るのではなく、「では、実際のところ、日本はどの程度の人口が適切なのか」、つまり、日本の「適正人口数」はどの程度か、ということの追及であろう。
ここを明確にしないまま、加えて、75年前は今の55%しか人口がいなかったのに、人口過多と日本人が自ら考えていたという事実を多くの国民は知らずして、これから向かう減少人口状態のことばかり心配しているような気がしてならない。
つまり、物事は事実から判断すべきというのがセオリーであるが、現在の人口減議論は、ついこの間のわずか75年前の人口への考え方を忘却して論議されている。
前原誠司民主党政策調査会長
「新しき土」映画を観た5日後に、前原誠司民主党政策調査会長の講演を聞く機会があった。前原氏は次期首相候補の一人でもあり、民主党切っての論客と評判が高いので、大変興味持ち会場に入った。会場では親切にもパワーポイント資料が配られ、その資料に基づいて前原氏の講演が始まった。テレビ・新聞で見る通りの爽やか、若々しい前原氏であったが、講演タイトル「社会保障・税の一体改革」というテーマ設定に、おや、これはちょっと期待はずれかなと思いつつ、話を聞ききはじめた。
確かに、現在、野田政権は消費税増税問題を重要政策課題として進めているし、賛成・反対側に分れ喧々諤々議論が展開されている時期なので、一見、前原氏のテーマ設定は妥当と考えられる。
だが、最初のパワーポイント資料が「人口減少社会・少子高齢化社会の到来」で、2050年までの人口数予測がグラフで描かれ、次のパワーポイント資料では「一般政府債務残高GDP対比の国際比較」という、いわば見飽きた図表が表示された時、ああ、これはダメだとあきらめに近い気持ちになった。
政治家とは何をする仕事なのか。当たり前のことであるが、政治家とは政治を行う人物である。古代ギリシアの哲学者アリストテレスは、その著書「政治学」で、政治を「善い社会」の実現を試みるためのマスターサイエンスであると位置づけているように、政治家とは政治によって理想社会を実現するため社会に働きかける役割を、担当する人物のことである。
つまり、政治家を志すならば「日本社会の理想状態」を描いていなければならないのであって、その理想状態を実現するために、自らが政治家として存在していると覚悟すべき職業なのである。
海外メディアから指摘
日本の政治家が弱いという指摘は以前からなされている。最近では小泉純一郎元首相以来、首相がころころ変わって、リーダーシップについて内外から問題視されている。
昨年3月11日の東日本大震災時、世界中のメディアは日本に目を向け、一斉にトップページとして実態状況を報道した。当然に、日本を取材すべく世界中の記者が日本に集まった。一時、原発恐怖で帰国した記者もいたが、この時期のマスコミ報道は全世界が日本一色であった。
外国人記者はどのようにして取材するのか。それは、当然に日本政府発表の内容に基づくが、その裏付けをとるべく、個々に政治家や専門家に接触することになる。
筆者が親しくしている日本在住アメリカ人から聞いた内容であるが、アメリカの最有力メディア東京駐在編集長は、この時期、自宅には帰らず、睡眠時間も少なく、取材に明け暮れしていたが、その中で、大震災を機に日本はどうすべきか、というインタビューを数多くの政治家に心がけたという。
その理由は、全世界が一斉に日本に最大関心を持つチャンスは今しかない。ならば、これからの日本はどういう姿を理想とすべきなのか、それを全世界に伝える機会として、この東日本大震災時を捉え、世界への日本PRとして利用すべきと考えたわけである。
結果はどうなったか。残念なことに、多くの有力政治家にインタビューした内容では、全世界に発信できないと判断し、ボツにせざるを得なかったのである。
政治家が語る中味が薄い。世界基準から見てビジョン面が弱すぎる。問題点を把握し、問題の根本を指摘する力は十分にあるが、そこから国家未来ビジョンにつなげるパワーが欠けている、というのが東京駐在編集長の見解である。
この見解には同調せざるを得なく、前原誠司氏の講演でも同様の見解を持ったわけである。少なくとも政治家ならば、講演に最初の発言が「人口減と財政GDP比率」という、誰もが熟知している内容を、改めてパワーポイントで説明するなぞはすべきでない。
このような問題指摘は、通常よく財務省か経済・証券アナリストが使うのであって、国民は十分に知っているし、この問題を大きく心配している。
特に前原氏は政策調査会長である。ということは日本国家の政策面の責任者であろう。問題点は熟知しているのであるからこそ、未来に向かってどのような国家像を描いており、そこへ行く道筋をビジョンとして語り、だからこそ「社会保障・税の一体改革」が必要だと熱意を持って国民を説得すればよいのである。
しかし、前原氏の講演は「高齢者保険料の低所得者対策」とか「医療保険・介護保険制度」について細かい数字を説明する内容であって、日本国家をどうしたいという発言は無かったのである。政治家を志す人はビジョン構築力を磨く事だ。次号続く。以上。
2012年04月05日
2012年4月5日 国の違いから物事を考える・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年4月5日 国の違いから物事を考える・・・その一
アルガルヴェ・カップはドイツでテレビ放映なし
2012年3月8日、ポルトガルで開催されたアルガルヴェ・カップ決勝、なでしこジャパンがドイツに敗れたので、早速、ドイツの友人にメール連絡したところ、次の返事がきた。
「女子サッカー試合でドイツが優勝したことは知りませんでした。最近スポーツ番組を見ていませんし、テレビニュースで伝えられるのは、各地で起こっているストライキの模様、ユーロ危機や国の借金の話、ギリシャのこと、アメリカの大統領選挙運動の中継などです。今インターネットでいろいろ探してやっと記事を見つけました。
日本では各メディアがこの試合について伝えていたのに反し、ドイツではテレビ放映されなかったということです。どうりで私も知らなかったわけです。
しかも この試合を見たい人はインターネットで見るように、とも書いてあります。テレビ報道されなかったことの理由は書いてありませんでした。
また一般市民のなかでも今回の女子サッカーは話題に上ることがありませんでした。サッカー試合のあった時間についても ユーロスポーツのほうで把握していなかったらしく、日本のメディアを通じて知ったほどだそうです。
アルガルヴェ・カップ大会がそれほど重要でなかったから、ライヴが流されなかったのだろうか、と書いてあります。ユーロスポーツ番組では サッカー試合でなく、同じ時間に行われたトライアスロン競技のほうのライヴを流していました。
結局 この試合を見たければ、ユーロスポーツのライヴ・ストリームで見て下さい、有料かもしれませんが、とも書かれています」
この事実を日本人に伝えると「本当か」と皆さん驚く。日本ではなでしこジャパンの活躍が詳細に報道され、帰国時の成田空港風景をテレビで放映したほどだが、ドイツでは全く無関心。国が違えば、対応が反対となる典型事例だろう。
美女でなくても美女とは!!
2012年3月25日の日経新聞「春秋」に、中国のレストランでウェートレスに注文する際、なんと呼び掛けるかについて、面白い記事が掲載された。
日本では、一般的にウェートレス女性に呼び掛ける際は「すみません・・・」とか「おねえさん」で、時には特別に「お嬢さん」と言うのが精々だろう。
ところが隣国中国では、呼びかけがドンドン変化している。計画経済時では「同志・トンチー」と呼ばれ、同志が同志に提供するのだから、サービスは悪いのが当たり前だった。
改革・開放政策が本格的に動き出して、急速に使いだしたのが「小姐・シャオジェ」という言い方。もともとは、未婚の女性に対する伝統的な呼び方であるが、これが復活した。これは今でも台湾や香港で使われている。
ところが大陸、特に北京や東北地方の都市部では近年、カラオケボックスやクラブが多くなってきて、これらに勤める女性にも「小姐」が使われて、レストランのウェートレスにとっては、好ましくないニュアンスになってきた。
代わって広がったのは「服務員・フーウーユエン」という呼び名だが、これはいくら何でも味気ない。ということで、とうとう上海では「美女・メイニュー」と呼び掛ける人が増えてきたという。
この「春秋」記事が出たのが3月25日、翌26日に上海に入ったので、早速地元の女性数人に聞いてみたところ「その通りです」という明快な回答。
時代が移るにつれて、言葉も替わるのは当たり前であるが、「美女」というのは言いすぎではないか。すべてのウェートレスがこの呼び名に当てはまるとは思えないし、言われた方も照れるのではないかと思うが、中国人は気にしないのだ。日本女性なら、多分、照れて、恥じらう可能性の方が高いだろうと思う。
しかし、この状況を知らず、中国へ旅行に行き、レストランで「美女」と呼び掛けしない結果、ウェートレスから雑なサービスを受けて「やはり中国はサービスが問題だ」と評価してしまうのは、間違いになるかもしれない。
国が違えば、同じ意味の言葉でも、ニュアンスが異なる場合が多いが、中国は変化が激しいので、観光客も大変だ。
だが、これが中国の実態なのだから、よいサービスを受けようと思ったら、相手国の実情に合わせないといけないのだろうが、目まぐるしいことだ。
リュクサンブール宮殿
パリ地下鉄でオデオン駅ODEONへ、そこから歩いて6区リュクサンブールLUXEMBOURG公園へ向かった。
地図では公園と宮殿が別表示されていて、宮殿と書かれている方はフランス元老院議会のセナSĒNATである。
16世紀の昔、ここにはリュクサンブール公が居住しており、ルイ13世の母マリー・ド・メディシスや、孫のモンパンシエ公爵夫人や、ルイ18世などが居住した宮殿が、今は議会になっているのである。
フランス議会は二院制である。国民議会と元老院があり、日本とは違って、両者とも独立した議会で、元老院は間接選挙で選出され、任期は6年、3年毎に半数を改選される仕組みである。国民議会は、7区のブルボン宮にある。
牡蠣養殖地として著名なアルカッション地区の女性市長が、この元老院の議員を兼ねていて、その紹介で特別に見学させてもらったのが、2月28日。フランスでは市長が議員を兼ねていることが多い。
この日は、フランソワ・フィヨン首相を廊下で見かけたように、ギリシャ問題で重要会議があり、議員は
多忙で秘書が案内してくれた。この秘書、父が戦後最初の在日外交官だったと打ち明けてくれる。
正面入り口から入ると、各政治家のための木製のキャビネが設置してあり、そこから「名誉の階段 Escalier d’honneur」が重々しく、ここを上がり1800年代に改築された議場に入ると、議長席の後ろには、歴代の著名な政治家ジャン=バティスト・コルベールなど、6人の彫刻が目を惹く。
さらに、一階の「ゲストの部屋 Salle du Livre d’Or」と名づけられた小さな部屋は、1816年にすべて木で造られ、装飾は繊細で、さすが文化国家と理解したが、最も華々しくみごとと感じたのは議会図書館である。王朝華やかし頃の一場面にいるような気持ちになる。
(名誉の階段)
リュクサンブール宮殿を見学し、改めて、分かったことがある。それは「主要な構造がすべて石造り」
あるということ。石であるから今日まで遺り、現在でも使われているのだ。過去の支配者層が権力をもって建築した石造りモニュメントが、現代に文化財産として生き遺って、実用化されているのである。
日本には、このような石造りの大きいモニュメントはない。何故に、日本人がフランスに行ってモン・サン=ミシェルやベルサイユ宮殿等を見に行くのは、日本にはなく、珍しいからで、これが観光であると、改めて納得した次第。
外国人から見た日本の魅力とは何か
日本を訪れる外国からの観光客は、日本には巨大な石造りのモニュメントがないことを承知し、外国にない日本独自の魅力を求めてくるはずだ。それは何か。そのところを妥当に理解して、そこから観光政策を展開しないといけないだろう。次号続く。以上。
2012年03月20日
2012年3月20日 日本のギリシャ問題を考える・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年3月20日 日本のギリシャ問題を考える・・・その二
日本はギリシャ化するか
2005年1月、日本の財務省はロンドンとニューヨークで戦後初の海外投資説明会(IR)を開いた。海外の機関投資家に日本国債の「魅力」をPRし、購入してもらおうとしたもので、その後も定期的に欧米、アジアの大都市で同様の海外IRを開催している。
その結果、海外投資家保有比率は2008年9月に7.8%となった。しかし、その後は低下し2010年末には4.8%にとどまったが、2011年6月末には5.7%に上昇した。これはギリシャ危機などの影響で海外投資家の日本国債への投資が増えたものである。 では、この海外投資家保有率が増えるとどうなるか。
ここでギリシャ国債の海外投資家保有比率を見てみよう。2005年から10年の平均で約71%である。ギリシャ国債の高金利につられて外国の銀行などが買っているのだ。
しかし、デフォルト(債務不履行)の危機になったので、一斉に売って逃げ出そうとする。だが、誰も買わないので、ECB(欧州中央銀行)が「売り逃げ」の受け皿として引き受けている。
ここを注視したい。日本国債の海外投資家保有比率が仮にギリシャ並みになって、日本がデフォルト危機に陥れば、市場は日本国債の売り一色になるが、どこが引き受けてくれるのか。日本の場合、ギリシャにとってのECBはない。 日本国債の海外投資家頼みは、ギリシャ以上に危険であろう。
明治天皇がご存命ならば
3月11日の政府主催の東日本大震災追悼式で、台湾代表に献花の機会がなかったことについて、「本当に申し訳ない。行き届いていなかったことを深く反省したい」と野田首相は12日の参院予算委員会で陳謝したが、台湾からの震災義援金は官民合わせて約200億円と世界トップクラスであり、親日国であることを考慮に入れない民主党政府の外交神経の雑さに問題だと感じる。
また、自民党の世耕弘成氏から、追悼式で、天皇、皇后両陛下がご退席になる際、場内が着席していたとして、「どこの国でも全員起立するものだ」と批判され、藤村官房長官は「(議事進行は)事務方で詰めてきたものを直前に聞いた。おわびするしかない」と謝ったが、民主党の尊皇神経の雑さには困ったものだと感じるが、その問題はさておき、明治天皇が外債発行に反対された事例を紹介したい。
今上天皇陛下と明治天皇では、そのお立場が異なるので比較は出来ないが、仮に、明治天皇がご存命ならば、国債の海外投資家への発行は、直ちに禁止する聖断を下されたであろう。明治十三年(1880)五月、大隈参議は財政難を救うため外債5千万円発行しようと閣議に諮ったが、賛否相半ばして大混乱に立ちいたった。そこで明治天皇に裁断を仰いだところ、次のような直筆の沙汰書で拒否されたのである。
「朕素ヨリ会計ノ容易ナラザルヲ知ルト雖、外債ノ最も今日ニ不可ナルヲ知ル。去年克蘭徳(グランド)ヨリ此ノ外国債ノ利害ニツイテ藎(じん)言(げん)猶耳ニ在リ。・・・中略・・・勤倹ヲ本トシテ経済ノ方法ヲ定メ、内閣所省ト熟議シテ、之ヲ奉セヨ」
この克蘭徳(グランド)とは、明治十二年(1879)に来日した米国前大統領U・S・グランド将軍のことであるが、当時、明治天皇は二十六歳、グランド五十七歳、通訳と三条実美のみを伴った会談が八月十日、二時間に渡って浜離宮で行われ、その際にグランドは特に外債について強調し警告した。
「外国からの借金ほど、国家が避けなければならないことはない。弱小国家に、しきりに金を貸したがっている国があることはご承知かと思う。そうすることで優位な立場を確保し、不当に相手を威圧しようと狙っている。彼らが金を貸す目的は、政権を掌握することにある。彼らは常に、金を貸す機会を窺っている」
この助言を明治天皇は深く理解しており、大隈参議への拒否となったわけである。
川北隆雄氏試算Ⅹデー
以下の表は川北隆雄氏(中日新聞・編集委員)が試算したものである。
-thumb.jpg)
約10年後に、政府債務残高が個人金融資産を食いつぶす。しかし、これは計算上なので、別枠で復興費、交付国債という形で増やしているから、現実にはもっと早まると推測し、そのタイミングは自民党の「Ⅹ-dayプロジェクト」の指摘した「今後七、八年以内」と川北隆雄氏も想定している。
だが、冒頭の日経新聞報道に見る如く「世界の多くのヘッジファンドが、今回は自信を持って売りを仕掛ける方針だという」という状況では「Ⅹデーは早まる」可能性も否定できない。
誰が被害をもっともかぶるか
財政が破たんした場合、誰が責任を取るのか。歴代首相や財務大臣か、政治家か、財務官僚か、彼らは責任を取らないだろう。政治家も官僚も破たんした場合、それなりに年金は大幅にカットされ、物価も急騰するから生活は苦しくなるだろうが、彼らは情報が豊富に入るのであるから、事前に対策を講じていくだろう。
ところが、一般人の大多数はそのような逃げ方ができない。では、どうなるのか。それは、自らが暮らす地方自治体の体力具合で影響度が違ってくるものの、大体はカリフォルニア州ヴァレーホ市の実態となるであろう。
「ブーメラン」最後のまとめ
マイケル・ルイスは「ブーメラン」の最後に以下のようにまとめている。
「返済がむずかしいほどの、もしかすると返済不可能なほどの額まで借金を重ねていくとき、人の行動は同時にいくつものことを語っている。明らかに語っているのは、手持ちの資金で購(あがな)える以上のものが欲しいということだ。やや控えめに語っているのは、現在の欲求はとても重要なものだから、それを満たすためなら、将来ある程度の財政難をきたすのも致しかたないということだ。
しかし、実際にそういう取引を行う時点で、人が暗黙に語っているのは、いざその財政難が訪れたら、なんとか切り抜けてやるということだ。当然のことながら、いつも切り抜けられるとは限らない。
しかし、切り抜けられるという可能性を排除することは誰にもできない。そういう楽観主義は、どれほどばかげたものに見えようと、それを胸に宿した人間にとっては、じゅうぶん賭けてみる価値があるものなのだ。ぞっとする話ではないか」
このまとめを深く胸に刻み、併せて、ヴァレーホ市新任の市政担当官が、いちばんの問題は、財政上の問題は症状にすぎず、その病根は文化にあると発言し、どうやって、市全体の文化を変えるのかの問いに、「まずは、自分の内面に目を向けることです」という言葉を再度振り返りたい。
我々日本人一人ひとりの人間性と借金に対する常識に通じる指摘と考えたい。
最後に提案したいことは、一人ひとりが自らの財政状況に応じて、今からシミュレーションし、その日が来ても慌てないようにすることが最も大事と思います。以上。
2012年03月05日
2012年3月5日 日本のギリシャ問題を考える・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年3月5日 日本のギリシャ問題を考える・・・その一
日本国債への仕掛け
日経新聞「大機小機」(2012.2.18)が
「これまで安全資産として買われてきた円が、2012年には円安への転換点を迎える可能性が高いうえ、過去に日本の国債売りを仕掛け、ことごとく失敗してきた多くのヘッジファンドが、今回は自信を持って売りを仕掛ける方針だという」と、世界からの日本経済への見方が変わってきたことを述べた。
では、ヘッジファンドはどうやって売りを仕掛けるのか。それにはCDS(クレジット・デフォルト・スワップ)というデリバティブ商品を使う。CDSとは債権のデフォルト(債務不履行)をヘッジするための金融商品である。
例えば、日本国債を持っている人がいて、日本が倒産したら日本国債はボロ値となる。しかし、日本国債のCDSを買っておけば、それを売った人から損失分を貰えるというもので、その為にはCDSを買う人が、最初に決められた保険料、仮に日本国債を100億円保有しているとして、年間1%の保険料であったら、1億円ずつ支払えば、日本が倒産しても損しないのである。
また、日本国債を保有していない人でも、このCDSを買える。この場合、年間1億円払えば、日本が倒産したら最大で100億円儲かることができる。
つまり、これはギャンブルである。 他人の家に火災保険を掛けて、他人の家が燃えるのを祈るような賭けであって、債権がなくても、デリバティブ商品の売り手と買い手がいれば成り立ち、無限大の大きさの市場を作り出せるのである。
これがアメリカのサブプライムローンの仕掛けで、ヘッジファンドが住宅ローン仕組み債を空売りし、巨万の富を得た手法である。
この手法でいよいよ自信を持って日本国債に仕掛けてくるのだという。
アメリカの中のギリシャはどこか
日本国がギリシャのような倒産状態に陥った場合、そのようなことはないと思うが、仮に発生した場合、日本のどこが、誰が、最も損害を被ることになるのだろうか。
その注意喚起のために、事前にシミュレーションしておいた方がよいと思うので、それをマイケル・ルイス著の「ブーメラン」(2012年1月)の中から紹介したい。
書名の「ブーメラン」とは、サブプライムローン仕掛けで、欧州が被った損失が、ブーメランのようにアメリカに戻って、地方都市に住む人々の生活を直撃しているという意味である。「世紀の空売り」(2010年)、映画になった「マネーボール」(2011年)に続くマイケル・ルイスの力作である。
まず、「ブーメラン」は最初にアメリカ全体の問題を述べる。
① 2002年から2008年にかけて、州は住民と足並みそろえて債務を積み上げた。住民の負債額は全体で見てほぼ二倍、州の支出は約一・七倍になった。
② 1980年には、州の年金原資のうち、株式市場に投資されたのは23%にすぎなかったが2008年には、その割合が60%にまで増えている。
③ 財政の穴は数兆ドルに広がり、その穴を埋めるには、ふたつの選択肢・・・公共サービスの大幅縮減か債務不履行か・・・の一方もしくは両方を実践するしかなかった。
④ この国はどんどん、財政的に安定した地帯と危ない地帯に色分けされていくだろう。お金があって引っ越しできる人たちは、引越しする。お金がなくて引っ越しできない人たちは、引越しせず、最終的には州や自治体の援助をそれまで以上に当てにする。それが、事実上の“共有地の悲劇”(多数者が利用できる共有資源を乱獲することによって資源が枯渇すること)を招く。
このようにアメリカの全体的な状況を述べた後、いちばん憐れむべき市としてカリフォルニア州サンフランシスコのベイエリア内にあるヴァレーホ市Vallejoを紹介している。
① 2008年、多数の債権者との折り合いが付けられず、ヴァレーホ市は破産を宣告し、2011年8月、スタンダード&プアーズがアメリカ国債の評価を格下げしたのと同じ週に破産申請が認められた。最終的に、ヴァレーホの債権者の手もとには1ドルに対し5セント、公務員の手もとには1ドルに対し20ないし30セント程度の金が残された。
② 破産の宣言以来、警察署と消防署の規模は半分に縮小された結果、自宅にいても安心できないと訴える人がかなりいて、その他のサービスは、事実上、まったく実施されなくなった。
③ したがって、どこにでも駐車することができ、違反切符を気にする必要はなくなった。駐車違反を監視する婦警もいないからだ。
ここまで「ブーメラン」を読んでハッと気づいた。そういえば昨年1月末にナパ・バレー NAPA VALLEY、ここはカリフォルニアワイン産地として有名なところだが、ここを訪問した際、途中二店舗のスーパーに立ち寄ったことがあった。
初めに行ったのがウォルマートで、次に行ったところの名前は覚えていないが、古く大きく暗いイメージのメキシコ人を対象にしたようなスーパーで、ここの所在地がヴァレーホ市だった。
その時地元の人からざっと聞いたメモを見なおしてみると、ヴァレーホ市の年間赤字は1600万ドルで、主な理由は歳入8000万ドルのうちなんと80%を警官、消防士等の人件費に充てていたとある。もともと労働者階級の多いあまり安全な地域ではなかったが、警官が減らされたことから、地元の人がボランティアで警備にあたっているが、犯罪は多くなり、売春婦が急増したともメモにある。
再び「ブーメラン」に戻ってみたい。
④ 新任の市政担当官は、ヴァレーホ市がかかえるいちばんの問題は、財政上の問題は症状にすぎず、その病根は文化にあると次のように発言した。
⑤ 要するに、人間の問題なのです。互いへの敬意、誠実さ、そして、美質を獲得しようという気概、そういうものを学ぶことです。文化はおのずから変わります。しかし、人間は意思的に変わらなくてはなりません。意思を曲げて納得しても、それは意見を変えたことになりません。
⑥ 著者が「どうやって、市全体の文化を変えるのですか」と聞くと「まずは、自分の内面に目を向けることです」と市政担当官が答えた。
破産したヴァレーホ市について市政担当官は、問題の根源を人間にあると判断しているのである。これを的外れと考え、財政問題と直接関わらないと思うか、それとも人間性の本質を突いた鋭い指摘と捉えるか。その受け止め方は様々であろうが考えさせられるポイントである。
次は日本について検討してみたい。
日本の財政悪化シミュレーション
2011年6月1日、自民党の「Ⅹ-dayプロジェクト」(座長・林芳正政調会長代理)は、衝撃的な報告書を発表した。「今後七、八年以内」に日本国債の発行は限界に達する、というのだ。つまり、日本財政破綻のⅩデーは七、八年後というわけである。(参照 川北隆雄著「日本国はいくら借金ができるのか?」)
このプロジェクトは、民主党のバラマキ政策による財政の悪化に懸念を抱いたメンバーが、関係各分野にヒアリング調査を行って報告書をまとめたもの。
現時点での日本財政は、豊富な国内金融資産などを背景に、国債市場は安定しているが、家計貯蓄率の低下や、経常収支の黒字幅の縮小などを原因として、国債を国内の投資家だけで消化できなくなるというものである。
国債などの政府債務残高を国内貯蓄だけで賄えなくなると、どうなるか。日本国債の市場価格が下落し、長期金利が高騰する。この因果関係は一般に熟知されている通りである。
だが、話はこれだけでなくなる。まず、国債を大量に保有している金融機関の財務状況が悪化し、破綻する可能性が生じ、預金者は引き出しを求めて、金融機関に殺到する、いわゆる「取り付け騒ぎ」が起きるだろう。加えて、銀行の機能が低下するので、資金調達面で難しくなり、投資が抑制され、債務を抱えた企業の倒産が続出する。
さらに、日本国の国債金利の上昇は、金利利払い費の増加を意味し、既に苦しい財政を一段と悪化させていく。
アメリカがサブプライムローンを仕掛け、世界中に経済恐慌損失を与えた結果、ギリシャの国家破綻問題として現れ、アメリカにもブーメランとして返っていったのがヴァレーホ市実態である。では、ヘッジファンドが狙う日本経済、我々はどう対応すべきか。次号続く。以上。
2012年02月21日
2012年2月20日 台湾総統選挙から日本を考える・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年2月20日 台湾総統選挙から日本を考える・・・その二
派手な選挙戦だったが争点は単純
今回の訪問で、台南の民進党の蔡英文候補陣営事務所に訪問してみました。事務所内には大きいポスターが一面に張られ、当然ですが留守番担当女性しか残さず、街中を選挙カーが10台以上連ねて連呼している姿を見ると、一見激しい派手な選挙であったことは認めます。
しかし、両者の主張は「対中国スタンスは大事にする」という点でお互い同じであって、差は「中国との関係構築づくりでどちらがより有利か」という視点、それは「経済的にどちらの方が今の台湾にとって有利か」に言いかえられますが、あくまでも経済面からの対決だけだったように思えるのです。
つまり、二候補主張の違いは「中国との立ち位置の差」なのです。かつての「大陸と統一か」「大陸から独立か」という二者択一をめぐった激しい舌戦とは異なっていました。それは行政院が2011年11月に実施した意識調査結果を、二候補が尊重して選挙に臨んでいるからです。
調査結果では「統一・独立」問題について、「現状維持」を望む層が86.6%もいるのです。大陸との関係で、今の状況を変化させたくないというのが圧倒的世論なのです。
たとえ話
大陸との関係を台湾20歳代女性に、大陸を剛健な男性になぞらえて展開してみます。
●「台湾ちゃん」・・・「確かに彼は(大陸)は、体が大きくて強い(人口・国土面積・資源力)が、まだまだお金持ちじゃないわね(一人当たりGNP)。それと荒っぽいでしょう(軍事力シャカリキ増強・南シナ海での行動)。相手にもっと優しくしないともてないわね」
●「大陸中国君」・・・「最近魅力的になったなぁ台湾ちゃん(大陸に進出企業)は、お金(経済力)と、おしゃれ感(技術力)もあるので大歓迎だよ。長いこと別居していた香港と、よりを戻して結婚(1997年香港が大陸に返還)してみたが、あいつらはインターナショナルな金持ち(国際金融市場保有)で、美人で高慢ちき(英国仕込み)だから、そろそろ新しい愛人(台湾)が欲しいなぁとずっと思っているよ」
●「台湾ちゃん」・・・「正妻のほかに愛人が欲しいなんて失礼だわ。私のお金と(経済力)とインテリ度(ハイテク産業力)の魅力に憧れるのは分かるけど、一度愛人になってしまうと大陸得意の虐待(税などで収奪)が始まるので、いくらうまい話をしてもうかうかのれないわ」
●「大陸中国君」・・・「そんなこと言っても、国連が台湾ちゃんは俺のものだと言っているぞ。早く来ないと一生男と縁がなくなるぞ」
●「台湾ちゃん」・・・「そんなことは分かっていわ。国連の意見は分かるけど、簡単に結論(統一か独立)は出せられないわ。だって今はお金があるし、世界中へ旅行出来るし、アメリカや日本と親友だし、とにかく快適な生活しているのよ。しばらく今のままでいいと思っているの」
●「大陸中国君」・・・「じぁ、まぁこちらもいろいろ問題(チベット等)を抱えているので、ジックリ長期戦で待つことにするか。その間にこっちはもっとよくなるから、その時台湾ちゃんにもてるような条件を出すので、いずれ愛人になること約束しようよ」
●「台湾ちゃん」・・・「そこが大陸君の欠点なのよ。すぐに結論を出そうとするから近隣(周辺国)から嫌われるのよ。私の今の気持ちを黙ってやさしく見守ること出来ないの」
●「大陸中国君」・・・「こっちも今年の11月には親父が代わる(主席交代)から、それまではお互い喧嘩しないでいくしかないなぁ。ただし、代わった親父(習近平)の考え方いかんでは、ちょっと乱暴になるかもよ」
●「台湾ちゃん」・・・「よくおぼえておいて。私の気持ちは当分今のままが良いの。そっとしておいてよ」
この「台湾ちゃん」の気持ちが台湾経済界の発言です。選挙前、創業者が急進的な台湾独立の主張で知られる、台湾化学大手「奇美実業」の寥錦祥董事長が「中国との安定した関係の発展は今後も続けるべきだ」と発言し、国民党支持を表明しました。今までの考え方を変えたのです。また、その他の大手有力企業の多くも、馬英九総統支持を明確にしました。民進党の蔡英文候補では、対中国関係が経済面で一抹の懸念が残ると考えているからです。
これは今まで企業が政治的発言を慎んできた台湾では見られなかった現象であり、ここに今の台湾人の気持ちが顕れています。
今や台湾人は、昔の「外省人⇒1945年以降に台湾に渡って来た漢族系の人=大陸との統一派=国民党」と、「本省人⇒1945年以前に台湾に来ていて台湾語を話す人=大陸からの独立派=民進党」という対立図式は、表面上時代遅れの感覚になりつつあると感じます。
フォルモサを考える時が来ているのではないか
しかしながら、台湾の国民生活にとって経済だけでよいのか、もっと大事なものがあるのではないかと強く感じます。そのことをついたのが日経新聞の特集「台湾の選択」(2012年1月16日から18日)でした。
この中での最後の結論見解で負けた民進党に対し「国民党よりも魅力的な政策を打ち出すしかない」と結んで、後は経済政策ではなく、他の面での魅力的な政策主張が必要だといっているのです。その通りと思います。
今回、高雄の国立中山大学 に行きました。台湾高速新幹線の高尾駅から、タクシーで大学構内の研究所建物前に行きますと、女性教授が階段を身軽に笑顔で降りてきました。とてもフレンドリーで、こちらの大型旅行バック見ると、今日宿泊する大学内のゲストハウスホテルへ、生徒に運ばせると非常に分かりやすい英語で語ってくれます。
研究室でもいろいろ親切に説明してくれ、資料も提供してくれ、昼食もゲストハウスでご馳走になり、ここでも「親日」を強く感じました。
夕食は町に出て、中華レストランで教授を招待したいと伝えると素直に頷き、楽しい会話を続けましたが、途中で当方から「台湾はフォルモサFormosaという 麗しの島」と称されるべき島ですね、と話題を提供すると、一瞬、顔が曇り、眉間に皺を寄せました。
実は、その表情変化の背景には、教授の専門が存在しているのです。
教授の専門は台湾近海に生育している「イボニシ(疣辛螺・疣螺) Thais clavigera」 の研究です。イボニシとは、腹足綱 アッキガイ科 に分類される肉食性の巻貝の一種。極東アジアから東南アジアの一部まで分布し、潮間帯の岩礁に最も普通に見られる貝の一つであって、他の貝類を食べるため養殖業にとっては害貝であるが、磯で大量に採取し易いために食用にされたり、鰓下腺(パープル腺)からの分泌液が貝紫染めに利用されたりしています。
ところが、環境ホルモンの影響によって、生物の生殖システムに与える危害は大きく、種の生存に大きな脅威となっていて、その証明としてイボニシの性別が乱れているらしく、その研究を手伝った助手、6か月の赤ちゃんがいる女性ですが、あまり海のものは食べないようにしていると発言しましたように、近海環境に懸念が残ります。
そういえば、高雄郊外の川辺を通った際、すごい数の煙突地区があり、あれは何かとドライバーに聞くと、製油所だという答えでしたが、空気が悪く窓は開けられなく、公害問題がまだ十分に改善していないというのが実態だと思います。
台湾人にとって魅力的な政策とは
教授とお酒を飲みながらレストランで一緒に食事し、胸襟を開いて話し合ってみると、ようやく台湾の位置づけが分かって来ました。
かつてフォルモサ・麗しの島と称されるべき台湾が、現在は経済優先・成長のために開発島にしてしまって、かつての公害日本と同じ道を辿っていると分かりました。
日経新聞の特集が示した結論見解「魅力的な政策」とは何か。それは、この教授が「これでよいのか」と、眉間に皺がよった問題ではないかと思います。つまり、それはフォルモサ・麗しの島に戻ることではないかと推察したいのです。
経済での豊かさ追求は必要でしょう。しかし、それを求めるあまり、海に囲まれた台湾が、肝心の海を汚して国民生活を脅かしてはいけないのではないかと思います。
しかし、3:11の福島原発で海洋投棄をした日本としては、大きな声では言えないのですが、敢えて述べれば、台湾の人々が、現在の経済重点思考を持ちながらも、自然環境も視野に入れた快適な生活島としてのフォルモサに戻る方向へ、ギアチェンジが必要なタイミングが来ているような気がしてならない。それが今回の台湾訪問の感想でした。
この課題は日本にもそのまま当てはまる
台湾の未来アイデンティティー検討と同じことは日本にもそのまま当てはまります。
日本は人口減を迎えて、いずれは1億人を切る人口数となりますが、その時の姿は今の経済構造社会では成り立ちえないでしょう。
日本人は新しいアイデンティティーを創造する必要があり、それを世論として構築していくことが必要です。
映画「山本五十六」は、マスコミに煽られ世論を間違えた事実を我々に伝えています。同じ過ちはしたくありません。
他国の選挙から自国の課題も考える習慣を身につけたいと台湾を事例にお伝えしました。以上。
2012年01月20日
2012年1月20日 今年の経済は難しい、だが鍵は米国だ(下)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年1月20日 今年の経済は難しい、だが鍵は米国だ(下)
湿板(しっぱん)写真家ジョン氏(John Coffer)のビジネス
前号でお伝えしたジョン氏の続きです。ジョン氏の放浪目的は修行であって、自分の原点とは何かを探る旅であり、自分は何者なのか、それを問うもので、結局、写真家であることを再認識した過程で、湿板写真に巡りあうことができた。
さらに調べてみると1946年に湿板写真の博物館があったらしいことと、二人くらい湿板写真家がいたらしいが、それ以上実態がよくわからず、今は誰もしていないことが分かった。
そこでスミソニアン博物館にも行ってみたが、学芸員も知らず、学芸員が上司に報告し、手助けしてくれ、写真の歴史を調べてくれた。これが1976年ころだった。ようやく湿板写真の実態が分かってきてチャレンジしようと意欲が湧き、それからずっと研究している。
この放浪旅の状況はウェブの自分のホームページで公開している。近くに住む大学生がつくってくれたというので、片隅の机の上をよく見るとパソコンがある。自給生活なのにソーラーパネルで最低限電力を持ち、パソコンは所有しているのだ。これになるほどと思う。
湿板写真家として知られてきたのは、このパソコンのおかげなのだ。生活は自給自活だが、情報発信はデジタル科学機器を活用する。だから、ジョン氏は有名になりつつあるのだと納得し、当方もジョン氏のホームページ公開がなければ知り得なかったのだから。
今の活動は、年一回開催のジャンボリー、これはここの土地で開く湿板写真の愛好家の集い。この参加は無料。但し、食費とテントは持参。自分の作品を扱ってくれているギャラリーが、NYに二か所とサンタフェと他に一軒あるように、自分の写真のイメージを評価してくれるクリエーターがいるとのこと。
その他にワークショップを開いている。ワークショップは世界中から申し込みある。オーストラリア、サウジアラビア、ノルウェー、スェーデン、韓国、日本からはまだない。今は愛好家がワークショップ参加者を通じて世界に1000人はいると思う。
ワークショップの2012年受講者は既に全部埋まっている。一回四人の受付で、5月から9月まで展開。このワークショップが最大の収入源。一人800ドル。参加者は変わり者と思える中年者や、南北戦争好きの人が多かったが、最近はアート志向の人と女性が半分来る。昔は女性が来なかったが、心理学と同じで、参加費用を高くすると多くの客が来ると発言。
この湿板写真が受け入れられているもう一つの理由は、ユニークで一枚しかないから。同じものをコピーできない。それが特徴。今までの作品数は何千枚。昔は肖像写真だったが、今はこの土地のものを映している。
と言いつつ写真撮りのスタジオ・テントに案内してくれる。このテント内に暗室と撮影に必要な各材料を保管している。
これは誰か。地元のインディアンか、老齢のサムライか。
さて、今の日常は、昼間は農業・酪農作業し、夜は手紙書き。メールはしないのですべて連絡は郵便。今回のアポイントも郵便だった。机上のライトとパソコン電源は日本製のソーラーパネルである。13時過ぎに取材が終わり、門まで行き長靴を脱ぐときも肩を差しだしてくれる。
とにかく、ゆったりした動作で、ゆっくり話す。すべてに慌てない。 カメラはアンティーショップで買うか、道端に捨てられているものを拾って使う。
湿板写真は準備に時間がかかり、撮影と現像から完成まで、手間と時間がかかるのが特徴だが、これがよいのだという。今のカメラは手間かからずよい写真が撮れるが、これとは全く正反対なのが自分の生き方であり、それに共鳴してくれる人がこの地に訪ねてくるのだ。だから今は幸せだと言い切る。
これからの生き方は、と問うと「今と同じことしている」と答え「自分の主張を守りながら、農業と畜産を続けること」だとつけ加え、歳をとったら死ぬだけだと笑う。
今の時代の進み過ぎた生活に対するアンチテーゼではないかと思い、再度「過去から見つけてきた湿板写真を通じて、現代生活がもう一度戻るであろう生活へのさきがけ」をしているのではないかと尋ねると「19世紀の生活と、現代の生活を比べながら生活している」と。
今回、この不便な僻地を訪問し、湿板写真家の実態を見聞きし、湿板写真愛好家が増えはじめ、その人達が自宅に同様撮影設備をつくるようになっていることを確認した。
グローバル競争世界では、他人と違うことに対して支払う対価が利益となるのであるから、ジョン氏の他と違う生き方が、少数ではあるが新しい需要を創ったといえる。
これはJPモルガンCEO ジエイミー・ダイモン氏がいう米国の不変な起業家精神の発揮であって、小規模ではあるが新ビジネスを創った、と思った次第である。
NYの二つ目の事例・手づくりで手間をかける
次の事例を紹介したい。NY地下鉄でブルックリンに行き、商店街の奥にある倉庫ビル、その大きな運搬用エレベーターで四階に上がりドアが開くと、段ボールの山で、これが会社かと思えないほどの乱雑さで散らかっている企業を訪問した。
これでは以前に見たインド・ムンバイで見た工場と同じレベルで、米国とはとても思えない。
この企業は液体石鹸、固形石鹸、キャンドルなどをこの倉庫内で製造し、日本のトゥモローランドや伊勢丹に納入している。NYではバーニーズなどで取り扱っている。
1991年に両親がブロンクスで創業、その後マンハッタン38丁目で製造していた当時は、ホームレスを使い、1ドルのローソクを100万個という体制の企業だった。
2004年に息子に経営権が移ってからは、今の方法の「完全手づくり・高付加価値方法」に変えたと、二代目30歳社長が次から次へとテキパキと話を展開し、写真も自由に撮ってよいという。写真撮られて、仮に他社に真似されてとしても、その時当社は違う事をしていると胸を張る。
今では磁器容器デザインから、石膏型つくり、粘土を練って型に入れ、それを乾して倉庫内の窯に入れ焼き、その磁器容器に蝋を入れる作業までを、全て手作業でこの乱雑な倉庫内で行っている。
従って、生産された製品は当然ながら均一ではなく、ひとつ一つが少しずつ違っている。不揃いなのであるが、それが当社の売り物だと再び胸を張り、一日に30個しかできない製品に6万個のオーダーがきているという。
工場内は雑然として、すべて手づくりだから時間と手間がかかっているが、在庫管理とホームページはパソコンで処理。お金出す宣伝は一切しない。パブリシティは歓迎。
昔の工場はこのような実態だったと思う。それを生産性向上という名目で、機械化等によって近代化し、大量生産できる体制にした。だからどこの工場もきれいになっている。
ところが、この企業は昔に戻して、近代化とは無縁の実態だが、それが今の時流だと言い切る。時代への逆行が時流であり、それが当社の伸びている背景で、そのためには「他との違い」を日夜考え続けることだと言い、「手間をかけることが価値を生む」と言い切り、再び自ら強く頷く。
帰りには製品をプレゼントしてくれた。成功したという自信に溢れている。再び、この企業はひとつの時流をつかんでいると感じる。これも起業の事例と納得した。
米国はVB大国だ
米国における2100年のベンチャーキャピタル投資は219億ドル。欧州の4倍以上、日本の15倍以上である。
米国の成人人口のうち起業に携わる人の割合は7.6%と主要先進国で最も高い。
アメリカ経済は難しい時に来ている。マクロ経済政策では救えないと思う。
ひとりひとり、一社一社の工夫と努力で救うしかないと考えるが、お伝えしたような事例の人達はほんの一例であるが、近代化と逆行するアイディアを出し続けている現場を訪問すると、もしかしたらJPモルガンCEO ジエイミー・ダイモン氏がいうように、米国の未来はまだ続くのかと思う。
今年は米国実態と経済データを注視しウォッチングしていきたい。以上。
2012年01月05日
2012年1月5日 今年の経済は難しい、だが鍵は米国だ(上)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2012年1月5日 今年の経済は難しい、だが鍵は米国だ(上)
今年の各立場から見た日本経済
新年明けましておめでとうございます。
まず、2012年の日本経済はどういう展開となるのか。それを各立場の予測を整理してみることから始めてみます。
①経営者⇒社長アンケートによると国内景気は「悪化している」と「横這い」で76%を超え「順調に拡大」はゼロ回答(2012年12月26日日経新聞)。日本航空の大西社長は「今年の景気について『こうなると言い切れる胆力のある経営者は今いないのでは』としつつ『悪いという見通しで構えをつくる必要がある』と発言。(2012年1月3日・日経新聞)
②民間エコノミスト⇒歴史的な円高や欧州債務危機などのリスクを抱えながらも、日本経済は実質2%前後の成長軌道で推移するとの見方で一致。(日経新聞2012年1月3日)
③日銀短観⇒日銀が12月15日発表した12月の企業短期経済観測調査(短観)は、日本経済が、急減速海外経済と比較的堅調な内需の綱引きになっている状況を浮き彫りにしている。
④政府財政投資⇒復興需要投資に加え、2012年度予算案で公共事業費が実質的に11年ぶり前年比11.4%増に増える。
経営者は弱気、エコノミストは条件付けながらも順調に推移すると見ています。
不透明要因は世界経済
昨年当初、日本経済は順調な歩みを始めたと思った途端、東日本大震災と原発問題危機、続いてギリシャから始まった欧州危機、タイの洪水危機と続き、加えて、超円高がのしかかり、苦しみの経済運営でした。
今年はどうか。国内要因からは大きな不安要素は見当たらない。返って復興需要の本格化と、公共事業費増がある上に、予てから批判の的であった日銀が、マネタリーベースを増やしたという変化、これは日銀が政府と協調して円高緩和策実施であるが、これが続けられれば円安局面に転じる可能性が高くなるので、日本経済にとってはフォローとなる。
しかし、問題は海外経済である。先の見えない欧州ユーロ情勢、米国の景気回復懸念、中国の景気減速傾向など材料に事欠かない。さらに、昨年の3.11のように、現実の世界は予想できないことがおきるから、先を楽観的に見通すことはやめた方がよいだろう。
だが、期待しないという条件下で「予想を裏切る景気回復」もあるかもしれないという「嬉しい誤算」も視野に入れておきたい。
意見が分かれる米国経済
欧州危機状態はしばらく片付かない。だから期待できない。中国はバブル崩壊という状態になったとしても、日本と違って土地は国有であるという前提条件で考えれば、それは上物のマンションバブル崩壊であるから、景気減速といってもそれなりに経済は動いていくのではないかと予測する。だが、米国の先行き予測は難しく、見解は二つに分かれる。
①米国ではリーマンショック後のバランスシート不況に苦しんでいる。2008年初めから四半期ベースでみた実質個人消費の伸び率は年換算で平均0.4%にすぎない。家計が貯蓄を十分に増やすには、まだ何年もかかるだろう。それまで債務が重荷になって米経済は低成長が続く。(モルガン・スタンレー・アジア会長 スティーブン・ローチ氏)
足元の指標が意外にしっかりしているが、長続きするかどうか分からない。家計の過剰債務が多く残っている間は低めの成長が続き、力強い回復はなさそうだ。大きな資産バブルが崩壊した後の典型的な現象だ。(元日銀副総裁 山口 泰氏)
②米経済は改善し始めた。個人消費にも強さが見える。米経済は下振れリスクよりも、上振れして驚くことになるのではと考えている。米国は世界で最もビジネスをしやすく、最高の大学と技術力を持つ。起業家精神も不変だ。成長力を取り戻せる。(JPモルガンCEO ジエイミー・ダイモン氏)
米国経済がジエイミー・ダイモン氏の発言通りになれば、日本経済にとって一つの大きな明るい条件となる。そこで、同氏が強調する起業家精神について、実際にお会いした起業家二人を紹介することで、米国経済実態を検討してみたい。
湿板(しっぱん)写真家ジョン氏(John Coffer)のビジネス
昨年11月末、ニューヨーク州のもう少しでカナダに入るという僻地に向かった。目的は湿板写真家ジョン氏のところである。
湿板写真は坂本龍馬の写真で知られている。この写真は高知県桂浜にある坂本龍馬像のモデルとなった写真で、1866年または1867年に長崎にあった上野彦馬写真館にて、井上俊三が撮影したもので、高知県立民俗歴史資料館所蔵品である。著作権の保護期間が満了しているので、各地で使用されている。
湿板写真は1851年にイギリスのフレデリック・スコット・アーチャーが発明したもので、撮影直前にガラス板を濡らし、乾く前に現像する必要があるため、写真乾板の登場とともに市場から姿を消したものである。
技術的には、ヨウ化物を分散させたコロジオンを塗布した無色透明のガラス板を硝酸銀溶液に浸したもので、湿っているうちに撮影し、硫酸第一鉄溶液で現像し、シアン化カリウム溶液で定着してネガを得る。日本語ではコロジオン湿板、または単に湿板と呼ばれる場合も多い。今のデジタル写真に慣れ切った我々には、手間と時間と設備が撮影に必要なので全く異次元であり、手が出ない写真撮り技術である。
朝の9時過ぎ、木組みでつくったジョン氏の粗末な門の前に立つ。門の下に太めの材木を数枚地面に並べ、そこに長靴が置いてある。雨が降ったのか地面がグヂャグヂャで普通の靴では歩けないので、長靴にはき替えようとするが、材木の上ではよくできない。
困っているとジョン氏が体を寄せて肩につかまれという仕草、それに甘えてようやく長靴に履きかえられた。長靴でも歩きづらく、道とはいえない地面を歩いて行くと、ひとつの小屋の前にたどり着いた。見るからに粗末な小屋。全部丸太組である。中に泥長靴のまま入る。
ジョ
ン氏の第一印象は仙人。優しい眼をしている。眼鏡越しに見る眼が柔らかい。眼は過去の生活体験が顕れるものだ。この土地は26歳の時に買った。1978年であるから、年齢を計算すると今は59歳だ。敷地は50エーカーある。約6万坪となる。広大だ。当時は安くワイン醸造業者から買ったという。今は高いので買えないともいう。
ジョン氏は小屋の中で、バターとシロップかけて朝食のパンケーキを食べている。シロップはカエデの木から煮詰めてつくり、黒砂糖や牛乳もつくる。そのための大きな装置もある。机らしき上にはいろいろな瓶とか缶が重なっていて、僅かな残されたスペースで食べている。食器はフライパンのまま。ジョン氏は全て自給自足生活。
ジョン氏が語り出す。昔フロリダで5・6年暮らした後、1978年の26歳まで7年間米全国を放浪した。
プロテスタントのメソジストが使っている馬車での一人旅である。
お金を持たず、お腹を空かした旅で、生きる最低限ギリギリの生活だった。一年間2000ドルしか使わない。自分の食事代のみ。 馬の餌は道端の草と時折街道筋で餌の提供を受け、自分も食事とシャワーの提供を各地で受け、元々写真家を目指していたので、各地で肖像写真を撮影し稼ぎ、生活費とし、何とか旅を続け、歴史・古いもの・昔の技術を調べているうちに湿板写真をみつけことができた。
ジョン氏訪問は次号へ続く。今年も世界から日本を見る視点でお伝えして参ります。以上。
2011年12月23日
2011年12月20日 ユーロ危機で分かったこと・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年12月20日 ユーロ危機で分かったこと・・・その二
戦後66年、EUの盟主はドイツになったこと
ユーロ参加主要国との比較でドイツだけが経常収支が黒字であることを前号で述べました通り、ドイツ一人勝ちなのです。何故にドイツが経済的勝利を得たのか。
それは簡単な背景です。EU体制がスタートして、ドイツの第二次産業の強さが発揮されたのです。EU体制前は、ドイツからヨーロッパ各国への機械類等の出荷は輸出扱いでした。各国毎の関税がかかっていましたが、今は関税なしで「域内出荷」となったことから、各国が優秀なドイツ製品を購入しやすくなり、一気に経常収支がよくなりました。EU体制が味方したのです。
表はユーロ諸国の経常収支で、一番上の青線がドイツです。これを見るとドイツは2000年のユーロ発足までは経常収支が赤字でした。1989年の東ドイツの統合の後、赤字に転落し、90年代を通じて問題でしたが、
ユーロ成立後、急速に黒字を拡大し始めたのです。
ですから、ユーロ加盟16カ国はドイツのお金が目当てで「メルケル詣で」し、その結果は「本来ユーロ17国で物事を決めるべきだが、ドイツが言ったことに他国が従う」(米コロンビア大ジェフリー・サックス教授)という実態になっているのが現実です。
もう一つ大事なポイントは、国民性というものがあるような気がしてなりません。
ドイツの一主婦から以下のメールを頂きました。
「今ヨーロッパは嵐のような状態です。ギリシャのみでなく、イタリアもどうなることか、はらはらさせられます。フランスは依然としてユーロ紙幣の増刷を主張しますが、怖い考えだと思います。”フランス人は考えずに走り出す”とはこのことでしょうか」
このメールには現在検討されている「ユーロ共同債」構想に対し、メルケル首相のみが反対している姿が反映しているのです。
メルケル首相は「国の競争力によって金利の格差がつくことが重要だ」と強調していまして、これは当たり前のことであり、この常識的なことをなくそうとする他国に対し牽制しているのですが、ここにもドイツ人の国民性が顕れています。
ハンブルグのミニチュア・ワンダーランド
そこで、今回訪問したドイツ各地で出会い、見聞きしたいくつかをご紹介し、ドイツ人の「しっかり度」を確認してみたいと思います。
まず、最初に感じるのは、訪問する企業・団体・大学・研究所等での対応の差です。ドイツでは大体のところで「説明するための資料が用意されている」のですが、他国では説明時にこちらから要求しないと資料は提供してくれないのが普通です。
ギリシャなぞは、後で送ると言いながら、送ってこないので催促すると「まだ、送ってありません」という返事だけで、その後も何も資料は届かないのが普通です。これが当たり前のギリシャビジネスの実態らしいのです。こちらが諦めるのを待っているのです。
今回、特にドイツ人の素晴らしさを実感したのはハンブルグの「Miniatur
Wunderland ミニチュア・ワンダーランド」でした。
海辺に近い倉庫街につくられたもので、今やハンブルグの人気スポットなっています。ここのアイディアは昔からある普通の発想で「ある場所のミニチュア版」を展示するというものですから、世界各地に同様な展示会場があると思います。日本にもあるでしょう。
しかし、それらとは違う魅力が会場に入ると一瞬にして分かります。倉庫を使っていますから、建物内は無造作なもので、内装なぞ全く綺麗さという点では劣りますが、本来的な素晴らしさがあるのです。
その一番目は、入口におかれているパンフレットです。16カ国の言語でつくられています。その中の日本語パンフレットの日本文を、慎重にチェックして読みましたが、全く違和感がなく正確に書かれていました。果たして、日本で同様の外国語パンフレットを作成した場合、どの程度の正確さが保たれているか心配します。多くのところで見ましたが、日本語を直訳した固すぎる英語になっているのが多いと思います。
二番目は、ミニチュアの緻密さです。以下の写真をご覧ください。
写真は実物はたった1.5cmの大きさを拡大したものです。アルプスの雪風景の中にあったものを撮影したのですが、屋根から雪下ろししていて、転落した様子がリアルにつくられているのです。このような細かい部分にも手を抜かず「しっかり」つくられています。従って、もう一枚の写真のように子供が身を乗り出して楽しむということになります。
まだたくさん説明したいことがありますが、このくらいにしてまとめますと
①古い発想で新しい創造⇒新鮮
②面白い・エンターティメント
③驚き・サプライズ
という三点になり、結果として本物としての魅力を感じるので、ここに人が集まり、収益が上がるのです。ドイツ製品がユーロ地域の他国に買われるのもこの理由と同じです。
日本人が見習うべきこと
このハンブルグの「Miniatur Wunderland ミニチュア・ワンダーランド」、技術的には日本人にも可能でできるでしょうが、日本人には②面白い・エンターティメント ③驚き・サプライズという二項目が全体的に欠けていると思われてなりません。
このところを外国人と提携して相互助け合うなら、世界中から観光に訪れる施設ができるのではないかと思っています。
最後に日本人が反省しなければならないことに、ドイツと日本は同じように経常黒字国でありながら、何故に純政府債務残高がドイツは57.6%で、日本は117.2%なのかという背景です。日本の国債発行は20年前のバブル崩壊時にとった財政政策に起因しています。簡単に述べれば「パル崩壊時の経済対策を、構造改革で乗り切るべきだったのに、景気対策を繰り返した」ことが今日の結果を招いていることは間違いない事実です。
当時のことを少し振り返ってみます。政権を握っていた自民党の政調会長だった亀井静香氏が次のように語っていました。
「坂道を転がり落ちている。支えねばならない」「トンネルを怪我人なしで抜け出たい」
「一家の稼ぎ頭の父ちゃんが倒れてしまったのだから、子供から借金をしても栄養をつけさせないといけない」(毎日新聞 1999年11月14日)等と言っては、景気対策の規模をどんどん拡大させていったのです。
また、当時の小渕首相は、1999年12月12日に「世界一の借金王にとうとうなってしまった。六〇〇兆円も借金をもっているのは日本の首相しかいない」と語ったのですが、今はその二倍に近づいているのです。
つまり、政治家の誰も構造改革を進めずに、小渕政権時代の自民党政権のままに国家経営をしてきた結果が、ドイツとの大きな純政府債務残高となっているのです。
ドイツのメルケル首相のみが、検討されている「ユーロ共同債」構想に対し反対している姿をみると、日本人と日本の政治家の戦略性なき国民性が問題だと痛切に感じ、日本人は「未来から今を見る」という思考力は皆無に等しく「先をあまり見ないで、今のところで頑張り続ける思考力」の国民だとつくづく思っています。真面目に努力する前に、未来を描き戦略を構築する脳細胞にする必要があります。
今年の日本は大変な年でした。このような年はしばらくないでしょうから来年は期待できると思っています。
皆さんの愛読に感謝です。以上。
2011年12月06日
ユーロ危機で分かったこと・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年12月5日 ユーロ危機で分かったこと・・・その一
フリクションボールのお土産で恥かく
11月は仏独に2週間出張しました。ドイツの知人に企業訪問時のお土産に「フリクションボール」をお土産にどうだろうと尋ねたところ、文房具店で販売しているが、日本からわざわざ持参したといえば歓迎されるだろう、という回答だったので東京駅前オアゾ・丸善書店で買い、贈答用に包装してもらい持参しました。
「フリクションボール」をご存じでしょうか。「消えるボールペン」のことです。昨年、パリで日本の消えるボールペンが話題なっていると聞きましたので、まだ新鮮だろうと考えてお土産にしようと思ったわけです。
ドイツで訪問した企業の社長にお土産ですと言って差し出すますと、すぐに袋を開けて一言「中学生の娘が3・4年前から使っている」というではありませんか。
ビックリし、それからいろいろドイツ人に聞いてみると全員が「子供が使っている」という回答です。日本に戻って大人の日本人に聞くと「フリクションボール」なぞは知らない、という方が多く、これはどうしてなのだろうかとパイロット社に問い合わせしてみると「2006年にヨーロッパで日本に先駆けて販売したところ大ヒットした」とのことで、その理由として「ヨーロッパでは義務教育では鉛筆使用が禁止で、万年筆かボールペンを使用させているのでヒットしたのだ」という回答です。
改めて仏独の義務教育の実態を調べてみると「しっかり明確に字を書くよう鉛筆使用が禁止」ということが分かりました。
なるほどと思いましたが、今まで何回もヨーロッパに行き、小学校・中学校にも訪問しているのに、鉛筆使用禁止ということは把握していなかったわけで、随分知らないことが多いと反省しているところです。これはユーロ危機でも同様です。
ユーロ危機で分かったこと
今回のユーロ危機で分かったことは、
(1)ギリシャという国は特殊であること
(2)戦後66年、EUの盟主はドイツになったこと
ではないかと思います。
(1)ギリシャという国は特殊であること
ギリシャが特殊なことは、既にお伝えしておりますし、新聞紙上で毎日のように問題点が取り上げられていますので、十分ご存じだと思いますが、大事なことをひとつだけ述べれば「今のギリシャ人には古代ギリシャ人の血が一滴も流れていない」というドイツ人学者の見解です。(内山明子著 国立民族学博物館『季刊民族学』123号2008年新春号の『ギリシャ・ヨーロッパとバルカンの架け橋』)
これが発表された時にはギリシャ国内に衝撃が走りましたが、実際にギリシャ各地を歩いてみた感じでは、古代ギリシャ人の血が入っていない、というのは事実ではないかと実感しています。
つまり、カール・ヤスパース(独)が言う「人類の枢軸の時代」、紀元前500年頃を中心とする前後300年の幅をもつ時代を「枢軸時代」と称し、人類の歴史に多大な影響をもたらした大いなる賢人がずらりと出現し、中国では孔子と老子が生まれ、中国哲学のあらゆる方向が発生し、墨子や荘子や列子や、そのほか無数の人びとが思索し、インドではウパニシャット(宗教哲学書)が発生し、仏陀が生まれ、懐疑論、唯物論、詭弁術や虚無主義に至るまでのあらゆる哲学的可能性が展開されました。
イランではゾロアスターが善と悪との闘争という挑戦的な世界像を説き、パレスチナでは、エリアから、イザヤおよびエレミアをへて、第二イザヤに至る予言者たちが出現し、ギリシャでは、ホメロスや哲学者たちパルメニデス、ヘラクレイトス、プラトン、更に悲劇詩人たちや、トゥキュディデスおよびアルキメデスが現われたのです。
以上の賢人たちが、地域が異なりながら、どれもが相互に知り合うことなく、ほぼ同時的にこの数世紀間のうちに発生したわけで、この時代を「人類の枢軸の時代」というのですが、この栄光ある古代ギリシャ人と、今のギリシャ人は血でつながっていないということを知り、改めて、今回のユーロ危機発生がギリシャ国家の粉飾決算から始まったことと結び付けると「なるほど」と深く納得したわけです。
「ギリシャ人のまっかなホント」(アレキサンドラ・フィアダ)という1999年に出版されたコミカルな本があり、同書で「これだけは断言できる。EU定数にギリシャ人を巻き込んだシステムは、じきにギリシャ的になる」と、EU加盟国はいずれギリシャに感化されていい加減になっていくと”予言”していました。(2011年7月2日週刊ダイヤモンド 加藤出氏)
また、ユーロ発足時のブラックユーモア「THE PERFECT EUROPEAN SHOULD BE...」直訳すれば「あるべき完璧なヨーロッパ人とは……」となり、「こういう各国の人々が集まっているのだからEUの将来も万々歳だよね」という皮肉を述べていました。
DRIVING LIKE THE FRENCH
(フランス人のように運転マナーがよく)
HUMOROUS AS A GERMAN
(ドイツ人のようにユーモラスで)
CONTROLLED AS AN ITALIAN
(イタリア人のように自制的で)
SOBER AS THE IRISH
(アイルランド人のように酒嫌いで)
HUMBLE AS A SPANIARD
(スペイン人のように謙虚で)
ORGANIZED AS A GREEK
(ギリシャ人のように整理整頓好きで)
ギリシャに対して、様々な忠告・提言が行われていますが、多分、その内容は実行されないと思います。
2008年の金融危機を予測していたルービニNY大教授がが「ギリシャのユーロ離脱は時間の問題だろう」と語っていますが(日経新聞2011年11月18日)、これが当たる可能性は大であり、ギリシャは「元々ユーロを導入する資格がない国だ」と日経新聞の「大機小機」(2011年11月25日)でも述べているように、ギリシャは異質な国であり、ギリシャを除くユーロ加盟16カ国は、ギリシャ一国に翻弄され、それが他国に影響波及することは必至ですから、ギリシャ排除をするのではないでしょうか。
(2)戦後66年、EUの盟主はドイツになったこと
ギリシャ問題から発生したユーロ危機で分かったもう一つの重要なことは、ドイツの強さです。今や各国首脳が毎日のようにドイツ・メルケル首相をベルリンに訪ねています。「メルケル詣で」という現象です。
どうしてなのか。それは次表で明らかです。
ヨーロッパ主要国との比較でドイツだけが経常収支が黒字なのです。ドイツ一人勝ちなのです。何故にドイツが経済的勝利を得たのか。
現在、日本で激しい議論が交わされているTPP(環太平洋戦略的経済提携協定)問題にも通じますので、他国制度の実態状況を把握は大事ですので、次号で分析続けます。以上。
2011年11月20日
2011年11月20日 観光地は超訳がお薦め・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年11月20日 観光地は超訳がお薦め・・・その二
マクロ対策での限界
観光とは異なるが、アメリカ経済の実態を見ていると、世にいう「マクロ経済学者」が唱える経済政策が失敗したとか思えない。
アメリカ経済はリーマンショックから3年たっても失業率は下がる気配がなく、各地でデモが発生し続け、米連邦準備理事会FRBが足かけ6年にも及ぶゼロ金利を予告しているのだから、日本と同様に低成長状態に陥ったと言える。
リーマンショック前まで、アメリカ経済学者やFRBの幹部が揃って「バブルが崩壊しても金融を迅速かつ十分に緩和すれば対処可能」と豪語し、その反面教師として日本を挙げ、「日本の失敗はデフレに陥ったことであり、デフレはマネーサプライを増やせば、たちどころに解決する」と日本の経済政策当局を嘲笑っていた。
その嘲笑いの通り、アメリカは大胆な金融緩和に踏み切り、さらに、景気が思わしくないとみると、追加的な量的金融緩和政策Quantitative EasingいわゆるQE2を実行した。
このマネーが国際商品相場を押し上げ、アメリカのデフレ懸念は遠のいたように思えたが、新興国が金融引き締めで対抗した結果、株価は一時的な上昇にとどまり、明確な景気回復にはつながず、ジョブレス・リカバリーjobless recovery (雇用拡大を伴わない景気回復)となって、アメリカ各地でのデモにつながったのである。
つまり、史上最大の景気刺激策を展開しても、予想に反して効果を発揮していないわけで、とうとうノーベル賞受賞学者のポール・クルーグマン・プリンストン大学教授も、日本に対して嘲笑った事に対し「謝るべきかもしれない」と述べている。(日経新聞2011年10月6日)
マクロ政策では解決しないだろう
「デフレの正体」の著者藻谷浩介氏は、次のように述べている。(デフレの正体16頁)
「健康診断にたとえましょう。『GDPが上昇すれば、世の中の隅々まで経済的な豊かさが波及していく』という考え方は、『総合体調指数が改善すれば、血圧も体脂肪率も血糖値も尿酸値もみんな改善する』という発想と同じです。実際は逆で、血圧や体脂肪率や血糖値や尿酸値が個別に改善していけば、その帰結として計算結果としての総合体調指数が上昇するのです」
その通りでしょう。我々の経済は一人ひとりの生活を保障するものでなければならず、一人ひとりが豊かになるところに国家の経済政策があるべきで、国全体の経済成長が図られたとしても、その結果、かえって経済較差が広がり、貧困家庭が増加するようでは国民生活が向上したとはいえない。
観光政策も同様で、観光庁が1万人作戦を採る事は、採らないよりはましだが、例えこのマクロ政策が成功したとしても、従来から著名の特定人気観光地に偏った外国人増加になってしまえば、外国に知られていない観光地には何ら意味がなく、効果もない観光政策となってしまうだろう。
日本政府観光局JNTOが外国に日本観光をPRしている一事例を紹介したい。それは英国航空BRITISH AIRWAYS機内誌の宣伝である。PRしているのは五カ所、東京、高山、高野山、京都、沖縄であって、他の各市町村は無視されているのである。
つまり、このようにPRされた観光地には外国人が大勢訪れると思うが、その他の知名度のないところには訪れない。したがって、知られていない各市町村は、自ら努力すべきで「今まで知られていない自らの観光地にどうやって外国人を来るようにするか」という事を考えるのが最重要課題で、外国人誘致政策立案能力が問われる事になるが、その為には最も大事な前提要件がある事を認識しなければいけない。
観光地は意識変革をしないといけない
それは、日本人観光客に対する対応する施策を、そのまま外国人に対応させるのは難しいという事である。日本人に対する観光政策と、外国人への対応とでは意識を変えないといけないのである。
時折、相談を受け、英語に翻訳された観光ガイド資料を見る機会がある。日本人である筆者が翻訳された英語を読んでも、あまり違和感を持たないが、先日、在日アメリカ人のコロンビア大学卒・ハーバート大学院卒の博士で、博士論文が日本企業研究という日本語を自在に話せる女性に、この英語観光ガイド資料を見せたらバッサリ「面白くない」の一言。
つまり、真面目に詳細に説明し過ぎているので、外国人に難しく、難しいから読まなく、読まないから分からず、分からないから面白くないという結果になる。
先日、このアメリカ女性と関東地区の観光地に行き、観光関係者から車で各地を案内受けた時の彼女の様子が参考になると思う。
最初に連れて行ってくれたのが博物館で、学芸員が説明を始めると、頷き関心を持ち、猛烈な速さでノートを広げ英文でメモを取り、説明が終ったあと「すごく楽しかった」と発言する。
次に、地元では著名な神社に行き、神主さんから歴史的説明が丁寧にあったが、今度は全くメモしなく、次に訪れた寺でも同様で、関心を示さない。
実は、この事は私が欧米各地を始めて訪問したところで、地元の方が、外国人である私を案内してくれる時と同じである。各地には著名な教会があり、その教会はその地の人々にとっては重要な意味を持っているが、キリスト教と聖書を十分に把握していない当方には、地元の方の説明が難しく、結局、建物の素晴らしさを見るのが中心ポイントになってしまう。
また、教会は各地にいくつもあり、それぞれ異なるデザイン・仕様で建設されているが、当方には詳細な部分の差が分からないので、全部が概ね同じように見えてしまい、結果として教会見学に飽きるという事になる。これと同様な事が日本の神社仏閣訪問時に、彼女の態度によって鮮明に示されたのである。
さらに、欧米人は文化的観光資源と、日本人の生活実態に関心と興味を持つ傾向が強い。この点、日本は長い歴史から構築されてきた文化遺産と、一般人の生活は狭い土地に住みながらも、その水準は世界でも最も豊かで清潔であるから、この実態に触れると大変驚き感激する。
もう一つ評価が高いのは日本食である。日本食はヘルシーであるという評価が世界中で定着しているが、日本に来て本物の日本食に接すると、外国の地で食べる味わいと異なり、さすがに違うと喜ぶのである。
このような背景であるから、その地の飲食店マップは最低の必要条件であり、そのマップ上に店を紹介する文面が外国語で書かれていると最高だろう。
最後に決定的に重要な事
もう一つ決定的に重要なのは英文化作業で、単に日本語で書かれた原文を英語に忠実に翻訳するのではダメである。外国人の立場から翻訳するという事が絶対必要条件である。
これは簡単な事ではないが、この「情報編集」を巧みに行っているのが、村上春樹であろう。村上春樹の小説は、全て日本が舞台で、日本人のみが登場するのであるのに、世界中から受け入れられている。その原作に忠実でない翻訳、つまり外国人によって「超訳」が行われているのである。これが村上春樹の人気理由の背景にあるひとつの重要な事実だ。
現在、先ほど登場したアメリカ人女性と一緒に、関東地区のある市の外国人用観光ガイドブックを作成したところである。勿論、私が外国人用に「情報編集」した日本文を、彼女が自分の言葉で再度「情報編集」し英文にする、つまり「超訳」したが、興味ある方はご連絡いただければ、その「情報編集」方法と英文化についてご案内したいと思っている。以上。
2011年10月20日
2011年10月20日 世界には日本人がのぞき込めない世界がある・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年10月20日 世界には日本人がのぞき込めない世界がある・・・その二
ボトルショック
前号に続くワインの闇の話。外国に行く楽しみの一つはワインである。日本では殆ど飲まないが、欧米に行ったときは、その地のワインを楽しむことにしている。それほど味に詳しくなく、ワインの知識もあまり持ち合わせていないが、その地で飲むワインは、その地の匂いと味わいがすると、いつも感じる。
世界のワイン市場は激烈な競争下にある。ワイン市場で新世界と称されるカリフォルニア、チリ、オーストラリアはじめ南アフリカワインや、最近では日本の甲府ワインまでが欧米に輸出されるようになってきて、ワインの旧世界・ヨーロッパはたじたじである。
特に旧世界の盟主であるフランスは、ボトルショック(Bottle Shock)で打撃を受けた。
ボトルショックとは、1976年にアカデミー・デュ・ヴァンの創始者スティーヴン・スパリュアが、パリで開催したブラインド・テイスティングにおいて、当時全く無名であったカリフォルニアワインが、バタール・モンラッシェ、ムートン、オー・ブリオンといった最高のフランスワインを打ち破った事件を映画化したものである。
この事件が引き金となり、その後世界中のワイン業界は激動の時代に突入したのである。
ボルドーの「ぶどう栽培、ワイン科学研究所 Institut des Sciences de la Vigne de du Vin」
パリの全国農業コンクールに毎年参加している。昨年二月開催時にボルドー地区の一つのワインコーナーで試飲した女性経営者と親しくなり、ボルドーに行くと彼女のワイナリーに立ち寄り、食事をご馳走になりながら、いろいろワイン造りを教えてもらっている。
というのも彼女のワインに関する蘊蓄がなかなかのもので、参考になるので「それはどこから仕入れたのか」と尋ねると「兄がボルドーの『ぶどう栽培、ワイン科学研究所 Institut des Sciences de la Vigne de du Vin』の教授なので教えてもらっている」との発言である。名前を聞くとボルドー大学教授でもあり、醸造学では世界的権威の人物である。
そこで、彼女の紹介を受け、長らく疑問に思っていた「良いワイン造りの条件」についてレクチャーしてもらおうと、今年の7月の暑い一日、研究所に訪問した。
さすがに研究所は立派である。世界各国から研究者が集まっている先端センターであり、サントリーとも提携していて、日本人研究者も多く訪れるところである。
ここでボルドー大学の醸造学教授からレクチャーを受けたが、良いワイン造りの結論は「葡萄苗から吸収する水の管理が第一重要条件で、次に葉と実のコントロール、これは葉に水が行きすぎると実によくない影響を与えるという二つが条件だ」とのこと。
とにかく明快スッキリ結論で、素人にもよく分かるが、何か欠けていると感じる。
それは、地質との関係が抜けていることで、教授の見解は地面の質が関係しないという見解になる。そこで、そのことを質問すると、勿論、地質が関係するが、それは土地の粗さと細かさで水の保湿力が変わるので、ぶどうの実への水吸収度合に影響するから、該当地質に合う苗木の種類選定に関係する程度だという回答である。
つまり、良いワインと地質との直接因果関係はないという事になる。これは素人考えだが、大いに疑問を感じるが、ボルドー大学教授があまりにもきっぱり断定するので、専門知識のない当方としては追及できなかったが、どうも釈然としない。というのも、世界各地のワインの宣伝には、必ずその地の自然条件、中でも土地環境が写真と共に語られているからである。
そこで、ここの研究所と関係が深いというサントリーに聞いてみようと、広報部に問い合わせしたところ、山梨県の登美の丘ワイナリーで説明してくれることになった。
テロワール(terroir)
山梨県甲斐市大垈の「サントリー登美の丘ワイナリー」では、責任者が親切に説明対応してくれたが、同氏はボルドー大学教授と若い時代にボルドーで一緒に学んだ仲であり、従って、結論は同じであった。
では、ぶどうの栽培地の環境条件、気候、土壌、水などは全く関係ないのか、という疑問に対して、次の説明が展開された。
まず、テロワール(terroir)という概念が大事だと強調した。 この言葉はフランス語特有で、英語にもこの意味をそのまま表わす単語はなく、日本語にも見当たらない。
その「テロワール」だが、フランス人のように体感的・感覚的な意味で理解出来ないが、しばしば登場するので、この概念や意味を把理解しようとすることは必要だ。
極めて大雑把な説明は、テロワールとはぶどう(ひいてはワイン)が生まれてくる環境全体を指すのだ、というもの。つまり、ぶどうが生育する環境が違えば、たとえ同じ種類のぶどうを植えたとしても、出来上がるぶどう(したがってワイン)も異なるという考え。
では、環境といっても具体的にはどんなことを言っているのか、つまり、何が収穫されるぶどう(出来上がるワイン)に違いを与えるのか、というその要素の説明が必要となる。 おそらくフランスのぶどう生産者(ワイン生産者)にとって、この手の質問は彼らを苛立たせるものだろう。
というのは、そんなことは彼らの長い長いワイン造りのなかではなんら説明を必要としない自明の概念なのであって、それをいちいちどの要素がどうで、それがどのようにぶどうやワインに影響するかなどということを、分析的に説明を加えるなどということはナンセンス極まりないということになる。
事実、ブルゴーニュのある高名なメゾンのオーナーがこの質問を受けたときに『テロワールはテロワールだ。』と憮然と答えたという。
彼らは、ぶどうができる場所によって出来上がるワインの個性が変わる原因を、経験的・体感的に認知し、それらの違いを『土地』『大地』『土壌』という意味を中核に持った『テロワール』という言葉で概念的に使っているのだ。日本語で敢えて考えると日本語の『風土』という言葉はフランス人の言う『テロワール』の感覚に近いかもしれない。
この説明を受けてようやく分かったことは、ボルドー大学教授は何故にテロワールに触れなかったということである。彼にとってテロワールなぞは説明するにあたらない概念なのだ。
一方、サントリーの責任者はワイン後発国の日本人であるので、日本人に対しては、テロワール概念を調べ研究し説明しないと分からないだろう、だからワインの説明にはテロワール概念をまず話すことが不可欠な要素概念と思っているので、当方にも時間をかけてレクチャーしてくれたのだ。
分かったが体では理解できないものだ
ここで冒頭のボトルショックに戻るが、ボルドー大学教授の「水の管理に尽きる」というレクチャー、これがテロワール概念から発したものだと今は理解し、ボルドーでは水のコントロールをしてはいけなく、すべては天然の雨ののみが水としてぶどうに与える水分となっている。つまり、コントロールしないで水の管理をする事になり、水分補給は天候次第というのが旧世界のヨーロッパのワイン造りなりである。
一方、新世界のワイン造りは乾燥地で展開されることが多い。ということは水を適度に与えるという事を行っているのである。水のコントロールを人工的に行うワイン造りとなっている。
これは雨量の多い日本でも同様で、多すぎるための対策は当然にとられている。土中の雨水を流す土管つくりなどであるが、このような水対応策を各自然条件下で展開している。
したがって、ワインのブラインド・テイスティングコンテストを行ったとしても、そのワイン造りの最も重要な条件である、水のコントロールが異なる方法であるから、妥当で的確なコンテストとはいえないかもしれないと今は思っている。
日本人がのぞきこめない世界があるのだ
良いワインをつくるためにはフランスではテロワール概念があるが、それをフランス人からは教えてもらえず、日本人から教えてもらって、ようやく何となく分かったような感じとなった事に複雑な思いをしている。
つまり、日本人には分からない世界、日本人がのぞき込めない世界があるのだということであって、その一つが「テロワールTerroir」なのである。その地に生まれ、その地で育たないと絶対に分からないというものがあるのだという事を、理解しないといけないと思っている。
ギリシャ化問題にある深い闇、草津温泉の欧米人との闇も同様に難しい課題だ。以上。
2011年10月05日
2011年10月5日 世界には日本人がのぞき込めない世界がある・・・その一
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年10月5日 世界には日本人がのぞき込めない世界がある・・・その一
欧州は日本化ではなくギリシャ化だ
エコノミスト(7月30日)の表紙は刺激的だった。オバマ米大統領とメルケル独首相が着物姿で登場して「欧米は日本化に向かっている」と特集を組んだ。
だがしかし、今年8月に入って状況は一変した。日本の実態は確かに悪く、バブル崩壊後20年間成長が止まって、デフレが続いているが、日本は世界各国に福島原発問題で迷惑と心配をかけている以外は、経済的に悪影響を及ぼしていない。
一方、今の世界はギリシャ問題が浮上し、これがEU諸国に多大な脅威を与えている。ギリシャのGDPは約23兆円、東日本大震災で被害を受けた岩手、宮城、福島三県のGDPとほぼ近い経済規模である。岩手、宮城、福島三県が日本全体に占めるGDPは約4%程度であるが、ギリシャがEU全体に占める経済規模はわずか2%に過ぎない。
この2%としか占めないギリシャが、今やEUを混乱させ、ひいては世界経済に悪影響を与えているのであるから、英国エコノミストが日本化なぞと揶揄している時でない。
エコノミストが表紙に掲載すべきは「日本化」でなく「ギリシャ化」であろう。他人の国を批判する前に、自国が深く関与しているギリシャ問題をどうするか、その特集を組むべきだろう。世界はギリシャ化という大問題に立ち至っているのである。
ギリシャは闇の国だ
ギリシャ問題を語る時、どうしても触れなければならない人種問題がある。今のギリシャ人は古代ギリシャの直系の民族なのかという疑問である。アテネを訪れると不思議な感じをもつだろう。タクシーの運転手や信号で物売りしている若者たち、通りを歩いている人たち、その体つきと顔を見ていると、ギリシアに来たとは到底思えず、今、ここアテネに住んでいる人たちは本当にギリシア人なのか、という疑問をもつ。
古代ギリシア人の彫刻は国立考古学博物館に行くとたくさん展示されているし、ギリシア文明を義務教育で学んでいるので、古代ギリシア人のイメージはしっかり脳に残っている。すばらしい理知的な瞳と顔立ちをしているブロンズ像でギリシア人のイメージが固まっている。
だから、街中を歩いている人たちは、皆古代ギリシア人のブロンズ像のようであることを期待し、その確認のためにアテネに来たようなものであるが、実際のアテネを歩いている人たちは、随分異なる。違った国に来た。これがアテネの第一印象である。
そこで改めて、ギリシアを地図上で見てみると、ヨーロッパの東南部、地中海のイオニア海とエーゲ海に挟まれたバルカン半島の南端に位置している。イオニア海の向こう側のイタリアとは陸続きではない。だが、北方はアルバニア、マケドニア、ブルガリアと国境を接し、驚いたことにトルコと陸続きなのである。 ギリシアはヨーロッパである、というイメージを持って訪れると妙な感覚になる。
さらに、独立早々ドイツの学者によって「今のギリシア人には古代ギリシア人の血が一滴も流れていないと書かれてしまったときには、国じゅうに衝撃が走ったのだった」(内山明子著 国立民族学博物館『季刊民族学』123号2008年新春号の『ギリシャ・ヨーロッパとバルカンの架け橋』)という指摘もあるほど、古代ギリシャ人と今のギリシャ人は関係がないという感じが強く持つ。
紀元前500年頃を中心とする前後300年の幅をもつ時代を「枢軸時代」と称し、人類の歴史に多大な影響をもたらした大いなる賢人がずらりと世界各地から出現したが、その代表はギリシャであった。ホメロスや哲学者パルメニデス、ヘラクレイトス、プラトン、更に悲劇詩人たちや、トゥキュディデスおよびアルキメデスなどであったが、この時代のギリシャ人と今のギリシャ人はどうしても違う、と現地に行くと強く感じてしまう。
1999年に出版された「ギリシャ人のまっかなホント」(アレキサンドラ・フィアダ著)というコミカルな本がある。 同書は、EU加盟国はいずれギリシャに感化されていい加減になっていくと次のように”予言”していた。
「これだけは断言できる。EU定数にギリシャ人を巻き込んだシステムは、じきにギリシャ的になる」と。
このように揶揄されるギリシャをEU加盟させた裏側には、欧米人がギリシャに持つ、しかし、日本人には分からない「のぞきこめない深い闇」があるのではないかと推察している。そうでなければ怠惰で、改革を嫌がり、毎日のデモで既得権益にしがみつくギリシャ国民を、勤勉な国民性のドイツ人が、多額の税金負担までして救おうという事にはならないと思う。だが、ギリシャの深い闇は奥深いから、容易に解決する問題ではなく、世界経済の先行きは難しい局面の連続だろう。今後とも強く関心し続けたいと思っている。
草津温泉に対する欧米人の闇
日本を代表する温泉地は草津である。これは日本人なら殆どの人が納得する結論であろう。文化年間(1804~18)に発行された温泉番付「諸国温泉功能鑑」でも、既に東の大関として(横綱はなし)位置づけられている程である。
草津の源泉は51度から熱いところでは94度もあり、しかも刺激の強い酸性泉であり、そのままでは熱くて入浴することができないので、加水しない「湯もみ」によって、自然に温度を下げる入浴法が「草津湯もみ唄」と共に有名で、日本の観光ガイドブックには必ず草津温泉が詳細に紹介されている。
また、海外の温泉専門書でも、日本の特徴である高熱入浴の事例として草津の「湯もみ・時間湯」風景が、江戸時代から伝わる独特な入浴法として必ず紹介されている。下の絵でも片隅に外国人らしき人物が描かれているので、幕末時から明治初期の昔から外国人も興味持っていた事が分かる。
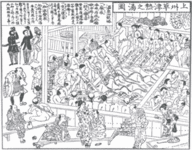
ところで、世界の代表的な旅行ガイドブック、それは仏ミシュラン社のグリーンガイドと、仏アシェット社のブルーガイドであるが、ここで草津温泉の取り扱いはどうなっているのであろうか。
ガイドブックを開くと、グリーンガイドでは東京周辺地図に名前が表示されているだけ、ブルーガイドに至っては地図上に草津の名前がない。
つまり、両ガイドブック共に草津温泉の内容紹介をしていないのである。無視しているとしか考えられない。
ところが一方、日本人の殆どが知らない別府鉄輪の「ひょうたん温泉」がグリーンガイドで最高ランクの三ツ星になっている。これは大変な驚きで、何か欧米人と日本人の間に理解の差、何かの闇があるような気がしてならない。
勿論、草津温泉は立派に英語のホームページを開設して、その中で詳しく情報発信しているのであるから、ガイドブックライターが紹介しようとすれば簡単であるのに、掲載されていない事、どうしても釈然としない。
この問題は草津温泉自らが解決すべき課題であるが、草津温泉関係者が動かない場合は、近いうちに両ガイドブックのライターに会い、その理由を聞きたいと思っている。
いずれにしても、日本人が温泉の代表と思っているところが、欧米人からは評価されず、日本人が知らない温泉が最高ランクに評価されているという事実、この背景にどのような闇があるのか知りたいと思っている。
ワインの世界の闇
さらに、日本人がのぞきこめない世界にワインがあるが、これを解説するためには前置きが必要であって、そのためにはテロワール(terroir)概念を説明しないといけない。だが、これは簡単にできないので次号でお伝えしたい。ワインの世界も一筋縄でいかない。以上。
2011年09月21日
2011年9月20日 ミシュラン空白ゾーンは狙い目だ・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年9月20日 ミシュラン空白ゾーンは狙い目だ・・・その二
前号に引き続き「ミシュラン空白ゾーンは狙い目だ」をお伝えします。
海辺の有名某市に提案した事
前号でいろいろ述べました背景を持って、ミシュランガイド空白ゾーンの海辺有名某市で「外国人観光客誘致」についてお話しました。
お伝えした内容は、こちらの市はもともと豊かな素晴らしい観光資源を持っているのだから、それを外国人用に情報編集し、英語・仏語にする事が必要であるという一点だけ。
しかし、その実現の為には前提があると次のように提案いたしました。
それは「戦略」を構築する事です。また、「戦略」を定めるには、その前に立場を明確に決定しなければいけません。立場を決めないと「戦略」を立てられず、「戦略」無き展開は成功しません。
戦略構築のためには立場を明確にすること
そこで、その戦略構築のためには、次の二つの「立場」があるだろうと説明しました。
① 景気がよくなって、その結果として自然に観光客が来るようにしたいという考え方・立場で、これは「日本がGDP成長すれば」「市が属する該当地域全般を県が活性化してくれれば」「市が画期的事業を展開してくれれば」という、いわば他者に依存する立場です。
② そうではなく、自らの工夫企画力展開で観光客を増やすという考え方・立場で、関係者の主体的行動によって進める立場です。
この二つのどちらの立場にするか、それを観光協会と市の観光課長に尋ねましたが回答はなく無言でした。多分、普段考えていない範疇の問いで、一瞬、答えあぐねたのでしょう。だが、自らの優れた観光財産がありながら、外国人観光客が少ない現状は、日本全国いたるところにあるでしょうが、これは実はフランスでも同様なのです。
フランス・アルカッションの牡蠣祭り事例
① フランスでも地域によって外国人観光客は少ない
外国人観光客を増やそうという、フランス・アルカッション市の事例を紹介したいと思います。年間8000万人という世界一の観光客を受け入れているフランスでも、地域によっては外国人観光客が少ないところが多々あります。
アキテーヌ地域圏ジロンド県に属する、大西洋岸のアルカッション市も同様で、芳醇な香りを誇るワインで有名なボルドーには多くの外国人観光客が訪れるのに、そのボルドーから60kmしか離れていない牡蠣の町アルカッションには外国人は少ないのです。
そこで、アルカッション市は地元活性化のために、外国人観光客を取り込もうと、同市の特徴である牡蠣をメインに「第一回インターナショナル牡蠣祭り」を企画し、当方に市長から招待状が届きましたので行ってまいりました。
アルカッション市の関係者とは、毎年春先に開催されているパリの農業祭における牡蠣品評会で知りあった関係から招待状が届いたのです。
② 牡蠣祭りが始まった
アルカッション湾は、25,000ヘクタールあるが、湾の入り口は幅3キロメートルしかなく、その狭い水路へ巨大な大西洋から流れ込み、潮の満ち引きにより海へ逆流し、毎日、37,000万立方メートルの水が、毎秒2メートルの速度で出たり入ったりする。水路はそのために変化し、そこに強風が加わると非常に危険で、船乗りたちが恐れる海域です。
さて、祭りの当日、海辺の牡蠣祭り会場入り口に向かうと、既に100人くらい集まっていて、ブラスバンドも演奏を始め、そのあとを市長と一緒にインターナショナル牡蠣祭りの会場に向かいました。海辺の会場には日本、アイルランド、スペイン、フランスの四カ国の牡蠣状況が展示された牡蠣小屋が設置されています。インターナショナル牡蠣祭りといっても参加はフランス含め4カ国にすぎません。これは第一回なので少ないのです。
③ 牡蠣剥きコンテストは定番
各国の牡蠣小屋を紹介した後は、いよいよ牡蠣祭り会場のテープカットでした。アルカッション牡蠣組合長が晴れがましい笑顔でテープを切ると、花火が上がり盛大な拍手。
その盛り上がった雰囲気の中で、テーブル上に置かれた四個の牡蠣、その産地当てクイズや、牡蠣剥きスピードコンテストが行われます。
牡蠣を生で食べるヨーロッパでは、牡蠣剥きコンテストはやはり牡蠣祭りの定番です。ここが日本の牡蠣祭りとは違うところです。
④ メイン会場の盛り上がり
再びブラスバンドを先頭に歩きだす。いつの間にか人数が増え、メイン会場には1000人以上集まっている。メイン会場正面に設置された舞台に、四カ国のメンバーが再び市長から紹介され、組合長が再び挨拶し、市長から四カ国からの参加者と、この牡蠣祭り開催に協力してくれた人たちにお礼の記念品が贈呈される。
これまでがオープンセレモニー。終わると舞台の前にコの字形に配置されたテーブルに参加者が殺到する。牡蠣とワイン・ジュースなどが無料で提供される。
このテーブルの食べ物がなくなったタイミングに、大きなテントが貼られた食事会場に案内される。このテント内の食事、隣の人との会話も不十分なほど、ブラスバンドがテーブルの上に乗って派手に演奏し、会場内を移動していく。とにかく雰囲気はすごい。全員が手拍子。人数も2000人くらいに増えている感じ。 テーブルに運んでくるのは少年少女たちで、これが可愛いし、しっかりマナーをもっている。さすがテーブルマナーのフランス人だと感心する。
このあたりからメイン会場での白ワイン、続くこのテント内で赤白ボルドーワイン、それに会場内の熱気が加わって、酔いが一段と体内を走り回るが、これが翌朝の2時まで続くのだという説明にびっくり仰天。これは体力の限界を超えると、23時前に失礼してホテルに戻った。この調子で明日も祭りが続いたが、このあたりで祭りの状況説明はやめたい。

海辺の有名某市で伝えた事
以上の状況を海辺の有名某市でお伝えし、注意点も申し上げました。
それは、このアルカッション市のような祭りを真似てはダメだという事です。
いくら盛り上がった祭りでも、アルカッション市の祭りと同じようにしてしまうと、日本の良さは薄れます。フランスには「フランススタイル」があり、日本には「日本スタイル」があります。
ですから、アルカッション市の祭りと同じようにしてしまうと、折角の海辺の有名某市の観光魅力が消えてしまいますし、真似ごとは本場ものに敵わないのですから無理が生じます。日本に外国人が観光目的で訪れるのは、欧米人にとって日本が異文化であるからなのです。
自分達の社会と異なっている自然と生活習慣、その違いを見つけるために日本に来るのです。違いが最大魅力だということを日本の観光地は理解しなければなりません。
ここを考え違いする観光地が時にあります。相手と同じシステムにすると観光客が増えるだろうと、建物・設備・システムを変えてしまうところが時折見ますが、これは誤りなのです。ただし、訪れる外国人がどのような生活スタイルなのかは知っておく必要があります。知った上で、こちらは今のままで、何も変えなく現状のままにし、その現状を外国人の立場に立って編集し、外国語で情報発信する事が、外国人観光客を増やす最大のコツなのです。
このところがミシュラン空白ゾーン地区の狙い目です。
しかし、まだ理解していない日本の観光地が多いうちは、日本の観光大国化は難しいと思いますが、ポイントは簡単ですから、理解され展開されるとその地区に外国人が多く訪れるのは間違いありません。
以上。
2011年09月05日
2011年9月5日 ミシュランガイド空白ゾーンは狙い目だ・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年9月5日 ミシュランガイド空白ゾーンは狙い目だ・・・その一
ミシュランガイド東京周辺地図
ミシュラン旅行ガイドに掲載されている東京周辺地図を見ると「東京」「日光」「高尾山」「富士山」の四カ所が三ツ星で、オレンジ枠で大きく表示されています。高尾山に欧米人が多く訪れるようになった理由は、この三ツ星が要因です。

イエローで囲まれた二つ星は「鎌倉」「伊豆半島」「修善寺」「下田」の四カ所、黒字に赤線が引かれている一つ星は「横浜」「箱根」「中禅寺湖」「河口湖」の四カ所です。その他星付きではありませんが、地名が書かれているのは「草津温泉」「湯元」「前橋」「高崎」「熊谷」「甲府」「千葉」「木更津」「銚子」「横須賀」「小田原」「三島」等。観光関係者は、ミシュランガイドをよく検討すべきです。
ミシュランガイド空白ゾーン
昔からの有名観光地・保養地でありながら、上図に掲載されていないところはたくさんあります。地図で表示されていない観光地の方が圧倒的に多いのです。どうして掲載され、どうして表示されないのか。その疑問を解く鍵は簡単明瞭です。
それは、このガイドブック作成のライターが訪問していないからです。ということは、ライターの手許にその観光地の情報が届いていないという意味になります。つまり、訪問させるような情報を発信していないという事で、具体的に言えば英語か仏語でのガイドブックが作成されていないのです。掲載されていない事を嘆くより、この当たり前の情報発信を怠っているという事実を認識する方が大事です。
先日、そのミシュランガイド空白ゾーンのある海辺の有名某市に招かれました。観光協会と市の観光課長に「外国人観光客誘致」について解説を求められたのです。一昨年から進めてきました世界の観光ガイドブックに関わる、仏人ライターを招聘した「日本の温泉を世界へ」セミナー開催が効を奏し、伊豆天城湯ヶ島温泉の一旅館がフランス・ブルーガイドに掲載されることになりましたが、そのあたりも含めて説明してまいりました。
野田財務大臣(現首相)の講演
野田佳彦首相が財務大臣であった8月18日に、内外情勢調査会で講演を聞きました。しきりに財政再建、国の借金経営を是正したい、その為には増税も視野に入れていると強調し、その根拠の数字を次から次へと羅列し、これは財務官僚が書いたシナリオではないかと思えるほどの内容でした。
講演が終っての質問で「増税の前に国会議員削減、公務員給与の減額をすべき」と反論があり、それは実行する旨の回答がありましたが、これに首を傾げました。増税に触れるなら政府自らの削減項目を、質問される前に言及しておくのが筋であり、指摘されるまで述べない講演シナリオセンスに、一国のリーダーシップは難しいのではと思ったわけです。
しかし、民主党代表選及び首相就任後の発言は見事です。国会議員削減、公務員給与の減額を行うと言及、加えて「どじょう」から始まって「ミッドフィルター集団が必要」、「思惑でなく思いを」、「下心でなく真心で」、「論破でなく説得を」等の語りが、多くの国民を捉えました。さらに、床屋も10分1000円という低価格店の常連客というのですから、正に「庶民派宰相」で、今のところ支持率も高く、これからの政治力発揮を期待したいと思っています。
さらに、8月18日講演で、次に示したエコノミスト7月30日号表紙にもふれました。このような批判から脱却したいという想いと、8月26日の米ワイオミング州ジャクソンホールで予定される、米連邦準備制度理事会(FRB)のバーナンキ議長講演に高い関心を示し、アメリカの追加金融策についても言及しました。
エコノミスト7月30日号
7月30日発売の英誌エコノミストは、 世界が恐れる「日本化japanificationジャパニフィケーション」で、 表紙には和服姿のアメリカ・オバマ大統領と、日本髪のドイツ・メルケル首相の似顔絵が登場しました。
ジャパニフィケーションとは、90年代の日本のバブル景気崩壊以後「失われた10年」「失われた20年」という「長期的な不景気」「デフレ」状態に、特定国の経済が陥っている状態を指す表現で、欧州のユーロ危機、米国の債務上限引き上げの対応の迷走に対応しきれない欧米の政治家に対して、適切な経済政策を展開しなかった日本の政治家達を反面教師として、同様になってはいけないと批判しているのです。
しかし、この批判には疑問を持ちます。日本の経済政策の失敗によるデフレは、マネーサプライを増やせばたちどころに解決すると、かつて米連邦準備制度理事会(FRB)の幹部や欧米経済学者達がこぞって主張し、それを実行しない日銀や日本の政策当局を責め立てていました。
また、サブプライムローン問題から発したリーマンショクの金融危機も、ジャパニフィケーションを既に20年近く十分研究済であり、金融を迅速かつ十分に緩和すれば対処可能だから、日本のようにはならないと豪語していたはずなのに、ここに至って日本化が心配だというのですから、経済関係の専門家や識者もそれほどでもないレベルと考えます。
ジャクソンホール
さらに、違和感を持ったのは、米ワイオミング州ジャクソンホールへの期待でした。8月26日、ジャクソンホールで米連邦準備制度理事会(FRB)バーナンキ議長が講演しましたが、その中で「何らかの追加緩和策」が打ち出されるのではないかという期待を、事前に野田大臣や世界中が持った事です。
ジャクソンホールは米最古の国立公園イエローストーン公園への入り口として知られ、一度空港に降り立った事がありますが、崖の下に位置する谷あいの町で、ここでカンザスシティー地区連銀が主催するシンポジウムでバーナンキ議長が講演したのです。
期待の講演結果は「FRBには追加で提供できる様々な手段がある」と述べるに止まり、さらに次回の連邦公開市場委員会(FOMC)で議論を深めるという、全く具体策無きもので、完全に肩透かしで、谷あいの町ジャクソンホールにふさわしく、米経済は深い谷間にいるという事を示唆した講演であり、マクロ経済対策で打つ手に詰まっているというのが正直なところでしょう。
バーナンキ議長講演から学ぶ事は、政府や日銀の経済・金融政策に頼るのではなく、自分の事は自分で解決していくべきだという事ではないでしょうか。
東日本大震災後の企業の大変化
その事を指摘するのは、東レ経営研究所の増田貴司氏です。(日経2011.8.19)
日本企業は、これまで先送りしてきた経営革新や成長戦略に、東日本大震災後の経営環境激変で、覚悟を決めて取り組みだしたのが、以下の三項目であると分析しています。
① 新興国市場を開拓目的で海外生産シフトやM&A(合併・買収)を活発化させた。
② 過剰な多品種少量生産、過剰品質を見直し、部品を特注品から標準品へ切り替え。
③ 国内同士の競争で体力を減らすのではなく、主戦場である海外市場での競争力強化。
この大変化はその通りと思い、観光関係者が傾注すべきは③でしょう。国内は生産年齢人口の減少を迎えており、消費需要は増えず、少ない観光客の奪い合いになって、体力消耗戦になっているのですから、外国人をターゲットにするのは当たり前の作戦でしょう。
これらいろいろ述べました背景を持ちミシュランガイド空白ゾーンの有名海辺某市で「外国人観光客誘致」についてお話しましたが、これについては次号となります。以上。
2011年08月20日
2011年8月20日 移住先で自分に合った新しい人生を築く(2)
YAMAMOTO・レター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2011年8月20日 移住先で自分に合った新しい人生を築く(2)
東日本大震災の外国での表現
世界各地で日本人と分かると東日本大震災のことで尋ねられる。フランス・トゥールーズのタクシードライバーも「日本での住いは北か南か。家族は大丈夫だったか」と聞いてくるように、世界中の話題になっているが、東日本大震災という公式表現、これが諸外国ではどのように訳されているか調べてみた。
ニューヨークタイムスはTohoku earthquakeと書き、CNNでは統一されていなく、ドイツではTohoku-Erdbeben2011とかErdbeben JAPAN等といわれていて、気になっていた大震災の「大・グレート great」が使われていないので少しホッとしている。
新しく決めたところは廃墟
さて、前号に続くフランスの生き方事例です。イギリス人の彼が最初に買った家は広かったので貸家にしたが、いろいろ煩わしいことも多く、別のところに住もうと探し出し始め、スペインやポルトガルやイタリアにも行って調べたが、やはりフランスがよいと現在地に決めたのだが、そこは当時廃墟状態であったことは既に紹介した。
とにかく屋根はなく、壁も崩れており、家の中から木が伸びていたほど。それを買ったのだから近所の人々はびっくり、どうするのかと興味津々で見られた程だった。
この廃墟状態の母屋の後ろに元は馬小屋だった建物があり、そこに前住民が住んでいたが暖房設備もなく、いろいろなところを修理補修しながら五年住み、ようやく一応の家になったので、いよいよ廃墟母屋の改修に取り掛かったのが五年前。
元々イギリス人は家を大事にする国民で、その素質もあると思うが、廃墟を住める家に変身させたいと思った一番の理由は、自分が考える家造りを一人で出来るという楽しみ、それで廃墟を買ったのだという。加えて周りの景観が素晴らしいこともあったともいう。
また、敷地も広いので、庭造りも進めたが、これは奥さんの担当で、イギリスはイングリッシュガーデンと言われるように庭づくりの国。
もうひとつ重要な環境条件は、フランスでは地震がないことだ。だから煉瓦の積み上げだけで家は大丈夫なので、古い石造りの家がたくさん残っている。ここが日本と大きく異なる環境条件だ。
まずは模型造りから
最初は家の模型を木でつくった、と大事そうに奥から持ってきて見せてくれる。細かく刻んだ木材で屋根も窓もドアも玄関も丁寧にできていて、この模型が最も大事だと補足する。だが、この模型造りは単なる素人ではできないだろうと尋ねると、自らの経歴を吐露してくれたので、ようやく納得できた。
彼は農業大学卒で、父親が従業員を十数人雇用し農場経営をしていたので、それを卒業後手伝って、会計や農産物の品種選定から設備投資と修理、それと牛飼い小屋や作業小屋等の建物造りも日常業務として行っていたのだ。いわば農産物づくりと、それに付随する建物造りや修理について総合的な経験を積んでいたことになる。
過去経験の集積化
この経験が大きい。全く素人では家造りは不可能だろうし、もともと家を造ろう、それも廃墟状態のものをひとりで手造りしようとは思わないだろう。
家の中を案内してもらう。暖炉、階段、手すり、風呂、寝室、書斎、特に床は税関事務所の解体時に出た材木4000ピースを買ってきて、それを全部磨いて削り、すべて同じ大きさにして一個一個貼っていったのだという。家の中も靴で歩きまわる生活スタイルなので、当然ながら頑丈でなければならないので、しっかり貼ったとのこと。聞いただけで気が遠くなる作業だ。
さらに、プールも掘って、さすがに掘るのは業者にしてもらったが、後は全部自分で作業して完成させたという。そのプールサイドでアペリティフの白ワインいただき、次にキッチンに面したテラスで夕食となった。テラスの池には鯉が泳ぎ蛙もいる。猫が足許でじゃれついてくる。
夕食ではガイヤックGAILIAC2008年赤ワインをいただく。上品な味わいで、これが店頭価格で5ユーロだというのだから、毎晩一本飲んでも安いものだ。今の気温は27度で、湿気がないので汗は掻かなく、ほろ酔い気分が快適。
家づくりで苦労したことはないのかと質問すると、全くなく、すべて楽しみだけだったといいながら、眼を屋根方向に向けて、一番の工夫はあれだと指さす。それは1.5m×1mの煙突で、屋根上の中心点に設置してあるが、あの作業には頭を使った、あれだけ大きなものを屋根に上げたのは、エジプトのピラミッドを古代人がつくったのと同じ原理だと、本当に嬉しそうに大きく笑う。
好きなことを通じて新しい人生を築く
この時、瞬間的に彼は「今の時代の高齢者として理想的生活を送っている」のではないかと感じた。その意味は過去に自分が経験したこと、それも若い弾力性ある時代に身につけたものの中で「好きだった」ことを、高齢者という「円熟味を増す」段階になって、再び自らの中から引き出す作業をしているということだ。
それも移住した国・場所で、完全廃墟状態の建物を蘇らせたいという発想を持ち、その実現のために過去経験の集積化に、日夜脳細胞を駆使し活性化させる工夫を加味し、明日への作業を夢見る毎日を続け、今もガレージ造り作業に励んでいる。
これぞ正しく、若い時代の発想や価値観を見つめ直し、自分の好みに合致した新しい人生を築いているのだ。
彼こそが、好きなことを通じて新しい人生を築くというテーマの実践者であろう。以上。
2011年08月06日
2011年8月5日 移住先で自分に合った新しい人生を築く(1)
YAMAMOTO・レター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2011年8月5日 移住先で自分に合った新しい人生を築く(1)
今号と次号では、先般フランスで出会った長寿社会において、参考となるイギリス人の生き方事例をお伝えします。
毎朝の散歩
毎朝、ビーグル犬の散歩をするのが日課で、同じく犬を連れた男女とは「おはようございます」と挨拶しあう。ところが、深く帽子を被り、向こうから速足で来る独り歩きの男性とは挨拶ができない。60歳後半から70歳前半だろうが、眼を正面に見据え、風を切るシャープな歩きで、一様に声をかけることを拒否する雰囲気を漂わせている。ひたすら歩くことが人生目的であるように。
長寿社会の実現
日本人は戦後60年余りの間に30年ほど長寿になって、2010年の平均寿命が女性86.39歳、男性が79.64歳になったと厚生労働省から発表された。(2011.7.27)
女性は26年連続で世界一、男性は世界第四位というおめでたい話だが、定年の方はわずかしか延長されていないので、定年後の儲けものといえる期間は一段と長くなっている。
勤め人として働いている間は、何かと束縛されていたのだから、今までの生活をリセットし、自由で人生最高の楽しい日々がおくれるはずで、20年もあればもうひと仕事出来る可能性もある。また、仕事はしなくても、若い時代の発想や価値観を見つめ直し、自分の好みに合致した新しい人生を築くことも可能だ。
「円熟味を増す」という言葉がある。年齢を重ねると肉体の衰えに反し、過去経験の集積化によって出てくる英知が育ち、人格はもちろん精神的能力など総合能力は若い時代とは格段にちがっている。
だから、仮に「歩くことを人生目的」だとしても、脚を鍛えることで賦活させた健康を何かに活かさないともったいない。また、その活かすヒントは「自分の好きなことをする」ではないかと思って、世界の中でその実践者を訪問している。
仏トゥールーズ郊外へ
7月上旬はフランス南西部オート=ガロンヌ県北部に位置する都市トゥールーズ郊外の、人口160人という小さな村に住むイギリス人邸宅を訪ねた。
トゥールーズは、地中海と大西洋とを往復する重要路の途上にあって、ピレネーから発したガロンヌ川が、北東の湾曲部にあたるトゥールーズで方向を変え、北西の方角に流れて大西洋に注ぎ、市街の南端からピレネー山脈の山並みが見渡せる。
気候は温帯に属する海洋性気候、地中海性気候、大陸性気候が交差する特殊性で知られ、暑く乾燥した夏、晴天が続く秋、涼しい冬、激しい雨と嵐のある春と一年が多様性に富んでいる。この郊外に今回の主人公が移住したのだ。
南仏プロヴァンスの12か月
ところで、1,989年にイギリス紀行文学賞を受賞したピーター・メイル著の世界的なベストセラー「南仏プロヴァンスの12か月 A YEAR IN PROVENCE」をご存じだろうか。今は大分下火になっているが、出版された頃から20年くらい、この本を族行者の多くがガイドブック代りに小脇に抱えプロヴァンスを訪ね、多くの外国人が当時この地に移住した。
今の人々はどこの国に移住したいのか。アメリカの調査会社ギャラップが、世界148カ国の人々に「自由に移住できるとしたら、どこの国に住みたいか」というアンケートを2007年から2010年にかけて実施した結果、最も人気が高かったのはシンガホールであった。政治・社会情勢が安定、医療水準が高い、英語が公用語、加えて交通渋滞の少なさ等が背景要因であるが、20年前まではピーター・メイルの本のおかげで南仏プロヴァンスが一番人気であったと思う。
イギリス人のピーター・メイルは、旅行者として何度もプロヴァンスを訪れるうちに、陽光溢れる南仏の豊かな自然と変化に富む食生活、純朴な人心・風土に魅せられて、ついにロンドンを引き払い、二百年を経た石造の農家を買い取ってこの地に移り住み、近隣の農夫や改築を請け負ってやってくる職人たちとの交流を中心に、今様に言えばカルチャー・ショックを体験しながら、次第にプロヴァンスの暮しに馴染んでいく過程を、月々の気侯の移り変りに沿って「南仏プロヴァンスの12か月」として十二編のエッセーにまとめのである。
7月のプロヴァンスは大渋滞
そこで改めて、この本の7月を開いてみると冒頭に
「友人がサントロペから数キロのラマテュエルに家を借りた。真夏の殺気立った交通渋滞に車を乗り入れるのは考えものだったが、会いたい気持ちはお互い同じだった。私が折れて、昼までに行くと約束した。
ものの三十分も走ると、もうまるで他所の国で、右も左も大挙して海を目指すトレーラーハウスやキャンピングカーでいっぱいだった」
とあり、7月は国内外から大量に訪れる観光客による車大渋滞状況が延々と綴られていて、この月だけは温暖な気候、美しい自然、おいしい食事とワインがあるプロヴァンスという憧れの地とは思えない描写となっている。
トゥールーズ郊外の邸宅
これに反し、トゥールーズの中心地からタクシーで向かった郊外への40分間、渋滞なぞ全く関係なく、なだらかな美しい眺望の丘陵地帯の中、ひまわり畑が連なり、古い教会前を通り過ぎ左折すると、そこはアプローチの美しい素晴らしい石造りの邸宅前であった。
昔は廃墟だった
さて、ドライバーに64ユーロ(112円レートで約7000円)支払い、まだ陽射しが強い16時過ぎに邸宅に入ると、ご夫婦が笑顔で出迎えてくれる。ご主人は70歳だが、年齢より若い。イングランド東部のノーフォーク州の州都ノーリッジNorwichからフランスに移住したのが20年前。フランスに移住しようと思った経緯はいくつかあるが、ひとつは太陽へのあこがれであり、次はフランスの文化と食べ物の豊かさであり、もう一つは家の価格がイギリスに比較し安く20年前は三分の一だったと笑う。ピーター・メイルの「南仏プロヴァンスの12ヶ月」は関係なかったのかと尋ねると、影響があったかもしれないともいう。
フランスで最初に住んだところは、ここではなく少し離れた別の地区でシャトー付きの大きな建物を買ったが、40室もあったので、自分たちが居住しないスペースは貸家にした。この家は入居前に完全リフォームしてあって、約10年住んだが、貸家はいろいろ煩わしいことも多く、別のところに住もうと探し出し始め、スペインやポ
ルトガルやイタリアにも行って調べたが、やはりフランスがよいと現在地に決めた
しかし、実際に探し決めたところは、当時写真のように廃墟状態であった。次号に続く。
以上
2011年07月20日
2011年7月20日 村上春樹の見事な解答
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年7月20日 村上春樹の見事な解答
フランスで
7月はボルドーにワインと土壌の関係について調査に行きました。今年はワインと関係する仕事が多く、2月はカリフォルニアワインのナパバレー巡り、5月はチリのサンチャゴ郊外のビーニ・コンチャイ・イ・トロ Vina Concha Y Toroを訪問し、今月がボルドーというわけです。
パリに着いた日に会った日本人女性、会った瞬間「フランスでは福島原発問題で、日本政府は何か重要な事を隠しているという評判ですよ」と忠告されました。指摘されるような報道態勢であった事は認めつつ、一般の人たちの感覚は鋭いと改めて思います。
次の日、ボルドー市街の中心地で、ボルドー大学地質学教授からいろいろボルドーの地質構造について教えてもらった後、原発問題の報道について確認してみると「私の関係する人たちは、研究者・学者が多いので日本政府の発表を信用しています」との発言です。
アンケート結果と合致している
パリでの指摘とボルドー大学地質学教授の発言にみる食い違いは、米ボストンコンサルティンググループ(BCG)のアンケート調査と一致しています。BCGが訪日安全性について、その情報源の評価を一般人に聞いた結果、日本政府を「信用できる」という回答は、わずか14%でしか過ぎませんでした。しかし、半面、国際機関や研究者のグループは90%の人が「日本政府を信用できる」と回答しているのです。
パリの日本人女性指摘と、ボルドー大学地質学教授の発言は、BCGのアンケート結果を完全に裏づけていますが、どうしてこのように「一般人」と「国際機関や研究者」で全く反対といえるような大差な結果となっているのでしょうか。
そのところを、このレターで安直に結論付けてはいけないと思いますし、ひとり一人が考えてみなければいけない大きな日本の課題だと感じています。
世界と日本の感覚ちがい
今回の東日本大震災時に、被災地の人々がとった行動を、世界の人々が賞賛しています。これは4月5日のレターでお伝え済みですが、再度、振り返ってみると、ル・モンドは「驚くべき自制心は仏教の教えが心情にしみ込んでいるからだ」と分析し、イズベスチヤは「日本人は自分たちを一つの大きな家族と捉えている。そこには宗教や道徳観、強い民族的自覚が影響している」と書き、デイリー・テレグラフは「何をするときでも正しい作法に則ってやりなさい、というのが日本の暮らしの大原則だ。茶道がいい例だ」というように解説していていました。
東日本大震災時の日本人の行動は、世界中の国とは価値観が異なる民族である事を認め、そこに日本の何かが存在しているのだと、日本人を精一杯研究し推考しているのです。
日本人からの解答がない
ところが、日本の新聞報道は被災地の人々の行動に対し、どのような報道だったでしょうか。
著名な作家・建築家・経営者の新聞掲載内容を読みますと、外国人の反応を誇らしげに受けとめ、日本人は「やさしさ・愛等の人間の本質的なものを持っている」というように、日本人のDNAに要因があるというような内容に止まっています。
日本人には世界の人々と違う何かがあり、それはどこでどのようにいつから身についたのか。その本質面からの日本人分析を行い、世界中の人々が称賛するが、その要因について疑問を持つ外国への解答を未だ明確にはしていないのです。
斑目委員長の自己批判
実は、この分析力の甘さが、今回の福島原発事故が人災だと言われている最大の要因ではないかと思います。
国の原子力安全委員会の斑目春樹委員長も「天災というより人災だった」と自ら認める発言をし、かつて国際原子力機関(IAEA)から規制行政庁として保安院が独自の基準を設けるべきだと勧告されてきたにもかかわらず「改定の議論ないままズルズルときてしまった」と述懐し反省している始末です。(日経新聞2011.6.27)
世界から見ると福島原発の管理基準は甘く、その事実を以前から指摘されたのに対応しない。つまり、世界からの疑問に解答しないまま3:11を迎えてしまったのです。世界から日本を見るという視点が甘いと言わざるを得ません。
被災地の人々の行動分析と解答
このレターでは、被災地の人々の行動がどこから起因しているのか。それを早く解答すべきと考え、それが「武士道」に起因しているのではないかとの洞察を行ってきました。
その根拠は、新渡戸稲造「武士道」第二章「武士道の源をさぐる」で「まず仏教から始めよう」と述べ、いくつか解説する中で仏教によって「危険や災難を目前にしたときの禁欲的な平静さをもたらす」述べているからです。これに従えば、被災地の人々が見せた行動は、仏教に起因している事になります。
しかし、この仏教に起因するという程度の解説では、論理的に鋭い外国の識者は納得しないし、私が世界各地で直接お会いした人々も同様でしたので、何とかしなければいけないと思い続けていました。
村上春樹のスペインでの解答
ところが、その解答を見事に展開してくれたのが、村上春樹の2011年6月9日スペイン・バルセロナにおけるカタルーニア国際賞授賞式講演です。以下がその内容です。
「日本語には無常(mujo)という言葉があります。いつまでも続く状態=常なる状態はひとつとしてない、ということです。この世に生まれたあらゆるものはやがて消滅し、すべてはとどまることなく変移し続ける。永遠の安定とか、依って頼るべき不変不滅のものなどどこにもない。これは仏教から来ている 世界観ですが、この『無常』という考え方は、宗教とは少し違った脈絡で、日本人の精神性に強く焼き付けられ、民族的メンタリティーとして、古代からほとんど変わることなく引き継がれてきました。
『すべてはただ過ぎ去っていく』という視点は、いわばあきらめの世界観です。人が自然の流れに逆らっても所詮は無駄だ、という考え方です。しかし日本人はそのようなあきらめの中に、むしろ積極的に美のあり方を見出してきました。
自然についていえば、我々は春になれば桜を、夏には蛍を、秋になれば紅葉を愛でます。それも集団的に、習慣的に、そうするのがほとんど自明のこと であるかのように、熱心にそれらを観賞します。桜の名所、蛍の名所、紅葉の名所は、その季節になれば混み合い、ホテルの予約をとることもむずかしくなります。
どうしてか?
桜も蛍も紅葉も、ほんの僅かな時間のうちにその美しさを失ってしまうからです。我々はそのいっときの栄光を目撃するために、遠くまで足を運びます。そしてそれらがただ美しいばかりでなく、目の前で儚(はかな)く散り、小さな灯りを失い、鮮やかな色を奪われていくことを確認し、むしろほっとするのです。美しさの盛りが通り過ぎ、消え失せていくことに、かえって安心を見出すのです。
そのような精神性に、果たして自然災害が影響を及ぼしているかどうか、僕にはわかりません。しかし我々が次々に押し寄せる自然災害を乗り越え、ある意味では『仕方ないもの』として受け入れ、被害を集団的に克服するかたちで生き続けてきたのは確かなところです。あるいはその体験は、我々の美意識にも 影響を及ぼしたかもしれません。
今回の大地震で、ほぼすべての日本人は激しいショックを受けましたし、普段から地震に馴れている我々でさえ、その被害の規模の大きさに、今なおたじろいでいます。無力感を抱き、国家の将来に不安さえ感じています。
でも結局のところ、我々は精神を再編成し、復興に向けて立ち上がっていくでしょう。それについて、僕はあまり心配してはいません。我々はそうやって長い歴史を生き抜いてきた民族なのです。いつまでもショックにへたりこんでいるわけにはいかない。壊れた家屋は建て直せますし、崩れた道路は修復できます」
何と見事な解答ではありませんか。さすがに世界の普遍性を説き書く村上春樹です。世界の人々の疑問・関心事を公の場で分かりやすく説明したのです。
本質的究明を行い、明確に具体的にするという表現力を我々は磨く必要があります。以上。
2011年07月05日
2011年6月20日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(後半)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年6月20日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(後半)
ブラジルサッカー
ご存知のようにブラジルはワールドカップ優勝5回のサッカー大国。しかし、自国開催であった1950年大会ではウルグアイに逆転負けを喫し、初優勝を逃した。また、前回の南アフリカ大会ではオランダに準準決勝で逆転負け。この時の監督がドゥンガ(Dunga)で、1995年から98年までジュビロ磐田に在籍していた経験を活かして、守備的サッカーに変貌させた事が、ブラジル人の特性に合わないサッカーを行ったので負けたと分析されているが、地元開催の2014年はどうか。楽しみである。
ところで、スラムの子供達の夢は、男の子はサッカー選手、女の子はモデル、いずれも体が元手の職業である。また、ブラジル人は「好きな事をして成功したい」という思考が強いので、サッカーは一人ひとりの芸術的なプレーで成り立っているし、サッカーが唯一無二のスポーツで、貧富に関係なく、殆どの子供の憧れの職業である。
その結果、優秀な選手が輩出し、外国で活躍する事になる。2009年には1017人のプロ選手を輸出している。選手を送り込んだ国は90近くになる。最大の顧客先はポルトガルの181人だが、ドイツやイタリアもいると日本にも同年に41人が来ている。
この事でサンパウロのサッカーに詳しい旅行会社マネージャーに聞くと、外国で活躍するブラジル人選手は、ポルトガルかスペインが多く、組織的なサッカーを目指すドイツやイギリスでは実力が発揮できない傾向にあるという。そういう事からネイマールもスペインかと納得し、レアル・マドリードで自由奔放にサッカーを展開すれば、素晴らしい活躍を示すであろう。
ブラジル人は南アフリカ大会で見たように、規制されたサッカーをしようとすると個性を発揮できないのであるから。
ルラ前大統領のボルサ・ファミリア政策
ブラジルのルラ前大統領の政治ボルサ・ファミリアが、大きな功績をあげた。ペルー新大統領のウマラ氏もルラ氏の政策を見習うと発言したように、南米ではルラ氏の位置づけは高い。
そのルラ氏が掲げた政策は「すべての国民が三度の食事ができるようにするのが,私に与えられた使命である」と述べ、子供を持つ貧困家庭に平均で月70レアル(約3,600円)支給し、支援を受けた親には子供を就学させ、定期的な健康診断を受けさせることを義務とするプログラムを推進した結果、貧困家庭を飢餓から救うだけでなく、子供の教育を継続させることにより、貧困が次の世代に受け継がれる悪循環を断ち切ることにあった。
実際、このプログラムの結果、800万人が貧困から脱却したと伝えられているまた、ブラジル国土地理院の統計データでは、全人口に占める貧困層の比率が1992年に35%、ルラ大統領が誕生した2003年でも28.1%と低所得国並であったものが、2008年には16.0%にまで減少している。
貧困層が減れば、必然的にブラジルの内需は増える。貧困層の人々が、今まで買えなかった物を買うのであるから当然である。つまり、貧困層がいた事が、今や財産化しているのである。このあたりが日本と大きく異なる。日本は全員中間層みたいな国、国内に急に物を買うことを増やす人口層が無いわけで、低成長に未だ喘いでいる。ブラジルとは根本的に異なる所である。
また、このような現金支出という、日本ではバラマキ政策と非難され、子供手当が問題視され財政赤字が大きい国では反対が強く、ブラジルのように財政赤字比率が低い国しか出来ないであるから、ブラジルは自国の財政有利さを発揮した独特の政策を展開した故で、世界が驚く経済成長を成し遂げていると判断できるが、この政策はいつまでも継続できるものでないことも事実である。
国家の財政との関連であるから、受け取った貧困層がどのような形で国家に貢献するかにかかっている。つまり、いつまでも受けとるだけの境遇に甘んじる国民が多くなると、この政策での経済向上はとまる。
ルラ政権における公務員の増加といい加減さ
ルラ前大統領の政策は、当然ながら支出は増える一方である。さらに、これらの推進のために公務員の大幅増員が行われてきている。2003年から2009年の間で16.7万人が新たに採用された。
これとは別に与党労働者党関係者4000人を連邦政府各省にはめ込み、大統領・大臣が直接任命する特別職を大幅に増やしたという。
これらから公務員は大場増加で、人件費が前政権時よりGDP対比で増えた割には、国民への公共サービスは少しもよくなっていないという批判がある。ルラ大統領という個人的人気の陰に隠れている問題点であろう。
その上、2010年3月10日、フォーリャ・デ・サンパウロ紙が公務員の給料二重取り事件を報じた。連邦政府と州政府の両方から給料を受け取っていた公務員が16万人以上いたというのである。これは法律で連邦と州の職務兼務を認められている者を除いての事件であるから、そのでたらめさが気になる。
最大の懸念項目は母国がポルトガルという事
もう一つの最大の懸念項目は母国がポルトガルという事である。
ブラジルは南米で唯一ポルトガル語を母国語とし、1822年にポルトガルから独立した。しかし、その独立はポルトガル側の事情からであり、一般的な独立運動を激しく展開した結果というわけでない。
実は、これにはナポレオンが絡んでいる。ナポレオンが皇帝に就いたのは1795年で、ヨーロッパに覇権を打ちたてようとして対立したのは海を隔てたイギリスだった。そこでナポレオンは大陸封鎖令を出し、ヨーロッパ諸国にイギリスとの通商を禁止したが、ポルトガルは態度を明確にしなかったので、ナポレオンはフランス・スペイン連合軍をもってポルトガル侵攻を決定した。
このナポレオン軍のリスボン侵攻を目前にし、国王マリア一世の息子である摂政ジョアンは、1807年11月36隻の船に、王侯貴族と主要な官僚15,000人を乗せてブラジルに向かい、翌年の1808年にサルバドール着、続いてリオ・デ・ジャネイロに上陸し、ここを首都と定めたのである。
つまり、一国を挙げて祖国から植民地に夜逃げしたのであり、この時点でブラジルはポルトガルの植民地でなくなった。
ところが、その後のナポレオン失脚とともに、ヨーロッパに旧体制が回復し、マリア一世を継いだジョアン六世は1822年にリスボンに帰還し、ブラジルに残ったペドロ一世が皇帝として、ここにブラジル帝国が1822年に独立したのである。
その後、ペドロ一世を継いだペドロ二世の時代に、軍部によるクーデターがあり共和制に変わり、ここで帝国制が終わって現代につながっているのであるが、一国が夜逃げした事によってブラジルという国が出来たということは、世界史上でも独特の物語であろうし、その帰還した元宗主国ポルトガルが、今やEUの中で問題国になっている事が気になる。
何が気になるのか。それは今のポルトガルが陥っている実態には、ポルトガル人としての国民性が何らか関与している事は事実だろう。そう考えて行くと、ブラジルの宗主国であるポルトガル人の血を引くブラジル人も、独特の政策で順調な時はよいが、いつか何かをキッカケに坂道を転がりかけるタイミングがあるのではないか。
先日経験したことも引っかかる。有楽町のブラジル銀行に行き、窓口女性にブラジルへの振り込み依頼をした。親切に振り込み機械の前へ連れて行ってくれ、振り込み手続きしてくれた。「ありがとう」と言いブラジル銀行を出て他の用事をしている際、何となく不安なので振り込み書類を確認すると、何と手数料を振り込み額から差し引いてある。
慌てて15時2分前にブラジル銀行に再び戻り、手数料分を再振り込み依頼したら、今度は計算違いで手数料分より4レアル多く振り込みしてしまう。
それを窓口女性に指摘すると、慌てて奥に入って行き電話で本部と訂正手続きし、戻ってきて「すみません」とゴホンと咳を何回も連発の夏風邪模様。
風邪で体調が悪いので計算間違いをし、手数料を二度払い手続きしたのならよいが、そうではなくこれが日常で発生するような国民性だとすると大いに心配だ。
だが、レアルは確実に高くなって、7月1日には1ドル=1.554レアルと12年ぶりの高値。ワールドカップとオリンピック開催までは、レアル通貨が強い実態が続くはずだから、開催まではレアル預金を継続して、オリンピック終了間際に引き出すつもりだ。以上。
2011年06月20日
2011年6月20日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(中)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年6月20日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(中)
前号に引き続いてブラジルの未来を検討したい。
世界四つの異国
世界には異様、異端、異質、異色の四つの異国があるという。(「ブラジルの流儀」和田昌親著・中公新書)
「異様」の筆頭は社会主義市場経済の中国、金融危機があっても成長する米国、共産主義崩壊後は主義主張が見えないロシアの三カ国だが、米国とロシアについて少し説明を加えたい。
まずは米国、米国は世界一の経済力と軍事力がありながら、歯が痛くなっても医者に行けない健康保険制度と、低所得者向けの食料補助対策 「フードスタンプ」受給者数は4500万人に達する生活困窮者急増国。米国の人口は約3億1千万人。単純計算では7人に1人の割合でフードスタンプと思われるが、しかし、赤ちゃんはもちろん、小学生や中学生は申請できないことを考えると、成人としての受給者の割合はもっと高くなる。従って社会人の5人に1人が受けていると考えていい。それでもFRBは金融緩和を続け、GDPだけは成長させようとする姿は異様だ。
一方ロシアは、13世紀の始めにチンギス汗・モンゴル軍によって征服され、キプチャク汗国を立国され「タタールのくびき」といわれる暴力支配が259年間続いた。この間ロシア農民はいくつもの重税がかけられ半死半生となり、反対すると軍事力で徹底的に抹殺されたので従うしかなく、この当時、育ちつつあった都市文化や石工、鋳金、彫金、絵画、鍛冶職も連れ去られ、文化が根こそぎ絶やされるという酷い実態であった。
これがロシア人の原風景に存在し、外敵を異常に恐れるだけでなく、病的な外国への猜疑心と潜在的な征服欲、軍事力への高い関心となって、世界からは異様な国に見える。
異質な日本
「異端」な国は言うまでもなく「北朝鮮」「イラン」で、理解不能国な事はご承知の通り。
ところで日本は何か。世界から見ると「異質」な国といわれている。どのように異質なのか。簡単に言えば国際化が進んでいないガラバゴス化国で、日本から日本を見て、国内ルールだけで物事を進めているというのが、世界から指摘されている内容である。
米ボストンコンサルタントグループが、東日本大震災後のアンケート結果を発表したが、日本に行くための情報の入手先で「日本政府を信用出来る」と判断したのは、たったの12%に過ぎない。(2011.9.14日経新聞)情報発信が世界的でない事を証明している。
それと、菅首相を引きずり降ろそうと不信任案を提出した政治家達、東日本大震災より権力闘争が重要という能天気な体質。これが世界から見ると不思議でならない。英フィナンシャル・タイムス(2011.6.3)が「震災直後に日本人が見せた無死・禁欲の精神は世界を感動させた。だが国会議事堂の厚い壁はそんな気高い精神すらはねかえした。政治家は安っぽい地位・権限を巡る際限ない口論に今も余念がない。ここが変わらなければ政治の行き詰まりを打開する見通しなど到底立たない」と厳しいが、妥当な指摘であり全く情けない。
我々が選んだ政治家がこのような様なのだから、日本の政治家達の思考回路は世界から見て「異質」なのだろう。
しかし、一般国民は素晴らしい。今回の東日本大震災時の行動、世界から絶賛された。東京に残された帰宅困難者の混乱無き行動も世界が驚いた。ということは他国ではこのようではないという事になる。これもよい意味で日本が「異質」といえる点であろう。
異色なブラジル
もう一つの異国の「異色」な国はブラジルである。その異色とは世界一という切り札をこれでもか、というほど抱えているからである。
まず、資源はアマゾンにあるカラジャズ鉄鉱山の埋蔵量は無限大、超伝導材料や耐熱合金に使われる鉱物ニオブ生産も世界一。石油はリオ沖の深海油田が発見され自給率100%の上、加えてサトウキビ利用のバイオエタノールを開発し現実に利用しているので万全。食糧生産も余裕たっぷり。世界一を維持する砂糖、コーヒー、オレンジジュース。また、淡水の量も世界一。サッカーワールドカップ優勝五回、リオのカーニバルの規模も世界一と続く。ブラジルは世界一が多い国である事は間違いなく、その意味で「異色」なのだ。
財政状態も堅実
ブラジルの財政状態はどうか。2009年GDPに対する財政赤字を、EUを混乱させているPIGSと比較してみた。ポルトガル△9.4%、アイルランド△14.3%、ギリシャ△13.6%、スペイン△11.2%であるが、ブラジルはたったの△3.3%であるから、かつてIMFから1998年に415億ドルの支援を受入れたことなぞ、今は全くその面影がない。
ブラジルの問題点
だが、ブラジルにも問題はある。それも結構大きい問題だ。
まず、治安。日本の外務省によれば、サンパウロの強盗事件の発生件数は東京の361倍、殺人事件は8倍となって、人口10万人あたりの殺人発生率は日本の30倍ともいわれている。これは企業にも関係する。保安要員の増強、不法侵入防止の強化、社有車の防弾改造等大変な安全対策コストがかかる。
次に、ブラジルコストといわれる他国にない余計な費用がかかる事。ブラジルの税金ではやたらに「何々納付金」という名称の実質的税金がある。これは憲法で同じ源泉から二重に課税してはならないので、ひとつは税金、ひとつは納付金という名称で徴収する仕掛けである。その項目を紹介したいが、あまりに多く難しいのでやめる。しかし、これらの処理で企業は大変な手間がかかっている。専門家がいないと経営は出来ないという事になっている。
さらに、労働者優遇の慣習がある。昔から労働者に優しい国で、働く側には悪くないが、企業側にとっては雇用契約の厳密化と、クビをきる時は相当慎重にしないと裁判沙汰になる。これらに対応するコストがバカにならないし煩わしい。この他に細かい事を書きだしたらたくさんあるが、次はブラジル人にとってサッカーとは何かを考えてみたい。
ナショナルアイデンテイティ
人種混淆が豊かなブラジルでは、多様な文化にならざるをえない。つまり、底流に民俗・人種という存在が絡まりあっているのであるから、ブラジル人としてのナショナルアイデンテイティを何にするか、ということは難しい。
例えば、リオのカーニバルに見られる熱狂的祭典、それは世界最大であるという点で、民族意識としてのナショナルアイデンテイティを醸成する一つの役目はあるだろうが、それはあくまでもお祭りであるという意味で、対外的に国民の民族意識を一つにするには力不足であろう。
その点、日本には皇室という存在がある。長い伝統と歴史で守ってきた国民の総意が、皇室を中心とした国体になっていて、天皇陛下は国の中心であり、日本国のナショナルアイデンテイティを象徴している。ところが、ブラジルでは共和国制である上に、人種混淆が豊かであるので「人物」をもってナショナルアイデンテイティをつくりあげるのは難しい。
ところで、ブラジル人と話していると、共通する話題が必ず出る。サッカーである。サッカーが確実に国民の中に位置づけられているので、サッカーがナショナルアイデンテイティではないかと推測し、「サッカー狂の社会学」(世界思想社 ジャネット・リーヴァー著)を開いてみた。この本はリオのブラジル人にサッカーについてインタビューしたものである。
「インタビュー対象者はリオの37人。工場労働者、事務員、セールスマン、そしてドアボーイと、年齢・結婚状態・宗教・宗教・人種の分布がリオの労働者階級をほぼ完全に反映するような一群の男性を選んだ。
ほとんどのブラジル男性は、他の娯楽に比べて、サッカーに膨大な時間を費やす。面接した男性の四分の三が、この一か月間に少なくとも一回はマラカナン競技場へ行っていた。仕事の帰りにビールを一杯やる以外では、サッカー観戦は男性を家庭から揃って引き離すもっとも一般的な活動なのである。
友人との話題を尋ねたときは、サッカーについて話すと答えた人がもっとも多く、他に何を話題にするかと尋ねたところ、『もっとサッカーのこと』と答えたように、サッカーは、ブラジル人にとって楽しみの源である上に、『サッカーについて何も知らなければ変な奴だと思われる』事にならないようにし、サッカーのニュースに遅れないようにしていれば、違う種類のニュースや違う話題との接触も促進されるという。
つまり、サッカーファンであることは、そこに住む共同体への参加を支え、繋がりを強化する役割を果たしているのである」
地元共同体と強固に結びついているサッカーがナショナルアイデンテイティと考え、ブラジルサッカーとブラジル国の未来とどう関係するのか。次号で続けて検討してみたい。以上。
2011年06月06日
2011年6月5日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(前半)
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年6月5日 ブラジルの未来・・経済とサッカー(前半)
有楽町のブラジル銀行で
ご存知のようにブラジルの経済成長は著しく、生産年齢人口が2015年から減少する中国よりは、ブラジルの方が未来の可能性が高いと考えるのか、世界中がブラジルへ関心を強め、日本企業も多く進出している。
今号と次号ではブラジル経済と、国技ともいえるサッカーを関連付けて分析してみたい。
ブラジルへ出発前に、現地のコーディネーターに必要経費を送金すべく、JR有楽町駅近くのブラジル銀行に入った。ロビーで受付順番券を取り、待っているとブラジル人女性が流暢な日本語で用件を聞きに来る。「送金に来ました」というと「こちらへ」と送金用機械の前に案内してくれ、今日のレアルレート換算の日本円を確認し、振込先のカードを差し込み、円紙幣を入れると送金は終わる。簡単だ。「ところで、お客様は当行に預金口座お持ちですか」と聞いてくる。「いや、持っていません」「そうですか。今は金利が6%ですからご検討くださいませんか」という。
日本の銀行で一年定期預金すると、金利は0.03%であるから200倍の利息がつく。ため息が出るほどの日本との差である。一瞬、預金しようかと思う。しかし、外国への預金は為替レートで変化するので、そこの判断が難しいので「検討します」と出口へ。
過去のパターンを乗り越えられるか
ブラジルには他国と違う成長大要因が二つある。それは「2014年のサッカー・ワールドカップと、南米大陸初の2016年オリンピック」開催である。相次ぐビックイベント開催が、現在の内需中心の経済成長に加えて続くのであるから、ブラジルの未来は明るいだろう。
しかし、ブラジルの過去の歴史を振り返ると、これらの経済成長実態について、一抹の不安を感じるのも事実だ。
第二次世界大戦後の1950年以降、急速な経済発展を遂げ、60年代後半から毎年10%を超える成長率を見せ、ブラジルブームとなり、日米欧先進国からの直接投資による現地生産や合弁企業の設立も急増し、自動車生産や造船・製鉄では常に世界のトップ10を占める程の工業国となった。だが、50年代後半の首都ブラジリア建設負担や、70年初頭のオイルショックなどで経済が破綻し低迷、同時に深刻な高インフレに悩まされるようになり、これ以降80年代にかけてクライスラーや石川島播磨(現・IHI)など多数の外国企業が引き上げ、先進国からの負債も増大した。
この間、ブラジルの通貨政策は悲劇的であった。まず、ポルトガルの植民地だった時代から統治国と同じ通貨単位レイスを使用していたが、1942年にクルゼイロに単位を変更してからは、激しいインフレーションへの対処の為、ちょっと数え切れないほどのデノミネーションを実施し、その度に通貨単位を変更している。
現在のレアル導入後は、1レアル=1米ドルという固定相場制から変動相場制に移行し、レアル安が続いていたが、今の6月時点では1ドル=1.6レアルとなっているように、ブラジル経済は好調なことを証明している。
TAM機内で
ブラジル・サンパウロにはニューヨークからTAM航空で向かったが、乗客の荷物の多さに圧倒される。大体、大型バックは二つか三つが常識、それに加えて機内持ち込み手荷物もパンパンに膨らみ、少なくとも二つは手に提げている。
機内は満員。回りを見回すと外国人はいない。ブラジル人だらけ。これはサンパウロ空港に到着し、入国審査のカウンターで分かる。外国人用という表示板下に並ぶのは自分を含めて10人程度。後は全員ブラジル国民用の窓口に並ぶ。
どうしてか。それは簡単。レアル高なので、ブラジル人はアメリカへ買い物に行くのである。また、これだけ買ってくるのは輸入税が高いのだろうと推測し、調べてみると大変な状況だった。ワインは54.7%、ブラジル家庭でよく食べるバカリャウ(タラでノルウェーなどから)は43.8%、子供が大好きなオーボ・デ・パスコア(チョコ丸型の菓子)が38%、包装セロハンが35.2%、リボンが34.04%という実態。(2010年4月時点)
サンパウロ市内の渋滞
世界三大渋滞都市はモスクワ、カイロとサンパウロだろう。いずれの都市も経験したが、日本では考えられない実態だ。特にサンパウロは雨が降るとお手上げだ。道路の排水施設がお粗末なので、水が溢れ、たちまち200km程度の渋滞が当たり前。通勤時間は市内に住んでいても車で1時間から2時間。日本の遠距離通勤とは異なる。日本は新幹線や列車で長距離の通勤だが、サンパウロ市内では距離は短いのに時間が猛烈にかかるのだ。朝5時ごろから通勤車が動き出す。それが終日続くから、アポイントは一日に二件は困難で、せいぜい一件訪問が妥当な目安。ビジネスマンはあきらめの境地に達している。
今回も企業訪問は一日に一社、展示会視察も一日に一会場という日程で動いたが、展示会で出会ったブラジルナンバーワン企業の社長が、翌日も来るならもっと詳しくブラジル市場をレクチャーするよと、わざわざ電話をしてくれたが、展示会場に行くのに2時間、会場に入る手続きに30分、受付係りの能率が悪いからだが、会場でのレクチャーが2時間30分として、ホテルまでの帰りに2時間、合計7時間と途中で食事すると9時間以上かかり一日がつぶれるので、残念ながら行けないという事になる。
ただし、展示会場にはスタイル抜群のブラジル美人女性が、各コーナーでシャンペンやワイン・ジュース・お菓子をサービスしてくれるので、美人をウオッチングしたければサンパウロにかぎるだろう。ブラジルから回ったウルグアイ、チリ、ペルーと美人が少ない事を確かめたので間違いない。美人見るため再び行きたいと思っている。
ブラジル企業の為替判断
日本の大手メーカー事務所を訪問した。社長は日本人でブラジル17年の在籍、この企業にスカウトされたのが5年前。扱う商品アイテム分野でシェアが第二位になったという自慢話と、進出日系企業は1ドル=1.8から2.0レアルにみていて、先行きレアル安と見ているという。
しかし、次に訪問した地元旅行会社のマネージャーは、1ドル=1.2レアルまで高くなるのを、政府が介入して1.6にまで戻しているとの見解。ブラジルは、資源は石油含めて自前であり、食料も問題なく、内需も盛り上がっているので、当然にレアル高になると見ているのだ。どちらが妥当なのか。それは時間経過を見ないと分からないが、レアル預金をする場合は、この為替レートを時間経過の前に判断しないといけない。
ブラジルのサッカーと経済政策
ところで、ご存知のようにブラジルはワールドカップ優勝5回のサッカー大国。しかし、前回の南アフリカ大会ではオランダに準々決勝で逆転負け。
この時の監督がドゥンガ(Dunga)で95年から98年までジュビロ磐田に在籍していた。ブラジル代表監督に就任後の指揮は、選手個人技を生かした攻撃的サッカーというより、守備的サッカーに変貌させた事で、ブラジルのメディアからはつまらないサッカーだと批判され、南アフリカ大会での早々敗退で解任された。ドゥンガは日本で経験した事を活かそうとしたのだが、ブラジル人の特性に合わないサッカーを行ったので負けたというのが、ブラジルではもっぱらの評価。ということはブラジルの敗退は日本が影響していると考えられる。
2014年は自国開催であるから優勝が国民の絶対使命である。ドゥンガに代わる新監督はブラジル最大のファン数を誇るサンパウロのサッカーチーム、コリンチャアンスのマノ・メネーゼス監督である。果たして自国開催で優勝できるか興味津々である。
スラムにいるブラジルの子供達の夢は、男の子はサッカー選手、女の子はモデル、いずれも体が元手の職業である。また、ブラジル人は「好きな事をして成功したい」という思考が強いので、サッカーは一人ひとりの芸術的なプレーで成り立っている。
その代表がサントスの19歳ネイマール、トレードマークのモヒカン風ヘアスタイルで人気実力ともナンバーワンだが、近々ヨーロッパに移籍し、移籍金は9000万ドル(72億円)という噂が飛び交っている。ブラジル人個性を発揮したサッカーが展開されれば、世界のどのチームも敵わないと、前述のマネージャーが強調する。その通りだろうと思う。
さて、世界が認めるブラジル経済の好調さは、それはブラジル独特の経済政策にある。それを語るには昨年末で退陣したルラ大統領の87%支持率という背景を分析しなければならない。日本ではバラマキとも指摘される貧困層への現金支給による内需向上政策であるが、これとブラジル個性的サッカーを関連付け、次号もブラジル経済の未来を検討したい。以上。
2011年05月19日
2011年5月20日 日本人が豊かになるためには・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年5月20日 日本人が豊かになるためには・・・その二
5月5日号の概要
前号に続きます。前号ではサンフランシスコのベンチャービジネス起業家が、インドに住むインド人に業務を移したことで、アメリカの内需が減るという事と、カリフォルニア・ワインづくりは手作業で、それに要する人件費が地元の人々に給料として支払いされるので、アメリカの内需に結びついて行く。というのが前号の概要でした。
労働生産性の誤解
サンフランシスコに行く前に、50万部ベストセラー「デフレの正体」の著者である藻谷浩介氏の講演を聞き、その後著書を改めて読み成程と思うところが多かった。
まず、藻谷氏は労働生産性への理解が誤解されていると主張する。
日本の経営者は労働生産性を上げるために、人件費を削減する省力化作戦を、労働生産性アップの切り札だと信じ込んでいるが、これが実は問題だとも言う。
経済学での労働生産性とは、労働者一人あたりにつき、どれだけの付加価値を生み出したかどうかを測る尺度のことで、これは「付加価値生産性」とも呼ばれ、各種生産性のうち最も重要なものとされ、具体的な算出方法については
「労働生産性=生産量(付加価値)÷労働量(従業員数)」
で産出される。
付加価値とは何か
では、この付加価値とは何かという理解が重要である。付加価値とは企業等の生産者が生産活動によって作り出した生産額から、その企業などの生産者が購入した原材料や燃料などの中間投入物を差し引いた金額である。
したがって、コストとしての賃金・利子・地代・家賃等と、利益が付加価値の内容を構成する。つまり、人件費として支払いされた給料は付加価値の重要な一部になっているのである。
極論を述べれば、人件費を高く支払えば、付加価値は増加するという事になる。勿論、利益が出ない経営では倒産するのであるから、本来の付加価値としての給料が払えないという事になってしまうので、健全経営体を想定した場合の人件費であるが、この考え方は大事である。
つまり、労働生産性を上げようと、インドに業務移管することは、アメリカの付加価値を下げる事になってしまうのである。勿論、起業家の利益が付加価値としてアメリカのGDPに加算されるので、国家としてのGDPは減らずにすむ。
ところが、今まで働いて給料を得ていたアメリカ人は失職するので、その人が生活するために支出していた消費としての内需は減る事になる。
利益を上げた経営者が、失職した人の分まで余分に消費すれば問題ないが、人間だから食べる量には限界があるように、減った内需を補うまでには至らない。
金は天下の回り物
江戸時代のことわざに「金は天下の回り物」がある。
お金は流通しているという意味で、今自分が所持しているお金は、あたかも自分のもののようであるけれど、実は流通の一環としてたまたま今自分のフトコロにあるだけのもの。お金は使わなければ意味を為さず、入った金は出て行くもの。出て行くからこそ巡り巡ってまた入ってくる。
そうしてお金が回っているから世の中は成り立つ。人の暮らしが成り立つ。という経済の成り立ちを意味している言葉だという。
これはお金に執着し過ぎることを戒める意味となって、使える時は使え!という教訓である。
ところが、無人化設備のハイテク工場とか、薄利多売で機械設備だけで人件費を掛けないビジネスの場合は、支払う給料が少ないのであるから、人を通じて工場が立地している地元にお金は落ちなく、したがって、付加価値が少なくなる。
地元にお金が落ちるビジネスの場合は、支払われたコストは、地元の別企業の売上や従業員の収入となるのだから、地域全体でみればプラスとなって、地域全体が元気になれば、結局、巡り巡って自社の業績につながるのではないか。これが現代版の「金は天下の回り物」という事になるはず。
サンフランシスコのベンチャービジネス起業家が、インド人へ業務移管している事や、機械設備だけで人件費を掛けないビジネスの場合は、付加価値が低くお金が回らない。
付加価値率が高い産業とは
藻谷氏が著書の中で、付加価値率が高い産業として、売上の割にGDPへ貢献する度合が高い産業とは、以下の産業リストのどこであるかと投げかけている。
① 自動車 ②エレクトロニクス ③建設 ④食品製造 ⑤小売(流通)
⑥繊維・化学・鉄鋼 ⑦サービス(飲食業・宿泊業、清掃業、コンサルなど)。
藻谷氏に言わせると、この問いに対する回答は、殆どの人が間違えるという。
実は①の自動車が二割を切って一番低い率なのである。ただし、GDPへの貢献は実額として大きい。付加価値が一番高いのは⑦のサービスであって、付加価値率が高く半分くらい。多くの人は「ハイテク=高付加価値」という思い込みをしているのが大問題だと指摘する。実際には、人間をたくさん雇って効率化の難しいサービスを提供しているサービス業が、売上の割に一番人件費がかかるので付加価値率が高いのである。
この最適例がカリフォルニア州ナパ・ヴァレーのワインづくりである。手作業によって地元の人々に給料が支払いされ、それがこの地の内需に結びついて行くという「金は天下の回り物」が実現している。
日本の実態
藻谷氏は日本の実態についても次のように主張する。
日本のように生産年齢人口が減少している国では、一人当たりで買う量が限定されているような商品、例えば車・住宅・電気製品・外食などは、人口減少に応じて消費者の数が減っていくが、既に生産力が機械化によって維持されているので、供給が減らず、売れ残り在庫が生じ、結果として安値処分か廃棄することになっていく。
すると、その対策として、企業は退職者分を新入社員で補わず、人件費総額を下げる事を当たり前とし、返って付加価値額と率が減少し、不可避的に日本のGDPが減少していく。
逆に、付加価値率を高めるとは、その商品が原価より高い値段で売れて、マージンも人件費も十分にとれるかどうかにかかっている。だから、同じような商品供給で過剰に陥らないようにし、加えて、お客から高い品質評価を受けるようにし、その高い品質評価部分を価格に転嫁できるようにする事だ。つまり、高価格でも売れるようにする事が必要であって、そのためにはその商品にブランド力があるかどうかが、内需拡大とGDP拡大の決め手となるのだというのが藻谷氏の結論。
確かにこれは、何度も例えて恐縮だが、インド人への業務移管と、カリフォルニアワインの実例で証明される。
次は日本人が豊かになるためのプロジェクト検討
今まで述べてきたように、付加価値を高めるためには、人件費を掛けたブランド商品づくりが必要である。
デフレ時代だから何でも安くするというのは、コストを抑えるという事になるので、人件費が下がる事を通じ、一人ひとりの収入を増やさないので、内需を減少させる。
日本が得意とするハイテク品の輸出は、日本全体のGDPを増やす事になるが、国民一人ひとりの豊かさに結びついていない。今の日本人が豊かさを感じていない理由だ。
仏大手出版アシェット社と連携し、世界50カ国書店に「日本の温泉ガイドブック」を配架しようと進めてきたプロジェクトは、結局、温泉の付加価値を世界に妥当に伝えるためのものだったが、今回の東日本大震災でしばらくお蔵入りである。
そこで次なるプロジェクトは、江戸時代に培って、今も日本各地で生き続けているが、多くの人が気づかない付加価値高き存在、多分、それは「日本独自文化」に類するものであるが、それに人件費を十分にかけ外需を稼ぎだす内需産業創りの検討である。以上。
2011年05月06日
2011年5月5日 日本人が豊かになるためには・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年5月5日 日本人が豊かになるためには・・・その一
めまいの街
東日本大震災による余震の「めまい」を引きずって、羽田から直行したサンフランシスコの4月末は結構寒い。この地も地震多く、太平洋プレートと北アメリカプレートが接しているサンアンドレアス断層の上に成り立っている。
105年前の1906年4月18日、この日も肌寒かった朝、サンフランシスコとその近辺の大地が突然に暴れだし、建物は崩壊し、発生した大火は3日間燃え続け、人口45万人のうち20万人が住む家を失った。
さらに22年前の1989年10月17日にも、マグニチュード6.9の大地震が発生し被害に遭っている。
日米修好通商条約の批准のため、万延元年(1860)咸臨丸で勝海舟・福沢諭吉、ジョン万次郎一行がここに初上陸したのは、お互い地震が多い事から、呼び寄せあったのかもしれない。
そういえば、サンフランシスコはアルフレッド・ヒッチコック監督の映画「めまい」(1958年)の舞台だ。高所恐怖症になったジェームス・スチュアート扮する元刑事が、キム・ノヴァク扮する友人の妻を追跡することによって、サンフランシスコを案内する巧みなスリラー物語だが、タイトル「めまい」は地震の街からだろう。
ベンチャービジネス起業家
サンフランシスコでアメリカ人8人と日本式の居酒屋で雑談した。その中の一人、まだ若いベンチャービジネス起業家、彼はツイッターを活用したマーケティング業務を展開している。業務内容はノウハウなので紹介できないが、彼を手伝う人物がインド人で、採用はamazon serviceの紹介で決めたという。
アメリカの最低賃金は、1997年以来アメリカ連邦政府が設定した時給5.10ドルだが、これでは人は集まらず、彼は近くに住む中年アメリカ人女性に、時給12ドル(約970円・81円レート)で、それまで働いてもらっていた。
だが、アマゾンの斡旋でインド・バンガロール近郊に住む若者に変更した。その理由は時給がたったの2ドル(約160円)という安さから。アマゾンにはインド人が多数登録してあって、その中からオークションで決める事ができる。
12ドルから2ドルへ。同じ業務が六分の一というコスト。英語は正確で仕事は出来るし、このインド人に下請け業務のインド人もいるらしい。2ドルで複数人が使えるというのだ。
また、この2ドルには、アマゾン経由の送金支払い手数料とルピー両替費用も含んでいるという。これにしばし言葉も出ない。
二つの愕然
さらに、このインド人はカースト制階級の下の方の人物らしいが、頭がよく、世界情勢に関心高く、東日本大震災に20ドル(約1600円)義援金支出したともいう。時給2ドルだから10時間以上の収入を日本のために支払ってくれたのだ。これにも愕然とする。
この愕然には二つの意味がある。インドでは2ドルの時給でも義援金が出せるという事と、アメリカ人はコンピューターテクノロジーを開発したために、アメリカ人が仕事を奪い取られているという事実だ。
つまり、本来アメリカ人に支払われるはずの人件費が、ただ同然の金額で外国に逃げ、アメリカ人の仕事がなくなって、とうとう起業家の彼のところに、一日20ドル(約1600円)でもよいから仕事させてくれと言ってくる人もいるという。
起業家のビジネス労働生産性は向上して、企業としての利益は増加するが、従業員として働いていたアメリカ人の収入は減るのだから、その人の生活消費は減少し、内需は増えなく、景気回復は難しいという事になる。
では、今後アメリカ人に残る仕事は何か。産業が少ないアメリカでは医者か、弁護士か、それになれない場合は軍隊に行くしかない。これはジョークではなくアメリカにとって大問題ではないか。そういうことがアメリカ社会に隠されていると感じる。
しかし、この事例は日本でも当てはまるだろう。日本企業が労働生産性を向上させようと、無人化工場を建設し、新たなる産業システムを稼働させたとすると、企業利益とGDPは増えても、当然ではあるが従業員は激減し、そのために人件費という人へのお金の支払いはなくなって、生活消費という内需は減るだろう。
日本もアメリカと同じ事を行っているのだ。
ケンゾーエステイト
サンフランシスコから帰りのJAL、機内誌を見ていたら「ケンゾーエステイトのワインをお楽しみいただけます」とあり、カリフォルニア州ナパ・ヴァレー奥の深い森に包まれて、誰の目にも触れることなく、ひっそりと美しい清らかなワイナリーが「ケンゾーエステイト」であると紹介されている。
ここは日本人の辻本憲三氏が20年前から開発していたエステイト(土地)。この土地のワインを食事時に飲んだのかと思いつつ、もう一度、改めて「紫鈴2007赤」と「あさつゆ2009白」を少し味見してみると、かなりいけるような気がする。
ワインについては、フランス各地のワイナリー訪問と、パリ農業祭で毎年金銀銅メダルのワインを試飲しているし、今回はシアトルでクマモトオイスターと合うワインコンテストにも参加したので、一応味は分かるのではと思っているが、この「ケンゾーエステイト」もなかなかである。
カリフォルニア・ワイン
元々カリフォルニア州ナパ・ヴァレーで、ワインづくりを始めたのはフランシスコ会の神父だった。
元来アメリカ人はステーキに代表されるアメリカ的料理で、ウイスキーとかビール中心であったのが、第二次世界大戦後ヨーロッパ的料理がアメリカに入り込んできて、ワイン需要が増えナパ・ヴァレーに多くのワイナリーが誕生。それも弁護士、学者、医者などが趣味でワイナリーを作りはじめ、次に大資本も入ってきて、現在約120のワイナリーがある。
さて、この地のワインの品質はどうなのか。1972年にパリで開催されたワイン品評会(Paris tasting)で、赤はボルドーを押さえ、また、白はブルゴーニュを押さえそれぞれ“1番”に輝き、この時から世界的に高い評価を得たわけで、その物語が日本では未公開だが「ボトルショック」という映画になっている。
その後も「ロバート・モンダビ」「オーバス・ワン」や「ケンゾーエステイト」のような優秀なワイナリーが誕生し、今では世界のワイン業界で確固たる位置づけとなって、アメリカを代表するワインブランドとして、一大産業になっている。
さらに、これは秘密でも何でもないが、ワイン造りには重要な条件がある。それは機械化をなるべく避け、ワインの苗を手作業で手入れするという事である。ぶどうの苗木に茂る葉の一枚一枚を日差しからコントロールするのを、人間の手で行う事。これが良質なワイン造りの当然の作業となる。
ということは、その手作業に人件費が膨大にかけられわけで、その結果として働く地元の人々に給料が支払いされ、それがこの地の内需に結びついて行くのである。
また、この手作業という結果は、価格を高くするという事になって、ロバート・モンダビのティスティングは四品で30ドルと15ドル。
オーバス・ワンのティスイングは一杯30ドルで一品だけ。高いが試してみると香りが豊かで、グラスを持って階上のテラスに行くと、ワイン畑が遠くまで見渡せ、ロスチャイルド家とロバート・モンダビが共同でつくりあげた物語と共に、グラス一杯だけなので、ゆっくり味わうから、なおさら美味いと思わせる。舞台づくりが上手なのだ。
このようなワイン造りは、地元の土地で行うので、インドに住むインド人には代替できない。したがって、完全なる内需産業であり、輸出する事で外需も稼げるのである。
日本人を豊かにする企画プランつくりへ
仏雑誌出版社アシェット社と世界50カ国書店に「日本の温泉ガイドブック」を配架するプロジェクトは東日本大震災で頓挫したので、次なる企画を検討中。次号へ。以上。
2011年04月21日
2011年4月20日 日本のイメージをどうするか
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年4月20日 日本のイメージをどうするか
今から143年前の江戸市中
今回の東日本大震災と福島第一原子力発電所(福島原発)事故、被害と問題内容は異なりますが、大事件という意味では143年前の江戸市民も同様でした。今まで将軍様より偉い人は知らなかった江戸っ子にとって、京に天子様がいるなぞということは、ずっと長い間意味のない存在だった。その身近で最も偉い将軍様であった十五代将軍徳川慶喜が、突然大坂から戻ってきて、江戸城で喧喧諤諤の大評定をしていると思っていたら、突然上野の山に隠れてしまって、代わりに京の天子様の命令で、薩長の輩が官軍という名聞で江戸城に攻めてくるという。攻撃されると江戸市中は火の海になって、壊滅するかもしれない。店や住まいが燃えてしまう。これは大変だ。どうしたらよいのか。町中大騒ぎになって、ただ右往左往しているだけだった。今まで考えたこともなかった事態が突如発生し混乱の極に陥りました。
山岡鉄舟が江戸市民に諭した事
この時に山岡鉄舟が登場し、そのことを歌舞伎役者の八代目坂東三津五郎(1906~75)が次のように、鉄舟研究家として著名な故大森曹玄氏との対談で述べています。
「山岡鉄舟先生は、江戸城総攻めの始末がついてからのち、それでなくとも忙しいからだを、つとめて人に会うようになすった。それも庶民階級、まあ、出入りの植木屋さんから大工さん、畳屋さんから相撲取りから、話し家、役者、あらゆる階級の人たちに会って、鉄舟さんのおっしゃった言葉は『おまえたちが今、右往左往したってどうにもならない。たいへんな時なんだけれども、いちばん肝心なことは、おまえたちが自分の稼業に励み、役者は舞台を努め、左官屋は壁を塗っていればよいのだ。あわてることはない。自分の稼業に励めばまちがいないんだ』と言うのです。このいちばん何でもないことを言ってくださったのが、山岡鉄舟先生で、これはたいへんなことだと思うんです。
今度の戦争が済んだ終戦後に、われわれ芝居をやっている者は、進駐軍がやってきて、これから歌舞伎がどうなるかわからなかった。そのような時に、私たちに山岡鉄舟先生のようにそういうことを言ってくれる人は一人もおりませんでしたね」(『日本史探訪・第十巻』角川書店)
さすがに歌舞伎界の故事、先達の芸風に詳しく、生き字引と言われ、随筆集「戯場戯語」でエッセイストクラブ賞を受賞した八代目坂東三津五郎です。鉄舟にも詳しいのです。
福島原発事故で諭せる人物はいるのか
三津五郎が指摘した鉄舟の諭しと同様な事を、福島原発事故で、国民が納得するように諭せる人物はいるのでしょうか。
多分、どこかにいると思いますが、仮に鉄舟と同様のことを述べたとしても、鉄舟とは人物の器が違っているので、影響力が比較にならず、国民に対して大きな感化力を持てないので、誰も気づかずに毎日をすごしているのではないでしょうか。
それより、返って諭すということでなく、東京電力の対応を責め、政府の対策を問題点とし、菅首相の辞任にまで公然と国会やマスコミで論じるのが今の実態です。政府や首相は、確かにまずい対応が重なった事も事実ですが。
だが、まずくても、原発の成りゆきを世界中が息をひそめて見つめているのですから、与野党の権力争いとして原発問題を対象とするのはもっての外です。
それより今最も必要で大事な事は、原発事故内容の事実を正確に把握する事です。事実が分からないから、東電や原子力関係者が困難を来たし、国民も分からないからハラハラドキドキの毎日なのです。事実確認に全精力を投入する事が、早い解決への道であり、先決事項で重要です。鉄舟は駿府で官軍実質総司令官である西郷隆盛と直に会い談判し、江戸無血開城を決めてきたという事実確認を持ち得ていたからこそ、江戸市民を諭す事が出来たのです。
どうして権力闘争に走るのか
政治家は、口では「与野党協力」と言いながら「行動は醜い権力闘争」をしているのが実態ですが、では何故にこのような国民の期待を裏切る行動をしているのでしょうか。
実は、その理由は我々国民に存在しています。福島原発事故が起きて、我々に何を一番もたらしたのでしょうか。勿論、マスコミから流される東日本大震災の状況に涙し、義援金を届け、ボランティアに参加しています。この事ではなく我々の精神面に3月11日以降、何が生じているかです。3月11日以前とは全く違う気持ちが生まれています。
それは「緊張感」です。原発問題が我々の生活に「恐怖感」をもたらしています。外国人が一斉に帰国したのが、この気持ちを表した実態姿です。外国人は帰るところがある。しかし、日本人は今住んでいるところから動けない。そこに毎日報道される放射能汚染の危険性、食べ物に対する注意事項、それらが我々に強い緊張感を生じさせているのです。
これが以前と異なる日本社会の実態で、それが政治家の権力闘争の要因なのです。
いじめと同じ構造
あるグループに緊張感という欲求不満、フラストレーションが溜まると、そのグループ内にどのような行動が発生するのか。実は、グループ内の人々は、欲求不満が講じてくると、必ずといってもよいあるパターン行動に移ります。
それは、欲求不満を解消しようとして攻撃する対象を定めるのです。そして、定められる対象は「弱き人」です。弱いものを見つけ出し、それに向かって集団で「いじめ」行動を取り、いじめられる側がいじめに従うと欲求不満が一応おさまるのです。
いじめられる側は大変ですが、これが差別とかいじめの背景にあるという実態を認識すべきです。今回の原発問題で、強く危機感と緊張感を持った我々の気持ち、それを政治家が察し、その解消行動として政府・首相を激しく攻撃しだしたのです。
だが、通常のいじめ対象と政府・首相は異なります。正面から受け立っていますから、攻撃側は激昂し一段と菅内閣打倒に走るでしょうし、これからも激しく醜い闘いが続くと思いますが、一日も早く攻撃する政治家連中が、自分が低レベルのいじめ構造で動いている事を認識して、権力闘争はやめるべきです。
今は一致団結して原発問題の事実確認を急ぎ解決する事です。そうすれば国民の強度の緊張感が消えますから、それからゆっくりと激しく権力闘争すればよいのです。
日本のイメージをどのようにつくり直すか
日本が観光立国・観光大国化政策を掲げた事に賛成し、フランスのアシェット社に協力を得て「温泉ガイドブック」を世界50カ国の書店に配架する計画を、観光庁と経産省のクールジャパン室に提案した事は既にお伝えしました。
しかし、この提案は藻屑と化しました。放射能の危険がある国に観光に来たいと思う人はいません。今後長期間、日本は観光客で低迷する事を覚悟しなければなりません。観光地は日本人のみでしょう。仕方ない事です。日本は安全で清潔だというイメージは崩壊しました。
原発問題はかなりの時間がかかるでしょうが、いずれは解決するでしょう。しかし、解決した後の傷ついた日本のイメージをどのような姿に再構築すべきなのでしょうか。
今はこのイメージ構築を議論すべき時です。既に、政治家の中で考えている人物はいると思いますが、鉄舟レベルの人物が存在しない実態ですから、政治家に任せるのでなく、我々一人ひとりが考えなければいけません。
鉄舟が「おまえたちは、自分の稼業に励めばまちがいないんだ」と言った事に加えて、もうひとつ「原発後の日本イメージ」をどうするのかという事を、自分の稼業に励む以外に、それぞれ考えなければいけないと思います。
援助受け取り世界一
東日本大震災で、日本が2011年に世界から援助を受ける額は864億円になる見込みで世界一になります。それまではスーダンが一番で638億円、アフガニスタン350億円、ハイチは280億円です。今までは援助する国の代表的存在だった日本は、世界中から助けられる立場に激変しているという事実を、世界中の人々が示してくれた「愛・同情」に感謝しつつ、我々は深く認識すべきでしょう。
ところで、日本は武士道の国です。武士道では「愛・同情」を「仁」と位置付けています。この「仁」を受けた日本は、世界中に「義理」を負ったわけで、「義理」に対する「お返し」をするのが「道理であり、条理であり、人間の行うべき道」でしょう。では、我々はどうやって「お返し」すべきなのでしょうか。
観光立国が非現実化した日本、変わるべき「イメージ戦略」の構築と、世界への「お返し」を具体的にどのようにすべきか、それを課題として一人ひとりが考えたいと思います。以上。
2011年04月06日
懐かしい生き方へ・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年4月5日 懐かしい生き方へ・・・その二
東日本大震災と危機管理
前号で「武士道」を考察するとお伝えしましたが、変更して、少し今回の東日本大震災から学ぶべき危機管理項目を取り上げたいと思います。
まず、大前提として大事な事は、日本列島は新たな地震活動期に入っているという事実を再確認すべき事です。また、現在の危機管理体制は、大正12年9月(1923)の関東大震災による88年前の体験からつくられたものが中心になっているので、それらを見直さなければいけないという事です。
関東大震災による88年前の体験からつくられたものが中心になっているので、それらを見直さなければいけないという事です。
具体的に言えば、当時と今では「オフィス・住環境」が著しく変化しています。今の都市では超高層ビルが乱立しています。88年前は存在していませんでした。今回の地震、高層ビルの上層階ほど揺れました。地震発生後、エレベーターが停まった高層マンションから階段を歩いて降りて、上を見ながら道路際に佇む人々をたくさん見ました。地震の揺れがさぞかし怖かったのでしょう。専門家に言わせれば、室内の家具転倒防止具のL字型金具で留めてあっても、その効果が効くのは6階までとの見解です。
近く予測されている「東京湾北部地震M7.3」が発生したら、家具類は凶器に変化するでしょう。冷蔵庫は90kg、洗濯機は60kgもありますから。さらに、オフィスに常備している自販機は350kgから800kgあります。これが凶器になって、人に襲いかかります。
人間は自分の体重の4倍以上の加重が、胸部を強く圧迫した場合70%以上の人が 10分以内に死ぬといわれています。
つまり、自分が関係する建物の耐震構造度合いによって、危機への事前準備と、実際の地震時の行動が違ってくるのです。「地震発生時に外に出ないこと」とか「机の下に入る」というような言い古された教訓は、自らの環境を判断して見直すべきでしょう。
3月11日の体験
東日本大震災発生時、私は浜松町駅ホームで電車を待っていました。突然、頭上の蛍光灯が大きく揺れ出し、目の前の広告看板が動きましたが、ちょうどその時、京浜東北線が到着しドアが開きました。
頭上からモノが落下する可能性もあるので、いち早く電車内に入りましたが、揺れは何回も続き、当然ですが電車は動かず、しばらくすると構内マイクで「この地区は芝公園が避難地区なので、そちらへ避難してください」とあり、駅が閉鎖されました。
この時、考えたことは「土地勘があるところに行こう」ということでした。知らない場所ではかえって危ないと思ったのです。土地勘があるところとは、長く勤め人をしていた銀座地区であり、今の仕事でよく行く東京駅近辺ですので、浜松町から歩きだし、最初は銀座の松坂屋に行きました。何故かというと、松坂屋の一階から地下に降りる角に固定電話があることを知っていたからです。
携帯電話は全く機能しませんでした。家族と、当日の会合責任者に連絡を取らねばいけないので、固定電話を探しましたが、公衆電話ボックスの前は長蛇の列。そこで思いだしたのが松坂屋なのです。次に、携帯電話は消耗して赤印となっていたので、松坂屋前のドコモショップ地下で充電しました。その間に、そこにいる人々と情報交換しましたが、皆さん、これからどうするか困っているだけでした。
一時間半程度で充電でき、東京駅の地下街に向かいました。もう夕刻でしたので、地下街なら何か食べられるだろうと思ったわけですが、行ってみるとどの店も既に完売で閉まっています。また、既に段ボールを敷いて夜を過ごす準備の人が大勢いました。
一瞬、一緒に地下街で過ごそうと思いましたが、何も食べていないので、八重洲口地上に出て食事場所を探しましたが、どこも満員。ようやく一軒の居酒屋に入り、カウンターに座ることができましたが、私の後から来た人は全店断られていました。
カラオケボックスに泊る
食事しながら回りの人々の会話を注目していましたら、若い男性の「今日はカラオケボックスだ」という発言が耳に入りました。そうかホテルがダメだからカラオケボックスにしようと、直ぐに居酒屋の女将にお握りをつくってもらい、カラオケボックスに行きましたら、既に大勢の人が受付に並んでいます。ようやく受付が終りましたが、私の次の人は「満室です」と断られました。
カラオケの部屋に入って携帯で家族に連絡しようとしましたが、まだつながらず、あきらめてソファに寝たわけです。飛行機の座席で寝るよりはずっと快適でしたが、朝五時には閉店で、東京駅に行きましたが、まだ電車は動いていません。
東京駅構内と地下街は人で溢れていましたが、驚いたことにゴミが無いのです。大きなビニール袋を持つ係りが廻り歩いてゴミを回収し清潔で、大勢の人々も山奥にいるような静けさで、誰も慌てていません。ただ、ジッとテレビに見入っていました。
自宅方面への始発電車がある上野駅まで歩こうと、日本橋の高島屋前を通りますと、店内一階売り場に大勢の人が椅子に座っているではありませんか。そこで正面入り口に行きますと、社員が「どうぞ、お休みください」とドアを開けてくれます。中には買い物にきたまま一晩過ごした着物姿の女性やベビーカーの若夫婦もいます。高島屋の社員が水や朝食代わりにお菓子を提供してくれ、暖房の快適さと、社員の親切さにホッとし感激しました。
ようやく電車が動きましたという店内放送で、地下鉄で上野駅まで行きましたが、始発電車は直ぐには出ず、かなり待ちようやく動き出しました。当然ですが電車内は超満員鮨詰めで、空調が利かず熱く汗だくですが、コートと上着も脱げないほどでした。しかし、誰一人文句は言いません。通常は20分で到着する区間を、線路の安全確認をしながら動くので1時間40分かかりましたが、乗客は静かに耐えていました。浦和駅に到着し降りる時「気をつけて」という声が車内からかかりました。ビックリすると同時に感激しました。日本人は何と素晴らしい助け合いの気持ちを持っているのだろうか。すごい民族だと再確認したわけです。
世界の報道
アメリカCNNテレビ3月12日夜のニュース番組が、被災地の状況を「略奪のような行為は皆無で、住民たちは冷静で、自助努力と他者との調和を保ちながら、礼儀さえも守っています」と報道し、これが全世界に流れました。
また、私が体験した東京の地震発生時の状況も、各国の新聞が「いつもと変わらず人々は冷静に対処し行動していた」と報道しました。その報道内容をNYタイムズ、ロサンゼルス・タイムズ、UKデイリー・テレグラフ、仏ル・モンド、韓国・中央日報、イスラエル・ハアレツ、ロシア・イズベスチヤ、伊コリエレ・デラ・セラ等で後日確認しましたので、間違いなく全世界の新聞は、東京における日本人の行動も共通認識で報道しています。
加えて、その行動が外国人には信じられないものである事を認めつつ、だが、どうして日本人はそのような行動をとれるのか、という背景要因を探ろうとしています。その分析が本質的で的確であるかどうかは別として、何かが日本人にあるのだという論理組み立てです。
例えば、ル・モンドは「驚くべき自制心は仏教の教えが心情にしみ込んでいるからだ」と分析し、イズベスチヤは「日本人は自分たちを一つの大きな家族と捉えている。そこには宗教や道徳観、強い民族的自覚が影響している」と書き、デイリー・テレグラフは「何をするときでも正しい作法に則ってやりなさい、というのが日本の暮らしの大原則だ。茶道がいい例だ」というように解説しています。
東日本大震災時の日本人の行動は、世界中の国とは価値観が異なる民族である事を認め、そこに日本の何かが存在しているのだと、日本人を精一杯研究し推考しているのです。
日本の報道
では、日本の新聞報道は被災地の人々の行動に対し、どのような報道だったでしょうか。著名な作家・建築家・経営者の新聞掲載内容を読みますと、外国人の反応を誇らしげに受けとめ、日本人は「やさしさ・愛等の人間の本質的なものを持っている」という事を再確認する内容で共通しています。
しかし、どうして日本人は外国人が信じられない行動を、システム崩壊時に発揮できるのかという事への言及と、背景分析が今一歩踏み込み不十分である事も共通し、日本人のDNAに存在するというレベルに止まっています。
日本人には世界の人々と違う何かがあり、それはどこでどのようにいつから身についたのか。その本質面からの日本人分析が甘いと思います。実は、この分析力の甘さが、今回の福島原発事故をもたらした根本要因ではないか。それを次号で検討したいと思います。以上。
2011年03月21日
2011年3月20日 懐かしい生き方へ・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年3月20日 懐かしい生き方へ・・・その一
今回の東日本大震災で亡くなられた多くの方のご冥福をお祈りし、被害に遭われた方々に謹んでお見舞い申し上げます。
当方にも世界各国からお見舞いのメールをいただき、また、中には「こちらに家族で移住するようにと」の申し出を頂きましたように、激甚な災害が世界中に伝わっています。
システムの崩壊
今回の東日本大震災は社会システムの大崩壊です。
我々は過去の世界が構築してきた、あるシステムの中で生活していて、このシステムから逃れられるこ
とはできませんし、通常の状態ではこのシステムを倒すことも出来ません。
しかし、特別な事件が発生した時は、この通常システムが崩壊する場合があります。それは、システム崩壊を予測していないか、予測を遥かに超える事態が発生した場合です。
例えば、サブプライムローン問題から発生した2008年9月のリーマンショク、これで世界的な金融危機に陥りましたが、これは金融経済面でのシステム大崩壊でした。
自然環境面では2005年8月に、ハリケーン「カトリーナ」がアメリカ・ルイジアナ州を襲い、ニューオーリンズ市にもたらした大被害、これは社会システムの大崩壊です。
今回の東日本大震災も、事前に予測された規模を遥かに超える大災害でした。
今の時代のシステムとは
今の近代社会は、経済力を充実させる事によって、安全で豊かなシステム社会を築いてきました。結果として、このシステム社会は、自己利益を最優先するライフスタイルを採ることが優先され、欲しいものは何でも金を出せば買えるという考え方が強くなってきました。
一方、小集団とか仲間づくりということが、ないがしろにされる傾向となって、集団の規律や仲間とのしがらみなんて面倒だ、という考え方が強くなってきました。
具体的には、親族の解体化、地域共同体の解体化、終身雇用・年功序列制度に基づく疑似親族体であった日本的企業組織の解体化等です。
また、このようなシステム社会では、個性とオリジナリティが資産とみなされ「誰にも迷惑をかけない、かけられない」という「スタンドアローン」、社会から「孤立」した生き方が理想とされてきて、多くの人々が「自分さえよければ、それでよい」というようになってきたように思います。
危機にはその国の国民性が表出する
ところが、東日本大震災にみるようなシステムの大崩壊という危機、この時に、突然のごとく、その所属する国民性が色濃く表出します。
日本国民の態度を、アメリカCNNテレビ12日夜のニュース番組は、スタジオにいるキャスターのウルフ・ブリッツアー記者と、宮城県・仙台地区にいるキュン・ラー記者との会話を通じて伝えました。
「ブリッツアー記者が『災害を受けた地域で被災者が商店を略奪したり、暴動を起こしたりという暴力行為に走ることはありませんか』と質問すると、ラー記者は以下のように答えました。『日本の被災地の住民たちは冷静で、自助努力と他者との調和を保ちながら、礼儀さえも守っています。共に助け合っていくという共同体の意識でしょうか。調和を大切にする日本社会の特徴でしょうか。そんな傾向が目立ちます』と。
更に、ブリッツアー記者が特に略奪について問うと、ラー記者の答えはさらに明確でした。
『略奪のような行為は驚くほど皆無なのです。みんなが正直さや誠実さに駆られて機能しているという様子なのです』と」
このラー記者の報告はCNNテレビで繰り返し放映され、日本人はこのような大危機状態でも冷静で沈着で、明らかに日本人のそうした態度が美徳として報じられ、その報道は全米向けだけでなく、世界各国に向けても放映されたのです。
更に、韓国の李明博大統領も、ソウル日本大使館で記帳し、日本人の冷静な対応について「印象深く感動的だった」と述べました。
世界から日本を見る
このレターで、何度も「世界から日本を見る」ことの重要性をお伝えしてきました。
我々は日本に住んでいますから「日本内から日本を見る」という見方が、当然のごとく行われています。しかし、日本の実態をより把握するためには、世界が日本をどう見ているかという内容も併せて確認することが、日本を妥当に判断するために必要で大事なことです。
日本内から日本を見るだけの場合は、日本の過去実態との比較になりますから、年配者がよく口にする「昔はよかった。それに比較し今はダメだ」という見解になりやすいのです。
ところが、社会は時間と共にドンドン変わっていきますので、過去の日本と今では環境条件が大きく異なっています。従って、今の日本実態を判断したい場合、日本内部だけでの情報でなく、世界の国々の実態と比較し判断すると、より一層日本の位置づけ実態が明確になるのです。
つまり、今回の東日本大震災被災によって示された行動、それが的確であったかどうか、その判断は世界の人々の反応から見てみることが重要です。つまり、CNNテレビニュースの報道内容を素直に受け入れることが必要で大事な事でしょう。
日本では略奪が無い
CNCの米国人キャスターは「略奪」という言葉を出しましたが、それはそれなりの理由があります。米国では同種の自然災害や人為的な騒動が生じた際に、必ずと言ってよいほど被災者側だとみられた人間集団による商店の略奪が起きています。
2005年8月のハリケーン「カトリーナ」が襲った時、ニューオーリンズ市から住民の大多数が市外へと避難しましたが、市内中心部にとどまった一部の人たちが付近の商店へ押し入り、商品略奪する光景がテレビで全世界に流されました。
広大なスーパーマーケットに侵入して、食物や飲料を片端からカートに投げ込んで走り去る青年。ドアの破れた薬局から医薬品を山のように盗んでカゴに下げ、水浸しの街路を歩いていく中年女性。テレビやラジオなどの電気製品を肩にかついで逃げていく中年男性。色とりどりの衣類を腕いっぱいに抱え、笑顔を見せ、走っていく少女。何かの商品を入れた箱を引っ張り、誇らしげに片手を宙に高々と突き出す少年・・・。他人の財産を奪い、盗むという「火事場泥棒」が当然のごとく表出したのです。
だが、日本ではニューオーリンズ市の光景は出現していません。
「日本人は、これほど無惨な被害に遭っても、沈着・整然として、静かに復旧作業に取り組んでいる。一体なぜ日本国民はこれほど秩序のある態度を保てるのだろうか」
これが全世界の人々が持つ率直な疑問点となっているのです。日本と他国との文化や国民の意識と価値観には、大きな隔たりがあると思わざるを得ません。この実態判断は「世界から日本を見る」ことから分かり、日本には独自の何かがあるはずと考えるべきでしょう。
日本独自のものとは何か
世界の人々が賞賛する、東日本大震災被災によって示された行動は、日本人が持つ「常識」が顕れたのです。では、その「常識」の中味は何で、それはどこで生まれ、どのように日本人の中に住みついたのか。その検討が必要でしょう。
実は、この検討は「日本人とは」という日本人論考察につながり、そのためには我々の「懐かしい思い出」を呼び起こすことが必要なのです。
その「懐かしい思い出」とは、親から受けた「しつけ・躾」のことです。
日本人は一般的に親からのしつけで「人から後ろ指さされないように」「恥ずかしい事はするな」「体を清潔にしなさい」等を幼少時代から叩きこまれてきたと思います。
このしつけの「し」とは能でいう「仕手」の「し」であり、意図的に行為し振る舞うことを意味し、「つけ」とは行為や振る舞いが習慣化されることを意味しています。
また、このしつけという日本文字は「躾」と書くように、身体に美しいという字を寄り添わせます。古くは「美」という文字に代えて「花」「華」という字を使っていました。
このように「躾」という意味には、内心の美的感覚が含まれており、それは、かつての時代、武士たちは花を賞でつつ、そのつぼみがつき、花開き、咲き誇り、やがて散る運命を自分の生き様に重ね合わし、戦闘で死ぬことと結び付け、その死を「花花しい討死」や「死に花を咲かせる」につなげたいという「日本の武士道」から発しているものなのです。
世界から賞賛される背景には、我々が忘却の彼方にした「武士道」という思いがけないものが存在しているのです。「武士道」検討こそが日本人論考察となり次号に続きます。以上。
2011年03月06日
日本人は武士道を理解しているか
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年3月5日 日本人は武士道を理解しているか
ザッケローニ監督が気づいたこと
日本のサッカーはザッケローニ監督就任以後、アジア杯で優勝する等、素晴らしい活躍で国民に明るい話題を提供してくれています。
そのザッケローニ監督が記者会見で語る言葉、なかなか参考になります。
例えば、
① 欧州への選手供給源だったアフリカの立場を「アジアが取って代わりつつある」と分析。
② 日本選手の「俊敏性」「勤勉さ」をチーム強化に生かしたい。
③ 攻撃では「サイドに展開したら、もう別サイドには運ばなくていい。そのサイドで縦へ行け」
④ 日本選手が「荷物を自分で運び、試合後の後片付けまでする。今まで見たことがない」と感心。
⑤ 日本人の武士道を学びたい。
等ですが、この最後の「武士道」発言は大事です。日本人のエートスに気づいたのです。
ボルドー魂
一月は、サンフランシスコ近郊に広がるNAPA VALLEY ナパバレーに行きました。ここはカリフォルニア・ワインの産地として有名で、その名を世界にとどろかせたのは、1976年フランスのワイン品評会(Paris tasting)での優勝でした。
赤ワインはボルドーを押さえ、白ワインはブルゴーニュを押さえ、それぞれ“1番”に輝き、フランスのワインが世界一だと自負しきっていたフランス人の鼻をへし折り、映画にもなりました。題名は「ボトルショック(Bottle Shock)」です。
二月は、パリ農業祭に行き、前号でお伝えしたマンガ「神の雫」に登場する、ボルドーワイナリー女性経営者と会いましたので、ナパバレーで見たアメリカ流ワインマーケティングを伝えますと、「全く興味ありません。当方は家族経営方針を貫くだけ」ときっぱり一言です。彼女は、今年も農業祭ワインコンクールで金賞を獲得、この金賞メダルと「神の雫」を武器にし 加えて上品なフランス式応対話法で、日中韓国に営業に行き成果を上げている姿を見ると、根源に何か「ボルドー魂」といえるものがあると感じます。
最後の忠臣蔵
昨年11月、パリ日本文化会館(Maison de la culture du Japon à Paris)で、日本公開に先立って映画「最後の忠臣蔵」が放映され、パリ在住の若い日本人男性が見に行きました。この男性とは、映画終了後食事する予定でしたので、レストランで待っていましたが来ません。翌日、どうしたのかと聞きますと、映画の最後の切腹場面がリアルだったので、何も食べられず寝てしまったというのです。
そこで、「最後の忠臣蔵」を観てみました。確かに切腹場面は激しく厳しいのですが、食事をとれないほどではなく、改めて彼にいろいろ尋ねてみると、どうも日本で上映されたものと、フランスで事前公開された映画では、最後の切腹シーンが異なっているようでした。フランスの方がよりリアルで、切腹場面の時間も長かったらしいのです。
この映画の制作はアメリカのワーナー・ブラザースなので、海外用は日本版と異なるのかと思いましたが、最後に表示されたタイトル、それが「最後の牢人 ラスト・ローニン LAST RONIN」であったことに興味を持ちました。
ラストサムライ
「ラスト」という表現は、映画「ラストサムライThe Last Samurai」でも使われています。これもワーナー・ブラザース制作ですから、アメリカから見た日本の心・武士道を描こうとした場合の普遍性用語かも知れません。
「ラストサムライ」は2003年の公開、主人公を演じたトム・クルーズのモデルは、江戸幕府のフランス軍事顧問団として来日し、榎本武揚率いる旧幕府軍に参加し、箱館戦争を戦ったジュール・ブリュネで、物語のモデルとなった史実には、西郷隆盛らが明治新政府に対して蜂起した西南戦争(1877年)や、熊本の不平士族が明治政府の近代軍隊に、日本の伝統的な刀剣のみで戦いを挑んだ神風連の乱(1876年)であろうといわれています。
ところで、今話題のソーシャルメディアのフェイスブック、当初、「The Facebook」としていたのを、「The」を取って単に「Facebook」とネーミングにしたことが、今日の躍進につながったという話も聞きましたので、タイトルは重要です。
さて、この機会に再び「ラストサムライ」をジックリ観てみましたが、感じるところ多々ありました。それはアメリカ人が武士道を理解して行くプロセスをストーリー化していることです。トム・クルーズが捕らわれ、武士達と生活を共にして行くうちに、武士階級に根ざしている武士道に興味と関心を持ちはじめ、最後には「無 ノーマインド」感覚までも意識して行く。アメリカ人にとって、理解を超える日本という国を解き明かそうとしているのです。これは今後の武士道研究に役立ちました。
仏トウルーズ大学
パリの農業祭を終えて、フランス南部のトウルーズ大学へ行きました。ここで第二外国語として日本語を学ぶ学生達と、武士道について話し合うためです。
日本語学科の教授が受け持つ授業90分間をいただき、出席学生50名全員に「武士道ということにどういうイメージを持っているか」を尋ねてみました。
回答は「サムライ、刀、自分を見つめるもの、律するもの、七人の侍のようなもの、生き方、考え方、決まりごと、規律、誇り、精神的なもの、戦うでなく人のために働く事、社会全体の規則、ラストサムライだ、武士の新しい関係、日本人の道徳、気遣い、日本人の価値観、生活の哲学、神道・儒教が混じったもの、明治の精神、戦士の誇り、厳格なもの、従うべき法則、世界に日本の価値を見せたかったから新渡戸が書いたのだろう、戦争に通じるもの、人に対する態度、仇討、ナイトの精神、到達したい分野 」
如何ですか。かなり武士道を分かっているような感じが致しませんか。特に「ラストサムライ」を観た人と尋ねると90%が手をあげたように、日本語を学んでいる学生達故なのか、武士道に対する関心は殊の外高いと思いました。
このほかに日本人の女子留学生から「フランスにいると、何かの時に、心の中でぶつかるものがあるが、それが武士道ではないかと思う」と発言したことが印象に残りました。
日本人は武士道を理解しているか
アメリカ人のスティーブン・ナッシュ著「日本人と武士道」(角川春樹事務所)に、「政治家であれ経営者であれ学生であれ、アメリカを訪れる日本人から新渡戸稲造の『武士道』のことを聞かされることはめったにない」とあり、日本人は新渡戸稲造の武士道を理解していないので、話題にしないのではないかと述べています。
また、北野タケシは竹田恒泰(明治天皇玄孫)との対談(日本はなぜ世界でいちばん人気があるのか・PHP新書)で、「羅生門をはじめ、日本映画で表彰を受けた作品は、絶対に外国に媚を売らない作品ですよ。ときどき勘違いした監督が、紋付き羽織袴姿で外国に行って、ちょっと難しい話になったら『禅』や『武士道』を出せば、外国人を騙せると思っている。だからおいらは外国でインタビューを受けると、日本の監督で『禅』や『武士道』を出すやつは信用するな、何もわかってないんだと言っています」と語っています。
世界のタケシが述べ、アメリカ人も同様な見解ですから、日本人は武士道を理解していないというのが事実ではないでしょうか。
テレビドラマ「遺恨あり~明治13年最後の仇討」
2月26日にテレビ朝日系列で「遺恨あり~明治13年最後の仇討」が放映されました。
このドラマの原作は吉村昭「敵討」(新潮文庫)で、日本の最後の仇討といわれ、秋月藩(黒田長政が開いた黒田藩の分家で5万石、初代は黒田長興、場所は福岡県朝倉市秋月)で実際に起こった事件です。このテレビを観た人から以下の質問がありました。
「主役は臼井六郎ですが、山岡鉄舟が準主役のように扱われています。このドラマを観て仇討というのも武士道の美徳だったなと思いました。いまどき仇討など流行りませんが、日本人の仇討感覚が『死刑』を肯定しているように思いますが、武士道との関係について解説願います」と。
今月16日の山岡鉄舟研究会で「遺恨あり」を取り上げ、武士道と関連つけて考察いたしますが、日本人は「武士道」を正しく妥当に把握しておくことが重要と思います。以上。
2011年02月19日
情報の区分けが必要
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年2月20日 情報の区分けが必要
ダボス会議
伊藤忠商事社長の小林栄三社長が、スイスのダボスで開催された世界経済フォーラムの年次総会、通商「ダボス会議」に参加した感想を、日経新聞(2011年2月14日)の「明日への話題」に掲載しました。内容は会議で日本の話題が出たのはたった二つ、ひとつは日本国債の格付けが下がった話、ふたつ目は中国のGDPが世界第二位になったが、一人当たりGDPは日本の10分の1程度だから、まだまだ中国は成長するという話から、日本の存在感はこれほどまでに薄いのかと非常に残念で寂しい気持ちになった。というものです。
ハワイとサンフランシスコから
元プロ野球巨人の選手で、西武と横浜の監督を歴任した森祇晶氏、現在はハワイに在住ですが、以下のコメントをある企業発行の小冊子に掲載しています。「ハワイのニュースは、日本のことより中国や韓国の話題が多くなったように思う。お家芸の家電が日本へ輸入されるようになったことは心配だ。日本という国が縮小しているように感じる」と。
また、先日のサンフランシスコで車を運転してくれた日本人ドライバーが、次のように発言しました。「日本の位置づけが下がっている。外国にいる日本人は、母国が元気でないと元気がでない」と。
サンフランシスコの日本食店
ところが、経済を離れた分野、特に食文化の面では全く異なる現象です。
サンフランシスコの人気レストラン、料理は洋食系ですが、メニューには「シソ、ユズ、ユズコショウ、ユバ、ウメボシ」とあってビックリしました。
テンプラ、ワギュウ、コウベビーフ、クロブタ、ダシ、ウマミ、コンブなども珍しくなくなってきつつあり、ラーメンやイザカヤも当然のごとく人気ですし、寿司はブームを通り越して、すっかり日常生活の中に定着化しています。週末のパーティに日本人家族が呼ばれるのは、持参してくるであろう「ノリ巻き寿司」が目当てだと現地在住日本人女性が語ります。
牡蠣も前号でお伝えしたクマモトオイスターが一番人気で、一番価格が高いのです。さらに、マガキのパシフイックオイスターで「SHIGOK」というブランド牡蠣を見つけました。販売生産者に意味を問うと「それは日本語ネーミングで、とても素晴らしいという意味だ」というので、辞書を見ますと「至極」という「最上・極上」という意味だとわかりました。何でも日本語にすれば売れると思っているようにも感じましたが、これは一月に訪れた台湾でも同じ傾向で、日本語ネーミング商品が店頭に溢れていました。
日本語を学ぶ子供達
昨年11月、パリのアシェット・フィリパッキ・メディア (Hachette Filipacchi Médias、略称アシェット社HFM)を訪問しました。ここはフランスに本社をもつ世界最大の雑誌出版社で、いまや日本の老舗出版社である婦人画報社を傘下に収め、「婦人画報」をはじめ「25ans」や「ELLE Japon」などの雑誌を発行しています。
ここで旅行出版部門の責任者と、日本の温泉ガイドブック出版の打ち合わせをしたことと、責任者と編集長二人の子供が日本語を学んでいて、子供を連れて家族全員で今年春に日本へ旅行するということは、1月5日号でお伝え済みです。
その後ドイツのカールスルーエ市でも化粧品店オーナーにお会いすると、同様に日本語を子供が学んでいるという発言でした。
これらの事実から推察できるのは、今は海外で空前の日本文化ブームというより、日本人気は世界に定着しているのが時流ではないかということです。
評価高い日本のソフトパワー
自国の生産物をブランド化し、付加価値を高く維持し、それを外国に認めさせることを得意としているフランス、そのフランス見本市協会日本代表のジャン・バルテルミー氏が次のように語っています。(日経新聞2011年2月14日)
「今日ヨーロッパでは、日本のファッションクリエーターやキャラクター名と『みそ』や『ワサビ』までもが幅広い世代に知られている。現代日本の建築家やアーティストの国際的評価はとみに高まっている。国内が萎縮しても、日本ブランドは海外のさまざまな分野で力を発揮しているように思う。
在日フランス大使館の2011年のニューイャーカードのビジュアルは、フランスでも高く評価されている漫画『神の雫(しずく)』。これはまさに、日本の現代文化へのオマージュではないだろうか?」と。
最後のオマージュとは、フランス語でHommage「尊敬、敬意、称賛」という意味になりますから、日本文化を褒め称えていることになります。
神の雫
神の雫は、原作:亜樹直、作画:オキモト・シュウによる日本の漫画作品、2004年に「モーニング」(講談社)で連載を開始し、2011年2月現在、単行本は27巻まで刊行されています。ワインの本場であるフランスでも「フランス人にとっても知らなかった知識が出てくるマンガ」だと絶賛され、2009年7月に料理本のアカデミー賞と言われるグルマン世界料理本大賞の最高位の賞である"殿堂"をパリで受賞しました。
この神の雫に登場する女性と昨年のパリ農業祭で出会いました。ワインブースで偶然立ち寄ったところの女性が、自分はマンガ「神の雫」に登場していると発言したのです。最初は英語で「God Shizuku」と発音したので、よくわからずしばらく考えて、そうか神の雫か思い、本当に掲載されているのかと不審気に尋ねると、翌日、自分が登場しているページをメールしてきました。左がマンガ画面、右がモデル女性です。


何となく似ているでしょう。このワインは、エリゼ宮の晩さん会で使われたワインだと自慢していましたが、今年もパリの農業祭に参加しますので、彼女と出会うことになると思います。因みに神の雫はパリの書店で大量に平積みされています。
情報の区分けが必要
日本という国が縮小している。日本の位置づけが下がっていっている。といような見解は最近よく聞きますが、その内容を分析すれば全て経済分野です。日本が高度成長した時期、人間でいえば伸び盛りの中高校生でしたが、今は成熟した中高年齢期に入っています。
一方、当時は無視されていた中国や韓国、今は経済躍進著しい中高校生期なのですから、経済状況変化は激しく、その変化が世界に与える影響は大きいので、マスコミが競って報道するのです。人間社会は経済中心ですから当然の事です。
だが、人間生活は一人ひとりの生き方が基本で、生きるための基本要件として安全・安心・教養・食品・環境・長寿というような分野での熟成度が求められます。
実は、この分野で日本は世界で断トツなのです。長い歴史と伝統で培われた文化が、ソフトパワーとして多くの国から迎えられ、私が出会う各国の人々は、その事実を語るのですが、その事はマスコミには出ません。
何故なら、マスコミとは変わったこと、珍しいことを報道するのが商売なのです。ところが、人々の生活・生き方に根ざしている日本の影響については、ジワーと入っていくものであり、急激な変化でなく、数字で判定できるものではないので、マスコミ材料としては不適切ですので、あまり伝える事に熱心ではないのです。
ですから、情報の受け手である我々が、マスコミの立場を知った上で、情報の区分けをして受けとめるべきなのです。これがソーシャル・メディア時代の情報処理の基本です。以上。
2011年02月07日
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年2月5日 三国一の花嫁
三国一の花嫁とは
広辞苑を引きますと、三国一とは室町時代の流行語で、日本、唐土(中国)、天竺(インド)にわたって第一であることとあり、多くは嫁入りや婿取りの場合に祝辞として用いたとあります。つまり、三国一の花嫁とは「世界一の花嫁」という意味になり、これを先日のアメリカ・シアトルで体験し、日本について考えさせられました。
シアトルの山下英一さん
昨年9月に出版した「世界の牡蠣事情」のシアトル編で、訪問したオイスターバーのシェフから「日本の牡蠣を最初に持ってきたヤマシロさんを知っているか」と聞かれ「知らない」と答えたヤマシロさんが、その後、ひょんなきっかけでシアトル在住の「山下英一さん」と判明しましたので、先月にお詫びかたがたご自宅を訪問いたしました。
シアトル市内の静かな住宅地の角のお宅、ドアをノックすると笑顔の山下英一さんが現れました。1923年生まれですから現在88歳。驚くほどに明瞭な発音で日本語を話します。奥様も小学校でピアノを弾くボランティアをしていて、同様に明確な日本語です。
シアトルに日本の牡蠣を持ってきた最初の人物は「世界の牡蠣王」と呼ばれた宮城新昌氏(1884-1967)で、山下さんの父上が宮城新昌氏から学び養殖業を始め、英一さんが後を継いでいたのですが、第二次世界大戦で日本人は強制収容所に入れられ、養殖業は中断するなどのご苦労話をお伺いしました。
オイスターバー
山下家でいろいろお話をお伺いした後、山下ご夫妻とオイスターバーに出かけました。82歳の奥様が運転されるのには驚きましたが、英一さんも毎日牡蠣養殖場に車で行くという現役にもまたビックリです。
オイスターバーに入りますと、シェフが飛んできます。山下夫妻はシアトルでは有名人なのです。勿論、牡蠣一筋の業界人として知られているのですが、それよりもご夫妻の人間性です。人柄が慕われていることが分かり、日本人として山下ご夫妻を誇らしく感じました。このオイスターバーで食べた牡蠣は、勿論、山下さんの牡蠣で、地元のワシントン州のドライな白ワインとのミックスに満足いたしました。
クマモトオイスターが一番人気
ところでオイスターバーでも、シアトル市民や観光客が訪ねるパイク・プレイス・マーケットでも多くの新鮮な牡蠣が並んでいます。
牡蠣は日本のマガキが主流で、アメリカではマガキをパシフイックオイスターと呼称し、養殖している海域ごとにブランド名をつけて販売しています。しかし、もう一つ「クマモトオイスター」という小ぶりの牡蠣があり、これは勿論、日本の熊本生まれ牡蠣で、この方がパシフイックより二倍近い価格で売られているように、アメリカでは一番人気です。
写真はパイク・プレイス・マーケットのクマモトオイスターです。

地元の新聞が報じたクマモトオイスターのすごい人気
クマモトオイスターの人気が素晴らしい事を、サンフランシスコの新聞クロニクル紙が報じました。(2002.4.28)
「サンフランシスコにおける生牡蠣は、どこでもクマモトはトップセラーである。このクモ(クマモトの愛称)現象はベイエリアだけに限られない。ロサンゼルスからシアトルにわたる全西海岸のオイスターバーでクモの人気は沸騰している。カリフォルニア、オレゴン、ワシントンの養殖場から仕入れられたクマモトは、シカゴのショウズ・クラブハウスでは週に800個、マンハッタンのグランドセントラルにあるオイスターバーでは日毎に数百個も売れている。更に、アジアやヨーロッパまで輸出されている」
この実態は年々高まっていまして、クモは今や人気トップの牡蠣ブランドになりました。
クマモトオイスターの養殖場
クマモトオイスターの養殖場現場に行くため、アメリカで牡蠣販売最大手のテイラー社に向かいました。ここで社長からクマモトオイスターと合うワインのコンテストを毎年開き、今年も開催する、というようにクマモト人気ぶりを確認し、いよいよクマモトオイスターの養殖場に向かいました。養殖方法は日本と違い、海底に地撒きするスタイルですので、海の干潮時でないと実態が分からないので、潮の引く夕方、もう少し暗くなりかけたタイミングに海に行ったのですが、案内役はワシントン大学のジョス・デービス準教授で、テイラー社の指導も行っている、熊本県の海まで調査に行った人物です。
クマモトオイスターの養殖場は素晴らしい景観でした。正に牡蠣養殖場として絶好の自然条件です。湾奥深く位置し、三方を森に囲まれ、一方から外海につながり、かつてはインデイアンの漁獲場だったところで、熊本から嫁入りする場所としては最高のロケーションであり、とても大事に扱われている実態に感激しました。その夕陽の情景写真です。
ところで日本の熊本ではどういう状況か
このようにアメリカ中で人気沸騰のクマモトオイスター、実際の生まれ故郷である熊本ではどういう状況なのでしょうか。前述のワシントン大学のジョス・デービス準教授が
1997年に熊本の海を訪ねていまして、彼の感想は「熊本の現実はとても悲しい」と歎きの一言で、熊本の海で撮影した写真をこちらに渡してくれました。
左が岸壁に蔓延っているクマモト牡蠣で、右は彼が岸壁から採取しているところです。
アメリカでは三国一、日本では無視
日本は観光大国を目指し、2008年10月に観光庁が発足、2010年6月経済産業省に「クール・ジャパン室」を設置、日本の戦略産業分野である文化産業の海外進出促進、国内外への発信や人材育成等に強化をしています。その成果か、昨年の訪日外国人数は過去最高の861万人となりましたが、日本の多様な魅力を考えると、もっと多くの外国人が訪れる国にすべきでしょう。それへの対策として温泉ガイドブックの世界50カ国書店への配架プランを、既に観光庁に提出しています。
しかし、今回、アメリカで熊本生まれの牡蠣が「三国一の花嫁」として、大事に受け入れられ、アメリカ一の人気ブランドになっている実態を再確認した反面、生まれ故郷の熊本では誰も見向きせず、養殖する人もいなく、市場に出回らず、日本人は一切食べないという無視された姿、この日米格差をどうのように理解したらよいのか。理由はいろいろありますが、日本人は自国の財産を知ろうとしていないのではと思わざるを得ません。以上。
2011年01月21日
日本経済に対するスタンスを定める
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年1月20日 日本経済に対するスタンスを定める
2011年の日本経済見込み
1月ですから日本経済を考えてみます。まず、新春3日の日経新聞に掲載されたエコノミスト15人による実質経済成長率平均は、2010年度が3.3%、2011年は
1.2%となっています。次に世界銀行が1月12日に発表した世界の実質経済成長率見込みでは以下のように、2010年度は日本の方がアメリカよりかなり高めとみています。
2010年 2011年
世界 3.9% 3.3%
日本 4.4% 1.8%
米国 2.8% 3.3%
中国 10.0% 8.7%
昨年10月時点での日本経済見込みは足踏み状態だった
昨年10月の日本政府月例経済報告内容では、次の景気判断をしていました。
「日本経済は、リーマン・ショックから立ち直り、2009年4月から回復を続けていたが、その歩みがいったん止まった『足踏み状態』である」と。
では、その足踏み状態はいつまで続くのか。エコノミスト15人による予測では以下の通りとなっています。
10月が底と予測する
上のグラフから見ると、全員が今年に入ってから踊り場脱却と見ています。しかし、鉱工業生産指数推移から判断しますと、既に昨年10月が底であったと思われます。
鉱工業生産指数とは、鉱業または製造業に属する企業の生産活動状況を示すもので、一般に鉱工業の国内総生産に占める割合が高く、経済全体に及ぼす影響も大きいことから、経済分析上重要な指標となっています。この鉱工業生産指数2005年度を100として推移を見ますと、09年6月が前月比△1.1%、7月△0.2%、8月△0.5%、
9月△1.6%、10月△1.9%と連続してマイナス基調でした。ところが、11月の鉱工業生産指数は一転して+0.9%と上昇し、12月見込みでもプラス、その後もプラスが続くと見込みますから、昨年10月が底であったと判断した次第です。
プラスとなった背景
この鉱工業生産指数がプラスとなる要因は、すそ野の広い経済全体に影響力の強い、自動車産業の今後の見込みからの判断です。自動車生産計画が11月+5.4%から始まって毎月プラスの生産となっているからです。(出典:自動車産業ニュース)
また、このプラス要因を探ってみれば、それは中国の自動車販売台数が09年7月を底として急速に改善増加に変化していることが挙げられます。
さらに、日本の昨年10月輸出実績構成比を見ますと、アメリカ向けが15.5%ですが、中国・香港は25.9%となっているように、中国への輸出がアメリカをはるかに超えているのが実態ですから、中国の動向如何が日本経済を左右しているのです。
2011年の経済見込みを検討して実務的に意味があるのか
ところで、以上のように日本経済の2011年予測をして、何か実務的に意味があるのか。つまり、単年度の経済予測を根拠に物事を判断し、行動してよいのかという素朴な問いかけを皆さんにしてみたいのです。という意味背景は、従来の日本経済体質と現在では、明らかに大きく異なっているからです。
思い出してみれば、80年代、90年代前半、諸外国から指摘されたことに「日本は内需主導経済に切り替え、輸出頼みの経済を修正すべきだ」という見解が多くなされました。
しかし、今では諸外国からこのような指摘はなされないし、政府・日銀の景気回復シナリオでも、先ず輸出の伸びだということになっていて、周りの国々をみても、輸出で経済かさ上げというのが各国の潮流となっています。いつの間にか、輸出に頼るのはよくないという議論でなく、輸出に頼らないかぎり立ちいかなくなるという状況に、日本を含む世界中が変わっているのです。特に日本の場合は、内需主導型経済成長は実現不可能ということを、内外当局者が暗黙の了解事項としていると思います。また、この了解実態への分岐点は、今から約15年前の平成7年・1995年であったと思います。
今後の日本経済をどう考えるか
日本の生産年齢人口(15歳から64歳)の過去最高記録は、95年の8718万人でした。だが、それから減り始め、平成20年・08年は8230万人となって、マイナス488万人減となって、これからも減っていきます。
この結果は名目GDPの推移に現れています。95年が495兆円で、人口が減り始めても、その年に直ちに減少せず、97年515兆円と増加しましたが、99年には497兆円と減り、09年は474兆円となって97年対比実額で41兆円減少しています。
要するに、人口減から需要が膨らまない一方、供給サイドは規制緩和もあり、数が増え、淘汰されずに温存されていくので、需要と供給のバランスが悪くなり、価格に下落圧力が加わってデフレ基調が定着し、既にビール、牛乳、ファミリーレストラン、書籍雑誌の販売額が減ってきており、今後は食べ物や衣類の需要に影響していくように、長期トレンドとして人口を基本に日本経済を考えれば、国内要因でのGDPは増えないと考えます。
経済成長率を上げるのは、他国状況で変わる輸出だけが増加要因ですから、日本国内の経済成長率を一年や二年を区切ってどうこうだと分析しても、あまり意味を持たないのではないかと思うのです。
そこで、その年に予測された日本経済成長率が、どのような数値であろうとも国内は今まで同様「程々・ぼつぼつ」だと受け止め、あまり大騒ぎしない方がよいと思っています。
自分のスタンスを明確にすること
それより、今の日本経済に対する立場を、一人ひとりが明確にした方がよいのではないかと思います。その立場を整理すれば次の二つでしょう。
A.今の日本経済でよいと考える立場⇒失業率は5%と安定、平均寿命は世界最高水準、犯罪率や殺人率も低く、所得不平等は国際的に見て低い等、諸外国に比べて見れば優れているのですから、今のままでよい。
B.そうではなく、あくまで日本経済を成長させるべきだという立場⇒この場合は①人口減に歯止めをかける、②輸出を増やす、③国内企業の工夫によって需要を増やす、の三方向となり、このどこに皆さんが位置するかで「戦略・戦術」展開が異なります。
Bの対策方向性
① 人口減に歯止めをかける⇒直ぐに可能なのは移民を増やすことですが、これは日本人自身に内在する意識問題が最大のネックで実現困難です。少子化対策と観光客増加が有効策で、この方向性に向かうしか戦術はないでしょう。
② 輸出を増やす⇒今は世界中で輸出競争している時代。今までは企業の海外輸出比率は50%超が目標数値といわれていましたが、キャノン、コマツのような優良企業を見ると80%という体質で、ターゲット地域を新興国にする事がポイントです。
③ 国内企業の工夫によって需要を増やす⇒人口減ではかなり難しい分野です。その難しいという前提の上での検討です。需要を増やすためにはどの方向性・分野を狙うかという「戦略」の策定と、その戦略に基づく「戦術」展開です。つまり、他人が行っていないアイデイァ・工夫という創造性が必要条件で、時代とのマッチングも大事ですが、その際の採算性は重要チェックポイントです。次に、仮にその新しさが成功したとしても、すぐに模倣され新しさがなくなりますから、次なる創造性を発揮するというあくなき創造性の継続を、あきらめずに繰り返し、繰り返し行動するという、執拗な努力が絶対に必要でしょう。
年初め初心に戻り、日本経済へのスタンスを自ら決める必要があると思います。以上。
2011年01月06日
日本を情報編集して再発信する
環境×文化×経済 山本紀久雄
2011年1月5日 日本を情報編集して再発信する
新年明けましておめでとうございます。本年もご愛読の程お願い申し上げます。
観光庁への提案
昨年9月20日号のYAMAMOTOレターで、世界の書店に配本ルートを持っている欧米の出版社から「日本の温泉ガイドブック」を刊行するための企画書をもって、近く観光庁に提案に行く予定ですとお伝えしました。この件は昨年12月末に霞が関の観光庁に出向き「世界50カ国の書店に配架する」計画書を提案して参りました。その際、観光庁の担当官と日本文化の捉え方について議論しました。計画の実施是非回答は後日になります。
アシェット社訪問
昨年11月、アシェット・フィリパッキ・メディア (Hachette Filipacchi Médias、略称アシェット社HFM)を訪問しました。ここはフランスに本社をもつ世界最大の雑誌出版社で、いまや日本の老舗出版社である婦人画報社を傘下に収め、「婦人画報」をはじめ「25ans」や「ELLE Japon」などの雑誌を発行しています。
パリの本社は元日航ホテルの隣ビルですが、ここで旅行出版部門の責任者と、アシェット社が世界50カ国で展開している旅行ガイドブック、ブルーガイドですが、この編集長と日本の温泉ガイドブック出版について打ち合わせしました。
私が説明する趣旨、話し終わるとよくわかると大きくうなずきます。これにビックリしました。世界的な大出版社が前向きに好意的に了解したのです。
その理由をいろいろ話し合っているうちに分かってきました。フランスでは空前の日本文化ブームであり、これは世界共通になりつつあると認識していることです。日本文化が世界の時流なのです。
さらに、旅行出版部門の責任者と編集長の二人の女史とも、子供が日本語を学んでいるといい、子供を連れて家族全員で今年春に日本へ旅行するというのです。
もう一つの国際標準化
今まで日本が展開してきた「国際化」とは、外国で国際標準になっているものをとりいれるか、外国に勝る技術を開発し、それを国際標準化しようとするものでした。これに対し「グローバル化」とは国際標準化レベルに、相手国の市場実態を加えることであると、サムスンの事例をもって昨年末レターでご案内しました。
しかし、もう一つ国際標準化という意味で、考えられることがあります。それは昨年9月来日し、一緒に「日本のONSENを世界のブランドへ」シンポジウムを開催した、リオネル・クローゾン氏発言の「温泉街には欧米にない異文化がある」という発言です。
この発言の意図は重要です。今までの温泉業界は、外国人に「合わせる」ことを考え、外国人に「すり寄っていく」という考え方が多かったのです。
しかし、クローゾン氏の発言は、この考え方を真っ向から批判しているのです。今のままでよい、そのままの温泉が魅力だという主張です。
日本人は戦後65年間、アメリカから様々な価値観を押し付けられたと感じている人が圧倒的に多いと思います。しかし、アメリカ人から見ると、確かに押し付けてはきたが、そういうことになったのは日本人にも大いに問題がある。日本人は「自分らが何ものであるか」について、隠しているのではないか、それとも現代の日本人は他者に知らせるべき自己を持たないのではないか、という指摘をされているのです。(「日本人と武士道」スティーブン・ナッシュ著)
この指摘の背景には、クローゾン氏の発言との同質性があります。自国の文化や社会や歴史を正しく語ろうとしないのが日本人だ、という本質的な指摘であり、逆に考えれば外国人は「日本は素晴らしい魅力がたくさんある国だ」という認識を持っていることになります。
問題は、この事実を受けとめ「世界に向けて情報化」編集する能力を発揮していない日本側にある、と考えるべきと思います。
子供が日本語を学ぶという意味背景
その日本に魅力があるという事実を、アシェット社の幹部二人の子供が、日本語を学んでいるということから理解できます。
欧米の子供たちは、日本のマンガを翻訳された言語で読むうちに、我々が気づかないところ、そこに日本の魅力を直感的に感じ、それを知るためには今の日本からの情報発信では不十分だから、直接に日本に行き日本語で尋ね知りたい、という欲望があるからと思います。
つまり、日本には、欧米とまったく異なるものがある故だと思わざるを得ませんが、この事実を日本人は分かっていないと、これまた思わざるを得ません。
坂の上の雲
NHKで放映されている「坂の上の雲」、制作の西村与志木プロデューサーが、ホームページで次のように語っています。
「司馬遼太郎氏の代表作ともいえる長編小説『坂の上の雲』が、完結したのは1972(昭和47)年とのことです。それ以来、あまたの映画やテレビの映像化の話が司馬さんのもとに持ち込まれました。無論、NHKのドラマの先輩たちもその一人でありました。しかし、司馬さんはこの作品だけは映像化を許さなかった、というように聞いています。
『坂の上の雲』が世に出てから40年近い歳月が流れました。そして、今でもこの作品の輝きは変わっていません。いや、むしろ現代の状況がもっとこの作品をしっかり読み解くことを要求しているのではないでしょうか」と、今が絶妙のタイミングだと自負しています。
司馬遼太郎の作品は翻訳できない
「日本辺境論」(内田樹著)に「日本を代表する国民作家である司馬遼太郎の作品の中で現在外国語で読めるものは三点しかありません。『最後の将軍』と『韃靼疾風録』と『空海の風景』。『竜馬もゆく』も『坂の上の雲』も『燃えよ剣』も外国語では読めないのです。
驚くべきことに、この国民文学を訳そうと思う外国の文学者がいないのです。いるのかも知れませんが、それを引き受ける出版社がない。市場の要請がない」と述べ、続いて「あまりに特殊な語法で語られているせいで、それを明晰判明な外国語に移すことが困難なのでしょう」とありますから、日本で最も有名な国民作家が、外国では全く無名というのが事実でしょう。
さらに、渡辺京二(選択2011.11)は、司馬小説は「小説としての『スカスカ』度は増していき、『坂の上の雲』に至っては『講釈が前面に出て小説はどこか行方知らずになってしまった』と断じ『司馬という作家から小説の提供を欲するもので、歴史に関する講釈を聞きたいのではない』とも論断しています。
今まで司馬遼太郎批判は、出版界でタブーでしたが、グローバル化という視点から検討すると、様々な解釈がなされ始めているのです。
村上春樹は国民文学でなく世界文学
村上春樹の「ノルウェイの森」が映画化されました。早速に満員の映画館で観ました。配役は全員日本人で、日本語ですが、監督はトラン・アン・ユンというベトナム系フランス人で、脚本も彼が担当しています。
村上春樹という人物は、東京の街中を歩いていても、殆ど誰にも気づかれない存在だと、自分で語っているように地味な風采らしいのですが、村上小説の物語は世界中から受け入れられていて、今や最も世界で読まれている日本人作家であり、数年前からノーベル賞有力候補者といわれています。
村上本人も、日本のマスコミを避けている節が強く、日本のマスコミには殆ど登場しないのですが、時折、外国でインタビューされた内容が雑誌に出ます。昨年の8月は、ノルウェイのオスロで村上作品を紹介する「ムラカミ・フエスティバル」に出席した際の講演会入場券が、わずか12分で完売となったこと、これは他の文学イベントでは想像できない勢いだとノルウェイ最大の新聞「アフテンボステン」がインタビュー記事とともに報道しました。
村上小説には、日本人のみが登場し、日本のみが舞台なのに、今や日本の国民文学ではなく、世界文学になっているのです。つまり、村上は「世界に向けて情報化」編集を行った結果、国際標準化レベルを創り上げ、それに基づいて物語を書いているのです。
日本を情報編集して再発信する
観光庁の担当官に伝えたことは、日本の温泉を村上春樹流に編集し発信すべきということでした。
現在、平成の開国が必要だと考えている日本人が多いのが事実ですが、一方、外国人から見た日本は魅力に溢れているにもかかわらず、それを外国に向けて発信していないという指摘があるのですから、情報面での開国は滞っています。村上春樹から学ぶべきでしょう。以上。
2010年12月20日
国際化とグローバル化(後)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年12月20日 国際化とグローバル化(後)
舛添要一氏の発言
12月16日に新党改革代表の舛添要一氏の講演を聞きました。東京大学卒業後ヨーロッパに留学、パリ大学現代国際関係史研究所やジュネーブ高等国際政治研究所の客員研究員などを経ています。なかなか鋭い内容でした。私が印象に残ったのは次の二つです。
一つは、厚生労働大臣時代に、後任の長妻昭前大臣が細かい、さしたる重要性のない議員質問を連発し、そのために国会に足止めされ、海外からの諸会議出席要請を殆ど断らなければならなかった事。これは大臣が海外出張出来ないシステムで問題だと思いました。
もう一つは、日本の家電メーカーが、サムスンに「束になってかかっても敵わない」実態に陥っているという事実認識でした。政治家もサムスンについてよく承知しているのです。
ドイツ・カールスルーエにて
11月末のドイツ・カールスルーエの街は雪で、マルクト広場のクリスマス・マーケットも白く、市電も寒そうでした。その様子が新聞に出ましたので写真を紹介します。
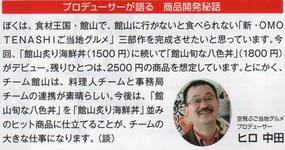
写真の市電は街中を縦横に通っていて、タクシーが必要ないほど便利で、宿泊したホテルからは滞在中の期間、無料カードが提供されます。ということは東京のようなSuicaスイカシステムではないということです。
この街に先日JR東日本が訪れSuicaの説明会を開き、そこに出席していたカールスルーエの関係者から、説明会場全体の雰囲気が「よくわからなかった」という状況だったと伺いました。市電カードで慣れている地元の人々には、見たことがなく、初めて聞く先端システムのSuicaは理解できなかったのです。これを聞き、改めて、日本の問題点を痛感しました。
バーデン・バーデンにて
ドイツでは雪の中バーデン・バーデンにも参りました。バーデン・バーデンとは温泉を意味するバ-デンという名を二つ持つ「温泉の中の温泉」であり、世界でもっとも有名な温泉地であると共に、今や「温泉と観光・文化とコンベンションの街」という総合観光都市に発展している人口5万人の街です。
2009年3月には、アメリカのオバマ大統領が、ここでメルケル独首相と会合し、マルクト広場から市役所、オ-ス川を渡りカジノ前まで散策したように、ここは「ドイツが誇る美しい街」として評価されています。そこで、この街を取材するため、小高い丘の中腹の元は城と思われる観光組合を訪れ、組合長の女性から説明を受けました。彼女のオフィスは、二方向に窓が大きく開かれ、バーデン・バーデンの街並みが見渡せ、その窓を背景に大きいコの字方デスクを配した、大きくて素晴らしい環境でしたが、最も感じ入ったのは彼女から発する「この街が本当に好きで愛している」という情熱説明でした。
その説明で、この街の魅力を十分に理解したと考えましたが、把握した内容が、彼女の情熱説明と合致しているだろうか、受けとめ方にズレがないだろうか、その点を確認しようと、こちらの認識内容を伝えました。
「バーデン・バーデンの温泉を健康と理解し、観光・文化を歴史文化と理解し、コンベンションを経済とすると、この三要素のバランスがとれている街で、そこを貫くコンセプトは『エレガンス』でないか。つまり『エレガントなバランス』がこの街のコンセプトだ」と。
彼女が大きく頷きました。これで双方理解が一致したので原稿を書き終えたところです。
日経新聞社の企業総合評価
12月9日の日経新聞一面は「企業総合評価NICES」の報道でした。一位キャノン、二位ホンダ、三位武田薬品で、企業評価上位の常連であった三菱商事は19位、トヨタ自動車は25位、日産自動車は27位、銀行の順位は探すのに苦労するほどの位置づけです。
解説に「過去半世紀の米国を引っ張った『株主価値の最大化』は曲がり角にある。近視眼的な株高経営を反省し、ジョンソン・エンド・ジョンソンやプロクター・アンド・ギャンブルの安定経営を再評価するのが、今の米国だ」とあり、「顧客は何を求めているか常に真摯に考え、自らの社会的意義を問う組織が持続的に安定した利益を上げられる」と述べています。
これを読み、ようやく日経新聞も「世界から日本を見る」という立場になったなと理解しました。というのは、今までは利益額とか規模とか投資額で企業を評価していたのが「顧客が何を求めているか」を重要な評価基準とし、その「顧客」という存在を「世界の顧客」と受けとめ、積極的に活動しているグローバル化企業が上位になっていたからです。
サムスンの改革
実は、サムスンが日本企業に先駆けて、いち早く改革したのは、この「世界の顧客が何を求めているか」であり、その顧客の主力を経済成長躍進著しい「新興国」においたことです。
サムスンが本当に改革しようと覚悟したのは、1997年7月のタイから始まった「IMF危機」でした。IMF(国際通貨基金)の支援を受けなければならないほどのショックが韓国経済に走ったのです。GDPは四割減になり、IMFからは「お金を借りたいなら生活を切り詰めろ」という国家として屈辱的な指示を受けざるを得ない状況で、給料は三割、四割カットが当たり前でした。
この「IMF危機」を契機としてサムスンは考え抜きました。技術力では日本企業に敵わない。しかし、日本に対抗し、追い抜くには、技術力ではない、別の何かがあるはずだと。
自らの弱点を克服する方法として、相手の強みである日本の技術力に対抗するのではなく、日本企業が手抜かりしている方向に目を向けたのです。ここがサムスンの逞しいところです。
それは「技術の使い方」の工夫です。技術があっても、その技術が「顧客の求めるレベルと異なっている」場合は、その技術力は効果が発揮しません。そこで採用した戦略は「顧客が求める技術に変換して提供する」ということ、つまり、新興国のレベルに対応した技術力の製品づくりに特化したのです。ということは、日本の技術力から、新興国の生活水準では進み過ぎている先端技術をふるい落とし、削り、カットして行くということになります。
具体的にいえば、あまりに優れている日本製品を解体し、分析し、該当新興国にとって不必要な技術部分を取りはずし、その国の顧客にふさわしい商品につくり直し、それを投入していくという戦略を採用しました。うまくて、ずるい方法です。
ただし、この戦略を成功させるために必要不可欠条件は、ターゲットになる国の情報について、そこに住
む人と同じか、それ以上に精通しなければいけません。
そこでサムスンは、「地域専門家」の育成に全力を注ぎました。情報収集のスペシャリスト人材の育成です。その人材によって、その国と地域の情報を徹底的に集め分析し、それに合わせた技術力に修正し、その国の「顧客が何を求めているか」に対応した商品づくりを実行したのです。孫子兵法の「敵を知り、己を知れば、百戦危うからず」の実践です。
考えて見れば当たり前のことで、サムスンの成功はセオリー通りに展開した結果です。
日本が対応すべきこと
優れた技術力を持つ日本企業が「束になってかかっても敵わない」という舛添発言の背景は簡単でした。だがカールスルーエのSuicaの事例はこの対応が未だしという証明です。
全ての物事は相手との対応力で成否が決まります。そこで相手が「何を求めているか」を常に問う姿勢と実践が重要です。今迄の日本の国際化とは、外国に勝る技術力を開発する事に特化していました。
グローバル化とは、この国際化レベルに、相手国の顧客視点を加えることだというサムスンからの教示、これは企業と個人にも該当する成功セオリーです。以上。
2010年12月05日
2010年12月5日 国際化とグローバル化(前)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年12月5日 国際化とグローバル化(前)
パリのデザイン企業
パリの6区、このエリアはサン・ジェルマン・デプレ教会があって、セーヌ川にも面している地域。その一角の細い迷路みたいな路地を通って、ひとつの古びた石造り建物の前に立ち、重いドアを開けて中に入ると、そこは中庭で意外に明るいスペースが広がっていました。
中庭に面した通路の突き当たりのドアを開けると、まだ若いフランス人男女が日本式と思えるぎこちないお辞儀をします。握手の前に頭を下げるのを見て、これは日本に関心高いなと思いました。
会議室に入ると、テーブルが部屋の角から対角線に置かれています。日本はどこに行っても壁と直角に、スクウェア四角直線的な配置でテーブルが並べられていますが、フランスはどこでも斜めスタイルで、ここに国民性と文化性が現れています。
企業変革した結果
社長が挨拶しながら出てきて、気負いなく静かに自社の状況を語り出しました。
「印刷業から15年前にIT企業に変革させ、インド企業を買収し、そのインド企業が日本の大都市からITシステムを受注したので、来春日本に行く」と。
ほおーと思い、どういうシステムですかと質問すると、自分でパソコンを開いて「例えばエクセルだが、今まではインプットと図表作成が時間差作業だった。今回のシステムは同時に同じ画面に配置できるので、スピードと見る側へ働きかける感度が全く違う。これを様々な分野で活用できると、日本の大都市が目をつけたのだ」と語ります。
そこで現在、私が課題にしていることを伝えると、すぐに次回パリに来るまでに作業しておいて提案すると言います。今までのフランス型商売は、必ずお金を受け取ってから作業に入るのが常でしたから、これには驚きました。無料で提案するというのです。
さすがに時流をつかんでいるベンチャー企業は違う、ということを現場で認識し、フランスでも時代が企業をドンドン変えていくということを感じました。
サムスン電子
シャルル・ド・ゴール空港からパリに車で入るには、必ず環状高速道路を通過して市内に入りますが、その環状高速道路に入るポイントのビル屋上には、昔から企業名の電飾看板があります。
つい、10年前までは日本企業名が電飾看板として目立っていました。ところが、今はサムスンです。少し離れたビルにはLGです。また、世界中の国際空港で見るテレビもかつては日本製でしたが、現在はサムスン製に代わっています。
サムスンは今や韓国GDPの15%も占める規模にまで成長したのですが、どうしてこのような状況までに躍進したのでしょうか。それを今号と次号で検討してみます。
どうして日本企業を追い抜いたか
サムスンの経営実態については「危機の経営」(畑村陽太郎+吉川良三著 講談社)に詳しいのですが、先日、吉川良三氏のお話を聞く機会があり、改めて同書を読んで感じたことをご紹介したいと思います。詳しくは同書を参考に願います。
ご存知のように、かつての韓国企業は日本の技術を導入するだけの製品づくりで、世界の市場では常に日本の後塵を拝していました。
この状態から脱皮したい、サムスンの経営を改善させたいと、会長の李健熙イゴンヒ氏が「妻と子以外はみんな変えなくてはいけないと思っている」という強靭な想いから改革を進めました。
まず、最初に打った手は
李健熙会長がはじめた方法は当たり前とも思えることからでした。
まず、グループの幹部を引き連れてドイツ、日本、アメリカなどの先進国を訪れ、グループの事業や他企業の様子を視察しながら、サムスンをどのように変えるべきかの話し合いを、その現地で行ったことです。
これは明治維新の際、日本が採用した伝統的な手段です。明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年)9月13日まで、日本からアメリカ合衆国、ヨーロッパ諸国に派遣された、岩倉具視を正使とし、政府のトップや留学生を含む総勢107名で構成された使節団のことです。
政府のトップが長期間政府を離れ外国を訪れるというのは異例でしたが、肌で西洋文明や思想に触れたという経験が、彼らに与えた影響は大きく評価され、留学生も帰国後に政治、経済、教育、文化など様々な分野で活躍し、日本の文明開化に大きく貢献しました。
これと同じことをサムスンは1993年に行ったのです。改革の前に先進国・先人から学ぶというのは、時代が変わっても、常に変わらないセオリーなのです。
他社製品との客観的評価の実施
次に、改革に取り組むには自社の実力を客観的に評価する。これが重要な前提条件であり、改革を始めるためのセオリーです。
そこでサムスンは、自社製と日本製のテレビを見比べました。外見はさほど変わらないものの、カバーを外して中を見ると、その差は歴然でした。日本製のテレビは部品や配線が無駄なくきれいに整って並んでいるのに対し、自社製のものは、部品も配線もごちゃごちゃでした。それを見た会長は「こんなものしかつくれないなんて、今まで何をしてきたのか」と激怒したのです。
その次にはデザインの評価です。何人かの幹部と共に、自社製と日本製のテレビを見比べるよう、メーカーのロゴを隠して状態で、自分が買うとしたらどちらを選ぶかを幹部に聞いてみると、その場にいる人たち全員が日本製を選んだのです。こうやって自社の評価を客観的に算定していきました。
韓国人の国民性の是正
冒頭のフランス企業のテーブルの配置の仕方、これは国民性でフランスの文化性です。
隣のドイツ企業にもよく行きますが、ここでは日本と同じくスクウェア四角直線的な配置でテーブルが並べられています。隣国でも国民性と文化性が全く異なるのです。
同様に韓国にも根強い国民性・文化性があります。それは「個人主義」ということです。
日本ではチーム制で仕事するのが常識ですが、韓国では深く根ざしている個人主義のため、サムスンのエリート幹部は格下と見ている現場には行きたがりません。現場を軽視し、現場を把握しないで仕事をする傾向が強いのです。
個人主義には別の問題もあります。個人主義は自分の非を認めると、すべての責任を個人がとらなければならなくなるので、これを避けるために、上司から指示されたことしかしないということになりがちです。
また、失敗した時には、「環境が変わったのでうまくいかなかった」「他の組織が協力してくれないから仕事が進まない」というような責任転嫁を平然と行うのが普通です。
このような国民性と文化性によって発生するもの、それがグローバル企業になろうとするときには大きな弊害となります。このような韓国人の実態を日本人はよく把握し、韓国と取引や交渉を行うことが必要でしょう。サムスンの事例を自らの教育にすることです。
日和見主義
韓国の企業では、日本のような定期人事異動はありません。異動があるのは、あるレベル以上の役員と、その部門に問題が起こった時だけです。
しかし、その異動が発生すると、つまり、上司が変わると、それまでに仕事の方針や仕方が大きく変わります。これは日本でも同様ですが、日本より振幅が大きいのです。
そのように上司の異動は、自分の仕事の大変化を意味し、そこに個人主義ですから、変化によって自分が損を被らないことを常に考えていますから、上司の異動の噂が出回ると、途端に部下は仕事をしなくなり、その部門の動きがすべて止まってしまう、というような事態が多く発生するのです。
これらの国民性と文化性を変えさせたもの
では、サムスンはこのような問題ある国民性と文化性をどのようにクリアしていき、世界のトップになったのか。最大のピンチをチャンスとした改革ポイントは次号です。以上。
2010年11月20日
フランスに学ぶブランド化戦略(後)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年11月20日 フランスに学ぶブランド化戦略(後)
パリ農業祭の牡蠣審査会場に入る
前号ではパリ農業祭で、牡蠣審査会場に入ったところまでお伝えしました。このように農業祭の審査の様子をお伝えするのは、今まで誰も行っておらず、日本初のことからです。何故なら、日本では同様全国レベルの生産物審査会が存在していないからです。
さて、審査室に入って全体を見回しますと、牡蠣は17テーブルが審査席で、15のカテゴリーに分けています。
その区分けはブルターニュ地方の牡蠣は5カテゴリー、ノルマンディー地方は2カテゴリー、ロワール地方は2カテゴリー、ポワトゥー・シャラント地方は3カテゴリー、アキテーヌ地方(アルカッション)、地中海地方牡蠣、平牡蠣(フランス産の牡蠣・生産数は少ない)の15カテゴリーです。
全部を全般的に見るのは、返って審査実態がわかりにくいので、一つに絞ろうと14カテゴリーの地中海地方牡蠣テーブルに的を絞り、ここには四人の審査員がいて、そこの回りに立ちました。ここに絞った理由は、地中海の海が瀬戸内に近いと思ったわけです。但し海域の広さが全然違っていますが、何となく瀬戸内播磨灘が浮かぶからです。
10時になり最初は、白いガウン姿の若い女性が、最初の牡蠣を皿に盛って運んできました。数は12個。殻を開けられているものが6個、殻つきが6個。いずれも養殖業者自慢の牡蠣です。どこにも名前は書いてなく、誰のものか分からないようになっています。
実際の審査項目
いよいよ審査が始まりました。審査項目は以下のとおりで、各人に用紙が配られます。用紙には6項目のチェック内容が書かれていました。
① 殻の外見 ②身の見た目 ③匂い ④味 ⑤後味 ⑥貝の内側面
この項目について、それぞれ次の5ランク評価を行っていくのです。
① 不十分 ②並み ③良 ④上等 ⑤優秀
これが終わった後、全体的な点数評価をつけます。1から20点まで。最後にコメントを書き入れるのですが、これを6皿ごとに行うのであるから、大変な手間です。
四人がそれぞれ開けられた牡蠣を手に取り、また、開けられていない牡蠣をナイフで剥き、それぞれの方法で見極めを始めました。
実際の審査方法
殻の上下、蝶番の位置、この蝶番のバランスで自然ものか三倍体牡蠣かが分かるようです。三倍体牡蠣とは人口交配でそだてたもので、日本では殆ど見かけません。
さらに匂いをかぐため鼻に持っていく。開いている牡蠣の中身を手で触って弾力性を確認する。フォークで中身をすくって身の状態を確認し、貝柱の位置を見るなどします。
次に食べてみる。口の中に広がる味わいを確認するかのように噛みしめる。次に食べた殻の中側を手で触り、肌触りと色具合を見ます。
つまり、わずか10センチにも満たない牡蠣一つひとつに、これだけ慎重に四人が確認し、その結果をお互いに発言し合うのです。
例えば、これは野性的だ、自然な形がよい、味が強そうだ、色がよい、ヨウ度が強い、地中海らしい、牡蠣殻の独特の文様が濃い薄い、肉付きがよい、厚みがある、匂いが全くしない、これは腐っているので危ない、殻のところに穴があいて海水が入って死んでいるのだ、後味が良い等、全部は書ききれませんが、とにかく真面目に真剣に一つずつ確認し、それを表現しつつ、かつ、お互いの見解を確かめあい、それを審査表に書き込み、さらに、各人が持参した別のメモ用紙にも記録用として書いておきます。審査表は事務局に提出してしまうので、別用紙に記録しておかないと自分の見解がわからなくなるからです。
各テーブルを見回すと、男性が多いが女性も必ず各テーブルに一人か二人います。こういうところからもフランス社会を垣間見ることができます。女性の社会進出が進んでいるのだと思います。
最後に評価が決まる
このような牡蠣の審査、それを6皿続けるのです。途中で口にするのはミネラルウォーターとパンだけ。ひと皿に20分から25分掛けています。終わったのが12時少し前。約二時間要したわけです。
さすがに集中し、続けて6皿、つまり72個の牡蠣を四人で審査していると、審査員としての意見が概ね一致していくようです。
良いものと、そうでないものが明確になってくるのです。勿論、ここに出てくる牡蠣なのだから、地元では優れているものばかりですが、この場所で同時間帯に同一基準で審査すると優劣ははっきりしてきます。
6皿全部が終わった後、次はまとめに入ります。一人一人が金賞に値する皿の番号を述べ、その評価点を合計すると75点、二番目に運ばれてきた皿の牡蠣が、このテーブルでの金賞となりました。五番目の皿が73点で銀賞、これを全員で確認し審査は無事終了しました。
終ってホッとした審査員のところに、事務局の女性が、審査用紙を回収しながら、白ワインを一本置いていきます。なかなか気がきくなぁと全員で「お疲れ様」と乾杯して終了しました。
審査の結果は、数日後、コンクール物品ごとに会場に張り出されます。コンクールメダルは金、銀、銅の三つで、牡蠣部門は15のカテゴリーごとに与えられるのです。
審査会を経験してみて
以上が、農業祭での「牡蠣審査会」の様子です。このパリ農業祭には、ここ五年ほど毎年視察しています。今までは、一般参加者として会場内を歩き回るのみでした。
今回、初めて農業祭運営の大きな柱である審査会の裏方を視察したわけですが、コンクールの結果は、該当品の評価として高く認識され、その地のブランドとして育成させ、定着させていくシステム、これがフランスを世界第一の観光客数にさせている源泉ではないかと認識した次第です。
つまり、地域の産物を競い合って、レベルを高めあい、その結果としてコンテスト入賞品はその土地の自慢物として、自信をもって推奨物としていく。
自分の土地からはこのような素晴らしい産物が生まれるのだ。だから、皆さん来てください。国が認めてメダルをくれたブランド品だから美味しいですよ、と自慢し、訪れる観光客に語りかけるのです。語りかけられた観光客は「そうですか。メダル品ですか。それで美味しいのか。お土産にしょう」ということで買い求め、自宅に戻ってお土産として配る際に、産地で聞いたブランド評価の内容を口にし、聞く方も国が公式に認定しているコンテストの入賞品だから、成程と頷くのです。
これが150年近く、毎年繰り返されているのです。今では世界の関係者に知れ渡り、私のように毎年農業祭を見回って、その後フランス各地を回った時、その地の産物に入賞メダルがかかっていると「おめでとう」とそれを飲み食べることになっていきます。
観光地の育成には、ハコモノづくりだけに執着するのでなく、著名人の訪問等のイベント的PRだけに特化するのでなく、専門性をもった日常的な相互研鑽交流活動、これは農業祭のような国主催のコンテストを意味しますが、これらがミックスした「総合観光力」が必要なのです。それを地道に150年近く続けているのがフランスの強みで、ここに世界一の観光客数維持の秘密があると判断したわけです。
日本はどうなのか
日本にこのような全国的な物品・産物が一堂に会したコンクールはありません。各地方、各県、各市町村で開催する事例は多くあるでしょうが、政府主催で全国区のものはなく、これはフランス以外の国でも同様と思います。
日本は、現在「観光大国」を目指そうとしているわけで、その方向は正しく妥当ですが、そのためには日本の各地の観光地と、各地方の産物が世界で認識されることが重要だろうと思います。
そのための仕組みつくりの一つとして、今回の農業祭審査会の実態を日本の関係者に参考にさせアドバイス願いたいと、2010年10月のパリで農業祭コンクール事務局長のフース氏に会い伝えたところ、日本における同じようなコンクールの実現にぜひ力をお貸ししたい、という力強い協力の申し出がありました。
日本の観光関連部門に所属している方、この申し出を真剣に検討されたい。ご希望の方から連絡を乞う。以上。
2010年11月06日
2010年11月5日 フランスに学ぶブランド化戦略(前)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年11月5日 フランスに学ぶブランド化戦略(前)
童謡歌唱コンクール
まず、山岡鉄舟研究会のメンバー高橋育郎氏の活躍を報告いたします。
11月3日、五反田の「ゆうぽうと」で開催された「全国童謡歌唱コンクール・大人部門」でグランプリを受賞したのは愛知県豊田市の宮内麻里さんで、歌は高橋育郎氏作詞の「大きな木はいいな」でした。
高橋氏は著名な作詞家です。偶々10月の鉄舟会例会で「何故に童謡はグローバル化がなされないのか」というテーマで、縷々お話が展開され、その際に今回のコンクールの事も紹介されましたので、会場に伺ったのです。
折角行ったのですから、舞台から三列目でじっくり童謡を楽しみましたが、グランプリの宮西さんが歌い終わった時「この人が獲得するだろう」と直感しました。
その理由は、歌い始める前の紹介で「新しい歌詞を探していたところ『大きな木がいいな』に出会い、自分の心に深く入ってきた」とあり、彼女と歌詞の一体化が会場内に大きい波となって流れ、場内の拍手も一番多かったと感じたからです。
この日の模様は11月28日(日)BS朝日で15時から放送されますので、ご関心ある方は是非ご覧いただきたいと思います。
しかし、これだけの規模でコンクールを展開している日本の童謡が、世界では無名に近いということに驚きます。童謡を素晴らしい日本ブランドとして磨くべきでしょう。
日本磨きをすべき
さて、本題にはいりますが、先日、フランス人のジャーナリストから慰めとも、アドバイスともとれる忠告を受けました。
「フランスは昔からずっと低成長経済で失業率も高い。この実態に国民は慣れ親しんでいる。日本人はここ20年ばかり低迷しているが、そのうち慣れるよ。そんなことを気にするより、もっと日本磨きに邁進した方がよいと思うよ」と。
この発言にいたく共感しました。というのも、私は70年代から毎年しばしばフランスを訪れていますが、日本が高度経済成長を示した時代は「日本は蟻のように侵略してくる」と当時の仏首相が発言したように、日本の経済進出が欧州で強く警戒されていました。
だが、バブル崩壊後は、経済面と逆比例するかのように、日本文化・観光面での人気がじわじわと高まってきました。冒頭のフランス人ジャーナリストの発言は、その特長をもっと伸ばし、深める方策を検討した方がよいというアドバイスと理解をしたからです。
日本人気体験
日本人気を海外でしばしば実際に体験します。先月、フランス南部トウルーズ市郊外の中華レストランでの昼食時、中年夫婦がこちらのテーブルに来て「日本人ですか。日本旅行から戻ったところだ。素晴らしかった。もう一度直ぐに日本に行きたい」と絶賛の嵐。私はただただ笑顔で「メルシー」と頷くだけでした。
また、ジャンヌダルクが火あぶり死刑なったところで有名な、ノルマンディー地方・ルーアン市郊外の村、そこの公民館で開かれた「香水愛好家の集い」に出たところ、ここでも中年の夫婦から「日本人か。四カ月前に日本中をバスで回った。皆よかったが、特に高山は気にいった」と褒め称えられ、面目をほどこした次第です。このように外国で日本人気を直接聞くことが多々あります。
フランスは不便・不潔な国だが世界一の観光客数
ところで、フランスは失業率が高く、ストライキも多く、今回も年金支給年齢二歳延長法案に反対して全国的なストライキが発生し、交通手段が遮断された上に、タクシーも石油精製工場ストでガソリン不足のため稼働台数が少ない等、移動には大変困り、ようやく動いたTGV一等車の四人席は前の人と靴が触れるほどの狭さ、さらにトウルーズ市内はゴミの山であったように、決して快適・便利とは言えず、加えて、パリの街路にはいつも犬の糞が散乱して不潔、しかし、それでもこの国は世界一の観光客を集めています。
具体的実数では7,930万人(2008年)と断トツで、二位のアメリカを2,000万人程度離しています。対する日本は、フランス人から褒められても観光客が全く少ない。どうしてなのか。もしかしたら世界遺産の数の違いか、それとも他に理由があるのか。
世界遺産の数は関係なし
世界遺産の数はイタリアがトップで44か所(2009年)、33カ所のフランスより11か所も多いのですが、観光客数は第五位の4,273万人(2008年)ですから、フランスの約半分の実績に過ぎないのです。ということは世界遺産という優れた観光地があっても、必ずしも観光客数に結びつかないということであり、逆にいえば、世界遺産以外の根本的な集客要因がフランスにはあるはずと考えるのが妥当と思います。
文化・観光ブランドづくりが強さの秘訣
それは何か。結論的に言えば「文化・観光ブランドづくり」の巧みさではないかと思います。一国の強さを経済力とか、軍事力とか、科学力というようなことで評価する事例が多くみられますが、フランスはこれらと別次元の「ブランド力育成に優れている」というところにあるのではないかと実感します。
つまり、自然や街・歴史景観と各地で産出される物品をシステム化し、マッチングさせ、観光文化国家像を鮮明化させる政策がフランスの得意技なのです。
日本が観光大国になるためには、そのところを観光政策部門や観光地・産地が学び参考にし、国家としての仕組みづくりに取り入れていく必要があり大事だと思いますが、このブランド力構築の仕組みの一端を確認できる機会をこの春に得ました。
ブランド力構築の仕組みの一端を確認
それは、今年3月に開催されたパリインターナショナル農業祭(通称:農業祭)の運営事務局から、牡蠣部門の審査に参加するよう招待され、実際の審査実態をつぶさに見ることができたことから気づいたのですが、今回はその様子をお伝えすることで、フランスのブランド作り仕組みの一端を解明したいと思います。
農業祭とは
さて、この農業祭、パリ市民にとっては、春の代表的な楽しみ大イベントですが、日本人にとっては全く馴染みがありません。
そこで、まず、最初にパリインターナショナル農業祭の概要をお伝えします。
フランスでは、18世紀に発足した農業振興会による家畜コンクールに発端、1870年にパリで公式に全国農業コンクールとしたのが始まりで140年の歴史があり、現在、農産業関連ではフランス最大のイベントになっています。
また、各種のコンクールも動物のみから各地の特産物に拡大発展し、国の食品農業水産省管理下における公式コンクールとして、その公平さによって賞の価値が高く認識され、金賞・銀賞・銅賞は名誉として、該当品目のブランド価値評価となっています。
今年の農業祭
2010年の農業祭には、フランス22地方、海外県、及び17カ国が参加し、品評される生産物は、ワイン15000種、その他様々な生産物4000種で、開催9日間での入場者数は65万人、サルコジ大統領も訪れるフランスの重要戦略コンクールになっています。
審査会場に入る
牡蠣審査は農業祭の開催初日に実施され、当日の朝、9時半過ぎに審査する部屋に案内され、入り口で一人ひとり名札を確認の上入ります。部外者は立ち入り禁止です。ここで審査され金賞・銀賞をとれるかは、今年一年間の営業に大きく影響するからで、それだけここの品評会は歴史と伝統と権威があるのです。
この会場で審査されるのは、牡蠣と鱒等の燻製魚、それとポモーと呼ばれるブルターニュやノルマンディー地方で作られる食前酒です。牡蠣の審査会場の白い布で覆われたテーブルには、既に水とパンが人数分置かれ、各テーブルに番号が書かれ、審査員は出席名簿にサインします。
以上は、今年の9月に出版した「世界の牡蠣事情」第一章「パリ国際農業見本市」の内容です。日本の観光大国化という視点からご紹介しました。11月20日号に続く。以上。
2010年10月18日
2010年10月20日 日本の政治劣化背景要因(後)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年10月20日 日本の政治劣化背景要因(後)
記者クラブとは
前号に引き続く日本外交が下手だという問題です。問題の要因は「記者クラブ」制にあると前号で指摘しました。
記者クラブとは、政府・公的機関や業界団体などの各組織を継続取材している、主に大手メディアが構成している組織で、英語でもkisha clubないしはkisha kurabuと表記され世界に通用するもので、日本記者クラブなどの「プレスクラブ」とは全く性格を異にするシステムです。
日本しかない記者クラブ
フリーの記者などに対し排他的であるとして、これまでOECDやEU議会などから記者クラブの改善勧告を何度も受けていますが、一貫して大手メディアは記者クラブに関する指摘次項を報道しないため、国民の殆どは記者クラブの持つ閉鎖性を知らないのです。記者クラブが存在しているのは世界中で日本とアフリカのガホンだけらしく、他の国では、事前に登録しておくと、危険人物としてリストに載っていなければ、大統領・首相の記者会見に自由に参加し質問ができるのです。これが世界の常識ですが日本は異なるのです。
小沢氏・岡田氏はオープン化した
記者クラブの運営は、 加盟報道機関が複数当番制で「幹事」社となってあたる事が多く、情報は情報源の広報担当から幹事社に伝えられ調整され、幹事が件名や発表日時などその報道に関する約束事を記者室の「ボード(黒板)」に書き、黒板に書かれた約束事は「黒板協定」「クラブ協定」「しばり」などと呼ばれ、加盟社が順守するべき約束事とみなされます。
記者会見は、ほとんどがクラブ主催となっており、参加者も加盟社に限られ、仮に加盟社でない記者が参加できても質問は出来ません。また、記者懇談会やぶら下がり取材、国会記者証の交付などもほぼ独占的に享受しています。
但し例外もあり、小沢一郎氏が民主党の代表時代と、岡田克也前外相の記者会見はオープンとしたので、これがニューヨーク・タイムズに大きく報道されましたが、この事実も記者クラブ性のため国民に報道されていません。
外国人が質問できない
記者クラブ制の最大問題は、外国人記者が質問できないことであって、外国人のマスコミ記者を排除して、鎖国化していることです。
これは何を意味するか。政治家は、日本人だけの、顔見知りの大手マスコミ記者からの質問に答えるという日常の継続で、いわば日本人同士の身内会見であるので、異質で利害が異なる外国の立場からの、厳しい質問を体験できないということになります。
日本人だけの質疑の意味
この結果の意味するところはお分かりになると思いますが、外国(人)と接しないままに、日本人同士の論理で諸問題が記者会見で討議されるので「世界から日本を見る」という視点の訓練がなされないままに、政府の要人になっていくことになります。
日本の国際競争力は経済だけでなく、政治も国際競争力が問われているのですが、さすがに今を遡ること140年前の明治新政府は分かっていました。
明治4年11月12日(1871年12月23日)から明治6年(1873年)9月13日まで、アメリカとヨーロッパ諸国に派遣されたのが岩倉使節団です。岩倉具視を正使とし、政府のトップや留学生を含む総勢107名で構成されて、鎖国体制から脱皮しよう、日本を世界から見よう、と意図された使節団であり、この成果は大きいものでした。使節団に参加していた大久保利通が征韓論を退けた後書き上げたのが「立憲政体に関する意見書」で、政体取調掛に任命された伊藤博文に手渡しました。
この中で大久保は「今までは国力というものを軍事力とそれを支えている軍事技術にあると思っていたが、それだけでなく様々な要因が国力を支えている」と書き述べています。
正に、ドイツのビスマルクを始めとする世界の政治家たちとの出会うことによって、国力の基盤が軍事・政治力を含めた多くの要因が複層的に重なるところの充実にあるということを理解し、その後の日本国を創り上げていったのです。
指摘されている記者クラブの問題点
ここで記者クラブについて一般的に指摘されているネット内容を紹介します。
1.メディアが政府の政策を代弁し、政府の広報となっている。
2.警察及び検察が自らの捜査に有利な方向に情報操作を行い、メディアも 調査報道に消極的なため、冤罪を生み易い(例:松本サリン事件、足利事件)。
3.NHKの報道部に在籍していたこともある池田信夫氏によると、警察記者クラブに多数の記者を常駐させることが日本の報道を犯罪報道中心にしているのではないかという。
4.フリージャーナリストの魚住昭氏は「官庁の集めた二次、三次情報をいかに早く取るかが仕事の7、8割を占めてしまうと、実際に世の中で起きていることを察知する感覚が鈍る。役人の論理が知らず知らず自分の中に入り込み『統治される側からの発想』がしにくくなる。自分はそうではないと思っていたが、フリーとなって5年、徐々に実感するようになった」と述べている。
5.衆議院議員の河野太郎氏は(日本では)記者が政治家から食事をご馳走になるのは当たり前、政治家が外遊する際には同じホテルに泊まり「政治家と記者はよいお友達」になることがメディアでは「良い記者」とされている現状を指摘している。
6.ニューヨーク・タイムズ東京支局長のファクラー氏は、「記者クラブは官僚機構と一体となり、その意向を無批判に伝え、国民をコントロールする役割を担ってきた。記者クラブと権力との馴れ合いが生まれており、その最大の被害者は日本の民主主義と日本国民である。」と述べている。
7.主要メディアが報じる捜査情報について、「検察が記者クラブを通じておこなう『リーク』に依存している」と指摘されることがある。
また、検察側は自己に不都合と考えられる報道をおこなった加盟報道機関に対しては検察関連施設への「出入り禁止」措置を取ることがある。
8.西松建設事件に際しては、一部の加盟報道機関が西松建設から献金を受け取った政治家の1人である二階俊博氏の件についての記事を掲載したことに対し、取材拒否および東京地方検察庁への3週間の出入り禁止措置を取った。この一件以後、加盟報道機関は検察および自民党に有利な報道をおこなうようになったといわれる。また、検察は記者クラブに加盟していない報道機関による取材を拒否している。
事実なのか確認
これが事実かどうか。知人の主要新聞社の解説委員に、以下の二つを質問し確認をしてみました。
1.主要メディアが報じる捜査情報は「検察が記者クラブを通じておこなう『リーク』に依存している」のか
2.検察幹部から「書き方のアドバイス」を指示されるような場合があるのか
回答は「よく知っていますねぇ」でした。
世界から日本を見るというセオリーが重要
政治家の国際外交力の欠如が、今回の尖閣海域問題の日本政府対応に現れたと認識し、その背景に世界から問題指摘されている「記者クラブ」制が要因として存在すると理解します。
政治家もマスコミも「世界から日本を見る」というセオリーを貫かないと尖閣海域問題の第二、第三が違う局面で発生すると推測致します。以上。
2010年10月05日
2010年10月5日 日本の政治劣化背景要因(前)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年10月5日 日本の政治劣化背景要因(前)
人を知る者は智なり、自らを知る者は明なり(老子)。
他人のことの批評や分析はよく行うが、自分のことはあまり追及しない。中国をけしからんと言うのはその通りであるが、日本側の不十分なことを考えると、日本国際競争力の基本的問題がわかる。
菅内閣の外交下手
今回の尖閣海域問題の日本政府対応に、日本人全員が怒り狂っているが、その要因を掘り下げていけば菅内閣の外国(人)との交渉下手ということに尽きるだろう。
菅首相の経歴は市民運動家であり、仙谷由人幹事長は全共闘の新左翼系学生運動家であって、商社やメーカーに勤務し、海外との難しい商売で苦労したり、海外企業や合弁会社の経営にタッチしたりした経験がない。
つまり、若い時代から今日まで外国人と対決するとか、仕事を通じて外国人と激しいディスカッションの経験が薄いまま、今日の日本政府要人となっている。ここに大きな問題要因があるように感じる。
その証明が菅首相の代表再選後の記者会見である。真っ先に取り組むべき課題として、経済問題を挙げたのは当然としても、国際関係が大きく変貌し複雑化している世界戦略については触れなかった。思うに、国内選挙用のマニフェストはあっても、グローバルな国家観を持っていないのではないかと推測する。
菅首相の歴史的認識力
もう一つは、尊敬する歴史上人物として長州・奇兵隊の高杉晋作を挙げ「奇兵隊内閣」になりたいと発言したことである。高杉晋作の功績は倒幕の狼煙を揚げ、その後の明治維新への最初のキッカケをつくったことで高く評価される。
だが、民主党は昨年8月の衆議院議員選挙で自民党に大勝したことにより、政権交代という倒幕は成し遂げ、鳩山前首相の不始末を引き継いで首相に就任した菅首相であるから、今後の日本国家運営を問題少なくスムースにさせるための、緻密な計画に基づく行動が求められていたタイミングであり、奇兵隊発言は歴史的認識が薄いと思わざるを得ない。江戸開城によって明治維新の扉は開いたが、実際の倒幕確立は、彰義隊壊滅から東北・函館までの戊辰戦争勝利によるもので、この勝利を指揮した大村益次郎の功績が大きい。
菅首相は同じ長州出身の大村益次郎を知らないわけはなく、首相就任後の現状認識から歴史上の人物を見習うとしたら、銅像として靖国神社に立つ大村益次郎でなければならないはず。このように何か時代への認識力にかけるのが菅首相ではないかと思う。
自らの体験から
私は40歳代の前半から後半にかけて日仏合弁企業に在籍した。最初の一年は副社長としてフランス人の社長と仕事をした。副社長就任直後は、相手が社長であるから仲良くしようと努力したが、一か月で対決路線に切り替えた。というのも、彼はフランス本国の言うことを日本側に押しつけるだけで、日本の実態を理解しようとしない傾向が強く、このままでは企業が成り立たないと対決戦略を採ったのである。事実、この合弁会社は赤字額が大きく、日本の親会社は早くつぶそうとしていたのである。
対決ということは、経営の仕方をディスカッションすることであり、見解が大きく異なるのであるから、ディスカッションは激しく長く喧嘩となる。通常は午後から夜まで毎日のように行なった。これを一年間続けていると、大体に相手の思考方法習慣が分かってくる。そこで、相手の出方を予測し、それを活用してこちらが手練手管を用いて交渉事を有利に展開しようとすることになっていく。当時は、朝起きると今日のディスカッション対策を考えることが楽しみになっていたくらいである。
押し通すことがセオリー
しかし、その間も通常の経営は進めるのであるから、意見が合わないままにしておくと、物事が進まず、得意先に迷惑を掛けることになる。そこで、見解が分かれることであっても、実行すべきことは私の独断でドンドン進めていった。つまり、当方の主張を押し通したのである。今までは、意思決定がはっきりしなく、現場に対応しないものであったので経営不振であったが、押し通すようになって経営改善は進んだ。
だがしかし、それらが続くと当然にフランス人社長は怒り心頭に達する。そこで彼が打った手は、フランス本国のオーナーの前で、どちらの見解が妥当か判断してもらうための会議を提案してきた。
来たな!!と、しかめ面をして承知したが、心の中では「しめた」と思い、準備万端整えて、ということは理論的に資料をつくり、バックデータも十分に用意してフランスに向かった。考え方が異なる外国人を納得させるのはしっかりした論理展開しかない。
フランス人オーナーは大企業を一代で築き上げた人物で、カリスマ性がすごいとの評判の人物であった。このオーナーの前で社長のフランス人と私がそれぞれ自説を展開したわけであるが、驚いたことに当方の見解に理解を示し、一年が終わった時に私が社長に昇格した。後で考えてみれば、業績向上の方がオーナーにとって得なのであるから、利口な経営者なら当然の判断だろう。
結果として、多額の累積赤字を、社長を辞任する際は完全黒字転換し、フランス人オーナーから感謝されたことが強く記憶に残っているが、この合弁会社での経験から言えることは、海外との交渉では自分が思った事を押しとおすことである。
責任は自分が採るのであるから、開き直って自説を押し通すことしかない。ところが、私の前任者はフランス人社長に迎合して、結果的に経営がうまくいかなかったので、責任を取らされ左遷になった。
「国益を守る」という判断基準
考え方の異なる外国人の見解を鵜呑みにしてはいけないのである。時には聞き、頷くべき見解もあるが、総じて事情理解が不十分であるから無理難題的な傾向が強い見解となる。その時が勝負である。相手がどう出ようと、判断基準を「会社の利益貢献」という立場から意思決定して行けばよいのである。
これを国に例えれば「国益を守る」という判断基準になり、その思考から日本の考え方を押し通すのが外国と交渉する際のセオリーである。
今回の尖閣海域問題における中国は、この押し通すというセオリーを忠実に貫いてきた。日本もセオリーを貫くことで対応すべきであった。
今も毎月海外に出かけ、多くの外国人と仕事をし、折衝事をしているが、最終的には当方の見解を押し通さないと目的の業務が達成できない結果となる。これが外国(人)との実践的な付き合い方セオリーである。
政治家は鍛えられていない
だが、これらのセオリーを知らないのは菅首相だけでなく、政治家全員に当てはまる日本の構造問題ではないかと考える。政府要人全員が、過去に海外との商売や、海外企業・合弁会社の経営にタッチできるわけはない。海外との交渉が薄いままに政治家として選挙で当選し、当選回数を重ねて、要職に就けば、当然に諸外国との対応が問われ、日本の国益を第一にした対応が要望され、妥当な判断を行わなければならないということになって、そこで改めて外国との考え方の違いを大きく認識し、自己判断基準の持ちように迷うことになる。
根本的な要因は「記者クラブ」制にある
加えて、外国の政府要人は、押し並べて主義主張の強い頑固な人物である。そういう人材を外交用に配置しているのである。こういう強敵と交渉に臨むのであるから、お腹が弱い人物は直ぐに下痢をしてダウンし退陣となってしまうことになる。日本の政治家は総じて対外国(人)に対して経験不足だと思う。
だが、これを政治家個人の理由にしては可哀そうである。もともと優れた才能の人物で、日本国内では立派に政治家として実績を挙げていたからこそ、政府要人になれたのである。ところが、その立場になってみると、小泉首相以後一年しか持たない。
それは実践的な海外勢との経験が少ないというところにあると思い、その根本的な要因は「記者クラブ」制にあると推察する。この問題は次号でも検討して参ります。以上。
2010年09月22日
日本のONSENを世界ブランドへ・・・その二
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年9月20日 日本のONSENを世界ブランドへ・・・その二
クローゾン氏の講演内容
9月13日・14日・16日と東京・鹿児島県指宿で開催された「日本のONSENを世界のブランドへ」シンポジウムでの、クローゾン氏発言概要をお伝えします。
40℃前後のお湯に浸かる習慣は欧米にない
クローゾン氏の温泉との出会いは1982年。仕事を終え大分県・湯布院を訪れた彼は、すぐに温泉の持つ魅力に惹かれました。それは、温泉地の風景、日本の美しい風景と日本旅館の調和、周辺の情緒ある田舎道の心地よさなどでした。
さらに彼に強烈な印象を与えたのは、温泉に入るということ、そのものでした。40℃前後のお湯に浸かるというのは、欧米の習慣には全くないわけです。だが、入浴してみると、初めてでありながらとても心地よく、この素晴らしい体験に魅せられ、以来、彼は来日のたびに各地の温泉を巡り歩いています。
温泉は異文化の塊だ
日本は全国どこに行っても温泉がある。これは素晴らしいことだ。と彼は強調しました。また、その温泉が源泉を中心に旅館・ホテルが多く立ち並び、一つの温泉街として成り立っている姿、これは欧米の街づくりとは異なった特殊な形態なので、その中を散策しているとさらに興味が深まってくるというのです。
これをひと言で表現すると、温泉街には欧米にない「異文化」があるということになります。日本の温泉地には、欧米にない温泉文化があり、温泉が人間社会に溶け込み、日本人の生活習慣となっていること、それが日本を訪れる外国人にとっては「異文化」として映るのです。
加えて、その異文化の温泉街の中は「日本の魅力をいくつも同時に体験できる場」であるとも強調しました。例えば、自然に溶け込んだ宿の佇まいの美しさ、きめ細やかな接客と共に提供される美味しい日本食、そして、人の素晴らしさ。これは女将のおもてなしのことですが、その女将が着物姿であること。これらが相まって、これほどの日本の伝統美をいくつも重なって感じられるところは温泉しかないというのです。
しかも、このような魅力に溢れた温泉が、日本全国いたるところに存在していることが、これまた素晴らしいと、彼は絶賛します。
ところが、一般の欧米人はこのような「異文化魅力」が集約された温泉を、全然知らないというのです。日本に行き、温泉を訪問すれば、日本文化が重なり合って感じられるのだから、その事実をもっともっと欧米人に知らせてほしい、と彼は何度も強調しました。
フランスは日本ブーム
さらに現在、フランスは日本ブームです。パリ在住の彼はこれを肌で感じています。特に、その火付け役となっているのは日本のアニメーションであり、それを受け入れブームを牽引しているのは10〜20代の若者ですから、彼ら熱狂的な日本ファンの若者が成人し社会人となったら、きっとバカンスで日本を訪れるようになるといい、彼らは将来の貴重な来日予定者であり、将来の温泉ファン候補でもあるともいうのです。
また、若者だけに限らず、日本に関する文化が各場面で活用されている事例を映像でいくつも紹介しました。
日本側が準備すべき事
最後に大事なポイントを語りました。欧米人が日本を訪れるために、日本側が準備すべきことです。
それは、欧米人に合わせて設備を整えることではありません。そのことはむしろ温泉の価値と文化を自らの手で壊すことを意味します。そのままでいいのです。そのままの姿が「異文化」であるから、欧米人はそこに大いなる魅力を見出すのです。
では、現在、何がなく、これから必要なものは何かです。
それは、温泉の魅力を知らせるもの、すなわち、温泉ガイドブックを作ることだと主張しました。温泉とは何か、温泉の入り方、温泉の楽しみ方、温泉旅館の特徴、予算に応じて楽しめる温泉地あれこれなど、それらをまとめて書かれたガイドブックが欲しい。
これは各地の温泉旅館・ホテルの紹介ガイドではなく、日本の温泉という世界の特殊性である存在物を、全く知らない欧米人に伝えるガイドブックです。
このようなガイドブックが、温泉を世界ブランドにするためには、まず、最初として、基本的に用意されるべきものであるというのが、クローゾン氏のまとめでした。
現在の観光業界PR活動
ここで改めて、観光業界と温泉業界の取り組みを振り返ってみます。
親しい温泉地の女将さん、時折、香港とかパリにPRに出かけ、観光業界の集まりとか、旅行業者への訪問し、着物姿でイベントとしてお茶のお手前を披露しながら、温泉の紹介をしているようです。
このご努力は認めつつも、訪れた世界各地の観光・旅行業界人は、日本の温泉についてある程度知っているでしょうが、クローゾン氏のような日本について事前知識を持って、日本に関する専門家になろうとしていたタイミングの時でさえも、湯布院で初めて熱い湯を体験するまで知らなかったというのですから、一般の欧米人は温泉を見たことも、触ったことも、聞いたこともないというのが事実実態なのです。
この事実実態に立って、日本の温泉関係者は「日本のONSENを世界ブランドへ」と行動してきたのでしょうか。どうも違うように感じます。
日本ではテレビで毎日のように有名人を使った温泉入浴場面が放映され、旅行するということは温泉に泊まるということと同意味みたいになって、日本人の生活に根ざしていますが、欧米人はこの反対の極にいるのです。
ですから、この温泉を知らない人達に日本の温泉に来てもらうためには何が必要か、それをクローゾン氏からまずはガイドブックから始めることだと提案受けたのです。
考えてみれば全く知らない人達に温泉を説明して、魅力を分かって貰うのですから、その理解のためには基礎的資料が必要です。
ところが、欧米の書店には観光ガイドブックは並んでいても、温泉のガイドブックはありません。ガイドブックの中に各地有名な温泉の紹介はあっても、温泉そのものの基礎的理解を与えるガイドブックはありません。
欧米人の旅行スタイル
欧米人の旅行スタイルを見ていると、必ず片手にガイドブックを持って歩いています。欧米人はガイドブックと現場を確認して行くのが観光であるという習慣を持っています。ということは温泉ガイドブックがあれば、それを片手に温泉に入り、その結果を国に戻ってからクローゾン氏が率直に感じたような、温泉魅力を友人等に伝えてくれます。また、その際に温泉ガイドブックを指し示すことでしょう。
だが今まで、このような基本的ツールとなるべきガイドブックなきままに「ONSENを世界へ」と行動していたのではないでしょうか。
クローゾン氏のような記者によって、世界から見た日本温泉を説明するガイドブックを書いてもらい、それを欧米の出版社で発行し各国主要都市の書店に並べることが必要です。日本の出版社では世界的書店ルートがないので無理なのです。
また、この実現は多分、観光業界や温泉業界に任せておいては実現が遠い先でしょう。観光庁が音頭をとって進めることが日本のONSENを世界のブランドにするために必要なことだと思います。
世界から日本を見れば、日本は魅力たっぷりな財産がたくさんある国ですから、それを情報化することが喫緊の課題です。
観光庁に提案する
クローゾン氏の見解と提案について、今回のセミナーでご参加された多くの方も同意見ですので、世界の書店に配本ルートを持っている欧米の出版社から「日本の温泉ガイドブック」を刊行するための企画書をもって、近く観光庁に提案に行く予定です。以上
2010年09月08日
日本のONSENを世界のブランドへ・・・その一
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年9月5日 日本のONSENを世界のブランドへ・・・その一
シンポジウムの開催
9月の日本は猛暑続きで秋はまだまだ遠い先ですが、パリはもう10月以降の寒い気候になっています。その寒いパリからフランス人ジャーナリストのリオネル・クローゾン氏を迎え、東京で13日と14日の二日間、鹿児島県指宿温泉の白水館で16日「日本のONSENを世界ブランドへ」というテーマでシンポジウムを開催します。
今回の開催は私が代表を務める「経営ゼミナール」と、経営者へ情報提供業務を行っている「清話会」、それと指宿温泉の「白水館」との共催で進めていまして、開催のご案内を各地にいたしましたところ、お陰さまで高い関心を呼んでいます。
クローゾン氏招聘の背景
クローゾン氏を招聘しようと考えたきっかけは、昨年三月ミシュラン観光ガイドブックのグリーンガイド日本版の発売でした。それをパリの書店で求め、三ツ星となっている日本の温泉はどこかと探しビックリ仰天しました。日本では無名に近い別府の「ひょうたん温泉」が三ツ星になっているのです。一方、日本で成功して最も元気だといわれている、あの有名な群馬県草津温泉は無印です。
これは、どういう評価で星付けをしたのだろうかと疑問をもち、早速にひょうたん温泉に行き、温泉に入ってすぐに選定理由が推測できました。それは「欧米の温泉地はすべて共同浴場なので、ミシュランの星付け担当者も自らが持つ温泉常識感覚で、共同風呂のひょうたん温泉に三ツ星を付けた」と推定したわけです。
しかし、これはあくまで推定ですので、実際に観光ガイドブックの編集に携わる人物に直接会って、星付けの判断根拠を確認しようとパリで伝手を求めて探しているうちに、ブルーガイド(仏アシェット社発行旅行ガイドブック)の記者であるクローゾン氏と出会ったのです。
伊豆湯ヶ島温泉・白壁荘のシンポジウム
その後何回かパリに行くたびにクローゾン氏と会い、話し合っているうちに、彼の見解を日本で発表してもらうことが、日本の観光業にも、温泉業界にも役立つだろうと企画したのが今年の4月、伊豆湯ヶ島温泉・白壁荘のシンポジウムでした。
ところが、この時大事件が発生しました。それはアイスランドの大噴火です。この影響でヨーロッパのエアーは全便運航不能となり、クローゾン氏は来日できなくなり、白壁荘のシンポジウムを取りやめようかと思いました。
しかし、時代は変化しています。インターネットの素晴らしさで危機は克服できました。クローゾン氏から発表する資料を急遽送ってもらい、それをパリ在住の柳樂桜子さんがちょうど日本に滞留、彼女は逆にパリに帰れないということで、彼女にクローゾン氏の代講をお願いしたところ、分かりやすく、具体性ある内容での発表が行われ、参加者から大変高い評価をいただき、危機をチャンスに切り替えることができました。
関係者と接して感じたこと
今回、再びクローゾン氏のシンポジウムを開催するにあたって、その準備も兼ねて日本の観光業界や温泉業界の方々に多くお会いしました。
中には世界各地に出かけ、日本の温泉について講演をされている著名な温泉人もおられましたが、これらの人たちとお話をしていて、何か共通するものがあるなぁと感じました。
勿論、日本の温泉についてとても詳しい。また、欧米の温泉地についても結構詳しい。団体で研修目的の視察を主要温泉地に行かれているからです。
しかし、何か引っかかるものがあります。それは何だろうかと考えているうちにようやく分かったことがあります。
加えて、直接には接してはいませんが、新聞や雑誌に掲載されている日本の観光大国化への提言を書いている人たちの内容を読みましても、今回お会いした人たちと共通する感じを受けます。それは何か。
それは「欧米人も温泉についてある程度知っている」という前提で発言しているのではないかと気づき、ここに引っかかったのです。
欧米人は40℃前後のお湯に浸かるという習慣が全くないわけで、日本の温泉に来て初めて知る「未体験」の存在物なのですが、その事実を余り強く認識していなく、漠然とした感覚で受けとめているのです。
ヨーロッパの温泉利用者は人口の1%足らず
その実態を「笑う温泉・泣く温泉」(山本紀久雄著)から紹介します。
「ヨ-ロッパ(ロシアを除く)には1,500か所の温泉がある。ドイツに320か所、イタリアに300か所、スペインに128か所、フランスには104か所、この四か国合計で852か所となり、全体の57%を占めている。
ヨ-ロッパ全体で年間約1350万人がこの1500か所の温泉を訪れる。このうちドイツには1000万人訪問しているので、ドイツは全体の74%を占めている。イタリアには100万人で全体の7.4%であり、35万人から61万人がフランス・スイス・フィンランド・スペインに行っている。
ドイツの人口は8233万人であるから、人口の12%の人が温泉を利用していることになるが、他のヨ-ロッパ16か国の温泉を利用した人は350万人であるので、該当国の人口3億5000万人に対しては1%に過ぎない」
このようにヨーロッパではドイツだけが傑出した温泉利用国であり、その他の国の人々はヨ-ロッパの広い地域に、1500か所しかないのですから、温泉に行くということは一般的には遠距離の旅になり、温泉地は空気が清浄で緑多き山地や高地・丘陵地に立地していることが多いので、温泉へ行くには大変な費用と時間がかかります。
その上、ヨ-ロッパの温泉で入浴する目的は病気療養と保養の場ですから、「つかる」ばかりでなく「飲む」「吸入」「運動浴」「蒸気浴」「泥浴」などバラエティに富んだ場として確立しています。
また、温泉療養を受けるということは、健康保険制度の適用を受けることにつながっていて、近年、各国とも政府財政の苦境から、健康保険適用の範囲が制限されるようになってきましたが、基本的には温泉医の指導に基づいて、健康保険適用によって温泉療養をする場が温泉ですから、ドイツ人を除けば国民の1%程度しか温泉を利用する人がいなく、限られた人のものとなっているのです。
つまり、99%の人々は温泉を利用していないというのが実態なのです。
ある高名な政治家の質問
かつて南ドイツのフライブルグにある温泉で、日本の代議士数人を含めた団体が視察に来ているのと一緒になり、折角の機会ですから団長に申し入れし、視察に同行した経験があります。
このフライブルグの温泉はリューマチの治療専門です。代議士の中に現在自民党参議員会長の要職にある人物が、視察後のディスカッションで次の発言をしました。
「入浴施設を拝見したが、バリヤフリーになっていない、お年寄りが多いのでバリヤフリーにすべきでないか」と。
日本の有名な代議士発言ですから、ドイツ側は必死に考え、通訳を通じ質問の言葉は理解したが、全くその発言意図が分からず、20分程度会議は中断し、ドイツ側は通訳と立ったまま協議し続け、次のように解答しました。
「当温泉施設はリューマチの治療リハビリ・トレーニングの場なので、当然に段差がないといけないのです」と。
日本の政治家は日本の常識でドイツの温泉場を見て発言し、ドイツ側はドイツの常識で回答したのです。第三者的に見ている私は大変勉強になった事件でした。
世界から日本を見る
日本の観光業界と温泉業界人からも同様な感じを受けます。40℃前後のお湯に浸かるという特殊条件の温泉経験が全くない世界の人々に、日本に多く来てもらうよう対応策をつくるなら「世界から日本を見て」具体的に構築しないといけません。その事の研究が9月のクローゾン氏を迎えてのシンポジウムで、結果は次号でお伝えします。以上。
2010年08月20日
日本の観光大国化への提言(その二)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年8月20日 日本の観光大国化への提言(その二)
前号に続いて日本の観光大国化への提言です。
パリから電話
パリ在住の主婦から電話が度々あります。家内の長い友人ですが、今日は家内が旅行で留守でしたので、代わりに長電話受けました。
この夏、パリは寒いくらいとのこと、8月15日は最高17度・最低14度、16日も同じ気温、17日は19度―16度、18日は20度―12度です。
彼女は日本の暑さをよく知っています。というのも息子と娘が夏休みに日本に来たのです。
小平市の友人所有の空き家を拠点に、毎日、西武新宿線で新宿を通って東京見物、結果はすっかり東京の魅力の虜になり、パリに戻ってからも日本の暑さに参ったとは一切言わず、「もう一度日本に行きたい」と言い続けているそうです。
フランスの少年少女から東京を見ると、我々が見慣れている繁華街の新宿・渋谷・原宿のようなところはパリにはなく、魅力に溢れているのです。同様なことは他の国の人からもよく聞きます。東京の街中は世界の観光名所になっているのです。
そういえば、山岡鉄舟研究会で上野公園探索会をしましたが、公園内にも徳川将軍の墓がある寛永寺墓地内にも、外国人が大勢地図持って歩いていました。これは日本人がパリのモンバルナス墓地を訪ねるのと同じ感覚なのでしよう。
ノルウェーから日本を見ると
ノルウェー水産物輸出審議会日本事務所代表のハンス・ペター・ネス氏が、日本経済新聞で日本のイメージについて次のように述べています。(2010.7.26)
「ノルウェーの平均的なビジネスマンで日本の政治・経済、スポーツの話題を話せる人は少ない。日本へ
の興味の対象は、最新の話題やニュースといった時事的なものではなく、恒常的な、いわゆる日本的なもの。例えば食べ物、電化製品、車、伝統文化、マンガだ。
ノルウェー人がとても良いイメージを持っているものとして、まず日本食がある。だれもが寿司を思い描き、多様な食文化と比べると知識が偏っているのだが、逆の見方をすれば、食に関するビジネスでのポテンシャルが大きいといえる。
日本製品が海外で信頼を築いている理由として、質の高い電化製品と車の存在がある。電化製品では韓国勢が売り上げを伸ばそうともメード・イン・ジャパンに対するイメージが揺らぐことはなく、日本車の性能や品質、技術力の高さに魅力を感じ日本車メーカーをひいきにするノルウェー人も多い。
近ごろ、急速に人気が高まった日本製品としてはマンガがある。子どもや若い人たちへの影響力の高さには驚くばかりだ。ある15歳の男の子は日本に行きたい理由として、マンガを挙げた。
日本に対する好意的なイメージは大いに歓迎したい。興味がより深い知識への入り口となり、日本企業が製品やサービスを展開する有効なきっかけとなればよい」
日本の魅力
この内容は私が世界各国を頻繁に訪れ、その国の人々と話し合う中で感じる日本へのイメージと正に同じでして、これが日本への外国人の平均的な概念と考えてよいと思います。
一般的な日本人は、自国の政治や経済について、情けないとか、だらしないとか、元気ないといって悲憤慷慨している人たちが多く、先日もお会いした一部上場企業幹部も「日本は悲劇的だ」と発言していました。
だが、世界の人たちからの日本への関心は、そんな政治や経済のことではなく、日本人の生活に密着したモノに好意的な感覚を持っているのです。この事実を、しっかり日本人は確認しなければいけません。考えてみれば日本の魅力はいっぱいあります。
日本が持つモノで世界的なレベルで光彩を放っているものに、茶道、華道から始まり、工芸、織物、染色。最近では建築家が世界をリードし始め、さらには和歌、連歌、俳諧、古典文学の数々。次いで日本料理、日本家屋、日本の祭りとかの年中行事といった生活文化。まだあります。能、狂言、歌舞伎、文楽という舞台芸術。柔道とか剣道、空手、合気道、まだたくさんあるでしょう。
日本人の生活に密着していて、海外で全く知られていない事例を、敢えて挙げれば「童謡・唱歌」くらいではないでしょうか。子供時代の郷愁を誘う「童謡・唱歌」が世界に人々に受け入れられていないのは不思議な物語です。
日本は好印象の国
ユーロ大統領のファンロンバイ氏は俳句が趣味ということは有名ですし、パリには「SUZUKAKE NO KAI」という著名人で構成する日仏親睦団体があり、その一人のお宅に伺って、屋上の庭園を拝見したときには驚きました。2000年に二カ月に渡って北海道の礼文島、利尻島から沖縄の与那国島まで回って、日本の草花を採集し、それで屋上に日本庭園を造っていて、この手入れが最高の楽しみというのです。また、書道も好きで、書道展にも出品するほどの腕前です。
ドイツの各都市には「独日協会」があり、毎年一回持ち回りでドイツ全国大会を開いているほどです。何度かこの独日教会に参加しましたが、とにかく日本好きが集まっていて、日本のイメージは好印象で受け取られています。
一部上場企業幹部による「日本は悲劇的だ」という発言、これとはまったく異なるのが、世界から見る日本なのです。
レスター・サロー氏の見解に対して
ところで、日本人は新しいビジネス構築が下手だとマサチューセッツ工科大学名誉教授のレスター・サロー氏が以下のように述べています。(日経新聞2010.8.1)
「日本に必要なのは新しい企業だ。日本のほとんどの新興企業は、米占領下の第二次大戦直後に生まれた。2000年以降に誕生した企業をいくつ挙げられるか。米国では00年以降に誕生した企業が経済を下支えしている。米国文化の方が経済成長に適している。我々は産業主体の経済から知識主体の経済に移っている。ジョブズCEOやビル・ゲイツ氏、ウォルト・ディズニー氏がつくり出すような知識だ。人々は楽しいものには金を払う。今の日本にはあまり楽しいことがない」
この発言は傾聴に値します。成程と思いますが、一部は的外れであるとも思います。例えば、前号で紹介したNYのイーストビレッジ地区の屋台村、「B級グルメ」を楽しみたいから大勢集まってくるのです。
日本社会には身近に楽しいことがたくさんある実例がNYの屋台村ですが、このようなことは既にブラジル・サンパウロでは昔から常識です。サンパウロの日本人街リベルダージ駅前の広場、ここは日曜日になると屋台がたくさん出ます。ヤキソバ、今川焼き、お好み焼き、焼き芋、天ぷらなど。観光客よりは地元サンパウロ住民の方が多く、広場を歩くのに苦労するほどの賑いです。「B級グルメ」はブラジルで昔から大人気となっていたのです。
システム化が課題
この「B級グルメ」、日本の各地で最近大人気だと、前号で岡山県日生町「カキオコ」の事例をお伝えし、海外でも同じく人気になってきつつあります。
しかし、ここで心配なのは、「B級グルメ」ブームを、このまま個々の民間業者に任せたままにしておくと、日本国内向け、日本人対象にだけで終わる可能性が高く、世界中に「B級グルメ」を発信できず、海外に大きく発信しないから、レスター・サロー氏は知り得ず「日本にはあまり楽しいことがない」と指摘受けることになるのです。つまり、日本の観光財産に引き上げられません。
既に日本食は世界で受け入れられ、次は「B級グルメ」まで海外で人気となりつつあるのですから、その魅力を海外へ発信し観光客を増やすこと、それを折角に観光庁があるのだから、国が乗り出して観光客誘引システム化策をつくるべきでしょう。
観光庁が予算化して進めた電信柱を地下に埋めることが、観光客誘致の目玉だという貧弱な発想ではダメだと思います。世界から見た日本の魅力実態を知れば策はいくつも考えられるのです。
しかし、策を考えようとするならば前提条件があります。思考方法の転換です。日本人が大得意な「日本から世界を見る」という思考でなく、「世界から日本を見る」という発想に転換しなければならず、これが観光庁の仕事ではないでしょうか。
日本の「普通」を外国に「魅力」として紹介するシステム確立、これが観光大国化への新しい策です。以上。
日本の観光大国化への提言(その一)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年8月5日 日本の観光大国化への提言(その一)
蚵仔煎・オーアーチェン
世界には日本と異なる習慣が存在する。国が違えば生活習慣が異なるのは当然で、何も不思議ではないが、その違いを現地で体験すると、改めて驚くことが多い。
日本では牡蠣は秋口から春までの寒い時に多く食べ、スーパー店頭では夏場に牡蠣はおいていないのが当たり前である。
ところが、隣の台湾では牡蠣は夏場に食べるもの。台湾で牡蠣を食するサイクルは台風が基準となっている。台湾は太平洋と南シナ海・東シナ海・台湾海峡に囲まれている島なのでので、台風が毎年多く直撃する。従って、9月は海が大荒れになるので、牡蠣養殖作業はできない。
そこで台風が去った10月から3月まで種付けから養殖作業の期間となって、牡蠣を食べるのは4月から8月の間となる。このようにすべては台風という自然条件によって、春から夏場にかけて牡蠣を食べることになる。
ここが日本と大きく違うところだが、台湾環境条件に合致しており、なるほどと思いつつ、この暑い中、台湾へ「蚵仔煎・オーアーチェン」、ガイドブックに「小ぶりの牡蠣が入った屋台定番料理のオムレツ。甘辛のタレをかけて味わうもの」と書かれているが、実際には牡蠣のお好み焼きに該当するものを食べに行った。
まず、台湾で最も有名な牡蠣産地の、台湾海峡に沿った海岸・雲嘉南濱海国家風景区の東石牡蠣養殖場に行き、そこで漁師さんに船を出してもらい筏のところまで行き、海から引き揚げた牡蠣をビニール袋に入れ持ち帰って、宿泊する台南市の一流ホテルで蚵仔煎を作ってもらおうと依頼してみた。
因みに、このホテルは欧米式の階数表示である。17世紀中期のオランダ統治時代に台南に拠点を置いた関係で、日本の一階は地上階表示となっているが、そのホテルからそのような大衆的料理は扱わない、という丁重なお断りを受け、仕方なく一般大衆が食する下町地区にタクシーで向かって、海鮮レストラン永上海産碳(たん)烤(こう)という店に入った。この店はどこにもドアがなく、道路との境がよくわからない状態の店、隣も道路の向こう側の店も同様の地区で、当然に、地元の人の集まるところ。
ここに牡蠣を持ち込み、ガイドが紹興酒と屋台で買ってきた魚を煮込んだスープみたいなものも持ち込んで、蚵仔煎を料理してもらいたいと頼むのだから、こちらも相当の図々しさである。近くで爆竹が派手に鳴っていて、支払いはカード出来ず現金のみであったが、牡蠣のお好み焼きなら日本でもあるなぁと酔った頭で思いだした。
「カキオコ」
それは「カキオコ」である。牡蠣のお好み焼きを略すると「カキオコ」になり、それは岡山県備前市日生(ひなせ)町の「B級グルメ」だという。
「B級グルメ」とは何だろうと、台湾から戻って早速日生町の観光協会を訪れた。竹林沙多子さんが一人で頑張っている観光協会で「B級グルメ」お聞きすると、それは贅沢でなく安価で日常的に食される庶民的な飲食物とのことだと、ご教示受けた。
なるほどとようやく理解して、次にジューシーなカキの風味とおねえさんとの楽しい話が味わえるまち『日生』」と書かれたカキオコ店のマップをいただき、説明を受けていると、次第にカキオコへの期待が高まって、ちょうど昼時、お腹が鳴りだしたので、マップに記載されている「タマちゃん」に向かった。
JR日生駅の次の駅、寒河(そうご)近くに「タマちゃん」はあった。自宅を改装した店づくりでオープンして8年目。建築業から転身した両親と息子夫婦で経営している。道路に面した自宅スペースの前に「日生カキお好み焼き研究会」の幟が立っている。へえー牡蠣も研究会があるのかと思いつつ、店に入って早速にカキオコを注文。
すると、この店の息子らしき若き男性が、大きな鉄板に最初はサラダ油で、最後にオリーブ油を加えると加熱が高く味が締まるのがコツだと解説しながら、冷凍ものの日生特産の肉厚な牡蠣を中に入れて焼きだした。見ていると、一般的にお好み焼きは焼きながら上からフライ返しで抑えるが、ここでは抑えない。ファっとしたものにするためと、親父が婿なので抑えられないという意味もあると笑いながら。
その厚みのある表面に、自慢の自家製のソースと、アンデスから取り寄せた岩塩とで、半分ずつ味付けする。二つの味が味わえるから試してくださいという言葉に、期待のカキオコを食べてみた。一口食べてみて美味いと感じる。それも上品な味である。店舗づくりは田舎風だが、味は都会風だと評すると、息子はまたニコッと笑う。価格は900円。
実は、この日生町でカキオコがはじまってから、日はまだ浅い。平成13年(2001年)の冬、赤穂市から岡山市の県庁へ電車通勤しているひとりの人物が、偶然に日生で昔からの「カキお好み焼き」を食べたことをきっかけに、日生在住の通勤仲間や他地域の仲間に呼びかけて「カキオコ食べ歩き調査」を実施し、翌年の1月に「日生カキお好み焼き研究会(略称:カキオコ研)」を立ち上げ、日生町に活気を取り戻そうとはじめたのである。今では各地のB級グルメフェスタに参加するほどの知名度となり、観光協会の竹林さんに全国から問い合わせが来るほどの盛況さとなった。
これは日生町の海が所属する、播磨灘牡蠣を活かした地域起こし成功例であるが、このような事例は全国に数多くあるに違いないと、カキオコの経験で思った。
「B級グルメ」
そう思っていたところ、近所の自動車ディラーから連絡があり、ハガキで応募した賞品が当たったというので、受け取りに行くと埼玉県鳩ケ谷市の「焼うどんソース」を「B級グルメですが」と言いながら渡された。そこで早速、このソースをかけて食べてみると、ブルドックソースも真っ青というほどの美味さである。以後、この「焼うどんソース」を専ら愛用している。
これで分かったことは日本全国各地に「B級グルメ」がたくさんあると推定できることで、日生町のパンフレットにも「姫路おでん」「高砂にくてん」「津山ホルモンうどん」「府中焼き」「出雲ぜんざい」等が掲載されている。
「B級グルメNYで人気A級」
これは日本国内だけのことだと思っていたら、「B級グルメNYで人気A級」(日経新聞2010.8.1)が掲載された。
内容は「7月中旬の週末、マンハッタン南東部のイーストビレッジ地区の一角に屋台村『ジャパンタウン』が出現した。並んだのは、お好み焼きやたこ焼き、焼き鳥、ラーメン、ギョーザなどを売る約40店。平均5ドルの日本食を目当てに、主催者の推定では5万人もの人々が集まった。あまりの混雑に警察が出動、入場を規制するほどだった。 『ピザみたいで好き』と割りばしでお好み焼きを食べる女性(22)。ニュージャージー州から友達とやってきたという高校生、トム・ヘイドンさん(16)は焼き鳥が好物だという。『日本のアニメも好き。日本に旅行するのが夢』と目を輝かせた。・・途中略・・
日本の『ソフトパワー』とされるアニメやグルメ、ストリートファッションなどの情報はインターネットを通じて米国の若者らに時差なしで届く。日本への興味は、より生活に密着した『日常』に向かっている。
日本政府観光局(JNTO、東京)の2009年の調査によると、日本を訪れた米国人観光客が訪日前に期待したこと(複数回答)は『日本の食事』が歴史的建造物などを抜き、初めて首位に浮上。すしやてんぷらだけでなく、おにぎり、そば、焼き鳥など庶民的な味への関心が高まっていることも明らかになった」
この内容はよくわかる。筆者がNYに住む米国人親娘を荒川区町屋の普通の居酒屋へ連れて行ったところ、店に入る前は「今日は昼食が遅かったからあまり食べられない」と言っていたのに、実際に料理が運ばれてくると「こんなに美味い食べ物は初めて」と、次から次へと出されたものを全部食べてしまったことがあった。この時に、日本人にとっては普通の食べ物が、外国人には宝物になっていると実感した。日本の街中には、日本人は分かっていないが、外国人とって魅力的なものがたくさんあると感じたのである。
この続きは20日号。なお私が司会を担当する清話会主催シンポジウム「日本を観光大国化するためには」を9月14日(火)14時~16時30分、会 場 お茶の水ホテルジュラク2階「孔雀」で開催します。ご興味のある方は清和会にお申し込み願います。
http://ameblo.jp/seiwakaisenken/entry-10598689152.html 以上。
2010年07月20日
歴史的思考力を磨こう
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年7月20日 歴史的思考力を磨こう
とうとつ発言
菅総理の参院選時における「とうとつ」消費税発言について、菅首相も「とうとつ」な感を国民に与えたと陳謝しましたが、身内からも非難が続いています。
7月16日のテレビ朝日で民主党の枝野幹事長が「消費税に触れるなら慎重にやってください」と伝えたが、と発言。
首相の経済政策ブレーン、内閣府参与の大阪大学小野善幸教授も「参院選での菅首相の消費税還付に関する発言は丁寧さが欠けた」との認識を日本記者クラブで会見表明。
これに関する話題は世の中に溢れるばかりです。だが、選挙が終わってからいくら反省しても議席数は戻ってこず、菅政権運営は梅雨が明けないままの状態になりました。
クリンチ作戦
ボクシングの試合でよく見られるのがクリンチです。クリンチとはどちらかといえば負け気味の選手の方から仕掛ける抱きつき作戦、いわば弱者の戦術です。菅首相は自民党が掲げる消費税10%公約に飛びつき、相手を抱きこもうとクリンチ戦術を展開したのですが、これが結果的に大敗北の要因となりました。菅首相は野党時代の癖が残っていたのでしょう。弱者の戦術に長け、政権党としての強者の戦術に慣れていなかったと推論します。
奇兵隊より大村益次郎
振り返ってみれば6月8日、菅内閣がスタートし、菅首相は記者会見で「奇兵隊内閣」になりたいと述べました。この発言について世間はあまり関心をもちませんでしたが、これは問題を残した発言の第一歩と思っています。
菅首相が、同じ出身地の長州藩・高杉晋作を、尊敬する人物と挙げ、高杉晋作が編成した奇兵隊を持ちだすのは、一見、何も問題がないように思われます。しかし、高杉晋作は奇兵隊をつくり倒幕の狼煙をあげた、という意義深い歴史的事実から考えれば、菅首相が鳩山前首相から引き継ぐという政治状況下では、適切な発言ではなかったと思います。
昨年8月30日の衆議院選挙で、民主党は一つの党が獲得した議席数としては過去最多となる308議席を獲得したことで、いわば既に自民党倒幕は終わっているわけです。
問題はその倒幕後の政権運営がしっかりしないことから、鳩山前首相が辞任し、菅首相になったのですから、この政治状況を踏み考え、見習うべき歴史上の人物を上げるとするならば、奇兵隊より大村益次郎になりたい、というのが筋だったと思っています。
大村益次郎も長州出身、長州戦争・戊辰戦争の作戦指導者で、近代明治時代の礎をつくった人物、特に優れていたのは彰義隊をわずか一日で壊滅させた上野戦争の緻密な計画に基づく作戦と指揮の見事さで、その緻密さと計画性について菅首相は学ぶべきでしょう。
歴史的思考力
考えてみれば、鳩山前首相も歴史的思考力が欠如していたと思えます。山内昌之東京大学教授は沖縄普天間基地問題に対し「歴史的思考に基づく常識力を発揮すれば、沖縄県民と米国政府と連立与党社民党のすべてを満足させる解の発見は絶望的なほど難しいか、不可能なことがすぐにわかったはず」と述べています。
ここでいう歴史的思考力とは、記録された歴史の事実から説き起こし、今の現実で発生している概念や特定の状況に適合させ、考えられる力のことです。
また、理想を性急に実現できるのは、革命期に限るわけですから、常識的に考えれば、昨年8月の自民党を倒した後は、緻密な計画性に基づく政治運営が求められていました。
司馬遼太郎のアームストロング砲説
司馬遼太郎は大村益次郎を「花神・かしん」で書きました。NHK大河ドラマでも放映されましたから、大村を知ろうとする人はたいがい「花神」を読みます。
この中で大村の緻密な計画性の事例として、幕末の上野の山で行われた、彰義隊壊滅の作戦を幾つか取り上げています。例えば、戦況ニュースというべき戦陣新聞「江城日記」を大村が自ら書き、毎日発行し、情報の一元化を図った事などです。
中でも「花神」で最も強調している成功作戦は、アームストロング砲の威力で彰義隊を壊滅させた事です。このアームストロング砲は佐賀藩が所有していた、後装式砲(後ろから弾を込める)ライフル砲を改良したもので、伝説的に語り草になっている砲です。
確かに、午前中までの戦いは彰義隊が優勢で、上野の山の諸門とも官軍を寄せつけませんでした。その苦戦の戦況を一変させ、彰義隊が一気に崩れたのは「花神」によると、午後から発射されたアームストロング砲の威力であり、これで彰義隊は動揺し、士気を落とし始めたその時に、薩摩兵が主力を黒門口に前進させ、防御を突破したというのです。
アームストロング砲への疑問
だがしかし、常に世には異説があります。それを伝えるのが「真説上野彰義隊 加来耕三著 NGS出版」です。この中で加来耕三氏は
「これまで世に出された彰義隊関連の書物は、例外なく上野戦争の勝敗の要因に、このアームストロング砲の脅威を掲げているが、黒門口に一発の砲丸すら当たった形跡がないように、不忍池を越えて二、三の子院を破壊したとしても、その実、彰義隊が夜までもちこたえられないほどの脅威ではなく、事実は覆面部隊の投入だった」と述べ、それを証言しているのが彰義隊の菩提寺である荒川区の円通寺住職の乙部融朗氏の以下の談話です。
「現在、円通寺に残っている黒門を見ても、大砲が当たって壊れたような個所はありません。ただし、小銃の弾痕はかなりたくさん残っています。黒門は上野の山の最前面にあるので、大砲でいちばん先に撃たれて当然のはずですが、円通寺の黒門が事実を証明しています」と述べています。
覆面部隊の投入
円通寺住職は続けます。「大村益次郎は卑怯な戦術を用いました。秘密にコトをおこなうため、手勢の長州兵を川越街道へ回し江戸を離れさせ、日光街道の草加へ大迂回をさせ、前の日の十四日には千住の宿に泊まり、翌五月十五日戦いの当日の昼ごろ、会津の援兵と称して上野の山に、今の鴬谷駅のあるところにあった新門から入りこんで、文化会館の北寄りのところにある磨鉢山という古墳のところまで来たときに会津の旗をおろして、代わりに長州の旗を掲げ、黒門口を中から撃ったので、山内は大混乱。こうして死ぬまで戦うつもりが、潰走しなければならなくなり、雨の中、昼を少し過ぎたころには、あっけなく崩れてしまいました。これが戦いの模様でありました」と。
現場で確認してみた結果
彰義隊が壊滅されたのは旧暦慶応四年五月十五日、新暦では七月四日になりますので、先日、この暑い盛りの日に鉄舟研究会メンバーと上野公園内を探索してみました。
まず、ことごとく焼失した寛永寺で唯一残った、輪王寺宮法親王が居住していた寛永寺本坊表門のところに行って、門を子細に見ますと、確かに銃弾の跡がいくつも残っていて、激しい戦いが行われたことが分かりますが、アームストロング砲が当たったと思われる傷跡はありません。
西郷隆盛銅像と彰義隊の墓の先に清水観音堂があり、堂内に明治期の画家五(ご)姓(せ)田(だ)芳(ほう)柳(りゅう)の描いた「上野戦争図」があり、その脇に実物の砲弾が展示され、これが椎ノ実型の砲弾であり、これが本郷台から発射されたアームストロング砲とすれば、大きさから見て木製の寛永寺本坊表門なぞは一発で破壊されたと思われます。
ここで大村益次郎という類稀なる人物の特性、それは優れた計画性にあるわけで、その資質から考えるなら、事前に佐賀藩のアームストロング砲を試射したはずで、その結果、アームストロング砲の実力を判断し、これでは決定的な壊滅対策にならず、そこで覆面部隊投入を考えたと理解するのが自然だと結論付けしました。
歴史的思考力を磨こう
大村は作戦を組み合わせできる優れた人物です。勝利のためにアームストロング砲だけに頼らず、敵の裏をかく覆面部隊作戦は、緻密な頭脳から引き出された当然必要な作戦であり、彰義隊がそれらを予測し対応をとらないのが問題なのです。過去の歴史的事実を把握し、そこから説き起こし現実の状況に適合させるという歴史的思考力が、今の時代を運営するリーダーには特に大事で、歴史を実践的に学ぶ必要性を改めて感じています。以上。
2010年07月06日
日本の実態は自らが調べる事
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年7月5日 日本の実態は自らが調べる事
参院選挙
参院選の候補者が激しく動き回っています。7月2日、東京ドームの巨人対阪神戦に行きましたが、JR水道橋駅出口には、中畑清、江本孟紀、西村修というスポーツ関係の候補者が街頭演説を競い合っていました。
また、山手線の中では、隣りに座った80歳の女性から小泉進次郎の顔写真が写った団扇をもらいました。ご本人は巣鴨のとげぬき地蔵にお参りに行き、そこでたくさんもらってきたからと、こちらに渡してくれたのです。さらに、自宅にも各所から電話がかかってきます。もう10年以上も年賀状も含め何も連絡のなかった元部下の女性、昔住んでいた所の真向かいの人、故郷の親戚から、それぞれ最初に無駄話をして最後に選挙の話になり、誰だれを頼むというストーリーは変わりません。
議席数
日経新聞の参院選情勢6月26日では、民主党は「改選54」を上回る勢い、自民党は「40台うかがう」というものでした。
政治学者の福岡政行氏から6月23日にお聞きしたものは「民主党は50議席に届かない」というもので、その理由として次の五つを挙げていました。①一人区は過疎地域が多く民主党不利、②統一地方選挙の年は保守層が自民党へ、③地方の景気が低迷、地方票が入らない、④消費税アップ発言が問題、⑤前回衆院選のマニフェストがでたらめ。
みんなの党幹事長の江田憲司氏からも、6月23日にお聞きしましたが「民主党の過半数はなく、参院選後は大混乱となり、政界再編成となる際に、小沢一郎は必ず自民党から同調者を募り民主党を離れる」というものでした。結果はどうなるかですが、それに我々が一票として参加している事をしっかり認識したいと思います。
公務員にボーナス支給
6月30日に国と地方の公務員に夏のボーナスが支給されました。
総務省によると管理職を除く一般行政職の国家公務員平均支給額は57万円との事で、平均年齢は35.5歳、昨夏より約4000円0.7%増という事でした。
この金額を聞いてどう感じるか。それは人それぞれの立場で異なるでしょうが、随分民間実態とかけ離れた支給額と感じる人は多いのではないでしょうか。日本経済はこのところ少し良くなりつつあるものの、一般企業は苦しい経営を余議されています。ですから、ボーナスはそれほど増えていない、減額されたままというのが実態でしょう。
一般企業のボーナス支給額
公務員が高いと感じるのは、一般企業のボーナス支給額の実態を入手したからです。知り合いの会計事務所、ここは545社を顧問会社にしている大手事務所ですが、その社長が顧問会社のボーナス一人当たり支給額を一覧表にして提供してくれました。
それによると、平均額で平成21年夏季ボーナスは23万円、平成21年冬季ボーナスは25万円です。
11業種別に算出された表を見ますと、最も多いのが不動産業で50万円(平成21年冬季)で、少ないのは飲食業の7万円(同期間)です。
公務員ボーナスとは相当の支給差があることが分かります。では、どうして公務員がこれだけ高いのでしょうか。我々の税金から支払っているのに・・・。
ボーナスは業績評価
昔、故郷の母親から公務員は給料が安いから勤めるな、と言われた事を思い出しました。だが、今のボーナス支給額を見る限り、公務員の方が高いというのが実態です。また、民間企業のボーナスは業績による成果配分ですから、経営が順調な時は多く支給され、今のように苦しい時は少なくなります。これが当たり前です。経営が難しい時にも、景気の良い時と同じ支給額を維持すれば、企業そのものが経営危機に陥ります。
こんなことは子供でも分かる事ですから、日本経済の状況と財政赤字の実態を考えれば、民間の二倍にも及ぶボーナス支給は考えられない額です。
しかし、実際に6月30日に公務員全員に大きい額が支給されました。何故か。それはルールに従っており、正当だと認識されているからです。
人事院勧告
どうして多額のボーナスが公務員に支払いされるのか。それは簡単な理由です。人事院の勧告で行われるのです。
では、人事院勧告はどういう金額でなされたのでしょうか。それを人事院が発表しているサイトで見れば一目瞭然です。
人事院勧告の基になっている民間ボーナスは、何と平成21年の夏季で729,596円(事務・技術等従業員)となっています。
つまり、6月30日に公務員全員に支給された57万円より21%も低い額となっているのです。民間企業に勤務する人達より、公務員は低い金額を支給しているという事になっているので、正当なボーナス金額ということなのです。
算定の基礎はどこから持ってきたのか
問題は人事院が調査算定した企業の実態です。どういう企業を調査対象としたのか、そこが関心事です。実は、人事院の調査は「企業規模50人以上で、かつ、事業規模50人以上の民間事業所から層化無作為抽出した事業所を対象」に9747カ所を調べているのです。この企業数の中には従業員1000名以上のところが2731カ所含まれていて、当然に大企業ですから、給料もボーナスも高い水準になっていると推定できます。
しかし、日本全国の中で事業所は588万カ所(平成18年)あるわけで、ほんのわずかの対象しか調査せず、加えて、従業員1000名以上の大企業が28%を占める調査ですから、当然に上方シフト、つまり、支給額は高いところに調査結果が決まります。
実際に街中にたくさん存在する飲食店とか美容院のようなところを、もっと多く入れていくなら、この人事院勧告基礎データにはならないわけで、そうすれば公務員のボーナスはもっと少なくなります。
これは給料も同じ算定方法ですので、今や民間ベースより公務員の方が高いという実態になっているのです。
公務員人件費は35兆円
政治学者の福岡政行氏が出版した「公務員むだ論」に公務員人件費は35兆円とあります。出所は財務省の「日本の財政を考える(2007年5月)」であり、これに独立行政法人や公益法人、地方の第三セクターの人件費を加えると37~38兆円と述べています。
平成22年度末の税収は約36兆円ですから、国民全体で納める税金が全額公務員人件費に支出されているという結果になります。
この実態を調べてみて、日本の高コスト体質の本質は公務員の人件費にあることが分かりました。大変な国家運営をしてきた事になります。政治家の責任でしょう。
問題は国民であり調査方法にある
日本はいつの間にか財政赤字は世界一、公務員だけで国家を食いつぶしている、という実態になっているわけですが、どうしてこうなったのか。
様々な要因があると思いますが、人事院勧告に見られるように、日本国の実態を網羅しない調査結果で判断しているという大問題があります。それが人事院勧告の基礎データと街中の会計事務所によるデータとの格差です。一般の街中の企業給料は人事院調査の半分なのです。ですから、正しく妥当に調べれば公務員人件費は当然に下がる仕組みになっているのです。調べていないのではなく、調べる対象が間違っているのです。
ということは、日々マスコミで報道される経済実態も、集めやすい大企業中心データから構成・編集された内容になっている事を示しています。
つまり、我々は大企業が提供するデータ中心で編集された記事、それを社会の事実として受け止めている、という大きな問題点をもっていることを改めて考える必要があります。
ですから、社会の実態を把握したいならば、マスコミデータに加えて、現場で調べたものを加えて判断する、という習慣を身につけたいものです。参議院選挙が近づいた機会に、もう一度我々の判断基準について振り返ってみることが大事ではないでしょうか。以上。
2010年06月21日
2010年6月20日 ユーロ安の円高をどう考えるか
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年6月20日 ユーロ安の円高をどう考えるか
イタリアからのメール
今回のギリシャ危機に当って、ギリシャに住む主婦からいただいたメール内容は前号でご紹介しました。同タイミングでイタリアからもいただきましたので、ご紹介します。
「ギリシャは大変そうですが、イタリアの財政は今のところ問題なし、ということで、特に変化はありません。ユーロが大幅に下がったこの機会を利用して、輸出を増やし、経済回復に拍車をかけるべきだ、と先日、プローディ前首相があるテレビ番組で力説されていました」・・・ボローニャの主婦。ギリシャとは大違いです。
スペインからのメール
同じタイミングで、スペインからもメールをいただきました。
「スペインは昨年から失業率が急上昇し、財政赤字も増加。7年目に入ったサパテロ社会労働党政権も、遅まきながら経済政策に大きなメスを入れて★ 公務員の賃金カット(12~15%)★ 社会年金・恩給の一部凍結★ 定年退職年齢の引き上げ(65歳から67歳)★ 幼児・子供への政府援助金の一旦中止など、右傾化した経済政策に方向転換し、来月国会でそれが承認されたらすぐ公務員がストライキを実施すると発表。
そしてスペインの2大労組(労働総同盟=UGT; 社会党系と労働者委員会=CC.OO.共産党系)がゼネストも辞さないと発表しているが、『このような時期にゼネストなどやっている場合じゃない』という声も多いし、国民やマスコミも余り支持していなくて、ギリシャのようなゼネスト、社会問題にはならないと思う。
デパートやスーパーでの一般市民の購買力も落ちていないし、夏のバカンスも財布を引き締めながらも、8割以上の国民がバカンスに出かけるとアンケート調査で答えています。
大多数のスペイン人は根っからの楽天的な性格で、何でもポシティブに考えるんです。マドリードの中心部を歩いていると、『経済危機なんてどこ吹く風?』という感じです」・・・マドリード在住のビジネスマン。これもギリシャとは大違いです。
ギリシャ人から聞いたこと
在日ギリシャ大使館公式通訳の方に、昨年3月の経営ゼミナールでギリシャ状況をお聞きしました。その際に述べられたことが記憶に残っています。
「2001年にユーロを導入したが、これを機にギリシャは急激な物価高に見舞われた。例えば、ユーロ導入前のギリシャの通貨はドラクマで、その頃はギリシャの朝市などでは『たったの100ドラクマ』という謳い文句があったのだが、しかし、ユーロ導入とともにそれが『たったの1ユーロ(=340ドラクマ)』になって、通貨切り替えの際の便乗値上げが横行し、その後も物価は上昇し、現在では日本とあまり変わらない物価水準となっている。
一方、賃金は物価上昇に合わせて賃上げされず、ギリシャの2005年の最低賃金は668ユーロ(約87,000万円・当時レート130円)で、EU加盟国の中で7番目の水準となっている」と。
このようにユーロ圏に加盟したが、インフレとなり収入は増えず、国民生活は一段と苦しくなった状況、また、ギリシャの経営者は「私たちはギリシャをバルカンの中心地にしたいという気持ちが強い」と述べましたが、これは結局、ギリシャ人自ら独仏などとの競争を諦めて、バルカン半島内での経済国になりたいということを表していると理解しました。つまり、EUユーロ圏に入ったが、意識はバルカン半島国家であり、国境を接しているアルバニア、マケドニア、ブルガリア、トルコという近東(Near East)諸国と関係を深めていると認識できます。
現代のギリシャ人とは
現代のギリシャは、古代ギリシャ人の直系子孫として1830年、オスマン帝国から独立を果たしましたが、独立早々ドイツの学者によって「いまのギリシャ人には古代ギリシャ人の血が一滴も流れていないと書かれてしまったときには、国じゅうに衝撃が走った」ということがありました。(内山明子著 国立民族学博物館『季刊民族学』123号2008年新春号の『ギリシャ・ヨーロッパとバルカンの架け橋』)
ギリシャの歴史は占領され続けた苦しみの連続です。その中で最も外国の支配が長かったのはトルコからで、アテネが1458年にオスマンによって支配され、1503年にはギリシャ全土が完全にオスマン帝国の州となり、キプロス島も1577年にオスマン帝国下に入りました。
したがって、トルコ人のギリシャ支配は、コンスタンティノーブル没落から1821年の反乱まで、約400年近く及んでいます。この期間は「トルコのくびき」と現代まで語り継がれるように、ギリシャは暗黒時代を過ごし、支配されてから1700年までにギリシャ人の人口が四分の一も減少した事実、それは征服下で厳しい圧政が行われたことを証明し、ギリシャ人のトルコ嫌いの原点になっています。
しかし、この約400年の間に、ギリシャ人とトルコ人との血のつながりは相当に進んだと想像できます。ご承知の通りトルコ人は黒髪です。本来、金髪であるギリシャ人とトルコ人との血のつながりの結果はどうなるか。それは黒髪となって現代に蘇っています。
2008年のアテネ訪問時、多くの家庭で子ども達と接しましたが、兄弟姉妹でありながら髪の毛の色が違っているケースが多く、同じ両親から生まれたのに、一人は金髪、もう一人は黒髪であり、顔は似ているが、髪の毛の色が異なると、一見別人の如く感じます。
これらから判断しますと、現代のギリシャ人は古代ギリシャ人の血にトルコ人が混じっていますし、その他の国の支配も受けているのですから、2500年という時間経過で、ドイツの学者の見解に頷かされる可能性が高いのです。
ギリシャの独立経緯
さらに、ギリシャ独立の経緯を内山明子氏の論文から整理しますと、
① 古代ギリシャへの関心が高まっていた十八世紀のヨーロッパでは、古代遺跡を巡るためオスマン帝国を訪れる旅行者が増えたが、彼らはそこに暮らすギリシャ語を話す人びとを古代ギリシャ人の末裔とみなし、その民族名称であるエリネス(ギリシャ人)の名で呼んだ。
② 一方、オスマン帝国内でギリシャ語を話す人々は、自分たちをギリシャ人ではなくローマ人(ロメイ)とみなしていたが、ヨーロッパ人の古代ギリシャ熱に接したことで、自分たちを古代ギリシャ人の末裔として自覚しはじめ、ギリシャ人としての民族意識を高め独立意識を強くし、1830年ギリシャはオスマン帝国から独立した。
③ ヨーロッパの協力を得て独立したギリシャは、外国から国王としてバイエルン王ルードヴィッヒ一世の息子、ヴッテルバッハのフリードリッヒ・オットーを迎え、そのオットーがギリシャを追われた1863年には、デンマークの王家出身のゲオルギオス一世をギリシャ王として迎え入れ、その後も王政が続き、1963年の国民投票で王政の廃止が決まって、ようやく現代のギリシャ共和国が誕生したという歴史経緯がある。
以上を整理すると、現代のギリシャ人は、ローマ人と認識していた人々が、ギリシャ語を話すことから、ヨーロッパ人の影響で古代ギリシャ人の末裔と認識し、現代のギリシャを創ったということになり、ギリシャ語というつながりだけが、古代ギリシャとの関係であって、そこには長い時間を費やしている民族としての血筋・歴史が明らかになっていない、ということになります。
ギリシャ危機によって円高となった
ここで長らくギリシャ問題を取り上げたのは、特別にギリシャに関心が深いのではなく、これが日本経済に大きく影響しているからです。ギリシャ問題から一段とユーロ安となり、その結果、円が高騰しているからです。
6月19日現在1ユーロ112円、一時は108円まで高くなり、2009年12月は132円でしたから20円以上の円高です。この円高は韓国ウォン、オーストラリアドルに始まり、殆どの国に対して高くなって、勿論、アメリカドルに対しても同様です。
日本人全員が承知しているように、日本は長らく景気が良くないのに、どうして円高になるのか。外国から見ると日本経済は別の認識になるのでしょうか。
この素直な疑問に対し新聞等で明確に解説されていません。どうして経済専門家達は整理しないのでしょうか。専門家が分析しないのであれば、我々一人ひとりが、この素朴な疑問について、実態的に整理しておく必要があると思いますが、いかがでしょうか。以上。
2010年06月06日
2010年6月5日 ギリシャ問題
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年6月5日 ギリシャ問題
企(つまだ)つ者は立たず、跨(また)ぐ者は行かず
これは老子の言葉で、意味は「つまさきで立つ者は立ち尽くすことができず、大股で歩く者は長く歩くことができない。功を急いだり、人目に立つように自分を見せびらかすような人は、長続きしないし、成功はおぼつかない」。
要するに、自分の実力以上に無理すると、息切れするという意味で、正に、これはギリシャに該当すると思っていますので、その理由を以下に述べたいと思います。
ギリシャの問題は予測できた
現在、月刊ベルダ誌で「世界よりみち紀行」(ペンネーム・南石堂)を連載しておりますが、ギリシャについて昨年2月号で以下のように書きました。
「欧州単一通貨であるユーロは、1999年1月に11カ国からスタートし、その2年後にギリシャが、続いてスロベニア、キプロス、マルタが導入し、今年元旦にスロバキアが加わりユーロ圏は16カ国になった。だが、ユーロ導入以後7年経つギリシャが、このように社会的安定を欠く実態とすれば、米ドルに代わってユーロが世界の基軸通貨になることは難しいだろう」と。
正に、このような危惧が当たりそうな状況です。今はユーロ売りが少し落ち着きましたが、今年前半の新聞記事をつぶさに追っていくと、EU金融当局、それはEU政府とECB(欧州中央銀行)や、独仏のEU強国政府を指しますが、これらが対策をとった直後に投機筋から売り込まれている状況が分かります。結果として、ユーロを今後の基軸通貨として認識判断し、保有した各国の中央銀行などは大損害を被っています。
何故予測できたか
ギリシャには2008年3月に訪問しました。その時の印象が強烈で、これはEUユーロ圏の一員として問題だと感じたわけでして、それをいくつか紹介します。
① 空港からアテネのホテルまでタクシーで向かい、アテネオリンピック開催にあわせて整備した高速道路を快適に走った。だが、高速を降りた途端に酷い渋滞。運転手が大げさに手を上げ何か叫ぶその窓向こうに、窓拭きや物売りの若い男が大勢いる。これを見ておやっと思う。ヨーロッパ圏では珍しい。南アフリカ・ヨハネスブルグやインド・ムンバイでは普通の光景だが、ヨーロッパの国々で見かけない物売りだ。
② 次に気がついたのは、タクシーの運転手や信号で物売りしている若者たち、通りを歩いている人たち、その顔や体つきを見ていると、ギリシャに来たとは到底思えない感じだ。
この感覚は1989年11月に、初めてアテネに来た時も感じた。その時もひとりで訪れ、街中を歩いているうちに、今、ここアテネに住んでいる人たちは本当にギリシャ人なのか、という疑問を持った記憶が強く残っている。
古代ギリシャ人の彫刻は国立考古学博物館に行くとたくさん展示されているし、ギリシャ文明を義務教育で学んでいるので、古代ギリシャ人のイメージはしっかり脳に残っている。すばらしい理知的な瞳と顔立ちをしているブロンズ像でギリシャ人のイメージが固まっている。
だから、街中を歩いている人たちは、皆古代ギリシャ人のブロンズ像のようであることを期待し、その確認のためにアテネに来たようなものであるが、実際のアテネを歩いている人たちは、随分異なる。違った国に来た感じだ。
③ 空港から利用したタクシー、メーターがあるので安心し激しい渋滞の車中から、ゼウス神殿とパルテオン神殿に見とれていると、急に狭い路地に入って行き、路地から再び大通りに出るところの角にくると、「あれがホテルだ」と指差す。
大きな建物のホテル名を確認し、間違いないと思い、支払いをしようと思ってメーターをみると、数字は全く消えている。路地から大通りに出る角までのメーター金額は確か13.50ユーロだった。運転手にいくらだ、と聞くと28ユーロだという。一瞬、ホテルのボーイを呼んで、タクシー運転手に文句言ってもらおうと思ったが、これもアテネでの貴重な実体験と思い支払う。すると、25ユーロの領収書と、高速の2.70の領収書をこちらに渡してくる。もう領収書が手書きで用意されていたのだ。
④ ホテルに入り、改めてギリシャを地図上で見てみると、ヨーロッパの東南部、地中海のイオニア海とエーゲ海に挟まれたバルカン半島の南端に位置している。イオニア海の向こう側のイタリアとは海があり陸続きでない。だが、アルバニア、マケドニア、ブルガリアとは北方国境を接し、驚いたことにトルコと陸続きなのである。
ギリシャはヨーロッパである、というイメージを持って訪れると妙な感覚になる。立地しているのはバルカン半島の突端、回りは東欧諸国とイスラムのトルコ、当然に近東諸国の影響を受けている。
近東(Near East)とは、バルカン諸国、トルコ、シリア、エジプトなど旧オスマン帝国に対するヨーロッパでの呼称であって、これらの国々に囲まれているのであるから、ヨーロッパ的雰囲気というよりは、実際に見かける光景や食べ物は、バルカン・近東なのだ。
⑤ 夕食はバルカン・近東の雰囲気を持つ、観光客で一杯のプラカ地区で食事をし、ホテルに戻るべく、アクロポリスの丘を遠くに眺め、迷路のような細い路地裏を歩いて、大通りに戻り、交差点に立ち、そこにいる多勢のアテネの人たちを見ていると、再び、今のギリシャ人は本当に古代ギリシャ人の末裔なのであろうか、という疑問を強く持つ。
この疑問について、後日調べて解明しましたが、これを述べ出すと長いので次回として、次にアテネの主婦から送って来た最新の状況をお伝えします。
ギリシャからの便り
アテネに住む主婦から最新の状況連絡を受けました。
「ギリシャ経済は今大変で、最初は、たいしたことはないだろう。又ストライキでもすれば・・・などと高をくっていたギリシャ人も、ここへ来て、あせっています。
とにかく、公務員だらけのギリシャですから・・・。共働きで学校の先生をしている人たちや、共働きで公務員をやっている人達、国営病院に勤めている人たちが賃金カットに一番怒っています。今まで、楽をしてお給料を貰っていたくせに・・・(笑)。
公務員以外の人たちにはそれほど影響はありませんが、やはり少しは賃金がカットされるようです。電気、水道、電話料金などは自分が使用した料金の2倍以上の税金が加算されていてびっくりします。たとえば自分が使った料金は50ユーロなのに100ユーロ以上もの税金、その他が勝手に付いてきて150ユーロ以上払わなければなりません。一体どうなっているんだと、怒鳴り込む人もいるそうですが、いくら怒鳴り込んでも国のすることには逆らえません。政府は町の統一もするそうです。小さな町は大きな町に合併されるようです。そうやって公務員の数を減らすつもりではないかと思います。
ギリシャ人は今までストライキをすれば(特に公務員)、国が要求を呑みいれていたので、今回もストライキをすればいいと思っていたようですが、今回は国もそういうわけには行かず強制的にするしかないようです。
ここに来て、ギリシャ人は初めて国が要求を飲まないことが分かったようですが、まだまだ現実のものとは受け止めていないようです。今まで政府は選挙の票取りのためにでたらめな政治を行ってきた付けが一般市民(公務員以外)にも及んで来てこれからはギリシャは大変な生活を強いられると思います。ギリシャ人の悪いところはどうにかなる…と思っていることです。ストライキを続けているのがその証拠で、そうすれば賃金カットはできないと、まだまだ思っているようです。
今まで気楽に、好き勝手なことをして暮らしてきたギリシャ人にとって、今回の政策は大変なことで、これから先、ギリシャは一体どうなるのか、国民は不安になり始めました」
ギリシャのEU加盟は失敗だった
EU内の経済的強者ドイツ・フランスに対し、明らかにギリシャは弱者です。これら国が一緒になると、ユーロ為替相場は参加国平均となるので、経済強国は割安で有利、弱国は割高で不利となり、結果としてギリシャは背伸び国家運営を行わざるを得ず、国内経済で歪みが生じます。自分の実力以上に無理すると息切れするよい事例です。以上。
2010年05月21日
ギリシャ問題が意味する背景
YAMAMOTO・レター
2010年5月20日 ギリシャ問題が意味する背景
PIIGSとは
PIIGSという五文字が、マスコミによく表現されています。PIGはブタという意味で、これにもう一つIが加わり、最後にSがつきますので、ブタ共という軽蔑的な用語になりますが、これはポルトガル、イタリア、アイルランド、ギリシャ、スペインの五カ国を意味しています。
誰が名付けたのか正確には分かりませんが、2008年ごろから英米経済ジャーナリストが言いだしたようで、このところ特にギリシャに関する経済問題が報道されない日はなく、PIIGSでもギリシャが世界の注目を一手に引き受けています。
五カ国に共通しているのは財政赤字
PIIGSのGDP合計は、ユーロ圏の四割弱に達しますので、ギリシャを機としてドミノ現象の危険も危惧されています。その危惧される要因は五カ国いずれも財政赤字問題です。
2009年GDP対比の財政赤字比率はポルトガル9.4%、イタリア5.3%、アイルランド14.3%、ギリシャ13.6%、スペイン11.2%となっています。
だが、これまでこれらの問題があったとしても、ユーロ圏経済は一般的に順調であると認識されていました。
ドル・ユーロ・人民元という三極基軸通貨になるという予測は?
ユーロが導入され、既に11年目を迎え、現在16カ国がユーロ圏となっています。
政治を統一しないで、通貨を統合したユーロは、ついこの間まで、成功したシステムだと喧伝され、拡大を続け、これからの世界の基軸通貨はドルとユーロと人民元になる、と予測する経済関係者が多く、円の存在が薄れつつあるという危惧と共に、これらの主張がしきりに叫ばれています。この主張背景には、ユーロが通過流通量では世界一となり、2008年末の世界準備通貨として64%のドルに対し、26%までに拡大され、ユーロ圏以外でもアフリカ諸国で使われ、5億人が常時使用する通貨に成長していたからです。
しかし、ギリシャ問題の発覚で、このような新三極基軸通貨はどうなるのでしょうか。新三極基軸通貨を信じ、外貨準備通貨としてユーロを保有した国々、特にアジアの中央銀行は膨らみ続けた外貨準備マネーをユーロに振り向けていましたから、今回のユーロ安で大損害を被りました。一方、問題だと言われている日本の円が急上昇で、5月20日は対ドルで
91円、対ユーロで113円となっています。明日は分からないというよい事例です。
ギリシャは粉飾紛いの経済数字だった
どうしてギリシャは問題となったのでしようか。実は、ギリシャは国家経済を、粉飾紛いの数字で運営していたことが発覚したのです。
ユーロ圏は政治統合されずに、通貨だけ統一したのですから、お互い自国経済規模にあった通貨供給をするというルールを定めています。
そのルールは、①単年度の財政赤字の比率がGDPの3%を上回ってはならない。②国債発行残高がGDPの60%以下であること。これがユーロ圏加盟国に義務付けられていますが、ギリシャはこの基準を結果的に満たしていないのに、ユーロに加盟したのは、粉飾紛いの操作を行っていたのです。
その操作を簡単に述べれば「通貨スワップ」の手法で、巨額の財政赤字を帳簿上から消してしまったのですが、この操作をアドバイスしたのが米のゴールドマン・サックスです。その状況を英のフィナンシャル・タイムスが次のように報道しています。
「02年、ゴールドマン・サックスがアテネにやってきて、GDPを上回るほどに膨張していたギリシャの公的債務の資金調達コストを軽減するため大規模なスワップ取引をアレンジした。50億ユーロ規模の市場外取引で、円やドルなど外貨建て債務を軽減する『クロス通過スワップ』と呼ばれる手法だった。この手法は借り入れでなく、為替取引として扱われたため、ギリシャ財政がEUの基準をクリアするために役立った。返済を先送りしたのである」
「投資銀行の幹部や政府高官たちは、この取引は合法だったと話している。すなわち、彼らは当時の会計ルールに従っていたし、イタリアやポルトガルを含む南欧諸国でも、他の投資銀行が同じような取引を行っていたというわけだ」
ギリシャの財政赤字
昨年10月の選挙でギリシャは政権交代しました。その結果、前政権の「債務隠し」が発覚し、財政赤字額を修正しました。
GDPに対する財政赤字は、2008年が5%から7.7%へ、2009年は3.7%から13.6%へと、財政赤字ルール3%の四倍以上という異常に大きな修正が発表されたのです。これで一気にユーロは下落し、ギリシャが毎日報道される国になったのです。
考えてみれば、経済力に大きく差がある国が集まって、統一通貨を採用すると、通貨の相場は平均となりますから、経済力のある国はいいが、弱い国は背伸びをせざるを得ないわけです。強国がより強く、弱国はより弱くなるわけです。
このような当たり前のことが、実際にギリシャの粉飾紛いの経済実態が明らかになるまで、世界は気づかなかったのですから、多くの経済専門家も詳しく実態を把握していなかったのだ、と思えて仕方ありません。これはサブプライムローン問題の発生時も同様の感じを持ちましたが、一般的な報道でなされる経済実態情報は十分にチェックすべきという教訓です。
そこに金余りが食いついた
最近の世界経済は「金余り」現象が続いています。世界の金融資産が増加した契機は、2000年のITバブル崩壊を始めとして、リーマンショク等の対策で、先進各国の中央銀行が金融緩和、つまり金利引き下げを行なったことにあります。
この「金余り」の使い道はどこに行っているのか。それはほとんど金融取引に向かっているのです。実際の実物経済には回らず、株式や債券、通貨、石油やゴールドに投資されているのです。その事例として米国にお金が還流しているデータがあります。米財務省が5月
17日に発表した3月の国際資本投資統計によりますと、海外勢による長期証券投資(国債、社債、株式)に伴う資本流入超過額は約13兆円と過去最高を示しました。
このような「金余り」の動きが、今回のギリシャ危機に伴って、どのような動きを示したのか。それはユーロ売りという投機につながったのです。
ギリシャ支援策を打てどもユーロは下落する
最近の新聞報道から、ユーロ売りの流れを追ってみたいと思います。
① 3月15日ユーロ圏財務相会議でギリシャ支援基本合意⇒3月22日ユーロ売り再燃
② 3月26日ユーロ圏首脳会議でギリシャ支援策合意⇒4月8日ギリシャ国債価格下落
③ 4月27日ギリシャ信用格付け引き下げ⇒NY株213ドル、日経平均も大幅下げ
④ 5月2日ユーロ圏財務相会議で1100億ユーロ融資合意⇒5日6日主要国株下落
⑤ 5月10日EU財務相理事会で7500億ユーロの融資枠決定⇒なおユーロ下落
⑥ 5月19日独政府ユーロ圏の国債空売り禁止発表⇒株とユーロ一段と下落
この流れを見ますと、ユーロ圏でギリシャ金融支援の政治決定がなされる度に、市場は反対の株安、ユーロ安に動いていることが分かります。
誰がマイナスの動きを仕掛けているか
20日までの動きを見る限り、世界の「金余り」はユーロ売りに向かっています。空売りして下げ、それを買い戻して利益を獲得する、正にマネーゲームになっていて、政府や中央銀行が対策を打っても、それは投資筋の仕掛け材料として利用されるだけで、解決に結びつかず、ユーロの売りを囃したてる材料になっているのです。
ということは、余りにも膨大なお金が世界中にあることから、そのお金が投資を求めて動きまわって、その格好のターゲットがギリシャであり、この問題は中央銀行が「金余り」金融市場の投機筋に敵わない、という姿を示しているようにも思います。
PIIGSとは誰が言い出したのか
このような動きから推測できるのは、PIIGSと命名したのは金融市場筋であり、それはこれからPIIGSをターゲットにするぞという暗号ではなかったのかと思うのです。
「金余り」世界を利用した投資の世界が次の儲けを探してグルグル回っている、それが今の時代だと考えると、財政赤字の膨大な国、日本に向かう可能性を否定できません。以上。
2010年05月06日
YAMAMOTO・レター2010年5月5日
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年5月5日 説明責任
21世紀はサービス・知識の時代
今までの日本経済成長を一言で述べるならば、今の韓国と中国と一緒です。先進国へのキャッチアップ過程がうまくいき、経済大国化へ走ったのです。GDPを増やして国民の暮らしをよくするという途上国型でした。
日本が高度成長を遂げていた当時は、世界中の空港で見るテレビは、ソニーであり、シャープでありナショナル製品で、これは世界で日本製造業が勝利したということでした。
しかし、今は、同じ手法をもって、低コストの韓国と中国・台湾勢に負けて、世界中の空港テレビはサムスン製に切り替わっています。薄型テレビの世界トップシェアはサムスンで23.3%(2009年)となり、ソニーは12.4%、パナソニックは8.5%、シャープは6.3%という実態です。これは、今までと同じことをしていたら、コストの安い国に負けて行くという事実を証明するもので、今の韓国と中国・台湾勢もコストアップが進めば同様のことが生じると思います。
ということは、日本が成長しようとするならば、低コスト製造技術の競争とは違う、他国ができないことを創り出し、他国と差をつけること、これは脱近代化ということですが、ここへ国民意識を集中させることが必要で、これを一言で述べれば「サービス・知識」分野の強化ということになります。
サービス・知識は視点を変えることから
もう一度整理をしますと、同じ技術で製品をつくるならば、コストの安い国の方が、製品価格を廉価にでき、普及価格帯商品市場でシェアをとれ、コストの高い国はとれない。
これは当たり前の事です。従って、日本はコストが高いわけですから、低コスト国と違うことを行って、脱近代化を進めなければいけない。これも当たり前の事です。
では、その脱近代化をどのようにして実現させるか。そのポイントはいたって簡単ですが、とても難しいことです。何故なら、日本人ひとり一人が、今までの自分と違う視点を持たねば、今まで気づかなかった他との違いを見つけられないからです。これは自分を変えるという作業追及となり、非常に困難なことは誰でも承知している事実です。
だが、自分の性格を変えるのは困難ですが、「サービス・知識」分野のレベルアップは可能だと思います。その事例をマスコミ情報の捉え方と温泉で考えてみたいと思います。
ホリエモンの講演
先日、ホリエモンの堀江貴文氏の講演を聞く機会がありました。
いろいろお話がありましたが、自ら逮捕を受けた経験から、今回の小沢幹事長の検察審査会の「起訴相当の議決」についてふれました。
鳩山首相は「不起訴相当」で、小沢氏と議決が分かれたのは、無作為に選出された国民11人によって構成される検察審査会であるから、マスコミ報道の影響を受けやすく、悪人面やマスコミ嫌いとされる点で小沢氏が随分損をしている。鳩山首相はその政治手腕を国民の70%以上が評価していないにもかかわらず、善人面の金持ちのぼんぼんの世間知らずの天然宇宙人と思われているから、起訴相当の議決は受けない。
小沢氏は起訴されただけで役職を辞する必要はない。小沢氏はそれなりに説明責任を果たしていると感じているし、起訴相当の議決が出たからといって即クロだとする報道姿勢をしているところには疑問を感じる。疑わしきは無罪。これが司法の大原則だ。まあ、そうやって政治生命を失わせようという事だろうが、この原則を国民に理解してもらうためにも徹底抗戦を小沢氏にはおススメする。
また、佐藤優氏の見解は正しいとも言っていましたので、佐藤氏の見解を「佐藤優の眼光紙背:第72回」(2010年4月28日脱稿)からご紹介します。
佐藤優氏の見解
現在、起きていることは、国民の選挙によって選ばれた政治家、あるいは資格試験(国家公務員試験、司法試験など)に合格したエリート官僚のどちらが日本国家を支配するかをめぐって展開されている権力闘争である。検察は、エリート官僚の利益を最前衛で代表している。過去1年、検察は総力をあげて小沢幹事長を叩き潰し、エリート官僚による支配体制を維持しようとした。
エリート官僚から見ると、国民は無知蒙昧な無象無象だ。有象無象から選ばれた国会議員は、「無知蒙昧のエキス」のようなもので、こんな連中に国家を委ねると日本が崩壊してしまうという危機意識をもっている。しかし、民主主義の壁は厚い。検察が総力をあげてもこの壁を崩すことはできず、小沢幹事長が生き残っている。そこで、ポピュリズムに訴えて、小沢幹事長を叩き潰し、民主党政権を倒すか、官僚の統制に服する「よい子の民主党」に変容させることを考え、検察は勝負に出ているのだ。
一部に今回の起訴相当の議決を受けて、2回目の検察審査会を待たずに、検察が小沢幹事長を起訴するという見方があるが、筆者はその見方はとらない。検察の目的は、国民によって小沢幹事長を断罪し、その政治生命を絶つことだ。そのためには、検察審議会の場を最大限に活用し、ポピュリズムに訴える。国民を利用して、官僚支配体制を盤石にすることを考えているのだと思う。実に興味深いゲームが展開されている。
二人に共通する普遍性
堀江貴文氏と佐藤優氏に共通している事は、マスコミに対する姿勢です。マスコミ報道をそのまま鵜呑みにせず、自らの立場で検証しようとする姿です。
一般的に世の中で発生する事実を知るにはマスコミしかないわけで、その意味ではマスコミ報道から離れることはできません。
しかし、マスコミ報道だけの情報で世の中を判断しようとすると、マスコミ報道が意図する何かによって、判断基準が定まり、結果としてマスコミに追随する見解となりやすく、一般的な「あるべき論」的な見解になりますから、他との違いは見出すことは困難です。
今の日本がおかれた立場は、既に見たように脱近代化を図らねばならないわけで、これを実現しようとしたら、まず、他との違いを見つけ、それを明確に説明できるという、日本人ひとり一人の説明責任が問われているのでしないでしょうか。
伊豆の白壁荘ゼミナール結果
4月の経営ゼミナールは、伊豆天城湯ヶ島温泉白壁荘で、フランス人ジャーナリスト、リオネル・クローゾン氏をお迎えし「日本の温泉、世界ブランド化への道筋」で開催を予定しておりましたが、アイスランド火山噴火の影響で来日が不可能となり、急遽、通訳兼コーディネーターの企画コンサルタントフローランタン代表の柳楽桜子氏に、クローゾン氏の講演内容を代講していただき、48名のご参加で盛況に終了しました。
講演の中で触れられたクローゾン氏と温泉との出会いは1982年で、仕事を終え大分県湯布院を訪れた際、温泉地風景と日本旅館との調和や田舎道情緒に加えて、最も魅力的だった事は40℃前後の温泉に入るということでした。この習慣は欧米にはないわけで、この体験以後、来日のたびに各地の温泉を巡り歩いて、今は専門家になったのです。
つまり、欧米から見ると「異文化」が日本にあるという「違い」が日本の最大魅力だという事を、日本の観光関係者は正しく妥当に理解し、外国に説明すべきと主張したのです。
説明責任
この講演を受け、私がまとめを行いました。
クローゾン氏の主張はその通りであり、日本を観光大国化するためには、欧米との違いを説明する必要がある。韓国・中国がリードしている普及価格帯商品は、日本製品と価格の違いを説明しシェアを伸ばしている。
だが、観光は地政学的な特長であって、製造物ではない。コストは決定要因でない。その土地の性格がもつ魅力によって人が訪れるものだ。
とするならば、その土地が持つ意味と、他国との違いを、妥当に説明する商品をつくる事が必要で、それは「日本の温泉ガイドブック」作成となる。既に同様の本は日本に多くあるが、それらは欧米の書店棚に並ぶ内容になっていない。欧米の書店にある「ブルーガイド」「グリーンガイド」と一緒に「温泉ガイド」が書棚に並ぶ事が実現した時、温泉業界は説明責任を果たしたことになり、その結果として、日本の温泉は世界ブランドと位置づけられ、日本が観光大国化に向かう大きな道筋になるだろう。21世紀は「サービス・知識」分野の強化の時代だ。欧米書店へガイド本を並ばせる行動を起こす時が来た。以上。
2010年04月21日
2010年4月20日 脱近代化は今の条件を活かすこと
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年4月20日 脱近代化は今の条件を活かすこと
アイスランドの火山噴火
アイスランドの火山灰がヨーロッパ上空を襲い、各国で空港が閉鎖されています。旅行客が空港に泊って何日も過ごすことになり、様々な場面で問題が出ています。
アイスランドは人口32万人、ここには1990年3月に行きました。家庭の水道が全て温泉ミネラルウォーターで、その水の良さのためか、街中を歩く、といっても地上が雪と氷でしたから、地下街で出会う女性の肌がきれいなことが印象に残っています。
その後のアイスランドは金融大国化へ大きく国策を変化させ、一時は国民一人当たりGDPで世界五位(2006年)となりましたが、2008年に発生した世界金融危機によって経済危機という状態です。
元々、国の中心産業であった漁業を、GDP対比6%まで減少(2006年)させた国策を、アイスランドの自然が怒り狂って、今回の噴火を起こしたのではないかと思えるほどです。
パナソニックの戦略
パナソニックが、新興国市場への開拓を加速するとの報道がなされました。(日経新聞2010.4.16)このパナソニックの戦略は遅きに失したと思います。
まず、世界市場でシェアを獲得するためには、ブランドイメージの定着が基本ですが、社名を「松下」や「ナショナル」と「パナソニック」に地域や用途に応じて使い分けていて、ようやく2008年後半にパナソニックに統一しました。これがイメージの定着化にマイナス要因で、連結売上の海外比率は47%にとどまっています。
ライバルの韓国サムスンは80%、ソニーは70%ですから、その差は大きいものがあります。今回のアイスランド火山噴火で空港に足止めされている人々が、状況を確認しようと見るロビーのテレビは、世界中の空港でサムスン製のテレビに切り替わっています。
以前は、ソニーであり、シャープでありナショナル製品だったのですが、今や完全に空港はサムスンに占拠されました。この背景には、もうひとつ決定的な要因があります。
上海の街中
アイスランドの火山噴火のタイミングに上海に行きました。今回は家族との観光でした。ここ数年、上海には度々訪れていますが、仕事でしたので観光地には出かけませんでした。
今回は、まず、上海郊外の七宝老街に行き、北宋時代を再現した水路や石橋など楽しみ、名物の臭豆腐を食べ、小舟にも乗りましたが、土曜日なので人でいっぱいです。土曜日休日の企業が多いということがわかります。
次に向かったところは豫園です。ここは更に人ばかりで、欧米人が多く、ヨーロッパに火山噴火で帰れないので、仕方なく観光地に来ているのかなと推測しましたが、南翔饅頭店の小龍包には驚きました。余りに人が列をつくっているので、試しに最後尾に並んでみました。立ち並ぶこと40分、ようやく手に入れた16個入り小龍包、価格は12元約200円と安く、味もさすがに超人気だけのことがあり、店頭応対も問題なしです。
最も驚いたのは公衆トイレです。七宝老街も豫園でも綺麗に掃除されていて、自動水洗とウォシュレット、手洗いも自動でペーパー&温風つき。1992年に家族と廈門と深圳に行った時は、公衆トイレには入れなかったほど不潔だったのですが、今の上海は道路のゴミ掃除もしっかりなされ、見事に万博開催にふさわしい都市に変化しています。
中国全体は、先進国へのキャッチアップ過程にあるとしても、上海の観光地のトイレを見る限り、万博開催都市としての目標は達成したと感じます。
残されたのは空気で、空はいつもどんよりスモッグで、環境問題が最大の課題です。
中国と韓国のタクシー料金
上海でタクシーに乗りました。豫園からホテルまで渋滞もあり40分乗車し42元で約670円。3月の韓国でもタクシーを利用しました。ホテルから釜山駅まで20分乗って5,900w494円。ソウル駅からタクシーでホテルまで25分6,100w511円です。
いずれも日本の一区間料金以内という安さで、ドライバーの対応も問題ありません。
韓国の新幹線の高速鉄道KTXも利用しましたが、料金は釜山からソウルまで最速2時間40分で、普通席47,900w4,014円、一等席67,100w5,622円で、サービスも問題なしです。
対する日本の新幹線、東京から新大阪まで13,750円、名古屋まで10,580円ですから、韓国KTXは日本の新幹線と比較にならない安さです。
中韓のキャッチアップ
実は、ここに韓国サムスンの伸びた理由があります。日本の技術を導入し、品質面での差が少ない上に、コストが安いので、価格が安く、結果として世界の普及価格帯商品ゾーンで、圧倒的なシェアを獲得できたのです。
対する日本は、高コスト体質ですから、パナソニックが普及価格帯商品で反転攻勢をかけようと意気込んでも、価格問題がネックとなって、シェア奪回はかなり困難でしょう。
また、上海観光地の公衆トイレ、万博を開催しようと意図した時から、今の清潔さをキャッチアップ目標におき、先進国のメンテナンス体制を導入して実現したと思います。
つまり、先進国を真似て取り入れるキャッチアップの好事例が、今の中韓の実態と判断します。
脱近代化を目指すこと
日本が高度成長を遂げた時代は、今の中韓と同じでした。先進国へのキャッチアップ過程がうまくいき、経済大国化へ走ったのです。GDPを増やして国民の暮らしをよくするという途上国型だったのです。
しかし、キャッチアップ過程を経て、GDP世界第二位になって、日本が近代化チャンピオンという勲章を受けてみると、既に、世界から見習うものが少なく、導入する産業がなくなった時点で、この体制は破綻し、もうキャッチアップという目標はとれない、という事実が分かったのです。
そこで、日本が改めて成長しようとするならば、他国ができないことを創り出すこと、他国と差をつけることしかあり得ず、これは脱近代化ということですが、今はこの目標段階に来て、新たなる自らの創造力をもって、日本を創るべきなのに、それが実現できないため、日本は低迷を続けているというのが今日の実態と思います。
脱近代化を図る方向性
脱近代化を、日本が目指す方向性と理解すれば、日本の現状に根差し、日本人の持つ個性をヒントに、一人ひとりが創造性を生み出すことで、日本全体の活性化を図ることが必要になってきます。
そういう理解でなく、脱近代化を、政府・行政が行うことだ、企業が中心になって開発することだと解釈すれば、その時点で一人ひとりの創造性とは結びつかず、実生活と離れた方向に向かい、今と同じく不活性な低迷を続けることになるでしょう。
ここは是非とも一人ひとりが参加する脱近代化を方向性とすべきと考えます。
公民館でお話したこと
先日、地元の公民館で講演しました。テーマは「地域は脳の活性所」で、高齢化社会に対応するには、地域に住む我々の脳を活性化させることが第一条件だ、という内容です。
このヒントは三菱総合研究所の小宮山宏氏が、高齢化社会こそが新しい需要を生み出し、
高齢化社会こそが「創造型需要は国内新産業技術開発」という目標を創り出すのだという主張からでした。
具体的には、本格的に高齢化社会を研究する過程から、生み出すべき新しい新技術・新商品、例えば「超安全自動車・ロボットスーツ・家事支援ロボット・自助介護ハウス・デジタルメガネ・眼や歯の再生技術・医療技術者支援製品群」等によって新産業を興し、介護や医療の負担を減らし、高齢者の社会参加を可能にすることを通じ、日本の活性化を図るというものです。
つまり、高齢化という地政学的な条件を活かすことで、新産業を生み出し活性化を図るわけですから、当然ながら各地域に住んでいる我々市民の「日々の暮らし」中に、日本の活性化のキーワードが存在しているのです。アイスランドが自国の地政学的条件とは異なる国策をもって経済成長を目指し、結局、困難化した事例に学ぶべきと思います。以上。
【2010年5月のプログラム】
4月21日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
4月23日(金)15:00〜 経営ゼミナール 特別例会
『日本の温泉、世界ブランド化への道筋』
於:伊豆天城湯ヶ島温泉・白壁荘
5月14日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
5月17日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
5月19日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 06:54 | コメント (0)
2010年04月04日
2010年4月5日 PIGSスペインから学ぶこと
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年4月5日 PIGSスペインから学ぶこと
消費税アップに学ぶ
日経新聞社とテレビ東京の共同世論調査(2010年3月29日)で、鳩山内閣の方針の「4年間は消費税の増税をしない」に対し、「反対」と答えた人が46%、「賛成」43%で、反対が賛成を上回りました。
また、参考までに世界各国の消費税率がグラフで示されていて、これを見ると、日本は世界一借金大国という実態とは全く逆で、世界一低いと思われる消費税率となっています。
さて、今や世界の話題の中心であるEUのPIGS(ブタども)といわれるスペインですが、先般訪問してみると、マドリード市内の市場はじめ商店は活況を呈していまして、低迷している状況とは思えませんでした。
そこに7月1日から消費税率アップをスペイン政府が決定しました。アップ内容は、自動車、家電、アルコール、たばこ、ガス、電話料等が現行16%から2%アップの18%へ、ホテル・レストラン、住宅、公共輸送等は現行7%から1%アップの8%です。
この決定をするところが日本政府と異なるところでしょう。お互い2016年の夏季オリンピック招致に失敗した国同士ですが、経済危機に関するアンテナはスペインの方が鋭いのか、それとも消費税値上げは大きなことでないのか。
いずれにしてもアップしますが、政府社労党は消費税アップで、失業者50万人を救う方針だと説明。一方、対する野党保守党の民衆党らは、消費者の購買力をかえって抑えることになり景気停滞を進め、さらにスペイン経済をマイナスにさせると主張しています。
増税に対しては、各立場から様々な見解があるのが当たり前ですが、スペイン国民は消費税アップにどう対応しているのでしょうか。
それは簡単で「スペイン人は割り切って、消費税がアップする前にと、自動車、不動産を買い捲っている」ということで、今のスペイン人の需要は盛り上がっているのです。
元々スペインはアングラ経済の二重財布で、個人一人一人はお金を持っているのです。日本も高齢者中心に貯蓄がすごいのですから、このところを日本政府もよく考えた方がよいだろうと思い、いつまでも消費税を上げないで済むのか、という素朴な疑問が国民の間にある事実を、冒頭の世論調査が示していると思った次第です。
姓名をつなげる大事さを学ぶ
スペイン訪問時に、一枚の新聞を地元の人から見せられました。それはスペインのクオリティーペーパー、エル・パイス新聞の1996年10月27日付けで、タイトルに「日系スペイン人(?)いや、セビリア人だ!17世紀の支倉常長遣欧使節団一行の子孫」とあります。
(クリックで拡大)
写真の男の子は、宮城県が贈った支倉常長の銅像写真の下で、日本人の面影があると思われるセビリアの男の子の写真と、もう一人の男性の顔写真はサッカー審判員のホセ・ハポン氏です。 以下が記事の要約版です。
「東洋の日の出る国、日本の大名伊達政宗の親書を持った支倉常長一行30数名が、大西洋のサンルーカルからグアダルキビール川を遡って、当時西欧最大都市の一つだったセビージャ市近郊のコリア・デル・リオ(現在の人口24,000人)内港の町に上陸したのが、今から約400年前の1614年10月24日のことだった。その遣欧使節団の目的は、スペイン国王フェリペ3世やローマ法王と謁見して伊達政宗の親書を渡し、徳川幕府とは別に独自で仙台とメキシコ・スペインなどとの通商条約やキリスト教文化交流などに協力要請することだった。
支倉はフェリペ3世国王と謁見できたが、ローマ法王とは会うことが出来ず、3年後の1617年に帰国することを決めた。ところが使節団一行の中の十数名がコリア・デル・リオに残留することにしたのである。彼らは身分が低く名字がなかったので、通称“ハポン(日本)、ハポネス(日本人)”と呼ばれ、スペイン女性との間に出来た子供に“ハポン”の名字が付けられてきた。それから“ハポン”姓は400年の間、スペインで受け継がれてきた。現在コリア・デル・リオ町に400人、近くにあるコリア町に270人、セビージャ市に30人、合計700人のハポンさんが住んでいる。
ハポン姓を持っている有名人は、1990年にミス・スペインに選ばれたマリア・ホセ嬢、セビージャ万博当時のアンダルシア州文化長官のホセ・マヌエル・スアレス氏そしてスペインサッカープリメールリーグの名審判ホセ・ハポン氏などである。」
このようにスペインと日本の関係は、今から約400年前からであることが、氏名という個人の姓から歴史的に証明・明確化できますが、それはスペインの姓名制度のおかげです。
スペインでの姓は「父方の祖父の姓、母方の祖父の姓」や「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓」、「名、父方の祖父の姓、父方の祖母の姓、母方の祖父の姓、母方の祖母の姓」という名乗り方をします。女性は結婚すると「名、父方の祖父の姓、de+夫の父方の祖父の姓」で名乗るのが一般的です。つまり、一度名についた姓は、結婚しても一生ついて回り、それは子供を通じ以後も同様ということなのです。このような姓名制度ですから、「日本」という名がついた人々は伊達政宗の親書を持った支倉常長一行30数名の後裔であると判断できるのです。
この新聞記事によって、一気にスペインに対する好感度が増してきましたが、現在、日本では夫婦別姓にすべきという主張があり、国会で検討されているところです。
この問題を論じるつもりはありませんが、スペインの姓名制度があるおかげで、日本という名前が400年間も残り、今につながっている事実を考えますと、簡単に夫婦別姓という制度に切り替えてよいのか、という素朴な疑問も浮かんできます。
聖ヤコブ大祭から学ぶ
今年のスペインは7月25日に、ガリシア州のサンティアゴ・デ・コンポステーラで「シャコベオXACOBEO(聖ヤコブ)大祭」を迎えます。
キリスト教12使徒の一人である聖ヤコブ(スペイン語名サンティアゴ)の墓が9世紀初頭、スペイン北西部サンティアゴ・デ・コンポステーラで発見され、それ以来、ローマ、エルサレムと並び、このサンティアゴがヨーロッパ三大巡礼地の一つとして崇められ、キリスト教信者の心の拠り所となっていて、中世には年間50万もの人が徒歩又は馬車でピレネー山脈を越え、聖地サンティアゴ・デ・コンポステーラを目指したと言われています。
この聖人の祝日7月25日が日曜日にあたる年は「聖ヤコブ年」といわれ、この年1年間、最低150kmのサンティアゴ巡礼道を歩くと(自転車では200km)罪が許され、大変なご利益があるといわれ、それに合わして多くのイベントが企画され、ガリシア州は2010年を通して一千万人以上の巡礼観光客を見込んでいます。
そこに先日(3月4日)ビッグなニュースが発表されました。それは「11月6日ローマ法王ベネディクト16世がサンチャゴ大聖堂で巡礼者として訪れ、ボタフメイロの大祭壇で聖なるミサをあげる」という発表です。これにスペイン人は大喜び、サンチャゴ市当局によると、ローマ法王が来ると、観光客が更に数十万人増えると見て、サンチャゴの旅行業界、ホテル・レストラン業界なども、この話題で持ち切りとなっています。
キリスト教を頭で理解する日本人にとっては、ローマ法王のサンチャゴ訪問について、その影響度を正確には測れませんが、スペインには国の垣根を超えた一大イベントが存在しているという事実を正しく認識したいと思い、日本には世界各国の国境を超えるイベントがないという事実を認識すべきでしょう。
オリンピックやワールドサッカーを招致しようとするのは、この国境を超えたイベントを開催したいという意図でしょうが、そうではなく、日本の普遍性存在物を、世界の普遍性へと飛翔させる取り組み、それに一人一人が努力し協力する時代ではないでしょうか。
それらの行動が日本を観光大国化への正道と考え、日本各地の普遍性財産である温泉を、世界ブランド化へと企画いたしましたのでhttp://www.keiei-semi.jp/ご参考願います。以上。
【2010年4月のプログラム】
4月09日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
4月21日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
4月23日(金)15:00〜 経営ゼミナール 特別例会
『日本の温泉、世界ブランド化への道筋』
於:伊豆天城湯ヶ島温泉・白壁荘
投稿者 lefthand : 09:54 | コメント (0)
2010年03月23日
2010年3月20日 世界から日本の姿を見る
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年3月20日 世界から日本の姿を見る
真似できない
パリのカフェ Laduree ラデュレはマカロンが有名で、パリ市内に三店ありますが、その中のシャンゼリゼ大通り店に、フランス人ジャーナリストのリオネル・クローゾン氏と打ち合わせのために入りました。
入ったところの売り場に大勢の客が並んでいる奥、そこは特別室的なフロアとなっていて、そこの椅子に座った瞬間、これは素晴らしいと、思わず声が出て、すぐにフロア内全体写真を撮りました。だが、仮にこの写真を基に同じようなインテリアを造ろうとしても、日本人には無理だろうと思います。持っているセンスが違うのです。
戻ってすぐに、丸の内仲通りに行き、昨年9月オープンした三菱一号館と、丸の内パークビル中の中庭に座った瞬間、これは素晴らしいと、思わず声に出しました。明治時代の雰囲気と現代的な感覚が混じりあって、さすがに三菱地所だと唸り、このような雰囲気は外国人では設計できないだろうと思いました。このようなオリジナルのある日本センスは、外国人が真似をできません。
円高と人件費の高さ
このところ円高が進んでいます。対ドルレートは2008年4月101円で、2009年11月には84円、2010年3月16日現在で90円です。対ユーロレートは2010年1月133円、2月からは120円台で、3月16日現在123円です。知人の輸出企業社長は、1円の変化が業績に鋭く影響しますので、毎朝真っ先に見るのは為替相場欄です。
ところで、日経新聞(2010.2.26)に、日系企業の現地事務系課長職の年収が発表されていました。それによると韓国は4.4万ドル、台湾は3.0万ドル、中国は1.5万ドル、ベトナムは0.9万ドルとなっています。
これを1ドル90円で換算しますと、韓国の年収は396万円、台湾は270万円、 中国は139万円、ベトナムは僅か81万円の年収となります。
この年収を日本人と比較するため、国税庁データ(2008年)を見てみました。一応、アジアの日系企業事務系課長職ですから、それなりの年齢であろうと、いくつかの年齢層の日本人男性年収を抽出し、韓国進出日系企業年収と比較してみました。
日本人の30~34歳年収は453万円で、これは対韓国比114%、35~39歳は530万円で138%、40~44歳617万円156%、45~49歳663万円167%、50~54歳670万円169%というように、日本人平均年収の方が韓国より各世代とも上回っています。
韓国のUAE原発落札
日本人の年収で、最も高い業種は電気・ガス・熱供給・水道業の675 万円、次いで金融業,保険業の649 万円です。低い業種は宿泊業・飲食サービス業で年収250万円です。
この金額は全年齢の平均ですから、アジアに進出している同レベルの課長職と比較すれば、前項で比べて見た年収格差はさらに開くと考えるのが妥当です。
この年収差が明確にあらわれた大事件が昨年末に発生しました。それは韓国の「UAE(アラブ首長国連邦)原発落札」です。受注額が韓国400億ドル、対するフランスは700億ドル、日米連合は900億ドルですから、勝負にならず韓国が国際入札の勝者となりました。UAEは価格のみ優先したのでなく、その後のメンテナンス力も考慮したという事らしいのですが、そうならば増して価格の安さが目立ちます。安い上にサービスが優れているとUAEは理解したのでしょう。
これが台湾や中国・ベトナムだったらもっと価格差は広がっているはずです。韓国の現代製自動車が海外でシェアを伸ばしているのは、この価格差です。
アジアには5001ドル~3.5万ドルの中間ミドル層人口が8億8000万人いると推測され、これらの需要を取り込むには、価格戦略が最優先となりますが、これが果たして日本企業にとって可能か、という素朴な疑問がアジア各国との年収比較で浮かんできます。
日本は高付加価値商品となる
円高による食糧と原材料価格のダウン、加えて居酒屋メニューに代表される人件費の低額化が進み、これらによってコモディティー品の価格ダウンが続き、それらが日本人に歓迎されている現実では、まだまだデフレは長引くであろうし、これが通常の経済実態だと理解した方が適切です。
また、韓国原発落札価格との極端な差は、アジア諸国と人件費の差が、まだまだあり過ぎるということを示している、このように理解すれば、この面からも日本のデフレは一層強制されていくでしょう。
仮に、このアジアとの競争を技術力で補うとしたら、さらなる技術力を付加した高付加価値商品にならざるを得ないのですが、そうなるとこの分野の需要層人口は限られてくることになります。勿論、アジアの中間層を狙った商品を、新たな技術と発想の転換で、低価格で提供していくことは不可欠条件ですが、追いついてきた韓国、台湾、香港の技術力との差を、さらにつけるには相当の努力が必要で、かなり苦しいと思います。
だが、考え方のポイントを変えれば、韓国、台湾、香港にはなく、彼らに真似できない優位条件が日本には多く存在し、それは地方に多くあります事を再認識したいと思います。
価格競争ではない日本の優位性を活かす
パリからロンドンにBAで向かいました。ふと機内誌を手に取りますと、日本観光PRのページに眼が行き、そこに「Historic Artisan Town of TAKAYAMA」とあり、岐阜県高山市が東京・京都・沖縄と並んで日本を代表する扱いを受けています。
この事を、日本に戻って多くの方に伝えますと「高山がそのように高く評価されているのがわからない。他にも素晴らしいところがある。例えば、北海道だ」と発言されます。
日本人の感覚からはその通りなのですが、ミシュランのグリーンガイドでも、アシェット社のブルーガイドでも北海道の評価は割合低く、高山市はいずれも高い評価を受けているのです。日本人とは評価の基準が異なっているのです。
では、この評価基準を理論的に説明できるか、これは難しく、結局、欧米人の主観的判断で高山を認めているので、彼らと日本人は基準が異なる、ということしか言えません。
白壁荘での研究会開催
そこで、パリのカフェ Laduree ラデュレで、ミシュラン社「グリーンガイド」とアシェット社「ブルーガイド」両ガイド編集に携わる、フランス人ジャーナリスト、リオネル・クローゾン氏と会い、前述の疑問を問うとリオネル氏の回答は明快です。
「日本人は間違っている。フランスの魅力は田舎にあり、日本の魅力も田舎にある。日本人が認識していない部分を欧米人は評価している。そのことを日本人は知らない。そのところをフランスは上手にブランド化したからこそ、世界で断トツの観光客を受け入れているのだ」と。
日本の田舎が素晴らしいという事は、他の多くの欧米人からも直接聞いています。しかし、日本の田舎の人達は全くそう思っていませんから、観光ブランド化しようなぞという発想が微塵もありません。これは新たな技術で商品を作るという課題とは異なり、人件費が高い安いという問題とも異なるわけで、発想の次元の問題であり、考え方の問題です。
日本人の弱さは、考え方の基準をひとつしか持たず、そのひとつで世界全体を判断しようとする傾向が強いわけですが、欧米人の立場に立つことで、別の基準を持つようにすることが重要で、それをしないと日本の魅力を見つけられません。つまり、欧米人の立場から考えるということ、これが人口減問題対策であり、日本経済活性化に結びつく鍵です。
そこで、2010年4月23日(金)に伊豆天城湯ヶ島温泉・白壁荘にリオネル氏を迎え、経営ゼミナール主催で研究会を開催することにいたしました。
→『日本の温泉、世界ブランド化への道筋』
湯ヶ島温泉は「グリーンガイド」「ブルーガイド」に全く掲載されていなく、当然ながら白壁荘も紹介されていません。しかし、リオネル氏は高い関心を示しました。何故に湯ヶ島温泉と白壁荘を評価したのか。
それは研究会でリオネル氏が語りますが「日本には世界にない素晴らしい温泉地が多く、世界の人たちが真似できない。これを世界中に、特に、欧米人に紹介することだ」と熱く語る日本の魅力再発見ロマン企画に、皆さま、ご参加されますことをお勧めします。以上。
【2010年4月のプログラム】
4月09日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
4月21日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
4月23日(金)15:00〜 経営ゼミナール 特別例会
『日本の温泉、世界ブランド化への道筋』
於:伊豆天城湯ヶ島温泉・白壁荘
投稿者 lefthand : 08:40 | コメント (0)
2010年02月21日
2010年2月20日 日本の貧困率について
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年2月20日 日本の貧困率について
立場の違いから消費実態が異なる
内閣府から、2009年10月から12月のGDP速報値が発表されました。実質のGDP年率換算で4.6%とプラス成長、名目でも年率換算で0.9%とプラスになりました。プラス要因の大きな項目は輸出ですが、個人消費も実質でプラス(名目ではゼロ)となりましたので、改めて、この消費支出実態を考えてみたいと思います。と言いますのも、どうも立場の違いで判断が異なるのではないかと思われるからです。
例えば、現在最も人口ボリュームゾーンが多い団塊の世代、この人たちが若い時であった頃の消費行動は「若いので一般的に裕福でなかったから、モノへの所有、特に高額なモノを持つことへ憧れがあり、それを獲得するのが最高の自己実現手段」でしたので、この感覚を持ったまま今のゼロベース消費を見て「経済が低迷している」と判断するのではないでしょうか。
ところが、今の若い世代は「生まれた時からモノがあふれている環境で育ったため、モノの所有を自己実現とすることへはこだわりが薄く、モノの効用が薄れてしまっている状態」ではないかと推察します。ということは、バブル崩壊以後の経済低迷時代しか知らない若い人たちは、今が消費不況だとは、特に感じていないと思うのです。
また加えて、デフレ現状で価格が下がっていくので、ローンを組んでまで、今すぐに焦って高額なモノ、自動車等を買う必要性を、若い世代は感じない、ということは日本の若者が、デフレ時代を生きていく知恵を身につけているといえ、インフレ時代の生活から抜け出せない団塊世代よりも、よほど賢い消費者といえるのではないでしょうか。
スペインの新聞に出た日本の貧乏記事
今月の初め、スペインに滞在していた時、地元の人から次の新聞記事を見せられました。
(クリックで拡大)
新聞タイトルに「6人に1人の日本人が貧乏に苦しんでいる」とあり、これはカタルーニャ州の新聞ラ・バングアルディア紙の2009年10月22日付で、同紙はカタルーニャ地方で最も歴史のある保守系の新聞社です。
この写真、どこかの劇場のポスターの前で寝ている若い人で、貧乏実態を表現するために使ったのでしょうが、これを見たスペイン人は「日本は貧困国だ」と判断したでしょう。
貧困率の上昇
ここで使われた基資料は、実は日本の厚生労働省が昨年10月20日に発表したもので、海外に次のように伝達されました。
「【10月21日 AFP】厚生労働省が20日初公表した「相対的貧困率」で、日本国民の6人に1人近くが貧困状態で暮らしていることが明らかになった。2006年の貧困率は15.7%で先進国の中でも極めて高い水準。相対的貧困率は、全人口の可処分所得の中央値の半分未満しか所得がない人の割合。1997年は14.6%だった。長妻昭(Akira Nagatsuma)厚生労働相は同日会見し、日本の貧困率が、経済協力開発機構(Organisation for Economic Cooperation and Development、OECD)加盟国の中でも最悪レベルだと述べた。08年の世界的な金融危機に端を発した景気低迷を受けて、給与額が減少していることから、現在の貧困率はさらに悪化している可能性もある」
スペインの新聞に掲載されたのは、日本政府が「日本は貧困」と認定したからです。
収入は減っているか
そこで、実際に給与額は減っているのか。それを国税庁のホームページで公表されたデータから見てみました。(平成20年)
(1)給与所得者数は4,587 万人(対前年比1.0%増、45 万人の増加)であるが、その平均給与は430 万円(同1.7%減、76 千円の減少)となっている。
(2)これを男女別にみると、給与所得者数は男性2,782 万人(同0.0%減、0.1 万人の減
少)、女性1,806 万人(同2.6%増、45 万人の増加)で、
(3)その平均給与は男性533 万円(同1.8%減、97 千円の減少)、女性271 万円(同0.1%減、2 千円の減少)となっている。
という状況で、確かに収入は減ってはいますが、年間で男性が10万円弱減額ですから、極端に大きくは減っているとは思えません。
年齢階層別の平均給与
次に、若い世代の給与が少ないのではないかという視点から、国税庁データから平均給与を年齢階層別にみますと、確かに19歳以下が平均給与134万円、20歳から24歳までが248万円ですからかなり低い実態です。
しかし、年齢が上がって45歳から49歳ですと511万円、50歳から54歳では506万円と高くなっています。特に、男性では55 歳未満までは年齢が高くなるに従い高くなり、50~54 歳の階層では670 万円と最も高くなっています。この意味するところは、日本ではまだまだ年功序列制で給与が支払われている、ということです。
業種別給与
では、次に「業種別の平均給与」を見てみます。最も高いのは電気・ガス・熱供給・水道業の675 万円、次いで金融業,保険業の649 万円で、最も低いのは宿泊業,飲食サービス業の250 万円となっています。また、この宿泊業,飲食サービス業では、給与100万円以下が全体の24.8%、200万円以下が27.1%、この二つの階層で合計51.9%ですから、かなり低いというのが実感で、ここで気がつくのは、最近の飲食店料理メニューの単価ダウンであり、弁当がさらに安くなっているという事実で、このような業態で働く人は、パート・アルバイトか外国人でしょう。国税庁のデータ説明にも明確に、従業員とはパート、アルバイトを含むとあり、日本の貧困とは直接結びつかない感がします。
貧困率の計算方法
ここで厚生労働省の貧困率計算式を以下に図示しました。
(クリックで拡大)
この計算式は全体の50%以下の所得の人を貧困と定義するものです。ここが問題です。日本は既に見ましたように年功序列給与が実態ですから、年齢層が低く、給料が安い世代は、いずれ高くなっていきますし、加えて、アルバイト層が低くさせている実態ですから、この計算のみで貧困率が高いと決定づけるには無理があるように感じます。日本が貧困であるかどうかの検討判断は、もっと多角度から見た方が妥当でしょう。
しかし、確かに若い世代の消費行動は変わっていますから、マーケティングを変化させることが必要で、そのためには常に今の時流や、人々の意識を検討すべきでしょう。以上。
(3月5日のレターはパソコンが使えない地区への出張ですので休刊します)
【2010年3月のプログラム】
3月12日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
3月15日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
3月17日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 17:13 | コメント (0)
2010年02月05日
2010年2月5日 ロールモデルなき人口減政策
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年2月5日 ロールモデルなき人口減政策
日本と中国の同一性
日本は島国である。これは誰もが認めるだろう。ところが、中国も島国だという見解もある。中国は広大な国土であり、人口も世界一であるから、とても島国とは思えない。
しかし、次の地図をよく見てみると、中国は海に面していない地域が通過不能な地形や荒れ地に囲まれている。北方には人口まばらで横断が困難なシベリアとモンゴル草原地帯、南西は通過不能なヒマラヤ山脈、南部国境はミャンマー、ラオス、ベトナムと接する山と密林地帯、東は大洋で、西部国境だけがカザフスタンと接し大移動が可能だが、もし行おうとしたら大変な苦労が伴うであろう。その意味で中国は日本と同じく島国といえる。
(クリックで拡大)
もう一つ同一性は鎖国である。日本の江戸時代は鎖国をしていた。しかし、中国も同様に鎖国をしていたことを理解する人は少ない。元々日本の鎖国は中国を見習ったものであった。清国が鎖国(海禁政策)をしていなかったなら、日本が鎖国をしたかどうか疑わしい。当時の日本は中国をロールモデル(お手本)にして取り入れることが多かった。
開国結果は異なった
だが、この両国の鎖国は、19世紀半ばから始まった、欧米列強のアジア進出で開国を迫られ、お互い鎖国から開国へと国是を変更させられたが、その結果は大きく異なった。
清国は、沿岸部を侵略占領植民地化され、その回復には第二次世界大戦の終了まで待たねばならなかった。一方、日本は幕末維新時代に他国に侵略されず鎖国を終え、その後の成長発展に開国を結びつけることができた。この差の要因はどこに起因するであろうか。勿論、それは国内の戦争、官軍対幕府軍の本格的戦いを避け得たことで、仮に内戦をしていたら、独立国として維持できたか、歴史に「たら」はないが、今考えてみても恐ろしい。
何故に内戦にならなかったか
それはいくつかの要因が重層的に重なり実現されたものである。
まず、徳川慶喜の勤皇精神と時代感覚が大きかった。慶喜は戦いを避けた勇気なき将軍という評価もあるが、日本を外国勢に侵略されないよう、自ら将軍の地位を去り、和平路線に戦略を転換したことが最大の理由である。ということは、慶喜が持つ当時の政治と世界の動向把握力が鋭敏であったことに起因する。ここで争っては清国の二の舞になる、その時代感覚が慶喜の恭順路線となり、江戸城を捨て、上野寛永寺に謹慎蟄居という行動になったのである。
では、何故に慶喜将軍はこのような時代感覚を要し得たか。それは、それまでの将軍とは行動する舞台が全く異なっていたからである。歴代の将軍は江戸城奥にて政治を行っていた。ところが慶喜は将軍就任時も、それ以降も、また、14代家茂将軍時代にも、慶喜の居住は京都であった。何故なら幕末時、すでに政治の中心は京都・大坂の地に移っていて、ということは天皇が政治に関与しだしたという意味であるが、そのためには京阪の地に将軍が常住する必要があった。その結果として、慶喜は時の情勢の中に身をおき、時代感覚を肌で感覚できる環境にあった。
これが慶喜将軍の強みであり、弱みであって、結局、戦わずして江戸城を官軍に引き渡すという意思決定に結びついたのである。
人事が日本の危機を救った
鳥羽伏見の戦いに敗れ、将軍になってはじめて江戸城に戻った慶喜は、上野寛永寺に謹慎蟄居を判断する前、今後の帰趨を決める重要人事を断行した。勝海舟を陸軍総裁に任命したことである。
ご存知の通り海舟は咸臨丸でサンフランシスコに行ったように、ずっと海軍育ちである。新たに陸軍を預かることなぞ、今までの海舟履歴からしてあり得ない。また、陸軍は元来、海舟の政敵たちの牙城であった。その中核には陸軍奉行並小栗上野介がいて、歩兵奉行の大鳥圭介がおり、さらにその背後にはフランス公使のレオン・ロッシユと教法師(宣教師)メルメ・デ・カション以下の軍事顧問団がいる。その上最悪なのは、第一次長州征伐以来、陸軍は連戦連敗であり、まさにその劣等感がとぐろを巻いているような部隊であった。
このような陸軍を海舟が抑えられるか。それが慶喜の打った人事の要諦であった。何故なら、慶喜が恭順を実行に移すために必要な第一歩は、なによりもまず幕府内の主戦派の抑制でなければならなく、それを行うのが海舟に課せられた最大の役目であった。
しかし、実は、もっと重要な要素、海舟が陸軍総裁にならなければならない必然性が存在した。それは官軍側に送る外交シグナルである。主戦派を抑え、恭順派によって幕府内を握らしたというサイン、それが慶喜にとって必要だったからである。
さらに、この人事の背景には、もうひとつ国防に対する認識があった。それは、この時期、日本にとって守るべきは内乱であり、海外からの脅威ではないということ、つまり、海防ではなく、幕府対官軍の全面衝突という戦いと、幕府内の対立抗争という二つの争い、それは内乱であるからして当然に陸軍を抑えるという戦略となり、そのためには恭順派の代表的人物の海舟が任命され、それは海舟が事実上幕府の全権を背負ったという意味になるが、その不可避の人事を成したのは慶喜であった。
敗軍の将軍、慶喜の時代感覚は結果的に冴えていたといえる。
その後の発展要因
このように内戦を避け得た日本は、幕末維新時を巧みに切り抜け、近代国家として変身した成功要因については、すでに十分に分析され、語られているが、もっとも背景条件として大きかったのは人口増であろう。幕末維新時約三千万人であった人口が、現在一億二千万人、四倍に増加している。これが国力を大きく発展させたことは容易に判断できる。人口増なくして今日の成長はなかったのである。
しかし、時は変わり、今は人口減に向かっている。未だその減少実数は少なく、全体への影響は顕著になっていないが、いずれ大きな問題となっていくことは確実である。
ロールモデルなき人口減政策
世界について考え、将来の出来事を予測する手法を地政学という。地政学は二つの前提で成り立つ。一つは、人間は生まれついた環境、つまり、周囲の人々や土地に対して自然な忠誠心をもっているという前提。この意味は、国家間の関係が、国民意識と非常に重要な側面を持つ。二つ目は、国家の性格や国家間の関係が、地理に大きく左右されると想定すること。この二つの前提で、一国は国民意識によって結ばれ、地理の制約を受けながら、特定の方法で行動することになる。中国は中国でしかない特定の方法で行動するということで、日本も他国も同様である。
日本を地政学的に考えれば、地理的に隔離された資源輸入国であり、日本人は実力本位で登用された支配層に対し従おうとする統制された国民意識があり、それらから国家の分裂を避けようとする社会的・文化的影響力を内在し、短期間のうちに秩序正しい方法で頻繁に方向転換できる民族で、これが明治維新に端的に顕れたのである。
しかし、ここで地政学的見地の別角度から指摘しなければならないのは、日本人は外国人を移民として受け入れること、これに強い抵抗感を内在させている国民であること。それが前号レターのサンパウロ日系三世女性の発言で証明された。
これが日本人が持つ大問題であり、この内在要因を抱えつつ、日本は世界にロールモデルなき先端人口減政策を展開しなければならないが、解答を見いだせない問題です。以上。
【2010年2月のプログラム】
2月12日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
2月15日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
2月17日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 07:01 | コメント (0)
2010年01月20日
2010年1月20日 日本の移民政策の課題
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年1月20日 日本の移民政策の課題
ブラジルの現在実態
今の世界でBRICsという言葉を知らない人はいないだろう。21世紀に入って、世界経済はBRICsに代表される新興国に牽引されて成長している。
その代表国は中国でありブラジルであり、世界経済の中で確かな存在感を示し始めている。特にブラジルは、金融危機の傷が比較的浅く、国内景気は消費主導で底打ちし、豊富な天然資源と、年々向上する工業生産力に支えられ、日米欧や中韓などが進出を競っている国である。ブラジル市場を制するものが、世界の新興市場を制する、そんな時代が到来する可能性が高いのではないかということが、昨年12月に訪問したサンパウロの街を歩いていると実感できる。
ブラジルの政治実態
その背景にあるのは、まず、政治の力である。ブラジルの2010年現在の大統領は、左派・労働党のルイス・イナシオ・ルーラ・ダ・シルヴァで、2003年に「飢餓ゼロ」計画を打ち上げ、貧困家庭向けの食料援助や援助金制度などを推進した結果、これは日本の民主党が行おうとしている子供手当に通じる政策であるが、貧困家庭の生活水準改善が着実に進み、経済発展に取り残されていた内陸部へのインフラ整備も進めている。外交面では、南米統合へのリーダーシップも発揮し、2006年10月に行われた大統領選挙で、貧困層の圧倒的な支持を得て再選された。現在のブラジルは次図の成長ぶりである。
ブラジルは内需中心で成長している
また、ブラジルの成長は次図の通り低所得層のウェイトを約10%減らし、その分を中間層の増加で進めている。つまり、貧富の格差を解消しつつ、成長しているのであり、これは中国とは大きく異なる実態であることを前提として理解したい。
ビックイベントの開催
これに加えて、ブラジル成長の背景には「2009年10月2日に開催された国際オリンピック委員会(IOC)第121回総会で、16年の五輪がリオデジャネイロで開催されることが決定。南米大陸初の開催で、ブラジルは14年のサッカー・ワールドカップ、16年五輪と大規模イベントの開催が続く。オリンピックによる経済効果は大きい」がある。
日系三世から聞いたこと
ところで、サンパウロで夕食を一緒にした若い女性、彼女は日系三世だが、彼女から受けた質問、それが今でも強く印象に残っている。
「自分はイタリア・スペイン系のボーイフレンドと結婚する予定だが、親戚は皆日系人と結婚済みか、日系人を希望している。日本人は外国人が嫌いなのか」というもの。
「そんなことはない」と答えたが、内心忸怩たるものがあった。
1908年6月、ブラジル・サントス港に781家族が笠戸丸で着いて102年、現在、ブラジルには120万人の日系人を数えるが、そのすべての人ではないとしても、彼女から指摘される「日本人の内部に持っている本質」を意識せざるを得ないのは事実だろう。
オーストラリアの移民政策
現在、世界で移民先進国といえばオーストラリアだろう。慶応大学の竹中平蔵教授が日経新聞「経済教室2010年1月7日」で次のように述べている。
「いま世界では、オーストラリアの政策が注目を集めている。背景にあるのは明示的な成長戦略だ。ラッド首相は、現在2,200万人の人口を2035年に3,500万人に増やす計画を表明した」
これによると25年間で1,300万人増やすわけであるから、一年に52万人となる。現在のオーストラリア移民受け入れ数が、15万人であることを考えるとちょっと疑問だが、昨年11月20日のレターでご紹介したM君が市民権を確保しているように、オーストラリアは移民受け入れ先進国であることは間違いない。
日本の移民政策
一方、日本はどうなっているか。鳩山内閣は永住外国人に地方参政権を付与する法案を国会に提出する意向だが、民主党内や自民党にはまだ議論すべきという見解もある。このことの是非は今後としても、国内外の多くの識者が指摘するように、日本が直面する最大の課題は少子化による人口減である。
日本人口の2050年予測は、2009年対比20%減の10,170万人(国連人口基金予測)、この時点で65歳以上が4,000万人、14歳以下が1,500万人、半分以上の5,500万人が労働力から外れるので、経済を管理可能な水準で維持することが難しい。
その対策は、一つは家族政策としての「出産休暇や出産後の職場復帰体制の整備」であり、もう一つは移民政策としての「国境の開放」になるだろう。
ところが、現実の外国人受け入れ実態は、先日、上海で会った中国人を研修生名目で斡旋している企業幹部から聞くところによると、企業は安価な労働力としてのみ受け入れる傾向が強いという。
それも、中国の経済発展によって、大都市では日本に働きに行く人材はいなくなり、今や内陸部の奥深くまで採用に行くらしいが、実際に働く職場は、日本人が敬遠する深夜労働などが多く、当然に低賃金であるものの、本人たちは無駄使いせず、年間何十万と貯金し、中国に帰って、そのお金で家や車を買うという目的で来日するというが、まだ賃金格差が大きい場合は、こういう実態が続くであろう。
しかし、日本経済の低迷状態が長引けば、中国人を含めた外国人の出稼ぎは、経済成長している他国に行く可能性が強まり、日本には来なくなる危険性がある。
もう一つ大問題なのは、現実の日本へ帰化を希望する人々への対応が、非常に冷たいという評価が世界に定着していることで、日本にいる経済的メリットが少なくなると出稼ぎ受け入れ人数も急速に減る可能性が高い。
これらを考えれば、移民政策について真剣に検討すべきタイミングが来ていると思うが、その検討前提として、ブラジル日系人三世の彼女の発言は重要だ。
日本人がもつ外国人に対する感情論、表面から真っ当に発言できないが、日本人が日本人同士で結婚したがる本質、そのところの検討が避けて通れない大問題だ。これをどう解決するのか。それとも解決しないまま人口減を実現するだけになるのか。
移民政策を考えずに2050年を迎えることは恐ろしい。しかし、もっと怖いのは日本人の本質が変わらないことだとすると、その事態の時に、日本人はどういう行動に出るか。それが今から恐ろしい気がする。
ブラジル日系三世女性の発言は日本の未来への警告と受け止めた方がよいだろう。以上。
【2010年1月のプログラム】
1月8日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
1月18日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
1月20日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 10:01 | コメント (0)
2010年01月06日
2010年1月5日 簡単に頷かない
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2010年1月5日 簡単に頷かない
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
石破茂氏の講演
昨年12月17日、自民党の政務調査会長である石破茂氏の講演を聞く機会がありました。テレビで見る石破氏のイメージより、実際の本人は物腰やわらかくて、内容は分かりやすく、話し方によどみなく、メモを一切見ないで、過去・現在のデータや人物名を正確に表現するのには感心いたしました。
おかげで最近の政治情勢がよく分かり、自民党内きっての安全保証通といわれるだけあって、沖縄の普天間基地問題への考え方も明確でよく分かり、日米同盟の重要性を再認識いたしましたが、何か大事なことを石破氏は漏らしているのではと感じました。
石破氏の講演に対するアンケート結果
講演会場は満員で、約200名以上がおられたと思います。講演後にアンケートを書いて事務局に出された結果(46名)は以下のとおり高い評価でした。
1.本日の講演会はいかがでしたか。
大変良かった31人 良かった12人 まあまあ3人 不満足0 非常に不満足 0
2.その理由
非常に解りやすく、わが国の課題を話された。 保守の姿が見えた。 わかりやすく、理解しやすかった。もっともっとTVに出て、国民へのPRを欠かさずに頼みます。 率直な考えが聴けた。心に染み入りました。 一度直接、石破氏の話を聴きたかった。大変よかった。頑張って下さい! ポイントがよくわかった。正直。報道だけではわからない側面が見えてきた。 趣旨に賛同できた。政治がわかりやすかった。真実の事項が明確になった。 石破氏の考えと自民党の現状がよくわかりました。熱意が感じられた。 タイムリーな話が多かった。 具体的に解説してくれた。
23年間石破氏は主要な政治家だった
石破氏は1986年衆院議員初当選以来、連続8期当選していて、23年間政治家であると、ご自分で何回も触れました。ということはバブル崩壊後の経済政策に与党自民党の一員として、また、主要閣僚として大きく関わってきたということです。
では、その自民党政治が招いた経済実態を、次ページの国債残高で示してみました。
図の通り、バブル崩壊以前の国債残高水準は、主要先進国とほぼ同じでしたが、その後急激に増加し、その結果、図には記載していませんが、2009年9月末の国債残高は820兆円となってしまい、これは過去10年で倍増、GDP比160%を超え、IMFでは2014年にGDP対比246% になるだろうと予測しています。
このIMFの予測に石破氏も触れましたが、何か他人事のような発言でした。
日本経済が長期間低迷しており、膨大な国債残高を抱え、国民が日本の将来に不安感を持っていることは、すべての人に共通していることです。従って、それを解除させるまでとは言いませんが、将来見通しについて何らかの方向性・ビジョンを、石破氏が語ると思っていたのに発言されなかったこと、それが漏れていると感じたことなのです。
日本は非ケインズ効果に陥っている
戦後、日本政府がとり続けた経済政策は、一貫してケインズ政策でした。それをバブル崩壊後も同様で、返って激しく景気対策の名の下に大量の国債を発行してきました。
その結果は「時代の変化に適応力を欠く産業に労働力を釘付けにし、新しい時代に向けての産業構造の転換を遅らせてしまった」ことで、35兆円とも指摘されている今の需給ギャップとなっているのです。
この経済政策の問題点をいち早く指摘したのは、富田俊基氏(中央大学教授)で、1991年のことでした。日本は「非ケインズ効果に陥っている」という発表と、国会での意見陳述と各地での講演、私も次のように直接お聞きした記憶があります。
「国債残高が少ない間は、積極財政が景気を拡大するという効果がある。これは国民が将来の増税を意識しないので、個人消費をするからだ。
しかし、国債残高が高水準に達すると、更なる国債増発は車が壁にぶつかろうとしているのに、アクセルをふかすのと同じ現象を引き起こす。国は壁にぶつかるという心理的恐慌を国民に与え、将来の増税負担という心理状態にさせ、将来の可処分所得の現在価値が下落し、個人消費が抑制される。これが非ケインズ効果だ」
残念ながら、現状はこの指摘のとおりです。あまりにも膨大な国債残高という事態なのに、更なる国債の増発を実施するという経済政策は、ケインズ政策が意図することとは反対の効果で、個人消費は増えず、経済は縮小気味になっていくのです。
ですから、これを石破氏が理解していれば、このことに触れ、非ケインズ効果に陥っているが、今後はこういう経済政策で打開していく、と解説すべきであったのです。
だが、分かっていて敢えて発言しなかったとすれば、聴衆を無視したことになり、ご存じでないとしたら、政治家として大問題でしょう。
中国・上海にて
中国は2008年11月に総投資額4兆元(約60兆円)の景気刺激策を打ち出し、世界中を驚かせた効果は、一時落ち込んだ実質成長率が昨年7~9月期には8.9%に回復することで示しましたが、この実態状況を12月の上海で確認しました。
まず、クリスマスイヴに上海書城という上海一番の書店に入ると、村上春樹コーナーが広くとられていることに驚き、レジに並んでいる客が買い物籠に30冊から40冊入れていて、それも数人が同様の冊数であることにギョッとし、次に向かった南京東路の上海市第一食品では、特AA1級大連産干し海鼠が500g9,800元(14.7万円)に目を疑い、噂に聞いていた日本のリンゴ新世界が一個88元(1,320円)という価格の店内が、買い物客で溢れているすごさに、中国の強い消費意欲を実感したのです。
加えて、タクシー乗るため歩いた南京路の200m、その僅かな時間に偽物売り、ポン引き、直接寄ってくる若い女性など10人から声掛けられ、吃驚仰天の連続でした。
中国の地方で感じたのは日本と経済背景が異なること
翌日の25日、上海万博会場の真ん中を通る高速道路で、浙江省の寧波まで走り、そこから強蛟鎮(チャンチンチャン)という昔風の海辺の小さな港町に行きました。上海のホテルを出たのが8時半、走った高速にはまだ一か所しかないという、一応きれいだが閑散としたサービスエリアで休憩し、到着したのが13時、4時間半かかりました。距離は上海から約400km。現地では輸出ブランド子供グッズ製造企業の成金風の豊かな顔した社長から、アウディ大型新車で、高速を降りてから強蛟鎮まで案内してもらいましたが、道路は舗装をしていない部分が多く、港も未整備で、これは今後の公共投資が大いに実施される余地があると感じ、これからも景気刺激策は有効だと思いました。
中国はケインズ政策が有効に利く財政状態ですから、景気刺激策はダイレクトに成長へ結びつきます。対する日本は「非ケインズ効果に陥っている」のですから、中国とは異なる政策を展開すべきで、そのために我々が経済政策組み立てと推進について、簡単に頷かず、本質的な鋭い追及をしていくこと、それが今年最大の課題と考えます。以上。
【2010年1月のプログラム】
1月 8日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
1月18日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
1月20日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 09:14 | コメント (0)
2009年12月21日
2009年12月20日 山岡鉄舟に学ぶ
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年12月20日 山岡鉄舟に学ぶ
今年最後のレターとなりました。
日本経済は一段とデフレ色が鮮明化、景気は上向かわず、政治も日米関係にきしみが見えはじめたような気配、それに合わせて世間が何となく落ちつかず、はっきりはしないが、将来への心配の種がいっぱいあるような気がする、という年末ではないでしょうか。
だが、このような時であるからこそ、時代に惑わされず、時代に迎合せず、しかも時代の流れを取り入れ、且つ、自分の特長に適する妥当な生き方を追求し続けること、それが今の混迷時代でありながら「ブレない生き様」につながるのではないでしょうか。
実は、この「ブレない生き様」を、激動の幕末・維新時に貫いたのが山岡鉄舟です。今回のレターは、皆様に、先日、山岡鉄舟研究会例会で発表した内容をお伝えいたします。
鉄舟の大悟
鉄舟が大悟したのは、明治十三年(1880)三月三十日、四十五歳。この時に小野派一刀流十二代浅利又七郎から、一刀流祖伊藤一刀斎から伝授された、いわゆる「夢想(無想)剣」の極意を伝えられ、同年四月、鉄舟は新たに無刀流を開きました。
その後、明治十八年(1885)三月に、一刀流小野家九代小野業雄忠政から「一刀流の相伝」と、小野家伝来の重宝「瓶(かめ)割(わり)刀」を授けられ、それ以来「一刀正伝無刀流」を称することになり、これで、ようやく二つの流派に分かれていた一刀流が、鉄舟によって再び統括されたのです。
大悟とは
では、大悟とは何か。これをある程度明確化しておかないと、抽象的な理解で終わってしまいます。
広辞苑を繙(ひもと)きますと、大悟とは完全な悟りといい、迷いを去って真理を悟ることとあります。では、悟りとは何か。同じく広辞苑に、理解すること、知ること、気づくこと、感ずることとあり、仏教でいう迷いが解けて真理を会得することとあります。
また、認知科学では、人間の知覚というのは、徐々に潜在意識に深く入って行き、知覚→意味付け→納得→悟りになると考えているようです。
しかし、この悟りや悟った状態を、言葉で完全に表現することは不可能であるともいわれています。確かに、我々一般人が悟りということを、いくら論理的に検討しても、悟りの状態を体験的に完全に理解することはできません。
そこで、先日、北京オリンピック開催時に、金メダルの北島選手を含む水泳日本選手団を指導した林成之氏(日大医学部付属板橋病院救命救急センター部長)からお話を聞いた際に、冒頭「私は、人間が能力を最大限に発揮するための方法論を述べる」と語りました。
これをヒントにすれば、自分自身が持つ能力、それが余すことなく、最大限に発揮されれば、誰でも素晴らしい人生を送れるはずです。能力を最大限に発揮していないから、多くの人は課題・問題をもって、不十分な環境下におかれているのではないか。また、他人に対する影響力も少なく、結果として思い通りの人生になっていないのではないか。
つまり、大悟するとは、自分が持つ能力全てが発揮できる状態になった時を言うのではないかと思われ、鉄舟はこの境地に達していたと思います。
「一刀正伝無刀流」を開く
鉄舟は、二派に分かれていた一刀流を「一刀正伝無刀流」と統括しましたが、何故に、これに取り組んだかです。これについては、鉄舟長女の山岡松子刀(と)自(じ)が、牛山栄治氏に次のように語ったと「定本 山岡鉄舟」(牛山栄治著)にあります。
「父は思うところがあって大悟した後、無刀流の一派を開きましたが、浅利先生の剣もまだ本当ではないところがあると、たえず工夫をこらしていました。晩年(明治十七年)のことですが、一刀流六代の次に中西派とわかれ、小野派の正統をついだという業雄という人が上総にいることを探し出し、自宅におつれして、その剣技を研究していましたが、これが正しいのだとさとる箇所があり、自分の研究と照らして満足したようでした」
極意「一刀正伝無刀流十二箇条目録」
このような経過で、「伊藤一刀斎」が編み出した一刀流が、鉄舟によって再度統括されたのですが、その際、流祖伊藤一刀斎から伝わる極意を「一刀正伝無刀流十二箇条目録」として改めて書き示し、門下に目録として授与しました。
では、この極意の目録にはどのような剣技が記されているのか、これをお話する前に、伊藤一刀斎について、少しお伝えした方がよいと思います。
伊藤一刀斎とは
伊藤一刀斎は戦国時代から江戸初期にかけての剣客ですが、一刀斎の経歴は異説が多く、どれが正しいか拠り所がありませんので、「剣と禅」(大森曹玄著)から引用いたします。
「一刀斎は、通称を弥五郎と呼び、伊豆の人とも関西の生まれともいわれ、生国も死処も明らかでないが、身の丈は群を抜き、眼光は炯炯(けいけい)として、いつもふさふさした惣(そう)髪(はつ)をなでつけ、ちょっと見ると山伏かなにかのような風態で、実に堂々とした偉丈夫だったという。はじめ鐘捲(かねまき)自斎について中条流の小太刀と、自斎が発明した鐘捲流の中太刀を学び、両方ともその奥儀を極めたうえ、さらに、諸国を遍歴修行して諸流の極意をさぐり、また、有名な剣客と仕合をすること三十三度、そのうち真剣での勝負が七回で、一回も敗れたことがなかったという。それらの体験から一刀流を創始したが、老年になってから秘訣を神子上(みこがみ)典膳に授け、自身は仏道に帰依して行方を晦(くら)ましたので、一層その人物像が神秘化されている」
極意を好村兼一氏から教えていただく
剣については全く素人の身ですから、この極意「一刀正伝無刀流十二箇条目録」を解説する立場になっても、一切分からないのです。鉄舟研究者として「何とかしなければならない」という困った事態に陥りました。
その時、「伊藤一刀斎」(廣済堂出版)が、著者謹呈という手紙とともに手許に届いたのです。2009年9月に好村兼一氏が、伊藤一刀斎を主人公にした小説上下二巻の大作を出版したのです。天の助けです。早速、熟読し、伊藤一刀斎をようやく理解できました。
著者の好村氏は1949年生まれ、パリ在住の剣道最高位の八段です。2007年に「侍の翼」で小説家としてデビューした際、縁あってパリでお会いしたことから親しくなりました。そこで、今回もパリでお会いし、いろいろ極意について、親切にご教示いただくことができました。大変ありがたいことです。幸運が舞い込んできた気持ちでした。
極意「切落し」
極意「一刀正伝無刀流十二箇条目録」には「二之目付之事(にのめつけのこと)、切落之事(きりおとしのこと)、遠近之事(えんきんのこと)」など十二箇条が取り上げられています。
これらについて好村氏から身振り手振りで解説いただきましたが、ここで十二箇条すべてを解説することはページ数の関係でできません。
ですから、この中で今の時代に最も大事で、鉄舟が成し遂げた偉業「江戸無血開城」の原点をなすものであり、好村氏が「一刀斎が築いた一刀流剣術は現代剣道の根幹を成しており、極意『切落し』は今なおそこに生き続けている」と高く評価する「切落之事」のみ触れたいと思います。この詳しい内容は好村氏の小説の中で、鐘捲自斎と弥五郎(一刀斎)の手合せ場面に詳しいので、できればそれをご参考にされることをお薦めしますが、
「自斎の二の太刀が頭上目がけてきた瞬間、今だーと弥五郎は怯(ひる)まず、よける代わりに上から鋭く切落す・・・・。弾かれたのは、今度は自斎の竹刀であった。」
とあるように、「切落し」とは、相手が剣を打ち込んでくる瞬間、逃げずに、間髪を容れず、真っ向から剣を振り下ろすことなのです。
時代から逃げない
剣の道は「人と人との闘い」、つまり、それは闘いという「人間関係論」とも言え、それを剣から説き起こしているのだ、と考え気づいた時、極意「切落し」は、今の時代の生き方を我々に提示しているのではないか。強いデフレという苦しい状況下でも、現実から逃げず、一人ひとりが必死に工夫と努力を重ねること。そのことを極意「切落し」が語り、鉄舟が目録として伝えたのです。本年の愛読を感謝。よいお年をお迎え願います。以上。
【2010年1月のプログラム】
1月 8日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
1月18日(月)18:00 経営ゼミナール(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
1月20日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 20:37 | コメント (0)
2009年12月07日
2009年12月5日 デフレ経済から脱却できるか
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年12月5日 デフレ経済から脱却できるか
ミシュラン日本観光ガイド編集者と会う
11月17日からのパリ出張は様々な人と会いました。まず、世界で著名な香水ボトル瓶デザイナーの女性、この人物とは9月にも会いましたが、彼女の業界デビュー出世作品が、友人と接点があったことがわかり、なるほど、世の中はどこかでつながっているなぁと、改めて感じた次第です。
次に、以前から考え続けている日本の観光大国化への道、それは多くの欧米人が日本を訪れるための方策検討ですが、その有効な手段としてミシュラン社・グリーンガイド、アシェット社・ブルーガイドをうまく活用できないかとの視点から、パリで両ガイドの編集に携わったジャーナリスト男性と会いました。
シャンゼリゼ大通りのお菓子屋の奥、そこで新しい展開を始めたアールヌーボースタイルのカフェで、ディスカッションしましたが、結果的に彼は日本ファンですから、当方が提案した内容について「それはグッドアイディアだ」と、かえってこちらに今後の協力を求められる素晴らしい出会いでした。この内容については、12月20日(日)・21日(月)に開催される経営ゼミナール伊豆湯ヶ島温泉「白壁荘」特別例会で、皆さんにご検討いただくことになっています。ご参加ご希望の方は「経営ゼミナール」のサイトからお願いいたします。観光客を増やし内需拡大への一方策と位置付けています。
ボージョレ・ヌーボー
シャンゼリゼ大通りからホテルに戻って、近くのスーパーに行きましたら、入口を入ってすぐのところで、粋なハットの男性が小さいカップを差し出します。
そうか、今日は第三木曜日の11月19日のボージョレ・ヌーボー解禁日かと思い、注がれるままに三種3杯試飲しました。
たまにはヌーヴォー(新酒)仕様で軽い仕上がり赤ワインもよいだろうし、今年のワインは、日照時間が多く、50年に1度の出来と報道されているので、ボジョレー・ヴィラージュ、ブルゴーニュ地方ボージョレー地区とボトルに貼られているものを一本買いました。しかし、実は、価格に釣られて買ったのです。
一本3.9ユーロ、4.9ユーロ、それと5.9ユーロの三種類、5.9ユーロ物を買いましたが、1ユーロ=138円換算で約800円です。安いと感じ、大型バックに重梱包して大事に持ち帰りました。
ところが、日本に戻って新聞を整理していると、スーパーイオンで一本750円、ビックカメラでは930円で発売とあるではありませんか。
パリのスーパー価格が安いと思って持ち帰ったら、輸入運賃を掛けた日本の方が安値とは、この事実に驚きました。ただし、実際にイオンのボージョレ・ヌーボーを飲んでいませんので、味わいは分かりませんが、それでもサントリーやメルシャンは2,000円以上、通販サイトで安い順序から価格を検索してみましたら、最低価格のものが1,785円ですから、イオンは安すぎでしょう。
政府がデフレ宣言
11月20日の政府月例報告で、日本経済は物価が持続的に下落する「緩やかなデフレ状態にある」と正式に表明しました。
そのデフレと判断した理由として
(1)、消費者物価指数(CPI)の下落が続いている
(2)、名目成長率が2四半期連続で実質を下回った
(3)、需要から潜在的な供給力を差し引いた「需給ギャップ」のマイナスが拡大し、年
40兆円規模の大幅な需要不足に陥っている
と述べています。今まで、政府は2001年3月に戦後初めて「デフレ」と認定しましたが、2002年以降に景気回復局面に入り、2006年7月の月例報告から「デフレ」の文言を削除した経緯があります。だが、昨年のリーマン・ショック後、日本経済は深刻な需要不足に陥り、CPI下落が今年8月に最大の2.4%になるなど物価の下落が目立ち、今回の表明となりました。実態から判断すれば当然と尤もな表明でしょう。
ユニクロの好調
ご存じのとおりユニクロは快調で、業界独り勝ちという勢いです。パリにも10月出店しました。オペラ座の隣のデパートが並び立つ繁華街です。
一か月と少し経過してどうなのか、11月18日午後2時頃に店内に入ってみると、明るくリズム感があり、活気に溢れ、大勢の客で、レジ待ちの人もたくさんいます。話題のヒートテックを大きく訴求していますが、いくつか手に取ってみた感じで、価格は高いと感じました。ジーンズは39.90ユーロ(約5,500円)、カシミヤのセーターは69.90ユーロ(約9,600円)ですから、これは円高を見込んで1ユーロ100円感覚で値段設定しているのではないかとも思いました。
ユニクロと他店と比較してみようと、翌日19日は周りに展開しているライバル店にも入ってみました。訪れた12時過ぎ、ユニクロは一階レジが10台で客13人、GAPはレジ4台で客2人、H&Mは1階が8台で3人、地下が7台で12人、ここは活気がありましたが、ZARAは3台で5人という状況でした。
一日だけでは状況が分かりませんので、20日も回ってみました。やはり12時過ぎ、ZARAは客3人、H&Mは1階に12人、地下に1人、ユニクロは1階3人、地下7人、GAPは1人。こうみてくるとH&Mが強く、次にユニクロかなという感です。H&Mはファッション性、ユニクロはしっかりした品質とテクノロジー性、どちらが世界市場で勝利を得るか、それが見ものですが、これから海外に出店数を無限に伸ばせるユニクロの未来は明るいと感じたパリでした。
ユニクロの成功は時代感覚への読み
10月開催された第11回日経フォーラム「世界経営者会議」で、ユニクロの柳井正会長兼社長は次のように発言しました。
「世の中には価格が高くて良い服と、安くて悪い服しかないという常識を破り、安くて良い服を作ろうと思った。そのために企画、生産、物流、販売をすべて自社でコントロールし、お客様に満足してもらえる服をと考えてやってきた。我々ほどまじめに服を作り、販売しているところはないと自負している」
この言葉、ユニクロ独り勝ちの実態からみれば、その通りとうなずかざるを得ませんが、もっと背景的で根本的な成功要因は「時流に適合した」ということでしょう。
つまり、デフレ時代という時流を先取りしたのです。創業は60年前の駅前商店、その後1984年に広島にユニクロ1号店を開業し、今日に至っていますが、その間、柳井会長は時代を分析し、今訪れている激しいデフレ時代が来るだろうと予測し、今日の業態をつくりあげたのでしょう。見事な時代の読みと感服します。
デフレは簡単には解決しない
完全なデフレ状態では、物価が下がり続けますから、企業の売上高は増えず、結果として賃金も増えなく、景気は好転しないことになります。従って名目GDP、これは物価動向に反映し、景気の実感により近いとされますが、その金額は479兆円となってしまい、これは1992年並みの水準になりました。
ということは、日本経済が約20年間に渡って成長していない事実を証明しているわけで、この実態を考えれば今の経済実体を、とても一時的な局面とは考えられません。
デフレは貨幣的現象というのが、多くの経済学者が主張する見解であり、伝統的な経済理論によって、現在のデフレ実態を解決しようとする立場から、日銀に対し超金利政策の維持や、更なる量的金融緩和の実施を求める声と、それに対応する日銀という姿が今の日本経済です。しかし、この日銀の政策を超える、もっと基本的・根本的な時代潮流としての何か大きな「歴史の峠」的な現象が背後にあって、それが轟音となって流れ、その表出現象の象徴がデフレ実態として表現化されていると思われるのです。
その背後に存在するであろう「歴史の峠」的な現象は、経済学者ではない歴史家・哲学者・作家などが主張する「時代は大転換期に位置している」というものではないかと思いますが、この指摘を真剣に考え論じ、時代の動向分析を本格的に行い、長期スパンでの未来洞察を行わないと、日本はデフレ実態からは脱却できないと考えます。以上。
【12月のプログラム】
12月11日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
12月14日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
12月20日(日)18:00 経営ゼミナール 伊豆ミシュラン戦略研究会
投稿者 lefthand : 09:49 | コメント (0)
2009年11月23日
2009年11月20日 これから5年~8年
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年11月20日 これから5年~8年
5年先を予測できるか?
毎日新しい事件が発生し、我々の生活に影響を与えています。特に、突如発生したサブプライムローン問題による金融問題、これによって世界全体の経済が混乱し、いまでも収まっていません。
このように予測つかないことが発生するこので、先行きの予測がつかないのだから、5年先のことなど分かるはずはない、と殆どの人が答えるでしょう。
また、多くの情報と分析力を併せ持つエコノミストでも、サブプライムローン問題を事前に予測できず、また、予測していたとしても、実際に発生した規模内容を的確に指摘していませんでしたので、確実な未来経済予測はできない、と一般的に思われています。
だが、確かに未来は不確定で、予測は困難ですが、5年先を考えることは必要なのです。
何故なら、未来を考えていないと、これからの計画ができなくなり、さらに、計画がないということは、企業経営も人生設計も、その場当たりにならざるを得ず、結局、目的・目標が達成できたかどうかも分からないことになってしまいます。
計画があるからこそ、結果と計画を比較することができ、その達成・未達成が判断できるのです。従って、何事にあたっても計画を作ることは大事で、不可欠事項であり、その計画をつくるためには、予測は難しいという前提ながら、未来を考えておくことが必要です。
天地人NHK大河ドラマ
NHK大河ドラマ「天地人」は平成21年1月から始まりました。主人公の直江兼続は、米沢藩初代藩主上杉景勝を支えた文武兼備の智将で、関が原敗戦後、上杉家の米沢移封に伴い執政として米沢城下を整備し、現在の城下町米沢の基盤を築きました。また、現在国宝に指定されている「宋版史記」や「漢書」などを集めた文人で、その深い教養と見識は豊臣秀吉や徳川家康からも高く評価され、上杉謙信を師と仰ぎ、「利」を求める戦国時代において民、義、故郷への「愛」を貫き、兜には「愛」の文字を掲げた人物です。
このような説明を大河ドラマ開始時に知りましたが、その時点で、直江兼続という名を理解していた人は少なく、NHKに登場するというので、初めて知ったのが殆どではないでしょうか。私もその一人で、一般的には無名の人物が、どうやって大河ドラマになり得たのか、それをずっと疑問に思っていましたので、先日、米沢の上杉神社境内で開催されている「天地人博」に行ってまいりました。
「天地人博」にはすでに20万人以上が訪れているとのことですが、会場を出て、上杉神社に参拝しようと歩いて行くと、天地人のジャンパーを着た男性が近寄ってきて、ガイドいたしましょうかと声をかけてくれました。
これ幸いと、いろいろ伺うことが出来た中で、次の一言が耳に残りました。
「無名の直江兼続をNHK大河ドラマにしようと、米沢市が中心になって5年~8年前から企画し、まず、火坂雅志氏に小説「天地人」( 2006年9月NHK出版)を書いてもらうことから始めたのです」と。
なるほどと思いました。無名を有名にしたいという考え、つまり、計画が前提にあったのです。さらに、ガイドは「直江兼続が無名であったからこそ、今回の成功があったのです」とも補足してくれました。
その通りと思います。今回の計画がなければ、米沢市は今まで通り、上杉鷹山だけの街で終わっていると思います。
シドニーのM君
先月はタスマニア島とシドニーにまいりました。タスマニアのホバートからシドニーのホテルに夜遅く着き、翌朝、朝食をとっていると、笑顔にあふれた若者がこちらに走ってきました。
2005年12月にシドニーを訪れた際、車運転してくれたドライバーのM君です。当時はシドニーのJTBドライバーでした。握手してM君の服装を見ますと、シドニー市営バス運転手の制服です。JTBを退社し、市役所勤務に代わったことは、以前に受けたメールで知っていましたが、勤務中の合間にわざわざ時間を割いて、会いに来てくれ「いろいろアドバイスありがとうございました」とお礼を言われました。
4年前にM君に何をアドバイスしたか忘れましたが、多分、5年先を考えて未来設計を
したらどうか、ということを述べたような記憶があります。
M君は「お土産です」とひとつの小冊子を渡してくれました。表紙を見ると、何とそこにはM君の写真があるではありませんか。小冊子は市営バスの時刻表です。その表紙をM君が飾っているのです。模範ドライバーなのです。すごいなぁーと褒めると、ポケットから三か月の長男の写真を嬉しそうに見せてくれます。市役所に勤務し、元同僚の日本女性と結婚し、子供が授かったのです。元気で頑張るよう励まし別れましたが、とても幸せな気持ちになりました。なお、JTBは今年9月末に閉鎖、元同僚は全員リストラになりました。
シドニーのNさん
この日の夕食は海辺のレストランに行きました。テーブルに着くとアジア系の若い女性が来て、流暢な英語で注文をとります。
シドニーロックオイスターのレギュラーサイズと、スモールサイズを各6個ずつ注文し、ワインは白のマーガレット・リバー Margaret Riverと伝えると、手許のメモ帳リストをすばやく見て「承知しました」とスピード感ある明確な応対に気持よくなりました。
この仕草を見て、直感的に「この女性は日本人ではないか」と思い、日本語で次のオーダーをしてみましたら、ニコッとうなずき「何にしますか」と日本語、それからスムースで、名前もNさんと自己紹介受け、地元の料理を推薦してくれ、夕食を堪能しました。
ところで、何年シドニーにいるのですか、と聞きますと5年弱との答え。それでは「永住権」は取れたのですね、と聞きますと、急に泣きそうな顔になって「まだです。あと5ヶ月でビザが切れます」というのではありませんか。
「永住権」を取得するには、医療やIT技術関連など人手不足分野業務か、美容師とかケーキ・寿司職人などの熟練技術者として認定されることが必要なのですが、Nさんはそれを持っていないのでしょう。レストランのウエイトレスでは熟練技術者として認められません。今までの5年間、何を考え、何をしていたのか、喉から出かけましたがやめました。
2009年4月~9月決算発表
2009年7月から9月のGDP(国内総生産)の伸び率は、前の3カ月に比べて、年率に換算して4.8%のプラスとなり、4月から6月の伸び率2.7%に続いて、2期連続のプラス成長となりました。世界の景気状況が若干改善し輸出増、それとエコカー減税など、前政権の景気刺激策の効果もあり、個人消費が持ち直したことが寄与したとの発表です。
一方、2009年4月~9月上場企業の決算発表を見ますと、業績の上方修正が多くなって、企業間・業種間で業績の差がはっきりしてきました。業績差の要因は、サブプライムローンダメージが限定的な新興国で、稼げる体制を築いているかにかかっています。例えば、ホンダはアジア地域が健闘しているため、2010年通期の業績予想を減益から増益に変えましたし、コマツも中国やインドネシアで活発活動の結果、業績を下支えしています。
つまり、業績の上方修正は、新興国に対する対策を進めてきたかどうかであり、それには数年前、少なくても5年程度前から新興国に手を打ってきたかどうかで決まっているのです。
ボリュームゾーンに軸足を
経済成長するという意味は、その国の中産階級が増加し、この層がモノを買いだして内需が増えて、結果的にGDPが増えるということです。かつての日本がその良い見本です。
世界経済は米国主導型から、新興国に向い、多極化、多層化に変わっていっています。そのような変化が5年ほど前から明確になってきて、サブプライムローン問題から一段と鮮明になってきました。つまり、今の経済状況変化が示すことは、需要の主軸が移転する端境期に位置しており、この構図はしばらく、それは5年~8年程度は変わらないと予測します。
2020年から2050年
しかし、その後の2020年から2050年、このころになると世界中で大変化と大事件が続発し、世界構図と情勢は今と大きく変わり、今の5年から8年程度の予測ではとても対応できず、未来計画つくりは相当の困難が伴います。しかし、長期行動方向指針を定めるためには、世界全体がどのような姿になるかという、概略の考察がどうしても必要です。以上。
【12月のプログラム】
12月11日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
12月14日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
12月20日(日)18:00 経営ゼミナール 伊豆ミシュラン戦略研究会
投稿者 lefthand : 09:41 | コメント (0)
2009年11月06日
2009年11月5日 来てみればわかる
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年11月5日 来てみればわかる
タスマニアの特殊性
タスマニア・ホバートの水産局係官から、名刺のデザインの説明について聞いたことの内容は、前回レターでお伝えしました。名刺のスローガンは「Explore the Possibilities」で、直訳すると「可能性を探検する」ですが、一言で述べれば「来てみたらわかる。来なくちゃ分からない」ということでした。
タスマニアは、自然環境を守っていることに絶対の自信を持っている。こういう島全体が環境保全されているところは世界でも少ない、つまり、環境保全面で特殊性があることが、観光としての魅力の源泉になっているという自負心がスローガンに溢れているのです。
日本の特殊性とは
観光として魅力となる特殊性、それを日本に当てはめればどのような要素になるでしょうか。日本では当たり前の普遍性であるが、外国人にとって特殊性となるもの、それは日本の温泉地、それも内湯旅館・ホテルではないかと思います。
そのことを今年の3月に発売された、フランス・ミシュランのガイドブック日本観光版「グリーンガイド」が教えてくれました。グリーンガイドが、日本に数多くある温泉地から三つ星に格付けしたのは、殆ど日本人に知られていない「ひょうたん温泉」と、坊ちゃん風呂で知られている四国松山市の道後温泉本館です。日本全国には、3,000余の温泉があるわけですから、この中から二か所のみが三つ星というのはさびしい限りです。
ひょうたん温泉ツアー
では、どうして無名のひょうたん温泉が選ばれたのか、その要因を探ろうとツアーを企画しまして、温泉研究熱心な仲間と行ってまいりました。
ひょうたん温泉は、別府市内の中心地から離れた鉄輪地区にあり、タクシーで向かいました。タクシー運転手によれば、最近、欧米人の観光客が増え、彼らは路線バスか、徒歩で目的地に向かう人が多く、手にはグリーンガイドやブルーガイド(仏アシェット社発行の旅行ガイド)を持っているとのことです。
さて、到着したひょうたん温泉の駐車場は満車、道路向かい側には葬祭場、その隣はスーパーで、周りは住宅街という市街地に位置し、日本の多くの温泉地が自慢する自然景観とは全く関係なく、全国各地にあるスーパー銭湯と何ら変わりはありません。
グリーンガイド掲載内容
ここでミシュランガイドに掲載された内容を翻訳紹介いたします。
■Hyotan Onsen★★★ ひょうたん温泉
「鉄輪にあり、駅よりバス33番または34番で地獄原下車、営業時間9時〜1時、料金700¥。鉄輪バス主要停留所から東に700メートルにある。
この施設は大変心地よい緑に囲まれている。砂場、露天風呂、館内にはひょうたん形の風呂、サウナ、肩のマッサージ用の滝湯、またレストランもある。家族だけで使用できる露天風呂を予約することも可能」
共同風呂が格付けポイント
グリーンガイドでひょうたん温泉について書かれていることは、これがすべてです。この程度の情報提供で、星を三つ与えているのです。もう少し詳しく書いてもよいと思うのが普通ではないかと考えつつ、料金を払い入りました。
入口から奥に進み、下駄で中庭に出ます。カランコロンと心地良い音色がします。中庭にはテーブルと椅子が配置されており、ここで待ち合わせやちょっとした軽食をとることができます。休憩所を兼ねたレストランも併設されています。男女別に分かれている入口をくぐると脱衣所があります。ここで衣服を脱いで温泉への階段を下ります。館内はとても広々としていて、高い天井に張り巡らされている板は少し隙間が空いていて、柔らかな日差しが差し込みます。中央には大きな木がそびえ立っており、自然の中で入浴しているかのようです。その周りに数種類のお風呂があり様々な入り方を楽しめます。隣には身体をマッサージする滝湯があり、10メートルもあろうかという高さから注がれており、強い刺激を得ることができます。外には大きな空と緑の広がる露天風呂があり、とても開放的な気分で入浴できます。奥には低温、高温二種類のサウナ室があり、体調に合わせて利用できます。別室に砂風呂があり、浴衣を着て熱い砂に入って身体を温めることもできます。
このような各温泉を回り楽しんでいるとき、突如、ひょうたん温泉と道後温泉本館の共通点に気づきました。それは「共同浴場」だということです。そういえば、別府の竹瓦温泉も二つ星ですが、ここも入浴料100円の市営共同浴場です。
日本の温泉地は世界の特殊性
実はここに日本の温泉がもつ、世界から見た特殊性があるのです。
温泉研究者の世界的権威である、ウラディミ-ル・クリチェクが世界の温泉国について次のように述べています。(「世界温泉文化史」1990年)
「統計学を信頼するならば、湯治場は今日、ほとんどヨ-ロッパだけに分布していることになる。1971年の大部の温泉誌では、全体で19か国1,100の温泉のうち、97パ-セントがヨ-ロッパに存在する。以下、中部ヨ-ロッパの枠を越えて、いくつかの特殊な湯治について一瞥してみることにしたい」
とあり、その特殊な湯治として「ロシアの温泉浴と蒸気浴」「フィンランドのサウナ」「イギリスとアメリカで流行の入浴」「トルコとアラビアの入浴」そして「日本、中国、アフリカでの入浴」が書かれています。このように温泉学の権威が「日本の温泉地を特殊性」と断定していることに、意外の感をする方が多いのではないかと思います。
何故なら、日本人は日本を温泉大国と考えているからです。たしかに温泉地の数は多く、温泉を国民の大多数が利用しているですから、その意味では温泉大国といえるのですが、世界の温泉の常識からは外れているのです。その常識の基準は「温泉とは湯治場であり、共同風呂」であるという前提です。
実は、この基準でグリーンガイドが格付けしたことを、ひょうたん温泉の露天風呂の中で気づいたのです。気づいてみれば簡単です。欧米の温泉地は共同風呂しかないのですから、ミシュランの格付け評価担当者は、自らの常識の範囲内の共同風呂を探し、その結果、日本で無名ではありますが、ひょうたん温泉を選んだのです。
背景が分かれば簡単です。だが、しかし、これは日本が観光大国化へ向かうためには大問題です。日本に数多く存在する温泉が、欧米人から見れば、自分たちの常識から外れているということです。ここを何とか欧米人に理解させないと、日本の温泉に多くの外国人が来ません。日本の特殊性を逆に魅力化し、受け入れられるようにすることが必要です。
「来てみればわかる」よう情報編集して特殊性を観光の目玉にする
観光庁の本保芳明長官が、2009年度の訪日外国人旅行客数は前年より二割減り、背景に金融危機は最悪期を抜けたものの、円高傾向が続いていることをあげ、今後の外国人旅行客数増加は中国を最重点課題にしていくと発言しました。(日経新聞09.10.29)
これも大事です。しかし、我々ができる身近な対策も必要と思います。
時折、宿泊する伊豆の温泉旅館、ここには外国人がよく来ています。その人たちに聞くと、日本の温泉は素晴らしいと発言します。勿論、内湯旅館の風呂のことです。
この事実を大事にしたいと思います。経験すれば、知らなかった日本の温泉が好きになるのですから、何らかの方法で欧米人に発信することです。
その発信の大きな要素は、外国の書店に並んでいる外国語の「日本観光ガイドブック」、グリーンガイドやブルーガイドですが、この中で「日本の温泉は、外国には存在しない特殊形態だが、一度経験すれば多くの人がその魅力に包まれる」、つまり、タスマニアの「来てみればわかる」という事例と同じようにすることが必要です。
では、そのためにはどうするか。それは、グリーンガイドやブルーガイドへの情報編集伝達力にかかっているのではないでしょうか。
観光庁が展開する全体的な対策に加え、グリーンガイドやブルーガイド編集部門へのアプローチを個別に具体的に行うこと、それが、実は、日本を観光大国化へ早めるための有効策ではないかと思っています。何故なら、一度掲載されるなら、それは世界中の書店に並ぶからです。その意図で、近々、伊豆の旅館を事例に、グリーンガイドやブルーガイド編集部門に提案しようと思っているところで、その研究会を12月に開催します。以上。
【11月のプログラム】
11月13日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
11月14日(土)18:30 山岡鉄舟研究会「生麦事件歴史散策研究会」
11月25日(水)18:00 経営ゼミナール川越・さつまいもビール工場見学
投稿者 lefthand : 06:56 | コメント (0)
2009年10月21日
2009年10月20日 環境条件にあわせる
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年10月20日 環境条件にあわせる
大分県別府駅前の交差点、一匹の猫がゆったりと渡っていて、名門デパートTOKIWAに入ってみますと、シーンと静まりかえり、店員だらけでした。だが、同じ別府市内の鉄輪地区のひょうたん温泉は、県外客と外国人で大盛況、さすがにミシュラン観光ガイド三ツ星の威力と思いました。
ホテルとひょうたん温泉を往復したタクシードライバー、市長が変わるたびに街のお祭り展開内容が変わるとぼやいていました。
時代はグローバル化、すごい速さで変化しています。環境変化にあわせているか、いないか。今号は環境条件にあわせようとしている外国都市事例をご紹介します。
タスマニアは環境島
「世界で一番空気と水のきれいな島。世界一ピュアな風に包まれ、欝蒼と生い茂った温帯雨林、太古の姿を残す動植物。歴史の漂う素朴な町、そこはオーストラリア最南端に浮かぶ島タスマニア。心の赴くまま静かに流れる時を過ごしませんか」という言葉に惹かれ、タスマニアへ行ってまいりました。
タスマニア島はオーストラリアの南東に位置しています。成田からまずシドニー空港に着き、持ち込み品の厳重検査を受けて乗り換え、タスマニアの州都ホバート空港に着きますと、またもや検疫官がいて、生もの食品の持ち込みを見張っているように、オーストラリアは、食べ物持ち込みに厳しい条件をつけていますが、その中でもさらに厳しいのがタスマニアです。
タスマニアは北海道の約80%の面積、人口は約50万人で北海道の9%、その上高い山がありませんから、広々とした景観がどこまでもつながっているところです。
ホバートで、まず、最初に訪ねたのが「タスマニア州第一次産業省水産局」で、ホテルを出ようとロビーを歩いて行くと「コンニチワ」とすごく明るい声で女性が声掛けしてきます。同行する現地の方の知り合いの人だと思い「お知り合いですか?」と尋ねますと「いいえ、知らない人です」との答えです。ホテル前道路を歩いていると、またもや「コンニチワ」です。タスマニアの人々は人情厚く親切で、道で地図を広げていると、必ず「どこへ行くのですか」と声掛けしてきます。これでこの地の人柄が分かりました。
水産局でタスマニアの漁業全般、水産業・養殖業の統計的な数字、漁獲割り当て・資源保護・今後育成すべき分野などの政策的な情報を入手した後、いただいた名刺のデザインを興味深く見ていると、坊主頭の担当官が説明してくれました。
上下の波線は海を表し、縦線はグリーンと森を表し、この二つに囲まれた中に野生動物タスマニアンデビルを描き、その下にスローガン「Explore the Possibilities」、直訳すると「可能性を探検する」だが、一言で述べれば「来てみたらわかる。来なくちゃ分からない」ということだ、と補足します。
この補足説明に納得しました。余計な宣伝はしない。自然環境を守っていることに絶対の自信を持っているので、訪れた人々がタスマニアの事実報告してくれ、それが宣伝になるのだ。つまり、地球環境問題が問われている今の時流に、完全に合致しているという自信なのです。タスマニア各地を回り、その事実を確認して戻ったところです。
パリは観光で持っている街
パリ市役所別館はオステルリッツ駅近くで、環境関連部門が集まっています。現在、パリ市役所に対する外部からの取材は、すべて広報を通すことになっていますが、広報を通すと取材拒否されることがあるし、面倒なので、何とか知り合いの縁を探して、パリ市の環境問題解決方向の実態を聞こうと、緑地環境管理本部の管理職を訪れました。
3階の管理職個室に入ると、髪を後ろに束ね、あごひげをきれいにカットした、50歳代の気さくな感じの柔らかい人が、机から立ち上がって手を差し出してきました。
まず、彼の最初の発言、それは「パリには工場がない」という言葉、これを聞いた瞬間、パリが理解でき、他都市との違いを納得できました。1980年までは工場が市内にあったが、全部郊外か外国に移転した。最後がシトロエン工場であったが、今は公園になっていると補足します。世界の大都市で工場が存在しないところはあるでしょうか。調べていないので断言できませんが、多分、他国の首都では必ず工場ひとつくらいはあると思います。工場を市内から排除すること、これがパリの行ってきた環境対策であり、その目的はパリ市の存在意義に通じるものであり、それを目指してパリをつくってきたのだということが、この工場がないという発言に凝縮しているのです。
また、交通対策も明快だと発言します。それは「なるべく車でパリに入らせない」ようにすることにつき、車排除する代替策は、バスとトラムと自転車の活用であり、その結果、CO2が少なくなり、街を歩く人に安全と健康を提供できることになる。
つまり、これがパリを訪れた観光客への最大のプレゼントになるというのです。フランスには年間、観光客が8,000万人訪れます。その首都であるパリには、企業の本社が多く、観光客も当然多いわけで、パリ市の人口は200万人ですが、パリ市にいる人の数は毎日1,000万人ですから、五倍の人が動いている街です。ここで観光客が支払うホテル代、飲食代、お土産にも当然19.6%の消費税がかかり、シャルル・ド・ゴール空港の免税手続きDetaxe窓口は、いつも人で溢れていますから、パリで高額品のお土産を買う人が、いかに多いかが分かります。
私のように免税手続きをしない、つまり、高額な買い物はしない者も多く、この人たちはホテル代、飲食代に19.6%だけ支払ったまま出国するので、パリ市は膨大な消費税で丸儲けでしょう。観光大国とは外国人から消費税を徴収する大国であるともいえます。
日本も観光大国を目指していますが、フランス並みになれば、財政赤字の軽減効果は大きいわけで、そのためにもパリの観光対策から学ぶことは多いと思いますし、パリの動きは今の時代の地球環境問題対策にも合致している事例と思います。
ニューヨークが挑戦する新しい環境対策
アメリカ・ニューヨーク・マンハッタンのスラム街としては、かつてはハーレムが有名で、犯罪と貧困に喘ぐ地域でしたが、1990年代に行った徹底的な治安改善政策により、環境が驚く程改善され、現在では街の再開発も進み、文化と経済のネオ・ハーレム・ルネサンス期に入っています。したがって、ニューヨーク(NY)市には貧しい人々が住む地区があっても、スラム街はない、と一般的には思われているのですが、今でもNY市にはスラム街が厳然と存在しています。それは、マンハッタンではない地区、イーストリバーを渡ったSOUTH BRONX(SB)地区です。
このSB地区、当然に単独行動では危険な地域であり、夜間はNY市民でも足を踏み入れない地区ですから、何らかの安全策を講じて歩かなければならないと思っていましたら「SUSTAINABLE SOUTH BRONX環境」(持続可能な南ブロンクスSSBx)という案内ツアーがあることを知りまして、一人10ドル支払うと、ボランティア活動しているメンバーが案内してくれるというので、申し込んでSBに向かいました。
このSB地区の失業者は全米9%の失業率に対し、27%の高失業率となっているように、歩いていると、道端からこちらを刺すような眼ざしが大勢います。カメラは大丈夫かとボランティアガイドの女性に聞きますと、私がいるから心配ないとの答えでしたが、タイミングを考えて写真を撮らねばならない地区です。
ガイドの彼女が語りました。ここの環境問題、自分で個人的に解決を図ろうとすればすぐできる。それはここから移住すること、この町から出て行けば解決するといいます。
しかし、それではハーレム改善と同じなってしまう。ハーレムのような解決はしたくない。昔のハーレムはここと同じだった。確かにハーレムは環境が変化したといわれている。犯罪は減り、住みやすくなったが、それは貧困層の人たちを消しただけだ。解決のために新しく計画されたコミュニティは白人中心であり、今まで住んでいた人を追い払う計画であった。そういう解決ではなく、ここに住んでいるコミュニティの人々の生活が向上するような進め方をしたいのだ、と情熱籠めて話してくれます。
さらに強調します。この地区を大事にする都市計画が必要だ。ソーラーパネル、グリーンベルト、野鳥の訪れ、また、この町に文化芸術を根付かせたい。今高校でリサイクルデザインを提唱している。リサイクル品を使用した新しいデザイン。マッカーサー助成金を受けてMIT工科大学の審査を受ける予定だと。
最後に彼女が胸に付けていたバッチをプレゼント受けました。「I GREENED THE GHETTO」(ゲットーをグリーン化する)。数年後のSOUTH BRONXに期待すると共に、住民自ら環境条件を変化させたいという時代の動きと思います。以上。
【11月のプログラム】
11月13日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
11月14日(土)18:30 山岡鉄舟研究会「生麦事件歴史散策研究会」
11月25日(水)18:00 経営ゼミナール(会場)銀行会館
投稿者 lefthand : 15:24 | コメント (0)
2009年10月06日
2009年10月5日 オリンピック東京開催落選
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年10月5日 オリンピック東京開催落選
オリンピック東京開催落選
東京は10月2日のコペンハーゲンで開催されたIOC総会で、2016年夏季オリンピック開催地決選投票の結果、二回目の投票で最下位となり落選しました。
選ばれたのはブラジル・リオデジャネイロで、スペイン・マドリードとの決戦投票では、66票対32票と圧倒的な勝利でした。
前回2012年夏季オリンピック開催地決定のIOC総会は、2005年のシンガポールでしたが、その際はマドリードが三回目で落選、決選投票はロンドンとパリという永遠のライバル都市同士の戦いどおり、ロンドンが54票、パリが50票と接戦でした。
今回の東京落選、その失敗の筋書きは、このシンガポールでの接戦によって誤差を生じたと思います。ここ数年の開催地を結果的に分析すれば、ひとつのトレンド・流れがあり、それを見誤ったと思います。
トレンド・流れで東京落選は当然
トレンド・流れで考えれば東京落選は当たり前でした。落胆する必要もないくらい、当然のこととして東京は当初から対象外だったと思います。
まず、2008年の夏季オリンピックは北京でした。次の2012年はロンドンで、今度の2016年がリオデジャネイロ、いずれも国力上昇期を迎えつつあるというトレンド・流れの中で選出が決定しています。
BRICSの北京・リオデジャネイロは分かるが、ロンドンは国力上昇期ではないのでは、という疑問を持たれると思いますが、選出された2005年時の状況を思い出してください。
当時のロンドンは、サッチャー改革後の金融革命で、灰色経済のイギリスを立ち直らせたというウインブルドン現象の時期でした。当時のロンドン・シティでは、毎晩、蝶ネクタイの紳士が、派手に着飾った女性を連れてパーティに現れる、といった華やかな金融経済絶頂期でした。ですから、当時はロンドン市の収入も莫大だったでしょう。
そのマネー経済成功地の迫力と、元気さを世界にアピールしました。金融という新しい21世紀型産業を興隆させたパワー、これがパリを破ったロンドンの源泉でした。
ということは、今のタイミングでロンドンが挑戦しても、落選は間違いないでしょうし、まず挑戦する気にもならないでしょう。それだけ経済力が落ち込んでいて、2012年の開催費用の捻出は大変だろうと推測します。
因みに2014年の冬季オリンピックは、事前予想で最有力だった韓国の平昌を、ロシアのプーチン大統領がIOC総会で英語とフランス語(IOCではフランス語が公用語)でプレゼンし、開催地をソチにかっさらいました。
ロシアはBRICSの一員で、冬季オリンピックの決定時期は2007年7月でしたから、アメリカのサブプライムローン問題の発生直前、すれすれのセーフタイミングでした。
東京の2016年への挑戦根拠
東京の2016年オリンピック挑戦根拠は何だったのでしょうか。
それについて猪瀬東京都副知事が以下のように今年9月に語っています。
「一言でいえば環境都市を前面に押し出していく。開催都市を決定するIOC総会が開かれるコペンハーゲンでは、2008年12月に気候変動枠組み条約締約国会議(COP15)が開かれ、京都議定書の次の枠組みが決まるので、その流れの中で『環境』を理念とした開催計画を訴える。
東京での開催が決まれば、非常に意義深い。確かにリオデジャネイロの理念『南米初の五輪』にもインパクトがあるが、『環境』を掲げるわれわれは理性に訴えていく。
五輪という将来の明るい希望が出てくれば、後ろ向きな国民の心理が前向きになる。経済活動にも好影響を与え、将来への悲観的な見方からこれまで控えられていた需要も喚起されるはずだ。これは直接の経済効果以上に大きい。
東京で開催することの最大のメリットは、希望や誇りを取り戻すことだ。日本には今、将来のビジョンがない。日本を再び世界をリードする国へとよみがえらせるには、環境と平和を訴えるしかない。優れた環境技術や環境施策を五輪を通して発信し、われわれが生き残る道として見せていくことが重要だ。
ロンドンは『成熟都市の五輪』の姿を示し12年開催を勝ち取った。日本の代表選手である東京がこれに続き、世界の先端にいなければならない。東京五輪は日本全体のためにも必要だ」
(日刊建設工業新聞 09年9月9日水曜日掲載)
東京の戦略的誤り
この猪瀬東京都副知事発言の中に、戦略の誤りを明確に指摘できます。ロンドンは『成熟都市の五輪』だと断定していることです。
ロンドンが成熟都市であることは間違いありません。だが、荒廃化しかけていたイギリス、それを立ち直らせたサッチャー革命以来、金融という武器を新たに手にいれ、再び経済力復興期を迎えていた2005年に選出された、ということを猪瀬さんは述べていません。ここを石原知事も猪瀬さんも見誤っています。
今回のコペンハーゲンでの最終プレゼンテーション「誰に聞いても東京が一番だと言っていた」と報道にあります。それは事実だったのでしょう。
しかし、このプレゼンの素晴らしさという事実を超えた「流れ・トレンド」が世界の人々の気持ちの中にあり、それを斟酌し汲み込んだIOC委員の気持ちがリオデジャネイロに傾き、圧倒的にマドリードを、東京を、そして今最も世界で人気の高い人物、アメリカ大統領オバマ氏とミッシェル夫人が出席プレゼンしたシカゴ、これも簡単に破ったのです。
オバマ夫妻と一緒に写真を撮りたいと、IOC委員が列をつくったというのに、結果は一回目でシカゴは最下位という屈辱的敗退です。オバマ大統領の支持率も下がりつつある中での負けですから、今後の動向に暗雲が立ち込めるかもしれません。
日本の東京という立場からは妥当な戦略
石原知事と猪瀬さんの主張は日本人の立場からは最適解です。妥当で正しい戦略でしょう。だが、勝負の鍵は世界中の外国人が握っているのです。世界の人々が何を判断基準にするか、そのところの事前把握が甘かったと思います。つまり、日本から世界という舞台を見て、戦略構築したのです。
しかし、今はグローバル化の時代であり、IOC委員2人の日本人を除いて、外国人による判断結果で決定します。オリンピックの開催地決定は正にそのグローバル化の中に存在するのです。
ですから、石原知事と猪瀬さんは「世界から日本の東京を見なければいけなかった」のです。それは難しい、と言ってしまえば終わりです。見なかったから落選したのです。
このYAMAMOTO・レターでお伝えしていること、その目的は日本の人たちが「世界から日本を見てもらいたい」という希望もあって続けています。
世界から日本を見る
「世界から日本を見る」という目的をもって、毎月、国内各地と海外各地を訪問しています。その訪問もなるべく行政の中に入り、企業の中に入り、家庭の中に入り、街角のショップやレストランの中で隣の人たちと語り合うことで、日本を世界から見ていき、その結果で世界における日本の成長発展を模索検討し、それを計画化すること、そのような業務を続ける立場から感じた事を月二回お届けしています。
IOC委員に明確な選出基準が無い
最後に、IOCのような組織、そこにはオリンピック開催地への明確な判断基準がないことを指摘しておきます。IOC委員はほとんど個人資格です。一国の政府代表ではありません。したがって、一人ひとり、それは世界中から集まった人たちですから、それぞれ異なる考え方を持ち、その上、単純かつ明確・厳密な選定基準がないのですから、アバウトな暗黙の判断基準で決定していくのです。そうであるからこそ、その時の時流・流れ・トレンドを「つかむ作業」が最も大事なのです。それが東京に欠けていました。
明確な判断基準がある場合と、それが不明確な場合とで戦略構築が異なるのです。以上。
【10月のプログラム】
10月 9日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
10月18日(日) 経営ゼミナール「ミシュラン温泉訪問研究会
10月21日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 07:01 | コメント (0)
2009年09月21日
2009年9月20日 トレンドで考える・・・その二
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年9月20日 トレンドで考える・・・その二
前号の衆院選に続いて、今回は日本経済と米国経済のトレンドを考えてみます。
日本経済は回復するか
日本経済は果してL字型の底を横ばいする実態から、上昇軌道を描けるかということ、それをトレンドで考えてみたいと思います。まず、最近の日本経済の状況を見てみます。
●下落し続けていた鉱工業生産指数も6月は前年比で4か月連続上昇
●2009年4月から6月のGDP年率換算は2.3%と5四半期ぶりにプラス
●日経平均株価はバブル崩壊後の最安値2009年3月10日の7,054円、それが9月18日は10,370円、+3,316円、147%アップ
と、下げ止まりがみられるような状況です。だが、
●バブル期の日経平均株価は1989年12月29日38,915円が最高額で、その約4分の1に戻ったにすぎない
●また、日本の1990年代の10年間実質成長率はプラス0.8%であり
●2009年の実質経済成長率は、各予測期間で異なりますがマイナス3%から6%と見込まれる
●そうなると2002年から2007年まで2%前後の成長があったものの2008年度はマイナス3.3%、今年も大幅なマイナス見込みですから、結局、21世紀初頭の10年間はゼロ成長見込みとなる
つまり、日本経済は1990年から2009年までの20年間、ゼロ成長というトレンドですから、急によくなるわけがないと考えた方がよいと思います。
米国経済はインディアン・サマーか
米国経済は日本経済にとって最大の鍵です。小泉内閣時代の成長、02年から07年までプラスは、米国の過剰消費に支えられた世界景気上昇の波でなされ、これが金融危機によって大変化したのですから、米国経済の行方が最大関心事です。
この米国経済を一言でいえば、インディアン・サマーで終わるのではということです。
インディアン・サマー(Indian Summer)とは、枯れ葉が落ちはじめ、寒さが身にしみ始める晩秋に、突然よく晴れ上がった暖かな日がくることをいい、日本語では小春日和とも表現します。どうして「インディアン」という言葉がつくのかといいますと、インディアンたちが厳しい冬を迎えるため、この晴れた日を選んで冬支度をするからですが、今の米国経済はこのような一瞬の小春日和にいるのではないか、と思われるのです。
最悪期を脱した米国経済
最近の米国経済は、最悪期を脱し順調な回復だ、というのが一般的な見解です。
●3月9日、NYダウ平均株価は12年ぶりの安値(6,547ドル)を付けた
●4月9日、NYダウ平均株価は246ドルの大幅な上昇、8,000ドル台を回復
●4月10日オバマ大統領は「a glimmer of hope(かすかな希望の光)」と表現
●8月21日にバーナンキFRB議長は「大恐慌以来の深刻な危機が引き起こした景気後退はいま終局を迎えている」との見解を示す
●8月に入ってL字型の底が4~6月に終わり、景気は今夏に上向きに動き始めつつあるとの観測
●9月18日のNYダウ平均株価は9,820ドル、最安値から+3,273ドル上昇の150%アップ
米国経済の自立的回復は可能か
では、トレンドから考えて、今後、米国経済は自立的回復が可能でしょうか。
まず、基本的な経済の構造として、経済循環的な景気論でいう経済向上は「生産→所得→支出」ですから、そのトレンドストーリーを見てみます。
●最初は「生産」の上昇がまず必要です。「生産」が高まれば雇用や賃金が増加し、「所得」すなわち家計収入や企業収益が増えます
●そこで家計は消費、企業は設備投資といった「支出」を拡大させるので景気は上昇し、経済成長につながります
●ところが、このつながりプロセス、これが今回の金融危機によって米国経済に「構造的変化」を発生させたました
●米国経済の主役はGDPの7割を占める個人消費で、この消費に「変化」が起これば、生産そして所得を通じて経済全体に「変化」が波及します
●それはサブプライムローン問題の発生で、金融機関は住宅関連融資を抑制し、住宅需要が増えないので、住宅価格が下落しました
●その下落が加速し、さらにサブプライム禍が拡大し、家計は借金の返済を迫られまれ、それは消費減となり、その分を返済へ回します
●これは実質的な「家計貯蓄率の上昇」であって、個人消費の減退となります
●「支出」(家計消費)が減少すると、企業の「生産」(企業の売上高・生産)が下がり、企業の損益分岐点が悪化し、企業は雇用削減、賃金カットに踏み切り、設備投資減に向かいます
●これは「所得」、すなわち家計収入と企業収益を減少させ、所得減少がさらなる消費減退を誘引しGDP成長を阻害させることになります
家計貯蓄率と大学新卒就職難
米国全体のGDP成長が下がりますと、中所得層の人々も所得減に追い込まれますから、プライムローン返済にも問題が発生し始め、これがさらなる「家計貯蓄率」の引き上げと「消費の減退」となって、GDP成長を下げさせることになります。
その家計貯蓄率実態は、2008年8月に1.7%、10月に2.9%と、極めて低かったのですが、12月に4.7%に上昇、2009年5月には6.2%にまでに高まって、さらに今後も家計貯蓄率は緩やかに上昇すると予測され、経済に影響を与えてきます。
その影響は大学新卒就職難として現れてきました。2009年6月の卒業時点で就職が決まっているのは20%、同時期の2008年は26%、2007年は51%でしたから大幅な悪化です。
就職難の対策は大学院へ進学することですが、米国の大学授業料は高く、すでに多額の借金を抱えているので、大学院へは恵まれた人のみとなり、就職できない新卒生はボランティア活動や起業やアルバイトに向かいます。だが、このアルバイトはもともと10代の仕事で、そこから奪うことになるのです。
米国は財政支出を継続できるか
2009年4~6月に世界景気は「底入れ」し、ようやく景気に回復基調を感じ始めたという一般見解の背景を整理してみると次の三つでしょう。
●一つ目はL字型に直撃されて企業が在庫調整に一斉傾注し今春にそれが一段落した
●二つ目は各国が世界的ニューデール政策の掛け声のもと、前代未聞の金融安定化策や金融緩和策をはじめ、財政大出動にまい進した
●三つ目は成長余力のある中国など新興国の経済がいち早く復元力を見せ、今後に期待を持たせつつある
この中で最大の懸念は、二つ目の対策が継続されるかということです。米国は大幅財政赤字国ですから、これからも財政大出動にまい進するのであれば、海外からの資金調達か国内貯蓄で賄うことになります。
海外資金を引き付けるには長期金利の上昇が不可避で、これは成長を下げる可能性があります。そこで国内貯蓄の増加を図ろうとすると、消費が抑制されることにつながり、結果としてGDP成長減になっていきます。
もう一つの大問題は、米国の金融拡張の制約です。金融危機の根本原因がウォール・ストリートの金融拡張方式、すなわち過大レバレッジ(テコ)手法と金融工学的リスク拡散手法にあったことは明らかで、ここしばらく「大火事後」の整理・修復に取り組む必要があって、まだ21世紀の新しい金融モデルは霧の中ですから、かつてのような金融で経済成長させるのは困難と考えられます。
トレンドから見た米国経済の自律的回復は厳しいので、日本経済成長も難しい時代です。では、このような経済環境下で、どういう対応策が考えられるか。それは次号です。以上。
【10月のプログラム】
10月 9日(金)16:00 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
10月18日(日) 経営ゼミナール「ミシュラン温泉訪問研究会
10月21日(水)18:30 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 09:24 | コメント (0)
2009年09月06日
2009年9月5日 トレンドで考える・・・その一
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年9月5日 トレンドで考える・・・その一
今回は8月30日の衆院選について考えてみたいと思います。
衆院選事前予測
今回の衆院選事前情報調査、主要新聞は以下でした。
◇読売(8/21付)「民主300議席超す勢い」「自民激減 公明は苦戦」
◇日経(8/21付)「民主 圧勝の勢い」「300議席超が当選圏」「自民、半減以下も」
◇毎日(8/22付)「民主320議席超す勢い」「自民100議席割れも」
◇産経(8/25付)「政権交代は確実」「民主、300議席確保へ」
加えて、週刊現代は7月21日発売号で「民主332議席、自民78議席」、夕刊フジも8月28日「自民党91議席、民主党325議席」と圧倒的な民主党の勝利予測でした。
そこで、日刊ゲンダイは直前の8月28日、いわゆる「バランス感覚」とも「ゆり戻し」ともいえるものを狙った、与党を利する目的とも思える「民主圧勝の選挙予想は謀略なのか」を掲載しましたが、結果は見事に予測通りでした。
花岡信昭氏の事前見解
圧倒的な民主勝利予測の妥当性を専門家に確認したく、産経新聞出身の政治ジャーナリスト花岡信昭氏に、8月20日にお会いし、見解をお聞きした内容は以下の通りでした。
「メディアの事前予測と選挙結果の関係を示すものとして、アナウンスメント効果があり、これはバンドワゴン効果とアンダードッグ効果の二種類ある。
バンドワゴンとは楽隊の先頭に位置する車のことで、メディア予測をそのまま受け入れ、勝ち馬に乗る心理が働いて、予測をさらに加速させる現象をいう。
一方、アンダードッグは『負け犬』だ。これは判官びいきが働き、あるいは、そういう予測なら自分が選挙に行かなくてもいいなと思わせる現象が生じる。その場合はメディア予測と逆の結果となる。
政治記者として選挙報道にたずさわってきた経験からいえば、かつては後者が圧倒的に多かったように思う。いまだから言えるが、選挙区の情勢分析を書く場合など、知己の政治家や秘書らから『当選確実のようには書かないでほしい。あと一歩、横一線、程度だとありがたい』などと『陳情』されたものだ。
このごろの投票行動は、バンドワゴン効果が生ずることのほうが多いように感じ、一定の予測が出ると、その流れに飛び込んで一緒に楽しもうといった心理が有権者に作用する方が強いと感じる。今回のケースだと、民主300という劇的な予測を受けて、その流れを確実にさせようという投票者が増えることになろう」花岡氏発言通りとなりました。
衆院選結果
選挙結果は民主党308議席、自民党119議席で、民主党の大勝で終わり、オバマ大統領から祝意の電話が鳩山党首に入りました。
ここで不思議なのは、大敗した自民党なのに、大臣は誰一人として落選しなかったことです。古い人が生き残ったということ、これからの自民党の先を暗示しているように感じますが、9月1日閣議後の各大臣の反省発言は以下でした。
◇舛添・・・お友達であるという観点が優先された内閣は緊張感が欠けた。
◇石破・・・民主党の勝利というより自民党の敗北だ。
◇森・・・・相手候補でなくて空気のようなものと格闘していた。
◇与謝野・・小泉内閣が終わって以降、人気先行型で自民党総裁を選んできた。
いろんな面で国民の失望感を買った。
◇野田・・・誰が総裁になっても首相になれない。
目先のことより歴史的惨敗を受け止めて、前向きな議論をしなければならない。
識者の見解
識者の見解を少し見てみたいと思います。
(田中愛治 早稲田大学教授)
・国民の期待は日本経済を良くすることだが、自民党は内閣支持率をいかに高くすることに腐心し、それを有権者に見透かされた
・選挙で勝てそうな選挙日程をうかがってきた首相の姿勢を国民は敏感に批判した
・小泉首相の大勝を小泉個人の人気と判断し、表面的な個人人気で選挙を勝とうとしたことが根本的な誤り
(御厨貴 東京大学教授)
・ここ数年自民党トップの一年ごとの交代や、いつまでも解散しないという便宜主義に対する嫌悪感が国民にまん延した
・自民党は具体的に政策優先順位をつけるマニフェストに適合的でない政党だ
・自民党の再生は難しい。首相経験者4人が現役議員として残ったことと、今の大臣が全員当選したこと、これが党改革を難しくする
(青木昌彦 米スタンフォード大名誉教授)
・古い仕組みで活躍したプロの退場は時の流れだ
・今後は少子化、高齢化、家族構成の変化で若い人と女性の責任と負担が重くなる、そこにマニフェストで政策主張したのが民主党だ
・民主党には霞ヶ関を脱藩した極めて優秀な若手が少なからずいる
・古い仕組みの世襲政治では起こりえなかったことだ
日本の政治トレンド
日本の近代化は明治維新からです。その明治維新は1853年のペリー来航から15年経過した1868年に成立しました。この15年という期間、これが妙に気になって、鉄舟関係の講演会ではいつもお話しています。
というのも、満州事変が1931年、それから14年で終戦の1945年、ほぼ15年で日本は民主義国家に変身しました。この終戦から15年後の1960年には、池田内閣が発足し、日本は高度成長経済に入りました。
さらに、細川政権が誕生したのが1993年、それから16年後の今年、民主党鳩山政権となります。約15年です。これが日本の歴史から見られる長中期政治トレンドです。
自民党はトレンドを意識していたか
今回の民主党勝利もこの15年周期で生まれました。だが、自民党大臣の発言からは、「流れ・トレンド」についてあまり意識がないように感じます。目先の動きで判断していたように思います。これは経済評論家の陥りやすいポイントでもあります。
経済を論じる場合、必要不可欠条件はデータです。経済が相手ですから当然で、そのデータは四半期ごと、三カ月期間で発表されるGDPが基本になっていますので、この内容を分析し、一喜一憂し、様々な論点を展開します。また、毎日の株価にも大変敏感で、どちらかといえば点で物事を見ることが多いのですが、これは長中期トレンドを軽視することに通じやすいのです。
短期トレンドからは自民大敗は必然だった
今回の自民党大敗、直近の短期トレンドを検討するだけで、素人にも判断つきます。
まず、2007年7月の参院選はどうだったでしょうか。今から2年前、自民党の獲得議席数は37議席と、第15回参院選の1989年以来の歴史的大敗を喫し、1955年結党から初めて他党に参議院第一党の座を譲りました。また、公明党も神奈川県・埼玉県・愛知県の各選挙区で現職議員が落選、比例でも票が伸びず議席を減らしました。
今年に入って名古屋市長選、さいたま市長選、千葉市長選と連続して圧倒的大敗を喫し、最後は東京都議選での大敗、自民党は改選前48議席で第一党でしたが、38議席に留まり、民主党は改選前34議席から54議席へと大きく躍進し、都議会第一党となりました。
つまり、参院選からの「流れ・トレンド」は、自民党敗退という必然化を示していました。流れのまま、トレンドのままに議席が表面化したのです。何事も、その時のトレンドを見抜くことが大事です。つまり、時流をどう読み取るかで決まります。
では、トレンドから見る日本経済と、米国経済はどう推移するか。8月21日バーナンキFRB議長は「大恐慌以来の深刻な危機による景気後退はいま終局を迎えている」との見解を示しましたが、経済トレンドから見るとどうなるか。次号でお伝えします。以上。
【9月のプログラム】
9月 7日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
9月10日(木)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
9月16日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 10:22 | コメント (0)
2009年08月20日
2009年8月20日 文化越境性
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年8月20日 文化越境性
司馬遼太郎
この夏休みは播磨灘物語を書くため、播磨の海辺で過ごしました。
播磨灘とは瀬戸内海東部地区の海域をいい、兵庫県南西部(旧播磨国)の南側に位置し、東は淡路島、西は小豆島、南は四国で区切られ、西北部に家島諸島があり、東西約50km、南北70km、水深は40m前後、播磨五川と称される加古川、市川、夢前川、揖保川、千草川が流れ込んでいる海域ですが、この播磨灘を題名とした小説として、司馬遼太郎の「播磨灘物語」が有名で、このタイトルに惹かれ、四部冊の大作を読みながら播磨の海を歩き廻りました。
しかし、「播磨灘物語」を読み進めても、一向に海に関することが出てきません。実は、播磨灘という題目ですが、黒田官兵衛の物語だったのです。
黒田官兵衛とは、知謀権謀術策を持って織田信長と豊臣秀吉に仕え、一大大名にのし上った人物で、そのストーリー構成を、今に遺されている「信長公記」「黒田家家譜」などの諸資料から拾い出し、官兵衛に強い愛情を持って書いているのです。
残念ながら海については参考になりませんでしたが、各資料の史実と史実のつながり、登場する人物と人物との絡みについて、司馬遼太郎が持つ人生哲学によって心理分析され、格調高き文章で、舞台は戦国時代なのに、現代人への素養書となっていて、さすがに文化勲章受章者だと深く感じ入りました。
村上春樹
村上春樹は今の時代、最も話題性がある作家でしょう。村上春樹の文体は、一見まったく異なった物語を組み合わせし、それらを交互に語ることで、豊かな反響を作り出すという書き方が特徴です。この手法と内容が大受けし、今や世界30カ国以上の国で翻訳出版されていますが、同じ一人の作家が、イタリアと韓国でベストセラーとなり、トルコで文化的事件となり、ロシアと中国という体制が異なった国々で最高の文学的経緯を得る、というような文学作品の事例は、過去において日本人作家にいたでしょうか。
村上作品について、現代アメリカ文学を牽引する作家であるリチャード・パワーズ氏が次のように述べています。
「今の時代、自らの拠って立つ場が曖昧になり、移動することが常態と化し、『いま・ここ』という感覚が失われ、心の中が難民化し、国家的アイデンティティや地理的固有性といった静的な観念が消えていくという、グローバリゼーションの時代精神を捉えているだけでなく、村上小説自体が、時代精神そのものになっている」と。つまり、村上作品には「文化越境性」があり、これが世界中の読者をとらえている要因であると分析しています。
文化勲章とカフカ賞
司馬遼太郎は、平成5年(1993)に文化勲章を受章しました。文化勲章とは、文化の発達に関し勲績卓絶者を文化功労者のうちから選考し、毎年度おおむね5名を内閣総理大臣に推薦する制度で、文化功労者以外からでも必要と認められる場合には選ばれることがあります。また、慣例として、その年にノーベル賞を受賞したが、文化勲章未受章である場合は、文化勲章が授与されます。
一方、村上春樹はチェコの文学賞である、フランツ・カフカ賞を平成18年(2006)に受賞しています。この賞は、特定の国民性に捉われず、世界文学へ貢献した作家に贈られるもので、これを受賞するとノーベル文学賞を受ける事例が多いことから、村上春樹がノーベル文学賞の最有力候補者と見なされています。
文化越境性の時代
司馬遼太郎の小説は、多くの日本人の心を捉えています。「竜馬がゆく」「坂の上の雲」によって、どれだけ日本人が勇気づけられたでしょうか。まさに日本人のロマンの原点を語ってくれています。「播磨灘物語」も同様で、そこにはしっかりとした日本人としての、拠って立つ場が明確に示されていて、そこから日本精神を語っていますが、敢えて、司馬作品に不足しているものをあげるとすれば、文化越境性ではないでしょうか。司馬作品がどのくらい翻訳されて海外にでているか把握していませんが、司馬作品の価値は、まだ日本国内にとどまっていて、世界の普遍的価値に至っていないと思います。
対する村上春樹の小説は、日本が舞台で、日本人が主役ですが、人種が異なる多くの人々を捉えています。小説で登場させる対照的な二人の主人公に、日常的リアリズムと別世間の幻想の間を、スパイスの利いたユーモアを含ませつつ、異質な物語を交互に語らせ、巧みな心理分析に基づく描写で、立体的な作品とし、結果として世界中の人々へ生き様のありようを伝えるという文化越境性が、世界の普遍的価値へシフトさせた理由と思います。
ブルーガイドブック
観光地を星印で格付けするフランスのガイドブック、ミシュランの観光版「グリーンガイド日本版」が、フランスで3月発売されましたので、ミシュランジャパングループに問い合わせし、日本の観光地を選択し評価した背景について、説明をして貰いたいと申し入れましたところ、回答はフランス本社で出版しているので、問い合わせと依頼はフランス本社にしてほしいという返事でした。
そこで、すぐにフランス本社に問い合わせと依頼をしましたが、なかなか返事が来ません。催促したところ、先日、回答がフランス本社から来て、「日本に出張するのは日程的に難しい。しかし、今後、日本観光ガイドに組み入れ、取り上げるところがあれば提案してほしい」ということで、フランスミシュラン本社と、コンタクトが取れたところです。
ところで、フランスにはもう一つ「ブルーガイドブック」があります。フランス在住の知人によると、フランスではミシュランより「ブルーガイド」の方が、文化的レベルが高いという見解とともに、知人がわざわざ送付してくれました。
「ブルーガイド」はアシェット・フィリパッキ・メディア社(Hachette Filipacchi Médias、略称HFM)出版、同社はフランスに本社をもつ世界最大の雑誌出版社で、1826年にルイ・アシェットによって創業され、1980年にはマトラを傘下におさめ、現在はフランス最大のコングロマリットであるラガルデール傘下で、フランスのみならず日本やアメリカの傘下企業を通じて数々の雑誌を発行しています。あのELLEもそうです。
日本では老舗出版社の婦人画報社を傘下に収め、アシェット婦人画報社として活動しており、「婦人画報」をはじめ「25ans」や「ELLE Japon」などの雑誌を発行し、教育書・教材・語学書・専門書など扱っています。
また、知人から「ブルーガイド」の編集者が私に会いたいといっている、という連絡が来ていますので、何かの機会に実現したいと思っています。
だが、編集者に会うにしても、ミシュランに提案するにしても、欧米人が認識する普遍的価値を日本の中からつかみだすということ、それは文化越境性あるものに編集するということになりますが、この作業が前提条件として必要だろうと思っています。
播磨灘の夏生牡蠣
播磨灘に戻ります。海辺での昼食は、毎日、各漁協が経営する市場内で食べました。
そのひとつ、赤穂市の坂越(さこし)漁協経営の海の駅・しおさい市場には驚きました。真夏ですから、どの漁協も岩牡蠣はあっても、冬牡蠣のマガキはありません。しかし、この坂越漁協にはマガキの生があったのです。メニューに載っていました。
ご存じと思いますが、フランスでは真夏でも牡蠣を生で食べます。というよりフランス人は生でしか牡蠣を食べないのです。一年中生で食べ、よくいわれる「Rのつかない月は食べない」は嘘で、5月から8月のRのつかない月でも生でよく食べます。
だが、日本では牡蠣は秋から春までのアイテムで、それも調理して食べるのが普通で常識です。特に、ノロウィルス騒動以後は、生で食べる人は少なくなりました。しかし、牡蠣の食通は生が一番だといいます。私もその口です。今まで多くの漁協市場を回りましたが、真夏の生牡蠣が存在したのは初めてで、メニューには「地元坂越のかき業者が数年前より取り組み、苦難の数々を乗り越え、ようやく成功しました。低温海域にて一粒一粒丁寧に育てられた逸品は『生かき』で召し上がって頂くことが最高の至福です」とあります。ネーミングは「なつみ」とあり「水揚げが少なく割高」とあるように、一個450円は高いと思いますが、真夏に食べられるマガキへの挑戦、それは欧米人の来客を意図したものなのか、それとも別の背景から始まったのか、近く漁協組合長にインタビューして聞いてみたいと思っています。いずれにしても真夏の生牡蠣養殖は、日欧の文化越境性に関わる要素になる可能性が高く、グリーン及びブルーガイドに伝えたいと考えています。以上。
【9月のプログラム】
9月 7日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
9月10日(木)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
9月16日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 09:09 | コメント (0)
2009年08月05日
2009年8月5日 普遍的価値
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年8月5日 普遍的価値
国立西洋美術館の世界遺産登録延期
フランス政府が中心となり、フランス人建築家、ル・コルビュジエ(1887年~1965年没。近代建築の巨匠)の世界各国に点在する作品を一括して世界遺産として登録する中に、上野公園内の「国立西洋美術館(本館)」が入っていました。
だが、2009年5月、ユネスコ世界遺産委員会の諮問機関・国際記念物遺跡会議(イコモス)は、「顕著な普遍的価値の証明が不十分」として、世界文化遺産への登録を延期すべきだと勧告、事実上世界遺産は難しい状況になりました。
現在、ユネスコは新規登録を抑制する傾向にあり、日本の候補では、一昨年の石見銀山(島根県)、昨年の平泉(岩手県)に続き、3年連続での延期勧告となりました。石見銀山は日本政府の精力的なロビー活動などで最終的に世界遺産に登録されましたが、随分苦労したと関係者からお聞きしています。
塩谷文部科学相は「世界遺産の登録が全体にだいぶ厳しくなっており、日本の推薦自体をもう少し考えていく必要がある」と語り、また、国立西洋美術館は「大変残念。登録は厳しいものとなったと認識している」とのコメントを発表しました。
ミシュラン観光ガイドでは
今年3月、初めて日本版ミシュラン観光ガイドが出版されました。この中で国立西洋美術館は一つ星の評価となっていて、同じく上野公園内にある「東京国立博物館」の三つ星より、明らかに評価は低くなっています。日本人には国立西洋美術館の方が、人気があると思いますが、ミシュランガイドでは逆になっているのです。
同様に同公園内にある東照宮は二つ星、谷中霊園は二つ星ですから、国立西洋美術館の方が評価は低いのです。ミシュラン社には、判定するための普遍的価値基準があるのです。
故郷に戻ってみて
先日、広島で、広島県庁から二年間、東京の政府関係機関に出向して、県庁に戻った女性とお会いした際、「久しぶりに戻ってみると、随分外国人観光客が多いと感じる」との発言がありました。
日本政府観光局(JNTO)の発表で、2009年上半期(1月~6月)の訪日外国人客数が、前年同期比28.6%減の309万5,000人となり、2005年以前の水準まで落ち込んでいるという実態なので、これは県庁に戻った女性の実感と異なります。
また、東京から広島に行く新幹線の中、近くの座席でフランス人がミシュランガイドを持って研究している姿を見ていましたので、日本全体は外国人減少となっていますが、広島地区には特別に外国人が評価する普遍的価値があるのではないか。
そう思った時、一昨年ドイツ・ポツダムを訪れたときの体験を思い出しました。
ポツダム会談
ドイツのポツダムは、今はベルリンのベットタウンとなっていますが、もともとフリードリッヒ大王の城下町で、ツェツィリホーフ宮殿がある街で、今ではポツダム会談が行われたことから、世界遺産となっており、世界中から観光客が押し寄せます。
ポツダム会談は、正式文書では「ベルリン三大戦勝国会談の報告」と言い、会談の議題は大きく分けて三つ、【1】戦後のヨーロッパを東西にどのように分けるか、【2】ドイツの戦後処理、【3】日本への無条件降伏勧告で、1945年8月2日に調印宣言された会談です。
この、【3】の議決が問題でした。既に同年7月26日、日本に無条件降伏を勧告通告済みでしたが、東西冷戦の対応に早く着手したいアメリカは、日本との戦争を早く終わらせたいので、米・トルーマンが英・チャーチルとソ連・スターリンに原爆投下を提案し、賛成を取り付け、会談日の四日後の6日に広島、続いて長崎に投下したのです。
当時、アメリカは6月にメキシコで原爆の実験に成功し、二個の原爆を所有していたものを投下したのです。この投下によって、原爆のすごさに脅威を感じたソ連は、その後原爆開発のスピードを速め、原発競争になりました。
私は広島生まれです
このポツダム会談が行われたツェツィリホーフ宮殿、そこでガイドの説明を聞いていた時、同行のドイツ在住の通訳女性が「私は広島生まれです」と、小さな声でしたが、ドイツ語で突然つぶやいた時の光景が忘れられません。
その場にいた観光客、多分15人程度だと記憶していますが、全員がギョッと彼女を見つめたのです。彼女の足元から頭の上まで、まるで原爆患者であるかのように、鋭く点検するような目つきで凝視したのです。
原爆投下は20世紀最大の悲劇で、世界中の小学校・中学校の教科書に教訓として掲載されています。ですから、広島・長崎という名前を知らない人は世界にいなく、世界の人々にとって特別な場所、つまり、普遍的価値として認識されているのですから、全体の訪日外国人が減っても、広島に影響は少なく、広島県庁にリターンした女性発言になったのでしょう。
かき専門料理店がない
その県庁に戻った女性、東京で知り合いになった人たちが広島に来て、多くの人が「広島はかきが名物だから食べたい」と希望を述べるそうです。
ところが、改めて探してみると、広島市内に「かき専門料理店」がないことが分かったと、これも二年間広島を離れてみて確認できたことだとお話されていました。
日本でのかき養殖は、天文年間(1532年~1555年)という450年も前から広島湾で始まり、それ以来、広島はかき産地として成長発展してきて、今や「かきは広島だ」ということを知らない人はいません。かきは広島の普遍的価値となっているのです。
したがって、かきを一年中食べられる専門店があってもよいのではないか、というのが当然の気持ちでしょう。しかし、存在しないのです。広島の独自性を発揮していません。
韓国には専門店がある
ところが、日本からかきの養殖技術を導入した韓国、つまり、かき養殖後発国の韓国には「かき料理専門店」が存在します。かき産地として有名な統営市、釜山から約150km離れたところですが、ここには専門店がいくつもあり、ソウルからわざわざ訪ねてくるくらいの人気です。ここを今年の二月に訪れ、かき焼きとかきご飯に満足しました。
また、養殖地まで行かなくても、ソウルの街中に「かき村」というかき専門店がチェーン展開しています。30店くらいあり、いつもかき好きの人で活気に満ちています。
また、一般の人もかきの食べ方を工夫しています。釜山で会ったかき好き主婦は、かきのむき身を買ってきて、塩水で洗い、それを唐辛子・みそ・水飴・酢・キムチの素を混ぜたたれをつけて食べます。かきの刺身というわけです。加えて、かきのキムチもつくります。白菜二三枚の間にかきを入れ、そこに大根とネギと人参とせり等を千切りにして加え、キムチの薬味を入れて、一週間後が一番美味いといいます。なるほどと思います。
観光地の独自性
人が旅行する意味は、自分が住む土地との違いを求めて動くのです。全く同じなら旅行する意味合いはありません。原爆投下の地という違いを持つ広島に来てみれば、そこは古き時代から伝わっているかきの養殖一大産地である。ならば、そのかきを食べてみたいと思うのが当然でしょう。広島が持つオリジナリティだからです。そうすると当然にかき専門店が必要になり、そこではフランスや韓国と異なる日本独自のかき料理が美味しく楽しめる。
このような普遍的価値が、どうして広島に実現していないのか、それが一大疑問です。
普遍的価値
外国人の日本観光地評価は、ミシュランガイド出版によって変わりました。ミシュランによる勝手評価が、普遍的価値となりつつあるのです。普遍性という基準が変化している事例です。国立西洋美術館の世界遺産登録延期の理由として「普遍的価値の証明が不十分」という指摘でした。その通りと思いますが、では、今の時代は、何が普遍的価値なのかを改めて問うこと、それが必要であり、大事な検討と思います。
我々は今、狭くなってしまった世界で、各国の独自性を尊重しながら、世界の人々が共有できる意識や価値観を育て磨き、それを普遍性価値にしていく努力が必要と思います。以上。
【8月のプログラム】
8月は夏休みです。9月のプログラムをお楽しみに。
投稿者 lefthand : 20:20 | コメント (0)
2009年07月21日
2009年7月20日 想魂錬磨
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年7月20日 想魂錬磨
1Q84
村上春樹の小説「1Q84」が大ヒットです。理由はたくさんあると思います。ストーリーが時代感覚に溢れている。幅広く深い知識・知見を論理的に巧みにつなげている。各章毎の予測つかない展開。文章はやさしく読みやすいなど。
しかし、この理由だけでは日本人のみならず、世界中の書店に並べられている村上春樹小説の背景を説明できません。何か他に重要な要素があると思います。
解答のあり方が物語的に示唆される
月刊ベルダ誌の書評に「今、世の中のある物事の在り様を、新聞・雑誌、新書、ネットなどに求めれば、眼からウロコが落ちるように、解答を見つけることができる。だがそれは、教養を深めることに役立つかもしれないが、今ここにある魂に安らぎを与えるものでない、今ここにある不安を鎮めるものではない。村上春樹の新作を求めた多くの人々は『解答のあり方が物語的に示唆される』方を望んでいるのではなかろうか」とありますので、「今、世の中のある物事の在り様についての解答」を、新聞記事から確認してみたいと思います。
麻生降ろしについて
日経新聞のコラムニストである田勢康弘氏が、自民党の麻生降ろしについて、次のように述べました。(2009.7.13)
「政党はどうすれば選挙に勝てるかだけを基準にすべてを考える。だれならば戦えるのか。顔を変えれば、まだ多くの人々が自民党を支持してくれるとでも考えているのだろうか。国民の政治を見る目は、それほど複雑ではない。ただ一点、政党や政治家の言動がうそ臭いかどうかを見つめているのである。顔の売れている人物を党の顔にする。これほどうそ臭いものはない。どの政党が政権の座に就くか、というのは政治家が考えるほど国民は意識していない。ほんとうの政治、国民のためになりそうな政治をするかどうかを見ているのである」
これになるほどと思います。
トヨタF1GP中止
トヨタ自動車の子会社、富士スピードウェイが2010年以降、「F1」の開催をやめます。これについて日経新聞編集委員の中山淳史氏が次のように述べました。(2009.7.13)
「自動車メーカーではホンダが昨年末、F1撤退を表明しました。日本を代表する二社がF1を負担と考え、相次ぎ距離を置き始めたのは偶然ではありません。時代の変化を感じているのです。トヨタとホンダが今、投資を必要としているのはハイブリッド車や電気自動車、燃料電池車です。内燃機関の象徴であるF1を見直すことでこれからの100年に向けた決意宣言をした。そう言えないでしょうか」
この解説にもなるほどと思います。
世界の経済成長の中心がアジアにシフトするか
一橋大学の北村行伸教授が、21世紀の世界の経済成長の中心がアジアにシフトするかどうかについて、以下のように述べました。(日経新聞2009.7.13)
「少なくとも19世紀の英国、20世紀の米国を見る限り、持続的な経済成長を続けるためには、技術革新に基づく生産性の上昇と同時に、中流階級の安定的な所得の確保、すなわち雇用の安定、そして漸進的な中流階級の生活水準の向上が必要であった。これを踏まえれば、21世紀の世界の経済成長の中心が中国・インドなどアジア諸国にシフトするかどうかは、これらの国でどれくらい広範な産業労働者が生み出され、技術進歩に貢献し、生活水準を引き上げることができるかにかかっているといえよう」
これにもなるほどと思います。
このように、今、世の中のある物事の在り様について、解答を見つけられたとしても、多くの人々が今、持つ不安を鎮め、魂に安らぎを与える解答にはつながりません。
虚空蔵求聞持法
先日、比叡山・高野山・大峰山で1200日間荒行修行された、市川覚峯氏(経営コンサルタント)からお話を聞く機会がありました。
その際、虚空蔵求聞持法について触れられました。虚空蔵求聞持法とは、弘法大師空海が真魚という名であった19才の時、室戸岬の波打ち際の洞窟(御厨人窟みくろど)にこもり、虚空蔵菩薩への祈りを唱え続けていた時、突然光が飛び込み、その瞬間、世界のすべてが輝いて見え、洞穴から見える外の風景は、「空」と「海」だけでしたが、その二つが、今までと全く違って、光り輝いて見え、そのときから、真魚は「空海」となり、虚空蔵求聞持法を悟り、会得し、無限の智恵を手に入れました。また、それまで四国のけわしい山々で修行したところが「四国八十八ヶ所」のお寺になりました。
ここでいう虚空とは宇宙のことであり、蔵とは人が持つ幸せ・財・知恵などが入っているところで、蔵の中味は人によって異なっています。つまり、すべての人はそれぞれがもつ特性、即ち、持ち味・強み・コアコピタンス、要するに美点を持っていますので、それを求め追及することが大事だというのが、空海が悟った虚空蔵求聞持法であると、市川覚峯氏は噛み砕いて解説してくれました。
セオリーがちりばめられている
村上春樹は「1Q84」の中で、主人公に向かって次のように述べています。
「何を書けばいいのかが、まだつかみきれていない。だから往々にして物語の芯が見あたらない。君が本来書くべきものは、君の中にしっかりあるはずなんだ。ところがそいつが、深い穴に逃げ込んだ臆病な小動物みたいに、なかなか外に出てこない。穴の奥に潜んでいることはわかっているんだ。しかし外に出てこないことには捕まえようがない」と。
自分の中にある美点を探しなさいと述べているのです。このような「生き方セオリー」文章がタイミングを見計らっていくつも意図的に登場することで、当面している問題とすり合わせができた読者は「解答のあり方を物語的に示唆してくれている」ということになります。
女優・浜美枝さん
「あの時代と比べようもないほど、今は豊かだ。ものはあふれ、飢える人は少ない。けれど『働けば豊かになれる』という希望が今は見えないと誰もが口を揃える。確かにそうかもしれない。が、ここでまた、私は思ってしまう。では、戦後、豊かさを求め、辿り着いたのはバブルだった。そして今、また同じ豊かさを目指すのか。そうではないだろう。私は自分がよって立ちうるものを必死に求めていて、何かに導かれるように民芸に出会ったのではないかと今になって思う。これからの社会に必要なのは、そうした身の丈の豊かさではないだろうか」(日経新聞2009.7.11)
自らの蔵の、穴の奥に潜んでいた美点を探し求めた結果、浜美枝さんは民芸を一生の目標にし得たのです。
想魂錬磨
100年に一度、未曾有の体験などという、今の時代を表現する枕詞が各方面で使われていますが、本当にそうでしょうか。
今から141年前の明治維新改革、日本は封建社会から近代社会に切り替える大革命を行いました。武士は全員失業しました。政治体制は抜本的に変わりました。大変化でした。
第二次世界大戦の敗戦、今から64年前です。殆どの人が今日の食べ物に窮し、海山川へ食べ物を求め歩き回りました。餓死する人も出ました。酷いという一言でした。
この二度の体験と、今の時代と比較してみれば、今の経済低迷などは、既に十分豊かさを確保した中でのことですから、根本的な問題とはいえません。
問題の中心は一人ひとりの生き方なのです。経済的豊かさが、幸せを持ってこなかった。返って魂に安らぎを与えてくれず、不安を鎮めてくれず、自分はどうしたらよいのか分からない、という時代になっているのです。
その答えを、市川覚峯氏は「想魂錬磨」に解答を見出すしかないと主張します。虚空蔵の中に一人ひとり異なる美点があって、蔵から出ることを切望している。だから自分の蔵に何があるかという探索をする、それは自分の想い・魂を尋ねることで、引き出したらその想魂を必死に練り磨き続ける、これしか解答はないというのです。その通りです。村上春樹の小説が大ヒットしている背景には、小説の各場面にちりばめられた「生き方セオリー」をヒントに、自分の想魂を探し求めようという人達が多い、ということではないでしょうか。以上。
【8月のプログラム】
8月は夏休みです。9月のプログラムをお楽しみに。
投稿者 lefthand : 19:01 | コメント (0)
2009年07月05日
2009年7月5日 村上春樹の背景にあるもの
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年7月5日 村上春樹の背景にあるもの
作家「村上春樹へのインタビュー内容」
村上春樹の7年ぶりの長編小説「1Q84」は、5月29日に発売され、一週間で上下巻合わせて100万部を突破しました。
この村上春樹、日本のメディアには一切出ないことで知られていますが、スペイン北西部のガルシア地方サンティアゴ・デ・コンポステラ、ここはあの聖ヤコブの遺骸が祭られているため、古くからローマ、エルサレムと並んでカトリック教会で最も人気のある巡礼地であり、世界中から巡礼者が絶えないところですが、そこの高校ロサリア・デ・カストロから賞を受賞したので、はじめてスペインを訪れ、地元紙の取材に応じ、いろいろ語った中に次のような発言がありました。
「日本人はいま、自分たちのアイデンティを模索しているのだと思います。戦後、日本は徐々に豊かになり、1995年までほぼ右肩上がりの良い時代を生きました。けれども90年代になってさまざまな危険に直面し、大きな揺らぎを体験しました。そのようなことは戦後、一度もなかった。それまではおおむね経済的繁栄が私たちを幸福にし、心を満たしてくれると考えられていました。でも日本は大変豊かになったけれど、我々は幸せにはなれなかった。そしていま、我々は改めて問い直しています。我々は何をすべきなのか。幸せへの道は何なのか。いまも我々はそれを探っているのです」と。
村上春樹の評価
村上春樹は、特定の国民性に捉われず、世界文学へ貢献した作家に贈られるフランツ・カフカ賞を2006年に受賞し、以後ノーベル文学賞の最有力候補と見なされていて、その小説は現在、世界中で読まれています。
その理由をスペインのインタビュアーが、次のように解説しています。
「広がりに広がって、いまではハルキ・ムラカミに魅了されない国がないほどです。しかしそれは、異国趣味、つまり日本への憧憬でなく、あなたの小説の内容に親しみを感じるからです。あなたの小説に登場する日本人の女の子のバッグのなかには、どんな国の都会の女の子のバッグにも入っていそうなものが入っています」と。
「1Q84」の書評に「今、世の中のある物事の在り様を、新聞・雑誌、新書、ネットなどに求めれば、眼からウロコが落ちるように、解答を見つけることができる。だがそれは、教養を深めることに役立つかもしれないが、今ここにある魂に安らぎを与えるものでない、今ここにある不安を鎮めるものではない。村上春樹の新作を求めた多くの人々は『解答のあり方が物語的に示唆される』方を望んでいるのではなかろうか」(月刊ベルダ誌)。
日本を舞台に、日本人を主人公に書いた小説でありながら、世界の人々が求める普遍性への解答になっているのでないか。このように理解できるのです。
「100年に一度」
普遍性といえば「100年に一度」もです。これは、グリーンスパン前FRB議長が「リーマン・ショック」前の2008年7月31日に、CNBCテレビで「100年に一度起きるかどうかの深刻な金融危機だ」と述べたことからで、以後、多くの場面で今回の金融危機を形容する枕詞として、また、他の問題にも引用されています。
「100年に一度」の金融危機は、ご存じのようにサブフライムローンという危ない住宅融資を行い、その担保証券を格付けの異なる証券と組み合わせ、効率のよい証券化商品であると、世界中に売りさばいたことが要因で、アメリカ人が行ったものです。
アメリカ人はどうしてこのようなバカなことを起こしたのか、それが以前から不思議でしたが、次の発言を知って納得しました。
ボーイング・ジャパン社長の発言
日経新聞「ビジネス戦記」で、ボーイング・ジャパン社長のニコール・パイアセキ女史が次のように述べていました。(09.6.15)
「米国では、ビジネスでは唯一結果を出すことだけが重要とされる。短距離走のようにできるだけ早く目指すゴールに到達することが最大の価値を持つ。『終わりよければすべてよし』。その過程はさほど問われることはない」と。
この女性社長はアメリカ人の本音を語り、これがサブプライムローン問題の本質に内在しています。米国型市場主義は「市場が決める価格が正しい」という前提で、利潤拡大を目的として行動し、最終的な利潤極大の局面にたどり着くまで引き返すことはありません。
だが、この利潤極大化がいつなのか、そのことが利潤を求めている過程では判断不可能です。利潤が増えている間は、もっともっと増やしたいという気持ちだけで、その儲けの仕組みが悪であろうが、そのプロセスに踏み込んだら、目をつぶって山を登るのです。利潤が上がっている今が、9合目か、又は5合目か、それとも頂上直前なのか、分からなくなっているのです。ここで引き返したら、その時点が5合目だったかも知れない。もしそうなら、残りの半分の利潤が獲得できないことになります。
ですから、前へ前へと進み、頂上に登りつめて「市場が決める価格」が下りはじめる時、それは問題が明確になった時点ですが、そこまでいかないと利潤極大点が確認できないのです。つまり、「100年に一度」という深刻な金融危機に陥り、これ以上利潤極大化が不可能時点になって、急に「この仕組みは問題だった」と気づくことになるのです。
しかし、その時は世界中に問題がまき散って、世界中の人々の生活に変化を与え過ぎていた、というストーリーなのです。これがアメリカ人の生活習慣思考方法だと、前述の女性社長が見事に語っているのです。
産業再生機構
日本はバブル崩壊から多くの企業が経営不振となったことから、2003年に国策機構の「産業再生機構」をつくり、大きいところではカネボウから、小規模では金精旅館のような従業員10人程度のところまで、41社の再建を行いました。
その産業再生機構で代表取締役だった冨山和彦氏から、先日ご体験をお聞きしたときに「再生をするためには、一流大学出身とか、アメリカのMBA資格を持つ人は返って問題で、実際の現場で必要とする人材は、情と理の衝突に耐え、現実と理念の相克を超えることのできるタフネスさと、哲学を持ち合わせた強い人だ」と明言しました。
つまり、アメリカ型の経営手法なぞは役立たず邪魔で、必要な能力は、相手と痛みを分かり合える日本的な思考で行動できる人でしか、企業再生はできなかったのです。
難解な日本の「舞踊」
ここでもう一度、前述の女性社長の発言に戻ります。
「ところが日本では、迅速に結果を出すことはもちろん重要だが、それだけでは『正しい』という評価が得られない。仕事の過程での微妙な人間関係や手続き、配慮が重要視されるからだ。それが私にはあたかも、リズムやニュアンスを持つ所作で美しさを表現する『舞踊』のように思える。実際、勝負に勝つことがすべてというビジネスの流儀が身に付いた米国人からみれば、日本でのビジネスで求められる『過程』は、本当に難解」と。
振り返ってみれば、日本は敗戦によって、64年前から民主主義という名の教育の下、アメリカ型がGHQによって強制されてきました。
しかし、この女性社長の発言は、変わった新しい戦後の教育が行われたのに拘らず、日本的思考習慣システムが依然として強く残っていて、それがアメリカ人には理解し難いという事実を指摘しています。この事実を再認識すべきと思います。
我々のDNAには、しっかりとした日本風土が潜在していて、それを基盤哲学として発揮できる人材のみが企業再生を可能にすると、冨山和彦氏も指摘しているのです。
村上春樹の背景
今、世界経済は「100年に一度」から、正常な状態に戻すための様々な対策がとられていますが、簡単にはいかないだろうというのが現実です。ところが、日本では90年のバブル崩壊があり、その後の「失われた10年」があって、経済停滞は世界に先駆けて経験済みという事実を再認識したいと思います。今後、世界経済の停滞が長引き、それによって世界が「失われた10年」といえる状態になるとしたら、世界の人々は「我々は何をすべきなのか。幸せへの道は何なのか」という村上春樹発言が持つ意味を理解しようと、日本のことをテーマにした小説であって、日本人が書いたものであっても、その背景に今後の世界が持つ普遍性があると理解し、受け入れているのではないかと思います。以上。
【7月のプログラム】
7月10日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
7月17日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
7月27日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
7月19日(日)9時 山岡鉄舟研究会(特例)飛騨高山にて鉄舟法要研究会
投稿者 lefthand : 11:50 | コメント (0)
2009年06月21日
2009年6月20日 生活が変わっていく
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年6月20日 生活が変わっていく
100年に一度
米国発で世界中に経済危機が広がった今回の金融危機、「100年に一度」とよく表現され、米国では「金融パールハーバー」という人も多くいるようですが、この言い方に米国金融界人の心象風景が出ています。
米国発金融危機なのですから、米国に問題の責任があるのに、他国から発して米国が迷惑しているという、責任転嫁の気持ちが表れています。今日まで、正式な場面で、米国人が金融危機で世界に迷惑をかけて申し訳ないという「お詫び」発言がなされたことがあるでしょうか。
昨年12月「米新政権と日米同盟の課題」シンポジウムに、米国政府関係者や著名大学教授が来日し講演とディスカッションを行いましたが、その席上で誰一人として「お詫び」発言はありませんでした。経済問題に触れても責任問題には論及しないのです。
また、今年の5月「米オバマ政権下の日米経済関係」と題して、在日米国商工会議所名誉会頭の講演を聞きましたが、経済危機の実態を分析し、巧みに解説しますが、その発生要因である米国の責任については何も触れませんでした。
大体、100年に一度という大げさな言い方は、世界共通の大問題なのだから、単に米国の問題ではなく、今さら責任云々なぞは関係ないという開き直りでしょう。
フードスタンプ
米国発の金融危機によって世界全体が大変な状況ですが、責任所在国である米国では、一段とひどい実態となっています。今や米国は世界最大の「経済大国」であり、一方、「貧困大国」になってしまいました。
その事例の一つが「フードスタンプ・プログラム」です。これは低所得者と無所得者が栄養のある食品を購入できるよう、食品購入時に割引できる電子カード、金券ともクーポン券とも言うべきものが支給されるシステムで、この利用者が3,400万人になっているのです。米国人の10人に一人は食べるものに事欠く貧困層になりました。
「フードスタンプ・プログラム」の説明書には「野菜・果物・脂肪分の低い肉をとり、運動を習慣化しなさい」と書かれていますが、実際にこのシステムを利用してこれらが実行されるのか疑問です。さらに、フードスタンプ支給家庭に高校生以下の子供がいると「無料一割引給食」の制度適用があります。これを利用して食べられるメニューはコスト削減から、栄養化が低く、高カロリーで安い、いわゆるジャンクフードといわれるものになります。その結果、肥満児童が多くなり、貧困が肥満をつくっているのです。
米国でバカ売れしている三品
オバマ大統領が住むホワイトハウス、その庭の芝生が最近は家庭菜園となり始めました。ミッシェル・オバマ夫人が、自身の娘やゲストに新鮮で健康的な野菜を提供しようと、ホワイトハウスに有機栽培の「家庭菜園」をつくることになり、南庭の一部の芝生を耕し、ほうれん草や豆類、ハーブなどを栽培しています。ホワイトハウスでの野菜作りは、第二次世界大戦中にエレノア・ルーズベルト夫人が「勝利菜園」を手掛けて以来のことです。この影響で米国では家庭菜園用の種子セット袋が爆発的に売れだしました。一袋30ドル程度ですが、このブームの背景には、普段食べている食品に対する安全性について、素朴な疑問があるからです。
次に売れだしたものは拳銃です。これはオバマ大統領が選挙期間中の公約の中で、銃規制を取り上げていたことから、銃愛好家の中で「駆け込み需要」が発生したことによるものですが、もうひとつ重要な背景に、経済が悪化し、失業者やホームレスが急増したことにより、犯罪の拡大が現実の問題となって、自らの安全を確保するためには、武装するのが一番だという心理が存在しているのです。
三品目は缶詰です。温暖化と気候変化で農産物の収穫が不安定となっていることから、米国政府機関が備蓄を始めたということで、一般人も備蓄を始めだし、それには缶詰が長期保存として最適なので、急に売れ出したのです。
備蓄二週間分リスト
世界保健機関(WHO)は6月11日、新型インフルエンザの警戒水準(フェーズ)を、広域流行を意味する現行の「5」から最高の「6」に引き上げ、世界的大流行(パンデミック)を宣言しました。インフルエンザの世界的大流行は、約100万人が死亡した1968年の「香港風邪」以来、41年ぶりです。
現在、日本は幸いにして小康状態を保っていますが、フェーズ「5」の時は日本国内が大騒ぎの真っ最中で、その5月1日、産経新聞が「備蓄食料品リスト」として家族四人で二週間分の内容を掲載しました。
かつて1918年(大正7年)、日本でもスペイン風邪で45万人もの人が亡くなりましたので、政府は慎重に対応しているのです。その対策の一つが備蓄です。
インフルエンザが蔓延すると、食料を運ぶドライバーが倒れ、結果的に輸送機関がストップしてしまうことから、補給が利かなくなる。また、その情報によって、スーパーの食料品売り場に人が殺到し、一気に売れてしまい、買えなかった人の間でパニックが発生する。その恐れから政府は家庭内の備蓄を勧めているのです。
さらに、インフルエンザ対策は海外旅行自粛、国内移動の制限、人混みを避ける、マスク着用、手洗いとうがいの徹底など、政府主導で行われていますが、これらの手段選択はWHOの判断結果を受けて講じているのです。
ということは、インフルエンザに関しては、事実上、世界中の国を統一して指示する機関、WHOの判断結果で我々の行動が決まっていくという社会になりました。
温暖化ガス中期目標
日本政府は2020年時点の温暖化ガス中期目標を、海外から購入する排出枠などを除いて「2005年対比15%削減」と発表しました。
米国の目標は05年対比15%減、EUは90年対比20%減と発表していますが、これら先進国が示した中期目標を積算しても、地球の温暖化を食い止めるとされる水準には不十分なことが明らかになっています。
ですから、12月コペンハーゲンで開催される国連気候変動枠組み条約締結国会議(COP15)の決定までには、困難な交渉が予測されますが、決定されるといずれも我々の生活に大きく影響してきます。
その理由は、今までは企業中心の温暖化ガス対策が中心でしたが、今回の目標が決定すると、省エネ余地が大きい「家庭部門」が主ターゲットなってきます。実は、07年時点で家庭の温暖化ガス排出量は、90年対比で40%も増えていて、その分「削りしろ」が大きく、家庭部門の負担が避けられないのです。結果的に各家庭のコスト増となるでしょう。いろいろ対策はありますが、主ターゲットは排出量が多い車です。新車の2台に1台をエコカーにする必要があるので、政府は経済的インセンティブを提供し始めたのです。ポスト京都議定書が我々の生活に関わっているのです。
次世代自動車
エコカーといえば、現時点で「低燃費」と「低コスト」を両立した供給可能な車はハイブリッド車しかありませんが、これにも次世代型がすでに登場しています。中国の新興自動車メーカーBYD、ここは携帯電話用電池メーカーですが、いち早く昨年12月にプラグインハイブリッド車の開発に成功したと発表し、本社のある深圳市政府に10台納入したと発表しました。ここがポイントで、次世代カーは新規参入が容易なのです。
また、三菱自動車は電気自動車i-MiEV(アイミーブ)を発売しました。電気自動車が一般に普及するためには、インフラ整備が前提条件で、まだまだ時間がかかりますが、普及したならば自動車業界の姿は一変します。
電気自動車は極端にいえば、モーターとバッテリーさえあれば走れるので、部品点数が大幅に減少し、開発コストも削減されます。このため新規参入が容易であり、かつ、部品数は少ないのですから、現在の部品メーカーの多くを必要としない社会、それは既存部品メーカーの廃業、失業者増という実態につながる可能性が高いのです。
100年に一度の金融問題、WHOのフェーズ宣言、ポスト京都議定書のCO2削減、外部環境の変化によって我々の生活が強制的に変えられていく時代になりました。
以上。
【7月のプログラム】
7月10日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
7月17日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
7月27日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
7月19日(日)9時 山岡鉄舟研究会(特例)飛騨高山にて鉄舟法要研究会
投稿者 lefthand : 11:49 | コメント (0)
2009年06月06日
2009年6月5日 経済は一気に簡単に一方向には動かない
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年6月5日 経済は一気に簡単に一方向には動かない
株価上昇
世界各国の株価が上昇しています。2009年3月(底値・安値)時点と比較した6月4日の株価は以下のとおりです。
| 2009年3月底安値 | 2009年6月4日 | 上昇幅 | 上昇率 | |
|---|---|---|---|---|
| NYダウ | 6,469(3/6) | 8,750 | 2,281 | 135% |
| 日経平均 | 7,021(3/10) | 9,668 | 2,647 | 138% |
| DAX(独) | 3,666(3/6) | 5,064 | 1,398 | 138% |
| FTSE(英) | 3,512(3/3) | 4,386 | 874 | 125% |
| 上海総合 | 2,071(3/3) | 2,767 | 696 | 134% |
| 韓国総合 | 1,018(3/2) | 1.378 | 360 | 135% |
上昇率を見ますと、主要国の株価は全てNYダウと連動していて、常にアメリカ経済の動向で世界株価が動いていることが分かります。また、この三カ月、大幅上昇した背景には、オバマ政権への信認度があり、更に、GMの連邦破産法11条の適用申請を機に、金融、自動車と続いた政府関与によるアメリカ経済の危機管理が一息つき、景気回復も見込まれ、アメリカ経済がV字型回復するという見解が専門家から出始めました。
基軸通貨ドルの信認が揺らぐ
しかし、アメリカ経済の先行きを危惧する専門家も多く、その要点を並べてみます。
- 大手金融機関6社の1~3月期決算が126億ドルの黒字となったが、これは次の2と3のような粉飾的会計処理で計上されたものである。
- 時価評価主義が改められ「市場で価格がつかない金融商品などは、理論価値または満期での償還価格で評価可能」となり、この結果、金融機関は未確定の含み損を明らかにしないですむので利益がかさ上げされた。
- 「負債評価益」を認めた。これは企業の負債である社債などの時価が下落した場合、企業から債権者への支払い義務も減少したとみなし、その分を利益に計上した。企業の信用が下がり、社債の時価が下がれば下がるほど、利益が積み上がることになる。
- 1,000億ドル以上の資産を持つ金融機関に資産査定(ストレステスト)を行った結果、合計5,992億ドルの損失が見込まれ、この程度の金額では「投資家と一般市民にかなりの安心感をあたえた」とバーナンキFRB議長が述べた。だが、IMFが4月に発表した米国の金融機関が抱える損失は4.5倍の27,000億ドルであり、金額がケタ違いであって、ストレステストは操作されているのではないかという疑問がある。
- 3月にアメリカ人の消費意欲をアンケート調査した結果(米アリックスパートナーズ)、貯蓄率が14%との回答であり、以前は0%だった。つまり、貯蓄が増える分消費は減るわけで、仮に貯蓄率が10%上がれば、GDPは10%減で、1兆ドル以上のGDP減額となる。
- ということは消費が伸びないのだから、早期に景気回復はできず、加えて、政府の財政悪化もあり「アメリカも失われた10年に陥るリスクがある」(クルーグマン・プリンストン大学教授・ノーベル賞経済学受賞者)と指摘されている。
- また、アメリカは日本の不良債権処理を支えた家計のゆとりがないのだから、経済対策に必要な資金としての国債増発引き受けは海外からとなって、これは国債金利に上昇の圧力がかかることになり、基軸通貨としてのドルの信認に懸念がでてくる。
従って、アメリカのパワーが減退していくという見方が専門家から主張されています。
預金封鎖本の結果はどうだったか
このようにアメリカ経済に対し、相反する見解が専門家の間で議論されています。
ここで少し前のことになりますが、日本で大騒ぎした預金封鎖について振り返ってみたいと思います。
2003年から2005年頃、小泉首相の時代でしたが、書店に「預金封鎖」「老人税」(副島隆彦著)、「日本国破産・五編」(浅井隆著)などの本が大量に並び、それらを読んだある主婦から真顔で「日本は大丈夫でしょうか。貯金が政府にとられてしまうのでは。タンス預金に切り替えた方がよいか」という相談を当時受けたことがありました。
かつて日本では実際に預金封鎖が昭和21年に行われました。今でもこの法律が抹消されずに残っていることを、国会図書館に行って確認したと、ある専門家から聞いたことがあります。つまり、今でもやろうと思えば法制上可能だというのです。
では預金封鎖とは何かですが、預金を封鎖することによって、各人の財産を把握し、その財産に対して税金をかけることを意味します。日本の個人金融資産が1,500兆円といわれていますので、仮に50%の財産税をかけると750兆円となって、これを実行すれば政府の赤字国債残高は相当額減り、これで財政状態を一気に改善できるのです。
2004年9月出版の「老人税」で副島隆彦氏は「アメリカ政府の財政赤字を端に発するドル暴落が発生し、その混乱防止のため日米が連携し金融緊急措置令を発し、一気に預金封鎖を行う。その時期は2005年から2~3年のうちだ」と書いています。
しかし、既に日本の不良債権処理が終わって、今は新たに発生したアメリカ発の金融危機からの経済対策で毎日騒がしく、一方、預金封鎖の声は全く消え、実施されずに無事今でも1,500兆円は残っています。物事は識者・専門家と称する人物が喧伝するように、簡単にはならないということを意味すると思います。
アメリカの底力
現在、世界で圧倒的地位を占めているのは、アメリカであることは疑問の余地がありません。そのパワーの第一は圧倒的な「軍事力」、第二はGDP世界トップである「経済力」、第三はオバマ大統領を登場させた「政治力」、この三つが際立っています。
今回の金融危機による経済危機混乱に際し、オバマ大統領が就任一ヶ月でGDPに対してほぼ4%にあたる「大規模不況対策予算」をまとめあげた手腕。それと、今回のGMに対する政府保有という国有化外科手術政策に対して、投資家や経営者から信頼を得始め、それが最近の世界株式相場の上昇となっていることを考えますと、やはりアメリカの持つ「政治力」は強く、今回の危機タイミングにオバマ大統領という人物を、登場させた底力を改めて感じます。世界は「米国主導の一極体制」がまだ続いているのです。
物事は簡単ではない
だが、いくらオバマ大統領に象徴される「政治力」がアメリカの強みといっても、物事には限度があって、一気の解決には進まないでしょう。時間が必要です。
解決への最大の課題は住宅価格です。住宅価格が上昇すると、個人は自分の所有する住宅の資産価値が増えたことになり、所得を消費に回すことが行われるからです。
逆にいえば、アメリカの景気が個人消費主導で成長していた時は、必ず住宅ブームが伴っていたのです。住宅価格の動向を見れば、その後の消費動向がわかり、ひいては、世界経済の先行きまで占うことができることになります。
しかし、サブプライムローン問題から、住宅価格はインフレからデフレになりました。これがいつ回復するか。それが不透明です。ですから、こういうアメリカ経済成長の基盤背景を考えてみれば、景気が一気にV字型回復は難しいと思えます。
だが一方、株価には景気の先行きを見極めるという原理原則があって、いかなる優れた経済学者よりも先行予知能力があるという過去経験則によれば、景気の先行きは明るいとも考えられます。
注意したいこと
要するに今は判断が難しいタイミングです。景気がV字型回復するのか、まだまだ混迷が長く続くのか、それぞれ専門家は各立場で主張しますが、預金封鎖を唱えた専門家達の失敗を参考にすれば、物事は人が考えるようなストーリーで、一気に簡単に一方向には動かないということです。
ですから、今後の経済状況を注意深くウオッチングすることが必要ですが、気をつけたいのはディリバティブという金です。これが儲けを求めて通貨や国債・証券へ、また様々な商品の間を動き回ってかき回しましますから、その行き先を見続けることです。もう一つ大事なことは、肩書に引かれて専門家の主張を鵜呑みにしないことです。以上。
【6月のプログラム】
6月12日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
6月15日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
6月14日(日)13時 山岡鉄舟研究会(特別例会)靖国神社参拝と散策会
投稿者 lefthand : 20:53 | コメント (0)
2009年05月20日
2009年5月20日 情報力が国を拓く
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年5月20日 情報力が国を拓く
ミシュラン観光ガイドブック
今年の3月16日にフランスで、ミシュラン日本観光ガイドブックが初出版されたことは既にお伝えしました。また、この中で日本の温泉星付きは、たったの9か所しかなく、そのうち三つ星は1か所のみで、それは別府の共同風呂「ひょうたん温泉」であることもお伝えしました。
この結果について、各地で多くの方にお伝えしていますが、先日、世界と日本の温泉について最も詳しいと自負されている、日本の専門家とディスカッションになり、以下の反論を受けました。
「ミシュランの格付けはおかしい。フランスの世界遺産モンサンミッシェルに行って、素晴らしいステンドグラスがあると思ったらなかった。それと同じでひょうたん温泉なぞは大したことない。自分が温泉の格付けをつくり、上位から並べてみる」と。
モンサンミッシェルのステンドグラスという意味がよく分かりませんが、とにかく激しくミシュランの星付けを非難しました。しかし、このような反論は無意味です。
その理由は、ミシュランが持つブランド力です。世界中の人々がミシュランという格付け力を評価しているのですから、「ひょうたん温泉」の三つ星認定を、多くの人々は疑問を持たず受け入れるでしょう。
日本の温泉第一人者がいくら息巻いても、世界の人々はミシュラン格付けを認識します。
観光立国、世界遺産は脇役
脚本家の橋田寿賀子さんが次のように述べています。(日経新聞2009.5.11)
「海外から観光客を誘致するとなると、すぐ世界遺産に登録された有名観光地などの名を挙げます。でも、日本の世界遺産が外国人の人々にどれだけ魅力的に映るのかというと、少し疑問もあります。
日本の観光面での魅力はもう少し違うところにもあるのではないでしょうか。例えば、日本の原風景ともいえる里山などごく普通の景色、四季折々の表情豊かな自然、そして何よりも日本人のきめ細やかなもてなしなどです。
NHKスペシャル『映像詩 里山』を見ても、外国にない日本独特の繊細な風景です。また、飛騨高山の町並み、北海道や瀬戸内海の自然の景観を楽しんだり、東京の下町の旅館に喜んで泊まったりする人が増えていますよ。ごく普通の自然や市民の営みが、外国の方々の人気を集めているのです」
欧米人の多い街
岐阜県高山市はミシュランの三つ星で、外国人それも欧米人が多く訪れます。
今年の7月19日、この日は山岡鉄舟の命日ですので、鉄舟が少年時代を過ごした高山の宗猷寺、ここは両親の菩提寺で、ここで「山岡鉄舟法要兼記念講演」を行うことから、このところ何回か高山を訪問しています。
先日も、宗猷寺の本堂でご住職と打ち合わせしていますと、お賽銭箱の間から本堂内を覗く欧米人男女がたくさんいますし、境内を歩いているのは欧米人ばかりです。「今日は」と挨拶すると「コンニチワ」と愛想良く答えます。ご住職は「日本人は古い街並みのさんまち辺りで止まってしまい、ここ東山界隈には来ませんよ」と語ります。
夜は高山陣屋近く、高山祭の屋台置き場真ん前、百余年の歴史を持つ後援者のご自宅でご馳走になりました。このお宅の玄関は格子戸で身体を折り曲げないと入れない低さですが、中に入って行きますと、天井が次第に高くなって、階段を上がると、そこは飛騨建築の見事な奥座敷、鴨居・欄間・屏風に見とれていますと、座卓上に飛騨料理が並びだし、これがすべて手料理、それが結構な味わいで、加えて、食器が美術品のごとき飛騨陶器なのです。
この座敷で、こちらの奥様、それと高山郷土館の学芸員、市会議員、飛騨の里のガイドの方と、飛騨高山文化の薫り高き話題でひと時を過ごしたことで、ミシュラン三つ星格付けと自分の実感が一致し、高山に対するミシュラン評価については納得しました。
小浜市
翌日はオバマ大統領で話題となった、福井県小浜市に行きました。JR小浜駅前の観光案内所に入りますと、係の女性がとても親切に地図を広げて説明してくれます。この対応を見て、この街は、多分、感じがよいだろうと先入観をもちました。
ちょうど昼時でしたから、まず、魚センターに行き、入口の食道に入り、さば焼き定食を食べましたが、これが最高の味です。こんなに美味い理由を聞いてみようと、おしゃれな若いウェイトレスに尋ねますと、ちょっと待ってくださいと言いながら、調理場から魚センター理事長の名刺をもった人物を連れてきました。この店のご主人ですが、これまた親切に小浜の魚について解説してくれます。なるほどと思い、ついでにすぐ近くの漁業組合に行きますと、課長の名刺を持った人物が、小浜の魚について巧みに教えてくれます。
この町は親切だなぁと、次に市役所に行きました。フロアの表示板で観光課を探しますと「観光局準備室」とか書かれています。観光部門を昇格させようとしているのかと考えつつ、二階に上がり窓口の女性に尋ねますと、すぐに主査の名刺を持った若い男性が飛んできました。
この主査がまたもや親切、加えて、詳しいのです。観光担当ですから詳しいのは当然だと思いますが、その言動が当を得て勘所をつかんでいるのです。そこで、夕食はどこがよいだろうかと相談すると、こちらが宿泊するホテルを確認し、直ちに近くの飲食店の名前と大体の予算額を述べます。感心しました。
従いまして、主査が紹介してくれたところに行きましたが、推薦通りの料理と女将の接客に「なるほど」と納得し、こういう日本人の持つきめ細やかな感覚、つまり、昔ながらの親切で対応してくれる町が、ミシュランの星付けになればよいなぁと思った小浜でした。
丸の内再開発
5月の経営ゼミナール例会は、東京駅周辺120haにわたる丸の内再開発について、実際に実務を担当している推進責任者と設計を担当された方から、詳しく経緯と現状、今後の計画を伺いました。
多くの地権者が存在している中で、全体の合意形成までに持っていくのは大変なのですが、日毎に変化していく丸の内界隈を見ると、再開発はうまく進んでいると納得しました。
特に感心したのはネットワークという考え方を取り入れていることです。地上と地下を歩行者の歩きやすさという視点から通路を整備し直し、ビルごとの地下駐車場を4街区にまとめ直し利便性を上げ、高層ビルが道路と隣接する部分を低層化し街並みと一体化を図って圧迫感を排除し、皇居の豊かな緑と東京湾からの風を取り込んだ風の道づくりなど、今までの都市形成では弱点とされた「つなぎ」感覚を新しく取り入れていることです。
併せて、世界主要都市の再開発動向についても勉強し、丸の内の実態は世界でも優れていると再認識いたしました。その証明は、世界の主要都市から大勢見学者が訪れていることです。毎日のように歩いている丸の内界隈の変貌、完成までには相当の時間がかかるでしょうが、全体が見えたある時点で、ミシュランガイド星付きを期待したい開発です。
情報は双方向
孫子兵法第三篇謀攻に「知彼知己、百戦不殆」(敵情を知って味方の事情も知っていれば、百回戦っても負けない)があります。さすがに2,500年の風雪に耐え生き残っている世界の生き方指針と思いますし、この孫子に従って考えれば、冒頭の温泉専門家のようにミシュラン格付けに反論するのでなく、逆に高く関心を持ち、どのようなところを認めて「ひょうたん温泉」を三つ星にしたのか、という情報収集が大事になります。
日本は第二次世界大戦で情報戦争に負けました。アメリカに日本軍の暗号が解読されていて、それがミッドウェイ海戦の敗北、山本五十六司令長官の戦死につながって、最後までアメリカの暗号を解読できませんでした。「ヒトラーのスパイたち」(クリステル・ヨルゲンセン著)には、ドイツの敗戦は情報戦に要因があり、ドイツ情報部の特徴を一言で表現すれば「多くの活動、少ない情報」とあります。全く日本軍と同じです。
いくら小浜が、丸の内が素晴らしくても、ミシュラン星付きにならないと世界へのデビューは不可です。知らざる「ひょうたん温泉」だけが、何故に3,000余か所の中から三つ星になったのか。その背景を冷静に探ることこそが、実は、日本を観光大国にする最適・最短の方策であり、ミシュランは「情報力が国を拓く」と教えてくれているのです。以上。
【6月のプログラム】
6月12日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
6月15日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
6月14日(日)13時 山岡鉄舟研究会(特別例会)靖国神社参拝と散策会
投稿者 lefthand : 07:25 | コメント (0)
2009年05月06日
2009年5月5日 日本は田舎がいい
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年5月5日 日本は田舎がいい
ゴールデンウィーク
各地の空港や駅は、家族連れや行楽客でにぎわっていますが、豚インフルエンザから変異した新型インフルのおかげで、海外に行くことをキャンセルした人も多く、当方も、5月の海外出張は取りやめまして、今後はインフル状況次第と考えています。
山梨県北杜市
ゴールデンウィークの前に山梨県北杜市に行きました。その内容を山岡鉄舟研究会ホームページに掲載いたしました。概要は以下です。
→山岡鉄舟研究会のホームページへ
(1)4月19日、山梨県北杜市に鉄舟の書があるとのことで、新宿から約2時間。JR中央本線・長坂駅を降り、北杜市白州(はくしゅう)町、ここは甲州街道の宿場町でして、今も昔の街道風情を残すところの酒蔵「山梨銘醸株式会社」を訪ねました。創業300年で、白州宿の本陣も兼ねていたところです。
(2)店構えは立派で、大きな杉玉に「七賢」の看板。中に入るともろみのいい香りがします。また、「行在所(あんざいしょ)ご案内時間」の看板もあります。
(3)ここには明治13年、明治天皇ご巡幸の折、母屋の奥座敷を行在所(仮の御所の意)としてご一泊され、天井が高く、立派な梁が縦横に組まれ、庭も趣があります。
(4)次の間に入ると、鉄舟書の屏風が目に飛び込んできました。高さ一間あまりの大きさです。鉄舟は明治天皇侍従でしたから、事前視察時に書いたものですが、ここは日本酒の試飲もあって、七賢酒造はうまい酒と知られていますから観光客が結構おりました。
(5)次に向かったのは「長坂郷土資料館」の「富岡敬明展」です。この資料館は山に囲まれた田園地帯に忽然と建てられた感の立派な建物です。「富岡敬明」とは、山梨県最初の権参事(副知事)で、晩年この地域の文化活動、文人育成に貢献した人物ですが、もともと佐賀の人で、この地に地租改正実施に絡む農民暴動を鎮めるため、佐賀から派遣されました。この派遣時に、鉄舟が伊万里県(佐賀県)権令(知事)の時期で、鉄舟が富岡敬明を推薦したといわれている経緯を、学芸員の大庭女史から教えていただき、詳しい解説に驚くと共に、他に誰も来館者がいないことにビックリしました。
知られていない増富の湯
北杜市はちょうど桜の季節。この時期だけ営業している桜バスで、七賢酒造から韮崎駅までの窓外は素晴らしい景観が広がっていました。さらに、韮崎駅から増富の湯までの道はこれまた桜の街道で、東京より少し遅れた山桜の満開を楽しみ一泊いたしました。
翌日は、益富の湯で経営ゼミナール四月例会を開催いたしました。その様子も経営ゼミナールホームページから概要をご案内いたします。
→経営ゼミナール2009年4月例会報告
(1)「増富の湯」は、増富ラジウム温泉郷の中にある日帰り温浴施設です。周りには9軒の温泉旅館がひっそりと点在する、自然に囲まれた山間の温泉地です。
(2)セミナー室で総支配人の小山芳久氏より、増富の湯の説明と、同館が実施されている「健康増進プログラム」についてのお話を伺い、実証データと社会背景からの温泉入浴の必要性を納得しました。
(3)増富の湯は3種類の温度の温泉浴槽があります。源泉そのままを浴槽に流している25度、30度に加熱したものと35度に加熱した浴槽です。
(4)小山氏からの入浴心得は、まずはそれぞれに浴槽に手を入れ、心地良いと感じる温度の浴槽に入ることが大事で、入っていて、寒いと感じたならば、すぐに出て温かいお湯(沸かし湯もあります)に入ること。決して我慢や無理をしないこと、つまり、「自分の気持ちに逆らわないで入ること」でした。
(5)たっぷり1時間ちょっとの入浴を経て、次は、地元の幸をふんだんに使った、その日の朝スタッフが摘んでこられた山菜料理「摘み草定食」をいただき、その後、裏山「命の径」に入り、じゅうたんのように厚く積もった落ち葉の上に、シートを敷き寝て、小山氏のゆったりとしたリードで深呼吸、続いて風の音、鳥の声に耳を澄ませ、自然の息吹を感じとるよう集中させると、いつの間に寝入ってしまうという経験をしました。
このようにすばらしい増富の湯ですが、驚いたことに一般に知られていません。経営ゼミナール例会に参加した方全員も知らなかったというわけで、勿論、温泉側は日夜熱心に伝える努力をしていますが、現実は知られていないのが事実です。
しかし、実際の北杜市には日本人が余り知らない、素晴らしい日本があります。
ミシュラン観光ガイドが選んだ三つ星★★★温泉
以下は温泉文化研究会で私がお伝えした内容です。
→温泉保養文化研究会ホームページへ
「09年3月、フランスで『ミシュランガイド・ギードベール・ジャポン』が発刊されました。これはミシュランが編集した観光ガイドで、日本版は初めての発行です。9月に英語版が発売されますが、外国人が日本に観光にやってくるためのガイドですから、日本語版は発刊されません。
さて、このミシュランガイドをひもといてみますと、様々な日本の観光地が紹介されています。もちろん、例の星★の評価付きです。東京近郊の三つ星★★★は、明治神宮など数多くありますが、その中に東京都庁もラインナップされています。日本人の我々から見ますと、評価基準の感覚が少々異なっていることに気づきますが、高尾山に急に外国人が訪れ出したと、以前に話題なったことがありますが、あれはミシュランの簡易版ガイドに★★★として紹介されたからです。
ところで、日本の温泉地はどのように紹介されているでしょうか。日本に温泉地は3,000余カ所以上あります。ところが、ミシュランガイドの中に紹介されているのは、何と9カ所しかないのです。これは驚きです。しかも、★★★であるのは、たったの1カ所です。一体どこが、ミシュランで★★★を獲得したのでしょうか。
その種明かしをする前に、選ばれた温泉地を順次ご紹介しましょう。
★=別府、登別 / ★★ =湯布院、黒川、指宿、野沢、新穂高、竹瓦
ほとんどは聞き覚えのある有名な温泉地ですが、★★の最後、竹瓦温泉(たけかわらおんせん)はご存知の方は少ないのではないかと思います。
では、3,000余カ所から選ばれた唯一の★★★温泉地は…。それはひょうたん温泉です。
ご存知でしたでしょうか? ひょうたん温泉は、竹瓦温泉とともに、別府にある『共同浴場』なのです。竹瓦温泉は、大分県別府市にある市営温泉で、入湯料100円。ひょうたん温泉は、これも大分県別府市にある日帰り温浴施設で、入湯料700円です。これらが、ミシュランが評価した日本の温泉です。
★の数の少なさもさることながら、我々日本人が一般に評価する温泉地との解離が甚だしい、ということにお気づきになられるのではないかと思います。例えば、日本一と謳われる草津温泉や、箱根、伊豆など人気の温泉地、また道後、有馬、など歴史ある温泉地が★を獲得していないのです。知られざるミシュランの格付け認識、これは一体どういうことなのでしょうか」
なお、研究会にご参加の温泉関係者の方々も、ひょうたん温泉を知りませんでした。知られていない地方の共同風呂が★★★という事実、ここに何かのヒントがあるのです。
日本は田舎がいい
今年の3月、エストニアのタリンで、立命館アジア太平洋大学を卒業し、日本語は普通の日本人と全く同じレベルのエストニア美人と会いましたが、彼女が「日本各地ほとんど訪問したが、日本の一番いいところは田舎だ」と断言しました。
また、昨年10月に、パリ・ブローニュの森に近い瀟洒なアパルトマンで、日本とフランスの親睦団体「SUZUKAKE NO KAI」、この会は上流階級の人ばかりで構成していますが、その会員の女性から「日本を二回にわたって、三カ月間かけて北海道の礼文島・利尻島から、沖縄の突端・与那国島まで回ったたが、日本は草花が咲く田舎がベスト」と述べました。書道を好み書き、日常は玄米茶か日本茶しか飲まない大の日本ファンの方が、日本の田舎を高く評価するのです。
さらに、同様の事例は各国で多く聞きます。もしかしたら、我々は欧米人が考える観光地と異なる判断基準で、日本をPRしているではないでしょうか。一度、日本を見る目を自己評価でなく、欧米人から見る他者評価に立つ必要があるだろうと思っています。以上。
【5月のプログラム】
5月 8日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
5月15日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
5月18日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
5月20日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 10:04 | コメント (0)
2009年04月21日
2009年4月20日 米経済には頼れない
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年4月20日 米経済には頼れない
日本経済
2008年度の日本経済成長率は、2009年1月から3月までの実績が5月に発表され、その結果で最終決定します。だが、事前の予測では相当悪いというのがもっぱらの観測です。
民間経済研究機関9か所が、3月に発表した2008年度と2009年度の見通しに基づく日本経済成長率は下図のとおりです。
野口悠紀雄氏説の見解
上図の数字は、3月中旬時点の各経済研究機関の予測ですので、実は、もっと悪化している可能性が高いのです。
実績が確定したところでもう一度上図を訂正しご案内したいと思いますが、日本経済は急下降で、この要因は勿論アメリカ発の金融危機による世界大不況からの輸出急減です。
これに関して2月20日のレターで、野口悠紀雄氏(早稲田大教授)が文芸春秋三月号で述べた次の内容をご紹介しました。
「分かりやすく言えば、経済の水準が6年前、バブル崩壊後日本の景気がどん底を示した2002年~2003年の状態に戻る、ということだ。2002年に底を打ってから、日本の実質GDPは6年間で10%増加した。ちょうどその上昇分が消失するのである」
そこで、今回の大幅落ち込み以前である、2008年1月時点のGDPは568兆円と、2002年10月時点のGDP、509兆円を比較してみますと、59兆円の減少となります。この額は正に日本のGDP総額の約10%分にあたり、野口教授の指摘が信憑性を帯びてきました。
アメリカ経済
日本経済が数年前の様に成長するためには、世界経済の賦活が前提条件です。また、その世界経済はアメリカの経済にかかっていますので、アメリカの実態がどうなのか。それが最大の関心事となります。そこで、いくつか最近の報道から拾ってみたいと思います。
(1)まず、オバマ大統領の発言。4月10日にバーナンキFRB議長と協議後の会見で「米経済はなお厳しい緊張下にある」としつつも「米経済にはかすかな光も見え始めている」と語りました。
(2)次に、米金融大手ゴールドマン・サックスは4月13日に、2009年度第一4半期(1〜3月)決算は最終利益が18億1,400万ドルと発表。これは市場予想の二倍に該当し、金融問題の損失処理が改善に向かっていることを伝えました。
(3)さらに、バーナンキFRB議長は4月14日、ワシントンで演説し、米経済に「前進の兆しが生まれつつある」と述べました。
(4)このところ株価が上昇傾向になってきました。4月17日の米株式相場は続伸しダウ工業株30種平均は8,131ドルとなり、3月9日に付けた6,547ドルからの上昇幅は1,500ドルを超えました。
(5)外国為替市場でもドルが優勢となって、昨年12月18日は1ドル=87円でしたが、4月18日は99円と円安傾向になっています。
(6)以上の状況から、アメリカではGreen Shoot(緑の芽吹き)という言葉まで飛び交うようになったといわれています。
本当はどうなのか
米国経済の動向をいち早く把握するためには、米労働省が毎月発表する「雇用統計」が群を抜いて優れているといわれています。
その中でも特に、非農業部門雇用者の前月比増減数が注目されます。それは、米国企業は経済が減速し始めると、迅速に雇用を削る傾向があり、雇用減少は個人消費の鈍化につながるため、やがてはGDPの悪化にもつながるからです。
各月分を翌月の第一金曜日に発表しますので、4月3日発表の3月雇用統計を見ますと、軍人を除く失業率は8.5%となり、1983年11月水準以来の悪化で、景気動向を示す非農業部門雇用者の前月比は前月から66万人減少しました。
これは昨年1月からの合計で510万人に達するもので、ここずっと60万人から70万人もの人々が雇用を失っている状況です。
FRBの判断基準は、増加幅が15万人以上であれば雇用・景気はともに堅調であり、10万人以下であればともに懸念する必要があるとされていますが、この判断目安が全く参考にならない惨状となっています。
株価と雇用との関係
下図は雇用統計と日米株価の関係を示したものです。
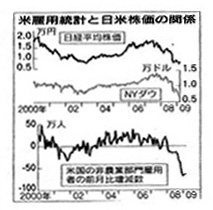
アメリカの雇用統計を見ていますと、米国経済だけでなく株価の予測もできる可能性があります。上図を見ますと、日経平均株価とNYダウはほぼ連動して動いていることが分かり、この株価と下段の非農業部門雇用者前月比増減数とほぼ連動していることも分かります。アメリカの雇用がGDPに影響し、結果として日米株価に影響しているのです。
デカップリングは誤りだった
米国経済が減速しても、新興国や資源国の高成長で世界経済は順調に推移する。というデカップリング論が著名経済アナリストによって、喧伝されていたのはついこの間のことでしたが、金融危機の結果はこの主張は全く当たらないということを証明しました。
今になって考えてみれば、全く市場規模が異なっていたのです。例えば、米国の消費は約10兆ドル(1,000兆円)、これに対し成長著しい中国とインドの消費を合わせても約2兆ドル(200兆円)ですから、米国経済が急激に悪化すれば、新興国の成長ではとても穴埋めできないわけで、この事実データを見誤っていました。
アメリカ経済は改善していないのだから
アメリカ人は、住宅バブルで借金を膨らませた家計のバランスを考え、借金減らしを優先し始め、雇用情勢が改善されていない状況下では、内需の柱である個人消費復活は期待薄です。オバマ政権の経済政策司令塔であるサマーズ米国家経済会議の委員長も「米経済は世界景気回復の原動力になれない」と言明しました。この発言背景は、世界経済の規模拡大は難しいという意味になります。世界経済全体が苦しいのですから、日本は内需を増やす方策しかなく、そのために何を戦略目標にするか。その答えは前回レターです。
以上。
【5月のプログラム】
5月 8日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
5月15日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
5月18日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
5月20日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 17:53 | コメント (0)
2009年04月05日
2009年4月5日 時代は外から変わっていく
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年4月5日 時代は外から変わっていく
訪日旅行者数の急減少
日本政府観光局が発表した2009年2月の訪日外国人旅行者は、前年同月比で41.3%の減少となりました。統計がある61年以降では、過去最悪だった大阪万博開催翌年の71年8月(41.8%)に次ぐ大きさでした。
要因として「世界的な景気後退や円高など」を挙げていますが、各国政府や自治体の「旅行自粛」も響き、国・地域別では香港の60.4%、シンガポールの56.4%、韓国の54.5%が目立つ減少でした。
この中でも中国は2月25.6%減でしたが、1月は31.4%増と、旧正月が昨年は2月、今年は1月であったことが影響して月別変化があるものの、全体的には中国人の訪日が増えている傾向です。
その理由の一つに「中国での北海道ブーム」があります。きっかけは正月映画として大ヒットした「非誠勿擾(フェイチェンウーラオ)」、日本語題では「誠実なおつき合いができる方のみ」という中国版ラブコメディで、知床や阿寒湖など北海道東部も舞台として登場し、美しい自然が評判となって、今年になって北海道ツアーが急増したからです。
ミシュランガイドブック
訪れる観光地を星印で格付けするフランスのガイドブック、ミシュランの観光版「緑のガイド(ギード・ベール)」が3月16日発売されました。
ホテル・レストランのガイドは2007年から東京版が登場しており、観光地に関しては簡易版「ボワイヤジェ・ブラティック」が刊行されていましたが、本格的なガイドとしてのギード・ベールの発行は初めてです。
すでにアジアではタイとシンガポールが発行されていて、日本は三か国目で「ギード・ベール」は、その国の文化に重点を置き、格式も高いとされていますが、今回の内容で「わざわざ訪れる価値のある場所」としての三つ星基準に選定されたのは56か所、二つ星は189か所、一つ星は301か所となっています。
この選定は、日本で暮らすフランス人10人と、本国スタッフ1人、日本人1人の合計12人で、国内各地を訪れ「印象深さ」「歴史的遺産価値」「自然の美しさ」「もてなしの質」など9項目を分析し、都市だけでなく史跡や公園、博物館などもランク分けし評価したものです。
ガイドを見てみると
ギード・ベールはフランス語によりフランスで発売され、9月に英語版が刊行されますが、日本語版の発行は未定とのことです。
したがって、日本ではちょっと入手が難しいので、3月末のパリ出張時に現地書店で購入し、早速にホテルの部屋で三つ星はどこか、二つ星はどこかとチェックしてみました。
三つ星は、京都、富士山、日光、伊勢神宮、姫路城、善光寺、松本城、屋久島、新宿御苑、東京都庁、明治神宮、東京国立博物館、高山、白川郷、五箇山、川平湾など、二つ星は浅草、谷中、六義園、築地市場、石垣島、黒川温泉、野沢温泉などです。
しかし、意外だったのは、先日一泊してきた日本で最も成功しており、集客力日本一という温泉地が無印となっていたことです。日本に戻ってから、早速、この温泉地の観光課に電話し、ミシュランガイドのことを知っているかどうかお聞きしたら、答えは「知らない」という返事です。なるほど 無印ですから無関心なのか思いましたが、何か違和感の残る観光課の返事でした。
さらに、「中国での北海道ブーム」で北海道に中国人が増加しているのですが、ギード・ベールでは北海道に三つ星はなく、二つ星として知床、層雲峡、旭岳、姿見、カムイワッカ湯の滝だけで、日本人に人気の高い小樽は無印という意外な結果ですから、仮に、中国人によるブームが一過性で終われば、北海道へ観光客増は苦しいのではないでしょうか。
経済状態はすべて苦しい
アメリカ発の金融問題から、世界中で輸出が急減し、外需が消え、ここ5年ほど輸出急増でGDPを伸ばしてきた日本経済は急変低迷化、国内需要にも影響しはじめ、企業経営環境を悪化させているのですから、経営が苦しいのは当たり前の実態です。
ところが、この金融危機以前から経営が困難化している企業も多くあります。そのような企業をいくつか拝見していますと共通していることがあります。
それはずっと同じことを続けていることです。「継続は力なり」ですから大変立派なのですが、実はその継続している経営方法に問題がある場合が多いようです。
かつて大成功し、素晴らしい業績をあげられていた企業でありながら、金融危機とは関係なく苦しい実態に陥っている共通要因は、時代変化に対応していないということです。
時代は30年前とは大きく変わり、そこに今回の金融危機が発生し、問題を複雑化させ、経済再生の処方箋なきままに世界中で経済対策を打ち続けている、というのが最近の状況ですが、このような大変化があっても、それは関係ないといわんばかりに、昔の経営スタイルを続けているのです。
結果はどうなるでしょうか。今の社会と馴染まないのですから、その企業の実績は次第に低迷化していき、如実に業績悪化という事実となって出てきています。
評価基準が変わった
業績悪化企業の経営者とお会いし、その際にアドバイスしていますことは「時代の変化を取り入れる」ということです。
時代は常に変わって、社会の姿も変化していきますから、この中で生活している人間も、自動的に変化に対応していきます。
ですから、経営者の一番大事な仕事は、時代の基底軸に流れている変化を把握することで、そのために大事な必要条件は、自らの感覚要素を磨くしかありません。
また、この感覚を磨くためには、連続していく毎日の動きをウォッチングし続け、そこから時代の変化を読み取り、採りいれ、結果として妥当で適切な経営手法を取り続けることしかありません。
つまり、経営者自身の判断基準を磨くことしかないのですが、ここで注意しなければならないのは、その判断基準は自分の中に存在するのではなく、社会変化から生ずる人々の感覚変化という他者基準にあるわけで、これに留意すべきなのです。
その典型的な事例が、今回のギード・ベールとお考えになってよろしいと思います。
ミシュランガイドをどう認識するか
ミシュランガイドは世界的に認識され評価されています。
それは、2007年に東京の飲食店ミシュランガイドが発行された時、発売日から4日間で初版12万部が完売し、人気の高さが証明されましたが、これは日本語ですから日本人用でした。
だが、今回の観光ガイドはフランス語と9月の英語版での発行で、日本語版は未定です。これは、考えてみれば当たり前で、外国人のためのガイドですから英語で十分なのです。
また、このガイドの効果は、簡易版ガイドで証明されています。簡易版に掲載された観光地に、急に外国人が増えだし、調べてみたらミシュランに乗っていたという事実がありますので、これから日本に来る多くの観光客は、今回の詳しいギード・ベールを手に持ってくることでしょう。そうなると掲載されたところに外国人が増えることは容易に予測つきます。
その証明が、簡易版でありながら、フランス人が昨年日本を訪れた人数は14万を超え、一昨年に比較し7%増となっていることでわかります。
ということは、ミシュランが勝手に価値づけした評価で、日本各地の観光地に訪れる外国人の人数増が決まっていくという意味になります。
つまり、観光地自身による自己評価基準でなく、他者評価基準によって観光客数が決まっていくという変化が訪れたのです。
時代は外から変わっていく
金融危機はアメリカからでした。人口減少下、観光客を増やしたいとしたら、頼りは外国人となり、それはフランス人による評価で決まる確率が高い時代に変わりました。以上。
【4月のプログラム】
4月10日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
4月17日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
4月20日(月) 経営ゼミナール例会 「増富の湯」日帰り現場見学
【ジョン万次郎のご子孫を招いての特別講演会】
★ジョン万次郎講演会★ 4月15日(水)18:30 上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 08:50 | コメント (0)
2009年03月21日
2009年3月20日 苦しいからこそ未来への「はずみ」を考える
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年3月20日 苦しいからこそ未来への「はずみ」を考える
金は世界を映す出す鏡
米連邦準備理事会(FRB)は、3月18日の米連邦公開市場委員会(FOMC)で、長期国債の買い取りなどを含む追加の金融緩和策を発表したところ、外国為替市場でドルが下落し、ニューヨーク金先物相場は時間外取引で4月物が一時前日比37.2ドル高の1トロイオンス(約31グラム)954.0ドルという大幅高となりました。
ちょうど一年前の3月も、ニューヨーク金先物相場で1,000ドル超えしましたが、金は周期的な動きを示すものなのでしょうか。
金はどうも違うようです。趣味の世界だった金貨が、昨年10月から12月にかけて突然売れ始め、世界の金貨需要が前年同期比3倍の67.9トンに達しました。一人当たりなら数十グラムに過ぎない、庶民の現物買いが積み重なって上がったのです。
金価格の高まりは、世界に潜むリスクの裏返しともいえます。金の絶対的価値は昔から変わっていなく、変わった方は世界であり、市場であり、それをつくり出している人間たちで、その変化が、ある時は買いとなり、ある時は売り、金の相対的価値を変えていっているのです。「金は世界を映し出す鏡」と思います。
アメリカ経済
公的支援で破綻を回避した米保険大手AIG幹部へ、高額賞与が支払いされていたことについて批判が渦巻き、共和党のグラスリー議員は「日本の例にならいAIGの幹部が米国民の前で頭を下げ謝り、辞任か自殺すれば私の気持ちも幾分晴れる」と発言し、オバマ大統領も記者会見で怒っていることを表明し、とうとう支払った金額に対して高率の税金をかけるようですが、すべてこの問題もアメリカ発の金融危機が招いたことです。
今回の金融危機が始まるわずか一ヶ月前の2007年7月、シティグループの当時の会長が「曲が流れる以上、踊らなければいけない」と発言しましたが、これは「いずれ限界がくることは分かってはいるが、まだ降りられない」という特異で危うい心理でありながら、目前のマネーゲームに狂奔した姿を示しています。
おかげで金融危機以後、何でもありの経済対策が打ち続けられていますが、開いた大穴をふさぐ「はどめ」対策の有効策を打ち出し得ないままです。
ノーベル経済学賞学者のクルーグマン米プリンストン大教授からは「欧米の財政政策は不十分で、失望している」と、アメリカやEUの景気対策を鋭く批判し、さらに、矛先はオバマ大統領にも向かい「この経済危機に対するオバマ政権の対応は、90年代の日本にあまりにも似ている。オバマ政権は後手に回っている」と厳しい見解です。
共和党グラスリー議員もクルーグマン教授も、いずれも日本を例えにしているところが、日本人としては気になるところですが、日本しか参考になる前例がないのでしょう。
需給ギャップ
クルーグマン教授は続けて「アメリカの議会予算局による予測では、3年後には、米国経済の生産能力と実際の生産高に2兆9,000億ドル(280兆円)の差が生じる」と警告を発していますが、これは需給ギャップ、それは需要にあたる実際のGDPと、供給にあたる企業の持つ生産設備や労働力によって生み出す潜在GDPとの差で、これがマイナスになっていると述べているのです。
日本の需給ギャップについては、2008年10月から12月はマイナス4.1%であると内閣府が発表し、金額では20兆円とみています。また、2009年1月から3月期ではマイナス6.9%、金額は36兆円(三菱UFJ証券景気循環研究所)と試算し、BNPパリバ証券は2010年にはマイナス10.3%となり、年間でほぼ50兆円の需要不足が続くとみています。
同様の見解は野口悠紀雄氏(早稲田大学教授)も同じで、「輸出の減少だけでもGDPの5%に相当する25兆円、設備投資も考慮に入れれば、GDP 10%分の50兆円が、有効需要の落ち込みとして、日本経済を襲う」と予測しています。
ソウルでの話題
硬い内容が続きましたので、話題を変えてソウルで聞いたことをいくつかお伝えします。
●韓国では3月危機説が盛んにいわれている。韓国の金利が約4%程度であるのに対し、日本の金利はゼロ%。そこで日本から金を借りて不動産投資した人が多い。ところが、ウォン為替レートの急落により、円が実質的に高くなって、その決済が3月に集中している状況から危機が来るだろうと。これだけ為替が急落するとは予想を超えていたのである。
●韓国では若者の失業率が非常に高い。そこで言われているジョークが「38歳までは安心して働きなさい。45歳は定年の年だ。56歳まで働くのは泥棒だ」。意味は、若い人の仕事が少ないので、働いている年寄りは若者に譲れということ。
●韓国も少子化である。それも儒教の影響か男の子を欲しがる傾向で、女の子の出生が少ない。学校のクラスでも明らかに女子がすくない。結果として男性があまっていて、結婚相手として外国人が増えている。ベトナム、フィリピンなどだが、子供が小学校の先生から「成績が悪いと外国人のお嫁さんしかいない」といわれ、家に帰ってきて「僕は外国人のお嫁さんは嫌だから一生懸命勉強する」と発言したという。真面目な話である。
●今、ソウルで流行っているジョークがある。韓国では子供を留学させることが多く、その場合母親が留学先について行くことが多く、残った父親は1年に一回子供に会いに行くが、これを「雁の親」という。しかし、今は不景気で「ペンギン親」となってしまった。1年に一回も会えない。飛べないという意味である。
●韓国の教育熱は世界一といわれている。そこで有名塾が位置している所が、地価が高いことになる。争って有名塾のある地区に引っ越すからである。
●韓国では最高額紙幣となる5万ウォン札が6月に発行される。今の最高額紙幣の1万ウォン札は発行から36年。物価上昇で財布がかさばるなど不便が指摘されていた。5万ウォン札の図案が公開された。表の肖像には詩や絵画など幅広い才能を発揮した朝鮮時代の女性芸術家、申師任堂(シンサイムダン)が描かれている。
ただし、同時に発行が予定された10万ウォン札は、図案に使う古地図に日本と領有権を争う竹島(韓国名・独島)が韓国になっていないので中止が決まった。
政府は「高額紙幣が物価上昇を招く懸念がある」などと説明しているが、領土問題が真の原因との見方が根強い。
何も考えられない
ソウルでガイドしてくれた50歳の女性。子供は長女が高校3年、長男が中学三年の二人。教育費として月に15万ウォン、今のレートで10万円だが、去年のレートでは15万円だから大変で、今は長女が大学に入って卒業し就職、長男が大学に入るまでの5年間、子供のことだけで頭がいっぱい、自分の未来など一切考えられない、と眉間にしわを寄せて真剣に何回もいいました。
黙って聞いていましたが、世界経済と同じではないかと心の中で思いました。
日米欧に新興国を加えた20カ国・地域(G20)財務相・中央銀行総裁会議が、3月13日・14日にロンドン近郊で開催されましたが、金融危機後の世界経済のあるべき姿を論議し、そのシナリオの延長戦として、世界経済を上向かせる「はずみ」処方箋を考えるのではなく、決議されたのは「非伝統的な手法を含む、あらゆる金融政策を活用する」でした。とにかく今の実体経済の悪化を止めることしか頭にないようです。アメリカ経済の原動力であり大問題の「過剰消費」を疑問視する本質的な議論はなかったのでしょう。
苦しい時ほど未来への「はずみ」を考える
苦しい時に苦しいと思うのは当たり前です。しかし、苦しいからこそ、その中で未来への「はずみ」処方箋を見つけだし、そこへ向かって明るい展望を持ちつつ、現実の苦しさの中で対応していく。このアドバイスにガイドは頷きました。世界経済も同じです。以上。
【4月のプログラム】
4月10日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
4月17日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
4月20日(月) 経営ゼミナール例会 「増富の湯」日帰り現場見学
【ジョン万次郎のご子孫を招いての特別講演会】
★ジョン万次郎講演会★ 4月15日(水)18:30 上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 20:28 | コメント (0)
2009年03月05日
2009年3月5日 お得感ネットワーク
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年3月5日 お得感ネットワーク
韓国・釜山
韓国の釜山に行きました。成田から金海国際空港に降り、タクシーでホテルに行こうと乗り場に行くと、黒塗りと青プレートの二種類の車があります。黒塗りは模範タクシー、青プレートは一般タクシー、しつこく呼びかける一般を避けて模範に乗り、市内まで約15km、中心地のホテルについて支払った金額は22,500ウォン。
空港で一万円両替したら152,000ウォンでしたから、1ウォン=0.0658円になります。従ってタクシーの22,500ウォンは1,480円です。
約15km走ってこのタクシー料金、ずいぶん安いと思いますし、得したと感じます。これは食事でも同じです。釜山を中心にした南部でしか味わえない珍味の「テジクッパプ」、豚骨スープに大ぶりの豚肉がいっぱい入って、スープは塩味がなく、塩や唐辛子ベースの薬味であるタデキなどを使い自分で調味するものです。さらに、いくつかの小皿に青い大きい唐辛子と生のニンニクが10個、それと白菜キムチや野菜もついてくるのにはびっくりしますが、市内繁華街西面ソミョンのテジクッパプ通り名物だけのことはあります。
食べ終わるとお腹がいっぱいで、支払はいくらかと聞くと4,500ウォンですから約300円です。小皿がたくさん出て、コース料理という感じでずいぶんお得感が残ります。
デパートで
テジクッパプ通りを出て、近くのロッテデパートに入り、8階の免税売店までエスカレーターで上がっていくと、妙な感覚になってきました。乗っている人が皆右左関係なく、バラバラに立っているのです。東京では左側に乗り、大阪では右側に寄って、反対側を急ぐ人用に空けていますが、釜山は関係ないようです。
どうしてなのか。地元の人に聞いてみますと、以前に一度、片側乗りを奨励したことがあったが、一方に重量が偏りすぎ、エスカレーターが壊れることが頻発したので、今は自由にしているというのですが、ちょっと信じられない理由です。だが、実際に釜山では、スーパーでもどこでも、エスカレーターで前の人を追い抜くことは難しい状態です。
エスカレーター終点8階の免税売店では、7階までの商品を安く売っています。ここで買うと、商品を韓国から出国する際の空港または港で受け取るシステムとなっていて、円安で日本旅行が盛んであった少し前は、韓国人で8階はあふれていましたが、今は客が日本人しかいません。
日本人観光客によって、韓国旅行業界は休日返上という空前の活況、毎日、日本人観光客のみ対応しているのです。結果は、ソウルのシティホテル予約がうまっており、ソウルからあふれた日本人が釜山に来るので、釜山のホテルも満杯です。
BB化粧品
8階の免税売店の中は、世界の著名ブランドショップが華やかに並んでいますが、そこには誰も客がいません。その中、客が異常に群がっているところがありました。それはメイドイン・コリアのコーナーです。それもBB化粧品が置いてある一角だけが、異様な熱気にあふれています。勿論、若い女性が多いのですが、男性も結構います。
一人の男性に聞いてみました「このBB化粧品はどうしてこんなに人気なのですか」「Ikko(いっこー)さんが推奨しているからですよ」「へえー。Ikkoさんて誰ですか」「知らないのですか。あのテレビによく出るヘアーメイクアップアーチストですよ」「お土産に奥さんに買って帰れば喜ばれますよ」そういえば、Ikkoがお勧めしますと書いて、一人のあまり美人とは思えない女性らしき人物のパネルがあります。
IKKOとは本名豊田一幸、名前の音読みに由来するらしく、美容師を経て、女性誌の表紙・ファッションページや、テレビ・CM・舞台と、最近では数多くのバラエティに出演し、トークショー等でも活躍していますが、このIkkoが勧めるBB化粧品とは何か。韓国の新聞・統一日報(2008年9月17日)で以下のように紹介されています。
「BBクリームとは、『Blemish Balm』クリームの略で、Blemishはキズ、Balmは香油といった意味を持つ。1980年にドイツで開発され、韓国では90年代から高級エステ店を中心に使われはじめた。韓日両国でBBクリームのトップシェアを誇る「ハンスキン」は06年、韓国の漢方で使われる14種類の薬草を混ぜたBBクリームを一般向けに韓国で販売しはじめた。
日本のテレビ番組でBBクリームが紹介され、ソウル市内の販売店に日本からの観光客が殺到。売り切れが相次いだ。美容液からファンデーションまでがBBクリーム1本ですむという便利さが好評を得たからだ」
内需拡大しかない
日本では、ここずっとモノが売れないという時代が続き、流通業はどこでも苦戦しています。その理由として、経済状態が良くないからだという見解は正しいのですが、中には絶好調の業態もあります。
先月もお伝えしましたが東京ディズニーリゾートには過去最高の入場者が訪れているのです。また、マクドナルドの好調、ユニクロの店頭が好調、まだまだたくさん事例はあります。これらをどのように考えたらよいのでしょうか。
金融危機で外需が激減したわけですから「内需拡大」が日本経済にとって大事なことは誰もが承知しています。今はデフレ経済下ですから、人はモノを慌てて買いません。インフレ経済下では、明日の価格が上がると予想しますから商品を早く買います。
しかし、今はその反対で家計は「予算制約」された財布となっているので、拡大消費に結びつかないのです。ですから、消費を伸ばすためには、人々の財布の中に、具体的にお金を振り込んでやらなければ増えません。
実は、この財布の役割を果たしているのが、米国では、「クレジット・カード」であり、「自動車や自宅担保のノンリコース・ローン」であり、日本では女性の大好きな「ポイントカード」や「クーポン券」JALの「マイレージ」などです。自分の感覚でも「マイレージ」がたまれば、これを利用しようという気になります。
この意図から計画された国の政策が、ようやく国会を通ることになった定額給付金でして、予算制約された家計財布の中に、国から2~3万円のお金を振り込んであげて、ちょっといい気持ちにさせ、これを機会に使ってもらって、その後の消費にも結び付けようというのが目的です。
これについては、いろいろ議論はありましたが、決まったものですから、この定額給付金をどのように活用するか、という視点で流通業界は検討したほうが良いと思います。
例えば、市町村と連携して、この定額給付金に該当する温泉一泊券などをつくり、それを利用してくれたらこのようなサービスをするなどの、前向き対策を考えたほうがよろしいと思います。
流通業界が、定額給付金は僅かで、大きな効果がないと考え、手を打たないままで過ごすのか。それとも、考え方を変え、これをきっかけに新しいワクワクするコトに結び付けようとするか。その思考差は今後に大きく影響していくと思います。
時代は変わった
どうしてモノが売れなくなったのか。これを論じだすと大論文になります。しかし、感覚的にいえば、時代の流れが「モノ」から「情報」に変わって、次のところ、それは「感覚のネットワーク」に向かって動いているような気がしています。
例えば、釜山のホテルロビーに溢れている日本人観光客、円高ウォン安という事実情報をきっかけに、韓国に旅行しようと思ったのでしょうが、それは来てみてお金を使ってみて、「お得感」を実感できた人の体験が、人々へ口コミネットワークとなって、共通感覚となり、それなら自分も、という気になって、韓国行きになったのだと思います。
また、ユニクロのアイテム、買った人が「この価格で、この品質」というお得感であることはよく知られています。BB化粧品もIkkoが推奨したこともありますが、買って使った人の間に「なかなか良い。なるほど、これはお買い得だ」という「お得感」情報がネットワーク化され、それによって次から次へと買いに訪れているのではないでしょうか。
時代は動き、常に変わり、事象として眼前を流れて行きます。今はデフレ経済下、人々の気持ちの中へ「お得感」ネットワーク化を作りだせるか。それが課題と思います。以上。
■今月の時流解説 3月13日(金)16時~18時
(株)東邦地形社 8階会議室
渋谷教育学園・渋谷中学高等学校正門前 TEL:03-3400-1486
参加費1,000円
投稿者 lefthand : 20:28 | コメント (0)
2009年02月20日
2009年2月20日 身の廻りから見立てれば
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年2月20日 身の廻りから見立てれば
新幹線
このところ東京駅から新幹線での出張が多く、改めて、新幹線ホームに立って時刻表を眺め、発車本数を数えてみて驚嘆しました。
一時間に13本の新幹線が東京駅を出発しているのです。ということは、4分36秒ごとの発車であり、その列車が時速300キロに迫るスピードなのですから凄いと思います。
しかし、もっと評価されていることがあります。日本人にとっては当たり前の、普通のことと認識されているものですが、外国人からみたら驚異なことです。
そのことを、ワシントンのアース・ポリシー研究所長のレスター・ブラウン氏が次のように語っています。(日経新聞 2009年2月18日)
「何十億人もの乗客を運んでいるのに、死亡事故はゼロ。平均の遅れは六秒」、さらに「現代の世界の七不思議を選ぶなら、日本の高速鉄道網は確実に入る」と断言しています。
ネットワーク鉄道網
日本には、外国人が知ったらまだまだ驚嘆する交通システムが存在します。それは日本のネットワーク鉄道網です。
例えば、新宿駅ですが、JR山手線、埼京線、中央線と、京王電鉄の京王本線、小田急本線、さらに、地下鉄の丸ノ内線、都営地下鉄の新宿線と大江戸線、お互い別会社経営ですが、これらが、たった一枚のスイカですいすいと改札を通過できます。このような構内集中効率は東京駅でも、渋谷駅でも、池袋駅でも同様です。
さらに、東京駅では東海道新幹線から、すぐに東北新幹線に乗り換えられるように、東京駅は総合通過駅機能となっていますから大変便利です。
では、世界先進諸国の大都市はどうでしょうか。一言で表現すればターミナル駅です。ターミナルTerminalとは末端という意味で、鉄道やバスの終点のことです。
ニューヨークを事例にとれば、ここには大きい鉄道駅が二つあります。一つはグランドセントラル駅、もうひとつはペンシルバニア駅で、両方とも巨大な建築物で外観も内部も素晴らしい装飾ですが、この二大駅は終点で、お互いつながりが非常に悪いのです。
地上を歩けば10分もかからない距離ですが、地下鉄を利用するとグランドセントラル駅からタイムズスクウエアに行き、そこで乗り換えてペンシルバニア駅に向かうことになります。これだとよほどうまい乗り換えができない限り10分以上かかります。
これは、パリでもロンドンでもミラノでも同様で、ターミナル駅ごとに各方面の鉄道が分断されていますから、異なる方面に向かう駅に行くには一苦労です。
欧米人は、日本の便利な鉄道実態を知らないので、不便さが鉄道の当たり前の状態と思っており、逆に、日本人は、世界で最も機能的で便利な状態を当然と思っていますが、日本は世界で最も効率面で優れているのです。
戦後最大の経済危機
内閣府が16日発表した2008年10月~12月期のGDP速報値は、実質で前期比3.3%減、年率換算で12.7%となりました。
与謝野財務・金融・経済財政相は「戦後最大の経済危機だ」と述べ、政府・与党は追加経済対策を急ぐことを表明しました。
このような落ち込みの要因は、輸出に依存する割合が大きく、輸出産業を中心に生産や設備投資が異例の高速調整に入ったことが、マイナス成長につながったと解説されています。そのとおりで輸出は前期比13.9%減、設備投資は5.3%減となっています。
これについて野口悠紀雄氏(早稲田大教授)が文芸春秋三月号で次のように述べました。
「GDPがマイナス10%に達する、とはどういうことなのか。分かりやすく言えば、経済の水準が6年前、バブル崩壊後日本の景気がどん底を示した2002年~2003年の状態に戻る、ということだ。2002年に底を打ってから、日本の実質GDPは6年間で10%増加した。ちょうどその上昇分が消失するのである」と。成程と思います。
個人消費を見てみると
次に、10月から12月期のGDP速報値の個人消費を見てみますと、前期比で0.4%の減となっています。この前期比という分析基準は2008年7月~9月期との対比ですので、これを前年同期(2007年10月~12月期)比に置き換えて計算してみます。
結果は同様で、やはり輸出が12.8%減、設備投資は11.1%減と大きい実態ですが、個人消費は0.1%減という数字でマイナス幅はぐっと少なくなっています。
また、この個人消費がGDP全体に占める割合を見ますと、2007年は54.5%、2008年は57.0%となっていて、2.5%ウエイトを高めています。
何を言いたいのか。それは個人消費が善戦しているということです。世界は金融危機で世界中の消費が激減し、それによって日本の輸出産業は二ケタ減という大打撃の反面、内需は輸出減にそれほど影響を受けず、ほぼ前年通りの実績を示しているということです。
さらに、民間住宅投資は前期比5.7%増、前年比では何と12.7%という二桁増加に転じています。
確かに野口教授の解説通り、日本の実質GDPは過去6年間、外国で稼ぎ増やした輸出によって10%増加させ、これから、その外国で増やした分を減らしていくのでしょうが、GDPの中で一番大きく占める国内個人消費はあまり減っていないのですから、外需大幅減、内需健闘というのが日本経済の実態と思います。
身の廻りに目を注いでみると
輸出減で企業の出張が少なくなり、その分交通機関の利用が減っていると思われますが、よく行く東京駅や渋谷駅、日本の鉄道駅は景観的には雑然として、見栄えは悪いのですが、人が動き回る機能としては大変効率がよくできていて、そこを動く人波や人の量は大きく変わっていないように見えます。
今年の正月5日は東京ディズニーリゾートに行きました。ここを経営するオリエンタルランドの今期利益は前年比41%増と発表しました。金融危機で「戦後最大の経済危機」だと大臣発言がありましたが、ディズニーリゾートには過去最高の入場者が訪れているのです。これをどのように考えたらよいのでしょうか。
昨日は駅近くの理髪店に行きました。老夫婦と従業員一人の規模です。ここが改装して一週間休んでいたので、どのような店になったのか興味持って入りました。ずいぶんすっきりして上品な雰囲気になっていました。よかったねと言いながら「景気はどうですか」と尋ねますと「ほぼ同じです。戦後最大の経済危機とは思えない」とつぶやきます。お互い戦後の苦しい生活体験を持っていますから、当時を思い出せば今は天国です。
もうひとつ、身近な事例が続き恐縮ですが、毎月一回料理教室に通っています。もうずいぶん長く、教室の中で古手株となっています。最初の頃、いつ行っても教室は参加者10人を超えることはありませんでした。一時は5~6人で寂しい思いをしていました。
ところが、昨年春ごろからじわじわと参加者が増えだして、2月の教室はとうとう定員25名に達してしまい、お断りする人もいたらしいのです。
理由はよく分かりません。ずっと同じ先生で、同じような料理で、同じシステムで続けているだけで、教えてくれている先生もびっくりし、運営する中堅スーパーの担当者も首を傾げていますが、とにかく満員となり、教室内は明るい活発な会話で溢れていて、帰りには「また、来月」と言って別れます。
内需は底固い
日本経済は、野口教授の解説通り、過去6年間成長したGDP10%を、これから減少させていく、つまり、それは、外需で増やしたものが消えていくのだと推断します。
一方、これだけ世界中で金融危機による経済停滞が声高に叫ばれているのに、内閣府GDP速報値の個人消費を分析してみれば、個人消費は僅かな減少で終わっている、つまり、それは、国内内需がいかに底固いのか、ということを証明しているように思います。
さらに、トヨタ自動車も、在庫調整が今期末でほぼ終わり、5月から増産に入ると発表しましたので、いずれ周辺産業にも好影響が表れていくでしょう。
様々なマスコミ報道が、日々多様になされていきます。マクロ情報に関心を持ちつつも、自分の身の回りの実態から見立てることが、精神健康上、今は最も大事と思います。以上。
【3月のプログラム】
3月13日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
3月13日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
3月16日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
3月18日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
【ジョン万次郎のご子孫を招いての特別講演会】
★ジョン万次郎講演会★ 4月15日(水)18:30 上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 07:25 | コメント (0)
2009年02月06日
2009年2月5日 日本経済新聞を読みたくない
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年2月5日 日本経済新聞を読みたくない
ある大学で
昨年末から日本経済は急激に悪化しています。一月はこの関係で、金融危機絡みの講演をする機会が多くなりました。先日も都内のある大学の経営学部が開催している勉強会でお話ししました。当然、世界経済と日本経済の実情について触れることになり、その結果は、厳しい数字が並ぶ内容となりました。
勿論、中には明るい企業もあるわけで、すべての企業と人々が経済困難化しているわけではありませんが、トータルで判断すれば、世界も日本も日を追うごとに経済実体は悪くなっています。この事実を日本経済新聞が報道し、多くの人はこれを読み、また、この情報を分析しお伝えしますから、経済危機に対する見解は、勉強会参加一同が一致します。
講演が終わり、休憩時間になったとき、一人のまだ若き女性経営者が走ってきて「もう日経新聞はみたくない」と叫ぶように言いました。経済悪化数字が並ぶ報道は読みたくないというのです。そこまで人の気持ちは追い込まれているのかと、改めて驚きました。
経営者は日本が世界で最も悲観的
世界の中堅企業で「2009年の景気動向を最も悲観しているのは日本の経営者だ」という調査結果が発表されました。
調査したのは、国際会計事務所グループのグラント・ソントンです。世界36カ国の中堅企業、日本の場合は従業員が100人から750人の非上場企業ですが、これらの経営者を対象に昨年10月、11月に7,200人(日本は300人)に行った調査です。
調査方法は、景況感を良いと答えた人の割合から、悪いと答えた人の割合を引いたDI数値で各国を比較したものです。
日本の経営者の回答結果は、DI数値で-(マイナス)85、日本の次はタイの-63、フランスの-60でした。逆に高かったのはインドの+83、ブラジルの+50です。
日本の回答結果に対し「危機意識が強く、先行きを厳しく考える傾向があるためではないか」と、調査機関関係者がコメントしていますが、そのとおりと思います。
どうしてブラジル経営者はプラス思考か
ブラジルのルラ大統領への国民支持率は84%と、過去最高になったという世論調査結果が報道されました。(2009.2.5日経新聞) 同大統領が就任した直後の03年支持率83.6%を上回ったのです。日本の麻生首相と全く異なる実態ですが、これがブラジルの今を示していると思います。
ご存じのとおり、ブラジルは1970年代後半に経済が低迷し、同時に深刻な高インフレに悩まされ、80年代にかけてクライスラーや石川島播磨(現・IHI)など多数の外国企業が引き上げ、先進国からの負債も増大する苦しい経済状況でした。
しかし、03年にルラ大統領が「飢餓ゼロ」計画を打ち上げ当選し、貧困家庭向けの食料援助や援助金制度などを推進した結果、貧困家庭の生活水準改善が着実に進み、加えて、経済発展に取り残された内陸部へのインフラ整備も進め、06年に貧困層の圧倒的な支持を得て再選されました。
今回、ルラ大統領が過去最高の国民支持率となった理由を、金融危機でも「ブラジルでは生活実感が極端に悪化していないことが、高支持率の背景である」(日経記事)と分析していますが、実はもうひとつ大事な要素があります。
それはブラジル人の国民性です。ブラジルは人種が世界で最も混淆している国で、ポルトガル人とインディオの接点に黒人が加わり、さらに、東洋系のモンゴロイドを含めたあらゆる人種間の融合によって形成された結果「明るい・くよくよしない」国民性であることはよく知られています。07年10月に訪れたサンパウロで「ブラジル人に躁はいても、鬱はいない」と現地の方が断言しましたが、この国民性が、世界の経営者景況感調査結果+50となった本当の理由と思います。日本人とは反対側に属する国民性です。
日本の実質GDP
下図は日本の実質GDP成長率(前年対比)の推移です。2008年に急減しました。
視点を変えて、2008年日本の実質GDPを月別前月比で見てみますと、08年11月は-2.3%、12月も-2.5%と大きくマイナスとなり、10月の-0.3%、9月の-0.5%に対し急激に悪化しています。この要因は輸出が11月-18.8%、12月-9.2%に落ち込んだことと設備投資の不振です。昨年末から急速に実体経済が悪化していることがこれでも証明されます。(日本経済センターデータ)
次に、四半期ごとの実質GDPを前年同期比で見てみても、08年1月~3月期が+1.4%、4月~6月期も+0.7%であったものが、7月~9月期では-0.5%、10月~12月期は-3.4%ですから経済急悪化は事実です。(日本総合研究所データ)
日本の個人消費
ところが、個人消費の前年同期比を見てみますと、違った姿が浮かんできます。
08年1月~3月期が+1.6%、4月~6月期+0.3%、7月~9月期+0.5%、10月~12月期+0.2%と、個人消費は未だにマイナスになっていないのです。善戦していることが明らかです。(日本総合研究所データ)
確かに日本経済は大きく悪化した結果、企業の生産動向は激しく落ち込み、全体がマイナス成長となりましたが、比較して個人消費は日用品などが中心ですから、安定需要がある分だけ振れ幅を比べると少ないのです。そのことを個人消費データが証明しています。
「もう日経新聞はみたくない」と叫んだ女性経営者の生産活動は停滞したと思いますが、多分、ご本人の日用品などの買い物は、それほど減らしていないのではないでしょうか。
ドイツ人経営者から
DHLジャパン社長のギュンタ・ツォーン氏が次のように述べています。
「日本は他国より痛みが少なく、この不況からいち早く抜け出せると思っている。それは、日本の国内経済規模が巨大で、個人消費がGDPの成長に寄与しており、私の母国ドイツに比べると輸出に頼りきりでない。(輸出対GDP日本15%、ドイツ39% 前図)
さらに、日本はGDPのより多くを研究開発に投資し続けている。(日本がGDP比3%強に対してドイツは2%台)また、日本には全体の福祉を維持しようという価値観もある。よほど深刻な状況に陥ったとき以外は、短期的な利益を優先して将来の可能性をつぶすような形での研究費や人件費を削ることはないだろう。
もっとも日本が今後、他国と同様、困難な道をいっとき歩まなくてはならないことも確かだ。ただ、チャンスと捉えることで、1~2年のうちに日本は危機を乗り越えると確信している」(2009.1.27 日経新聞) ドイツ人の方が日本を客観視しているのです。
今こそ明るく
約6年間続いた「実感なき好景気」を「根拠なく楽観視」した人々が、今度は「根拠なき悲観」から「恐怖心理ショック不況」に入り込んでいるのではないでしょうか。以上。
投稿者 lefthand : 09:48 | コメント (0)
2009年01月21日
2009年1月20日 オバマ米大統領への打つ手
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年1月20日 オバマ米大統領への打つ手
オバマ米大統領就任
バラク・オバマ第44代米大統領が、20日、約200万人の大観衆が見守るなか、宣誓を行い就任し、次の演説をしました。
「われわれは危機のさなかにある。米国は、暴力と憎悪の根深いネットワークに対する戦争を遂行中だ。また、一部の者の欲望と無責任さの結果であると同時に、われわれ全体が厳しい決断を下し、国家を新たな時代に備えることに失敗したことにより、経済は激しく弱化している。さらには、米国も衰退は不可避であり、次の世代は視点を下げねばならないという、自信喪失もみられる。
私は本日、こういった挑戦は現実であり、簡単に短期間で解決できるものではないと言いたい。しかし、アメリカよ、これを知って欲しい。これらの問題に応えられるのだ」
オバマ大統領に期待する声
英BBC放送と読売新聞社が実施した「オバマ新政権で米国の対外関係はどうなるか」の、1万7,356人調査をご紹介します。
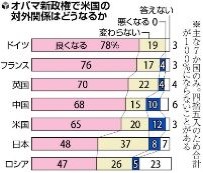
「『良くなる』と見ている人は、すべての国で多数を占めた。オバマ氏が、ブッシュ政権時代の『一国主義』から『多国間協調』への転換を掲げていることが、関係改善への期待感につながっているようだ。『良くなる』との答えは日本では48%で17か国中2番目に低く、『変わらない』37%は最高だった。『良くなる』はドイツ78%、フランス76%など、ブッシュ政権下でのイラク戦争への対応で、対米関係がぎくしゃくした欧州諸国で高かった」 (読売新聞2009.1.20)
各国の回答結果は困窮度を示す
欧州三国が調査結果の上位を占めました。これをどう理解するか。どうもこの結果は、米国発金融危機の影響で困窮度が強い国、つまり、米国より困っている国が、より多くオバマ新政権に期待しているのではないかと推測いたします。
それを証明するのが、1月19日に発表された英国大手銀行「ロイアル・バンク・オブ・スコットランド(RBS)」の損失です。2008年通期の最終赤字が280億ポンド(約3兆7,000億円)で過去最大となりました。
常識的には、米ウォール街が最も影響を受けたと考えますが、実は違うのです。ニューヨークの世界最大級銀行シティグループは、2008年通期で187億ドル(約1兆7,000億円)の赤字ですから、RBSはシティを2兆円も上回る損失です。多分、銀行では世界一の赤字でしょう。
これを受け、英国のブラウン首相が「米サブプライム関連商品の約半分は欧州の金融機関が抱える」と発言しましたが、この背景には「米景気の悪化が欧州銀行の不良債権の増加に直結する」という意味が入っています。
つまり、自国では解決しようにもできない他国の景気悪化により、自国の銀行が損失を増やし、金融が傷つく結果、国家が銀行に公的資金を投入せざるを得なくなり、それが国債の増発につながっていくのですから大変で、この困窮度の強い国順に、上図が並んでいると理解しています。
どうして米国発なのに欧州の困窮度が高いのか
その最大理由は、金融危機の発端となった「新種の金融商品」が、欧州金融業界が開発したものではない、つまり、米国から「新種の金融商品」を輸入し、それを国内の投資家・金融機関に販売したことにあります。
という意味は、米国でサブプライムローンが問題だという兆しが表れた時に、素早い初動動作をとれず、米国での換金処分の動きにも遅れ、気づいて慌てて換金処分をしようとした時には、すでに広く「破綻リスク」が広がっていたので、誰も引き受け手はいなく、結果として所有したままとなっているのです。
ですから、この「新種の金融商品」が時間の経過とともに、評価がさらに下がる場合、英国銀行RBSがその事例ですが、評価損を計上し損失となり、資本不足になりますから、国家からの金融支援が必要となってしまうのです。
また、仮に「新種の金融商品」を満期まで保有したとしても、元本保証は難しい上に、価値がゼロという事態も予測されるという、厳しい困窮実態になっているのです。
アメリカ人はあまり感じていない
このことを示しているのは、英BBC放送と読売新聞社調査で「金融危機にオバマ新大統領がどう対応すべきか」を聞いたところ、17か国すべてで「最優先で取り組むべきだ」との意見が大多数でしたが、国別では中国が最高の93%に達し、日本は77%であるのに対し、米国は75%という回答結果なのです。
つまり、米国は金融危機の発端国ではあるが、他国よりは問題意識が低いということで、これは一見奇妙な現象と思えますが、現実の国別困窮度から考えれば頷けるのです。
日本のバブルとの違い
次に、もうひとつ考えてみたいことがあります。それは日本のバブルとの違いです。今回の米国サブプライムローンから発した金融危機は、あっという間に世界中に同時経済停滞という事態を招きました。
一方、日本のバブルは、その絶頂期でも世界に波及しませんでした。同じく不動産から発したバブルでありながら、米国は世界中へ、日本は国内だけにとどまりました。
この理由としてあげられるのは、日本は不動産という実物バブルだったのに対し、米国は住宅という不動産ではあるものの、それを証券化した、つまり、お金化したことです。
実物の不動産は国から国へ移動できません。現在地を変化させられません。しかし、その不動産の価値を証券化し、それを細分化し、株式のように売りやすくしてしまえば、それは実物のモノではあるが、新型の流通する証券・お金として回流させられるのです。
お金はモノより「はやい」
これにウォール街が考えつきました。実物の不動産を流通化させるためには証券化することだ、そうすればお金の流通と同じになると気づき、そこに金融工学とIT技術を加えて仕組みを構築したのです。つまり、証券化というお金にすれば、実物の移動とは比較にならないスピードで動く、お金の「はやさ」を活用したのです。
また、そのお金も米国人のお金だけではなく、外国からお金を取り込むというシステムをつくり、その米国に入ってきたお金をさらに他国に投資するという仕組みにしたこと、これが米国金融帝国化といわれる所以です。
この仕組みづくりには、お金の動きはモノとは比較にならない「はやさ」がある、ということをつかむことが重要です。このお金の「はやさ」を分からないと、今回の金融危機の背景はなかなか理解できないと思います。なお、日本人はモノづくりに優れている反面、お金の「はやさ」ということへの理解が一般的に薄いのが特徴です。
オバマ新大統領打つ手はお金の「はやさ」
オバマ新大統領が打つであろう、金融危機経済問題対策は大規模な公共事業です。この投資配分が適切であればあるほど、お金という特徴の「はやさ」が効いてくるはずで、その結果、米国経済の意外に「はやい」立ち直りを期待したい気持ちでいっぱいです。以上。
(2月のプログラム)
2月13日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
2月13日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
2月16日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
2月18日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 20:29 | コメント (0)
2009年01月06日
2009年1月5日 基本を踏み条件変化に対応する
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2009年1月5日 基本を踏み条件変化に対応する
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
オールドマンパー
球聖と言われたボビー・ジョーンズ(Bobby Jones 1902-71)が語っています。
「ゴルフは、誰かに対してプレーするものではなく、何かに対してするものであるということに気づかなかったら、わたしはメジャー選手権に勝つことなどなかったろう。そう言っても決して間違いではないと思う。何かというのはパーのことだが・・・」
さらに続けて「そのことを学ぶまでには長い時間がかかって、ずいぶん悩んだものだ」と語り、目の前の対戦相手に惑わされずに冷静にプレーするために、OLD MAN PARオールドマンパーおじさんという架空の人物を考え、ゴルフは誰かに勝つためのスポーツではなく「各ホールのパー」言い換えれば自分自身との闘いであると定義しました。
トヨタが赤字決算見込みに
トヨタ自動車は昨年12月22日に連結決算見込みを発表し、売上21兆5,000億円の企業グループであるにもかかわらず、営業利益では1,500億円の赤字見込みとしました。最終的な純利益は500億円の黒字ですが、世界を代表する超優良企業のトヨタ自動車が、営業利益段階で赤字に没落したショックが世界中を走りました。
赤字要因の7割が売上減による影響で、残りが為替変動の要因であると明快ですが、今回の金融危機問題の重大さを再認識させ、世界経済への危惧をさらに深めさせました。
年末から正月の経済報道
これを追いかけるように、暮れから正月の経済関係報道は、懸念一色です。
「日本経済は08年、ほぼ6年ぶりの景気後退に陥り、経済規模が縮小した。年前半は原油高の重圧にあえぎ、後半は米国発の金融危機に伴う実体経済の悪化が深刻さを増した」(日経新聞08.12.30)
「金融危機の影響で、外資による国内企業買収や日本法人の設立といった対日直接投資に急ブレーキがかかっている。2008年4月〜10月の直接投資額は前年同期に比べ約4割減少し、08年度は03年度以来5年ぶりに前年実績を下回る見通しとなった。資金面での余力が急減し、リスク低減を迫られる海外勢が、自国を中心に内向きの投資に傾いているのが背景。今後は事業撤退や出資引き揚げも増えそうで、資本流入の縮小は雇用など実体経済の悪化に拍車をかける恐れがある」(日経新聞08.12.30)
テレビニュースでは、派遣契約の打ち切りなどで仕事や住居を失い、東京・日比谷公園の「年越し派遣村」に支援を求めて集まった人たちに対し、公園に近い厚生労働省庁舎内の講堂を宿泊用に開放し、そこに入った人々が「数日間何も食べていない」「昨日は野宿した。寒くて寝られなかった」などと語り、配給された温かいうどんを食べている風景が映され、国内経済に一層の憂慮感をもたらしました。
アメリカは対応策に困っている
どうしてこのような経済状況に変化したのか。それはアメリカ発の金融危機問題によって起こったことで、これはすべての人が理解しています。
ですから、アメリカから世界に向かって何か「お詫び」と言えるような、メッセージがあってもよいだろうと思いますが、これまで明確な言動がなされた気配はありません。
昨年12月18日に「米新政権と日米同盟の課題」シンポジウムが開催され出席しました。ハーバード大教授ジョセフ・ナイ氏、元米大統領補佐官マイケル・グリーン氏など5名のアメリカ政府要人に対し、谷内前外務事務次官と西原前防衛大学校長が質問するスタイルの展開でした。活発な議論がなされ「日米間でハイレベルな戦略対話が必要」「日本が国際社会に強力な影響力をもつことが重要だ」というような提案がなされましたが、ここで不思議に感じたことは経済問題について誰も敷衍(ふえん)しなかったことです。
政治問題が討論のメイン課題とはいえ、現在世界中で大問題となり、経済停滞を起こしている要因はアメリカで、そのアメリカ政治に関与している著名要人たちですから、何らかの「背景説明やお詫び」的な発言があると思っていましたが、全くありません。
何故なかったのか。推測すれば、多分、問題要因について責任を感じていないか、または、問題が大きすぎて簡単に解決つかないので触れようがなかった。この二つだと思います。
ユーロは基軸通貨になれるか
元旦にスロバキアがユーロを導入し、これでユーロ圏は16カ国になりました。欧州単一通貨であるユーロは、1999年1月に11カ国からスタートし、その2年後にギリシャが、続いてスロベニア、キプロス、マルタが導入し、今回スロバキアです。
このユーロ、今回の金融危機によって、世界基軸通貨であるドルの信認が問われ、それに代わる通貨として論じられていますが、ユーロ圏の実態はどうなのでしょうか。
結論的には、ユーロは基軸通貨にはなり得ない実態と思います。そのひとつの証明がギリシャの暴動です。ギリシャでは昨年12月6日、15歳の少年が警官に射殺されたことから、全国で暴動が発生し被害が広がっています。この暴動の発生要因について、ギリシャ・アテネ在住の知人に連絡をとり、日本在住ギリシャ人の方に状況をお聞きし、加えて昨年ギリシャを訪問した経験から、次の見解を持つに至りました。
「最初の発端は、若者グループに投石された警官が、少年を撃ち殺したことから始まったのは事実で、これがメールや、口で伝えられ、学生が暴動を起こし、この騒ぎに乗じ、外国人やテロリストや政党関係者などが、商店や車に放火し破壊に加わった。
この背景には経済問題がある。若者は毎年、大学新卒の半数が就職できない厳しさで、アルバイトなどをして生活して『700ユーロ世代』と呼ばれ、月収が700ユーロ(8万5千円)ほどで不満がたまっている。さらに、ユーロ導入とオリンピック開催により、外国人観光客が急増して物価が一気に上がり、期待したオリンピック景気でもギリシャ国内産業が育たず、加えて、ギリシャ特有の官僚主義や汚職によって、外資に対して融通が利かず、手続きが複雑で時間がかかるので、外国企業が入って来にくい」
ユーロ導入以後7年経つギリシャが、このように社会的安定を欠く実態では、米ドルに代わってユーロが世界の基軸通貨になることは難しいのです。ですから、アメリカ自身による金融危機対策を見つめ、その情勢変化に対応することしか方法はありません。
トヨタは生産方式を変えたわけでない
トヨタが営業利益段階で赤字見込みになったことは、社会に大きな影響を与え、これを持っていろいろトヨタを詮索する声も聞かれます。だが、この赤字見込みはトヨタが生産規模を減らしたから発生したのです。では、どうして生産台数を減少させたのか。それは世界中の自動車売上が金融危機で落ちたからであって、当然の決定です。
つまり、市場の実態に合わせたのです。市場に合わせなかったらどうなるでしょうか。在庫の山になるでしょうし、経営は滅茶苦茶になります。ということは、トヨタは市場の条件変化に対応した適切な経営手段を採ったことになり、赤字という結果は市場対応したという証明であって、トヨタ経営の基本である「カンバン方式」などの生産スタイルを変えたわけではありません。ここが大事なポイントです。
ゴルフのパー
我々の生き方も同じだと思います。時代の変化に対応しなければ、適切な生き方はできません。しかし、自らが持っている生き方指針までを変えてはならないと思います。
ゴルフのパーは、雨でも雪でも嵐でも晴天の日でもいつも同じです。ただし、気象条件によって攻め方を変えてプレーをします。
これと同じです。金融危機から発した世界規模の経済低迷事態に、迅速・的確に対応していくことが、企業にも一般の人々にも求められていますが、適切である経営方針や、妥当な生き方指針は変えるべきでない。そのところの区別と整理が大事です。金融危機に翻弄されるのではなく、基本を踏み条件変化に対応することが必要と思います。 以上。
(1月のプログラム)
1月 9日(金)16時 渋谷山本時流塾(会場)東邦地形社ビル会議室
1月14日(水)18時30分 山岡鉄舟研究会(会場)上野・東京文化会館
1月16日(金)14時 温泉フォーラム研究会(会場)上野・東京文化会館
1月19日(月)18時経営ゼミナール例会(会場)皇居和田蔵門前銀行会館
投稿者 lefthand : 14:39 | コメント (0)
2008年12月20日
2008年12月20日 気持を不景気にしない
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年12月20日 気持を不景気にしない
好景気と不景気の区別
知り合いの税理士さんから連絡がきました。
「私は、単純に株や不動産が上がっているときは好景気。下がっているときは不景気だと思っています。汗をかいて稼いだお金は使わないが、株などで臨時の収入があれば、儲けた人は思いきった消費をするからです。アメリカは、株が悪い時は不動産がよいという具合に、過去には必ず株か不動産のどちらかが上がるように政策をしてきました。ところが、今度だけはうまくいかないのです」 簡単明確でよくわかります。
マクロにだまされるな
再び、同じ税理士さんから連絡がありました。
「どんな好景気の時でも精々6~7割の企業だけが好業績で、全てが好景気になるわけでない。一方、不景気でも3~4割の企業は好景気を維持している。その差は3~4割にしか過ぎない。不況業種といわれているところでも、長年の経験でいいますと、実はいい会社が結構あります。自動車・家電メーカーのように、世界的にシェアが高い会社は、好不況の波に左右されますが、中小企業はどうでしょうか?
一般的に好不況の影響があるほどシェアが高くないので、世間の景気と個々の企業業績は、あまり相関関係がないのが事実です」
データで確認してみると
日経新聞の「核心」(2008年12月8日)で、論説委員の平田育夫氏が、今回の金融危機から、アメリカが保護主義政策をとれば世界中が迷惑すると述べ「最も困るのは外需依存度が高い日本」と断定しています。
保護主義に対する見解には同調しますが、ここで問題なのは「外需依存度が高い日本」という判断です。そこで、外需依存度が本当に日本は高いのか、それをデータで確認してみたいと思います。
まず「外需」とは何でしょう。それは海外の需要のことですから、輸出額のことになりますので、外需依存度とはGDPに占める輸出額の比率ということになります。
そこで、日本の「輸出対GDP比率」を調べてみますと、2006年が15%です。2007年で16%です。
次に、2006年の同データによる主要国を見てみますと、アメリカが8%と低い他は、イギリス19%、ドイツは39%、中国と韓国は37%となっています。
日本の外需依存度はアメリカに次ぐ低さなのです。ということは日本を世界の主要国と比較すると外需依存度が高くないのですから、逆に内需依存型国家ということになってしまいます。このところが、昔から内需を増やせと言われ続けている背景なのです。
日経新聞論説委員の断定はおかしいということになります。
非正規社員解雇問題
次に、今問題となっている非正規社員解雇問題です。
これも日経新聞の報道(2008年12月11日・きしむ雇用)をみますと、事例として建設機械大手のコマツをあげています。
今回コマツは、金融危機後の未曽有の世界需要減少に対応するため、1,500人規模の非正規社員を解雇するとのことです。コマツが海外展開を加速し始めた2003年当時、非正規の期間社員はわずか数十人でした。しかし、新興国のインフラ投資需要の波に乗って、08年までの5年間で約2,000人に膨らんだのですが、それを一気に500人程度までに減らすのです。
また、このように世界各地の需要減に対応して、スピード生産調整を始めたのは、トヨタ、ホンダなどの自動車メーカーからで、部品メーカーを含めれば数万人程度の非正規社員が職を失う見通しだと解説しています。
つまり、今大問題となっている非正規社員解雇問題は、輸出産業に属する企業、それは外需依存の高い企業に集中しているのです。
世界的金融危機は外需依存企業を直撃したことが分かります。
いざなみ景気を思い出すと
いざなみ景気とは、2002年2月から2007年10月までの69ヶ月間に見られた好景気(正式名称、詳細な景気拡大時期は未定)のことです。
名称の由来は、古事記に記された「いざなぎ・いざなみ」による国生みの伝説からで、過去の「いざなぎ景気」よりも上回る記録的な好景気によることから、名称化されたのですが、この「いざなみ景気」は一部企業に好景気の恩恵が集中したことと、2%前後の低い経済成長であったため、史上空前の長い好景気期間の割に「豊かさを感じなかった」というのが特徴といわれています。
そのとおりで、景気のよかったのは一部企業で、その企業とは「海外需要で稼いだ」ところなのです。先ほどのコマツの事例でも、非正規社員は海外展開が進むことで、人員を急速に増やしてきており、その増やしたタイミングは「いざなみ景気」に該当しています。
ということは、外需に関係しない国内一般の企業は、内需だけですからもともと好景気とは関係なかったことになります。
つまり、外需で潤った企業は、前述したようにGDPの16%程度であり、これに当てはまらないGDPの84%の需要をあてに経営していた企業は、ずっと「いざなみ景気」の中でも低成長下にいたということになります。
結局、日本経済は外需依存企業と内需依存企業に分かれていて、金融危機が発生するまでは、外需依存企業の好決算によって、日本の経済成長率が支えられていたのですから、百年に一度というべき未曽有の事態になれば、当然に日本全体の経済成長率は「いざなみ景気」以前に戻ります。
いざなみ景気は2002年2月から始まったその前の年、2001年のGDP実質経済成長率はマイナス0.8%でしたから、当然にマイナス成長になると思います。
何ら不思議でも何でもない現象になるだけです。
再び税理士さんから
景気が悪いといわれていますが、夜の忘年会は盛んなようですし、先日、秋葉原のヨドバシカメラに行き、レジの女性に忙しいですか、と聞いてみますと「先ほどまで大変でした。ブラジルから団体客がきて、その人たちが日本の化粧品を大量に買ったので」と教えてくれました。電気関係の店だと思っていましたら、化粧品もお酒も扱っているのです。
そこで、また税理士さんからご連絡が来ましたのでご案内します。
「賢者は歴史に学び、愚者は経験に学ぶという有名な言葉がありますが、普通は歴史にも経験にも学ばないのが人間です。懲りない人々というのでしょうか。また、置かれている状況も過去とは違いますものね。
前のバブル崩壊を経験した大先輩に『当時、どうでしたか?』と聞いたことがあります。その答えは『あの時は飲まず食わずだったからな・・・。今は贅沢だもんね』という答えでした。
ですから、昔に比べれば経済のベースが格段に違います。前向きにいえば、その経済ベース下の不況であるという事実も考えてください」
気持を不景気にさせないこと
勿論、世界経済の後退が長引けば、外需産業から内需産業へと影響が出てきます。当然です。しかし、内需産業企業はもともと長期に低迷していたのですから、苦しさが増えるかもしれませんが、今までの状態がまだまだ続くのだと考えれば、基調は今まで通りです。
そのところを整理し理解しないと、マスコミ報道が伝える外需産業による不景気ブームに左右され、強い危機感を抱き「気持を不景気」させてしまいます。それが大問題なのです。年末から正月は気持ちを「プラス発想」にし、新年度への期待を考える事です。以上。
【1月のプログラム】
1月09日(金)16:00 渋谷山本時流塾/東邦地形社ビル会議室
1月14日(水)18:30 山岡鉄舟研究会/上野・東京文化会館
1月16日(金)14:00 温泉フォーラム研究会/上野・東京文化会館
1月19日(月)18:00 経営ゼミナール例会/皇居和田蔵門前銀行会館
投稿者 lefthand : 20:24 | コメント (0)
2008年12月05日
2008年12月5日 ブレない生き方
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年12月5日 ブレない生き方
麻生首相対小沢代表
11月28日(金)15時、NHKテレビの前に座りました。麻生首相と民主・小沢代表との党首討論です。攻めたのは小沢氏で「二次補正を今の国会に出さないのは国民への背信行為だ」「出さないなら直ちに解散・総選挙で審判を仰げばよい」。対する首相は「政党間協議をお願いしたい」と防戦一方でした。
結果は内閣支持率の急落。日経新聞世論調査によりますと、とうとう31%しか支持がなく、不支持は62%となり、首相にふさわしい人でも、麻生首相は前回調査の36%から17%に急落し、発足二カ月で早くも失速状態に陥ったのです。
その始まりは10月30日に、麻生首相が27兆円規模の追加経済対策を公表した際に「政策を実現して国民の生活不安にこたえることが優先順位の一番だ」と強調し、衆院解散の先送りを表明しましたが、この時は世界金融危機であり、日本経済も深刻な後退局面に入っているので、首相の判断はやむを得ないと受け入れられましたが、その後がいけません。定額給付金あたりから発言がブレ出し、迷走状態となってきて、与党内に「二次補正を今国会に出したら、民主党の攻勢に立ち往生する」という警戒心が生じ、今回の党首討論防戦発言につながったのです。しかし、解散権が封じられた国会運営は難しい、このことは福田政権で証明済みで、麻生首相はブレによって黄色信号となりました。
里見香奈
将棋の女流タイトル「倉敷藤花」を、島根県出雲市に住む高校二年生16歳の里見香奈さんが獲得しました。史上三番目の若さです。
「倉敷藤花」とは倉敷市出身の大山康晴十五世名人の功績をたたえ、平成5年に創設された女流プロ棋士全員参加の、日本将棋連盟女流公式タイトル戦で、「藤花」という名称は、倉敷市の市の花が藤の花であることにちなんで名付けられました。
里見香奈さんの将棋は、鋭い終盤力に定評があり「出雲のイナズマ」との異名を持っていますが、このニューヒロインの誕生について、女流棋士の高橋和さんが里見さんとの出会いを含めて、以下のように論評しています。
「初めて出会ったのは、私が出雲で行われたイベントに参加した時のことだった。大人たちに交じり、可愛らしいおかっぱ頭の女の子がお兄ちゃんに手を引かれ指導対局にやってきた。確か六枚落ちのハンディで対戦したように記憶している。
指導対局の後に行われた立食パーティーの席で『どうやったら強くなれますか?』と聞いてきたので『一日一題でいいから毎日詰め将棋を解いてごらん。そしたらきっと強くなるよ。できるかな?』こう言うと彼女はコクリとうなずいた。
それから数カ月たったある日、将棋連盟宛に一通の手紙が届いた。鉛筆で書かれた差出人の名は里見香奈、彼女だった。『ちゃんとやくそくまもって毎日詰め将棋をといています。大会でゆうしょうもしました』早速彼女に返事を出した。『優勝おめでとう。約束を守ってくれてとってもうれしかったよ』と。その後、彼女は12歳という若さでプロの道へと進んだ。勝負への執念と日々の努力、これは彼女の才能であり、誰でもできるわけでないが、彼女は今でも毎日詰め将棋を解いているという」。誠にブレない実例です。
ユニクロ
このところユニクロだけが業績よく、不景気の11月なのに国内既存店売上高が前年同月比32.2%増には驚きです。衣料品業界は「昨年の冬は大寒波の厳寒で、冬物衣料全般の売上が好調だったが、今年の冬は暖冬で、そのため冬物衣料の売上が不振だ」というのが一般的な業界見解で、百貨店、スーパー、専門店を問わず衣料品の販売不振は深刻になっている中、ひとりユニクロだけが快調なのです。
ユニクロは海外でも好調ですが、ニューヨークで体験したことを報告いたします。
昨年の6月、新規出店したソーホーのユニクロの入り口に立って驚きました。店舗があまりに素晴らしいことと、店内に客が殆どいないことに・・・。
同じ時間帯で比較してみようと、ユニクロから三店離れた50メートル先のH&Mに入ってみますと、客が結構います。H&Mは日本で先般東京・銀座に一号店を出し、長い行列が連日続いて話題となりましたが、世界中の国々に出店して成功しています。
ユニクロはNY初出店に賭け、膨大なお金を投入し宣伝をしました。それも日系媒体関係にはPRせず、アメリカ人向けの媒体に力を入れていたのに、現地人の客が少ない実態を目の前にし、これはユニクロの海外展開は難しいのではと思ったのが昨年でした。
再び、今年の10月末、今回はどうだろうとユニクロの入口に立って大変驚きました。客がいっぱいなのです。若い人もいますが中高年が目立ちますし、男性がコートを選んでいまして価格を見ると99ドル、同品の日本での価格は3990円ですから倍以上に設定しています。また、試着室前にも、レジ前にも列ができています。昨年とは雲泥の差です。
NY在住者に聞きますと、ユニクロ大好きという人が結構多いとのことで、受け入れられたらしいことが分かりました。この時も50メートル先のH&Mにも行ってみましたが、ここは昨年と同じ程度の客数で、黒人が多いことが目立ちました。
ユニクロのビジョンは「世界中にビジネス展開するグローバル企業になって、2010年に1兆円の売上と、1500億円の経常利益をあげ、最終的に世界一のアパレル小売企業になる」というもので、柳井正会長兼社長によって世間に明言されています。
日本企業が世界に通用していない代表業界はアパレルです。しかし、参入障壁の高いNYでの成功実態をつぶさに見て、これはひょっとしたらユニクロが初めて世界的アパレル企業となり、世界一というビジョンを達成するのではないかと思い、一時の低迷状態からユニクロが脱皮できたのは、柳井正会長のブレがないビジョン明言力と思いました。
日本航空
ニューヨークのシンクタンク、外交問題評議会(CFR)が開催した日米関係をテーマにしたセミナーが大盛況で、竹中平蔵・元金融担当相などが出席し「近年、日本がらみの講演会でこんなに集まった例はない」(日本総領事館)とのことですが、日本の「失われた10年」は思わぬところで人気となりました。
人気といえば日本航空(JAL)の西松遙社長兼CEOも米国で評判です。CNNが11月に「米国の高級CEOと日本の質素なCEO」という視点でJALを取り上げ、その内容は、米議会で財政支援を求めている企業のCEOが「年収2億ドル(約2億円)」なのに、西松社長は年収が960万円で、パイロットの平均年収1954万円の半分であることと、都バスで出勤し、社員食道の列に並んで会計し昼食をとり、社長室、役員室を無くし「大部屋」で仕事していることなどですが、これがユーチューブ(米ネットベンチャーYouTube社が運営する動画コンテンツ共有サイト)にも転載され、12月3日現在約7万回再生され、コメントも120以上寄せられているのです。
この西松社長、2006年に社内クーデターで新町敏行前社長が退陣する抗争劇の中、消去法で選ばれた非主流派財務畑の人ですが、就任後はトラブルが急減少しています。
このことは長いことJALを利用し、今年も既に21回搭乗していますからよく分かります。また、機内で客室乗務員に尋ねますと「西松社長になってから仕事がやりやすくなった」と何人も発言します。西松社長の方針は「シェアを取りに行く経営でなく、いいサービスを必死で作り、それを評価してくれるお客様を大事にするビジネスを展開する」というもので、この方針で経営を進めているブレない事例と思います。
ブレない人物の代表は鉄舟
11月29日に明治神宮で開催された山岡鉄舟全国フォーラムでお話ししましたが、ブレない生き方の代表例は鉄舟です。
鉄舟は15歳で「修身20則」を定めた以降、その後の剣・禅・書三位一体の修行過程で気づいたことをいくつも書きとめ、それを自己の生き方指針としました。
その代表的なひとつに23歳の時に書いた「心胆練磨之事」があり、その中で「私は小さい時から心胆練磨の事をいろいろ工夫してきたが、今になっても真理をつかむことができない。自分の熱意が足りないからであるから、今まで書きとめた指針を何回も読みなおし、自分を励まし、さらに勤勉に心胆練磨の源に到達したい」と述べ、そのとおり厳しく人間真理探究修行を続けた結果、45歳の明治13年(1880)3月30日払暁大悟し、境地に達し、明治時代を代表する何事にもブレない偉大な人物となり得たのです。
時代に適合した妥当なブレない指針を持つこと、これが生き方の要諦と思います。以上。
(12月のプログラム)
12月12日(金)16:00「渋谷山本時流塾」於:東邦地形社ビル会議室
12月15日(月)18:00「経営ゼミナール例会」於:皇居和田蔵門前銀行会館
12月17日(水)18:30「山岡鉄舟月例研究会」於:上野・東京文化会館
12月19日(金)14:00「健康と温泉フォーラム」於:上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 08:10 | コメント (0)
2008年11月21日
2008年11月20日 お互い知らないことが多い
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年11月20日 お互い知らないことが多い
法案8
今回のアメリカ大統領選挙時に、カリフォルニア州では同性結婚を禁ずる「法案8」の投票も併せて行われました。結果は僅差で可決されましたので、同性結婚は法律で禁じられることになりました。
その経緯は、今年5月、カリフォルニア州最高裁判所が「結婚を異性間に限らせている州婚姻法は、州憲法違反である」と判決を下し、同性結婚を合法化しましたが、この判決を受けて「それなら州憲法に、同性結婚を禁止する改正条項を付加させてしまえばよい」と、同性結婚に反対するキリスト教保守派やモルモン教グループが提案したのが「法案8」です。
特にモルモン教は、「法案8」に対する州有権者の支持を得るために、莫大な金額を費やしてキャンペーンを行い、逆に、シリコン・バレーのネット・ハイテク企業のグーグル、ヤフー、アドベ、シスコなどは反対声明を発表し、アップルは反対陣営に100万ドル(1億円)の寄付を行ったように、激しい投票合戦が展開されました。
11月4日の選挙当日、サンフランシスコの街中では、それぞれの陣営がプラカードを持ち、投票に行く人々に訴えかけていましたが、日本人には違和感が残る風景でした。
サンフランシスコの街で新たに気づいたこと
サンフランシスコに行っていつも感じるのは、明るい陽光と、坂道が多く、そこから見下ろす海が綺麗で、住んでみたい都市で常に上位に存在する美しい街だという感覚です。
これは今回の訪問でも変わらなかったのですが、新たに加わった感覚は「この街は乾いているのでは」ということでした。というのも皮膚の中で弱いところ、腕の裏側とか、ベルトあたりのところが少し赤くなって痒みが出てきたのです。水の影響かとも思いましたが、サンフランシスコの水道水はよい水として有名ですから、空気の乾燥によるものと思います。
もうひとつ感じたのは、欧米の諸都市で必ず匂う香水の香りが街中になく、お会いした何人かの女性全員が、香水を付けていないことでした。これは不思議で妙で珍しいと思います。
「法案8」が審議される街、皮膚が乾く街、香水の匂いがしない街、この三つに関連性があるかどうかわかりませんが、これがサンフランシスコで新しく発見した感覚でした。
カリフォルニアワイン
しかし、カリフォルニアワインには満足しました。訪問した家がソノマバレーでワイナリーを経営していて、お土産にいただいたジンファンデル葡萄の「イレーン・マリア」という赤ワインは絶品でした。
一般的にはワインはフランスだ、という概念がありますが、ワインコンテストを目隠しですると、世界各地で生産されている様々なワインが入賞し、かつてのようにフランス産が上位を独占することはなくなって、その中でもカリフォルニアワインの評価は高いようです。
ですから、日本人の多くは、サンフランシスコに行きますと、街中を一巡観光した後、一時間半ほど車を走らせてナパバレーかソノマバレーに向かいます。
ここは全米一のワイン生産量を誇り、別名「ワインカントリー」と呼ばれるように400か所以上のワイナリーがあり、そこでワインを楽しむ日本人が多いのです。
牡蠣養殖場
しかし、今回は「ワインカントリー」には向かわず、ゴールデンゲート・ブリッジを渡って101号線を北に向かいました。
目的地はタマレス・ベイ・オイスター Tomales Bay Oyster です。
こちらに向かった理由は二つ。一つは2010年に「世界牡蠣事情」(仮題)を出版するための取材と、二つは殆どの日本人はこちら方面に行かないと聞いていたからです。
101号線から1号線方向に入ると大変な道になってきました。左側に海、右側に丘、交互に景観が猫の目のように変わって楽しいのですが、丘陵地帯の中を曲がりくねる七曲り道、素人には運転が難しいので、プロの日本人ドライバーにお願いしたのですが、その運転ぶりを後部座席からびくびく見つめ続けるほどでした。
ようやく到着したタマレス・ベイ・オイスターの浜辺、この辺りはもともとネィテブのインディアンが牡蠣をとつていたところ、そこに1906年から養殖を始め、カリフォルニアで最も古い牡蠣養殖場という風格を漂わせています。
早速、海岸に隣接し設置されている、浄水槽から取り出した牡蠣を剥いてもらって味見しました。この瞬間が牡蠣取材で最高の至福の時です。牡蠣が育った海の味と匂いが口の中に広がっていき、其の昔、欧米では王侯貴族しか食べられなかったという風韻の味わい、一般店頭で食べる牡蠣とは比較になりません。
「うーん・・・。素晴らしい」と言い、ふと隣のドライバーを見ると「私は生れて初めて生で牡蠣を食べました」と少し情けないような声を発しました。
これにはタマレス・ベイ・オイスターの社長がビックリ仰天で、眼を剥いて「日本人は刺身を食べるのに」と怒ったような声で指摘しましたが、これが一般的な日本人の実態と思います。日本では調理して食べるのが常識ですが、欧米では牡蠣は生で食べるのが常識です。
牡蠣養殖場に来る観光客
社長が剥いてくれる牡蠣を遠慮なく食べ続けていると、ロシア人観光客が入ってきました。このタマレス・ベイ・オイスターの牡蠣は、毎日サンフランシスコのオイスターバーに出荷されていますが、海辺で食べたいという人々がこの地に訪ねてきます。
そこで、社長にどこの国の人が多いかと聞き来ますと、まず挙げたのがメキシコ人、ロシア人、その次に韓国人も来るなぁと言います。日本人はどうかと聞きますと、はっきり「来ない」との答え。アメリカ人を含めて、ここに来て食べる客の売り上げシェアは40%だといいますから、この浜辺に来る観光客は多いのですが、日本人は「ワインカントリー」に多く行き、これほど美味い新鮮な海の牡蠣には無関心なのです。

月岡温泉
サンフランシスコから戻って一日おいて新潟県新発田市の月岡温泉に行きました。大正4年、石油掘削のための井戸から噴出したお湯によって開かれた湯治場でしたが、今では素晴らしい設備の旅館・ホテルが林立しています。
宿泊するホテルに着いて、すぐに大浴場と露天風呂に三回入ってみました。体がずいぶん温まる感じがして、やはり温泉はいいなぁと思いつつ、翌日の朝になって驚きました。
サンフランシスコで発疹した皮膚の痒みがなく、かえって肌がすべすべとして気持ちがよいのです。なるほど、これが日本の温泉力かと納得した次第ですが、この日本各地に湧出する自然の力を世界の多くの人々は全く知らないと思います。
また、温泉関係者による温泉トータル情報の発信力が弱いため、日本の財産である温泉が、世界中に正しく妥当に理解されていないのです。
そこで、この度「温泉を文化として研究する月例会」を開催することにいたしました。
主催は「NPO法人 健康と温泉フューラム」です。
http://www.onsen-forum.jp/
お互い知らないことが多い
日本人は生牡蠣の実態をよく知らない。外国人は日本の温泉についてよく知らない。
世界にはお互い知らないことがまだまだ多く、世界との情報交換が大事で必要です。
以上。
【11月・12月のプログラム】
・11月29日(土)13時 山岡鉄舟全国フォーラム (会場)明治神宮至誠館会議室
・12月12日(金)16時 渋谷山本時流塾 (会場)東邦地形社ビル会議室
・12月15日(月)18時 経営ゼミナール例会 (会場)皇居和田蔵門前銀行会館
・12月17日(水)18時30分 山岡鉄舟月例研究会(会場)上野・東京文化会館
・12月19日(金)14時 温泉フォーラム月例研究会(会場)上野・東京文化会館
投稿者 lefthand : 09:00 | コメント (0)
2008年11月06日
2008年11月5日 学んで時に之を習う(論語)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年11月5日 学んで時に之を習う(論語)
オバマの勝利
サンフランシスコは民主党の街です。11月4日の夜、オバマ新米大統領が決まると、ダウンタウンの中心ユニオンスクウエアでは、車が一斉にクラクションを鳴らし、人々が集まり、勝利を祝福していました。ホテルロビーの大型テレビ前でも、演説に聞き入り、拍手し、喜びを表していましたが、新大統領の前途には多くの大問題が横たわっていて、そのひとつが、アメリカが直面する財政問題です。下の写真はそれらを示しています。


借金時計
ニューヨークの繁華街タイムズスクウエアには「借金時計」があります。
これは1989年に不動産業者が寄付したもので、アメリカの公的債務の金額を示しているものです。19年前に作ったときは5兆ドル(500兆円)の借金額、それがとうとう金額を表示する桁数がなくなって、このたび左隅の$表示のところに1を組み込む応急措置をしました。ということは10兆ドル(1000兆円)を超えたということになります。下段の数字は国民一人当たりの借金額です。
日本も大変な借金国ですから、アメリカのことは他人事ではありませんが、今回の金融危機克服のために、公的資金を投入する結果は、さらに借金が増えます。オバマ新大統領が、問題を起こした既存の政治体制をどのように改革するのか、期待と心配が交錯します。
アメリカには他国を巻き込むすごさがある
今回の金融危機は、熟知されているようにサブプライムローンからです。信用力の低い個人向けの住宅融資を積極的に展開したところに、不動産バブルがはじけ、今回の騒動が始まりました。
今になってみれば愚かな住宅貸付行為だったと、世界中から非難されていますが、この事態になるまでには背景があります。それはアメリカが金融を中心にすえた国づくりをしてきたことと、これをアメリカが世界経済に組み込ませたということです。
アメリカには、他国に影響を及ぼし、世界中を運命共同体にもっていくというすごさがあります。したがって、アメリカで発生する出来事は他人事ではないのです。
金融経済の歴史
ここでアメリカの金融について、簡単に歴史を振り返ってみたいと思います。
(1)まず、始まりは1980年代。
ご記憶の方も多いと思いますが、1987年に「ウォール街」という映画が話題になりました。主演はマイケル・ダグラスです。映画の内容はインサイダー取引にかかわるもので、マイケル・ダグラスは逮捕されるというストーリーですが、これには実在のモデルがいました。それはマイケル・ミルケンです。
マイケル・ミルケン(Michael Milken)1946年生まれですが、学生時代からジャンクボンドといわれる「焦付きリスク高めの高利回り債権」への投資で成功し、ウォール街に進出、ナンバーワンの投資銀行をつくったのですが、1989年にインサイダー取引や、他の脱税幇助罪で禁固刑に服しました。今は出所しアドバイザー業務をしていますが、彼の実績がアメリカ80年代金融の実態を表しています。
(2)次は90年代。
90年代はジョージ・ソロス(George Soros)に代表されます。1930年生まれで、今でも活躍していますが、1992年9月のポンド危機で、100億ドル以上のポンド空売りを行なったことで名を挙げたように、ヘッジファンドで巨額の利益を上げ、1997年のアジア通貨危機では、マレーシア首相マハティールが、ソロスを名指しで非難したことでも有名な人物で、90年代のアメリカ金融実態の内容を表しています。
(3)その次は2000年代。
ここまでは、アメリカが得意とする金融工学を駆使したもので、いろいろ異論はあるかとは思いますが、それなりに理論化された金融取引として根拠がありました。
しかし、今回のサブプライムローンは、金融工学というレベルよりは、今まで住宅を望んでも夢だった低所得層に、家を持たせるために貸し込みをしたもので、そこに不動産バブルが崩壊し、加えて、これをCDS(クレジット・デォルト・スワップ)という債権保証システムに組み込ませ、それも優良債権と混ぜ合わせ、世界中に売り込んだ結果、世界経済の混乱に拍車をかけ、大規模金融企業の倒産にまでに陥らせたのです。
アメリカ人の借金生活
2006年ですから、今から2年前になりますが、ニューヨーク在住の日本人女性と食事した際の会話が記憶に残っています。一人は映画の研究者で大学を卒業し大学院に学ぶ30代。もう一人は日本の某テレビの現地法人に勤めていて、離婚してフィレンツェとセベリアへ休暇とって行ってきたばかりの二人です。
この二人の共通点は「収入の全部を使い切る」という生活態度であることです。その理由として挙げたのが2001.9.11のアメリカ同時多発テロ事件です。あれ以来ニューヨークで働いている人の気持ちに変化がおき、人生にはいつ何が起きるかわからない、明日はわからない、だから今をエンジョイする、という気持ちが強くなって、結果として収入の全部を使ってしまう生活になって、貯金は全くしなくなった、というのです。また加えて、これは出身国籍を問わず、これがアメリカ人の一般的な傾向だと言い切りました。
これを聞いたときは驚きました。一般的な日本人にはちょっと信じられない暮らし方です。だが、その後もアメリカのテレビ報道などで見ると、確かに貯金はしないで借金生活を平然と行うのが普通とのことであり、今回、大統領選の激戦州であるオハイオ州のアクロンに行き、長距離をタクシーに乗ったので、その運転手と雑談しながら、さりげなく尋ねてみると「アメリカ人は平均一人当たり1.3万ドル(130万円)のカード支払い残がある」と明るく発言します。これについて別の人にも確認してみましたが事実らしいのです。つまり、これは借金で、日本の消費者ローンに当たると思いますが、国民の平均額がこれですから、国家全体ではすごい借金額になります。
今回の金融危機は予測できたこと
このような借金体質に馴染んだ国民に、それもサブプライムローンとして低所得層対象に展開すれば、大受けする反面、いずれ返済不可能になることはわかっていたはずです。
また、これを承知の上で世界中が経済成長を謳歌していたかと思うと、本質的な怖さを感じます。根本にアメリカ国民が持つ借金生活体質、そこに真の問題起因があります。
学んで時に之を習う(論語)
論語の言葉です。学んだことはそのままにしておかず、それを今後に実践する必要性を述べたものです。今回のアメリカ発の金融問題から学ぶとすれば、アメリカ人の借金習癖を「チェンジ」させることであり、そのためには根本的な価値観の「チェンジ」をアメリカ人に求めていかねばなりません。オバマ新大統領の仕事は価値観を変化させることによって実現するであろう、新しい国家像を具体的に提示することではないでしょうか。以上。
【今月のプログラム】
11月14日(金)16:00〜 渋谷山本時流塾
〈会場〉東邦地形社ビル会議室(渋谷)
11月17日(月)18:00〜 経営ゼミナール例会
〈会場〉皇居和田蔵門前・銀行会館(東京駅)
11月29日(土)13:00〜 山岡鉄舟全国フォーラム
〈会場〉明治神宮・至誠館会議室(原宿)
投稿者 lefthand : 23:43 | コメント (0)
2008年10月20日
2008年10月20日 士道にあるまじき
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年10月20日 士道にあるまじき
かもめ食道広場
フィンランド・ヘルシンキのハカニエミ(HAKAMIEMI)広場に行きました。ここは2006年に公開された映画「かもめ食道」が撮影されたところです。
ご参考までに映画「かもめ食道」のPR文を紹介します。
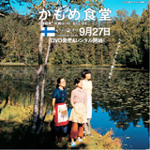

『東京から10時間、日本から最も近いヨーロッパの国、フィンランド。そんな何だか遠くて近い国でひそかに誕生した映画「かもめ食堂」。フィンランドの首都ヘルシンキは青い空にのんびりとかもめが空を飛び交い、ヨーロッパ各地からの客船が行き交う美しい港町です。その街角に、日本人女性サチエ(小林聡美)が経営する「かもめ食堂」(ruokala lokki)は小さいながらも健気に開店しました。そんなかもめ食堂を舞台にそれぞれの登場人物の、丈夫だけれどちょっとやるせない、日常的なようでそうでない不思議な物語が始まります』
上の写真の左側は映画のポスターです。右側はこの映画が撮影されたハカニエミ広場の一角ですが、写真の真ん中は男性がドラム缶式のゴミ入れに、ゴミを捨てているところです。地下にゴミ収集小屋が三つあり、市役所がゴミ処理するときだけ地上に現れるシステムとなって、一番左側の小屋がそれです。普段は地下にあって景観を損なわず、一番右側は亀の置物が置かれ、ここに駐車させないようになっています。
日本では、毎朝カラスの宴会が行われているゴミ収集システムと比較し、フィンランドは景観を配慮した実態となっています。
一国の総合評価
2006年度の一人当たりGDPでフィンランドは世界第14位、日本は18位です。一位はルクセンブルグ、二位はノルウェー、三位はアイスランドとなっていて、この順位をもって、その国の豊かさを測る基準と理解されていましたが、世界の金融危機で分からなくなりました。例えば、三位のアイスランドは富裕国のはずですが、急激な資金逼迫に陥り、世界各国に融資を要請する実態となっていますから、一概にGDPのみで一国の評価を断定できません。
また、フィンランドでは9月に職業専門学校で、銃乱射事件が発生し11人が死亡し、前年11月にヘルシンキの中学校で乱射事件があり、生徒6人と校長、保健士が殺されるという問題、さらに離婚・自殺も多く、詳しく見ていけば多くの社会問題があります。
しかし、OECDの学習到達度調査(PISA)で世界一という実績と、ヘルシンキでいくつかの家庭を訪問し、人と会い話し、街並み観察など現地現場確認を行ってみますと、フィンランドは世界各国との相対比較で「よい国」の分類に入ると判断します。
日英・日仏百五十周年
今年は、安政五年(1858)に徳川幕府と米英仏蘭露の五カ国が修好通商条約を結んで百五十年に当たります。
それを記念して各国で様々なイベントが開催され、そのひとつがロンドンのヴィクトリア&アルバート博物館での「山岡鉄舟書展」であり、パリのユネスコ本部で開催された今西淳恵さんによる「源氏物語現代画展」(A World of "Tale of Genji")です。


写真の左が鉄舟書展です。右の写真の源氏物語現代画展のオープニングパーティには、ユネスコ本部の松浦事務局長も出席挨拶される華やかなものでしたが、この二つの会場で強く感じたのは、歴史と文化に裏付けされた日本は「よい国」であり、その「よい国」となった要因は、幕末時の政治判断が優れていたからだ、という深い感慨でした。
江戸無血開城
ご存じのとおり明治維新は慶応四年(1868)四月の江戸無血開城で事実上成し遂げられました。仮にこの無血開城による政治判断がなされず、官軍と徳川側が一戦を交える事態となっていたら、日本国内は大混乱に陥り、今日までの日本国家発展は別の形になっていたと思います。その意味で、同年三月の駿府における官軍参謀の西郷隆盛と山岡鉄舟による会談で、実質の江戸無血開城が決まったことの意義は大きく、また、それを指示した勝海舟の政治判断力を高く評価します。
福沢諭吉の批判
だが、あくまで主戦を唱える勢力陣を抑え、平和的解決へ持っていった勝海舟等の和平派に対して、当時も今も一部から大きな強い批判があります。
例えば、明治時代の最高の文化人であった福沢諭吉が、明治二四年(1891)に「痩我慢の説」を書き、その中で次のように述べています。
「痩我慢とは、個々人についていえば、主に対しての節操であり、その存亡が問われる危機にのぞんで、主を守り抜こうとする気概を強くすることである。勝敗の打算を度外視して、犠牲になることを惜しまない。このような節を守る痩我慢こそ、立国の大本となる心情である」と述べ「徳川の末期に、家臣の一部分が早く大事の去るを悟り、敵に向かいてかつて抵抗を試みず、ひたすら和を講じてみずから家を解きたる」者ありとして、その批判の対象を名指しで勝海舟と榎本武揚に向けました。
士道にあるまじき
士道とは「武士として守り行わなければならない道義。武士道」と明鏡口語辞典にあり、広辞苑には「士たる者の履み行うべき道義」とあり、新撰組の土方歳三がいうように「士道とは、すなわち、節である」と解釈すれば、福沢諭吉のいう「主に対しての節操」とは士道であり、それに反して「二君に仕えた」者は「士道にあるまじき」者となります。つまり、勝海舟が明治政府で参議兼海軍卿となり、伯爵の爵位を受けたこと、榎本武揚が函館で戦いはしたが、のちに明治政府の大臣になったという身の処し方、これは「士道にあるまじき」行為であり「二君に仕えた」ことを批判されているのです。
その点では、福沢諭吉からは名指しで批判はされなかったものの、鉄舟も「二君に仕えた」のですから「士道にあるまじき」者に該当するかもしれません。
世界との比較で日本は豊かだ
確かに「義と情」を「理」として判断すれば、福沢諭吉のとおりです。だが、米英仏蘭露と修好通商条約締結後、百五十年を経た現在の日本、その実態は問題が多々あるにせよ経済面で豊かな国であり、文化面でも「山岡鉄舟書展」「源氏物語現代画展」の開催で証明されるように日本文化の成熟度は高く、これらから考えれば時代の大変換期に「士道にはもとづかない」世界観による和平路線の「理」を受け入れた徳川幕府の江戸無血開城は正解で、日本が「よい国」となった最高の政治判断と断定できます。
以上。
投稿者 lefthand : 08:14 | コメント (0)
2008年10月06日
2008年10月5日 スマイルライン
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年10月5日 スマイルライン
欧州でも
サブプライムローン問題は世界中を駆け巡り、リーマン・ブラザーズの経営破綻は、ヨーロッパでもその飛び火はただならぬもののようで、ドイツ復興金融公庫(KFW)銀行グループが、リーマン・ブラザーズ破綻の発表当日、同社に対して3億ユーロ(約450億円)の送金を行っていたと報じられました。
送金は事前に取り決めていたスワップと呼ばれる金融取引で、原因は「技術的なミス」による送金だったという発表です。同公庫はリーマン・ブラザーズに返金を求める方針ですが、全額が戻ってくることはまずないでしょう。
イギリスでは、銀行大手「ロイズTSB」が、住宅金融最大手「HBOS」を買収すると発表しました。HBOSはサブプライム問題のあおりで業績が悪化し、これにリーマンの破綻をきっかけに信用不安が拡がり株価が急落。資産規模が下回るロイズによる買収救済という異例の展開となりました。これによってイギリスで総資産4位の巨大金融機関が誕生することになりますが、世界中の金融界が大編制です。
NEW YORK POSTの記事
今まで世界の景気は、米国の消費によって支えられてきましたが、9月に入って続発した一連の金融問題発生と、その結果の混迷化によって、頼みの米国が危ないという認識、それと米政府が景気対策の柱として打ち出した総額千百ドル(約12兆円)の所得税還付も、その60%が借金の返済や貯蓄に回って、支出拡大には結びつかなかったことから、一気に世界経済は低迷観測方向に走り出しました。
そのような中、いち早くファッショントレンドを打ち出したのが、H&M(ヘネス・アンド・モーリッツ)、GAP、バナナリパブリックの三社です。7月28日のNEW YORK POST新聞は、今年の秋ファッション情報を伝え、この秋のポイントは1929年のNY株式大暴落の結果、一気に1930年代の米国は大不況となった事実を取り上げ、当時の失業者が被った帽子、当時の新聞売り子の服装など、それが2008年秋のトレンドだと訴求しました。(写真参照)
銀座七丁目
9月13日に銀座七丁目のガスホール跡に「GINZA gCUBE」が完成し、そこにスエーデンのH&Mが日本初出店しました。
現在、世界の衣料品専門店売上高トップはGAP。このH&Mは第三位で、すでに世界29カ国に約1600店を展開しています。アイテム価格は婦人用カーディガン2400円、ジーンズ3200円から分かるように、国内最大手のユニクロとほぼ同水準です。因みにユニクロは世界第7位の売上高規模です。
このビルのオープン日は、H&Mを目指して銀座は客で埋まりました。その後も毎日行列が続き、オープン5日目の17日夕方行ってみましたが、ビルの前から博品館劇場前交差点まで、人の列が続いていました。つまり、銀座大通りの終わりまで行列なのです。おかげでいつもはガラガラの松坂屋銀座店も五割増しの客数、ライバルのユニクロも、世界第二位のインディテックス(スペイン)の衣料専門店「ザラ」も、あふれるような盛況ぶりです。H&M出店効果で銀座は大混雑です。
銀座の高級ブティック
ご存知のように銀座地区には、世界のトップブティックが軒並み進出しています。業界関係者が「ニューヨーク、ロンドンに並んでプレステージの高い銀座に出店することで、そのブランド価値がさらに高まる」と指摘するように、ここ数年世界の一流ショップが競って進出しました。その中で特に目立つのか銀座二丁目交差点です。
この四つ角はルイ・ヴィトン、シャネル、カルティエ、ブルガリという、世界トップブティックで占拠され、今や四丁目を凌駕する勢いです。
その他にもエルメス、プラダ、クリスチャン・ディオール、ティファニー、ランバン、ダンヒル、セリーヌ、バレンチィノ、コーチなど、銀座進出のブティックを数え上げたらキリがありません。だが、銀座にはこれら高級価格帯の店がある一方、ユニクロやザラ、今回のH&Mのように中低価格帯のショップも進出し両立しています。
これはロンドンも同じです。高級デパートのあるハロッズが位置するプロンプトン・ロードに面するナイツブリッジ地区、ここはハロッズとユニクロとH&Mとザラが並んでいます。
中間層の店が不振
銀座大通りを歩いていると、といっても混雑で歩きにくいのですが、その中に店頭で声を枯らして叫んでいる店がありました。店主と思われる男性が、客の呼び込みをしているのです。多分、老舗でしょう。松坂屋前ですから一等地です。扱っているのは女性用バック類ですが、声の大きさに反比例し客は一人もおりません。目の前は人込み、向かい側の歩道にはH&Mを目指す長い列。少し先のユニクロは客で一杯なのに、この店には入ってこないのです。
どうしてなのでしょうか。歩きながら思い出したのは、オンワードのジルサンダー買収です。オンワードの今年3月から5月の売上高は前期比△3.9%と減少しました。以前は国内デパート内の常勝将軍でしたが、ここ数年かつての勢いがなくなって、海外高級ブランドに負けていました。そこで投資したのがドイツの高級ファッションブランド・ジルサンダーです。華美な装飾をそぎ落とした作風が特徴のプレステージブランドですが、この買収になるほどと思います。
オンワードブランドでは海外勢に負けて、売上が獲得できないのです。世界で評価されている日本人ファッションデザイナーは何人も輩出していますが、日本のアパレル企業は、ユニクロ以外は世界で成功していません。不思議です。
ビール売上
第3のビールが売れています。これは発泡酒とは別の原料と製法で、最大の特徴は、酒税法上「ビール」と「発泡酒」にしないために、原料を麦芽以外にする発泡酒に、別のアルコール飲料を混ぜていることです。
今年上半期のビール系飲料(ビール・発泡酒・第3のビール)の出荷量で、サントリーがサッポロを抜き、初めてシェアで三位に浮上したことが話題となりました。
その要因は、サントリーの高価格ビール「ザ・プレミアム・モルツ」が上半期で前年同期比20%増と伸びたことと、第3のビール「金麦」が同37%増と好調に推移したことです。加えて、他社と一線を画した価格戦略も奏功しました。キリン、アサヒとサッポロが順次値上げを実施するなかで、サントリーは業務用を値上げしたものの、家庭用の缶入りの価格据え置きを決めたことも大きいのです。
イギリスの出版社
イギリスでも「大人のぬりえ」が売れ出したというので、ロンドンから列車で1時間のノーサンプトン駅へ、そこから車で15分、道路が突き当たった町外れのバラック建て出版社へ訪問し業績を聞いてみました。イギリスも世界各国と同じく経済低迷下なのですが、この出版社は不思議と世間と反比例して伸び始めていると語り、その要因は価格の安さにあるといいます。立派な風景画ぬりえブックの価格がたったの50ペンス(100円)、卸は22ペンス(44円)という徹底した低価格路線です。
スマイルライン
人は笑うと唇の両サイドがつりあがります。これが今の時代のマーケティングを示しています。つまり、高価格帯と低価格帯のアイテムだけが伸びているのです。以上。
投稿者 lefthand : 07:02 | コメント (0)
2008年09月20日
2008年9月20日 文明と文化の衝突
文化×環境×経済 山本紀久雄
2008年9月20日 文明と文化の衝突
旧中山道の大ケヤキ

京浜東北線与野駅東口近く、旧中山道の交差点真ん中に、一本の大ケヤキがあります。江戸時代には、この大ケヤキ下に、関東六国の山々が見渡せるという「六国見」の立場茶屋があり、旅人が一休みする名所でした。今でも地元の人々、つまり、私を含む交差点を通る人たちは、この大ケヤキを誇りに思い、いつも敬愛の眼差しで見上げます。
また、大ケヤキの根元には、春夏秋冬、その季節の花が小奇麗に咲いていて、幹にリボンがかけられているようなイメージを与えています。さらに、この交差点では、ゴミがなく、タバコの吸殻もなく、清潔に路上が保たれていることも、大ケヤキ交差点の魅力となっています。誰かが花を咲かせ、道路を綺麗に掃除してくれているのです。
誰か。それは、交差点に面しているビル一階の床屋さんご夫婦です。このご夫婦が、樹齢数百年という大年寄りとなった大ケヤキを見守り、交差点の路上整備をいつもしてくれているのです。
先日、そのご夫婦から質問を受けました。「このケヤキは大丈夫でしょうか」と。質問の意味は「与野駅前再開発によって伐り倒されるのではないか」という心配で、市政に詳しい人を知っていたら聞いてほしいという依頼です。
駅前再開発
早速、市関連福祉施設で評議委員会があった時、会長の大物市会議員に尋ねてみました。
確かに再開発計画はありました。というより、もうずいぶん前からの課題で、いろいろ問題があって今まで進んでいなかったものが、ようやく来年春を目途に再開発計画を作り、市民に提示されることになっているとのこと。
さて、心配の大ケヤキ、文化財的な意味合いがあるので残したいが、すでに幹の中は半分空洞化して、もう寿命も長くなく、何かのタイミングで倒れる危険もあるので、伐りたいとの意向です。
ただし、伐るにしても地元の人とジックリ相談したいので、大ケヤキ委員会を作り、多くの方の意見をお聞きし、なるべく遺伝子を遺すような文化的対応を図りたいということでした。
そこで早速、床屋さんご夫婦に報告したところ「そうですか。そうだろうなぁ。再開発だから仕方ないなぁ・・・。もう少しだからケヤキを大事にしてあげないと・・・」と、肩を落としながら、小さな声でつぶやくのが精一杯でした。
交差点を毎日通る一人としても、大ケヤキが消えるのは残念ですが、問題の多いままとなっている駅前が再開発され、整備されるという、いわばこの地区一帯の改革変化ということも大事です。
例えれば、駅前再開発は文明の潮流変化であり、大ケヤキは文明潮流によって変化させられていく文化遺産ということでしょうか。
米国金融の急変化
昨年8月のサブプライムローン問題表面化から一年、問題は落ち着くどころか、ますます混迷の事態となってきました。9月に入って20日までの動きを振り返ってみますと、米金融当局が経営難に陥った金融機関の処理に追われたことを示しています。
9月7日 経営難に陥っていた住宅金融公社、ファニーメイとフレディマックの二社を政府の管理下に置く
と発表
15日 米証券四位のリーマン・ブラザーズが破綻
バンク・オブ・アメリカが米証券三位メルリリンチ買収で合意
16日 米保険最大手アメリカン・インターナショナル・グループ(AIG)を米政府とFRBが救済に踏み切
る
17日 株式の空売り規制の強化を発表
18日 日米欧の主要銀行と協調してドル資金供給で合意
19日 米政府が不良債権の買い取りを含む総合的な金融安定化策に乗り出す
救済、破綻、そして救済・・・当局の方針は揺れ動き、世界各国の株価は乱高下しました。
市場が米政府に対応を迫る21世紀型の危機管理です。
世界全体への影響
このように米国の金融危機は、世界の経済に逆風を巻き起こします。
「米金融危機による実体経済への悪影響は、まだ一、二合目にすぎない。米国の家計部門が過剰債務の圧縮に走るため、米経済は五年近くゼロ成長の低迷が続き、世界経済は2%程度の成長に鈍化する」(三菱UFJ証券・水野和夫氏)という見解もあり、2007年に5%近い成長だった世界経済が、一気に2%にダウンすれば、日本を含めてグローバル化した世界経済は大きく影響を受けることになります。
日本経済
日本経済はご承知の通り、2002年2月から緩やかな景気回復過程に入って、2006年11月に60年代後半の戦後最長「いざなぎ景気(57カ月)」を超えた今回の「新いざなぎ景気」は、70カ月弱(約6年弱)続き、GDP成長率は2003年度から2006年度まで4年連続で2%台に乗せ、復調ぶりを示しました。
だが、昨秋「屈折」し景気停滞局面となり、2007年度は1.6%に減速、2008年度については、政府は1.3%と見込んでいますが、4月から6月期実績がマイナス0.6%となったので、さらに悪化する可能性がある、というのが一般的見通しです。
つまり、簡単に結論付けすれば、2000年ごろから続いた世界規模の高成長によって、日本経済も順調に伸びてきたものが、世界全体がおかしくなってきて、それと同じ傾向になったのです。
外需によって成長し、外需で低迷するのです。
文化潮流が変化しているのではないか
外需によって日本経済が変動するということは、日本だけの現象でしょうか。そうではありません。これは世界中同様なのです。まさに世界の経済はグローバル化という一体化になっているのですが、かつてこのような事態は存在したことがあったでしょうか。これは、世界が初めて迎えた事態です。
また、ついこの間まで「デカップリング論」がもてはやされていました。「デカップリング論」とは、米国経済が停滞しても、新興国経済が成長するので、世界全体は問題なく成長していくというもので、多くの識者が喧伝したものです。
しかし、米国経済がサブプライムローン問題で躓くと、あっという間に世界は同時停滞化に向かおうとしている実態、これは明らかに「デカップリング論」は時期尚早の議論だったということになります。
このように経済専門家の予測を超える何かのもの、それは過去と異なる新しいうねりであり、大きな流れであり、世界の文明潮流ともいえるものが、世界の底流にうごめき始めているような気がしてなりません。
日本独自の潮流
そこで、世界の文明潮流が脈動し始めている、という理解に立って、もう一度日本を見つめてみれば、そこに日本独自の大きな潮流変化が、事実として浮かび上がってきます。
それは人口です。人口推計が見直され、2050年の日本人口は約8900万人(低位推計)と予測され、これと同じ人口をたどってみれば1955年(昭和30年)であり、石原都知事の「太陽の季節」が大ベストセラーになった年、人口は8927万人でした。
つまり、戦後60年を経て2006年に12,700万人に増えた人口が、44年かけて約50年前の昔に戻っていくのです。回帰するとも言ってよいと思います。
明らかに、日本は高度成長や大阪万博、東京オリンピックに象徴される「躁の時代」を終え、バブル崩壊後10年の低迷期を経て、「欝の時代」文化になっていきます。
どう対応するか
このように、我々が今まで生活してきた文化スタイルは、外部要因としての文明潮流で変えさせられていく事態となっています。しかもその変化原点は長期潮流にあるのですから、対応策を簡略に組み立て、手軽に結論付けしてはいけないと思います。
中山道交差点に位置する江戸時代からの大ケヤキ問題は、文化を遺しながらその適切な対応策を地元民が考えることです。同様に、世界の文明潮流と日本独自の人口減によって生じる文化との衝突は、一人ひとりが責任もって考えるべきことです。以上。
2008年09月05日
2008年9月5日 ネット化でヒトはバカになるのか?
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年9月5日 ネット化でヒトはバカになるのか?
太陽の塔
大阪モノレールの万博記念公園駅を降り立つと、真夏の陽射しが強く、それが高さ65メートルの「太陽の塔」に当たり、照り返し、未だに1970年・昭和45年の熱気を感じさせます。当時の日本は高度経済成長の真っ直中にいました。まさに「躁の時代」のシンボルが大阪万博で、テーマは「人類の進歩と調和」、入場者数6400万人という博覧会史上最高の人数でした。
それから35年後、2005年に開催された名古屋万博、こちらのテーマは「自然の叡智」、入場者数2200万人で大阪の約三分の一、明らかに低成長経済を示し、日本は「鬱の時代」に入っていることを証明する人数です。
国立民族学博物館
万博記念公園駅を降り立ったのは、国立民族学博物館の図書館に行くためでした。8月初旬と中旬の二回訪れました。訪問目的は、現在取り掛かっている研究のためです。
この図書館の蔵書は60万冊。文化人類学・民族学関係の資料を収集している図書館としては、日本最大規模を誇っていることもありますが、最も素晴らしいのは直接書庫に入ることができ、自ら書棚から書籍を取り出せ読めることです。
東京の国立国会図書館は、検索用端末で調べた書籍を閲覧請求するシステムで、書庫内には入れません。ところが、民族学博物館は自分で書棚から探せるのです。ということはテーマとキーワードで検索用端末から探す以外に、五層建てになっている書庫内を自由に歩き、関係すると思われる分野の書棚に行き、それを見つめているうちに、そこに新たなる資料発見があって、思わぬ収穫が期待できるのです。
これをやりだすとその醍醐味に取り憑かれます。今まで想像もしていなかった資料に出合え、それを抱えて書庫内の片隅にある机で読み出すのですが、この繰り返しをしていると時間の経つのも忘れ、館内に響く終了時間のアナウンスでハッと気づくまで、濃密な時間を過ごせます。図書館を後にして、駅に向う緑多き万博公園内を歩いていくと、何か昔に戻った懐かしさに溢れ、豊かな気持ちになります。
現代人は何かを失っていないか
多くの現代人は、何か分からないことがあるとパソコンで検索し、ネット情報を集め、さらに、そこから短くまとめてある一節を探しだし、ざっと走り読みするようになっているのではないでしょうか。ある人は、この状態をスタッカート(一音ずつ短く区切る奏法)といっています。当然、私もそうなっています。
これに対し、インターネットが普及する前はどうだったのでしょうか。何かを調べるには図書館に通い、そこに所蔵されている本に没頭したり、保管されている長い記事に読みふけったりすることが一般的であったと思います。
また当時は、テレビや新聞紙上で展開される長い議論にも、それほど抵抗なく一緒に議論できたのではないでしょうか。さらに、トルストイの「戦争と平和」を一心不乱に読んだように、長い文章を何時間も夢中になって目で追い続けたのではないでしょうか。
簡単に検索で知ることが出来る
国立民族学博物館の図書館内には、ごく僅かの人だけが訪れてきます。ここに勤務している人よりずっと少ないのです。ですから、書庫内はいつも深閑としています。
かつては図書館に何日も通って調べなければ分からなかったものが、今は簡単にネット検索によって、数分・数秒で必要な情報が入手できるのですから、調査で図書館に行く人は少ないのです。便利になったものです。分からないことはすぐに知ることが出来る素晴らしい時代になっています。
今や、ネットは「複合的メデイア」になっていて、目と耳を通じて意識に多くの情報を伝えてくれる媒体として有効で、膨大な情報が瞬時に手に入るメリットは多いと思います。グーグルやヤフーでちょっと検索をし、いくつかのリンクをクリックするだけで、必要な情報や、使える引用句を見つけ出せることが出来ます。
さらに、メールマガジンを読み、ブログの投稿をチェックして、リンクからリンクへと簡単な旅が出来、その楽しみは大変なものです。
人間の脳は可塑性があるから危険性が高い
しかし、この結果は人に何をもたらしていくのか、何かの危険を最近感じています。
例えば、仕事関係者に懸案事項を調べるよう依頼した場合、ネットで検索し見つからないと「調べた結果わかりませんでした」と答えることが当然化し、それで業務責任を免れることかできると思っている事例が、多々発生しています。
これは、ネット検索以外に調べる術を失っていることを証明しているもので、人間が持つ本来思考力が、ネットによって侵食され始めているのではないかと怖れています。
私の師、故城野宏が「脳力開発」を提唱した当初は、脳の神経細胞は140億個といわれていました。今はそれが1000億個を超えるといわれています。また、脳細胞のシナプス結びつきパターンは、成人するころにはほぼ固まっていると考えられていましたが、脳の研究が進んで、常に可塑性、つまり、大人の脳でも変化していくことが分かってきました。ということは、脳は常に古いつながりを破壊しては、新しいつながりを形作っていることになりますので、ネットの普及と活用は、ネット用の脳に作り変えている可能性が高いのです。
ですから、ネット検索結果のみで「調査終了」という指令が、脳回路に新たに組み込まれてしまう結果になるのです。
クジラたちが船に激突死
世界各地でクジラが船舶と衝突して、死んでいく事例が多くなっています。
フランスの生物学者が、貨物船と衝突した二頭のマッコウクジラを調べたところ、敏感なはずの聴覚機能が著しく損傷していたと発表し、それは、おそらくスクリューが水をかき回す音に常にさらされていたせいだろう、と生物学者は推測しています。
海洋生物学者の間では、高性能の軍事用ソナー(音波探知機)が海洋生物に致命的な影響を与えていることが知られています。海軍が低・中周波ソナーを使うことで、クジラやイルカが音響に混乱して浜に打ち上げられ、死んでいくという事態が頻発し、ソナー使用の論争が激しく繰り広げられているのです。
また、エンジンやボイラーの音などによって、海は40年前に比べて10倍ほどもうるさくなっていることが分かってきました。
勿論、自然界にも、もともと騒音は存在しているのですが、それらと音の種類が違うので、クジラたちは今まで経験したことのない騒音によって、脳の探知力が衰えていくと考えられるのです。つまり、クジラたちの脳も可塑性があるからこそ、聴覚脳が組み替えられ、結果として船舶に激突する危険性が高くなっているのです。
パンケーキになるな!!
国立民族学博物館の図書館からの帰りに、何か昔に戻った懐かしさに溢れ、豊かな気持ちになったのは、久し振りにネットから離れ、集中して活字の海に潜れたからではないかと思っています。
仕事柄、本を読む機会は多いのですが、知らず識らずにネットの持つ便利性と速さに満足し、そこに表現されている文脈と、内容の真偽妥当性を十分検討しないまま受け入れてしまうという、知識の単純処理業務をくり返している日常となっているのです。
本来、集中して読み込むということは、著者が持つ知識を集めることでなく、著者が発する文字による言葉が、こちらの意識に知的な共振を生じさせ、自分の中に連想と独自性の考えを浮かばせ、結果的に豊かな思考力を養わせるものではないでしょうか。
ニューヨークのアンダーグランド演劇界で活躍しているリチャード・フォアマンは、「膨大な情報に接するようになって、薄く拡がっていくパンケーキ人間になる危険を冒している」と警鐘を発しています。
その通りと感じます。ネットが、我々を助けてくれ助長する読み方、それは「効率性」と「即時性」を強化してくれるものであって、我々が昔に獲得していた「思考に結びつく読み方技術」を失う結果を生じさせる、という危険があるように感じています。
そのような気づきを、真夏の国立民族学博物館図書館の静寂が教えてくれました。
以上。
投稿者 lefthand : 08:33 | コメント (0)
2008年08月20日
2008年8月20日 ロールモデル
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年8月20日 ロールモデル
東条元首相の手記
太平洋戦争開戦時の首相である東条英機陸軍大将が、終戦直前に書いた手記が国立公文書館で見つかり、その昭和20年8月13日に「戦いは常に一瞬において決定するの常則は不変なる」と書いています。これと全く同じことを開戦前にも発言しています。
それは昭和16年4月、当時の近衛内閣が「もし日米戦わばどのような結果になるか」を検討し、結論は「緒戦は勝つであろう。しかしながら、やがて国力、物量の差、それが明らかになって、最終的にはソビエトの参戦、こういうかたちでこの戦争は必ず負ける。よって日米は決して戦ってはならない」でした。
だが、東条陸軍大臣は「この結論は、まさしく机上の空論である。日露戦争も最初から勝てると思ってやったわけではない。三国同盟、三国干渉があってやむを得ず立ち上がったのである。戦というのは意外なことが起こってそれで勝敗が決するのである」と発言し、同年10月に東条内閣が成立し、12月8日の真珠湾攻撃となったのです。
開戦前も、ポツダム宣言受諾後でも、同じことを述べていますので、これは東条元首相の信念と思いますが、明らかに戦争に勝利するための信念・思考力ではありません。
戦争ですから「意外なこと」が多々発生するでしょう。しかし、戦争とは国家の総力を挙げた、国の基盤同士の戦いですから、時間の経過とともに基盤力が表出し、「意外なこと」ではなく「力どおり」の結果になっていくのです。
ロールモデルのシフト
山岡鉄舟の研究を通じ、幕末維新を検討していく過程で気づいてきたことがあります。それは、嘉永6年(1853)6月にペリー提督が浦賀に来たとき、これを切っ掛けにして、日本はそれまでの「ロールモデル(あこがれの対象)」を中国・清から欧米に切り替えたのではないかということです。
それまでの日本は中国という大国を見習ってきました。文字でも、儒教でも、詩文でも、すべての基盤思考は中国で、そこに独自色を如何につけるかで、国家のアイデンティテイをつくりあげて来ました。
例えば、寛永18年(1641)に完成させた鎖国です。これは日本独自の政策と思っている人が多いのですが、すでに明と清が鎖国政策を採っていたことが、関係していないはずはありません。
仮に、清がヨーロッパ諸国と広く交易を展開していて、ヨーロッパの文物を採り入れた近代国家であり、豊かな国であった場合でも、日本は国内政局を理由として鎖国を完成させたかどうかです。清がヨーロッパ諸国と上手に付き合っていたならば、鎖国ということは考えなかったのではないでしょうか。逆に清を見習って、ヨーロッパと積極的な関係になったと思います。
日本の歴史書には明と清の鎖国政策との関係がふれていない場合が多いのですが、隣国の清が海禁政策を採っていなかったならば、徳川家光は果たして鎖国を断行したかどうか疑問です。
アメリカを採り入れた
ところが、この清がアヘン戦争、アロー戦争、太平天国の乱によって、凄まじく瓦解する状態を知った幕末の日本の政治指導者は、「日本は清と同じ運命になるのでは」という恐怖心と危機感に襲われ、もう清をロールモデルにはできない、どうすればよいのか、とういう事態に陥ったと思います。
まさにそのとき、ペリー提督が浦賀に来たのです。おそらくこのタイミングに、日本は千年来のロールモデルであった中国を見限り、欧米をロールモデルに選び、シフトさせたのです。そう考えないと、明治時代の「脱亜入欧」を理解できません。
明治4年、まだ江戸時代の名残が深く、落ち着いたとはいえない時期に、右大臣岩倉具視を大使として、木戸孝允、大久保利通、伊藤博文、山口尚芳の4人を副使として、総勢50人に及ぶ大使節団を、欧米に派遣しました。内閣の主要メンバーが、2年間も一斉に日本を離れるということ、それはロールモデルを中国から欧米へとシフトさせたことの行動であり、その延長線上に今の日米同盟関係があると考えます。
世界の動向
先般の洞爺湖サミットでは、地球温暖化や石油・食糧価格の高騰などの問題に対し、先進国だけでは解決策を提示できないという事実、それは参加国がG8とEU委員長を中心に、招待国を含め23カ国に及んだことで分かります。また、ジュネーブでの世界貿易機関(WTO)閣僚会議も、アメリカとインドの対立で結論を得ないまま頓挫しました。
これらの事実は、新興勢力の台頭で、アメリカ中心に先進国が築いてきた秩序が崩れ始め、世界の勢力バランスが確実に変化していることを証明しました。
さらに、北京オリンピックの開催時期に、ロシアとグルジアが軍事衝突を起しました。ようやく8月16日に停戦合意が署名されましたが、ここで分かったことはロシアとアメリカの関係です。原油をはじめとする資源高を追い風に、ロシアが大国として再登場しようとする意図の紛争に対し、アメリカは初動対応が遅れ、代わってEUを代表してフランスのサルコジ大統領が調停役を務めたのです。
紛争が少し落ち着いたあたりから、アメリカはサミットからロシアを排除しろ、2014年の冬季オリンピック開催地をロシアのソチから変更させろ、というようなロシア非難を強く始めましたが、どうも犬の遠吠えのような感で、明らかにアメリカ中心の時代に陰りが出ていると感じます。
これからの大国はどこか
2007年度のGDPはアメリカが13兆ドル超で世界一、次にEUを除けば日本で4兆ドル超、中国は3兆ドル超です。しかし、中国の人口13億人はこれからも増えていくはずですから、現状様々な問題があっても、全体では成長していくと多くの識者が指摘する通り、数年後には中国が日本をGDPで追い抜くと思います。
といっても、中国がアメリカを抜いて世界一になると予測するのは早計ですが、世界での地位、重要性は今より格段に強くなっていくでしょうし、そこに資源大国ロシアが絡んでいくと考えられます。
これに対し、日本は明らかに人口減が始まっていますので、今までとは異なった方向での国家戦略、それはアメリカとの関係見直しを含めた新たな検討が必要となっています。
躁から鬱へ
作家の五木寛之氏が次のように語っています。(日経新聞2008年7月30日)
「僕の言う『鬱』は個人の病気や、短期的な社会の気分ではない。もっと大きな社会の流れとして実感している。日本は高度成長や万博、オリンピックに象徴される『躁の時代』を終え、バブル崩壊後10年の低迷期を経て、今『欝の時代』を迎えたと考えている。
身の回りを見ればすべてが鬱の様相を呈している。がむしゃらに働いたり、遊んだりする躁の生活様式に対し、ロハスやスローライフは鬱のそれだ。エネルギーを消費せず限られた資源でやりくりしようというエコロジーも鬱の思想。予防を第一にするメタボは鬱の医学だし、敵が見えないテロとの戦いは鬱の戦争といえる。躁が50年続いたのだから、鬱も50年続くとみるのが自然だろう」と。
なるほどと思います。
ロールモデルを自分の中からつくる
「アメリカ中心の時代」が陰ってきたことは、日本がアメリカをロールモデルとした時代の終わりを示しだしていると思います。そこで、過去を見習い、次のロールモデル国を探すかですが、それは現在の日本の立場と国際情勢からありえなく、新たなる方向性を見いだすしかないでしょう。
日本は、今その岐路に立っていますが、それは企業も人にもいえる課題です。躁の時代が終わって、欝が長く続く時代に変わったのに、躁の時代に成功した方策を、相変わらず続けていると、時代に合わないのですから、次第に企業実態は悪化し、個人は苦しい環境下になっていくでしょう。
新たなるロールモデル探しが必要です。また、それは、時代の変化・時流に合致した、生き方基準探しともいえ、信念づくりともいえますが、この作業は自らの基盤的なものであって、時代と自分の両方に適合したものでないと、東条元首相と同じ失敗となります。
多分、そのヒントは自分の中に存在する「好きなこと」「得意なこと」を探すこと、つまり、自分の奥底へ向う探検の旅であり、その事へひたむきな努力を続けることであり、また、その努力過程を楽しみにすることであろうと、変化した時流が教えてくれています。以上。
2008年08月06日
2008年8月5日 予測に必要なセンチメント感覚
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年8月5日 予測に必要なセンチメント感覚
山岡鉄舟講演
経営者が集う勉強会の名門である「清話会」で、「山岡鉄舟の生き方」について講演しました。大勢の方が参加されまして、鉄舟の生き方にご関心を持つ経営者が多いことが分かりました。
鉄舟は一身にして二生を過ごしました。幕末の封建時代は徳川幕府に仕え、江戸無血開城という明治維新への糸口を成し遂げ、維新後は少年明治天皇を侍従として補佐し、偉大な天皇になられることに貢献しましたが、生き方思想は常に一貫していました。
つまり、鉄舟の生き方思想は、徳川幕府と明治維新後の両時代を包含する体系となっていたからこそ、時代が変わっても「ブレない生き方」ができたのです。
この生き方思想を、現代的に編集し、今の時代に活かせるセオリーにしようと、山岡鉄舟研究会を毎月開催しているところですが、鉄舟の生きた時代と現代では、グローバル化を含め大きく変化していますので、併せて今の時代・時流研究も行っているところです。
センチメント(漠然感傷感覚)認識になりやすい
その時流ですが、今はデジタル時代で、ヨコ軸で動いているような気がします。世界中から届くマスコミ情報、それはその日の出来事の集計で、翌日になれば、また、新しい出来事情報が届いてきます。あっという間に、今の新しいことは忘れ去られ、次の問題に右往左往させられているように感じます。
加えて教育が、幼稚園から小中学校も高校大学も、同年代の友達中心行われているという、ヨコ並びの学びと遊びのシステムとなっています。
ところが、国の歴史も、社会構造も、企業構造も、すべて過去からの積み重ねで出来上がっているという、タテ軸結果となっているのです。
ですから、過去から延々と流れ続くタテ軸の来歴を知らずして、今の問題解決は成り立たないのですが、ヨコ軸で慣れきっている現代人は、タテ軸で見直すという思考力を苦手にする傾向があり、結果としてセンチメントに認識する傾向が強いと思います。
つまり、「ブレない生き方」を持つことが難しい時代になっています。
長州砲の行方
フランスが戦利品として持ち帰った多くの大砲が、パリのアンバリットに展示されています。この間、それを一つひとつ確認してみました。パリも暑く、汗が滴り落ちます。どこの大砲を探したのか。それは下関戦争で奪われた長州藩の大砲です。
1863年(文久三年)5月、攘夷実行という大義のもと長州藩が馬関海峡(現 関門海峡)を封鎖、航行中の英仏蘭米船に対して砲撃を加えたことから、1864年(元治元年)7月、英仏蘭米の四カ国は、艦船17隻で連合艦隊を編成し、8月5日から7日にかけて馬関(現 下関市)と彦島の砲台を徹底的に砲撃し、陸戦隊が上陸占拠し砲台を破壊し、大砲を奪ったのが下関戦争といわれるものです。
この奪われた大砲について、全部海中に捨てられたという説と、四カ国に戦利品として持ち去られたという見解の両方があることを、鉄舟研究の過程で見つけ、フランスが持ち帰った大砲がパリ・アンバリットにあるという資料を見つけ行ってみたのです。
しかし、2日間にわたる調査でもアンバリットにはありませんでした。おかしいと思い、再度詳しく調べていくと、既に下関長府博物館に戻って保管されていることがわかり、先日、早速、その確認のため下関に行ってきました。
下関長府博物館では、若い男女2人の学芸員の方から、ご親切な説明を受け、資料をいただき、ようやく日本に戻ってきた背景理由を納得しました。さすがに博物館は歴史の事実をタテ軸で捉えており、センチメント感覚ではありませんでした。
世界の動向
このように歴史事実はセンチメントでなく、過去からつながるタテ軸で認識していくことが必要ですが、未来洞察をタテ軸の事実だけからはできません。
例えば、これからの世界の動向、これをどう読み取ればよいのでしょうか。
世界は大きく動いています。昨年のアメリカで発生したサブプライムローン問題は、世界の超大国として君臨してきたアメリカの覇権的地位を、次第に弱体化させています。
そこに加えて、原油高騰などによるエネルギー価格の高止まりは、先進国から資源国へ富の移転を加速させ、オイルマネーは世界のあらゆる金融市場へなだれ込み、政府系ファンドは資金力を武器に新たな展開を始めました。
一方、成長が続くBRICsの中でも、アメリカと輸出入関係が強い中国やインドは、経済成長にかげりが見られ、世界経済の先行きは一段と不透明になってきました。このような動向から、今やアメリカによる覇権時代は終わり、新興国にパワーシフトが急速に進み、新たなる国家群の幕開けになる、というような見解が一部でなされ始めています。
そこで、これら見解の妥当性を判断するためには、過去の事実認識の積み重ねに加えて、未来洞察という作業が必要ですが、未来は不確定要素ですから、どうしてもセンチメント感覚で行うことになります。
ですから未来予測は難しいのです。
中国人女性実態・・・その二
経済成長にかげりを見せ始めたオリンピック開催の中国。その動向変化は日本に大きく影響しますので、中国の未来をどう見通すかは大きな課題です。この場合の洞察もタテ軸としての歴史事実に、センチメント感覚を加えていくことになりますが、それを検討するひとつの材料として、中国人女性を一人、前号に続いてご紹介したいと思います。
それは上海の30歳独身女性です。上海は住所表示が大雑把で分かりにくく、何回も人に尋ね、ようやく訪ねる住居のアパート群の中に入っていきますと、ジャンバー姿の姿勢のよい女性が犬を連れて散歩風に立っていました。この人かな、と思って近づくと頷き、犬を連れて自宅前まで案内してくれましたが、とにかく姿勢がよく、身長があまり高くないのにすらっと見えます。
三階の部屋に入ると、すぐに気がつくのは正面の大きな等身大の鏡であり、鏡は洗面所にも寝室にも洋服ダンスにも、ベッド枕上の窓近くにグリーンデザインの丸鏡、それと机の上にも平面の卓上鏡があります。
これだけ鏡を持っている中国人は少ないので、鏡という存在について少し説明しました。「自分を見つめようとする意識が強い人が鏡に興味があり、たくさん持っていて、その人は鏡を見つめることで自分探ししているのではないか」と。
そうすると本人が語り始めました。大学は映画を専門に勉強し、大学院でも同様で、映画プロデューサーになろうとしたが、上海の現実は問題があり、夢どおりにはならず、今は銀行に勤めている。学校時代は成績優秀だった。趣味は幼い頃からバレーを踊っていたことと、中国古典楽器の演奏。旅行は自然のあるところに行くのが好き。外国にはまだ行っていない。行きたいところは北欧。山と湖が好きだ。上海は人多く空気が悪いから。
将来の目標として特に大きな希望はなく、家族と楽しく話し合って仲良く暮らすことで、自分に素直に生きたいという。
そこで、上海の人はお金持ちになりたいという希望が強いだろうと聞くと、そういう人が多いが、自分は違う。お金にはあまり関心がない。お金を求めていくと人生にひずみが出るだろう。お金を持ちたい人はそれでよい。そういう人にお金は譲る。自分は自分の気持ちに素直に生きたいのだ。仮にそれによって問題が起きても、それでよいのだ。自分の人生は自分が生きるのだから、と言い切ります。
何か宗教を持っているのですかに、無宗教との答え。それぞれ価値観が異なる人が、それぞれ生きていくのが現代だろうともつけ加えます。正にグローバル時代の生き方です。
この女性に会って、上海人の中にも、お金至上主義者だけでない人がいることがわかったが、今まで会った多くの中国人は、とにかく金々という人たちで、中国人は儲けのためには何をしてもよい、という人ばかりのイメージが続いていた。
今は経済至上主義下の中国で、その最先端が上海。モノの豊かさが行き渡ると、多分、今度は自分とはどういう存在なのか、という段階に至ってくる。今の日本人がその段階だが、その時点になって、改めて、自分とは何ものか。自分とはどのような意味合いで生まれてきたのか、ということを問い直し始めるが、その時点にいたっているのがこの女性だろうと思い、その旅を今後も続けて欲しいと、エールを送って失礼しました。
中国のタテ軸事実、既に把握されている中国実態、紹介した中国人女性の生き方二事例、そこにご自身のセンチメント感覚を加味し、中国未来予測するのも夏日の一興です。以上。
2008年07月21日
2008年7月20日 ガラパゴス化現象を避けたい
環境×経済×文化 山本紀久雄
2008年7月20日 ガラパゴス化現象を避けたい
ガラパゴス化現象
南米エクアドルの900キロ太平洋上の沖合に、ガラパゴス諸島があります。ここはダーウィンが進化論のアイディアを持った場所として有名ですが、諸島内には独自に進化をとげた固有の生物が生息しています。大陸から隔絶された環境下であるため、他の環境の影響を受けなかったためです。この事例が日本に例えられることがあります。
一億人超の人口を持っているがゆえに、日本固有の商慣行や独自の技術や機能サービスにこだわって、世界とは異なる市場になっている業界を指すのです。具体的には日本の携帯電話です。世界最高水準の技術を活かして、海外企業では真似できない機能を盛り込んでいますが、世界市場ではほとんどシェアが取れません。独自の進化をとげている間に、世界では機能要求水準の低いレベルで、事実上の使用標準が決まり、その標準下で拡大成長し、日本は取り残されたのです。
競泳水着の敗北
ミズノの社長が、英スピード社と競泳水着の着用競争で敗北した結果について、以下のように語っています。(日経新聞2008年7月6日)
「ミズノが開発した水着は選手の要望を完全に満たしていたと思う」「過去のスピード社の水着開発は我々も一緒にやってきたという自負がある。ところが実際は海外選手から直接、要望を聞いたことはなく、体形データすら取っていなかった」と。
この発言からいえることは、ミズノはスピード社と提携していたことと、選手の要望を完全に満たしていたのに負けた、という奇妙な思考力を持っていることです。
負けたのは、要望を完全に満たしていなかったことと、日本人選手だけに対象を絞って水着開発をしていたからで、ガラパゴス化現象ともいえるのではないでしょうか
脳の構造
養老孟司氏が次のように述べています。
「10年前の自分の脳にあった記憶と、今の自分の脳に入っている記憶とは、果たして同じだろうか。体をつくっている物質はほとんど入れ替わっている。同じ事柄について同じ記憶を保っていると、本人が確信しているだけで、脳全体が変わってしまえば、違いがあっても気づかないはずだ。別の言い方をすれば、その時々のその人の脳にとって整合性があるように、つまり覚えやすいように記憶を変形させている」と。
これは怖い発言です。つまり、過去のストーリー性のある記憶はアテにならないということなのです。自分にとって覚えやすいように、説得力あるように、勝手に脚色し編集してしまうのが脳だ、といっているのです。脳は過去を思い込みにするのです。
篤姫
しかし、この脳の思い込みは、過去の歴史を現代に蘇えさせ、多くの人に共感を得るという作業に活用できます。つまり、ある優れた人物によって、歴史を脚色し編集するという意味ですが、その優れた脳力基準とは、今という時代への感覚度合いです。鋭い時代感覚があれば、歴史を今に蘇えさせられます。
その成功事例がNHK大河ドラマ「篤姫」と思います。
天璋院篤姫は第13代将軍家定の御台として、家定死後は第14代将軍家茂に嫁いできた、孝明天皇の妹・和宮(静寛院宮)とともに、徳川家を守ろうと江戸無血開城を成功させるストーリーですが、これまでの展開では、本土最南端の薩摩の地で、桜島の噴煙を見ながら、錦江湾で遊ぶ純朴で利発な一少女が、将軍家の正室となり、3000人もの大奥を束ねるという、ただならぬ人生の歩み、それを史実とドラマフィクションとで上手に描き、それが多くの視聴者に受け入れられています。
このように、過去の歴史を今の時代に共感させるためには、現代人からの認識、理解、共鳴、同感が条件ですが、この点で「篤姫」は成功しているのです。
大奥が中国で大ヒット
中国でもこれまで韓国ドラマが、高い人気を誇っていました。いわゆる韓流ブームで、日本と同じでした。だが、このところ日本と同様、中国でも韓流ブームは凋落傾向で、 韓国ドラマの不振にとって代わったのが、しばらく鳴りを潜めていた日本のドラマです。
中国の日本ドラマの輸入は前年比30%以上も増えていて、その象徴が今年4月に放送された「大奥」です。放送開始直後から人気を呼び、4月7日の夜には中国全土で2000万人もの人々が、この時代劇ドラマを見たのです。
関係者によると、マンネリ化傾向の韓国ドラマに対し、題材が幅広く、俳優陣も多様、ストーリーのテンポが速い点、それが日本ドラマが評価されている理由とのことです。
このように大奥が受け入れられたということは、徳川将軍の江戸城という特殊性を、時代感覚で脚色し編集し直すと、中国人にもわかるという事実、つまり、物事を世界標準にしていけば、異なる国、過去に問題を抱えている国でも、受け入れられていくという意味につながります。
また、中国人もこういうドラマを通じて、日本に対するかつてから持っている認識を、変えていく可能性もあります。
中国人女性の実態
その中国、オリンピック開催が間近に迫っていますが、大地震に襲われた四川地域の復興課題や、いまだ尾を引いているチベット問題、加えて、猛烈なインフレと頻発する各地の暴動、さらに多くの労働争議による「世界の工場」の揺らぎなど、様々な問題が山積しているとマスコミ報道が伝えて、これは事実と思います。
では、これらの状況下で生活している一般の人々は、どのような実態なのでしょうか。マスコミが伝える諸問題のように、個人も動揺して生活しているのでしょうか。
例えば、大奥をみた人たちの多くは、二億人ともいわれている中間所得層であって、テレビの前に座った視聴者は女性が多いと考えられますが、その人々の生活はどういう状況なのでしょうか。今年3月と6月に訪問し、北京と上海でお会いした数人の実態、それを今号と次号に分けてご案内したいと思います。
(専業主婦を楽しむ)
最初はAさん26歳。北京の18建マンション三階に住み、結婚して二年で、子どもはいないし、仕事もしていません。夫は37歳で国営企業の管理職。
Aさんは子ども時代に両親が亡くなり、国からの援助金で学校を出るなどして、苦労して育ちましたが、成績が優秀だったのでマンション販売会社の営業に就職できました。
ある日、一人の男が販売事務所にやってきました。営業担当のAさんが早速対応したわけですが、そこで彼はAさんに一目惚れし、Aさんが推奨するマンションを買うことになりました。その男が今の夫で、その買ったマンションに二人が住んでいるのです。
夫が買ったときは一㎡6000元(1元=16円換算で9.6万円)でしたが、今は15000元(24万円)と倍以上となっています。広さは2LDKの南向きで、ベッドルーム二部屋と広いリビング。テレビは大型壁掛け式で、ベッドルームにも薄型テレビがあります。
趣味は欧米式の刺繍。スポーツはクラブに行ってバドミントンを楽しみ、旅行が大好きで、タイ、マレーシア、シンガポール、サイパンに行きました。日本にはまだ行っていないが、興味あるところは原宿、秋葉原、富士山、箱根、北海道、銀座とすらすらと日本の地名が出てきます。イメージを聞くと銀座は買い物天国、箱根は温泉と答えます。
歌舞伎に興味あったので、以前に日本語学校へ通ったことがあるので、日本語が少し分かります。壁を見ると結婚式の写真が掛かっていて、夫が色白で少し歌舞伎役者に似ているので、それを伝えると笑い、今来るからとまた笑います。
実際に現れた夫は写真と反対の色黒で、タバコ吸うので歯が脂で真っ黒。夫は会社の慰安旅行で毎年海外旅行に行くといい、日本、サイパン、タイ、マレーシア、シンガポールに行って、今年はスイスに行く予定だといいます。さらに、中国人は頭がよく、経済成長はこれからも続くと明確に発言します。
なるほど、これがよく言われる「PRIDE of CHINA(中国の自負心)」かと、感じた次第です。次号も中国人女性の生活実態事例を続けてご案内します。以上
2008年07月05日
2008年7月5日 日本人は自由発想が好き
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年7月5日 日本人は自由発想が好き
渋谷の街
渋谷山本塾が始まって、毎月、第二金曜日の夕方、渋谷の繁華街に向かい、終了後の懇親会で様々な業態の飲食店に入ります。ハナ金という表現は古いのでしょうが、どこも若い人が一杯、店側の対応も声が大きく、はっきり明確、元気一杯です。
渋谷から原宿一帯は、欧米ファッションデザイナーたちが「ストリート・ファッション」の世界的聖地と称し、デザインアイディアを求めて来るところとして有名ですが、渋谷を歩くたびに、その意味を再確認しています。
また、それを証明するのが、渋谷発のカジュアルファッション「ア・ベイシング・エイプ」で、今や世界中の若い層から支持を受けるグローバルブランドとなりました。
町屋の街
荒川区の町屋でも山本塾を開いています。ぬりえ美術館での開催です。町屋は渋谷と大きく異なる不思議な街です。昔がそのまま残っていて、通りには懐かしい都電が走り、そこに都内とは思えない昔スタイル姿の商店が並んでいます。また、店と店との間にはいくつもの路地があって、この路地奥に入り込むと、はじめての人は必ず方向感覚を失います。
これは断言できます。何回も挑戦してみた結果の断言で、入り組んだ路地からの脱出は極めて困難となって、そこを歩いている地元人に尋ねますと、一様に困った顔をします。
住民であるからこの地区の路地に精通して迷わないのですが、はじめての人に説明するのは難しいのです。何故難しいのか。それは目印となる存在物、例えば郵便局とかコンビニとかが、路地内に存在しないため、漠然としか説明できず、説明するほうも、受けるほうも一様に困った顔となる街、それが町屋です。
好きなことを仕事にしている
その町屋で音楽関係者の方と食事する機会がありました。知人が「山本さんは、いろいろ好きなことを仕事にしている人です」と私を紹介しますと「いいですねぇ」との返答です。こちらから考えると、音楽が好きでプロになっているのだから、そちら様のほうが羨ましい立場だと思いましたが、そのまま笑って過ごしました。
最近、このような形で私が紹介を受けることが多くなりました。世界の牡蠣、日欧温泉、ぬりえ研究、世界旅行記と山岡鉄舟の雑誌連載、経営コンサルタント業、確かに様々な分野に広がっており、勝手気ままな仕事をしていると思われているかもしれません。
形はその通り
表面に顕れた形はその通りです。さらに、本の出版分野も相互関係がないので、よく「混乱しませんか」という質問を受けます。これへの回答は「全く混乱しません」とお答えしています。人から見た自分への評価は、概ね妥当なことは言うまでもありません。自己評価は自分を的確に見ていないことが多いのです。
しかし、知人が私を紹介した内容については、違うと思っています。表面上に形として顕れているのは、様々なテーマを扱っているので、異なる分野と思われるのですが、それを進めている当事者としては、すべて「好きな」分野の範疇内なので違和感がないのです。
考えることを作業化している
実は、本当に「好きな」ことは「考える」ことなのです。
といいますと、哲学的や思索的なことを思い浮かべるかもしれませんが、そうではなく、日頃の行動を「考える」ことのシステムに結び付けることが好きなのです。
私の専門である脳力開発では、考えるということを五つの行動に分類します。まず「集める」「分ける」「比べる」「組み合わせる」「選ぶ」という五段階です。考えるという行動を分析すると、どのようなパターンでも、また、対象の軽重差があっても、必ずこの五つのシステムステップに集約します。
ですから、日頃から意識して、このシステムステップを継続していますと、どんな対象・問題・テーマが来ても、対処できることになります。
つまり、形は異なる仕事でも、すべてこの好きな「考える」システムステップで進めていますので、自己矛盾なく、結果として割合自由な発想を浮かべることができるのです。
ソウルの新聞記事
朝鮮日報というソウルの新聞があります。そこに「『国民総魅力』で世界をリードするお隣ニッポンを見習え!」という記事が掲載されました。
内容を一言で述べますと「現在の日本は経済大国から『文化大国』へと姿を変え、世界で最も魅力的な国のひとつになり、それを活用して、金を生み出し、富を創り出す『ソフトパワー』の経済モデルをつくった」というものです。
その背景には、2005年に発表された経済産業省の「新日本様式・ネオジャパネスク」という報告書が存在すると分析し、付加価値の源泉が「量から質」、さらに、「質から品位」へ移行させ「21世紀版ジャポニスム」の栄光を目指しているとあります。
各国の肯定的影響調査結果
英国BBCが世界34カ国、1万7000人に対し、指定した14の国・地域のうち「どの国が世界によい影響を与えると思うか」を2008年4月に再び調査しました。
結果は、日本とドイツを挙げた人が最も多く、昨年に続き日本の魅力が高いことを、世界の客観的調査結果が明らかにしてくれました。因みに、最下位はパキスタンで、その次はイスラエル、イラン、北朝鮮と続きます。何となくイメージでわかります。
ホテル関係者のアンケート調査
大手オンライン旅行社エクスペディアが、ホテル関係者4000人に行ったアンケート調査で、総合的に最も評判のよいのは日本人という結果が出ました。
逆に最も行儀が悪いのは英国人、続いてロシア人、中国人であり、最も声が大きくうるさいのは米国人、最も静かなのは日本人とドイツ人という結果です。
確かに、6月末にドイツ鉄道ICEでフランフルトからミュンヘン、それとTGVでパリに行きましたが、ドイツ人は車内で静かです。日本の新幹線並みです。また、ドイツのホテルの朝食でも皆静かに食事していますから、このアンケート結果は妥当だと思います。
国際フェスティバル
ドイツ南部の街カールスルーエでは、ちょうど国際フェスティバルが開催されていましたので、そこへ参加しました。ここは人口27万人、ドイツ最高裁判所や原子力研究所があって、城を中心に、道路が放射線状に造られている落ち着いた品格のある街です。
会場には国際フェスティバルの名にふさわしく、何十カ国の関係者が集まって、屋台や特産品販売、舞台での踊りやコーラスが朝から深夜まで行われ、大人気でした。
日本コーナーは浴衣をピチっと着こなしたドイツ人女性が対応し、舞台では日本人とドイツ人の混声合唱、曲は日本語で荒城の月、ホタル来い、サクラ・サクラ、村祭り、ソーラン節。特に最後のソーラン節は迫力があり、太鼓のリズムと合致し、観衆から大拍手でした。この現象を見ていますと、諸外国もそれぞれ趣向を凝らしているのですが、どうも日本の人気が頭ひとつ他国をリードしていると感じました。
ソウル新聞記者の疑問解消
前述のソウル新聞記者が、どうして日本文化はこんなにもパワーがあるのか、という疑問を持ちつつ、それを解消したのは、ある大学教授の次の発言からと書いています。
「日本はすべての事物に神がいるという汎神論の国です。石にも木にも川にも神がいると信じられていた。そのため森羅万象に人格と生命を与え、自由自在に擬人化することが出来る。だからアンパンから『アンパンマン』というキャラクターを生み出せるのだ」と。
なるほど、形として表に顕れている日本のキャラクターや、ファッションやソフトパワー、それを生み出す根源に汎神論があって、そこが唯一神の諸外国とことなるという見解ですが、そうだろうと頷きつつ、もうひとつ大事な要素があると思います。それは日本人が、何ものにも神が宿っていると信じることを、本来「好きな」国民性だということです。
自由な発想を浮かべるには、「好きな」ことを行うという前提が重要と思います。以上。
2008年06月20日
2008年6月20日 ビル・エモット氏の進言
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年6月20日 ビル・エモット氏の進言
上海現代美術館
前回レターでお伝えしました、イタリア・フィレンツェのフェラガモが、ブランド回顧展を行った上海現代美術館、そこへ6月初旬に訪れてみると、今度は「四川大地震写真展」が開催されていました。被害状況の生々しい写真が大型サイズで展示され、大災害ということがよく分かると同時に、救済・復旧活動の写真も数多くあって、外国からの救援部隊の活躍も掲示されていましたが、写真展示国はロシアと日本だけです。
多くの国から支援を受けているはずなのに、二国の写真しか展示されず、そこに日本がはいっていること、それは「日本の援助に感謝する」という発言を、北京でも上海でも一般人から多く受けましたが、それを証明する上海現代美術館であり、今の中国の日本に対する感情を表していると思いました。
その反面、韓国に対しては「問題だ」という発言が多く聞かれました。韓国も空軍機で救援物資を送るなど積極的な支援活動をしているのに、中国は韓国に対して反発感情を持っているのです。
ソウル
その韓国ソウルに入ったのは、ちょうど李明博大統領が就任して100日目で、ソウルは反政府デモで大変な騒ぎでした。大統領がソウル市長時代に環境再開発に成功し、ソウルの気温を二度下げたといわれる清渓川の前広場で、「MB反対」の幟が翻り、MBとは李明博を意味する頭文字で、加えて「民心・天心」の旗、つまり、民の気持ちを取り入れて政治を行えという意味ですが、米牛肉輸入問題だけでなく、国宝一号指定の南山門焼失で、ソウル市長時代に対処した警備手薄を追求されていることや、物価上昇・公企業民営化・経済低迷など多様な問題が輻輳し重なり大騒動になっているのですが、この発端はオリンピック聖火リレー問題だろうと推察します。
聖火リレー
北京オリンピック聖火リレーは、チベット問題によって世界中で騒乱を巻き起こして、4月26日に長野に入りましたが、ここでは若干のトラブルあったものの無難に終え、その翌日はソウルに移りました。
ソウルでは大問題化しました。チベット問題提起の韓国・欧米人に対して、韓国にいる中国人留学生が石やペットボトルなどを投げつけ、怪我人が発生、中国人が逮捕されるという騒ぎとなり、外交問題化していたのです。
中韓関係
韓国の李明博大統領が就任後初の中国訪問で、5月27日に北京に入ったその日に、中国外務省報道局副局長が「米韓軍事同盟は歴史の産物。冷戦時代の軍事同盟では安全保障問題を解決できない」と外交政策を批判しました。
これに対して韓国側では「胡金濤主席との初の首脳会談直前に相手国の外交政策を批判するのは礼を欠く」と非難応酬し、さらに、中国外務省のホームページに、訪問した27日まで韓国の国家元首として、前大統領を掲載していたことも判明し、両国の関係は微妙な関係に陥っているのです。
善光寺阿弥陀如来の御利益
このような中国と韓国の関係が、北京・上海における中国人の態度にも反映し、上海現代美術館の「四川大地震写真展」に、韓国救援部隊の写真がなく、日本が展示されるという伏線になったと推測しますが、その起因を辿っていけば、ソウルの聖火リレーが警備体制のまずさから、中韓両国に外交問題を発生させたことが発端と思います。
一方、長野での聖火リレー、警備は大変でしたがトラブルは最小限に抑え、その要因としては、善光寺境内からの出発を取りやめたことが影響したと思います。
仮に善光寺境内から出発し、国宝の本堂に重大な瑕疵が生じたならば、問題が発生したはずで、その危険を避け、警備体制がとりやすい地区からの出発へ、善光寺の意思で変更させたこと、これがトラブルを抑えた最大要因であり、さすがは善光寺阿弥陀如来の御利益と思っていますが、いかがでしょうか。
過去経験
しかし、今回は中韓関係の微妙さもあり、四川大地震救援活動で「日本の援助に感謝する」という見解が強く出され、胡金濤主席の日本訪問も問題なく終わりましたが、過去の経緯をたどれば、中韓両国とも「国内問題が発生すると、国民の眼をそらすため、日本の戦争責任へ振ってくる」ことが多々ありました。
そのことが日本の最大の弱みだと主張するのは、イギリスの元エコノミスト編集長であるビル・エモット氏です。この度出版した「アジア三国志」(日本経済新聞社出版社)で次のように述べています。
「日本の最大の弱みは歴史と、歴史を過去のものにするのに何度となく失敗していることだ。教科書問題、靖国参拝、戦時の強制労働や慰安婦への補償、第731部隊や南京事件のような残虐行為のどれについても、中国と韓国は歴史的事実に関する議論や争いに乗じて、道義的に優位に立ち、日本を守勢にまわらせることができる。中韓は、それぞれの世論を煽ったり、世論に反応して、国内政治にこうした問題を利用している」
靖国神社参拝
6月15日の父の日は、山岡鉄舟研究会イベントで靖国神社参拝と史跡探訪を開催しました。あまり暑くない天候に恵まれ40名余の方々が、靖国神社の奥深くで正式参拝をし、その後遊就館で同館の大山課長の武士道の講演を受け、遊就館内をご案内していただきました。参加者の中には、身内が戦争でお亡くなりなった方も多く、大きな感動をもって見学されましたが、案内の最後は「大東亜戦争がアジア各国の独立に貢献した」というパネルと資料の前でした。大山課長は「ここはマスコミには敢えて説明しないところです」という前提でのご説明でしたが、納得するところが多々ありました。
というのも昨年インドを訪れたとき、2006年3月にコルカタ(カルカッタ)のチャンドラ・ボース記念館から「インドの独立に対する貢献」の感謝状、宛名は「内閣総理大臣東条英機殿」で孫の東条由布子さんに贈られた事実を確認していたからです。
だがしかし、このような日本の主張・見解については、中韓両国の立場からは認めがたく、日本の政治家発言が過去に両国と何度も火種を起していますので、大山課長はマスコミを避けているのですが、このところを正面から突破させないと、いつまでたっても中韓両国から追及される結果が続くと思います。
ビル・エモット氏の進言
この永遠に続きそうな追求への解決策を、ビル・エモット氏は次のように進言します。
「中国と韓国にとっては、歴史問題をそのまま残しておくほうが政治的に有利だ。歴史的な恨みを飯のタネにしている低レベルの組織や市民団体にも、往々にしてそれが当てはまる。だが、日本政府がやる必要のある行動そのものは、そう多くない。
もっとも賢明な措置は、歴史的事実の正誤や改悛の念という全体をひっくるめた抽象的な問題を、特定の出来事や苦情の責任、謝罪、悔恨と切り離す作業だろう。
別のいいかたをすれば、東京裁判のパール判事が意見書で述べた反対意見を銘記するということだ。パール判事は、旧日本軍の残虐行為については日本は有罪だが、戦争を国家政策の道具に使ったという全体の告発については、偽善的であり、法的には不合理であるとした」(アジア三国志)
国家戦略
つまり、ビル・エモット氏は「日本が戦争せざるをえなかったことは無罪」ということを国家戦略・目的として成し遂げる必要があり、その手段として「旧日本軍の一般人への残虐暴力行為については、改めて首相か皇族が中韓両国の主要地に出向き謝罪し補償する行動」をとるようにとの進言です。なるほどと思います。戦争責任という抽象的問題を、二つに区別し、それを戦略と戦術に分ける思考方法です。
この検討が、中韓両国との未来関係改善への布石となるのではないでしょうか。以上。
2008年06月05日
2008年6月5日 中国の消費意欲が日本を再認識させる
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年6月5日 中国の消費意欲が日本を再認識させる
北京オリンピック
北京の街中を歩いて妙なことに気づきました。どこにも8月8日開催のオリンピックの看板、ポスター、垂れ幕、横断幕、スローガンがありません。もう開幕まで二ヶ月に迫っています。メインスタジアムは完成し、予行競技も開催されましたので、北京市内に「北京オリンピックを成功させよう」というような表現があってもよいし、当然あるだろうと予想していましたが、全くありません。
勿論、テレビではオリンピック開催準備状況の報道をしていますが、PR掲示がないことを地元の北京人に聞いても「それは質問されるまで気がつかなかった」という実態です。ホテルのバーで隣り合った韓国人に聞いてみると、それは「四川大地震のせいで抑えているのだ」とすぐに語ります。そうかと思いますが本当かどうか分かりません。不思議です。
北京大学図書館
この雰囲気は北京大学でも感じました。北京大学図書館に行くため校内に入りましたが、学生が歩いているだけで、特別の催事・お祭りを迎えるというムードはありません。
図書館は北京大学の学生が利用するか、外国人の見学しか出来ません。一般人は入れませんので、中は大学生だけです。感心したのは学生が熱心に勉強していることです。閲覧室の椅子はほぼ埋まっています。その机で静かに本を読み、写し、書きしています。真面目だというのが第一印象です。
図書検索データで探し、目的の本を見つけ、それを閲覧請求するとすぐに書庫から出してくれ、受け取り、本を開いてビックリしました。全く違和感がないのです。何となく理解できるのです。理由は漢字です。日本語と同じ漢字で書かれているので、漢文を読むのと同じように読めば、ある程度分かります。つまり、今の中国の漢字ではないのです。
1912年に成立した中華民国37年版本ですから、1948年の印刷ですので、昔の字体なのです。次にコピーを依頼すると、目の前ですぐにしてくれます。これも意外です。顔つきは不親切・仏頂面の係員が、親切サービスをしてくれるのに驚きましたが、図書館内にもオリンピックポスターらしきものはありません。
オリンピック長者
しかし、一歩大学を出ると、そこは猛烈な渋滞とビル建設ラッシュが続いていて、いたるところ粉塵が撒き散って、もともと悪い空気がさらに悪化しています。
メインスタジアムの「鳥の巣」周辺は、粉塵濃度が五段階で上から二番目の「4」、繁華街の建国門外は最悪の「5」で、「数人がたばこを吸っている狭い部屋で生活するようなもの」というレベルです。肺にも喉にも悪いのですが、これがオリンピックが近いことを示している一番の状況と感じました。
もう一つ感じたのは、「鳥の巣」からさほど遠くない「天通苑北」という新興住宅地に入ったときでした。真新しいマンションが広大な土地に立ち並んでいます。ここはオリンピック開催に伴う再開発による立ち退きで、政府から多額の補償金を得た「オリンピック長者」が多く住んでいるところです。
人民大会堂の裏から移り住んだ夫婦、古い家に対して、平均年収の60年分に当たる
130万元(約2100万円)が入り、この「天通苑北」で3LDKを30万元で購入、マイカーや高級家具、息子に別のマンションを買っても、まだまだ残ってお金持ちになったという事例など、枚挙に事欠きません。
影もある
だが、オリンピックでお金持ちになった人ばかりではなく、開発されない地区の人々は、昔の貧しい中国の実態のままの生活をしています。
その事例は北京市北東部の「黒橋村」です。金持ちが住む「天通苑北」から車で30分、そこは探すにも苦労するほどの、幹線から奥まった袋小路の一画で、舗装されていない土埃の舞う細い道路がくねくねとつながり、両側は小さな狭い汚い店が立ち並び、殆ど外部から人が訪れないところです。歩いていて危険は感じませんが、写真を撮ることはやめておこうという雰囲気を感じさせる、オリンピックと経済成長から取り残された「貧困村」です。
すべてのことには、必ず両面があるという事実を証明している事例と思います。
家の中と英語力
しかしながら、数軒訪問した二億人に育った中間所得層のアパートメント、そこにはいずれの家も大型の薄型テレビがリビングにあり、寝室にも壁掛けテレビがあって、オリンピック開催にタイミングを合わせて購入したといい、応援するスポーツの入場券も買ったと発言するように、一般市民はオリンピックムードに入っています。
ただし、訪れる側から見た心配事は英語力です。北京空港からタクシーに乗って、ローマ字で書いたホテル名メモを見せると「分からない」という仕草、漢字で書くと走り出します。日本人は漢字が書けるから何とかなりますが、他国の人たちは相当困ると思います。
だが、英語が通じないのとは関係なく、街中には欧米ビジネスマンが溢れています。その理由は、本質的に中国に対する期待を強く持っているからです。
フェラガモの上海記念式典
欧米人を集めている背景を一言で語れば「消費意欲」です。3月28日に創立80周年を迎えたイタリアの老舗ブランド・フェラガモは、記念式典を本店のあるフィレンツェではなく上海で開催し、中国有名スターを招いたオープニング・セレモニーは全国ネットで生中継され話題を呼びました。
上海で開催した理由は「売り上げの47%がアジアの消費者によるもの。なかでも中国は全体の売り上げの10%も占めているから」と最高経営責任者のミケーレ・ノルサが語り、今年だけでも中国に新たに8つの店舗をオープンする予定だと言い、上海現代美術館でブランドの回顧展を大々的に行いました。
今後の売上増加策の切り札としているのです。
中国人の日本人気場所ベストスリー
その「消費意欲」の中国人が日本にも溢れています。
中国人の人気場所ベストスリーは秋葉原、銀座、大阪心斎橋筋。どこでも群をなしているのですぐに分かります。ビザの関係で個人旅行は難しいので団体となり、その層は金持か優良国営企業の社内旅行です。
まだ、二億人といわれている中間所得層の外国旅行は少ないのが実態で、秋葉原でデジカメ10個買った、銀座のワインセラーで100万円のロマネ・コンティを買ったというのは金持ちの中国人です。また、心斎橋筋は異国情緒があって、物が安く、タコヤキが美味いと、訪日必見コースとなっていて、先週の大阪出張時に、心斎橋筋を旗持った添乗員の後をぞろぞろ歩く中国人を何組も見ましたから事実と思います。
金持ち中国人にとって日本は買い物天国です。
日本の品質
先日、ある企業へ訪問し幹部とお話しする機会がありました。幹部は昨日ニューヨークから戻ったばかりだと話しながら、実はニューヨークの得意先に召集をかけられ、急遽行ってきたのだと話してくれます。召集されたのは納入した部品の不良率が高すぎるので、その対策会のためで、集まったのは世界の部品メーカーです。
会議で配られた不良品のリスト、それを見てこの幹部はビックリしたのです。自社の不良品は一個もない。全部他社のもの。つまり、外国メーカーの部品だったからです。
では、どうして召集をかけられたのか。それは不良品が一個もない企業があるという事実、それを他の外国メーカーに示したいから、わざわざ呼ばれたのです。
外国メーカーの前で「何か一言話せ」と要望されたということですが、日本企業の品質レベルの高さを証明する事例です。
時代の風は日本に吹いている
中国人の消費意欲に対応すべく、世界中のメーカーが中国シフトを敷き、中国で激しい販売競争が展開される結果、そこで何が発生するでしょうか。多分、品質格差競争になるでしょう。
そうなると最後に販売シェアを握るのは、品質に勝る企業、それは日本になるだろうと予測し、中国人の猛烈消費意欲が日本のレベルを再認識させると思います。 以上。
2008年05月20日
2008年5月20日 二つの二億人
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年5月20日 二つの二億人
景気は足踏み状態
今回は少し経済状況について考えてみたいと思います。日本の当面景気は、次の三つが重なって「雨傘用意」という状態ではないでしょうか。
1.米国サブプライム問題
これは、毎日のように新聞を賑わして、すでに一年近くになろうとしていますが、まだ解決の方向性は見いだしていません。発生要因は単純なのに、要因を切り刻んで複雑にする「金融高度テクニックによる証券化」によって、要因をミートホープ化にしてしまった。
つまり、北海道・苫小牧市のミートホープ社が行ったこと。それは、牛肉の挽肉の中に豚肉を混ぜたり、色の悪い肉に血液や漂白剤を混ぜて色を変えたりしたことで、本来の牛肉がどれであるのかが分からなくなりました。これとサブプライム問題は同じと思います。
2.一次産品価格の高騰
原油のWTI(ウエスト・テキサス・インターミディエート)価格が130ドルを目指そうという勢いです。産油国はドル安で輸出代金の減少を補おうとする見込みもあるのでしょうが、とにかく騰がりすぎです。小麦も騰がって、食料品価格に値上げが続いて、インフレ懸念が景気に影響してくると思います。
3.建築着工の大幅減少
昨年6月の改正建築基準法の施行以降、住宅着工戸数が大幅に減少し、建設財出荷が低水準となっています。6月以降は前年対比で向上すると思いますが、これは昨年大幅に落ち込んだ「揺り戻し」ですから、必ずしも楽観視できないと思います。
世界の経済の流れは変わった
世界経済は、2005年から2007年の間、米国及び先進国の景気が緩やかに減速するなかで、BRICsなど新興国の個人消費や固定資本投資などの内需によって成長しました。結果は、世界のGDPに占めるシェア、2007年で先進国は47%、BRICsなど新興国は53%と逆転しました。2000年では先進国は55%、新興国は45%でした。米国のシェアも2000年が21%台、2007年は18%台に下がっています。
明らかに世界経済の流れは変わっています。米国一辺倒の政策は時流ではありません。
トヨタ自動車の決算
そのことの証明がトヨタ自動車の決算です。2008年3月期はゼネラル・モーター社を超えて世界一の売上高、利益も過去最高を更新しましたが、2008年1月から3月までの四半期決算内容を見ると、これまでドル箱だった北米市場で営業損益が124億円の赤字に陥りました。原油高と個人消費の冷え込みが影響し、高い車が売れなくなって、利益率が低い小型車にシフトしたことが大きいようです。
今後の懸念
今後、懸念される材料は二つの二億人です。
1.中国の二億人
まず、最初は中国です。ご存知の通り、中国は高成長を続けています。それは人口13億人ともいわれる中で、中間所得層の人が育って、その人数が二億人いると推定され、これらの人々の消費行動が変わって、内需が向上、それを目指して世界中から企業が進出し、世界経済に大きな影響を与えています。
しかし、このところの中国は少しツキが欠けてきた感がします。胡錦濤主席の日本訪問は無難に終わりましたが、北京オリンピックを目前として、次々と問題が発生しています。
今年1月の冷凍ギョーザ中毒事件、まだ解明されていません。3月のチベット騒乱、国際社会に懸念が広がりました。株価も下落しました。昨年10月に6092ポイントの最高価格をつけた上海総合指数は、今年4月に3000ポイントを割り込みました。インフレも2月は前年同月比で8.7%、3月は8.3%、4月は8.5%と高く続いています。
そこに四川大地震が発生し、被害は甚大です。世界各国から支援を受け入れ、大変な状況ですが、時間経過と共に被災地も復活してくると思います。
だが、このような経済的マイナス状況によって、中間所得層二億人の内需に影響が出始めますと、世界経済に大きな打撃を与えることになります。
2.米国の二億人
①超格差社会
米国の二億人の説明に入る前に、米国の格差社会の実態を整理しないと問題点が見えてきません。米国は大きく四つの階層に分かれています。(アメリカの真実 小林由美著)
一つは資産1200億円以上の超金持ち400世帯と、120億円以上金持ち5000世帯、これらが「特権階級」を構成しています。次は「富裕層」で、資産12億円以上の
35万世帯と、年収2000万円以上の460万世帯で構成しています。
最下層は年間所得230万円未満で、スラムに住む人、黒人、ヒスパニック、インディアン保留区に住む人たちですが、この層が全体人口の25%から30%いると推定されています。この3層で全体の35%占めます。
残りは65%で、米国全体人口三億人の65%は約二億人となり、この層が実はサブプイムローンの対象層人口なのです。
②「特権階級」「富裕層」と「最下層」は影響なし
先日、シリコンバレー、デトロイト、ニューヨークの不動産事情を視察してきました。
結果は、金持ちが住む地域と、活発な経済活動の地域は、サブプライム問題の影響はないということが分かりました。勿論、最下層地区も影響はありません。
まず、シリコンバレーのスタンフォード大学がある高級住宅地パロアルト、ここは値下がりしていません。高級住宅地域で1億円以上の家はサブプライムに関係なく、ここから車で30分離れたサンノゼ地区は、銀行ローンよりも家の価格が下がった物件を売り出す、ショートセールが活発に行われていました。
次に向った自動車の街デトロイトは大問題でした。街には人通りは少なく、サブプライム問題によって全体で25%下がり、当分上がる見込みはないという実態でした。
一方、ドル安で世界中からの観光客で溢れているニューヨークは、2008年3月現在で前年比18%不動産が上がり、現在でも新規コンドミニアム建設が80件も行われていて、完成前にドンドン契約が成立し、中には完成前に値上がりするので転売して利益を上げている実態でした。
つまり、個人も地域も超格差社会の米国を、全体で論じても実態がわかりません。サブプライム問題対象人口層を明らかにし、その上で分析する必要があるのです。
③米国人の収入源
サブプイムローンに関係する米国人の収入、それは基本的に二つあります。ひとつは当たり前ですが給料です。もうひとつは資産価格の向上をキャッシュに換えることでの収入です。例えば、自宅の時価が騰がると、銀行に担保価値を上げてもらって、増えた分を借り入れることで収入を増やし、その分を消費に回すのです。これが不動産価格の下落によって減りはじめ、ローン返済が出来ない人々が増えだして消費に影響を与え始めました。
④銀行が大打撃を受けた
住宅ブームによる貸出条件緩和で、一段と増やしたサブプライムローン。これが価格下落と、ローンや金利延滞の急増で、銀行は巨額の評価損を計上し、自己資本不足となりました。世界全体のサブプライム関連損失は、IMF試算で9450億ドル(約100兆円)と発表されました。金融機関の損失で金融が収縮すれば、経済も当然縮むことになります。
3.二つの二億人の影響
今月19日、国連が2008年の世界経済成長率予測を発表しました。1月時点では3.4%だったものが、5月時点では1.7%と、半分の成長率に減速させ、また、米国は昨年2.2%の成長に対し、マイナス0.2%になるという大幅ダウン予測です。
米国の二億人が、サブプライム問題やガソリン高などの理由で、消費を減らし出し、経済に影響が出始めていることを認めているのです。
これに加えて、中国の二億人中間層が、中国国内のマイナス要因で、消費支出を抑え始めれば、これまた世界にすごく大きな影響を与えることになります。
改めてよく考えて見れば、米国と中国という二つの二億人が、ここ数年の世界経済成長主役要因であり、当然に日本経済もこの二億人に影響されていました。
世界から日本を見るということが、重要になっていることを痛感いたします。以上。
2008年05月06日
2008年5月5日 本気
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年5月5日 本気
イオンとマルエツ
2008年2月期スーパー業界の決算発表があり、話題となっているのはイオンとマルエツです。イオンの低迷、マルエツの好調Ⅴ字型回復です。
イオンはご存知の通り小売業最強のスーパーで、売上高は7%増の5兆1673億円ですが、営業利益は1560億円(売上高比3%)と前期比18%減になりました。また、5兆円もの売上に対し、当期純利益はたったの439億円(売上高比0.8%)ですから、黒字決算にするために相当無理していると推測できます。
一方、イオンが33.2%の株式を所有するマルエツ、売上高は3355億円で2.6%増、営業利益は75億円(売上高比2.2%)と前期比29%増、純利益は47億円(売上高比1.4%)で前期比33.6%の増益です。対比的な業績ですので、対策も対比的です。
イオンは主力の総合スーパーの約四分の一を閉鎖、または業態転換する方針に変換、つまり、国内市場は縮小、海外事業は拡大という戦略ですが、結局、旧態依然とした店作り展開を失敗と認め、大規模なリストラに踏み切ったのです。
マルエツは2年前の2006年2月期、上場以来初の営業赤字に転落し、そこから改革を始めました。改革の第一は社長の交代です。新たに就任した生え抜きの高橋惠三社長、方針は「開かれた経営」ですが、実行したことはお客の声を聞く「店長への直行便」、社長から社員へ呼びかける「予算達成メール」、仕入先を増やして強化した「生鮮食品の強化」、結局、「お客の要望に徹底的に応える」ことで、首都圏という肥沃な市場を開拓し、16ヶ月連続の既存店増収という快挙を遂げ、「絵に描いたようなⅤ字回復」を示しました。
高橋社長は「よそ者、若者、ばか者をつくる」と宣言。新しい発想を持つよそ者、何をも恐れない若者、徹底して物事をやり遂げるばか者、これを「本気」で進めています。
最近お会いした女性経営者
「本気」といえば、ここ一ヶ月の間にお会いした三人の女性経営者、それぞれ業種が異なりますが、共通しているのは「市場と本気で対応」していることです。
①ニューヨーク(NY)のY社長
最初は、私がいつもお世話になっていて、先週もお会いした企画調査企業の日本人社長です。既にNYに26年住み、ご主人はフランス系のアメリカ人で副社長。事務所は国連本部の近くで、住んでいるコンドミニアムも国連本部前で、ヤンキースの松井選手が住んでいるところの隣です。業績は順調で、起業当初に抱えた多額の借入金も完済し、上げ潮路線に乗っているので、発言はいつも前向きです。
ご存知の通りNYは世界経済・金融の中心地として一攫千金の野望が渦巻き、訪れた人の感覚を刺激する街、あらゆる言語が飛び通う「100の国籍」を持つ街ですから、ここで企画・調査の仕事を展開するためには、世界各地の言語に対応するスタッフが必要となります。そこで社員10人の共通言語は英語ですが、全員を異なる人種で構成し、それぞれ得意な出身国の言語能力でお客との対応を図っています。
従来、NYは「人種のるつぼ」と呼ばれてきましたが、今では「サラダボウル」というのが定説です。その意味は、異民族の人々がNYという同じ地域に所属してはいるが、そこでは常に「民族の違い」が発生するので、相互に限定した距離関係をもって暮らし、前号でも触れましたが「どうしても理解できない矛盾」がある結果、何か「ひやりとした人間感覚」が横たわっているのがNYだというのです。
この中で企業経営するということ、それは単一民族の日本とは明らかに異なります。常に対立が社内に発生します。これをどうするか。それが最大の課題で、この克服が最大の経営ノウハウで、これにY社長は見事な手腕を発揮しています。
例えば、日本隣国出身に多い常に怒り狂う人物には、「わめきタイム」を週一回設定し、思う存分自己主張させることで、社内の日常の穏やかさを守り、「ミュージカルや野球観戦」などの社員慰安的なイベントの実施、これは若き頃東京で体験した日本企業経験を活かしているのですが、それらを駆使して全員のコミュニケーションづくりを図って、社内の「和」を保ちつつ、世界中から異なる言語で依頼される市場に対応できる体制を確保しています。
勿論、これだけではありませんがグローバル世界の典型である、NYの「サラダボウル」感覚を、社内でなるべく調整・克服していくこと、これに「本気」で立ち向かっていることが、NYで成功した基本であると推測しています。
②㈱TEI(ツーリズム・エッセンシャルズ)の三橋滋子社長
三橋滋子社長から先日ジックリお話をお聞きする機会がありました。また、日経新聞の「人間発見」に、4月7日から5回に渡って連載されましたから、ご存知の方もあると思いますが、社団法人日本添乗サービス協会専務理事も兼ねておられるように、空港などでパッケージ客を世話する添乗員、その90%が派遣社員であるように、このビジネスを発案、推進してきた方です。
最初に起業した1973年の添乗員は10名、それが今では協会加盟53社で1万3千名という業界に育て上げました。
三橋社長は日本航空の15期生の客室乗務員でしたが、お子様の育児で退職、子育てが一段落した34歳のときに、添乗業務を請け負うというアイディアを浮かべ起業したのです。
発想の原点は主婦時代、同期生とよく自分たちの経験やスキルを活かす道はないか話し合っている中から、旅行会社とのパイプ役になるビジネス構想を持ったことからです。
その後多くの危機や苦労が続いたことは「人間発見」に述べられていますが、日経新聞を読んでみて感じたことは、三橋社長から直接伺った内容、それは手許のメモに残っているものと微妙にニュアンスが異なっていることです。
何か中心ポイントがずれていると感じます。聞き手の受け止め方の違いといってしまえばそれまでですが、「人間発見」に書かれていなく、私のメモに重要と二重丸したものに「市場との対応力」があります。
三橋社長は何度も「お客からの問い合わせから仕事を発見する」と発言しました。相手の話を聞くこと、相手の話の中にビジネスニーズがあり、市場は奪うものでなく創りあげるもので「仕事の中から仕事を見つける」と述べたのです。
これが「人間発見」では強調されていないこと、それは今後、日経新聞の読み方について考えさせられることに通じますが、いずれにしても三橋社長は「市場と本気で対応」した結果が今日の成功を導いたのです。
③㈱クレアの町田典子社長
町田社長には、私が代表しております「経営ゼミナール」4月例会でご発表いただきました。社団法人ニュービジネス協議会・アントレープレナー大賞を受賞され、八王子商工会議所初の女性政策委員に選任されているように、外食業界では著名な経営者です。
ご発表の内容は経営ゼミナールHPのワンポイントレッスンで「ゼロからのスタート、経営ポリシーは強い志」として掲載したものを、以下ご紹介いたします。
「お客は多様な価値観の集団であり、首都圏という密集した地域に集積していると捉えれば、買いまわり、食べ歩きの範囲は都市交通の至便な立地条件に、多様な店舗を設置していくことになります。
㈱クレアは現在、日本全体人口の27%が集積している首都圏に、24タイプ、70店舗を擁しています。明らかに一人のお客は、多様な好みで行動すると捉えているのです。
『今日は体に優しい和食をとりたい』『たまにはステーキの味を楽しみたい』『イタリアンもいいなぁ』『超多忙だから立ち食いソバですますか』『待ち合わせは東京駅前のオアゾのカフェで』『それともハイセンスな六本木ヒルズにするか』。
これらの多様な行動をとる人々に対応するためには、多くのタイプ店舗構成となり、結果的に24タイプ、70店舗の経営展開が必然となるのです。
しかし、一般的に考えますと、多様な店舗展開は経営全体のコンセプトに問題を発生させることが予測されますが、そうならないのが㈱クレアなのです。
その根本的な要因は『町田社長のリーダーシップ』にあります。町田社長のもつ強い志・想いが、多様・多店舗のベスト経営を実現させているのです。
経営ゼミナール終了後の懇親会は、『丸の内OAZO』丸善書店4階に展開している『M&C Cafe』で、町田社長を囲んで現場見学をいたしました。
そこで町田社長からいただいた色紙には次のように書かれていました。
『本気』 本気ですれば 大抵のことができる
本気ですれば 何でもおもしろい
本気でしていると 誰かが助けてくれる 以上。
2008年04月21日
2008年4月20日 折り合いをつける
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年4月20日 折り合いをつける
ロンドンのアルコール飲酒量
新しく4月から、渋谷で「山本時流塾」を開催させていただくことになりました。毎月、第二金曜日の午後4時から6時まで、㈱東邦地形社の会議室で行います。
その第一回で、話題としてロンドンの「ビンジ・ドリンカー」、これはBinge=暴食(飲)、つまり、度を超した飲酒癖を持つ人を指し、この結果「飲酒が絡んだ犯罪」が増えて問題が多いことを紹介しました。(日経新聞2008.4.6)
ビールを多量に飲む要因としては、価格が安いことも影響しています。ロンドンのパブでは、ビール1パイント(568ml)が2ポンドですから、1ポンド208円(4/18レート)で換算しますと416円です。地下鉄初乗り料金が4ポンド(832円)の半分です。
また、イギリスでは10代前半の子どもにビールを飲ませる家庭が多く、「11歳から15歳の5人に1人が過去1週間で平均5パイント強のビールに相当するアルコールを飲む」と同記事にあり、ビール5パイントは2840mlですから、これを日本の缶ビール350mlに換算しますと、何と8缶に相当します。
子どもが1週間に、毎日缶ビール1缶以上飲むというのですから驚きです。
当然の疑問
日本人の常識感覚では、子どもがビールを飲むことさえ問題で、その上、毎日缶ビール1缶以上飲むというのですから尋常ではありません。
当然、ご参加の方から「どうして子どもがビールを飲むのか」という質問が出ました。
これへの回答は難しいのですが、日経新聞記事では「英国人の大量飲酒癖は千年前にさかのぼる」とあり、「当時は衛生的な水の入手が難しく大人も子どもも朝からビールを飲んでいた」とあります。
時流塾にご出席のタイに詳しい方が「タイでも水が問題なので、ビールを子どもが飲む」と補足説明をしてくれましたが、子どもがアルコールを飲むこと、それは健康上に問題があるというのが常識ですから、日本人の感覚では釈然としないのも当然です。
上海女性のパジャマ姿
次は中国・上海の話題です。先般、上海でアパート最上階六階の住居に訪問しました。玄関を入ると家の中は、中二階スタイル、その中二階の窓を工事していまして、ご主人が仕事休んで、半袖シャツ姿で工事人の監督をしています。ご主人の今の仕事は自動車修理工、以前は韓国系企業に勤めていた時に、日本に行くこともあろうかと日本語を勉強したことがあるので、挨拶は日本語で、穏やかニコニコ丸顔です。
29歳の奥さんも挨拶に出てきました。ご主人は半袖シャツですが、奥さんは一見してパジャマと分かる上にコートを着ています。ビックリして「それはパジャマでは?」と聞きますと、「そうです」と平然と答えます。
この奥さん、仕事はしていなく、現在は二つの大学で昼間は会計学、夜は経済学を学んでいます。いずれご主人が起業するので、その際は会計を担当するためといいます。
家の中はソニーの大型テレビ、応接セットも立派で、上海では広いスペースなので、素晴らしいですねといいますと、家は奥さんの母が買ってくれたとの説明、余裕ある生活をしています。中国の経済成長によって中間所得層が増えた、その代表的な家庭ですが、家の中では奥さんはパジャマ姿で過ごしているのです。
日本人の常識感覚で判断すれば、今まで一度も話したことのない外国人が訪ねてくるのですから、パジャマ姿というのはどうしても理解できません。ドレスアップしたファッションは望みませんが、一応の普段着程度は着衣して欲しいと思います。
しかし、後で通訳に確認しますと、上海の女性は休みの日はパジャマで一日中過ごすことが多く、上海に長く駐在している日本人ビジネスマンに確認しましたら、家の中だけでなく、表の通りを女性がパジャマ姿で、歩いているのを見かけることがあるそうです。だが、何故にパジャマ・ファッションで歩いているのか、その理由はわからないといいます。
アテネの天皇制批判
ギリシア人が日本について、一番疑問に思うのは天皇制のことだと語ってくれたのは、長い間アテネで日本語教師している女性です。日本語を教える都合上、日本の社会について説明することになりますが、天皇制については必ず議論が紛糾して収まりがつかないといいます。
そこで仕方なく「天皇に使える人たちはたくさんいる。天皇制がなくなるとこの人たちは職を失う。だから維持している」と説明すると、一応納得し議論は収まるといいます。ギリシアでは失業率が高いので、こういう日本では考えられないような議論解決法がここでは有効なのです。なんとも国が違えば意見が異なる事例ですが、これもギリシア人の立場から考えると理解できなくもないのです。
それは過去何回もギリシアは王政を布き、問題を起こし、また王政に復帰した歴史があるからです。
まず、1832年にバイエルンのウィッテルスバハ家出身の、ドイツ名オットーが、ギリシア名のオソンに変え、ギリシア王となって1862年に追放されると、次は1864年にデンマーク王子ゲオルギオス一世をギリシア王と迎え、50年間在位し、さらに、1917年には第二王子アレクサンドルがギリシア国王になって、その後コンスタンティン国王の復帰や、息子のゲオルギオス二世が王位となり、その後の第二次世界大戦時の混乱を経て、1946年に再び王政に戻したが、1963年の国民投票で王政の廃止が決まって、ようやくギリシア共和国が誕生したという歴史経緯があります。したがって、王政=天皇制に対する深い疑問があるのです。
しかし、日本国体の中心に位置している天皇の存在理由を、失業率を持ってしか理解させられないということについては、どうしても違和感が残ります。
清河八郎
幕末維新の時代は、日本の歴史の中で、戦国中期以後の時代とならび、英雄時代といってよい時期で、さまざまな型の英雄が雲のごとく出ました。その中で特によく知られているのは「維新の三傑」としての西郷隆盛、大久保利通、木戸孝允です。
また、幕府側にも「幕末三舟」の鉄舟、海舟、泥舟が存在し、また、異色ではあるが、清河八郎も同様で、その他にも多くの英雄といえる人材が輩出したからこそ、あのような偉大な改革が遂行されたのです。
清河八郎・・・山形・清川村の酒造業の息子が、江戸で儒学者を目指していたのに倒幕思想へ転換し、「回天の一番乗り」目指し、薩摩藩大坂屋敷に逗留するほどの人物になり、伏見寺田屋事件や幕府の浪士組から新撰組の登場にまで絡んでいき、最後は幕府によって暗殺されました。
これが清河の一生ですが、清河は儒学者を目指していて、著述数も多く、それが今でも遺っていて、これらを見ても清河の勉学修行は、並ではなかったことがわかります。
だが、この猛烈なる漢学の勉学が生涯の運命を決めた、と述べるのは牛山栄治氏です。
「清河は漢学によって『名分論』から結局は維新の泥沼にまきこまれて短命に終わり、勝海舟などは蘭学の道にすすんだために時代の波に乗っている。人の運命の分れ道とはふしぎなものである」(牛山栄治著 定本山岡鉄舟)
この名分論を「道徳上、身分に伴って必ず守るべき本分」と解釈すれば、あるひとつの見解・立場からのみ物事を決め付け行動していくことは、将来に危険をもたらす可能性があることを、清河の事例が教えてくれるような気がします。
折り合いをつける
グローバル化の時代とは、価値観の異なる人種と交わることです。日本人も外国人から見たら、よく分からないところだらけです。分からない同士が、直接出会ったり、情報を連絡し合ったりして、お互いの関係付けを図っていかねば、物事が進まない時代です。
日仏合弁企業の社長時代、フランス人と本心から理解し合えませんでしたが、ビジネスですから適当なところで「折り合い」をつけて解決しておりました。
よく分からないが、しかし適切に「折り合いをつける」。それがグローバル化の時代と思います。以上。
2008年04月05日
2008年4月5日 ミシュランガイド東京版騒動が示す先
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年4月5日 ミシュランガイド東京版騒動が示す先
ケータイとタバコ
上海から北京まで中国東方航空で移動しました。出発の上海・虹橋空港手荷物検査は厳重でした。今まで受けた中でロンドンに次ぐ厳しさと思います。靴を脱ぎ、ベルトを外し、ジーパンの中に手を入れてきます。ですから、当然に時間がかかります。国内移動だと軽く考えて空港に行くと、出発時間に間に合わないくらいの時間がかかるのです。多分、オリンピック前という時期的なことが影響していると思います。
搭乗した機内のサービスも意外でした。なかなかのサービス状況です。客室乗務員の対応もよく、これもオリンピック対策かとも感じました。
しかし、北京首都国際空港に着き、ゲートに向かうタイミングになって驚きました。乗客の多くが携帯電話を取り出し、大声で喋り始めます。ここが日本と大違いです。機体はまだ動き、ベルト着用サインが出ていて、客室乗務員も座っているのに携帯電話は花盛りです。中国は架設電話が全国に普及する前に携帯が広がった国だと、改めて認識しました。
タバコもすごい実態です。どこのレストランでも、すべてのテーブルの上に灰皿があります。見ていると中国人同士でタバコを一本ずつ交換し合って吸い、耳にタバコ一本載せている人がいます。世界の禁煙化とは関係ないとばかり、中国のタバコは花盛りです。
上海のスバゲテイ・ナポリタン
日本ではスバゲテイ・ナポリタンが定番メニューです。だが、イタリアに行って、ナポリタンとオーダーしても存在しません。
多分、日本のナポリタンは、イタリアのナポリ風料理で、ベースがトマトソースのハムや玉ネギなどが入っているもの、またはミートソースが上にかけてあるものと同じと思います。
このナポリタンが、上海のホテル内レストランのメニューにありましたのでオーダーしました。このホテルは日本の資本で上海でも名門です。しばらく待って期待のナポリタンが出てきましたが、見てビックリ、色が黒いのです。トマトベースのはずですから赤いだろうと思い込んでいましたが違うのです。
一口食べてさらにビックリ。不味いのです。その不味さも普通ではありません。世界中でナポリタンを食べていますが、ここの不味さが一番です。セメントを噛んでいるようなもので、食べるのをやめようかと思いましたが、空腹でもあったので、ようやく半分食べフォークを置くと、ウェイターが寄ってきて、問題ありましたかと日本語で聞きます。
「今まで食べた中で最も不味い」と答えると「もう一度作り直します」というので「もう食べられない」と伝えると「では、無料にします」と言います。ナポリタン以外のスープとグラスワイン分だけ支払いましたが、見事な不味さに感心しました。
北京のスバゲテイ・ナポリタン
北京の欧米系資本ホテルのレストランで、スバゲテイ・ナポリタンを食べました。当然、メニューにはありませんので、スバゲテイメニューのトマトソースをオーダーしました。
このレストランは調理場がオープン式で、働いている人たちが客席から見え、欧米人がシェフです。ここなら本格的な味のナポリタンが出てくるだろうと予測したとおり、しばらく待ってテーブルに運ばれてきたものは赤い色で、一口食べて「美味い」と思いました。さらに、北京で偶偶入った中国料理店も、調理場が客席から見えるスタイルで清潔でした。
これもオリンピックの影響かと思います。また、上海のナポリタンが不味かったのは、シェフの国籍の違いではないかと推測しますが、中国料理は抜群でした。昼夜何回も異なる中国各地の料理を食べましたが、すべて満足味でした。
ナポリタンだけが不味かったのです。地元の中国人に聞きますと、フランスやイタリア料理は、中国ではまだまだという見解です。本格的なレストランは少ないという意味です。
北京のようにオリンピック目指している都市は、店造りを工夫し、本場外国人シェフが導入され、急速にレストラン業界のレベルが上がったと思います。
ミシュラン騒動
昨年11月、「ミシュランガイド東京版2008」が発刊され、これが一大騒動を発生させたことは、記憶に新しいと思います。星付けを発表した週は、テレビを中心にワイドショーだけでなく、ニュース番組までミシュラン一色でした。
そもそも「ミシュランガイド」とは、1900年にフランスのタイヤメーカーであるミシュラン社が、当時数千人しかいなかったドライバーへ、タイヤ修理工場や給油所の地図を無償で給付したのが始まりだと言われているように、ホテルやレストラン情報はおまけのようなものでしたが、厳しい評価と覆面調査という信頼性が権威化してきました。
星の数結果でシェフの首が飛び、オーナーが自殺したとの噂もでるほどになって、さらに、権威付けに拍車をかけてきて、とうとう日本に乗り込んできたのです。
ところがこの星の数、パリは64店、ロンドン43店、NY39店となっていますが、何と東京は150店もあるのです。パリの2.3倍、ロンドンの3.5倍、NYにいたっては3.8倍ですから、いかに東京の「ミシュランガイド」店数が多いかがわかります。
それほど東京の外食状況のレベルは高いのか。という素直な疑問が浮かびます。東京には16万軒の飲食店があるといわれているように、確かに外食産業は盛んで、美味しい店も多く、それらが世界の日本食ブームに一役も二役も貢献していることは事実です。
しかし、世界の一流都市と比較し、星数が何倍も多いという格付けには、次のミシュラン戦略があると考えた方がよいと思います。
三ツ星カンテサンス
ミシュランガイド東京150店のうち、最高峰の三ツ星は8店です。いずれも著名な店ばかりと思ったら間違います。資生堂のロオジエのように銀座を代表する本格派フランス料理ありますが、無名といってもよい店もあります。
その事例が「カンテサンス」です。勿論、レストラン業界では知られていた存在店なのでしょうが、2006年5月オープンですから、一般的な知名度は薄かったのがカンテサンスです。QUINTESSENCE 辞書にはエッセンス、真髄、典型とあります。
ここのシェフは岸田周三氏、33歳です。今やマスコミにも登場していますのでご存知の方も多いと思いますが、先日、このカンテサンスに行き、食べ、岸田シェフにも会いました。
カンテサンスの所在地は白金台、大通りからほんの少し入ったビルの一階。隣は空手道の組合らしき事務所があって、特別に目立つ店構えではありません。昼も夜もコース料理です。昼は一人7,350円ですが、サービス料10%と飲み物は別料金ですから、一人当たり一万円は超すことになります。
コースは七品、まず、最初は前菜三皿、最初はトマトのバジルゼリー載せ、次は山羊乳のババロアにマカデミアンナッツとユリの球根スライス載せに、南イタリアのオリーブとフランスのゲランド塩が添えられてきます。前菜三皿目はホタテの貝柱をスライスし、里芋とミルフィーユのように重ね、下地にタルト生地があり、そこにビートのソースと、付け合わせがウイキョウ。こうやって説明してまいりますと、カンテサンス料理教室になってしまいますので簡略化しまして、あとは魚と肉とデザートとコーヒーで七品となります。
食べ終わるまでに3時間、次の予定に間に合わないくらいの豊かなフランス料理の時間を過ごしまして、カンテサンスのドアを出たときは満足感とともに、日本の食事は世界的なレベルであると確認できました。なお、予約のための電話は猛烈渋滞ですからご注意です。
フランス料理を世界遺産へ
フランスのサルコジ大統領が、2月23日(土)のパリ農業祭で「フランス料理を世界遺産」へ登録申請するとの発言をしました。この背景には、フランス料理は世界一だとの自負と、料理は文化であるという認識からです。また、その食文化へ一環の中に「ミシュランガイド」が組み込まれており、その延長線上に今回の東京版があって、東京の食文化の高さをミシュランが証明したのであり、それがカンテサンスの体験で確認できました。
消費地・中国が世界経済の潮流
「ミシュランガイド」東京版の次はどこでしょうか。世界の経済認識が生産工場としての中国から、大リーグ開催にみるように「消費地・中国」へ変化させ始め、その中でも北京はオリンピック開催を迎え、ナポリタンに見られるように、食文化を急速に向上させています。
世界経済の潮流が、近々北京で「ミシュランガイド」騒動を発生させることでしょう。以上。
2008年03月20日
2008年3月20日 日本の評価
環境×経済×文化 山本紀久雄
2008年3月20日 日本の評価
このところ各国メディアから日本の政治混乱、経済停滞を懸念されることが多いので、改めて、日本人から見た評価と、外国人からみたもので比較してみたいと思います。
日本人から見た日本
まず、日本人から見た評価を、みずほフィナンシャルグループの新光証券が作成した「日本株式の評価は正しいのか」(2008年2月7日作成)という資料から見てみたいと思います。結論は「投資指標からみて、日本株式の評価は歴史的な低水準」と判断し、その根拠を各指標から分析しておりますのでご紹介します。
1.80年代半ば以降、主な大幅調整(下落)局面は7回あり、昨年7月高値からの今回の下落率は30%以上で、そろそろ大幅なリバウンド局面の起点に来ている。
2.PER(株価収益率=株価÷一株当たり利益)、これは一株当りの利益と株価を比較し、利益に対して株価が何倍まで評価されているかを見るもので、数値が低いほど割安となり、このPERの東証一部予想は一時14倍台まで低下し、80年以降、最も低い水準にあり、更に遡ってみると70年代前半以降となり、歴史的な低水準となっている。
3.リスクプレミアム(株式益利回り-長期国債利回り)は80年以降最大になって、株式が割安である。株式益利回りとはPERの逆数(一株当たり利益÷株価)で、株価に対してどのくらいの利益をあげているかを見るものである。したがって、相対的にリスクが高い株式益利回りが、相対的にリスクが小さい長期国債利回りを、どのくらい上回っているかを示す指標であって、この数値が高いほど株式が割安を意味する。
4.PBR(株価純資産倍率=株価÷一株当たり純資産)は85年以降最低の水準で、割安である。一株当たり純資産と株価を比較したもので、財務安全性から見るもので、数値が低いほど割安を意味する。
5.配当利回り(一株当たり年間配当金÷株価)は、85年以降最高の水準となっている。これは株価に対してどのくらい配当金が支払われるかを見たもので、高いほど株主に有利となる。
6.経済規模と比較した時価総額は米国、英国より小さい。GDPに対して、株式時価総額が何倍まで買われているかを見たもので、いわばマクロベースのPERといえ、日本は相対的に割安である。
7.この他に多くの指標を使って、米国、欧州、香港、中国、インドと比較し、日本の株価は割安という見解を述べている。
8.更に、日本の強みは「ものづくり」にありとして、代表的な企業の世界シェアを紹介している。
①トヨタ自動車 売上高54兆円 世界シェア31% 海外売上比率78%
②キャノン+村田製作所+東芝の三社合計売上高40.3兆円。情報通信機器分野の世界シェア54%。海外売上比率はキャノン79%、村田製作所75%、東芝53%
③信越化学工業 売上高9407億円 世界シェア74% 海外売上比率69%
つまり、新興国は目覚しい成長を遂げているが、日本の製造業は素材や部品、製造装置などにおいて優れた要素技術や効率的生産といった強みを持っており、今後も安定した成長が出来るので、高シェア・高技術を持つ日本企業を見直しすべきであるとの主張です。
外国人から見た日本
モルガンスタンレー証券経済調査部長の、ロバート・A・フェルドマン氏が以下のような見解を述べているのでご紹介します。(猪瀬直樹・日本国の研究メールマガジン)
まず、結論的に「2003年から2006年までは、『改革する日本』、『不良債権を克服する日本』だったが、最近は、『米国、欧州で深刻化してきたサブプライム問題は、日本の失われた十年とどこが似ていて、どこが似ていないか』になった。すなわち、日本は、回復ストーリーでもなく、不在でもなく、反面教師の文化財である。博物館に置かれている恐竜のようで、どういうものだったのか、なぜ絶滅したのか、との関心になっているという見解です。
1.投資家が日本を見切売りをした理由
「外人投資家が売っているから日本株が下がっている」とよく聞くが、これは半分真実で半分嘘である。一見、外国人投資家の行動が日本株安をもたらしたように見えるが、80年代後半も外国投資が日本株をアンダー・ウェートにしていた。すなわち、日本株が一番上昇した時期は外人が買っていなかったのだ。「外人が売っているから株価が下がっている」論に反対証拠がある。当時は、外人が売っても邦人は買っていた。すると、今の株安は、外人が売っている理由も邦人が買っていない理由も考えないといけない。
両者の行動は異なる理由ではなく、同じ理由である。一言でいうと、日本のマクロ改革もミクロ改革も逆戻りをしているからで、この傾向はすでに小泉政権後半の与謝野経済財政担当・金融担当大臣時代に遡るが、安倍政権になって加速し、福田政権になって更に加速した。
2.道路財源の議論が日本売りを加速させた
道路財源問題も内外投資家に悪影響を与えた。小泉政権のとき、道路族のビジネス・モデルである道路汚職、無駄遣いを直す動きが始まった。20兆円の費用がかかる高速道路計画を見直して、10兆円に抑えて、道路公団の改革を行った。だが、道路財源問題は残った。道路関係税(主にガソリン税)の約5.5兆円はほとんど道路の建設や管理に利用するルールになっており、これは、汚職と無駄を支える道路族の永久「埋蔵金」である。一般財源化をすれば、道路族の政治ビジネス・モデルはすぐ消える。
安倍政権が小泉政権を継いで、道路財源の一般財源化を唱えたが、指導力の弱い安倍政権に対して道路族が強く反発し、一年間延期になった。福田政権になって、福田総理は一般財源化に関して「慎重に検討する」(翻訳:「やらない」)に、当然、内外の投資家は失望した。
3.経済学、ビジネスを知らない裁判官の被害
TOB(企業買収)に関する裁判所の判決も、内外投資家の日本に対する自信を落とした。会社法の改正によって、ようやく効率の悪い経営者に対する圧力が増すものと思った投資家は、判決をみて、保身経営は許されるとわかった。
加えて、株主たち自身が旧経営がいいという例もあったので、本来価値が潜在している日本の企業は、いつまでもその価値を実現できない状態が続くとわかった。これだけアジアに活気があるなか、わざわざ日本で頑張っても意味がない、という結論に達したというわけだ。
日本の投資家も海外で資金を運用したほうがいいと思って、日本株に冷たい態度を示した。日本企業の役員会はビジネスではなく、カントリー・クラブであるという印象は免れ得ない。日本ブランドが悪くなった結果、ガバナンスがしっかりしている企業も当然評判が落ちた。
4.日銀総裁の選択劇
日銀総裁の選択方法も投資家の反感を買った。すなわち、永田町と霞が関のインサイダーたちで自分の都合で決めて、どのような人が日本にとって適材適所かを考えない選択である。
武藤さんは大蔵省時代、人事が上手で強力な役人であったが、マクロ経済の知識もなく金融業界で仕事をしたこともなく、投資家の間では金融政策の理解に関して評判は高くない。
国際交渉と迅速なコミュニケーションのために不可欠な英語力が弱いと国会議員も指摘している。なのに、任命する福田総理は旧来の選び方を優先した。投資家は、日銀総裁の選択が「財務省、日銀」の交代に戻って日銀を天下り先に過ぎないと当然皆が思うのは仕方ない。
5.とどめを刺した北畑発言
その中で、北畑発言はとどめを刺した。経産省の北畑隆生事務次官が、1月24日のスピーチで、デイトレーダーのことを「バカで浮気で無責任」と批判した。投資ファンドを名指して、「バカで強欲で浮気で無責任で脅かす人というわけですから、7つの大罪のかなりの部分がある人たち」との発言が報道された。経産省次官が金融商品、企業統治の基礎知識がないことがばれただけではない。世界の投資家がこの発言の報道を読んで、政府高官がこのようなことを言うなら日本株を持つ理由がないと結論した。日本に対する失望感が一層悪化した。
北畑次官がその後、記者会見で自分の発言に関して、2月7日の記者会見で「講演録をまとめる段階で訂正をしていただく」と思っていたと自己弁護したが、経産省の次官が自分の言葉の重みをわかっていないのは充分大きな問題で、「赤ちゃんを産む機械」発言、「しょうがない」発言で当事者をかばった安倍政権は投資家が横目で見始めたが、北畑発言を許している福田政権は、投資家があきらめる可能性が高い。
以上のように、新光証券の主張は各データ指標のとおり、日本の力は低く評価されすぎているとの見解です。一方、モルガンスタンレー証券は日本を買えないという主観的見解を展開しています。皆さんはどちらの見解を支持し、我々の日本をどう評価しますか?以上。
2008年03月05日
2008年3月5日 メタボリック症候群
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年3月5日 メタボリック症候群
ロンドンのJALラウンジにて
ロンドン・ヒースロー空港のJALラウンジで、若い美人女性が乗客にインタビューしています。順番がこちらに来ました。「ちょっとお時間をいただけませんか」。「何でしょう」。「エアラインの満足度調査をしております。ご協力お願いします」。
世界中の空港で一斉に調査し、その結果を航空関連雑誌に発表しており、ここ数年のトップエアラインはシンガポール航空、次いでヴァージン・アトランティック航空が続き、残念ながらJALは徐々にランクを下げています、と解説してくれます。
この結果は、JAL愛用者としては残念ですが、客観的評価として実態を受け入れないといけないと思いつつも、機内でうけるJAL客室乗務員のサービスは丁寧・上品・親切で、他国のエアラインより優れていると思っていますので、その要因は何だろうかと考えているうちに、JALと日本国全体が頭の中でオーバーラップしてきました。
改めて以前に利用した、ヴァージン・アトランティック航空を思い起こしますと、機体は決して新しくなく、食事なども普通と感じましたが、機内に流れている活気、明るさ、リズム感が違っていたと感じます。一言でいえば「元気度」が異っています。
これか!!と気づいて、これは、日本全体を覆っているものと通じる、と思いました。
日本の元気度
このところ伊勢の赤福や北海道のチョコ、その他多くの偽装事件が発覚しました。再生紙も嘘だったようで、大企業も中小企業もいずれも問題だというムードです。考えてみれば、安倍政権時のタウンミーティングもやらせでしたし、昨年後半の経済状況を悪化させた住宅建築基準法改正も偽装からでした。そこに、世界共通の経済問題である、原油価格の暴騰とサブプライムローン問題が重なって、世界中で株式市場が暴落し、地球全体が先行き不透明という状態となりました。
このような不安心理のところに、日本には人口減という長期変動要因があり、これらが重なって、何か日本全体に活気・元気度を失わせているような気がしてなりません。
会食時の話題
先日、フランス人と結婚して里帰りした女性を囲んで、何人かで食事しました。話題はフランスと日本の比較論から、次第に日本の過去と今の比較に移っていきました。
ジッと聞いていると、最近の若い者はけしからん、という昔から年配者が常に言う話題になって来ました。礼儀を知らない、基本的なビジネスルールを知らない、親も知らないから子どもに教えられない、最近の若者は着物の着方を知らない、琴と三味線の区別ができない、ダメダメのフルコースで、日本没落会議のような雰囲気になってきました。
暗い話が一段落した後で、ひとつ提案をしました。比較の対象を「日本の昔と今」ではなく「日本と外国」で検討してみたらどうかと提案しました。
その事例として、アフリカ大陸で最も経済的にも、政治的に安定した国として評価されているエジプトと南アフリカ、そこへ訪問した実態をお話し、両国の現実は日本と比較できない程の問題があること、既にレターでもお伝えした状況を話しました。
物事の判断は比較から生じます。同じ対象でも比較する基準の持ち方で、結果は異なるのです。昔の実態と、今の日本を比較する場合は、その背景にある時代状況が変化していることを考慮しなければなりません。日本は確かに昔より厳しい社会になっているでしょう。グローバル化が大きな環境変化をもたらしています。
しかし、外国から見る日本は大変な人気国です。日本がすばらしい国であるという評価があるからこそ、世界中で日本食がブームとなり、日本のマンガやアニメなどのソフト文化が受け入れられ、世界の多くの人たちは日本に行ってみたいと憧れているのです。
いつもお伝えしていますように、世界の多くの国を訪れ、日本人だと分かると、急に態度が変わり、どの国でも大歓迎してくれるのです。これが外国から見た日本の実像です。
恐怖心
伊藤忠商事会長の丹羽宇一郎氏が次のように述べています。(日経新聞)
「『我々が恐れるべき唯一のものは、恐れることそのものだ』。1929年の大恐慌の悪夢のような光景が続く1933年。米大統領に就任したフランクリン・ルーズベルトは最初の演説で、経済の悪化に対し過剰ともいえるおびえを抱く国民にこう呼びかけ、ニューディール政策で恐慌に立ち向かった。
今、世界に広がっている信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)問題に端を発した、株価急落など世界的な市場混乱についても、およそ75年前のこの言葉は生きている。経済は『人間の心理の織りなす綾』だからである。
客観的にみれば、サブプライム問題はまだ底がみえていない。ミンチ肉のように細かく刻まれたサブプライム関連の債券が様々な金融商品に組み込まれ、どこまで広がっているか、まだ誰にもわからないからだ。相場には「もうはまだなり」という言葉があるが、金融市場の混乱は『もう終息するだろう』といっているうちはなかなか底打ちしない。
重要なのは、日本や世界の実体経済は強く、健全なことだ。日本は住宅着工の遅れなど特殊要因を除けば、年率2%近い成長をしている。だが、人々が相場に引きずられて不安心理を高めれば、実際の経済も悪化しかねない。人間は心を病めば身体も病気になることがある。今警戒すべきは恐怖心が実体経済をむしばむ恐れだ。こんな時こそ世界のリーダーはルーズベルトのメッセージを共有して欲しい」。なるほどと思います。
偽装は昔から
京都新聞で山岡鉄舟を連載している山本兼一氏が次のように述べています。 「食品の種類やら産地やらの偽装がたいへんな話題となったが、そんなことは平安時代から行われていた。むかしの説話を集めた『今昔物語集』に、こんな偽装の話がある。
平安時代のなかごろ、京の内裏を警備する舎人たちの詰め所に、魚の切り身を売りに来る女がいた。味がいいので、みんな喜んで買っていたが、秋のある日、北野のあたりに鷹狩に出ると、その女がいるではないか。女が竹かごを持っていたので、むりに中を見てみると、四寸(約12センチ)ばかりに切った蛇が入っていた。女は蛇に塩をふって乾かし、魚だといつわって売っていたのだ―――」。(京都新聞2008.1.11)
昔も今もいつの時代でも偽装を行う人がいるものだ、という事実を教えてくれます。
新学習指導要領案
先日発表された「新学習指導要領案」は参考になります。
フランスから里帰りした女性との会食時の話題、ダメ日本の事例として提起された「最近の若者は着物の着方を知らない」は、中学校の「技術・家庭」で「和服の基本的な着方を扱うこともできる」として改善の方向を打ち出しています。
また、「音楽」では「和楽器の指導は3年間を通じて一種類以上の楽器の表現活動を通して、生徒が我が国や郷土の伝統音楽のよさを味わうことができるように工夫する」とし、「保健体育」では「武道は柔道、剣道、相撲のうちから一つを選択して履修できる」としています。食生活にもふれ「日常食の献立と食品の選び方、日常食の調理と地域の食文化」についても言及しています。今回の「新学習指導要領案」は、今の多くの大人が批判する今の若者の問題点、それらを改善しようとする内容となっています。
さらに、ヤクルトが実施した朝食実態、20年前に比べると朝食を「毎日必ず食べる」「楽しい」と感じる子どもの割合が増え、「家で毎日飲むもの」に牛乳を抑え「お茶」が1位になっています。いつの間にか子どもの食生活、つまり、家庭の食が変化しているのです。(日経新聞2008.2.18)
人口減
日本が迎えている人口減の時代を恐怖心で受け止めている人が大勢います。しかし、考えてみれば、明治維新時の日本の人口は約2700万人、それが140年経った平成20年で12600万人ですから4.7倍に増加したのです。国土面積は敗戦で減った中での増加、つまり、狭い面積の中で人口だけが「膨らんだ」のです。それが昔と比べて生活し難い実態を作っている大きな要因でもあります。その修正作業に入って、その過程の中にいる、人間の身体に例えれば、お腹回りが膨らんだ、メタボリック症状を、改善させる方向に向かい出したのだ、と考えたら如何でしょうか。考え方で心理は変化します。以上。
2008年02月21日
2008年2月20日 エジプト・一言で語れない
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年2月20日 エジプト・一言で語れない
カイロの街
ルクソールから乗ったエジプトエアーから見る地上は、一面茶色の砂漠です。
国土の96%が砂漠で、残りの4%の土地に7130万人(2006年)が住んでいて、特に、首都カイロを核とする大カイロ圏には、約2000万人(構成比28%)が集中しています。
人口集中の結果は、道路の渋滞ということになります。カイロ空港からホテルに向かった道路、渋滞と信号無視の世界が続きます。誰も信号、つまり、交通ルールを守らないのです。というより信号がないのです。あっても真ん中の黄色が点滅しているだけで、そこでは一応警官が手信号で交通整理をしていますが、人はかまわずに車と車の間を巧に泳ぎ、交差点・道路を横断します。実際に、これを真似してみたところ、結構できるもので自分ながら感心しましたが、排気ガスがすごく、当然ですが健康にはよくありません。知人から、エジプトの平均寿命は短い(70.1歳・2002年度)のは何故か。それは水が悪いからではないか、ということを確認してくれと依頼されましたが、こういう排気ガスが充満している環境では、いろいろ要因が重なって、平均寿命に影響していると思います。それを示すようにエジプト大使館ホームページでは、乳幼児死亡率が高い理由として呼吸器感染症と下痢症を挙げています。
さらに、人口集中の結果は、失業率の高さを生み、貧困層がギザのピラミットの近くの「死者の町」、つまり、墓地にまで住み着く結果となっているのです。
アスワン・ハイダムによる環境問題
ナイル川上流のアスワン・ハイダム建設について、エジプト博士の早稲田大学・吉村作治教授が、以下のように述べています。
「このアスワン・ハイダムのお陰でアスワンより下流に氾濫が起きなくなって、エチオピアやケニアから流れてくる肥沃な土砂が運ばれなくなった。そのために土地が痩せて、化学肥料を入れなければならなくなった。なおかつ約六十メートルも水位が上がり、そのため地下水の水位も上がって、遺跡やその他が塩害に苦しむようになった。また、地中海の河口の所にプランクトンが湧かなくなったり、ダムによって広大なナセル湖ができたために蒸発した水分が雲となり、雨が降りやすくなるなど、いろいろな弊害が出てきている。ナセル大統領は、アスワン・ハイダムを造ることが国を裕福にする唯一の方法だと考えたのだろうが、歴史というのは大変冷酷であり、こういった結果をもたらしてしまったわけである」(ピラミット文明・ナイルの旅)
このことの証明が日経新聞(2007年12月31日)の報道です。
「三大ピラミッドやスフィンクスで知られるエジプトの首都カイロ郊外ギザの古代遺跡群周辺で地下水位が年々上昇し、一部で地上に水があふれて遺跡が浸水、ピラミッド建設に当たった労働者や貴族らが暮らした街の遺跡『ピラミッドタウン』の発掘作業に深刻な影響が出ていることが分かった」
アスワン・ハイダムは、古代エジプト人の「ナイルの賜」文明に反したのでしょうか。
ホテルで
渋滞の中、13時過ぎにホテルに着きました。ホテルは高さ142m、716室と巨大建物です。部屋に入って、インターネットLAN回線でつなげてみると問題なく、ホッとしてボーイにチップ渡し、さて、メールしようと受発信するとエラーとなり、インターネットもつながらなくなりました。そこで電話してネット係りに来てもらい、いろいろ操作してもダメです。一緒にビジネスセンターに行ってくれというので行くと、そこの担当者が6時過ぎに開通するので待っていてくれといいます。
仕方ないので、ホテル内をウオッチングし、外にミネラルウォーターを買いに出ましたが、どこにも店らしき姿なく、排気ガスがすごいので、すぐに部屋に戻り、まだ6時前でしたが、念のためインターネットを試してみたらつながります。
しかし、一週間宿泊した後半の2日間は、地中海に配置している回線の故障で、完全にインターネットが使えなくなりました。カイロ全体が不通なのだと、地元の人が語りますが、このようなトラブルはよくあるのか、ちょっと不思議な社会であると感じます。
着いた日の夕食は、一階レストランに行きました。エジプトはイスラム教なので酒類は禁止のはずですが、エジプト産のワインがあるというのでグラスワインを飲みました。結構いけます。食事が終わり、支払伝票を確認しましたら、グラスワインの金額が倍に印字されています。それをウェイトレス指摘しますと、走ってどこかに行き、戻ったときはチーフらしき蝶ネクタイがついてきて「この価格にはサービス料が加わっている」といいます。そこで、伝票の合計欄下に別項目で書かれているサービス料12%を「これは何だ」と手で示しますと、黙って引き下がり、しばらくすると減額した伝票を持ってきて「訂正しました」といいます。イスラム社会はちょっと難しいと感じます。
ムバラク大統領
何人かのエジプト人に聞いてみますと、ムバラク大統領の評判はいたって悪いようです。その理由は、政権が長期間になりすぎていることです。サダト大統領が1981年10月に暗殺され、そのときに就任してから27年間、年齢は80歳になろうとしています。本来、憲法で任期6年、二期までという規定がありましたが、その終了時に任期規定を条項修正した上に、2005年に行われた5選目の選挙では、国民や海外から不正疑惑を問われましたが、結局、当選し事実上の終身大統領となっているのです。
このまま行けば、後任大統領には息子がなるだろうと、地元の人が語り、今の政治は貧しい人を豊かにさせない政策を採っていると指摘します。
国民が豊かになって余裕が出ると、政治に関心を持つことで、現政権への批判が強くなるので、貧乏社会にしているのだ、という声が多くあります。
この声には、まさかと思いますが、そういうことが国民の間で語られているという事実、そこにエジプト社会の深い闇があるように感じます。
日本人に対する意識
書店で買った、ぬりえブックの出版社を訪ねました。アポイント取らず直接訪問するという荒業です。渋滞で全然車が動かず、ここで事故が発生し、怪我や急病になっても、これでは救急車も入れず、命の保証がないだろうと考えていると、ようやく出版社に着きました。立派なビルです。カイロの中心地で、エジプト考古学博物館の近く、エジプトテレビの隣です。玄関ホールから、エレベーターの前に立つと、ガードマンがどこに行くのかと聞いてきます。通訳が「日本からぬりえの研究者が来て、社長に会いたい」といいますと簡単に通してくました。
エレベーターで上がり、薄暗い廊下を歩き、窓にぶつかる右側のドアが開いているので顔を出しますと、女性が入れという手招きをします。中では大きなデスクに年配の女性が座り、その前の女性と何か打ち合わせしていたようです。
大きなデスクの女性が、大声で電話しながら「何の用事ですか」聞きますので、ぬりえの調査をしていて、本屋で貴社のぬりえを買い、その住所をみて訪ねて来ました。いろいろ教えてもらいたいと、名刺を差し出しますと、まぁ座れという仕草をしてくれます。遠慮なく座りますと、「何か飲みますか」と聞いてくれます。折角ですから紅茶をお願いしながら、デスクの女性が渡してくれた名刺をみますと、何と社長です。
また、この企業は大きそうなので、創業以来何年ですか、と聞きますと118年だといい、当社はアラブ世界で一番大きい出版社だと補足します。大企業なのです。しかし、こういう大企業にアポイントなしで来て、社長と直接会えることに驚くと同時に、そういうことができる社会であると言う事実に、エジプトの新しい一面を感じます。
この企業が扱っているジャンルはすべての分野。政治、経済、文学、科学、法律、歴史、アート、子ども・・・。印刷はこのビルの中と、もうひとつ向こう側のビルの中で行って、アラブ世界各国の36の書店系列に卸していると説明受けます。手土産代わりに、「ぬりえの心理」英文版を贈呈すると、漢字でサインしろといい、ページをめくりながら、こういう本を出したかったとお世辞かどうか分かりませんが、至って好意的で、 日本人だからだと思います。エジプトでは日本が高く評価されています。
他国理解は難しいのですが、特にアラブ社会は難しいと感じたエジプトでした。以上。
2008年02月08日
2008年2月5日 エジプト・ナイルの賜
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年2月5日 エジプト・ナイルの賜
日経新聞で紹介される
昨年末に出版しました「ぬりえを旅する」(小学館スクウェア)が、1月17日(日)日本経済新聞図書欄で紹介されました。小さな掲載記事ですが、経済紙のメジャーが取り上げてくれたという意味、それはこの本が、時代の動きと、どこか重なっていること、それが評価されたのではないかと、素直に喜んでいます。
引き続き、「ぬりえを旅する」二冊目出版のため、エジプトを訪れました。
ナイル川クルーズ「エジプトはナイルの賜」という有名な言葉があります。前五世紀のギリシャの歴史家ヘロドトスが述べたものです。この言葉どおり、ナイル川のお陰で、エジプトは世界四大文明を遺したのです。
したがって、エジプトを理解するには、ナイル川を体験しなければ話になりません。
しかし、どうやって体験するか。ナイル川の辺に立ってみるか、ナイル川に入ってみるか、ナイル川の中から岸辺をみてみるか、様々な体験方法がありますが、何といってもナイル川はアフリカ中央部、ルワンダ共和国のカゲラ川を水源とし、全長6600メートルを超える世界最長の川であって、エジプト国内に入ってからも1500キロメートルもある巨大な自然です。加えて、地域によってナイル川の持つ自然条件が異なり、一地域を切り取るようなスタイルでナイル川を体験しても、ナイルの賜という意味合いは理解できません。
そこで、今回はナイル川クルーズ三泊四日の旅、行程はアスワンからルクソールまでの200キロメートルに乗船してみました。エジプト国内1500キロメートルのうちのたった200キロメートル、ごく僅かなナイル川の体験のため、当然、不十分さは承知していますが、少しでもエジプトを理解しようと、クルーズに乗船したのです。
アスワン・ハイダム
クルージングのスタートはアスワンです。エジプト最南端の町で、スーダンとの国境まで350キロメートル、アスワンまでカイロから飛行機で行きました。
アスワンを世界中に知らしめたのは、1960年から70年にかけて、旧ソ連の協力で建設されたアスワン・ハイダムです。エジプト社会を発展成長させるためには、農地を増やし、増える人口を養い、工業化もしなければならない。そのためには、アスワンにダムを造って電力を起こし、灌漑を行い、農地を広げようと、幅3600メートル、高さ111メートルのダムを建設しました。また、その結果生まれたのが全長500キロメートルにおよぶ人造ナセル湖です。大きさは琵琶湖の7.5倍もあります。
折角来たのだから写真を撮ろうと、堤防上に設置された展望所から、ナセル湖と下流に流れていくナイル川、それとソ連との建設記念塔などに向かってシヤッターを押していると、突然、どこからともなく一人の兵士がこちらに向かって走ってきました。手には当然ながら小銃を持っています。
しかし、当方は何も悪いことはしていないので、自分とは関係ないだろうと無視して、写真を撮っていると、こちらの目の前に立ち、怒り顔で、
「今、ズームを使用しただろう」と叫びました。
予想がつかない詰問に、何と答えてよいか分からないので、黙っていると「ズームは禁止だ」と厳しい顔つきで、一歩前へ迫ってきます。
そこで「ズームは使わない」と答えると、「いや、今、使ったように見えた」「使っていない」「使った」「使わない」。二三回言い合いしているうちに、最後は兵士があきらめ向こうに去っていきました。実はズームを使って撮影したのですが、危険を感じたので使用しないと言い張ったのです。だが、どうして遠くにいた兵士が、こちらのズーム使用を分かったのか、それが今でも不思議であるほど、警戒が厳重なのです。
何故にズームが禁止なのか
最近はデジタルカメラにも高倍率のズームが付いています。3倍ズームが多いのですが、6倍や10倍といった機種もリリースされています。このズームレンズは1カ所から広い画角や狭い画角がズーム操作ひとつで簡単に切り替えられます。高倍率ズームなら、離れた場所からでも遠くの被写体を大きく写すことができること、これが一番のズームレンズの効果です。
ということは、ナセル湖には何か撮影されては困る存在物、それは軍事的に重要なものが遠くに存在していて、それをズームでクリアに撮影されてしまうと、エジプト軍隊が困る事態になる恐れがあるもの、それがあるからこそ禁止しているのです。
そこで、地元の人にズーム撮影禁止の理由聞いてみますと、もし仮に、アスワン・ハイダムが破壊されるようなことになったら、水が一気に流れ出し、ナイル沿岸は8時間以内に全部埋まってしまうといいます。つまり、カイロ市内は大洪水になってしまうのです。だから、その危険防止で軍隊が守っているのです。実際に、第四次中東戦争時、ダム防衛のため高射砲でイスラエル空軍の攻撃を防ごうとしましたが、簡単にペイント弾を落とされ、この恐怖でエジプトはイスラエルと講和したといわれているほどです。
フルーカの若者
ナイル川にはフルーカという、帆で動く船がたくさん浮かんでいます。観光客を乗せるもので、ヨットをイメージしていただくとよろしいと思います。このフルーカは、風だけで動かす、つまり、帆で動く船ですので、結構、操作テクニックがいるようです。
そのひとつに乗ってみました。帆を操るのは色黒の現地ヌビア人男性で、20歳代の後半に見えます。裸足で船内を動き回り、風の向きを巧みに扱って、ナイル川の上をすべるように走り始めました。ナイル川のゆったりとした流れの上の風が、涼しく頬に当たり、船の動力は自然ですから、一切音はなく、鳥の声と岸の向こうから聞こえてくるコーランの祈り声ばかりです。
フルーカはナイル川の観光名物ですが、ふと、このフルーカはどのくらいするものか。それを若者に聞いてみました。答えは、フルーカの面積一平方メートルあたり1500ポンド(3万円)だといい、乗船したフルーカは7平方メートルだから約一万ポンド
(20万円)。若者が買うにはちょっと高いと思ったので、あなたの所有物かと確認してみると、違うといい、オーナーがいて、週3日間この仕事に雇われているといいます。後の4日はどうしているのか、これには「何もしていない」との答えにショックです。
いい若者が週3日しか仕事がないのです。生活が大変だろう思い「結婚しているのか」と聞くと、「まだだ。だけど恋人はいる。写真見たいか」、頷くとポケットから一枚の写真を渡してくれ、見ると少女と本人が並んでいます。若者の肩くらいしか身長がありません。「学生か」「そうだ、16歳だ」「エッ、すると君は何歳か」「20歳だ」。まじまじ顔を見てしまいました。老けている!!「ところで何年この仕事をしているのか」「10年している」この答えに返す言葉がありません。
つまり、10歳ごろから船の操作をしていることになり、そうすると学校に余り行っていなかったことになります。さらに「僕の収入はチップだけ。オーナーからは貰っていない」に、うーん、またもや考え込みました。
フルーカ体験は楽しかったのですが、エジプトの若者の実態を垣間見た気分で、心が少し重くなって、その分、下船時にチップを弾みましたが、この程度で若者の生活が向上するわけがありません。社会全体のシステムが問題です。
エジプト政府の発表で失業率は9.1%(2006年)ですが、若者の失業率は実際には20%を超えるようで、特に、大学卒業者は5人に2人は就職できないのが実態だと、地元の人が語ります。
クルーズ船のゴミ処理
フルーカから上陸し、堤防の上を歩いてクルーズ船に戻ったとき、ギョッとする光景にぶつかりました。それは、クルーズの最後部甲板から、どっとゴミがナイル川に落とされたのです。乗客が出したゴミ、船のゴミ、それらがナイル川にそのまま捨てられる。当然、分別処理などはしておりません。環境問題が世界の課題で、洞爺湖サミットの議題となっていますが、世界四大文明発祥の地エジプトでは、ゴミ処理やアスワン・ハイダム建設による影響、そり他の環境問題があります。次号もエジプト報告です。以上。
2008年01月20日
2008年1月20日 変化の質を変える
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年1月20日 変化の質を変える
京王駅弁大会
1月10日から22日まで、京王デパート新宿店で「元祖有名駅弁と全国うまいもの大会」、略して「京王駅弁大会」が開催されています。今年で43回目、昨年の売り上げは13日間の開催で、36.6万個販売、売り上げは6億6千万円というすごさです。
開催2日目の夕方行ってみました。エレベーターで7階へ、その間満員の客は、誰も途中階で降りず、揃って会場に到着すると、そこは押し合いへし合いの駅弁売り場です。
すでに完売した駅弁、整理券を発行している駅弁、長蛇の列をつくっている駅弁、47都道府県から厳選された200アイテム、誠に壮観です。
買い求めたのは、義母の故郷、自分の故郷、旅行したとき食べたもの。列に並んで買うのも雰囲気があって楽しく、持ち帰って美味いと家族から喜ばれ、これだけ多彩な駅弁文化ともいえる存在は世界にないだろうと思いました。
その通りで、世界の列車に詳しい櫻井寛氏(フォトジャーナリスト)が、台湾、韓国、タイにあるものの、質、量、歴史からみて日本の駅弁は世界一と言明しています。
本質洞察力
司馬遼太郎氏が、勝海舟と坂本竜馬について語っています。(日本歴史を点検する)
「『アメリカを興したのは誰ですか』と、坂本は訊く。『ワシントンだよ』と勝。ワシントンといえば創業の人で、日本に翻訳すれば徳川家康だと思ったから、『ところでワシントンの子孫は今どうなっていますか』ときいた。坂本は将軍とか大名とかになっているのだと思ったのでしょう。ところが訊かれた勝は、ワシントンの子孫が、靴屋をしているのか、コックになっているのか、そんなことは知らない。実際は子孫は絶えているのですが、むろん勝は知らない。『しかし、子孫なんざ、問題じゃないんだ』と言って、アメリカの制度を説明した。坂本にとってこれほど大きな驚きはなかったでしょう。家康に相当するワシントンの子孫がどうなっているかもわからないということが。―――この場合、当時の日本人の驚きが代表しております。同時に、坂本はいっぺんに頓悟した。『ああそうか、日本もそうしなきゃいかん』と。」
司馬遼太郎氏がここで言いたかったことは、日本は海に囲まれた孤島であり、国際環境は地理的に分かり難い。だが、日本人が得意とする、いっぺんに分かる「本質洞察」法で、日本は変化しなければいけないと理解し、納得し、その変化の方向性は欧米化基準であり、そこから明治維新につなげていった、ということであると思います。
変化に対する抵抗感と日本人気の絶頂
今の日本の現状を、橘・フクシマ・咲江氏が「日本がどのような経済的、政治的な立ち位置にいたいのか自画像が見えない。疲れ果て、内向きになり、もう経済競争で遅れてもいいよ、という雰囲気もある。その一因は、変化に対する抵抗感だろう」と指摘しています。ところが、この反面、世界で日本人気は絶好調である、という事実が存在します。
12月5日レターで、元サッカー日本代表の中田英寿氏の「日本人って非常にいろんな国で受け入れられている」という発言、さらに、ドイツのカールスルーエでは、日本好きの高校生から高齢者まで幅広いドイツ人が、毎月日本食レストランで、食事しながら熱心に定例会まで開催している事実、加えて、世界のどの国でもマンガ、アニメ、すしなどで日本の存在は高まるばかりなのです。また、この人気の不思議なことは、バブル崩壊の日本経済の低迷を機として、日本のソフトパワーが世界中で認識され始めたということです。
別のプラットホーム
今の世界経済は、日米欧がアジアや中東、アフリカ諸国を付き従えて引っ張っていく、という図式は過去の幻想です。名目国内総生産GDPの年間増加額は、2007年度の
IMF推計で、BRICsが1兆2900億ドル、この中で中国は単独で6000億ドル占め、減速した米国の増加額を追い抜き、世界の経済成長の三分の二以上を、新興国と途上国が稼ぎ出している。これが現実の世界の姿です。
つまり、今までの日米欧という経済プラットホームに加えて、新しい経済規模のプラットホームができたのです。最近のキーワードで言い換えればデカップリング(非連動性)で、世界経済が米国経済の影響を受けにくく、相関関係が薄くなる現象を意味します。
中でも中国は、いろいろ所得格差の問題を指摘されていますが、中産階級は人口の2割もいて、この人数は日本の総人口を遥かに上回っている上に、2020年には4割に増えるという見込み(中国社会科学院)というのですから、日本人の常識感覚を超えます。
別に中国進出を推奨しているわけではありませんが、ちょっとデータを拾えば、このような現実が分かります。
日本企業は、人口1億ちょっと超える中で、激しい販売競争をしていますが、世界に眼を転じれば、そこには膨大な人口を持つ、新たな別のプラットホームが存在しています。
弁当は世界に通じる
櫻井寛氏が、駅弁は台湾、韓国、タイにしかないと指摘していますが、昨年6月、NYのグランド・セントラル・ターミナルから、メトロノース・レイルロード線で北へ向った列車、その際一緒だった地元の女性、まだ昼食していないからといって、駅構内ですし弁当を買ってきて食べ始めました。世界の大都市のスーパーでは、サンドイッチとすしが並んでいて、勤め人が昼食に買って食べるのは普通の風景です。
また、サンパウロ国内線専用コンゴーニャス空港では、メインロビーが「現代」という漢字表示のすしバーだけ、そこで多くの人が箸で食べています。すしは世界の普通食になっているのです。30年前は「日本人は魚を生で食べる人種だ」と蔑視されたことを憶えていますが、いつの間にか世界の定番食になっているのです。
加えて驚いた経験は、昨年11月、ドイツのカールスルーエからパリにいくため、フランス高速鉄道TGVに乗車したところ、ボーイが赤いオシャレな包装の、三段重ねの弁当を持ってきました。中はパン、チーズ、ハム、サラダに白ワインと水。今までヨーロッパで多くの列車に乗りましたが、弁当のサービスは始めてでした。これはサービスが変わったなという印象とともに、ヨーロッパの鉄道で駅弁商売が可能ではないかとも思いました。
日本流で勝負
再び、橘・フクシマ・咲江氏の指摘に戻ります。「以前は米欧の標準に合わせて日本人が変わらなければ、と考えていた。しかし今は日本固有の付加価値をどう世界に売り、差別化していくかが重要だと思っている。定時に到着する電車や宅配便。旅館のおもてなしなどのきめ細かなサービス。世界をリードする環境技術。ビジネスや経済だけでなく、政治、外交でも日本ならではの価値を探し出すことが大事だ」。なるほどと思います。
変化の質が変わっている
どうも変化に対する質を、検討しなければいけない時に来ているように感じます。司馬遼太郎氏が、勝海舟と坂本竜馬について語っている幕末時は、欧米基準に対して追いつく必要から、欧米のシステムを取り入れなければならない、という変化でした。
だが、今の実態は、日本固有の文化価値が、欧米に受け入れられ、歓迎されているという事実実態なのです。ということは、今までは欧米基準に合わせて、日本人が変わらなければならない、という考えでしたが、今は日本が持っている文化を世界に普及させる、売り込む、という変化が必要とされてきているように思います。
12月の経営ゼミナールを開催した山形県の銀山温泉・藤屋旅館、ここは年間客数の4分の一が外国人でした。それも欧米・アジア・アフリカ、世界中から来ているのです。これは伊豆の下賀茂温泉伊古奈も同じで、日本の旅館のきめ細かなサービスを、外国人が認めた結果なのです。加えて、環境問題が世界の最大課題となっているのですから、日本の持つ環境技術など、その他日本固有のもの、いくらでも売り込む価値があると思います。
そのひとつの提案事例として、京王駅弁大会の会場でみる多彩な駅弁、日本国内でそれぞれ努力し、厳しい競争を展開していますが、この努力を別のプラットホームに向けたら、長期的に大きな成果を得ることができるように思います。
つまり、世界に日本固有の付加価値を伝えるために、何をするかということへの変化。これが今求められていると思います。日本から日本を見るのでなく、世界から日本を見て、日本に存在する素晴らしい文化を伝えること、それが日本の成長条件と思います。以上。
2008年01月11日
2008年1月5日 現在地(You are Here)の確認
環境×文化×経済 山本紀久雄
2008年1月5日 現在地(You are Here)の確認
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。
ロンドンで道に迷う
昨年の2月末、ロンドンのジャーミンストリートのレストラン・グリーンス、ここのマネージャーと打ち合わせし、夕食を終え、食後の散歩を兼ねてハロッズデパートに向って歩き出しました。地図上で確認すると、ピカデリー通りを行けば、それほど遠くないと判断したのです。
ロンドンの2月は寒くて暗いのですが、ハロッズは何回も行っていますので、道に迷うことはないだろうと、速足で歩いているうちに、いつの間にか暗い道から、さらに暗い人気がなくなって、これは道に迷ったな、と慌てて地図を広げましたが、周りに標識がなく、今の自分はどこにいるのか、その現在地が確認できない状態になりました。
ロンドンの治安
ご承知の通り、ロンドンの景気は絶好調です。一人当たり2006年の名目国内生産(GDP)では、日本が世界18位、英国は11位です。
英国病に罹り、長らく低迷していましたが、サッチャー革命でロンドンシティ金融力が盛り返し、お金と共に世界各地から人々も集まって、結果はヒースロー空港での入国審査がしつこい、ということになりました。
ニューヨークの入国審査が9.11で厳しくなったといいますが、ヒースロー空港の方がより厳しい上に、係員は最初から何かを疑ってくるので、全員目付きがよくありません。ようこそロンドンへ、というウェルカム態度は皆無です。
という意味は、ロンドン市内は危険だということを表しています。外国人が大勢入ってくると治安は悪化します。ですから、ロンドン市内の暗い道を一人で歩くのは危険です。そのロンドンの暗闇で道に迷い、現在地を見失い、一瞬不安に陥りました。
正月不安のスタート
この正月は不安が歩いています。昨年の正月とは大違いです。サブプライムローン問題は根深く、アメリカ経済も減速気味、株式市場も日米欧ともに下落、原油は1バレル100ドルを一時超え、いよいよインフレ気配が強くなり、日本の財政悪化の改善も期待薄で、福田内閣の支持率は低迷したままです。
ロンドンでの道迷い不安は、コート姿の英国紳士を、暗闇の中でようやく見つけ尋ね、地図で現在地を確認でき、ピカデリー通りに戻り、向こうにハロッズの明かりを見出すことで解消できました。地図という道標があったからです。
しかし、日本の不安は簡単に解消できないでしょう。時間がかかると思います。その最大の理由はグローバルな世界になって、日本が世界の中でどの現在地にいるのか、それを判断する道標を、的確につかむことが難しいからです。今までのように、日本人だから日本のことだけ考えていればよい、という視点では解決が難しいのです。
例えば、日本の株式市場への投資は60%が外国人ですから、株式投資に当たっては、世界が日本をどう見るか、つまり、日本の位置づけを世界的視野で判断しないと、的確な株式投資のリターンは難しいということになります。日本の眼前に展開される実態を、いくら日本の立場で分析し、整理したとしても、それは万全とはいえないということです。世界の動きと、日本の動きがつながっている時代なのです。
変化に対応していない
堺屋太一氏が以下のように指摘しています。(1月4日.日経新聞経済教室)
「日本は急速に衰えている。知価革命のうねりの中、中国やロシアですら改革を進めたが日本はできない。このままでは日本は『最後に滅ぶ社会主義国』になりかねない。『内弁慶』主義を脱し、荒廃した官僚の倫理を高め、夢と楽しみに満ちた社会を築く未来志向の改革が必要だ」と述べ、そうなった要因は、世界の変化・人類の変質に対応していないと主張します。
つまり、物財の豊富なことが幸せだ、という信念に基づき規格大量生産化したことによって、過去日本は成功した。だが、80年代から文明が変わりだし、人間の本当の幸せは、物財の豊かさでなく、満足の大きさになった。
ところが、この変化に日本の社会運営システムが合致していないというのです。
世界から日本を見る
そうだろうと思います。政府も企業も改革という掛け声は元気よく発します。しかし、実際に改革が進んだかどうか分からないのです。事実、一人当たり2006年の名目GDPが、ピークの95年より7700ドル・18%も減っているのですから、この間は改革が進まなかったのでしょう。改革を先送りし続け、それが世界における日本の存在価値を減少させているのです。
では、どうして改革が進まないのか。それは日本の経済規模がそこそこあるので、国内市場にしがみついていれば、中途半端なサイズの事業でも生きていけるという「共同幻想」が日本人にあり、そこから脱皮できない癖がついているので、結局、改革を先送りさせるのです。
このような人の中から、時折、外国は嫌いだと発言する人にお会いすることありますが、嫌いということと、世界と日本はリンクしているという事実認識を区分けしないといけないと思います。
ペリーが来航した以前の、江戸時代ではないのですから、眼を世界に向け、世界から日本を見るという視点が不可欠と思います。
来年こそ改めたいこと
日経新聞「何でもランキング」(12月29日)の「来年こそ改めたいこと」は、頑張って直そうと思っているのに、なかなか直せない、そんな「ぜひ改めたい性格や行動」を、20代から60代の男女103人ずつ、合計1030人からの回答です。
1位は「整理整頓や片づけができない」、2位が「飽きっぽくて長続きしない」、3位が「やるべきことを先送りする」がベストスリーで、これを見てなるほどと思いました。「整理整頓や片づけ」は、物事の分析問題に通じます。情報を分析し未来を予測するためには、実態データの整理整頓が最低必要条件で、これが出来ない人は、問題点の抽出と分析が出来難いと思います。
「飽きっぽい」は、目的に到達しない根本原因です。途中挫折の癖がついていては、目的達成は出来ないでしよう。
しかし、3位の「先送りする」、これが日本全体の問題点と思います。掛け声ばかりで改革が進まないのはこれです。「特に仕事面で、面倒なことほど先延ばしにしてしまい、余計に状況を悪化させてしまう」(34歳男性)と補足説明があるように、改革という簡単ではないことを先延ばしする癖が、日本人に多いことを証明しています。
先送り体質が、世界の中で日本の存在感を低下させている、最大要因と思います。
道標で現在地(You are Here)の確認
この正月の、日本を覆う不安の解消には、改革を断行するしかありません。また、その改革の方向性は、世界の「80年代からの文明変化」に対応することしかありません。さらに、その改革を先送りする日本人の体質を、改革することしかありません。
そのためには何が必要か。その方策にはいろいろあるでしょうが、まず不可欠な前提は、今、どこの時点に位置しているのか。どういう環境・条件下にいるのか。という現在地(You are Here)の確認が必要です。加えて、それはⅠ am Hereではなく、他者から見た客観性ある現在地でなければなりません。
暗いロンドンで、自分がいる位置を、地図という道標上にペンで「お前はここにいる」と示されたとき、不安が消えることを学びました。
不安を解消するには道標が必要であり、道標を持つから現在地を知ることができ、現在地を知るから改革の必要性を強く感じ、しっかりした強い改革認識を持つことで、先送りせずに改革を遂げる。これが不安解消の工程プロセスです。しかし、道標を決め、現在地を確認する作業は、かなり困難です。だが、それが今年の課題と思います。以上。
2007年12月21日
2007年12月20日 何を成功基準とするか
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年12月20日 何を成功基準とするか
NYに来た香港人
前号で、ドイツ人の日本好きをお伝えしましたが、香港にも「東洋迷」と呼ばれる、熱心な日本ファンが増えているようです。「東洋」は日本を意味し、「迷」とはマニアを意味し、普通程度の日本理解では満足しない人たちが、日本研究を様々な角度から行ってから、日本に来ているらしいのです。
その影響は「ぬりえ美術館」にも現れています。昨年、掲載された香港の雑誌を手に、都電巡りしながら荒川区の「ぬりえ美術館」を、何人もの香港女性が訪ねてくることを確認できることから、「東洋迷」は事実であると判断します。
しかし、今年の6月、NY元パンナムビルの近くの、弁護士事務所勤務の香港人女性は、意外な事実を語ってくれました。現在40歳。7歳のときにNYに来ましたが、それまでは香港の小さな一室に6人で住む困窮家庭であり、自宅の回りも同様の貧しい家庭だらけで、玩具など買ってもらえる環境ではなかったといいます。
この女性が香港にいたのは、今から33年前の1974年、昭和49年ですが、その頃の香港は貧しかったのでしょうか?。
当時、仕事の関係で何回か香港に行きましたが、街中は活気に溢れていましたし、あの頃は多くの日本人が、世界の一流ブランド品を買いに香港に行ったと思います。ですから、景気は悪くなかったと思っていましたが、この女性から聞いた内容は、こちらの理解とは大きく異なっていました。
今の香港
香港郊外に住む19歳の女性、ファストフード店勤務で月収6万円、35平方メートルのアパートの4人暮らし、お金がないので高校にも行けない。
このような貧しい人たちが増えて、所得格差が広がっていると、日経新聞「民力アジア」連載(2007.11.26)の中で報道されました。
さらに、同記事は続けます。香港で貧しい人が増えていることに加えて、会社員は「仕事が楽しくない」という人が全体の89%もいて、これは前年より14%も増え、その要因として「香港ドリーム」が見えないことだと結論化しています。
また、その延長として、起業家が減少し、起業家の割合は調査対象35カ国の下から3番目であり、挑戦を恐れる機運が広がっているとも伝えています。
しかし、最後に、有機野菜レストランで成功した経営者が語った言葉、「自分の足で成功の機会を探さない限り問題は乗り越えられない」という記事で終着させています。
ストーリーの筋書き
この記事を読み終えて、なるほどと思いつつも、NYで香港女性の話を聞いている立場としては、今も33年前も、いつでも貧しい家庭は存在するという、世の中のセオリー通りである事実確認情報として、まず受け止めました。
次に、記事のストーリー展開が、最初に貧しい人の事例を挙げ、次に、その要因は所得格差の拡大であり、その背景には「香港ドリーム」が見当たらないからであり、事業意欲も低下しているが、しかし、個々に見れば成功している人もいる。
だから、「自分の足で成功の機会を探すべき」という「べき論」、つまり、成功者になれという主張で、その成功とは「お金」を得ることにおいています。
成功基準
成功というものを、お金を基準として判断すれば、必ず持ち高で序列がつきます。また、金額という数字は明確ですから、必ず所得格差として表現できます。
つまり、格差が確実に発生するものを成功基準として、今の実態を論じるのですから、当然に生じるであろう格差へのからくり、それをわかっていながら、次に、今度は、その生じた格差を問題として指摘する、というストーリーの展開です。
このような書き方が、日経新聞の一面紙上でなされ、読者はそれを疑問を持たず読んでいる人が多いと推察いたします。
時代は変わっている
第二次世界大戦が終わったとき、日本人の殆どは食べられない生活でした。その当時を体験している者として、お腹を空かして、食べ物探しに歩き回ったことを鮮明に記憶しています。ところが、今はどうでしょうか。食べられない家庭という存在、皆無とはいえないと思いますが、周りを見渡すと「ほどほどの生活レベル」の人たちが普通です。
つまり、普通の生活ができているという前提に立った上で、お金を基準にして格差を論じているのです。NYで会った女性、香港にいては一家が食べられないので、手づるを探して、アメリカへ脱出し、NYの叔母さんから人形を貰って、生まれて始めて人形を抱きしめたという、哀しくも嬉しかった思い出を語ってくれました。
しかし、今の日本も香港も、一般的に「食べられない」「人形を持てない」というレベルではありません。日本の戦後や、33年前の香港とは比較出来ない豊かさなのです。
良い仕事を続ける
ロボットデザイナーの松井龍也さん、ロボットデザインの草分けで、1969年生まれの38歳が、次のように語っています。(日経07.11.25)
「研究者やマニヤのものだったパソコンは、アップルのようなベンチャー企業が一般の人にどのように使ってもらうか考えて、工業製品としてデザインしたから、産業になった。ロボットでもそれができないかと思って、2001年にロボットのデザイン会社を設立しました」と語っています。
ロボットに眼をつけたのはパソコンの事例からであり、それまでの都市計画分野から転じた結果、今や世界的評価の高い人物になって、さらに、次のように語ります。
「僕たちの世代にはマネーゲームに懸命な者もいますが、少人数で質の高いものを創出したいという者が多い。生意気なようだけれど、物質的な豊かさを知っている世代ですから。良い仕事を続けるには、会社も家計も赤字を出さないことが大切だけど、お金持ちになる必要はないのです」
つまり、成功基準は「お金」ではなく「良い仕事を続ける」ことにおいているのです。
中田英寿
元サッカー選手の中田英寿さんが、責任監修したというクーリエジャポン2007年
12月号が、発売直後完売し、増刷したと編集長が1月号で語っています。これで中田さんの人気のほどが分かります。その中田英寿さんが国際サッカー連盟(FIFA)の親善大使になりましたが、クーリエジャポン1月号で、30代女性読者からの質問「世界のために自分は何ができるのだろうか」に、「自分が“良い”と思うことを少しでもこつこつ積み重ねてやること」だと答えています。
野村ホールディング
米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)関連で、1400億円超の損失を計上した野村ホールディング、米国の関連事業から完全撤退を決め、来年に向け、次の戦略を古賀信行社長が次のように語りました。(日経2007.12.15)
「米国では、自分の得意な分野以外にも中途半端に事業を漫然と広げすぎていた。これまではグローバル化を進めることが自己目的化していた。しかし、本来はまず顧客がいて、顧客ニーズがある分野に事業を特化すべきだ」と。
なるほどと思います。あの優れた野村集団でも、自社にとって「良い仕事を選ぶ」という基準ではなく、事業を漫然と展開していたのです。
何を成功基準とするか
サブプライムローン問題で、一斉に日本経済も世界経済も成長率を下方修正という事態となりました。時代の変化は常に続き、予測できない大問題が発生します。このような社会で生きていく、企業経営を続けていく、そのためには判断基準を変化させる必要があるようです。つまり、成功基準として何を選定するか。それが問われる2007年の年末ではないでしょうか。今年一年間の愛読を感謝します。良いお年をお迎え願います。以上。
2007年12月06日
2007年12月5日 ドイツの日本
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年12月5日 ドイツの日本
中田英寿さん
サッカー界から引退した中田英寿さんが旅を続けています。その中田さんが旅の中で感じた日本について、次のように述べています。(クーリエ・ジャポン12号)
「悪い印象はないでしょうね。日本人って非常にいろんな国で受け入れられていると思うんですよ。もちろん戦争で戦った国なんかは別かもしれないですけど、特にヨーロッパでは日本のイメージは良くて。まずは経済、あとはテクノロジーとかで日本はすごいというイメージがありますし、他には禅のイメージも強くて、日本人は他の人種に比べて怒らないし、すごくいい人たちが多いと思われている。ビザや国境での手続きでも、日本人は信用されているし、これは大きなメリットだと思いますね」
これに全く同感です。
カールスルーエの街
カールスルーエはドイツ南西部、バーデンウェルテンベルク州、街の中心に城があり、そこから放射線状に道路が広がっている、バロック時代の典型的な計画都市です。第二次世界大戦で大きな被害を受けましたが、歴史的建造物の大部分を元通りに修復しました。ドイツでは戦災の被害から、街を元通りにすることが多く行われていますが、どうもその発想の根源に、「街は記憶装置」(池内紀氏)という考え方があって、街並みをがらりと変えてしまったら、過去の歴史が消えてしまう、という意識が強いように感じます。
その代表例がカールスルーエで、ドイツで始めての名門工科大学もあり、石油精製、電機、機械、鉄鋼、建築資材、医薬品などの企業も多く、人口は約30万人の街です。
カールスルーエの独日協会との縁
カールスルーエを知ったのは一人の建築家からでした。温泉で有名なバーデン・バーデンで、かの美人女優マレーネ・ディートリッヒが「世界で最も美しいカジノ」と称した建物を見学し、これがフリードリヒ・ワインブレナー(Friedrich Weinbrenner)の建築であって、カールスルーエで市庁舎他有名建築物を遺していることを聞き、それを見に行ったことからでした。
その後何かとこの街には縁があり、何回か訪ねるうちに、ここの独日協会という組織の存在を知ったのです。独日協会とは、日本に関心ある人々が集う会です。
ドイツのクラブ活動
ここで少し補足したいと思いますが、ドイツ人の余暇の過ごし方は、日本人に比べ個性的で、多くの人は「クラブ」を拠点として余暇活動をします。
この「クラブ」とは、同好の士が集まってつくるもので、いわゆる何々同好会とかの名称をもち、おもに公益法人としてNGO・NPO のような性質と、学校のクラブ活動の性質を兼ね備えたものです。合唱会、切手収集、つり同好会、コーラス、まんがアニメ同好会、ありとあらゆるスポーツ団体もあり、その中には黒い森同好会(活動はおもにクロスカントリー)などなど多彩で、この一つとして独日協会があり、この他に日本語学校も同好会として組織化されています。
独日協会の日本好きな人
現在、カールスルーエの独日協会は、会員200名、内日本人は12名、年齢は高校生から高齢者まで幅広く、毎月定例会が開催され、平均して30名から40名が参加し、日本食レストランで食事しながら熱心に活動しています。
活動内容は、勿論日本の研究ですが、今回、その会員のお宅にお伺いする機会がありましたのでご紹介いたします。
(横浜に4年住んで好きになった)
カールスルーエの目抜き通りを走る路面電車で終点まで行き、森を開発した住宅街の地下一階と地上三階の棟続きの家、そこの46歳の専業主婦を訪問しました。
ご主人は電機関係の仕事で日本に転勤し、昨年まで4年間横浜に住んでいました。
玄関に入るとコート掛けの隣に、見慣れた日本語がかかっています。何と相田みつをの掛け軸です。日本にいた時に三回も「相田みつを美術館」行ったと、日本語で語ってくれます。上手な日本語ですので、日本で一人旅ができたでしょうと伝えますと、頷き、一番の思い出は、夫と子供が先にドイツへ帰った2006年の夏、一人で京都と紀伊半島を廻ったことだ、とうっとりした表情で語ります。
さらに、日本食も大好きで、中でもすしが好きで刺身も自分で作って食べるし、てんぷらを揚げ、そば・うどんも打つというレベルです。カレンダーも日本の風景物ですが、企業名はカットするという細かい配慮が行き届いていて、二階への階段には東海道の浮世絵が飾ってあります。
玄関からキッチンと居間はワンルームで、水道水を薬缶で沸かし、急須に煎茶を入れて出してくれます。水道水はそのまま飲めます。壁の食器棚の上には、ヤマサ風味出しの缶、柿の種の大きな缶、だるまが三個など飾られ、家の中は日本が一杯です。
趣味はスポーツで、サイクリング、ハイキング・ワンダーフォーゲルですので、日本でもよく鎌倉界隈と東京周辺、加えて北海道から伊豆、京都、紀伊半島、岡山、広島、九州を廻り、温泉も各地に行ったが草津の露天風呂が一番よかったといい、日本のよさは伝統文化と自然だと言い切りますが、地元の温泉バーデン・バーデンには行ったことはないと笑い、日本人より日本が詳しいと、再び爽やか笑顔を見せます。
(すし教室参加から日本好きに)
教会前に建つアパートメントの二階。入ると天井が高く、廊下の壁には現代絵画デザイン、居間には大きな現代画が立てかけてあり、機能性と知的感と創造性がミックスされた、180㎡の夫婦二人住まいの高級住宅です。
その中の一部屋は日本部屋で、奥さんの名前であるルボム「留慕夢」の掛け軸から始まって、日本に関する本や資料・物品が部屋に溢れています。
日本とのきっかけは、すしです。奥さんがご主人に、市民大学「すし教室」のチケットをプレゼントし参加し、独日協会を知り入会して、カールスルーエ合唱クラブの日本公演に随行し、日本各地を廻って、今や大の日本ファンになったのです。
この合唱クラブは、カールスルーエ音楽大学教授が指導し、アマチュアの域を超えていると自慢していますが、すしの魅力から日本好きになったように、今やすしの人気は、世界中に広がっていることを証明する事例です。
(日本の軍人に出会ったことから)
カールスルーエの郊外駅を降り、小高い丘の坂道を歩き、道路からのアプローチが長い一軒家のドアを開けると、赤いセーターにジーンズの76歳の長身女性がにこやかに立っています。お土産のポーチを渡すと、中から膨らませるためのビニール袋を取り出し、ここに日本の空気が入っていますね、と懐かしさに溢れる表情を示します。
この女性と日本の接点は11歳の時に遡ります。北ドイツ地方で父が軍港を造る仕事をしていた関係で、その地方に住み、よく妹と海岸の砂浜で遊んだ。
ある日のこと、向こうから他国の見慣れない軍服の人が、手を後ろに組んで歩いてきて、一つの果物をくれた。始めて見るもので、リンゴではないということは分かったが、どうやって食べるかわからなかったので、そのまま口にすると苦かった。その軍人は笑って皮を剥いて食べさせてくれた。甘いみかんで美味しかった。
次に、ポケットから一枚の写真を出して見せてくれた。家族が写っていたが、ドイツとは違う服装、中国人ではないと直感的に思い、後で知ったが着物姿であり、日本人だと分かった。そのとき以来、ずっと強く日本に興味があり、日本の本や資料で日本を研究し、庭を日本庭園にした。そう言われ庭を見ると灯篭がいくつもあります。
この庭仕事をしてくれた庭師から、独日協会の存在を知り、紹介してもらい訪ね、日本に行きたいと申し出をすると、入会しなさいといわれ、1998年に3週間、憧れの日本に行くことが出来た。実際の日本は素晴らしかった。表現できないほど夢中で旅を続けた。勉強した日本語がデパートで通じ、買い物が出来たのも嬉しかった。
中田英寿さんの発言通り、ドイツ地方都市でも日本が受け入れられています。以上。
2007年11月21日
2007年11月20日 すべてに戦略が優先する
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年11月20日 すべてに戦略が優先する
アジア王者
サッカーのアジアのクラブ王者を決めるアジア・チャンピオンズリーグ(ACL)は、14日に決勝を行い浦和レッズがセパハン(イラン)を2-0で下し初優勝しました。
この日の埼玉スタジアムは59,000人が入って、全体が赤で埋まり、そこに星印の人文字が一段と鮮やかでした。
スタジアムに行けなかった、さいたま市浦和区民の多くはテレビに釘付け、永井選手が思い切り打ったシュートが先制点となって、さらに追加点を加え終了すると「ウィーアーレッズ」の歓声があちこちの街角で爆発しました。早速、伊勢丹や10月オープンしたばかりの浦和パルコなどが「浦和レッズおめでとうセール」を実施し、そこに人が集まって、NHKテレビがニュース報道するほどです。
もともと浦和レッズは、熱心なファンとその人数の多さ、収入も大きく、以前から黒字で、立派なクラブ経営をしていました。しかし、かつては実力なき人気先行で、
2003年にはJリーグ最下位になり、J2に陥落したときは終わりかと思いましたが、よく復活し、今年のJリーグ優勝も目前です。
何故に、このように強くなったのか。それにはいろいろ要因が重なっていますが、それをひとつに絞って理由を挙げれば「戦略思考」です。野望ともいえる「アジアから世界へ」という目標を掲げたことです。世界の一流クラブのACミランなどと戦い、それに勝って、世界の王者になる。それが浦和レッズの戦略なのです。この野望「戦略思考」を持ったこと、それが今回のアジアチャンピオンを獲得させたと思います。
橋本高知県知事
NHKから地縁のない高知県知事に転じ、地方自治に新風を吹き込んだ橋本大二郎知事が今期限りで引退します。
その橋本知事に県議会の決議が大変なことを突きつけました。それは「今期分の退職金(約2700万円)返上を求める決議」を賛成多数で可決したのです。
決議に強制力がないため、知事は受け取る意向を示していますが、どうしてこのように知事の仕事を全面拒否する姿勢を、県議会は示したのでしょうか。
11月15日に行われた守屋武昌防衛省前事務次官に対する、参議院外交防衛委員会における証人喚問では、本人から「退職金は返納する」と明言発言がありましたが、これは過去8年間にゴルフ接待が300回以上、1500万円以上という明白な倫理規定違反であり当然です。
だが、橋本知事はこのようなスキャンダルはありません。かえって4期在任中に打ち出した斬新な施策は多いのです。例えば、官官接待の全国初の廃止、職員の勤務年数などを基準に上の階級の給与を支給する「わたり給与」の廃止、個人・法人から一律
500円を徴収し森林整備に当てた森林環境税を全国初の導入、同時に情報公開も進め、従来からのしがらみを断ち切り、さまざまな業界団体の圧力・要求をはねつけるなど、評価する県民も多いのです。
では、何故に、議会から退職金返上を求められる決議を受ける結果になったのでしょうか。それは「高知県経済の低迷」の一言に絞られます。県経済は「足踏み状態が続き、よいところがみつからない」(四国銀行・青木頭取)という見解が示すように、確かに各経済データでも全国最下位に近い実績で、議会は知事の経済政策の妥当性に疑問を呈したのです。では、どうして、4期にわたった県知事時代に経済が浮上しなかったのか。
勿論、高知県が持つ構造問題もあるでしょうが、県幹部が「知事の経済政策には戦略がなかった。悪く言えば行き当たりばったりだった」という指摘、これが重要です。
橋本知事が16年間、改革派知事の先駆けとして、一生懸命に仕事をした。新しいことも多々取り入れた。だが、経済政策行動に一貫性が欠け、県民の生活基盤である経済が不振で、「橋本知事では経済再建は期待できない」という評価になって、退職金返上議決となったのです。厳しいものです。
もし仮に、16年前の就任時に、経済を中心においた適切な戦略を構築し、それを議会に提案し、了解を得て進めていたならば、たとえ、現在と同じ経済実態であったとしても、退職金返上決議という結果とはならなかったでしょう。
物事を進めるに当たっては、最初に戦略構築を図ることが必要で不可欠です。
スーパーオオゼキ
先日訪問したスーパーのオオゼキ、その好業績にはビックリしました。多分、このオオゼキという名前、東証二部上場企業ですが、殆どの方が知らないと思います。新聞雑誌に一切記事が出ません。しかし、業界では知られた優良企業として著名です。
経営実績は18期連続増収増益で、平成19年2月期の売上高626億円(前年比
12.2%増)、経常利益46億円(前年比10.8%増、売上高比7.4%)、純利益27億円(前年比13.6%増、売上高比4.4%)という見事さです。
店の数は29店舗。出展地域は世田谷区、大田区、目黒区、品川区に限って、方針は①個店主義、②お客様第一主義、③地域密着主義の三つです。
好実績を支えている実態は、食品スーパー業界の各指標から証明できます。
1.経常利益率は業界トップ。
2.生産性が抜群で1平方メートル当たり売上高はトップ。
3.従業員一人当たり売上高は2位。
4.在庫回転率はトップ。
5.売上高販管費比率は3位という低さ。
6.総資産利益率(ROA)は第2位。
店舗運営について補足します。
1.開店時間は10時、閉店時間は21時ですが、お客さんが来れば開けるし、いれば閉めない。
2.正社員比率は70%。
3.各店は独立採算。店頭価格設定は各店舗に任されている。
4.本社要員は僅か10名で、年間150人の採用を行っている
5.業界初のキャッシュバック式ポイントカード発行、現在70万枚。
6.休日は元旦と2日のみ。
実際の店頭で、いろいろ説明を受けている間に分かったことは、ここは「個店主義」と「お客様第一主義」を本当に貫いているということです。
食品スーパーに来るお客さんは何を求めるか。それは時折スーパーに買い物に行く、自らの経験で分かりますが、食品の鮮度であり安全です。
一般的に、大型スーパーでは、本部が一括大量仕入れし、流通センターから各店に配送され、その時は価格が決まっています。つまり、仕入れと価格設定は本部の仕事であり、流通センター経由ですから、そこに時間がどうしてもかかります。
ところが、オオゼキは違います。29店にそれぞれ仕入れ担当者がいて、毎日、築地と大田市場に行くのです。その日に仕入れたものを、その日に販売するシステムです。 一見、無駄なことのようです。29店分をまとめて仕入れした方が、人手もかからず、仕入れ値も安いと思いますが、そうしていないのです。ということは、その店ごとに、その日に仕入れた魚や野菜が店頭に並ぶのですから、当然ながら鮮度が違います。それが魅力で、その事実を分かっている人によって集客が図られ、結果として生産性が上がって、経営は好実績となるのです。つまり、「個店主義」の展開と、鮮度を求める「お客様第一主義」を追及するという「戦略方針」の徹底実行が、オオゼキの結果を示しているのです。一度、買い物されながら、実態見学されると勉強になると思います。
時代は不透明だから戦略が優先する
サブプライムローン問題、半年前までは、例え問題が発生しても、金額的に見てたいしたことなく、リスクは限定的で、全体の中でコントロールできるものであるといわれていました。ところが8月9日の問題発生から、一転してアメリカだけでなく日本も含めた国際金融市場は大荒れです。リスクを広く薄く分散させる金融新技術が、結果的にリスクがどれほどのリスクであるのかがよく分からない、という恐ろしい結果なのです。
正に時代は不透明で、巨大なヌエです。こういう時代に何がもっとも大事で重要か。それは自ら向う方向性の確かさで、戦略がすべてに優先するという思考です。以上。
2007年11月05日
2007年11月5日 そう単純でない
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年11月5日 そう単純でない
BRICsとブラジル人
BRICsのブラジルは日本から遠い。成田からNY経由の直行便利用で24時間、ようやくサン・パウロのグアルーリョス国際空港に到着しました。空港から市内中心部に向かう道路は四車線の広さですが、一日中渋滞していて、経済実態が順調なことを、車の増加による渋滞が示しています。
ブラジル経済成長率は1995年が2.9%、06年が3.7%、07年1月から6月は4.9%、年々成長率が増えてきて、以前は資源輸出中心でしたが、07年1月から6月の家計支出は5.9%増、民間建設は4.3%増となっているように内需中心に成長しています。このようにBRICsのブラジル・ロシア・インド・中国の成長が、先進国が成長鈍化しつつある世界経済を引っ張っていることは、よく知られています。
そこで、その事実を確認してみようと、ブラジルでお会いした多くの人にBRICsについて話題を向けてみたが、思わぬ答えが帰ってきて驚くばかりでした。
まず、BRICsという言葉、それを全く知らない。こちらが解説しても、眼は疑いを持って納得しない顔つきを示す。そこで、ブラジル地理統計院発表の経済データを示すと、今度は「そのようなことはテレビで発表されていない」「政府が知らせないようにしているのではないか」というような疑問系で反論してきます。
では、海外からブラジルはどのようなイメージで受け止められているのか、という質問をすると「余りよいイメージはないだろう」「治安が悪く、貧しさが目立ち、文化面が遅れている」という答えに、今度はこちらが唖然とするばかりでした。
この体験をサン・パウロの日系企業幹部に話してみますと「その通りだ。殆どBRICsということを知らない」との回答でしたから、まず、ブラジル国民は全く認識していないといってもよいと思います。
日本では、毎日のようにBRICsが話題となって、関連するデータや資料が多く出回っていますが、当事者のブラジル人は無関心ですから、現地でBRICsと関連づけようと一般の人々に聞いても、世界が認めているBRICsブラジルの背景要因を、「そう単純」に現地でつかめません。
現代美術とヘリコプター
MASPサン・パウロ美術館には、中世以降の世界の作品絵画約1000点の名画が並んでいます。ここの建物は特徴があって、四ヶ所の角柱でしか建物を支えていない構造となっています。したがって、一階は外と連動した吹き抜け。二階からの展示場も柱なしの美術館で民営です。
ここで展示されている現代美術作品を見ましたが、作品の意味背景が分からない。そこで学芸員のパウロ・ポルテラさん、小柄なイタリア系の親切な人ですが、ガイドブックを持ってきて説明してくれました。
例えば、黒色の四角が九つランダムに壁に貼られている作品、これは上空からビルを撮影すると、屋上は四角形で建築されていることが多いので、その四角をヒントにしたものであり、現代美術のアイディアの基は現代の実態にあることを示している。これがパウロ・ポルテラさんのガイドブックを見ながらの説明でした。
なるほどと思いつつも、サン・パウロの実態を知ってみると、作者はもっと違った風刺的要素で創作しているのではないか。サン・パウロのもつ現代矛盾を表しているのではないか、「そう単純」な思考から作品を創作していないと推測しました。
現在、サン・パウロの自家用ヘリコプター機数は世界一で、その利用者は富豪者であり、用途は日常の移動手段という実態です。
ブラジルは、約500の家族が、一年に生産される国富の5分の2を蓄財し、残りを1億8000万人が分け合っている、と言われている格差大国です。特に、サン・パウロはブラジルで最も豊かな街であると同時に、最も貧しい街です。
ここでの富豪者たちは、酷い交通渋滞とスラム街が同居している街中には、なるべく足を踏み込まないようにし、誘拐・強盗からの防衛もかねて、200以上ものヘリポートを使って、タクシーを乗り回すようにヘリを活用しています。
また、ブラジル人は海が大好きで、週末は市内から70km離れた海岸に向う高速道路は大渋滞となるのですが、ヘリだと30分で到着するので、金曜日の午後は数百機のヘリが海岸に向います。さらに、サン・パウロでは、最高級のスポーツジムやレストラン、銀行などはすべて高いところにあって、富豪者たちは、騒音や悪臭とは無縁なもう一つの空中都市で生活しているのです。
つまり、サン・パウロでは、上を見上げる人と、下を見下ろす人の生活が区別されていて、上空ではヘリによって自由に飛びまわっている社会。一方、庶民たちは予定時刻に来たことがないバスを待ちながら、停留所でひしめき合っている社会。それが混在している街がサン・パウロです。
MASPサン・パウロ美術館に展示されている、黒色四角現代美術作品の背景要因を、ビル屋上から発想するにしても「そう単純」ではない視点があると思いました。
東洋人街の日本語看板
サン・パウロの日曜日、地下鉄で東洋人街があるリベルダージ駅に向かいました。改札口を出ますと、そこは緩やかな階段であり、その途中のベンチに座っているお年寄り夫婦の日本語が耳に入ってきて、日本人の多い東洋人街に来たという雰囲気になります。
階段を上りきったところは狭い広場で、日曜日は屋台がたくさん出ています。ヤキソバ、今川焼き、お好み焼き、焼き芋、天ぷら、民芸品、革製品、銀細工など。観光客よりはサン・パウロ住民が多勢繰り出して、広場は歩くのに苦労するほどです。
この広場から商店が並ぶガウバオン・プエノ通りには、両側に赤い柱に提灯型の街灯、日本語の看板が並んでいます。昔の日本の駅前商店街という感じですが、日本とは活気が全然異なって人が多勢歩いています。通りに面した小さい丸海スーパーに入ってみますと、日本の食料品が何でも揃っています。出口にはレジが七台もあって、土日は店内に入りきれないほど客が来ます。
ところが、この日本語看板の商店の多くが日系人経営ではないのです。客が溢れている丸海スーパーは中国人経営であるように、今や日系人経営は化粧品のIKESAKI、着物の美仁着物、宝石の明石屋、それと地下鉄駅前書店の太陽堂くらいです。
そのことを聞いてすぐに「経営の失敗か」と想像しましたが「そう単純」ではない状況が背景にあり、そこに日本経済が関係していました。
1988年から90年にかけて、日本はバブル絶頂期で人手不足でした。そこで各企業は人材を海外に求め、法務省が認める日系人、それは日本人の親族がいることで、それに合致すると労働ビザが下りるので、ブラジル日系人の間で日本行きが一大ブームになりました。確かに、日本で一年も働けば相当のお金が溜まり、ブラジルは当時不景気で超インフレ、一年間の貯金を持って帰ると一大財産となり「日本は宝の山」と言われたのです。その結果、日本行きの斡旋会社がたくさん出来、そこに1000USドルから1500USドルの現金を払っても、日本に行きたい希望者が殺到した上に、日系人と結婚したいブラジル人が多数発生しました。日系人花嫁求めるという新聞広告も出るほどのブームで、日本までのエアーは常に満席。空港は日系人で一杯。週二便のJALだけでは足らず、週二便のブラジルVARIG航空、加えてヨーロッパ周りで日本へ行く便の利用もあったくらいの過熱ブームだったのです。
その日本行き大ブームに、東洋人街の商店主も乗り、店の権利を中国人に売って日本に行った結果、日本人経営が少なくなりました。勿論、その他の理由もあり日本人経営は少なくなったのですが、いずれにしても、その後、日本のバブルが崩壊し、一転、不況になると、働いても残業は減り、収入の伸びは少なく、為替の変動もあり、「日本は宝の山」神話は崩れ、ブラジルに帰った人もいましたが、日本に長く住み続けて、子供の教育問題や、ブラジルに戻っても失業率が高いので適切な仕事先確保が難しく、結局、そのまま日本で働いている人が30万人くらいいます。
日本移民として始めてブラジルに渡ったのは1908年。ブラジルに「金のなる木」があると言われ、これはコーヒーのことでしたが、多くの日本人が農業移民として渡って、来年は移民100周年となります。ところが、今になってみると、当時とは反対の「ブラジル日系人逆移民時代」ともいえる現象となっているのです。
現実実態の背景に「そう単純でない」要因が存在することを実感いたしました。
以上。
2007年10月20日
2007年10月20日 閾値(いきち)
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年10月20日 閾値(いきち)
ミステリーツアー
ようやく秋になりました。旅行社から毎日のように旅行案内が届き、新聞に旅行広告が掲載されます。その中で「さわやか名湯ミステリーツアー3日間」が目に入りました。
そうか、さわやかな秋だ、温泉に入るのもいいなぁ、もう紅葉も色づいているかな、多分この時期だから北海道か東北だろう。早速、申し込みしました。
旅行社から案内パンフレットが送られてきました。初日は羽田空港から「とある空港」へ。そこから「とある観光地」を経て「とある温泉ホテル泊」とあります。翌日も「とある観光地」経由で「とある温泉ホテル泊」と書かれているのを見て、期待は膨らみます。
どこへ行くのだろう。九州や四国はまだ暑いし、台風の恐れもあるから旅行社も安全を考慮して、ら絶対に北海道か東北に決まっている。そうならば寒いのでセーターをバックに入れないといけない、いろいろ考えながら準備に時間をかけ、出発当日は早起きし羽田空港に向いました。
羽田では、もうすでに多くのミステリーツアー参加者が集まっていました。さて、どこの空港に行くのだろう。ツアー団体専門カウンターでチケットを貰ってガッカリとビックリ。何と四国の松山空港行きになっているではありませんか。完全に期待と予測は外れました。ミステリーツアーなのですから、期待に反しても文句は言えません。行き先を知らせないという企画で、それを承知で申し込んでいるのですから当然です。
さて、松山空港に着きますと、添乗員が待っていて、全員が揃ってみると、何とバス三台という人数です。随分人気があるのです。これが毎日催行されているのです。
バスに乗ると、添乗員が最初に発言しました。「本日はありがとうございます。このミステリーツアーが四国と思って参加された方はいらっしゃいますか」、答えはゼロです。
全員が四国以外、それは北海道と東北を予測していたのです。後で添乗員に確認すると、他の日にちの参加者も全く同じ傾向だと苦笑します。
ところで、外国でもこのようなミステリーツアーがあるのでしょうか。具体的に調べていないので確実には言えませんが、多分、外国にはないと思います。
家を空けて旅行に出かけるのに、その行き先も宿泊先も確認しないで、事前にお金を払い込んで、到着空港に着いてからも、その先の行程が明確でないままに観光し宿泊先に向う。もし仮に、テロ組織がこのような企画を催行して、バス一台の人たちを誘拐しようとしたら、簡単に出来ます。だが、そういう危険性を全く考えない人たちが、毎日バス三台もの人数がいるという現実、改めて、日本の安全性の高さを確認しました。
沈下橋
一泊目は足摺岬でした。岬への遊歩道入り口にジョン万次郎の銅像が立っています。なるほど、万次郎は秘密結社フリーメイソンかと、銅像の手が持つ「コンパスと直角定規」を確認し納得しました。フリーメイソンのシンボルマークは「コンパスと直角定規」です。
バスが駐車した前は、四国お遍路の第38番寺「金剛福寺」です。この寺には嵯峨天皇勅額の「補陀落東門」があり、山門前にも「補陀落東門」との碑があるように、ここが「補陀落浄土(観音菩薩が住む浄土)」へ渡海するための道場でした。昔はこの寺のように海岸沿いの道や土地のことを「辺地」(へち)とか「辺路」(へじ)と称していましたが、その後、弘法大師信仰が四国に広がって、「辺地」「辺路」は、「偏禮」「邊路」と変わり「遍路」と変化したと言われています。
また、別の説では、この「辺」という言葉には「さかい、はて」という意味があることから、験が良くないため「邊」や「遍」などに変わったとも言われていますが、今でも四国ではこの「さかい、はて」の感覚が残っていると思われる場面を見つけました。
それは四万十川に架かっている「佐田の沈下橋」を見た時です。沈下橋とは橋の上に「欄干が無く」水面からの高さがあまり高くないことが特徴で、これは、増水時に、橋が水面下に没し、流木や土砂が橋桁に引っかかり橋が破壊されたり、川の水が塞止められ洪水になることを防ぐためであり、また、壊れても再建が簡単で費用が安いという利点もあると説明され、四万十川には支流も含め47の沈下橋があります。
「佐田の沈下橋」は長さ291.6M、幅は4.2Mです。橋の上を歩きだして、中央あたりに行った時、向こうから自動車が来ました。そこで端によって避けようとしましたが、急に足がすくみ、立っていることが出来ずしゃがんでしまいました。
橋の幅は4.2M、向こうから来た車の幅は1.8M、残りの幅は2.4Mとなり、それが車の両側に分かれますから、片方が1.2Mずつとなります。この幅を人が車を避けて安全に立ち続けるに十分なのか、それともこの幅では不安となるのか。
通常、人と人とが直線に並んで歩く間隔の幅距離、これ以上詰めるとお互い息が詰まるという、いわゆる臨海距離は1Mと言われています。また、広がって歩行している時は、1㎡当たり約1.8人で、これはお互いの幅距離は50cmに相当します。これは、ホールや劇場などから退出する場合、お互いの幅距離を50cm以上詰めない方が、全員が出終わる時間が短くなることを意味しています。
「佐田の沈下橋」上に車が来た時、この臨海距離で車との間隔を50cmとり、次に自分の体の幅として60cm、そうすると片側の1.2Mの残り幅は僅か10cmとなりました。その向こうは「欄干がない」という「さかい、はて」、これを越えますと川底に直下することになりますから、足がすくみしゃがんでしまったのです。
閾値(いきち)
我々の体が行動するスタイルには、臨界値というものがあり、普段からこの臨界値を守りながら行動しているのです。そうでなければすべてやりすぎということになりますが、実は、この体の内部に潜む具体的臨界値を我々はよく知らないのです。暗黙値です。
例えば、10Mほどの道幅がある場合、誰でも問題なくその道を歩けます。しかし、人間工学的に計算するならば、人が歩くには10Mの道幅は必要がなく、せいぜい3から4Mくらいあれば十分ですから、その道幅だけ確保し、両側を削りとり、その両側を切り立った深い崖や谷をつくって、「さぁ、どうぞ」と言われても、誰でも足がすくむでしょう。
すくむ状態になる幅・地点がどこかにあるのです。逆に、すくまない道幅として何M以上ならば大丈夫だという幅ポイントがあるのです。これは、その人の精神や意識、考え方やイメージ、感覚や行動のなかに知らず知らず持ちかかえているものによって異なってきますが、これが、実は変化点なのです。
このある時点からある時点へ変化するポイント、それを閾値と言います。もし自分の閾値を知っていて、それをうまくコントロール出来たとすれば、その人の行動はリズミカル・スムースで、何事も問題なく進められ、日常生活は大きく変化するでしょう。
ティッピング・ポイント
この閾値ポイントを社会的に考えたらどうなるか。人間集団ですから、そこには多くの人が共通する閾値ポイントがあるはずです。それを知ってうまく活用すれば、社会全体が大きく変化するはずです。
これを活用して成功した事例はニューヨーク(NY)です。1990年代に入ってから、NYの治安は劇的に改善し、今では女性の夜の一人歩きもできるようになりました。
この劇的改善対策ポイントは、警察官の増員などの直接防止策ではなく、それは「地下鉄の落書き清掃作戦」でした。それまでの落書きは酷い状態で、清掃作戦は1984年から90年まで続けられました。一見、治安と関係ない落書き清掃作戦を選定した根拠は「割れた窓」理論です。ある家で一枚のガラスが割られたとします。仮に割れたガラスをそのままにしておくと、次々と他のガラスも割られていき、あっという間に荒廃した家になっていくというのが「割れた窓」理論で、これをNYの治安対策の切り札として地下鉄の落書きに適用したのです。
これは見事に成功しました。地下鉄の落書きが消えた時点を機に、NYの治安は劇的に回復し始めたのです。つまり、ある行動の累積結果が、ある一点を超えた瞬間に野火のように広がって、劇的転換するのです。この劇的転換する瞬間をティッピング・ポイントと言いますが、これは社会的な閾値を探り当てた事例です。
四国88ヶ寺お遍路とは
四国88ヶ寺の多くは海との「さかい」陸地の「はて」。弘法大師がお遍路によって教え遺した真意、それは自らの閾値を探ることを暗示しているのではないでしょうか。以上。
2007年10月05日
2007年10月5日 集中と継続
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年10月5日 集中と継続
カレーショップが増えている
9月のインド・ムンバイ滞在では、毎日カレーを食べました。ホテルの朝食はカレー中心のバイキング、昼食もインド料理店に行けばカレー、招待されたインド人家庭でも当然にカレーですから、カレーの嫌いな人はインドは難しいでしょう。
日本でインドカレーといえば新宿中村屋です。戦前インドから亡命してきたビハリ・ボースが、中村屋の娘の相馬俊子と結婚し、新メニューとしてインドカリーを取り入れ「中村屋のカリーは恋と革命の味」と評判を呼びました。
ところで、このところカレーショップの市場規模が広がり、2006年度は730億円、これは4年間で15%の成長、店舗数は20%増です。(日経新聞2007.9.27)
CoCo壱番屋
カレー専門店の日本最大は1122店舗の「CoCo壱番屋」です。この店の味を試してみようと新宿西口店に入ってみました。西口ガードに近いところですが、入ると元気の良い挨拶が気持ちよく迎えてくれます。「ニコニコ・キビキビ・ハキハキ」という社是が実行されています。野菜カレー650円を食べました。味は「グッド」。カレーにはうるさいを自認していますが満足味です。
CoCo壱番屋は中国にも進出し、カレーなど食べない習慣だった中国人に受け入れられ、上海に展開している7店舗のうち、6店舗が過去最高の売上実績を示したという経営は見事なものです。
2007年5月期の売り上げは369億円、前期比8.3%増、経常利益は36億円、前期比8.6%増、売上高経常利益率9.8%、東証一部上場企業で株価は2300円前後で推移しています。
このCoCo壱番屋創業者の宗次徳二氏に、先日お話を聞くことができました。
非常に穏やかな微笑を浮かべる宗次氏は59歳。捨て子として孤児院で育てられ、3歳で養父母に引き取られましたが、養父が競輪に狂い、財産を無くし、ホームレスすれすれの生活を送ったと淡々と語り、今はCoCo壱番屋の経営は後継者に譲り、名古屋で定員310席、地上7階のコンサートホール「宗次ホール」のオーナーで、創業者利益を基に社会還元事業をしています。
宗次氏が創業した時、それは25歳でしたが、その時から53歳まで、一人の友人も作らず、スナックもクラブにも行かず、一年間の労働時間は5600時間超、一日あたり
15時間を超えた経営集中力。朝3時に起床し、全国から送られてくるアンケートハガキに一枚一枚目を通し改善を進めてきた継続性。その驚異的な集中と継続がカレーショップを一部上場企業に育てたのです。
宗次氏ほど凄まじい努力は稀としても、物事を成功させようとするならば、ある期間「徹底的に集中し継続する」いうことが絶対のセオリーであると思います。
サブプライムローン
米国発のサブプライムローン問題、「今のところ米国と独仏英という主要先進国にとどまって『グローバル危機』にはなっていない」(日経新聞本社主幹・岡部直明氏2007.
10.1)という見解ですが、日本株式は大幅下落し、損害をこうむった人が大勢でました。そのことをグリーンスパン米連邦準備理事会(FRB)前議長は講演で次のように述べ、日本を含む世界市場に直接間接に影響を与えていると表明しました。
「日本の金融市場は米国の信用力の低い個人向け住宅融資(サブプライムローン)関連取引そのものでは打撃を受けなかったが、欧米市場でサプライム関連損失を抱えた投資家が日本株を売却したため株式相場が急落した」(日経新聞2007.10.2)
ところで、これだけ大問題となったサブプライムローン、発生するまで問題指摘はなされていたのでしょうか。世の中には優秀な経済分析専門家が多々います。この人たちは問題発生前にどのような見解だったのでしようか。
大和證券の野間口毅氏は「サブプライムローンの残高は住宅ローン全体の一割程度だから、過度の懸念は不要」(2007.5.9)、日本総合研究所の湯元健治氏は「残高ベースでのサブプライムのウェートは13%程度であり、影響は限定的に止まる公算」(2007.5.23)と、両氏から直接お聞きしましたが、結果は大問題となりました。
特に、湯元健治氏は、今回の福田内閣改造に伴って、内閣府審議官(政策担当)に就任したほどの日本でも著名な経済アナリストですが、こういう優秀だと評価されている人物でも、サブプライムローン問題を軽視していたのです。つまり、経済予測は当たらなかったのです。
社会は巨大なヌエ
考えてみれば、経済予測は当たらないのが普通です。そのことをお茶の水大学教授の土屋賢二氏は次のように述べています。
「経済現象に影響を及ぼす要因は、素人考えでも、選挙結果、異常気象、災害、感染症の流行、主要国の政変、国際紛争、テロ、有力政治家の死、画期的発明、証券取引所のコンピューターの異常発生、阪神の優勝など、数え切れない。これらをすべて考慮することは不可能である。正確な予想ができるはずがない」(日経新聞2007.9.6)
巨大なヌエを相手に予測しようとしているのですから、天気予報の場合と異なります。天気予報はデータを網羅して、高速処理すれば予測の精度は上がると思います。だが、経済予測の場合は、仮にすべての要因を計算に入れることができたとしても、精度は決定的に上がることはないと思います。現実の社会が発生させる経済は、非常に複雑で巨大すぎるのです。さらに、天気予報になく、経済予測にある要件は「人間の関与」です。人間が下す決断というのは、本質的に気まぐれで予測不可能なものです。人間の気まぐれな行動を考慮しなくてはいけないということは、最初から無理な相談なのです。その無理な相談を経済アナリストはある条件下で予測していくのですから、当たらないのが当たり前なのです。さらに、土屋賢二氏は次のように述べています。
「経済学者は予測を求められたらこう答えたいのだろう。天変地異も政変も国際紛争も起こらず、有力な投資家やファンドが予想通りの行動をし、石油価格が安定し、冷夏にならず、わたしが計算間違いをしておらず、かつ、この予想が外れなければ、六割の確率で円高に推移するかもしれない」と。
いくら湯元健治氏が内閣府審議官(政策担当)に就任するほど有能でも、巨大なヌエ相手と、人間の気まぐれな行動を相手にしているのですから、当てるのは無理な相談です。
徘徊する巨大なマネー
加えて経済予測を難しくしているは、運用先を求めて徘徊する巨大なマネー集団です。錬金術のように金が金を生むことを期待し、現代の錬金術師たちが国境を越え、合理性のみの基準で動き回っていくという実態です。
グリーンスパン前議長が解説したように、「欧米市場でサプライム関連損失を抱えた投資家が日本株を売却した」というマネタリー経済の合理性で「日本株式は暴落した」のです。つまり、我々が所有している日本株式価格が、該当企業の業績に関係なく動かされていくのであって、そこには国家が介入する余地もなく、情報としての時差なき「一つのマネー世界」が動いていくのですから、日本経済という視点から様々な要件を材料として分析しても、株価予測は当たらない確率が高いのです。国境なく存在する「マネー市場」が現実の株価をつくっていくのです。
必要なことは集中と継続
社会は巨大なヌエであり、そこに巨額のマネーが徘徊し、ユダヤ陰謀説、フリーメイソン策謀説、ロックフェラー支配説などの諸説紛々が入り交じって議論百出、それらで問題をさらに難くしています。何が真実なのか明確でないのです。
だがしかし、我々は生きる一人の人間として、経営する一つの企業として、どのような問題が発生しても、経済予測が当たらなくても、陰謀・策謀・支配説が流布されても、毎日の生活と経営を進めていかねばならないのです。社会が、経済が、マネーが起こす荒々しい大変化に惑わされず、目的達成という結果に結びつけることが必要です。
そのためには何が必要か。その答えはCoCo壱番屋創業者の宗次徳二氏が教えてくれます。定めた目的達成の目処が立つまで、ある期間「徹底的に集中し継続する」という努力が絶対要件です。その過程を経ない人生と経営は成功に結びつかないと思います。以上。
2007年09月21日
2007年9月20日 自然の理
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年9月20日 自然の理
サブプライムローン問題
今回のサブプライムローン問題、時間の経過と共に、問題点の解説がマスコミで報道されてきました。まだ片付いていない途中ですが、少し概要を整理してみたいと思います。
米国の住宅ローンには、優良顧客向け融資(プライムローン)と、低所得者やクレジットで支払いが滞ったことのある人達への融資(サブプライムローン)の二種類があり、この融資はいずれも「住宅価格が値上がり・転売する」することを前提にしていました。
しかし、このところ住宅価格が下落し始め、借入れ当初は低金利ですが、三年後には二倍の金利になる等のサブプライムローンの返済が滞り始めました。
サブプライムローン残高は1.3兆ドル(150兆円)で、住宅ローン市場全体では一部にすぎないのですが、これを証券化していることから問題が複雑化しました。
まず、第一にサブプライムローンを原資産として、証券化商品ABS(資産担保証券)が組成され、第二にこれを買い込んだグループがCDO(債務担保証券)という証券化商品を組成し販売し、第三にこれらをヘッジファンドが買い込み、レバレッジの効いた高利回り運用と称し世界中の投資家からお金を集めたのです。
ところが、原点のサブプライムローンが問題化し、第一から第三までのプロセスで損失が発生したのですが、このプロセスのどこでどのくらい損失が発生しているのかが明確でなく、投資家たちが疑心暗鬼になり、損失補てんのために株売りを一斉に行い、日本でも株式が暴落し、欧州では銀行から預金引き出しが相次ぐなど、金融市場が混乱しています。
今から考えてみれば、住宅価格は上下することがあるはずなのに、上昇のみを前提として証券が組成されていたということは、世の中の「自然の理」に反した証券化がシステム商品として世界中に広がったことが、問題の本質と思います。
FRB前議長グリーンスパン氏も、退任直前(2006年1月)まで事の重大さに気づいていなかった、という発言もなされ、今回のサブプライムローンはサプライズです。
安倍首相辞任
9月12日、安倍晋三首相は首相官邸で記者会見し、辞任の意向を表明しました。本人は政策実行力の不足を理由に挙げましたが、与謝野官房長官は健康問題が一因との見方を示しました。一方、日経新聞の田勢康弘コラムニストは、祖父の岸信介元首相が「あれが総理総裁の器でないことだけは私にも分かりますよ」と述べたと記事で明らかにし、首相としての資質問題を指摘する厳しい見解を示していますが、安倍首相の記憶力と読書量は抜群であり、能力的な問題よりは体力的な要因が今回の辞任につながったと考えます。
安倍首相は慶応大病院に入院したままで、病名は機能性胃腸障害ですが、この病名が示すとおり、安倍首相は胃腸が頑健ではなかったようです。かねてから食の細さなどを根拠に、健康不安説がくすぶっていたようで、体が弱い「蒲柳の質」だったと指摘されています。蒲柳とはカワヤナギの異称で、秋が来ると早くに葉が散るところから体質の弱い人のことを表現します。
安倍首相の好きな食べ物は「焼き肉、ラーメン、スイカ」、嫌いな食べ物は「生カキ」です。これは昨年就任時の新聞報道で明らかにされましたが、その際、オャと疑問を持ったことを思い出します。生カキが嫌いということは、間違いなく生カキを食べてお腹を壊したことがあるからです。
何かの機会に生カキを食べ、それが当たったのでしょうが、生カキは新鮮ですと絶対にお腹は壊しません。それは、世界各地のカキ養殖場で数多く食している経験からわかります。しかし、胃腸が弱い人が生カキをよく噛まずに食べると壊す場合が多々あります。
安倍首相の場合、カキに問題があったのか、よく噛まずに食べたのかは分かりませんが、生カキが嫌いということから推測して、この人は胃腸が弱いという印象を持ちました。首相という激務、それをこなすには体の強さが一番大事で必要です。
人間にはその職に「向き不向き」があります。適性です。いくら能力に優れていたとしても、その能力を発揮すべき体力、それも首相という国家最大の権力者としての毎日の行動を支える体力に問題があるとしたら、それは時間軸の経過と共に表象化してくるはずで、それが今回の事例に当てはまると思います。
その根拠として、先日、11年前に安倍さんを診察したことがある日本で著名な医師に出会い、直接お聞きしましたが「体が弱いので激務は無理」との診断を当時下していたというのです。これは、安倍首相自身が自らの体を知っていたという事実です。
結局、安倍首相は自分の体力と、首相の激務との較差に負けたのですが、その較差を知りつつ、首相になったということ、そこが、人間としての「自然の理」に反していたと思います。
国際柔道連盟
国際柔道連盟はリオデジャネイロで開かれた総会で、理事の改選選挙を行った結果、
山下泰裕氏がアルジェリアの人物に61対123の大差で敗れ、執行部から日本人がいないという結果になりました。しかし、新しく会長に就任したマリアス・ビゼール氏(オーストリア)が、議決権を持たない指名理事8人を新たに追加指名し、その中に上村春樹氏が選ばれ、日本人不在という事態は回避されました。
この追加措置は、新会長の「柔道の本家であり、主要なスポンサーや放映権料にかかわる日本を重視」する意向からですが、当初の山下氏排除は、前任の朴容晟会長と新会長が率いる欧州勢との対立からなされたものでした。
山下氏はご存知のように「世界のヤマシタ」ですから、その柔道界での業績は誰しも認めるところですが、そのような人物でも国際柔道連盟の権力争いに巻き込まれ、結果的に再任されなかったのです。どのような権力争いがあったのかは詳しくは分かりませんが、新会長が矢継ぎ早に打ち出した改革案を見ると従来の柔道イメージと大きく変わっています。まず、世界選手権の毎年開催と、2009年から世界を転戦する「8カ国グランプリ」と世界ランキング制度の創設で、これらから考えるとテニスやゴルフなどのメジャースポーツを目指していると思いますし、そのためにマーケティングやテレビ放映に関する専門家を招き、専門部署を新設します。つまり、完全にプロスポーツ化するのです。
日本人の気持ちの中には、加納治五郎が創設した講道館柔道「精力善用、自他共栄」の理想と技術を、広く世界に展開させてきた経緯が記憶として残っています。また、姿三四郎の小説に見られるような「柔能く剛を制す」という理念に対するあこがれが底流にあり、そこから柔道を見つめようとする気持ちが残っています。この考え方から日本の柔道試合ルールはアマチュア規定が残っているのですが、これに対して、新会長の方向性は「商業化の拡大」です。日本人には異論が残る改革ですが、よく考えてみれば、ここまで柔道が国際化したという証明であり、世界の多くの国で柔道が広まったことを示しているので、加納治五郎の目指した国際化は成功したのです。さらに、国際柔道連盟総会で選ばれるという民主的な選挙の結果ですから、受け入れるしかありません。
日本で発祥した柔道が、世界の柔道になったということを理解し、その方向で日本の柔道を変えていかなければならないということ、それは「自然の理」であると思います。
旅館革命
私が代表しております「経営ゼミナール」で講演いただいた法政大学の増田辰弘客員教授に対して、ゼミ正会員の伊豆下賀茂・名門温泉旅館「伊古奈」の女将から質問がなされ、それに対し増田教授が示唆に富んだ結果を月刊「中小企業と組合」で発表してくれました。
「旅館業は今日の図書館に似ている。図書館の側は本を揃えて貸したいが、利用客は静かに本を読む場所が欲しいのである。閲覧室がなく、本を貸すだけの図書館だと殆ど利用客が見込めないのではないか。いつの間にか図書館へのニーズが大きく変化してきた」と。
続いて、「今の旅館は①高度成長時代の、②社員旅行、忘年会の多い会社中心のライフスタイルで、③普段は貧しい粗食しか食べていない、④あまり人から頭など下げられない、⑤ホテルや海外旅行などの選択肢がない時代のビジネスモデルである」と。
日本の旅館の問題点本質を鋭くついていると思います。つまり、時代の変化という本質面からの改革がなされていない業界であるので、時代本質変化に合わせるという「自然の理」に従うしかないといっているのです。
金融証券界、国家最大の責任を負った激務としての首相職、国際化が成功した柔道界、古い体質を遺したままの温泉旅館業界、すべてに通じるセオリーは「自然の理」です。
以上。
2007年09月07日
2007年9月5日 哲学を持つ
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年9月5日 哲学を持つ
無意識選択
ある科学者の研究によると、人間は一日に3000回超の意思決定選択をしていますが、本人が明確に意識して判断しているのは、わずか4~5回で、それ以外はすべて無意識で判断しているそうです。また、量子論の学説に「多世界解釈」という理論があり、ある選択をする際に、Aを選んだ世界、Bを選んだ世界がそれぞれ存在し、その選択を重ねるたびに、そこから無数の世界に広がっていくといいます。つまり、自分が選ばなかった世界が無数に存在しており、自分が選んで生きていく世界は、その中のたった一つに過ぎないそうです。ですから、無数の世界から、自分にとって最も良い選択をするためには、一つひとつの意思決定選択を大事にすべきであり、それが無意識化で行うものであっても、妥当な選択をできるような体制を脳の中に構築しておくことが必要になります。
白い恋人
インド・ムンバイにバンコック経由で行くことになり、成田空港でチェックイン時に、バンコック乗り継ぎ時間帯のラウンジ利用を訊ねますと、JALのさくらラウンジがあるから利用してくださいという返事でした。
バンコックに着き、さくらラウンジに行きますと、入口にクローズと書いてあり利用できません。仕方ないので、乗り継ぐキャセイ・パシフィックのラウンジに行き利用しました。当然、このような利用方法になるだろうと訊ねたのですが、JALのカウンターでの回答は異なっていました。大したことはない細かいことですが、少し気になりつつ機中で持参したAgoraアゴラ、これはJALカード会員に送られてくる月刊誌ですが、何気なく読み進んで行き、一瞬、ため息が大きく出るページに出会いました。
それは、実力経営者が推奨する本の紹介記事「旅への一冊」で、経営者の業績を紹介し、その業績の背景としての人物像と、経営者が推奨する本と結びつける編集になっており、なかなか面白いので読んでいますが、この8月号は何と「白い恋人」チョコレートの石屋製菓㈱の石水勲元社長が登場し「徳川家康」(山岡荘八著)を取り上げているのです。
周知のとおり石屋製菓㈱は「白い恋人」の賞味期限違反で摘発を受け、その違反を長期間にわたって継続していたことを石水勲元社長は承知していました。つまり、改竄を指示していた事実から、一気に著名「白い恋人」ブランドは壊滅的状態になりました。
しかし、アゴラ記事で石水勲元社長は「座右の銘は努力。目の前の競争や戦いばかりに勢力を傾注していると、こちらにもダメージが生じる。将来の安定を考えて体制をつくりあげた『徳川家康』を読み深めていくと、会社の将来展望や若い世代への権限委譲などについて、実に含蓄のある一冊になっていると思います」と述べています。
誠にご尤もな見解ですが、これと今回の事件をどう説明するかということ、さらに、このような石水勲元社長を結果的に選択してしまったJALのセンス、それが大問題です。
勿論、取材したタイミングは数ヶ月前ですから、当然に今回の事件は発生しておりません。ですから、JAL側は情報がなかったのだから「仕方ない」と思うかもしれません。
だが、ここで指摘したいのは、偶然にせよ、結果的に賞味期限違反という、消費者の信頼を裏切る経営行動をしていた人物を、立派な経営者と判断してしまった、という事実です。このように結果的に妥当な選択をできなかった背景要因が、JALの内部に潜在していると感じ、これがJALの各部門で表象化しているような気がしてなりません。
予測は当たらない
歴史的惨敗に終わった参院選を、総括する報告書が自民党内から出ました。敗因として年金記録漏れ問題などに加え、安倍首相の「国民の側でなく、永田町の政治家の側に立っているイメージが持たれた」政治姿勢を指摘し、今後の課題として「国民の目線に沿った政権運営が求められる」と異例とも言える首相に批判的な内容です。
また、日経新聞「核心」のコラムニスト田勢康弘氏からは「首相自身がまず、敗北はおのれの指導者としての決断、指導力、うつろな言葉にもあるということを自覚しなければならない」と厳しく、今回の改造でも回復は難しいという見解です。
しかし、この参院選の結果を事前に専門家はどう予測していたでしょうか。一週間前の報道機関による事前予測では今回の惨敗を予測していましたが、このタイミングより前の専門家見解、例えば白鴎大学教授の福岡正行氏から直接聞いた(5/10)のは「参院選は基本的に引き分けだ」と言い、選挙後に「国民新党をどう取り込むか」の戦いなるというものでした。結果は大きく異なりました。
専門家の見解の予測誤差は選挙だけではありません。経済についても同様です。日本総合研究所の湯元健治氏は「中国のバブル崩壊が今年は起こらないという前提で考えれば、まず、安定的な経済が続く」「安倍政権は景気回復を更に強め、成長力を高めていく成長路線を打ち出している」(5/23)と話しましたが、その後の米国サブプライムローン問題から発生した、世界的な大変動は予測しておりませんでした。
世界は考え方が異なる
インド・ムンバイの中心街は一人歩きしても心配ありません。南アフリカ・ヨハネスブルグとは全く違います。多くの人が街中を出歩き、人と車の多さに圧倒されますが、その中に豊かさを感じます。勿論、田舎に行けば貧困層がいますし、ムンバイにも世界最大というスラム街がありますが、一般人が歩き生活するところでは、物量多く豊かさが溢れています。また、街中でのファッションは、Tシャツとジーンズにスニーカー、手には携帯電話、カフェでくつろぎ、ミュージックもロック、このムンバイの実態は世界的に共通しているものです。このグローバル化をアメリカ発の「マクドナリゼーション」と言いますが、これはインターネットでも同じであり、プロバイダー上位企業はアメリカ資本が上位を占めていますので、客観的な事実に基づいて情報が伝えられていると思いたいのですが、実は、そこには、無意識、あるいは意識的なマインドコントロールが、グローバル化という名のもとに行われているのが実際です。
このように衣食住で世界画一化が進み、情報操作によって、世界中が同一の考え方になりつつあると考えやすいのですが、インドの実態をみるとそれぞれの考え方は大きく異なっていることを感じます。それもそのはずで、インドは3000年の歴史を持つ国であり、隣国の中国も長い歴史があり、ヨーロッパも中東諸国も同様で、これらの国々はそれぞれ全く異なる価値観を持っていますから、日本人の価値観だけでは理解できないのです。
つまり、行動は同じように見えるのですが、その背景に存在する価値観は国によって大きく異なっているのです。
考えない日本人
世界では常に想像できない出来事が発生する。このことを強く認識すべきと思います。JALもまさか「白い恋人」の賞味期限違反摘発が発生するとは思わなかったでしょう。安倍首相も事前に厳しいとは思いつつも、ここまで惨敗するとは考えず、参院選に臨んだのでしょう。ムンバイについた日、隣のアーンドラ・プラデーシュ州の州都ハイダラーバードで爆弾テロ事件が発生し多くの人が亡くなりました。
世界の人々の価値観が異なるからこそ、世界中で毎日のようにテロ事件や騒動が発生します。その結果、事前に考えた予測とは異なる結果が発生し、そこから新たなる対応をとることが必要になります。つまり、現実に適応する考える力が要求されているのです。
前回のレターでお伝えした「草の根の軍国主義」(佐藤忠男著 平凡社)の日本人は「あいまいな『気分』がその時どきの判断を左右してしまう国民性、そして『途方もないほどの従順さ』が軍国主義を押し広げていった」と指摘されている事実があるのですから、特に、日本人は考える力について再認識が必要と思います。
神戸女学院大学の内田樹教授は、最近の「あっと驚くような学力の新入生」が多く、このままでは「国民総六歳児化の道」に進むと危惧しています。大学生がこのような実態になったのは、日本人が総じて「考えない結果」から生まれたものと思います。
哲学を持つ
行動のためには意思決定選択が大事であり、妥当な選択をできるような体制を脳の中に構築することが必要です。そのためには「哲学を持つべき」と思います。哲学とは何か。これは難しく考えずに「疑う心を持つことだ」と外交評論家の磯村尚徳氏が主張しています。衣食住と情報が世界画一化した中、今、改めて、重視すべき指摘と思います。以上。
2007年08月21日
2007年8月20日 流されない
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年8月20日 流されない
終戦記念日
8月15日の終戦記念日も猛暑でした。昨年の関東地区気温は28度でしたから、今年は一段と暑さが堪えます。
この日になると、いつも「あの戦争はなぜ始めたのか」と思います。圧倒的な軍事物量格差があることを、最初から分かっていたのですから、専門家が日米両国の力関係を分析すれば、終戦記念日の結果は簡単に予測しえたはずですし、当然、それを行っていました。
今年の2月9日(金)衆議院予算委員会で、前防衛庁長官の石破茂さんが猪瀬直樹著『日本人はなぜ戦争をしたか――昭和16年夏の敗戦』という本を取り上げ、以下のように発言したことを3月20日レターでご紹介しました。
「なぜ『昭和20年夏の敗戦』ではなくて『昭和16年夏の敗戦』なのか、ということであります。昭和16年4月1日に、いまのキャピトル東急ホテルのあたり、首相官邸の近くですね、当時の近衛内閣でありますが、総力戦研究所という研究所をつくりました。そこにはありとあらゆる官庁の30代の秀才、あるいは軍人、あるいはマスコミ、学者、36名が集められて、『もし日米戦わばどのような結果になるか、自由に研究せよ』というテーマが与えられた。8月に結論が出た。緒戦は勝つであろう。しかしながら、やがて国力、物量の差、それが明らかになって、最終的にはソビエトの参戦、こういうかたちでこの戦争は必ず負ける。よって日米は決して戦ってはならない。という結論が出て、8月27日に当時の近衛内閣、閣僚の前でその結果が発表されたが、東条陸軍大臣によって拒否されたのであります」
草の根の軍国主義
客観的立場から冷静に分析した結果「日本は負ける」という結論。その通りになったわけで、一人の陸軍大臣の反発でこの結論が「流された」というところ、そこに、また、疑問を持ち続けていたところ、7月末に出版された「草の根の軍国主義」(佐藤忠男著 平凡社)がその疑問を解明してくれました。佐藤氏は1930年生まれ。終戦時は少年兵でした。その当時の日本社会について、映画評論家としての鋭い視点から次のように結論化しています。
「戦争開始当時の日本の雰囲気は、軍部の抑圧で息詰まるものだったというは少し違う。あのころは『鬼畜米英』に打ち勝つという目標に向かって、社会が和気あいあいとすらしていた」と述べ、「戦争を始めることも、終えることも、本気で考えていたのだろうか」と問いかけ、「あいまいな『気分』がその時どきの判断を左右してしまう国民性、そして『途方もないほどの従順さ』が軍国主義を押し広げていった」と指摘し、さらに、「真珠湾攻撃を忠臣蔵の松の廊下刃傷事件に重ね『意地悪な相手に一太刀浴びせたという気分』が明らかに国民の間にあった」という忠臣蔵史観でのまとめは秀逸で、成る程と思いました。
クリスピー・クリーム・ドーナツ
連日続いた猛暑が一転した8月18日、新宿に行きました。新宿サザンテラス口を出て、子供連れの親子や若い男女が通りを行き交うなかを歩いていきますと、大勢の人が立ち並んでいるところに遭遇しました。この店だけに人が群がっているのです。
昨年12月にオープンした、アメリカの「クリスピー・クリーム・ドーナツ」日本一号店です。1937年にアメリカ・ノースカロライナ州の小さなドーナツ店から始まって、今や世界11カ国、約400店に成長しています。
この一号店、人の群がりは店頭だけではありません。1時間20分待ちと書かれた表示板の向こうの角を曲がった陸橋の上、そこでも並んでいるのです。離れていますからちょっと見には分かりませんが、合わせて150人くらいでしょう。ジッと立ち待っているのです。
少し涼しくなったといっても30度です。木陰もない外ですから大変です。しかし、この気象条件下で、ただドーナツを買うために待つのですから、それにはそれなりの理由があるだろうと思います。例えば、飛びぬけて美味いとか・・・。
この店の評判は一月ごろから聞いていました。しかし、今回まで新宿店までいけず、ようやく味を試すことが出来ると思ったわけですが、1時間20分炎天下で待つのは大変ですからあきらめました。だが、このドーナツの味見は5月のニューヨークで経験済みです。
ニューヨークで泊まった42丁目のホテルから、朝食代わりに食べてみようと、朝9時、33丁目のペンシルバニア・ステーションまで歩き、ここはマデイソンスクウェアガーデンの地下ですが、ここに「クリスピー・クリーム・ドーナツ」店があります。
この店で、ドーナツ3個とコーヒー一杯で4.02ドル、通勤客が発車時間を待つフロアの椅子に座って食べてみました。さて、期待の味はどうか・・・。
結果は、不味くはありませんが、甘さが強く残る感覚で、特別の味とは思えません。また、店の前は忙しく通り過ぎる人ばかりで、買っている人は見かけません。新宿の店とは大違いです。ニューヨーク在住の複数人にお聞きしますと、この店は、どこにでもあるので珍しくなく、それほど美味いとは思わない、という見解です。新宿の群がりはどうしてでしょうか。
オーシャンズ13
フランク・シナトラと、彼の芸人仲間の共演で生まれた映画「オーシャンと11人の仲間」(60年)の遊び心を、引き継いで生まれたリメイク作に続編がでました。「オーシャンズ13」です。早速、観にいきました。
今回は、ラスベガスに新築オープンするカジノ付きホテル「バンク」を世界最高と認定させ、受賞の証しのダイヤを増やしたいホテル王を破滅させるストーリーです。カジノのセキュリティを破るのに停電、地震、女誑し、様々な手を使う芸の細かさの一つ一つを、これが映画だと言わんばかりに映像で見せてくれるので、終わってスカッと爽快感が残りますが、この中に登場する背景シーンにビックリしました。それは、いかに日本ブームが広がっているかという事実確認です。
カジノオープンセレモニーとして、大相撲の取り組みを土俵上で展開させ、和太鼓も登場し、日本酒「久保田」での乾杯、それも日本語でカンパイと一斉に言わせる芸の細かさ、さらに、資金調達の助っ人を迎え椅子に案内し、何か飲みますかと聞くと「煎茶か玄米茶」と日本語で言わせるところ、この他にもまだまだ日本を取り入れているシーンが多くあります。
ハリウッドのトップスターが演じる華と、観客サービスを徹底させた最新人気映画が、ここまで日本ブームを意識した内容で展開していること、これは確かにアメリカや世界中で日本ブームがすごいことを物語っていると再認識できました。
さらに、日本では有り触れて、珍しくもない普通の居酒屋やラーメン店頭に、人が群がっている事実をニューヨークで確認していますが、これらの実態は、世界的な日本ブーム化現象が背景に存在しているからだと思います。
一方、アメリカでは誰も並んでいない「クリスピー・クリーム・ドーナツ」が日本では長蛇の列になるという事実、これをどのように理解するか、そのところに新しい疑問が浮かんできました。日本でそれほどアメリカブームが発生しているのかという疑問です。
朝青龍
大相撲横綱の朝青龍が、本場所二場所出場禁止処分を受け、この状況は格好のマスコミ報道騒動になっています。出場禁止処分を受けた理由は明白です。夏の巡業を体調問題で断った、つまり、大相撲会社の一大イベントに参加できないほどの体なのに、モンゴルのサッカー場で溌剌とした笑顔で走り回り興じている姿がテレビで放映されたから、さすがの相撲協会も怒り、今回の処分になったのです。横綱としての品格を欠く態度が、これまで何回も非難されていたことも背景にあると思います。
マスコミ報道騒ぎが始まった当初、何人かに、この話題を出してみました。すると答えは決まって「朝青龍の病気は本当か。仮病ではないのか」というものでした。最初はマスコミの関心が病気の真否に重点が置かれていたので、その報道を素直に受けた発言でした。
実は、この反応にギョッとしました。あまりに報道どおりの発言だったからです。
朝青龍がどうしてそのような事態に追い込まれたのか、という本質的な心理要因について関心を持つのではなく、マスコミ報道が関心持って伝えていること、それに合わせて自らもそこに関心を寄せるという実態、この姿にギョッとしたのです。
流されない
「草の根の軍国主義」佐藤忠男氏の「あいまいな『気分』がその時どきの判断を左右してしまう国民性、そして『途方もないほどの従順さ』が軍国主義を押し広げていった」という「流される」日本人が持つ心理的特性への問題指摘。終戦記念日に再認識いたしました。以上。
2007年08月07日
2007年8月5日 結果が招く未来の予測
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年8月5日 結果が招く未来の予測
参院選
7月29日の参院選は、自民党と公明党の与党が惨敗しました。完敗の安倍首相は、まさかここまで負けるとは、と思う気持ちだけでしょう。
だが、この結果は、一週間前の新聞で報道されていました。7月22日(日)の各紙は一斉に事前予測を掲載し、日本経済新聞も全国21,563人からの回答と、全国の日経新聞支社・支局の取材も加えて情勢を探ったものを報道しましたが、それと選挙結果を⇒でみますと、今回の事前予測はほぼあたっています。
1.自民党は選挙区と比例代表の合計で40議席割る公算もある。
⇒自民党は37議席。
2.公明党は選挙区で優位なのは2選挙区のみ。比例代表は前回獲得の8議席を視野。
⇒公明党は9議席。
3.民主党は一人区の6割近くで優勢な戦い。選挙区、比例代表の合計では60議席の大台をうかがう。
⇒民主党は60議席。
4.共産党は前回並みの4議席と予想される。
⇒共産党は3議席。
5.社民党は比例代表の2議席の攻防になっている。
⇒社民党は2議席。
6.国民新党は島根選挙区と比例代表でそれぞれ1議席の可能性がある。
⇒国民新党は2議席。
7.新党日本は比例代表での1議席の確保が微妙だ。
⇒新党日本は1議席。
前回の7月20日レターで「今回の参院選は結果が分かりません。今のところ与党不利の情勢ですが、選挙は終わって見なければ分からない、というのが過去の実績から証明されています」とお伝えしましが、これは完全に誤りました。
事前に専門家からいろいろ聞き、過去の選挙結果も検討してみると、一週間前のマスコミによる事前予測が片一方に傾く、つまり、一つの党が大勝するということが予測される場合、国民はバランスをとる傾向があるので、実際に選挙が終わってみなければ分からない、という意味でお伝えしたのですが、今回は全く事前予測がそのまま当たりました。この過去事例を変えた国民意思、それはどのような意味を持つのでしょうか。
ヨハネスブルグ
参院選の当日は、南アフリカ・ヨハネスブルグにおりました。事前投票してまいりまして、29日の選挙結果はホテルの部屋で、インターネットで刻々と開票が進むのを見ていましたが、このヨハネスブルグに来て、一つだけ困ったことがありました。それはホテルを出て、一人で街歩きができないことです。
勿論、道路は整備され、立派な家が並び、街路樹も豊かですから、散歩する環境は整っているのですが、一人での外出は困難なのです。
その意味は、出発して機内で、初めてヨハネスブルグの旅行ガイドブックを広げて、分かりました。ガイドブックには「世界で一番危ない都市」と明確に書かれているのです。犯罪発生率が高く、一人歩きは絶対に危険だ、というガイドブックを読んでいくうちに、行くのを止めようと思いましたが、既に飛行機の中ですから戻れません。
改めて、出かける寸前に印刷してきた外務省海外安全ホームページを広げて見ますと、以下のように注意が書かれていました。
「ヨハネスブルグのダウンタウン地区では、殺人、強盗、強姦、恐喝、暴行、ひったくり、車上狙い、麻薬売買等の犯罪が時間、場所を問わず発生しています。
特に、鉄道のヨハネスブルグ中央駅付近やバスターミナルのパークステーション等において、公共交通機関(長距離バス等)を利用する邦人旅行者が、バスターミナル付近を歩行中に路上強盗(突然、背後から首を絞めて複数で襲い所持品を奪う等)に襲われる事件が頻発しており、邦人旅行者にも被害が出ていますので、可能な限り公共交通手段の利用は避け、同地区には立ち入らないようお勧めします」(2007/02/15)
これは大変な都市で、今まで訪れた中では最も危ないところです。
実際のヨハネスブルグ
一人歩きが出来ないので、ガイドと専用自動車で動くことになります。ガイドは日本女性で、こちらに19年間住んでいて、危険な目に何回も遭遇している事例を話してくれました。自宅にピストル強盗が入って縛られて盗まれたことがあった。風呂から出ると、廊下に男がピストル持って立っていて、お金を渡せば危害を加えない、手を前に出せといい、手を縛られベッドルームに行くと、お手伝いも縛られていた。後で考えるとお手伝いが手引きしたように思っていると言います。
また、車で交差点に停まったら、左側の窓ガラスを割られ、左座席においてあったハンドバックを盗られた。バックの中の現金、パスポート、カード、運転免許証を失った。「スマッシュ・アンド・グラブ」という強奪で、これは窓ガラスをしっかり締めておくと返って割れやすく、少しあけておくと割れにくいが、この時はしっかり締めていたのでやられたと言います。このほかにケーキ屋で二人組みのスリに財布を盗られた事もあった。怖い話を続けて聞いていると、運転手のドイツ系の白人男性も話し出しました。
両親が外出先から戻ってくると、家の前に五人ほど黒人がいて、鍵を開けろ、おとなしくしないと殺すぞ、と脅迫され、家の中に入ると、めぼしいものを所有していたトヨタ車に積みこみ、車ともども盗まれた。このショックでしばらく両親は精神科に通ってリハビリをすることになった。車の後部座席で自分の膝頭が震えだし、ガイドブックと外務省海外安全ホームページは、正確な事実を伝えていることが分かりました。
アパルトヘイトの弊害
ヨハネスブルグの人々が住むところは、他の国の大都市に見られるような高層アパートメントは少なく、土地が広いので一戸建ての住宅に住んでいますが、それら個々の住宅は、ある広さに区分けされたエリアの中に集められ、その全体の周りを高い塀で囲い、そこの出入り口にはガードマンがいて、一人一人チェックするという、一つのタウンハウスとなっています。
日本の別荘地でも、分譲販売した会社が入り口に門を配置し、出入りの人たちをチェックしているところがありますが、それと同じで、ヨハネスブルグでは集団の個人住宅をガードするシステムとなっています。理由は、勿論、安全対策です。
その一つの住宅の白人女子大学生の家を訪れました。家の前に行きますと、フォーセールと書かれています。売りに出ているのです。両親は既にニュージランドに移住し、学校の関係で娘だけが残っているのです。中は転居前で雑然としていますが、友人が遊びに来ていましたので、お茶を飲みながら雑談しているうちに、徐々に南アフリカの実態について辛らつな意見が出てきました。
それは嘗ての白人優位というシステムが崩れ、政府関係の重要な職には黒人が就いている上に、企業が10人採用する場合は黒人を8人、カラードを2人と法律で決めたため、白人は仕事がなくなっていく傾向で、この国の未来は白人にとって暗い。だから、チャンスがあるならば、外国に移住したいと思っている。つまり、この家の女子大学生が羨ましいと言うのです。後でガイド聞きますと、あれは本当の気持ちだと言います。
こちらは2010年にFIFAワールドサッカーが開催されるのですから、未来に明るい都市づくりの話が聞けると思っていましたが、暗い話に終始しました。
未来は予測どおりになる
南アフリカは1991年、アパルトヘイト関連法が廃止され人種差別の法律が全廃、黒人の地位が向上し、白人が優位性を失い、訪問した女子大学生のような国外移住が増えました。これはアパルトヘイト廃止が起こした予測どおりのことです。
では、日本の未来はどうでしょうか。前回の衆院選で自民党は圧倒的大勝利。今回の参院選では記録的な敗北。衆議院と参議院は完全なねじれ現象。これは、実際に投票した日本国民がつくった結果です。衆院選は郵政民営化という政策で判断、参院選は政府がけしからんという民意で判断。この事態をつくりあげた我々日本国民は、日本の未来の姿をどのように予測しているのでしょうか。その予測どおりになると思います。以上。
2007年07月20日
2007年7月20日 将来の納得
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年7月20日 将来の納得
参議院選挙
今回の参院選は結果が分かりません。今のところ与党不利の情勢ですが、選挙は終わって見なければ分からない、というのが過去の実績から証明されています。
今回の参院選争点は年金問題、経済政策、そのたいろいろあり、マスコミで与野党双方が激しい応酬を繰り広げています。
この中で年金問題の本質を考えてみますと、政治家が国会で決定したことを実行する役目の官僚、その官僚が全く単純な記録計算である年金データ管理を行っていなかった、というところにあります。一般企業では考えられないことです。その上に、莫大な年金運用資金を、大規模保養施設「グリーンピア」をはじめとする無駄なところに投資し使ってきたのです。
ここから考えると、日本の官僚は優秀だという評価は下せません。責任能力を持ち得ない人材が、大事な国家運営に携わっているという事実と、この官僚を使う政治家を選んだ我々に問題があると認識したいと思います。政治家の選び方が不味かったのです。
福沢諭吉は衆論、つまり、多数の議論が大事といい、衆論を決める基は智徳の分量にあり、智には私智と公智があり、私智とは物の理を究めてこれに応じる働きをいい、公智はこれを時と所を選んでさらに大きな目的に用いることで、公智が最も大事だと主張しました。
言い換えますと、私智とは囲碁将棋が上手というような場合、公智とは「社会に大きく貢献する知恵」ということになります。政治家の選び方が不味かったということは、一人一人の公智に問題があったと認識したいと思います。
一人一人がプロになる
1.ミネラルウォーター
アメリカのソルトレークシティ市は、アメリカ国内で最も良質な水道水を提供しているので、ボトル入りのミネラルウォーターを目の敵にし、ペットボトルは地球温暖化の問題にもつながると、市長がボトル入り飲料水の不買を市職員指示しました。また、カリフォルア州はペットボトルの製造に8セント掛かり、そのリサイクルには18セント掛かるので、ペットボトルの使用規制に入るということから、先日、ニューヨークで知人とミネラルウォーターについて話し合ってみました。
アメリカのミネラルウォーターは硬水だ、ということを知人は知っています。日本は軟水だということも知っているようです。では、硬水、軟水の区別はどのようにするのか、それはカルシウムの含有量である、では、その含有量はどのくらいかという辺りから、知人の理解は曖昧になってきました。
硬水・軟水の区別は、水中のカルシウムやマグネシウムの量で表され、WHO(世界保健機関)の定義で、120mg/ℓ以上の水を硬水とします。また、マグネシウムは下剤の成分ともなる硫酸マグネシウムと同様ですから、硬度の高いミネラルウォーターを飲み続けると、旅行者は下痢症を起しやすいということ、続いて、どうしてアメリカは硬水が多く、日本は軟水なのか、というあたりになってきて、とうとう知人はお手上げです。これは国土の形状が影響しているのです。
人間の体は60~70%が水。水を知らないということは、自分の体を知らないということに通じます。特に、旅行が多い方は最低の水に関する理解を持つことが大事と思います。
2.勤務時間
長いこと一つの企業に勤務して、先日退社した人と会いました。今まで毎日決められた時間に出社し、定まった時刻に退社していた環境から、その制約がなくなった人です。
今まで、この人には口癖がありました。平日の昼間、何かの用事でデパート、スポーツ施設などに行くと「暇人がいるものだ」と発言するのです。自分は忙しい身だ。それに反して、このような場所に昼間大勢いる。羨ましい、というよりは、自分の忙しさを誇示する意味の発言でした。ところが、退社してみたら「暇人がいるものだ」と、批判的発言をした人たちと同じ立場になり、ちょっと困惑気味の感情になったところに出会ったのです。
そこで、少し解説をしました。
「今までは、自分が決めた時間ではない勤務時間、それに疑問を持たず、そこに合わせる生活をしていた。だが、今は、それがなくなった。つまり、自分で自分の生活勤務時間をつくるときが訪れたのだ。自由という意味は、自分で自分のルールをつくることだ。自分に適切な時間帯を構築することだ」
「それは分かっているが、どうしたらそれを上手く出来るのか」
「それへの答えは、自分を知ることしかない」
「自分を知る?知っているつもりだが」
「なら、自分の最も相応しい生活する内容構築が出来ているのですね?」
「それが出来ていないから、戸惑っているのだ」
「ということは、自分を知らないことですよ」
つまり、この人は漠然と自分を知っているだけなのです。本当の自分とはどのような存在なのか。それを突き詰めて考えずに来たこと、その結果が今の戸惑いになっているのです。
もう一歩自分の中味を研究し、自分を冷静につかむこと。それが自分にとっての適切な生活時間設定のキーであるとアドバイスしました。自分に対してプロになることが大事です。
3.オシム監督
サッカー日本代表監督イビチャ・オシムが「日本人よ!」を出版しました。この中で日本代表が負けた際に評論家がよく口にする「経験不足」、これに対し「人生において、経験は20年間あれば十分だと思う。サッカーではもっと短くなければならない。サッカーにおける経験は一年半あれば十分だというのが私の考えだ」と述べています。考えさせられる内容です。
また、文芸春秋八月号で「日本人はみなさん、戦術やフォーメーションにものすごく詳しく、4-4-2とか3-5-2といった言葉をよく好んで使います。しかし、どうやったらこのフォーメーションができ、なぜこのフォーメーションにすべきなのか。そのフレーズは知っていても、その裏付けや必然についてしっかり理解していないように思います」と述べています。これにも考えさせられます。
さらに、「日本人は、あまり責任や原因を明確にしないまま次に進もうとする傾向があるように思います。私は日本人の選手やコーチたちがよく使う言葉で嫌いなものが二つあります。『しょうがない』と『切り換え、切り換え』です。それで全部を誤魔化すことができてしまう」これにもなるほどと思います。
世界の一流サッカーに伍するためには、「自らを客観的に見通すための視点」を再構築すべきであると、オシム監督は語っているのです。言葉を換えて言えば「一人一人がプロになる」ことが必要で大事なことだと言っているのです。
プリウス「ゼロ排ガス車」として認定
前号レターで、NYのタクシーがハイブリット車に切り換わることをお伝えしました。
今年のアメリカでトヨタのプリウス販売台数は、25万台から30万台が予測され、日本の昨年実績は7万2千台ですから、アメリカで大きく伸び、その結果、搭載電池生産能力を5割増させると、トヨタが発表するほどです。(日経2007.7.15)
このようになった要因はいくつもありますが、一つに絞るとすれば、カリフォルニア州の大気資源委員会、ここは電気自動車しか認めていなかったのですが、ここに電気モーターとガソリンエンジンを組み合わせたプリウスを、10年前に認めさせたこと、つまり、プリウスが電気自動車に代わる「ゼロ排ガス車」であると認定を受けたのです。
認定を受けるために様々な戦術を駆使したと思いますが、基本に「地球環境問題に対応する」という時代方向性から「将来の納得戦略」を持ちえたから、鋭くて、うるさい論客が揃っている大気資源委員会を説得できたと思います。
今ではトヨタの売上高24兆円、ロシアの国家予算に匹敵する規模になりました。
今の納得をとるか、将来の納得をとるか
目前に現れる出来事に対し、今の納得をとるか、将来の納得をとるか。参院選にどのような公智で臨むのか。体の基礎部分としての水に関心を向けるのか。自分に最適の生活時間帯設定をどう組み立てるか。オシム監督の指摘内容をどう考え対応するのか。トヨタの将来戦略性から何を学び取り入れるのか。いずれも将来の納得視点から決めたいと思います。
以上。
2007年07月05日
2007年7月5日 経営感覚の前に時代感覚
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年7月5日 経営感覚の前に時代感覚
トヨタと日産の格差
3月期決算の東証一部上場企業の株主総会が終わりました。特に、今回目立ったのはトヨタと日産の二大自動車企業の格差です。トヨタは役員報酬・賞与枠の40%増の株主総会決議を行ったのに対し、日産は役員賞与ゼロという結果に陥りました。明らかに両社の業績に格差が生じたことを示しています。
ニューヨーク(NY)の街中
NYは「人種のるつぼ」と呼ばれてきました。この表現を最初に使ったのは、イギリスのユダヤ人作家イスラエル・ザングウィルが、1908年にNYのユダヤ人移民の生活を描いたドラマの題名「人種のるつぼ」(メルティング・ポット)で、そこで「アメリカは神のるつぼ、巨大な溶鉱炉である。そこではヨーロッパのすべての人種が溶け合い、再形成しあっている」と述べたことからでした。しかし、今では、この「人種のるつぼ」という概念ではなく、もっと文化的な多様性をもった「サラダボウル」であるべきだ、というのが現在の支配的な世論となっています。
確かにそうで、共同体としての地区全体が住民の地理的、文化的ルーツを示すところが目立っています。アイルランド人地区、リトルイタリア、チャイナタウン、ロワー・イーストサイド(ユダヤ人)、アフリカに韓国、さらにプェルトリコ人は飛び地を占拠しているように、一つのNYというサラダボウルに入って、それにドレッシングを入れかき回しても、サラダは元の原型を残しているという姿なのです。
つまり、溶け合ってはいないが、異民族の相互関係に距離を持ちつつ、同じNYというエリアで生活している。これがアメリカ・NYで生活する基本なのです。
NYのひやりとした関係
6月はこのNY「サラダボウル」に参りました。街中を歩き、信号に立ち止まり、企業訪問し、家庭に伺い、レストランに座って異種の顔を見回しますと、お互いが一つのNYルールで暮らしてはいるものの、そこに何か「ひやりとした人間感覚」が存在することを感じます。それは情感とも、しっとり感ともいえるものが欠如しているとも言えるのですが、お互いが孤独であるという前提こそが、異種の人間共同生活ルールであるのです。さらに、孤独だから他人の邪魔にならず、だからこそどんな人間ともいっしょに暮らせるのだといった雰囲気も漂っていて、それを黙認しあった者達のみで街が構成されていることが「ひやりとした人間感覚集合体」にさせている要因であると感じます。
勿論、東京という大都市にも大都会共通の孤独はあります。しかし、東京の孤独は、集まっている人々は日本人として民族は同じで、NYとは全く異なる条件下での孤独です。つまり、言語体系が同じであるから「お互い話せば分かる」という意味での暖かさが、まだ残っていますが、NYではこの分かり合える暖かさの温度が違い、どこか距離感のあるひやりとした人間感覚が、NYの街に漂っているのです。
へそだしルックと大統領選
しかし、ファッションには敏感です。ここ数年、世界中で女性のへそだしルックが全盛でした。この間のミラノ・パリ・モスクワでも目に付きました。ところが、今回のNYではお腹を殆どの女性が隠しているのです。明らかにファッションの流れが変わったのです。多分、来年は世界中でへそだしルックは消えると思います。人間関係のひやり感は存在しても、ファッションには敏感なのだと改めて感心します。この速さがNYの魅力であり怖さです。いつ何がどのように変化するのか?。加えて、その変化がNYから始まるのです。ちょっとウォッチングを怠ると一瞬にして変わってしまっている、という怖さがあります。
この変化の速さは、来年11月投票の大統領選にも言えるような気がします。今は、民主・共和両党合わせて20人近い候補が出馬する大混戦となって、両党候補者による討論会が始まっていて、現在の状況では民主党がヒラリー・クリントン、ジョン・エドワーズ、バラク・オバマの三人、共和党はジョン・マケイン、ルドルフ・ジュリアーニ、ミット・ロムニーの三人が強いと言われていますが、これから何が起こるかわからないと思います。ちょっと先の予測はつきませんので、ウォッチングを怠らないことです。
NYのタクシー
次に、NYのタクシーですが、これは年々綺麗になって、運転手のレベルも上っているような気がします。その上、今や景気絶好調のNYですから、タクシー営業権利金も数千万円するといわれているくらいに上昇しています。
そのタクシー業界に新しい流れが始まりました。ブルームバーグNY市長が2012年までにタクシーをすべてハイブリッド車に切り替える方針を打ち出しました。地球環境化対策で、温暖化ガスの排出量を三割削減するとの計画を発表しましたが、その一環でタクシーのハイブリット化を進めているのです。まず13,000台のタクシーのうち、来年10月までにハイブリットタクシーを1,000台まで引き上げ、その後は毎年20%ずつ増やして、2012年に全車ハイブリット車にするというものです。
この動きにレンタカーも続きました。レンタカーの大手ハーツは、来年中にトヨタ自動車のハイブリット社プリウスを3,400台購入すると発表しました。ライバル会社のエイビスも、最近1,000台のプリウスを購入しています。
これらの動きは、地球環境化対策や業務用ガソリン経費の大幅削減に通じるだけでなく、もっと何かの時代感覚を象徴しているような気がしてなりません。
NYの時代感覚
さらに、ブルームバーグNY市長は、共和党を離脱し、地球環境化対策で「潮力発電」の試みも始めました。マンハッタン島の東岸を流れるイーストリバーの川底で、タービン六基を使って、世界初の試みを開始しました。この潮力発電とは、ダム建設が必要な水力発電と異なり、自然の潮流を利用するため、生態系に与える影響が少ないといわれ、民間企業によって開始し、既にスーパーと駐車場に電力を供給していて、最終的に8,000所帯への電力供給を計画している意義は大きいと感じ、時代感覚への鋭さを感じます。世界に先駆けて新しい環境対策行政を打ち続けていく。
もしかしたら大統領選の大穴になるかもしれません。
時代感覚
先日、ある人から相談を受けました。企業を役職交代退職し、その後いろいろ模索したが「講演家」になろうと思うがどうだろうか、という内容です。自分の方向は自らが決めることですから、積極的に取り組むようお伝えしましたが、一つだけ大事で外してはならない要件を強調しました。それは時代への感覚です。どのようなテーマで講演をするのか、それは自由なのですが、時代と合わない内容では人は聞いてくれないと思います。講演という一つの方法論、それは形として成り立ちますが、時代感覚がないものは人に受け入れられません。話がうまい下手ではなく、人がなるほどと思える内容構築、時代感覚が大事なのです。
今回、この時代感覚の差がトヨタと日産の業績に現れたと思います。トヨタのハイブリット車が売れていることは日産も熟知しています。ところが、日産からは未だにハイブリット車が発売されていないのです。技術的な問題もあるかもしれませんが、実は損得の関係で日産は発売を見送ってきたのです。トヨタのハイブリット車は一台売るごとに、何万円もの損失が出るといわれています。その損失が発生したとしても、トヨタは地球環境化対策として必要だと、ハイブリット車を発売したのですが、日産は損してまで売ることはしない、という方針を貫きました。この経営に対する意思決定の前提は、トヨタは経営感覚の前に時代への読みを先行させ、日産は時代感覚の読みよりは経営感覚を優先させました。結果は今回の株主総会の決議内容で結果が証明されました。
ブルームバーグ市長
NYのブルームバーグ市長は、ハイブリットタクシー導入、潮力発電の試み、さらに、オーナーである情報企業オフィスビルを、先端ハイテク装備し、レキシントン通に完成させ、日本企業が多く見学に行っています。NYの変化が世界に影響を与えます。以上。
2007年06月20日
2007年6月20日 BRICs・・・ロシア編その二
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年6月20日 BRICs・・・ロシア編その二
ロシアの未来
HISの沢田秀雄会長が次のように語っています。(2007年3月18日 日経新聞)
「約30年前、まだソ連だったころのモスクワを初めて訪れた時に直感しました。『この国は滅びる』。壮麗な建造物の陰で進行する病のにおいがしました」と。
確かに、ソ連(ソビエト社会主義共和国連邦 CCCP)は、世界最初の社会主義国家として、1917年のロシア革命を経て、1922年15共和国によって成立し1991年に崩壊しロシアとなったので、沢田秀雄会長の直感は当たりました。
だが、ソ連後のロシアは、ゴルバチョフ、エリツィン時代の経済混乱を、プーチン政権が進めた資源外交、石油や天然ガスの輸出収入で国内を潤し、資金力を拡大した企業が積極的な拡大戦略をとって、中産階級にも浸透し、個人消費が伸びてきています。
この動きが本物で、数年後にロシアは素晴らしい国へと変化しているのか。それとも再び低迷する国家に戻るのか。モスクワに在住する日本人でも見解は半ば反していました。
いずれにしても、ロシアの動向は、ロシア自身にとっても、世界にとっても、勿論、日本にとっても大きな関心事ですから、注視しなければならない国です。
ロシアという国の成り立ち
司馬遼太郎は、次のようにロシアを若い国と見ています。
「人類の文明史からみて、ロシア人によるロシア国は、きわめて若い歴史をもっていることを重視せねばならないと思います。ロシア人によるロシア国家の決定的な成立は、わずか十五、十六世紀にすぎないのです。若いぶんだけ、国家としてたけだけしい野性をもっているといえます」(ロシアについて 文芸春秋)
ロシアにおける最初の国家は、862年に建国されたキエフ公国からで、その後、13世紀の始めにチンギス汗(君主)・モンゴル軍がやってきて征服され、ロシア平原に居座って、キプチャク汗国(ハンこく 1,243~1502)を立国し、ここに「タタールのくびき」といわれた暴力支配が259年間続き、ロシア農民に対して行った搾りは凄まじく、いくつもの貢税がかけられ、ロシア農民は半死半生にさせられ、反対すると軍事力で徹底的な抹殺を行うというやり方に、ロシア人は従うしかなかったのです。
一方、この時期の西欧は華やかな幕開きでした。花のルネサンスが進行しつつあった時期に、ロシアでは「タタールのくびき」によって文化が閉ざされていたわけです。
ようやくキプチャク汗国からの支配を脱し、モスクワを中心として、ロシア人のロシア国家が成立するのは、ロマノフ朝という専制皇帝を戴く王朝が17世紀に成立するまで待つことになります。日本で言えば江戸初期、大阪落城の直前あたりに相当します。
ロシア人の文化感覚に重要な影響を与えているのは、この「タタールのくびき」で、国民の母型感覚、マザータイプとしての人間文化の奥にあるものに大きく影響させ、これがロシアというものの原風景にある、という事実を見逃してはならないと思います。
外敵を異常に恐れるだけでなく、病的な外国への猜疑心と潜在的な征服欲、軍事力への高い関心、これらはキプチャク汗国の支配と、その被支配を経験した結果と推測します。
問題の数々・・・サービスの悪さ
前回に続いてモスクワの問題点を列挙してみます。
まず、レストランのサービスは最悪です。店に入っても「いらっしゃいませ」とは絶対に言いません。支払いを済まして帰る背中に「ありがとうございました」とも絶対に言いません。日本食レストランのよさの一つとして、日本式サービスの丁寧さが評価されていますが、モスクワの一流すし店には驚きました。店に入っても何も言わず、座ると黙ってウェイターがメニューを持ってくるだけ。すしは美味かったが、支払い明細伝票に「モスクワではチップ制です。従業員の励みになりますから、お気持ちをお願いします」と日本語で書かれているのを見て、急にすしの味が不味くなりました。チップを払う気にならないサービスなのに、チップを強要することはロシアの印象をさらに悪くします。
しかし、このようなサービスではない日本食レストランもあることも付け加えます。一週間滞在中にモスクワ市内の日本食レストランに二度行って、一軒は酷いサービス、もう一軒は素晴らしいサービス。素晴らしいサービスの店はロシア人で満員で、酷いサービスの店は数組だけという現実、やはり、ロシア人も日本的サービスを期待しているのです。
問題の数々・・・離婚の多さ
よくない印象と言えば、離婚の多さもあります。ロシア人は肌着を脱ぎ捨てるように離婚を繰り返すといわれています。離婚率はアメリカを超えているらしく、離婚の主な理由の一つは夫か妻のアルコール依存症です。ロシア人のウォッカ好きは有名です。
離婚理由に兵役逃れ対策もあります。18歳から28歳までの男性は兵役の義務があり、大学生や病人で逃げる方法もありますが、28歳以下で妻と子どもがいれば兵営免除されるので、ロシアの男女は愛が実る前に、まず子どもをつくり、兵役逃れの必要がなくなるとさっと別れるといいます。
モスクワのよい点・・・地下鉄の素晴らしさ
ロシアの悪い面だけ挙げては不公平です。よい点もたくさんあります。まず、経済が順調であることは既にお伝えしたが、問題の車渋滞対策は地下鉄によって救われます。
11路線ある地下鉄は素晴らしい、という一言です。モスクワ滞在中、地下鉄乗車は40回しました。20回分の回数券を二枚購入し、使い切ったことでカウントできます。
電車は二分間隔でプラットホームに入ってきて、停車時間は30秒。それが分かるのは、一番前の車両から見える位置に、電光掲示板で現在時間と、停車秒時間が表示されるからで、それをかっちり守って動いています。
駅のホームやエントランス、天井には見事なレリーフ絵があったり、大理石の壁がつながっているところが多く、コンコースにゴミは無く、改札口の通過は日本のスイカと同じICチップ制で、日本より早く導入されています。
さらに、車内で感心するのは、お年寄りに席を譲るということが自然に行われていることです。お年寄りが乗ってくるとさっと若者が立ち上がります。お年寄りを大事にするということが常識になっていると感じます。
もっと大事なことは、地下鉄車内で見かける若い女性、美人が多いことです。スタイルもよく、眼の保養になるので居眠りする必要が無く、それとアメリカに見られるような巨大なデブは皆無。デブが消えたのは経済状態がよくなってきてからだと言われています。
モスクワのよい点・・・緑の多さと素朴な人柄
市内の樹木の多さもすごく、通りに面して森が連なっています。市電に乗ると、森の中を通過するので、近郊の田舎かと思いますが、ちゃんとしたモスクワ市内であって、軽井沢に街が造られているという感です。
家はたいてい高層アパート。その一人の女性の住居に訪問しました。森の中に点在するアパートメント群一角の二階、中は居間と寝室、台所、洗面所だけの狭いスペースに夫婦二人。この間まで長男が同居していたというが、どうやって三人が起居していたか疑問もつほどの狭さですが、お話はいたって率直。素直に自分をさらけ出し、打ち解けた雰囲気で対応してくれます。他の国より素直な感じを受けました。
地下鉄の中でも、合気道と印字されたTシャツを着た若者から話しかけられ、一緒のかわいいガールフレンドからも英語で質問受けます。急速に英語が通じるようになっているようです。さらに、日本外務省管轄の独立非営利法人「日本センター」で、日本語を学ぶロシア人に同行者が講演しましたが、眼を輝かして聞く態度と、熱心な質問、それへの回答に対して頷き、明るい笑顔が印象的に残りました。
ロシア理解は難しい
一般的に、ロシア人は個人で接すると素朴でおおらかで親切であるが、ひとたび集団化すると横柄な態度になると言われています。モスクワでお会いした人たち、皆さんにこやかで親切でした。しかし、その人たちが集団化して起こす違法運転や、レストランの無愛想な対応、この落差は何から来ているのか。多分、その要因はロシアが持っている過去の歴史を含む様々な要因が絡み合って、論じるのは難しいのですが、しかし、ロシアを結論付けしたい方は、渋滞と高額ホテルを覚悟しモスクワに行くことをお勧めします。以上。
2007年06月07日
2007年6月5日 BRICs・・・ロシア編その一
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年6月5日 BRICs・・・ロシア編その一
ホールインワン経済
日本経済は全体的には順調と言われていますが、その内容は外需、つまり、輸出のおかげで持ちこたえている実態です。また、その輸出の中心はBRICsと呼ばれる、ブラジル、ロシア、インド、中国などの途上国であり、そこへの輸出は昭和40年代の中心だった重厚長大産業が元気よく展開しているのが特徴です。
ですから、鉱工業生産が景気を判断する最重要指標のため、この分野が好調なので景気は大きく崩れないと予測されているのです。
そういう実態ですから、今回の景気は、一般の企業や人々には直接の恩恵が少ないとも言われています。いくら「いざなぎ景気を超えて史上最大」と称されても、実感に乏しいのは事実です。
そのことをあるエコノミストが「今回の景気はホールインワン景気」と言い、その心は「パットしない」・・・。なるほど上手いこと言うなと思います。
ロシアの成長
五月末から六月初めまで、ロシアのモスクワに出張しました。BRICsの一員国です。いろいろな実態に遭遇し、様々な考えを持ちましたので、今回と次回のレターでロシア中心に検討してみたいと思います。
まず、ロシアについて、皆さんお馴染みの日産自動車ゴーン社長が次のように語っている内容をご紹介します。(2007年3月24日 日経新聞)
「成熟市場で減速に直面する自動車メーカーにとって、BRICsは胸を躍らせるような『ニューフロンティア』だ。中でも、欧州最大の市場に浮上すると予測されるロシアに強い関心が集まっている。
一億四千二百万人が住むロシアでは、千人当たりの自動車保有台数は百六十七台にすぎないが、需要は急速に高まっている。
2005年から06年にかけて販売は26%増え百九十万台になった。外国ブランド車の成長は著しく、70%増の九十七万台に上る。
日産は62%の成長を記録した。日産は年五万台の生産能力を持ち、七百五十人を雇用するサンクトペテルブルグの組立工場を09年に稼動するため二億ドルを投資する。
ロシアは製造業にとって多くの点で課題を抱えている。産業基盤や物流、労働者の能力、供給業者、規制環境などの面で、ロシアは中国やインド、ブラジルと比べて勝っている点が少ない。コストや品質面を見ても、短期的な潜在能力はほかの三カ国より低い。
しかし、昨年六月に初めてサンクトペテルブルグとモスクワを訪問した私を感動させたのは、国の未来を造る決意に燃えるロシアの人々自身だった。私が人を判断するうえで常に重きを置く『意欲』を彼らの中に見た。
70年以上にわたりロシアは海外からの投資の歴史が皆無に等しく、多くの人にとって先行きを予測しづらい国のままだ。効率的な生産を実現するためには、日産のやり方をロシアの供給業者に幅広く浸透させる必要がある。
さらに私たちのやり方で従業員を訓練しなければならない。簡単ではないが、同時にチャンスでもある」
これがロシアに対するゴーン社長の判断です。ロシア人が世界で一番親しみを持つ国はフランス、そこのゴーン社長からこのようなメッセージを、ロシア人はどう受け止めているのか分かりませんが、ロシアの成長は日本の経済成長に重要な影響を与えることは事実です。
ロシアの成長率と日本企業の進出
世界の経済は2003年から06年までの四年間、実質成長率は年5.1%と高率でした。常識的な考えでは3%台の成長率でまず順調という見方ですから、5.1%とは大変な成長率です。
その要因は、世界の消費中心国のアメリカが、いろいろ心配されながらもそれなりに消費が拡大し、加えて、中国、インドが10%を超える成長をし、ロシアも2006年実質成長率6%台を達成し、世界経済全体に大きく貢献しているからです。BRICs全体の成長率5%台という実績は、世界経済全体に対して半分近く(2.5%弱)の寄与率になるとIMFは推定しているほどです。
ロシアの成長要因は、プーチン政権が進める資源外交です。石油や天然ガスの輸出収入で国内を潤し、資金力を拡大した企業が積極的な拡大戦略をとって、中産階級にも浸透し、個人消費が旺盛となっています。
その結果、日本の自動車メーカーの輸出は、トヨタ・日産共に2006年は輸出台数を前年比で60%以上増やし、ロシアの国民が自動車を買う余裕が出ているのです。
一方、日本の安倍首相はロシア重視の姿勢を示しています。安倍首相は対ソ連外交に尽力した父、安倍晋太郎氏の影響か「ロシアは大事な隣国」と位置づけているようです。2007年一月はモスクワで初の両国次官級戦略対話、二月にはフラトコフ首相の来日。五月に日本の麻生太郎外相の日本大使館落成記念と合わせたモスクワ訪問もあり、お互いの関係を深めようとして、日本の企業もロシア各地に進出しています。
サンクトペテルブルグには、トヨタ・日産・スズキ・三菱自動車が工場建設・検討を進め、モスクワでは石川島播磨重工業が現地トラック大手と合弁、旭硝子がガラス工場建設、サハリン沖資源開発事業サハリン1に伊藤忠・丸紅などが出資、サハリン2には三井物産・三菱商事などが出資することになっています。
問題はインフラ整備・・・渋滞道路
素晴らしい成長をしているロシアですが、実際に訪れてみると問題は山積しています。
まず、最初に、空港からホテルまでの間で発生した事件をお伝えしたいと思います。
夕方4時にモスクワ・シェレメチェボ国際空港に着き、入国審査はビザがあるため、女性係官はじろりとこちらの顔を確認するだけで、簡単に通過しました。
空港から市内中心地まで35kmで、タクシーで40USドル、約一時間とガイドブックにありますが、タクシーはいろいろ難しいと書いてあるので、知人がベンツ車をチャーターして迎えに来てくれました。
この日の気温は30度を超え、平年5月の平均気温は最高20度ですから、異常気象のようですが、もっと暑いのはベンツの車内です。クーラーが壊れていて、窓は運転手席の窓しか開かないのです。
市内と空港まで列車や電車はなく、手段は車だけなのに高速道路はないとの説明にウーンと唸り、顔面全体に滴る汗を拭うだけです。
実際に走り出して、すぐに渋滞です。四車線もある広い道路に車がびっしりで、全然動きません。この状態はモスクワ市内だったらどこでも同じだと言います。
そこに、突然、超中古車ベンツが妙な音を出しエンストしました。慌てて知人と運転手が道路端にベンツを押し動かし駐車させましたが、まだまだホテルまで遠い地点です。
知人にパスポートだけ持って車から出るよう指示され、広い歩道をバス停へ向かいましたが、驚いたことに歩いている歩道の後ろから車が走ってくるのです。それも乗り合いミニバスで、その後ろに乗用車もつながっています。歩道も実質車道になっているのです。
マナーが悪いのはベトナム・ハノイで慣れていますが、ハノイはオートバイ。だが、ここモスクワは冬場の氷結状態道路となるので、バイクでは危険なので四輪者です。モスクワの道路事情がこれほど酷い実態とは、どのガイドブックにも書いてありません。
問題はインフラ整備・・・ホテル宿泊代
モスクワの観光客は、他の大都市に比較し少ないと言われています。理由はホテル代がバカ高いからです。ビザ取得のためにはホテルの予約が必要ですから、最初、旅行社経由でホテルを探しましたが、回答は一泊六万円から八万円だと言います。ビックリしてモスクワ行きをあきらめたところ、知人が妥当適切価格の日本人経営ホテルを紹介してくれましたが、一般的な旅行社ルートでは桁外れの料金となり易いので、観光目的でモスクワを訪れるのは難しいだろうと思います。次回もモスクワ事件は続きます。以上。
2007年05月21日
2007年5月20日 労働生産性・先進国最下位の背景
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年5月20日 労働生産性・先進国最下位の背景
コンベンション都市
毎年4月後半のイタリア・ボローニャは、1964年から続いている国際児童図書展が、コンベンションセンターで開催されます。地元新聞記事が、今年は芸術的作品を児童図書に使う傾向が強いと報道しましたが、会場では絵本原画展入賞作品も展示され、世界中から関係者が集まって、ボローニャの中心マッジョーレ広場も外国人で溢れ、ホテルは満杯で、当然、宿泊料金は倍近くに高騰しました。
これはミラノでも同じです。毎月、何らかの見本市が開かれていますが、春(3~5月)と秋(9~11月)は大規模展が多く、ホテルの確保は難しく料金もバカ高くなります。昨年秋のミラノ・プレタポルテコレクション、史上初の“太め”サイズのモデルがデビューして話題になった時も、今回のミラノ国際家具展時も、定宿ホテル料金が2倍近くとなり、それも前払いカード決済、キャンセル時返金なし、という強硬条件となります。
しかし、宿泊するところがなければ仕方なく、ホテル側の言いなりになるしかなく、同じ固定設備でありながら、コンベンション開催中はホテルの売り上げ・利益は倍近くになるのです。
お金を落とす旅行客の種類
ある場所に、世界から旅行客が集まるニーズには大別して二つあります。一つは観光であり、もうひとつは見本市とかセミナーです。どちらの方がその都市にお金が落ちるか。その事例を世界的温泉地として著名な、ドイツのバーデンバーデン観光局資料で調べてみたことがあります。
訪れた人が一日当たり使うお金は、①温泉療養と保養客は70ユ-ロ、②観光とバカンスは100~110ユ-ロ、③見本市・コンベンションは280ユ-ロでした。つまり、コンベンション収入は温泉療養の4倍、観光の2.8倍になっているのです。
地方自治体が狙うべきコンベンション
このような実態を考えれば、日本の地方都市で、コンベンションセンター建設済で、財政悪化で苦しんでいるところは、世界の事例に学ぶことが必要と思います。特に、イタリア・ボローニャのような37万人口の地方都市でありながら、国際見本市・展示会が目白押しで開催されているのは何故か、その要因を探ることが急務だと思います。
しかし、現地で既に、多くの視察団が訪れていると聞きました。だが、その視察はコンベンションセンターを訪れ、市役所から説明を受けるのが中心らしいのです。これでは真の要因はつかめないだろうと思います。
日本の労働生産性
経済協力開発機構(OECD)2005年労働生産性、日本は先進主要七カ国の最下位で、米国の70%の水準だと、内閣府から発表されました。
その理由として挙げられているのは
IT投資の遅れ
卸小売業は米国の五割弱
ホテル・外食産業は四割弱
家族経営の商店が多い
などで、非製造業小規模企業の労働生産性が極端に低いことが、大きく影響していると、識者が指摘しています。
労働生産性算出式は国内総生産(GDP)÷(労働投入量)であり、労働投入量とは(就業者数×労働時間)ですから、投入量に対してGDPが少ないと、生産性は低いのです。
設備生産性
次に、設備生産性はどのようでしょうか。例えば、世界の鉄道のスピード、現時点ではTGV(仏)、ICE(独)、日本の新幹線がピタリ横一直線に並んでいるといわれています。 TGVは今年4月3日、試験走行で最高時速574.8キロを達成し、線路を車両走行する従来型の鉄道では世界最高速だと自負しました。日本では磁気浮上式リニアモーターカー実験線が時速581キロを示していますが、これに迫る記録です。
一方、東京―大阪間には、今年の7月1日から5分短縮となる新型新幹線車両「N700系」が登場します。時間短縮のカギはカーブにおける車体を傾ける制御技術で、遠心力が緩和され、安全を確保しつつ、直線と同じ時速270キロで曲線を走れるのです。
高速鉄道を利用する立場としては、いくらスピードが高まっても安全性が確保されなければ意味ないわけで、ある定まった走行期間内で実施された世界最高速競争、これについてはあまり関心を示さないほうがよいと思っています。つまり、本来の設備生産性ということを考えたいのです。鉄道の目的は的確に目的地に着くことですから、無理なスピード競争で安全が脅かされるのは大問題です。つまり、設備をする目的に合致する内容充実面から判断したいと思います。
鴨川シーワールド
設備と言えば話題の東京湾アクアライン、これは1997年12月に開通されましたから、今年でもう10周年になります。そのアクアラインの海ホタルPAを通って、外房の鴨川シーワールドに行ってきました。さいたま市から1時間40分、あっという間に着きます。信じられない気持ちです。
昔、新入社員時代、会社の慰安一泊旅行で行ったときを思い出しました。2日間の日程で房総の海を回ったのです。それが今や日帰りで簡単、あっという間に到着します。素晴らしい設備生産性向上です。
また、久し振りの鴨川シーワールドにも驚きました。シャチ・イルカ・アシカ・ベルーガのパフォーマンスも見事なことと、館内の水族館のレベル、これも素晴らしいのにはビックリしました。多分、世界でも遜色ない水準にあると思います。
さらに、ビックリ仰天、大笑いで楽しめたのは「笑うアシカ」です。最後にご挨拶として一頭のアシカが、台の上から笑顔でパフォーマンスするのには、満員の客席から大拍手で、しばらく鳴り止みませんでした。入場へのお礼の笑顔だと理解し、設備ときめ細かなサービスに満足しました。
きめ細かなサービス
日本の商店・レストランの特長は、休日が少なく、営業時間が長い上、商品を丁寧に包装したり、入店時・退店時の挨拶が励行されるなど、きめ細かなサービス提供がなされていることです。
実は、その点が労働生産性を低下させています。きめ細かなサービス提供が行われないという状況になれば、生産性は上昇する余地はあると思いますが、その場合、商店・レストランでの消費満足度は極端に減少すると思います。
さらに、日本に来る外国人にとって、このきめ細かなサービス提供は、最大の魅力なのです。母国では決して受けられないサービス、勿論、高いお金を支払う特別なところからでは上質のサービスが受けられるのは当たり前ですが、日本では、普通の価格でありながら、諸外国の高級レベルのサービスが実施されているという実態、それを失ってはいけません。他国と差別化する最大の切り札がきめ細かなサービスなのです。
考え創造する力の継続化
日頃、マスコミから伝えられる内容、日本の国際競争力が中国に抜かれたとか、長寿世界一とか、世界各国との比較でいろいろ報道されます。そのデータは正しいでしょうが、中味を分析しないで鵜呑みは危険です。
データには必ず背景条件があります。それが異なっているから違いが発生しているのです。労働生産性が先進主要国で最下位、その中を分析してみれば、きめ細かなサービス提供という、日本の最大特長が背景条件として存在していたのです。
ですから、そこに、ミラノやボローニャの見本市開催時にホテル料金がアップするほどの集客力、それは「考え創造する力」を継続的に発揮させることですが、それを発揮させれば労働生産性は更に向上するはずです。5月5日レターでお伝えした、イタリア人の「日本人はバカか」と言われた指摘レベルからの脱皮、それが労働生産性向上の鍵です。以上。
2007年05月05日
2007年5月5日 アイディア・創造力
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年5月5日 アイディア・創造力
英才教育で名人となる
(山岡静山)
山岡鉄舟が真から心酔し、傾倒した人物は山岡静山であった。静山は、幼き頃より諸芸を学んだが、十九歳の時に省吾し、その後は槍に専念し、二十二歳で天下にその名が轟いた。静山の槍の師匠は、静山の母の父である高橋義左衛門で刀心流。稽古は猛烈だった。厳冬寒夜に荒縄で腹をしめ、氷を割って水を浴び、東の日光廟を拝して、丑の時(午前二時)ごろから、重さ十五斤(9kg)の重槍をひっさげ、突きを一千回、これを三十日続ける。平常の昼は門弟に稽古をし、夜は突きを三千回から五千回、時には黄昏から夜明けまでに三万回続けたという。元々天才的な槍の才能を持っていた静山が、義左衛門による猛稽古と、静山自身の常人では不可能な稽古に没入し、その成果として「槍の名人」としてその名を遺したのであるが、その背景には才能を引き出した高橋義左衛門が存在した。
(横綱大鵬、現在・相撲博物館館長)
先日、第四十八代横綱大鵬親方から、現役時代の稽古について伺った。
「マスコミなどで、私はよく『百年に一人の天才』と言われたから、努力もしないで横綱になったと思われている。いろんな人から『大鵬は、最初から大きくて強かったのでしょう』とも言われる。とんでもない。私はむしろ努力型だ。私が天才と言われるとすれば、相撲界のエリート教育を受けたからだ。このエリート教育とはしごきのことで、稽古場で気が遠くなることがしばしばだった。コーチ役の十両、滝見山さんからぶつかり稽古で土俵にたたきつけられ、これでもかこれでもかと引きずり回されたから、見ている人は『もういい加減にやめさせろ』と言った。へとへとに倒れこむと、口の中に塩を一つかみガバッと入れられる。またぶつかって気が遠くなりかけると、バケツの水や砂を口の中にかまされる。この特訓の上に一日四股五百回、鉄砲二千回のノルマがあり、それをきつくても黙々とやり通した」
静山は高橋義左衛門、大鵬は滝見山によって鍛えられた。このような人に会え、激烈な稽古から逃げなかったこと、それが名人と称されることになった最大要因である。
日本人はバカか利巧か
(日本人はバカか)
イタリア・ボローニャ市で開催された、国際児童図書展と絵本原画展に行きました。原画展では今年も日本人が入賞し、日本の絵本レベルの高さを示しました。そのボローニャに住む日本人女性から、イタリア人から見た日本人の評判を聞きました。
日本のある企業が、イタリアの機械を買ったが、壊れたのでイタリアから修理に来てもらったところ「こいつらはバカか!!」と通訳に発言したというのです。壊れた部分、ちょっと考えれば誰でも直せるところであり、イタリアからわざわざ来る必要が全くない。機械の仕組みを常識レベルで考えれば出来る。日本人は考えるということが弱点だ。日本人はマニュアルがないと何も出来ない人種なのだ。と判断しているそうです。
(日本人の利巧さ)
この話を聞きましたので、この女性にトヨタ自動車が世界一になった要因について説明しました。それはトヨタ生産方法の「次工程はお客様」のことです。トヨタの工場で徹底的に教育を受けるのは、自分が受け持つ部品セットラインの作業結果で、次工程へ絶対迷惑をかけない、次工程でトラブルを発生させないということです。そのために次のセットライン作業を「お客様」と考えること、これが最も大事な前提だという思想教育を受けるのです。この思想がトヨタ自動車の品質を高め、世界一のメーカーに成長させた一つの要因だという説明をしますと、現地女性は始めて聞いたと言い、ビックリすると同時に、日本人の組織展開力の素晴らしさを納得し「優れたリーダーの下では日本人は利巧なのですね」と発言しました。
リーダーにも会えず、もう若くない
山岡静山にも、横綱大鵬にも、優れて厳しい指導者がいました。その指導者が本人の天性素質を見抜いて、徹底的な稽古を課し、本人もそれに応える超人的な努力を積み重ねた結果、名人と言われる境地にたどり着いたのです。
トヨタ自動車も同じです。トヨタ生産方式という優れた方法を考えつき、工夫し、現場に落としこんでいった結果、世界一の自動車メーカーに成長したのですが、その背景にはトヨタ生産方式を考えついた人材と、その人を見抜き、その人を育てた優れた指導者としての経営者がいたのです。
しかし、このような事例に見られるような優れた指導者は、実際には多くいないのが現実です。また、仮に優れた指導者に運良くめぐり合え、指導を受ける機会があったとしても、自分の日常生活状態と激しく異なる厳しい指導についていけず、折角のチャンスから自ら逃げ出してしまう。これが多くの人の実際の現実と思います。
静山と大鵬が稽古修行に入ったのは年少時でした。ですから、厳しいしごきに耐えられたのです。まだ脳がフレッシュな時に、新入社員としてトヨタに入社したから、トヨタの思想に共鳴できたのです。
だが、もう若くない我々は、どのようにしたら「日本人はバカか!!」と、イタリア人から「けなされる」ところから脱皮できるのでしょうか。それには日常の生活に密着した中での訓練しかないと思います。
ボローニャの幼稚園
そのヒントをイタリアの幼稚園で見つけました。
ボローニャ市の高級住宅街、サラゴッサ幼稚園の朝九時半。三歳児から五歳児25名は、先生が読んでくれる、青虫からさなぎ・蝶に成長する絵本に集中します。読み終わると、音楽を聴きながら、蝶が羽ばたく手まねして体操室に移動し、「ハーイ、青虫になりました」という先生の声に床に寝転び、「次はさなぎでーす」に体を丸め静止状態、曲が変わって「蝶になりました」で立ち上がり、自由に羽ばたく動作をし、再び元の教室に戻ります。
机に座ると、当番の子どもが蝶のぬりえを一枚ずつ配り、マジックペンで塗りだします。輪郭線からはみ出さないように、という先生の声に全員ぬりえに集中。五歳児はさすがに早く塗り終わり、先生に見せて誉められ、自分の書類引き出しに仕舞い、三歳児は時間がかかるが、せかさず、全員塗り終わるまで待ってから、今日の給食当番をくじ引きし、当番は教室に残り、その他の子どもは先生のクイズ式反対言葉に答えた順序で並び、その順番で庭へ遊びに飛び出します。斜面の庭は樹木と芝生で覆われています。
授業を担当するのは、世界最古のボローニャ大学卒ベテラン女性。授業の中での体験と、ぬりえを結びつけ、ストーリー性あるものにし、ただ単にぬりえを塗るだけの授業は絶対にしない。これは他の科目でも同じだと強調します。
幼児時代にこのような教育を、継続的に受け続けると、現実世界での物事成り立ちには、必ず何かと連携するつながり関係があることを理解し、その結果として戦略方向性ある人間に育つだろうと感じます。
創造力とは組み合わせ能力
アイディアとか創造性発揮とは、「異種なものと、異種なものの組み合わせ」から生じます。このことが分かって、体に癖づけていますと、日頃経験しているものと、新しく接した異体験を、何かのキーワードで結びつけられないかと、いつも工夫することになって行きます。
つまり、アイディアと創造力の原点とは、日常体験と異体験の中に存在するというセオリーを体得できるのです。まさに、サラゴッサ幼稚園はこのアイディア・創造性発揮に通じる教育をしているのです。
イタリア人から「日本人は考えるということが弱点だ」「日本人はマニュアルがないと何も出来ない人種なのだ」と言われないためにも、また、年齢的に激しいしごき稽古ができず、加えて、優れたリーダーに出会えるチャンスがない中で、自らが持っている脳力を十分に発揮し、豊かに生きるためには、サラゴッサ幼稚園の授業が実施している「物事には必ずつながり・物語性がある」ということから学んでは如何でしょうか。以上。
2007年04月20日
2007年4月20日 普遍性で考える
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年4月20日 普遍性で考える
4月8日の選挙は現職勝利が多数
第16回統一地方選は4月8日、前半戦の13都道県知事選と4政令指定市長・県会議員・市会議員選などが行われました。
さいたま市浦和区も市議会議員選挙で、毎日うるさい選挙カーが走り回り、8日の夜半に議席が決まりました。トップ当選は自宅すぐ前の40歳民主党議員、二位に三倍の得票差で、いつもにこやかな笑顔で感じのよい挨拶をする女性が、この議員の奥さんです。二位は市議会議長もつとめた自民党大物議員、この人物はさいたま市管轄の福祉法人の代表で、私がそこの評議員をしている関係で、投票は悩みましたが、結局、当選者は定数八人中現職が七人、元職が一人という結果で新人当選はありませんでした。
知事選の方も、東京の石原都知事はじめ現職九人が全員再選されました。日経新聞春秋は「民意は結局、雪崩をうたず地滑りもしなかった」と伝えましたが、この選挙結果は花見と同じでないかと思います。
現職勝利は花見と同じ
日本の花見は独特で、一本二本の桜花を見るのでなく、大勢の群集で、群がっている桜を、飲食しながら見る、こういう花見は世界中にないと専門家が指摘しています。花の観賞は世界中で当たり前のことですが「郡桜、飲食、郡集」という三要素が独特なのです。
確かに、桜の名所に行きますと、全体の郡桜がこちらの気持ちを豊かにさせ、全体の調和が美しさを創造しています。よく見れば、枯れかかった幹枝もあるはずですが、郡桜全体の咲き誇りが、個別の問題点を覆い隠し、桜木の下で飲食する郡集の酔いが、それに輪をかけます。
選挙で現職が多数勝利したのも、この郡集心理と同じではないかと思います。個々には問題、不満があるでしょうが、所属する行政全体の運営について、雪崩を起す程ではない、という民意を反映したと思います。
マスコミで報道される事件・事故
東京の石原都知事が当選談話で「嫌なことが多い日本の現状をオリンピックで変えたい」と発言しました。今の日本は問題が多いという認識を持っているのです。
また、毎日々、マスコミは多くの事件・事故を、報道のトップ記事として報道していることが多い状況です。先日、元検事の人とお会いしたら「どうして日本は、このように問題が多いのでしょうか」という発言があり、周りの人も同調する雰囲気で、日本の現状を問題点多しと考えていることが分かりました。
マスコミが、目立つ事件・事故を取り上げ、そこに関心を向ければ、このような気持ちになるのも当然と思います。
よいことを取り上げればたくさんある
選挙の翌日(9日)の日経新聞「核心」は次のように述べました。
1.先月、国土交通省が発表した公示地価は全国平均で16年ぶりにプラスとなった。土地デフレもようやく終わった。
2.2002年に始まる景気回復は「実感がない」と言われながら「いざなぎ景気」を抜いて戦後最長になると、さすがに御利益が目に見えてきた。
3.三選を果した石原慎太郎東京都知事は、選挙戦中の記者会見で「(二期八年で)都財政は完全に再建できた」と胸張った。
4.東京都は特に恵まれているが、地方全体でも07年度末の自治体の債務残高が四年ぶりに割る見通しで、国よりひと足早く借金財政のピークを脱した。
5.国も、07年度予算では、新規国債発行額を過去最大幅の4.5兆円圧縮できた。2011年度に国と地方合わせた基礎的財政収支(プライマリーバランス)を黒字化させるという政府目標の前倒し達成も期待できる。景気回復のおかげである。
6.人口減にも歯止めがかかる。05年は死亡者数が出生者数を上回り「人口減少時代に入った」と騒がれたが、人口動態統計によると昨年(06年)11月、国内の日本人の人口が、一年一ヶ月ぶりに自然増に転じた。団塊ジュニアの婚姻数、出生数が増えたためだ。
7.企業の好業績は株価を押し上げ、公的年金や企業年金の運用利回りが改善し制度への信頼が増す。
この羅列の後に「日本経済に内在するさまざまな『難点』が持続的な景気拡大で覆い隠されている」と指摘し「景気が悪くなると好循環が逆転し、隠れた゛七難゛が再び表面化することも覚悟しなければならない」と結んでいます。
つまり、今回の景気拡大を更にしっかりしたものにしていきたい、という主張が成されているのですが、最近の日本について問題点を探せばいろいろあるが、良いところを探してもいろいろある、という事例です。
事件・事故は減っている
いったい全体、日本の問題点の事件・事故は増えているのでしょうか。減っているのでしょうか。警察庁のホームページからひろってみたいと思います。
刑法犯の認知件数 凶悪犯
平成14年 2,853,739件 12,567件
15年 2,790,136 13,658
16年 2,562,767 13,064
17年 2,269,293 11,360
18年 2,050,850 10,124
刑法犯の認知件数は、平成14年まで7年連続して戦後最多を記録していましたが、平成15年以降毎年減少しています。
平成14年が2,853,739件に対し、平成18年が2,050,850件ですから、4年間で802,889件減少しています。28%の減少率です。
凶悪犯は平成15年の13,658件まで増加傾向でした。しかし、その後毎年減少しまして平成18年は10,124件ですから、平成15年に対し3,534件減少しています。26%の減少率です。また、ご存知の通り、交通事故も減っています。
しかし、自殺者数は減っていません。平成9年までは年間二万人台であったのに、平成10年から急に増加し、年間三万人を超す人が自殺するようになりました。
年齢的には中高年と高齢者が多く、その要因として「うつ病にかかっている割合が多い」と政府の自殺総合対策の在り方検討会が、4月9日の最終報告の中で指摘し、急速な改善は難しい状況という結論です。
だが、テレビ番組がトップで報道していることが多い、事件・事故の発生件数はデータで見る通り、確実に減少している、という事実を認識する必要があります。
普遍性で考える
物事の判断は事実を「普遍性と特殊性」に分けて考えることが大事です。マスコミから伝えられる事実報道の、どちらが主流で、どちらが支流なのかということです。バブル崩壊後の、当時の心理状態を省みますと、日本人の多くはマイナス不安に駆られました。「公になった問題は氷山の一角ではないか」「問題がさらに拡大する可能性が大きいのではないか」という心配・疑問に襲われ、先行き悲観論が多数見解になり、これが一気に経済・社会の停滞を招いたとも言えます。
しかし、日経新聞「核心」の記事が指摘している内容、警察庁が発表している犯罪件数の減少、これらから考えますと、日本人の多くは現状認識として、全体方向の前途をプラスに受け止めた結果が「民意は結局、雪崩をうたず地滑りもしなかった」という今回の選挙結果として示されたのではないか、と考えています。
以上。
2007年04月05日
2007年4月5日 イメージ先行
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年4月5日 イメージ先行
春のパリ
関空発のJALパリ便は学生の春旅行で満員。エコノミー席を見回すが、パソコン開いているのは自分だけ。皆、映画を見ているかゲームをしている。ビジネス客はいない。
隣の大学生男女、女性がいつも独り言のように喋り続ける。男性は無口で、女性の言うことを黙って聞いている。時折、手持ちバックの収納と出し降ろしを女性が命じ、それを黙って行っている。この女性、パリに着陸する直前、滑走路混雑のため飛行機が旋回しだすと、突然、子どもが泣き出したような声で「頭が痛い、痛い・・・」と、喉の奥からヒューと絞りだすように叫ぶ。この声を聞いたとき、どこかに幼い子どもがいたのかと探したほどの独特の泣き声。客室乗務員が何人も来て、お凸を冷やし、鼻から耳に通す薬を持ってきて対応しているうちに納まって、ドゴール空港に着陸したら、ケロッと元気になって、再び独り言のように喋り続け、男性は黙って聞き、手持ちバックを二人分下げて機内から出て行く。こういう女性は将来どうなるか。余分な心配だが・・。
大学生が多い実態はルーブル美術館でも確認できる。ルーブル美術館では世界中の観光客によって床が軋めいているが、この時期目立つのは日本人学生の一団である。一階中庭に面した椅子で休んでいると、女子学生二人が「ピラミットが反対なっているところはどこですか」と聞いてくる。集合場所が分からなくなったのだ。突然に「ピラミットが反対なっているところ」と聞かれてもこちらも分からず、いろいろ相手に質問して記憶していることを聞きだし、ようやく集合場所らしきところへの行き方を教える。
日本人はイメージ過剰反応
ところが、パリの、一昨年の秋から昨年の春は、日本人は少なかったと言う。その理由は2005年秋の移民系若者による各地での暴動と、2006年春の初期雇用契約に反対する学生や労組のデモなどが、世界中に大きく報道された結果、日本や他の一部の国の観光客が減った。
しかし、その時もパリはいつもの通り年間2600万人訪れる観光客であふれていた。日本人は過剰に反応し過ぎる。一般の人は通常の生活をしており、パリの日常は問題なかった。もっと一般のパリジャンの実態をつかむべきだと言う。(パリ観光・会議局局長2006年7月12日日経新聞)
日本人は事件に敏感だということは外国旅行関係者からよく聞く。確かに、日本人はマスコミ報道を信じ、それを頼りにし、鵜呑みにしやすい。つまり、与えられたイメージ情報に左右されやすく、それで行動が制約されていく。逆に言えばガイドブックに掲載されていないところや、一般家庭に訪問しないということを示している。
従って、その国の実態を把握し難い習慣が日本人にある。
農業祭に日本人はいない
ルーブル美術館に大勢の日本人が押し寄せている同じ日の「農業祭」、その会場では日本人を見ない。「農業祭」とは、既に100年以上開催しているパリ名物の「フランス物産展」で、農・海産物から牛豚羊馬から犬猫も出展していて、パリ市民最大の楽しみイベント。地下鉄12号線ヴェルサイユ駅上の広い会場は、家族連れが各地名産の買い物を楽しんでいる。ここへ毎年行く当方の関心事は、パリ市民が何に興味を持ち、どのような物を買うかという日常実態をつかむことだが、それに加えて、金メダル受賞の生牡蠣を食べ、金賞ワインを飲むこと。これがすべて無料。今年もブロン牡蠣を十数個食べ、シャブリ白ワインをティスティングし、価格を聞くとワンボトル124ユーロだと言う。二万円近い。美味いわけだ。
因みに、パリの「農業祭」は日本のガイドブックでは紹介されていない。
フランスの経済
フランス経済は順調で、2006年度の実質GDPは2%成長しているし、2006年2月の失業率は24年ぶりの低水準(8.4%)、主要40社の2006年12月期純利益は10%増と好調、その上欧州一の「子だくさんの国」に変身している。一般人たちの日常生活がこのような経済実態をつくりあげているのだ。だから、その国の実態をつかむにはマスコミ情報に加えて、パリジャンの素顔生活に触れることも大事。
パリジャンの生き方一例
パリジャンの生き方実例を一人ご紹介したい。
地下鉄一号線終点ヴァンセンヌの森に近い住宅街は、パリの高級住宅街だ。有名私立小学校もあって、親が子ども連れて大勢登校している。中にはランドセルを親が背負っているバカ親姿もある。
その一角のアパートメントに53歳の女性経営者を訪ねた。エレベーターで6階へ、玄関ドアを開け入ると広い居間。ガラスの机とテーブルがオシャレ。職業は不動産仲介業。事前に駅近くのオフィスに寄ってみた。なかなか立派な事務所。物件を見ると
230万ユーロの建物(34,500万円)や180万ユーロ(27,000万円)。高額物件を扱っている。
屋内にある階段を上がると屋上で、ヴァンセンヌの森とエッフェル塔が見渡せ、近くに動物園もあり、隣のアパートメント屋上はプールとなっている。主人はコンピューター会社社長。起業したのはバブル崩壊した時。不動産が値下がりし、買い手もいない時だった。だが、どんな不況でも不動産を買う人はどこかに少ないけど必ずいる。という信念で不況を突破してきた。
いつもCA va?(サヴァ・元気?)と聞かれたら、つねに元気ですと答えることにしている。この気持ちが本当に大事なことで、この生き方ですべてに対応し、うまくやってきた。どんなに環境が変わっても同じ生き方をする。変えない。生き方信条は「積極的」の一言。「積極的」にするためのコツは、自分の頭の中だ。脳細胞で決まる。
もう一つ意識しているのは、常に人生の新しい計画を持つことだ。死ぬまでこれを続けること。この考え方が、年毎にさらに積極的になっていると自分で確信し、今後も続けていく。
世界は、一般の人の行動結果の積み重ねで、その国の実績がつくられていく。それはフランス・パリでも同じだと再確認した。
前駐日韓国大使の発言
この3月に駐日韓国大使を退任し、帰国し又石大学総長になった「羅鍾一」氏が次のように述べている。(2007年4月2日日経新聞)
「駐英大使などを歴任したが、日本にはなじみがなかった。日本人に対する様々な偏見が耳に入ってきたのも事実だ。外国人嫌いとか、本音と建前を使い分けるとか・・・。社会科学者として『国民性の違い』というものはあまりないとの持論を持ちながら、実際には偏見に影響されかねなかったのだ。
ところが、暮らしてみた日本は、海の外で考えていたものと相当に差があった。日本人は行儀が良く気配りをしてくれる半面、率直でもあった。その点を趣味のテニスなどを通じ強く感じた。離日を名残惜しんでくれる仲間には、韓国人と変わらない情の深さがあった。
昨年秋、妻と一緒に長野・上高地を訪れた。印象的だったのは、日本人の自然に対する態度だ。自然を観賞して休息を取り、保護も怠らない姿勢に教養を感じた。
言葉の美しさとも相まって、日本人を嫌だと思ったことはない。高校を卒業した息子に、日本への留学を勧めた。すぐに韓国の大学に進学するより、日本に来て学ぶことが大事だと考えたからだ。人はイメージを先行させがちだが、日常に溶け込んだものは強い。日本の『日常』を体験し、固定観念に左右されない日本観を持てるようになった」
この内容、日常体験の重要性を述べている発言だと思う。
ボンジュール・パリ
日本人がパリジャンの素顔の生活に触れる「ボンジュール・パリ」を企画中だと、パリ観光・会議局局長が述べている。パリだけでなく、世界の実態を妥当につかむためには、塊だけでなく、個人としての一般人の中味に目を向け、その人の考え方を聞くこと、そのようなことの継続が、その国の「実態」を把握する近道ではないかと思う。以上。
2007年03月21日
2007年3月20日 「ジャパン・クール」の位置づけ
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年3月20日 「ジャパン・クール」の位置づけ
昭和16年夏の敗戦
2月9日(金)の衆議院予算委員会で、前防衛庁長官の石破茂さんが猪瀬直樹著『日本人はなぜ戦争をしたか――昭和16年夏の敗戦』という本を取り上げ、以下のように発言したと、猪瀬さんから連絡受けましたのでご紹介します。
「なぜ『昭和20年夏の敗戦』ではなくて『昭和16年夏の敗戦』なのか、ということであります。昭和16年4月1日に、いまのキャピトル東急ホテルのあたり、首相官邸の近くですね、当時の近衛内閣でありますが、総力戦研究所という研究所をつくりました。そこにはありとあらゆる官庁の30代の秀才、あるいは軍人、あるいはマスコミ、学者、36名が集められて、どのようなテーマが与えられたか。『もし日米戦わばどのような結果になるか、自由に研究せよ』というテーマが与えられた。
8月に結論が出た。緒戦、最初の戦いですね、これは勝つであろう。しかしながら、やがて国力、物量の差、それが明らかになって、最終的にはソビエトの参戦、こういうかたちでこの戦争は必ず負ける。よって日米は決して戦ってはならない。という結論が出て、8月27日に当時の近衛内閣、閣僚の前でその結果が発表されるのであります。それを聞いた東条陸軍大臣はなんと言ったか。
『まさしく机上の空論である。日露戦争も最初から勝てると思ってやったわけではない。三国同盟、三国干渉があってやむを得ず立ち上がったのである。戦というのは意外なことが起こってそれで勝敗が決するのであって、諸君はそのようなことを考慮していない。この研究の成果は決して口外しないように』と言って終わるわけです」
この人物が戦争時に総理大臣となったわけですから、開戦前から敗戦は必至でした。
大英博物館
3月の出張はロンドン・パリで、ロンドンでは仕事の合間に大英博物館へ参りました。
大英博物館に行った目的は、元治元年(1864)に英米仏和の四国連合艦隊が下関を攻撃し、長州藩の砲台が戦利品としてイギリスに獲られ、大英博物館に所蔵されていると聞いたからです。砲台が獲られた要因は、前年の文久三年(1863)長州藩が攘夷実行だと、下関海峡を通る外国の軍艦や商船を砲撃し、その仕返しが四国艦隊攻撃となり、上陸され、砲台を戦利品として持ち去られたのです。
獲られた砲台は、日本コーナーにも、膨大な展示品リストブックを調べてもなく、現在、問い合わせをしているところですが、調べるため日本コーナーに一時間半いますと、外国人が日本に持つ関心の内容が分かってきます。
日本コーナーは5階で、縄文時代から現代まで展示してある中、サムライと説明している鎧兜と刀が展示してあるところ、ここで写真を撮る人が一番多いのです。サムライが世界の人々に知られていることが分かり、また、結構多くの人たちが日本コーナーに入ってきます。日本に関心が高いのかと思いました。
しかし、1階のエジプトコーナーに行ってみますと、黒山のような人の多さです。日本とは比較できない人の群がりで、その差は同じ時間帯での比較ですから鮮明に分かります。
一番人気はミイラ、次にロゼッタストーンの象形文字・ヒエログリフです。1799年ナポレオンのエジプト遠征時に、ナイル川の西支流の河口、ロゼッタ近くで発見された石碑で高さ114m。内容は紀元前196年、メンフィスの神官会議がプトレマイオス五世の善行をたたえ、王に特別な神官の称号を与えることを決議した布告文で、これもナポレオンの戦利品です。
大英博物館は世界中から略奪した物品の一大展示場ですが、展示物を見ようと集まってくる人数、その集客数は国別の魅力度、それは今のものだけでなく過去の歴史という財産への評価を正直に示しています。
日本が問題にならないエジプトの集客数、考えてみれば当たり前で、エジプトは世界四大文明の発祥地であり、その後の世界の発展に大きく貢献した基盤文明の地で、紀元前3200年という想像を超えた大昔に文明が誕生し、その当時の日本は闇の中だったのですから、比較にならない文明格差があるのです。つまり、世界のエジプトは基盤で、日本は基盤文明を受けて派生した表層文化であるという関係になると思います。
日本のソフトパワー
世界中の国々はいずれも四大基盤文明の影響を受け、その後に自国の文化を育てて来ました。日本も中国黄河文明から始まった中国文化の影響を最も多く受けつつ、長い歴史の中で磨き、独自の日本文化を創りあげ、世界から評価されています。以前は古典芸能としての歌舞伎や能楽などでしたが、これに加え、最近は「ジャパン・クール」(かっこいい)という評価を得だしているのが、サブカルチャーの分野です。
かつてサブカルチャーは正当な文化ではない、B級文化だ。とそこに所属する人たちが自虐的に語っていたのですが、今では日本食にはじまり、すし、マンガ、アニメなど、その中に「ぬりえ」も入るだろうと、現在いろいろ研究しているのですが、世界の人々が日本発のソフト文化を取り入れ始め、世界の普遍性に広がりつつあります。
その実態を確認しようと、パリの高級住宅街16区パッシー通りの回転すしに入ってみました。12時ちょうどに入りますと、まだ店内には数組しかおりませんでしたが、すぐにいっぱいとなり、後ろに席待ちの人たちが並びだしました。見渡したところ日本人は他にいません。前も両隣も欧米人です。フランス人とは限りません。パリには年間2600万人が訪れるという観光都市ですから、街の中にいるのはフランス人と思うのは誤りです。
すしの皿は、日本と同じように色を違えた価格とし、その皿を数えて勘定書きをウェイトレスがつくり、レジで支払うシステムです。欧米ではレストランの支払いは食事したテーブルで行うのですが、回転すしでは客がレジに行く日本式で、これが普遍性となっています。ただし、すし皿の種類は日本より魚のネタが少なく、それに代わってヤキトリや甘いものが多くなっているところが違いますが、客全員が箸を上手に使い食べています。いずれにしても回転すしが繁盛していることが分かり、確かに日本のソフト文化が「ジャパン・クール」として、世界中の人々に受け入れられていることを確認いたしました。
「ジャパン・クール」の位置づけ
「ジャパン・クール」として世界から認識されだした日本のソフト文化、20年前は刺身を食べる人は僅かでした。しかし、今では「サシミ」を当たり前に食べ、すしのネタを特定するのが普通になっているのです。急速な日本のソフト文化の採り入れ方です。これをどのように位置づけて考えたらよいのでしょうか。日本文化だけの特徴でしょうか。
実は、このような現象は日本だけの特殊現象ではありません。かつての事例としてジーンズがあります。ジーンズは今やどこの国に行っても溢れ、世界中で愛用されている普遍性です。アメリカから発したジーンズ、第二次世界大戦後の衣服簡略化の傾向を受け、各国の若者の間で流行しました。つまり、若者達に「かっこいい」と受け入れられ、その後に年齢・性別を超えて普及してきたのです。イタリアのスパゲティも同じことです。イタリアの押出し麺であったものが、今や世界の普遍的人気の食べ物です。
このように各国のソフト文化の中から、世界の人々が魅力として感じたものを、世界の普遍性として受け入れていく、という文化受容セオリーがあって、そのセオリーに則って最近の「ジャパン・クール」もあると思います。
基盤文明と普遍性文化
ここで東条陸軍大臣の「戦というのは意外なことが起こってそれで勝敗が決する」という日露戦争を事例に述べた発言、これを検討してみたいと思います。
これは戦争に勝利するための思考力でしょうか。戦争ですから「意外なこと」現象も多々発生するでしょうが、戦争は国家の総力を挙げ、国の基盤同士の戦いですから、時間の経過とともに基盤力が表出し、「意外なこと」ではなく「力どおり」の結果になっていきます。現象として現れる「意外なこと」を正しく理解するには、その背景に存在する基本的・基盤的なことから思考しないといけないと思います。東条陸軍大臣の思考にはこの部分が欠けていると思います。現象と本質という視点です。
人気が出ている「ジャパン・クール」という日本文化の「意外な人気」現象も、その基盤には世界四大文明があり、その影響を受け長い時間をかけて創り出してきたものです。
大英博物館に訪れた世界中の人々は自然に興味と関心のあるコーナーに向います。エジプトと日本の大きな集客数格差は世界文化の本質と今の現象を表出しているのです。以上。
2007年02月24日
2007年2月20日 主因は内因にあり
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年2月20日 主因は内因にあり
伊古奈で感じた内的世界
二月の経営ゼミナールは、静岡県南伊豆町の下賀茂温泉「伊古奈」で開催しました。ちょうど桜と菜の花祭りのタイミングで、大勢の観光客が訪れていました。
伊古奈といういかにも古式ゆかしいネーミング、その通りで日本の神話が背景にあるのです。この世をおつくりになった天の常立の神、その七代目のイザナギ・イザナミからお生まれになった天照大神、月夜見命、スサノオノミコト。このスサノオノミコトの五代目が大国主命となって日本を治め出雲に地に、そこへ天照大神によって国譲りが命じられ、それに従ったのが大国主命の長男である事代主命。国を譲った事代主命は、伊豆で再生し三島明神となり、その御后が白浜神社の祭神、伊古奈なのです。
古代の人々は、すべて神話とともに生き、その神話を信じて生き、自分の住む世界と、神話の世界が調和し、神話の世界から発した世界観で、自らの内部と、外部の自然現象を調整することが、何の疑問もなく行われていました。
ところが、今の現代人は、これが逆転しています。外的なことに対しては、様々な術と技で上手に対応していますが、内的な落ち着きを失っている毎日です。
しかし、伊古奈の1.5万坪敷地から発する源泉露天風呂、銀河の湯に入り、思いきり四肢を伸ばすと、何ともいえない気持ちよさになり、自らの内的世界に浸り、埋没でき、古代人に戻ったような気になります。
武士の一分
「ゲド戦記」「海猿」等がヒットし、邦画のシェアが洋画を昨年追い越しました。21年ぶりのことです。そこで、元気な邦画を見ようと「武士の一分」、木村拓哉主演を見に行きました。
山田洋次監督、さすがに泣かせます。藤沢周平の小説を舞台に、主人公の毒見役三村新之丞が毒に当たり、盲目となって、それを回復させようと妻の加世、これは宝塚出身の檀れいですが、裸足で神社にお百度参りします。神の加護に頼る姿が、痛々しくも嫋やかで凛凛しい美しさです。最後は加世を手篭めにした大番頭、坂東三津五郎と武士の一分の果し合い、盲目剣谺(こだま)返しで倒します。一瞬の殺陣です。
三村新之丞の食事、麦飯とお椀と一品、芋の煮物が好物だと語ります。里芋の茎ずいきですが、自分の好みと同じだと妙に納得しました。
それ以上に納得したのは、日本の神社仏閣が多い理由です。日本人は古代から、病気、怪我、不幸があると、それは祟り、怨霊、悪霊、物の怪が降り懸かってきたのだと思い、その解決には神仏の加護に頼ったのです。特に、疫病が多かった古代、日本書紀にも「国内に疫病多く、民の死亡するもの半ば以上に及ぶ」という一文もあるように、医学が発達していなかった当時では、神仏に頼るのは当然といえ、結果的にいたるところに神社仏閣が発生し、そこへのお参りという行動は、必然的に「自己の内部への洞察力」を深めていくことになり、結果的に内的面の訓練がなされていきます。
ベトナムの「カワイイ」
「クールジャパン」の流れは、今や「カワイイ」を国際語にしようとしています。
前回、お伝えしたベトナム女性の可愛い美しさ、世界でも一級と思いますが、しかし、この「カワイイ」女性たちの大好物が犬肉であると聞き、一瞬自宅のビーグル犬を思い出しました。朝夕の散歩時に、尻尾を縦横左右に振って、とても「カワイイ」ビーグル犬です。名前はココロと言います。
そのココロと同類の「カワイイ」犬が、ハノイの市場で、毛を剥がされ、尻尾が小さくついたままで、戸板の上に盛られています。ベトナム語で犬肉はThit ChÓティト チオーといい、プロティンが多く、腹持ちがし、味は牛より豚に似ているらしく、筍とのスープ、蒸す、春巻きに入れる、焼いて食べる、煮物、鍋、串焼き等なんでも美味しいらしいのです。
いずれ世界の動物愛護団体から禁止勧告受けるだろう。と犬肉売り場に同行してくれた「カワイイ」ベトナム女性に毒突きましたが、彼女は「美味いものは美味い。大好物だ」と譲りません。
この「カワイイ」ベトナム女性と一緒に、ハノイで一番という幼稚園を訪問いたしました。幼稚園の各教室では、子ども達が皆穏やかに先生の話を聞いています。服装を見ると整っているし、躾もよさそうですし、学習と遊びの設備も整っています。
ある教室では、イギリスから買った英語教育スライドで、3歳児がABCを声合わせて歌っています。3歳から英語を勉強しているのです。それらを見ていると、世界のどこに出しても一流と思える幼稚園だと思い、また、3歳児達がとても「カワイイ」ので、それを伝えようとすると、「カワイイ」とは言ってはいけない、禁句なのだと言うのです。
エッ、「カワイイ」と言ってはいけないのか、とまじまじと同行の女性を見詰めてしまいます。ベトナムのマナータブーで、子どもを誉めてはいけなく、誉めるとよくないことが起きると言われているのです。田舎に行くと名前も綺麗なものはつけないそうです。つまり、「カワイイ」と言う表現はあまりしないのです。
その理由は、昔は医学が進歩していなかったので、子どもが亡くなることが多く、昔の人々は神様がそうさせるのだと思い込み、神様に怒られるようなことはしないようにする風習が発したことから、子どもを誉めないことになったと解説してくれます。しかし、今は医学が進歩し病気は少ないのだから、良いこと行った子どもは誉め、かわいい子どもはかわいいというのが自然であるので、今後はこのような迷信は徐々に消えていくだろうとも解説してくれます。
「クールジャパン」の「カワイイ」が、ベトナムで国際語となるのは他国より時間がかかるでしょうが、ここでも昔から病気、怪我、不幸があると、それは祟り、怨霊、悪霊、物の怪が降り懸かってきたのだと思い、その解決を神様に頼ったことが分かります。外的要因を内的に捉えていたのです。
メジャーリーガー
アメリカ・メジャーリーグ、アナハイム・エンゼルス球団職員のタック川本さんにお会いし、2002年にワールドチャンピオンになった、その記念のリングを指にはめさせてもらいました。チャンピオンリングに触れると、幸運が訪れると言われています。
それも正しい運ということです。何が正しいかは、その言葉を受け取るこちらの判断で変わりますが・・・。
タック川本さんからいろいろお伺いしましたが、とても強く感動したことに「メジャーリーガーとして成功する為には、毎日、四食食べること」という言葉でした。
人はたいてい三食です。時には一食や二食の人もいますが、通常は三食です。しかし、メジャーリーガーは四食という意味、そのうちの一食とは何か。
それは「一日終わって寝る前に、必ず、野球以外の知識を食べろ」ということなのです。アメリカではメジャーリーガーは社会の規範的人物です。子供たちの夢の実現者であり、多くのファンの憧れの対象です。そういう立場であるからこそ、自らの行動は社会規範に違反しないこと、社会人として正しい行動がとれる人物になること、それが要求されるのです。その要求に応えるには、自らの内部、内的面の訓練が必要なのです。
バットと、ボールの扱いに優れている。これだけでは一流のメジャーリーガーと認定されないのです。もう一つ、人間として正しい姿が必要であり、この人間力無き選手は大成しないというのです。なるほどと思うとともに、人間にとって、いかに内的面の訓練が重要であるか、それをメジャーリーガーの事例は語っていると思います。
主因は内因にあり
自らの内的面を鍛えるには、その為の前提思想が必要と思います。それは、自分に発生するすべての現象に対して「主因は内因にあり」と考えることではないかと思います。
本と出会うに登場します
東京放送TBS系列「本と出会う」30分番組に、「フランスを救った日本の牡蠣」の著者で出演いたします。3月3日(土)CS「TBSバラード」11時30分、4日(日)BS「BS-i」7時30分、CS「TBSバラード」11時30分です。以上。
(3月5日号は海外出張のため休刊です)
2007年02月05日
2007年2月5日 日本のソフトウェアパワーの原点
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年2月5日 日本のソフトウェアパワーの原点
伊勢神宮
今年の初詣は伊勢神宮でした。前日に内宮近くの神宮会館に宿泊し、早朝、大浴場にて斎戒沐浴し、6時半から神宮会館職員のご案内で参拝いたしました。
伊勢神宮には安倍総理と閣僚も参拝し、多くの日本人が一度は訪れる日本の原点神社です。今までに何度かお参りいたしましたが、この度も鬱蒼とした木々と、清らかな五十鈴川の水、簡素で神々しい美しさの内宮に、早朝の寒気も気にならない感動を与えられ、日本人でよかったと、本当に思いました。
内宮とは正式名称を豊受大神宮と称し、天照大御神をお祭りしてあります。ご存知の通り20年ごとに行われる式年遷宮により、既に62度の御遷宮を行っていますから、1240年という長き伝統が続いています。式年遷宮は内宮だけでなく、外宮やいくつもある別宮、さらに装束や神宝にいたるまで、すべて20年ごとに造り替えられます。
その意味を解釈すれば、頑丈な建物を造って長もちさせるという、いわばハードウェア重視ではなく、20年ごとの式年遷宮という取り壊しと建て替えによって、古来から伝わる技能や伝統を後の世代につなげていくということ、つまり、日本のソフトウェアを保つという意味が、伊勢神宮の中に保たれていると考えます。
ベトナム・ハノイの交通状況
1月はベトナム・ハノイに参りました。夜遅くノイバイ空港に着き、翌朝、ホテル
12階の部屋から見下ろした道路は、センターライン無視のオートバイ大集団と、その間に挟まれた車とが、蟻のように黒い集団となって、蛇のようにうねり重なって交差点を曲がっていく姿、これに大変驚きました。世界で最も酷いと思い、ふと、以前、皇居を参観したときを思い出しました。皇居前広場に日本人も外国人も整然と四列に並び、皇宮警察官に引率され、桔梗門から皇居内に入って、四列が少しでも乱れると、すぐに注意されるという整列歩行が行われています。しかし、ここハノイは皇居参観と正反対で、交通ルール無視の運転と騒音が道路に溢れています。
ベトナム人は何か大きな不満足があると思います。1975年4月30日のサイゴン没落によって、ベトナム戦争に勝利し終結させ、その後の経済発展によって、食べるものも、着るものも豊かになり、都市家庭にはテレビも、水洗トイレも常備されましたが、まだ大きな何かが足りず、その鬱積をハノイの道路に爆発させているような気がしてなりません。
ハノイの人も、東京の道路のように、信号を守る整然さの方がよいと知っているはずです。だが、路上は、市民全員参加による交通ルール無視であり、その無視に率先して同調しなければ、ハノイの道路は走ることができない、という現実を見ると、そこには社会全体を覆い被せる自然感覚ソフトウェア、それが欠けているのではないかと思わざるを得ません。
ハノイのレストランサービス
ハノイの街の樹木は、何百年も経った巨大なものが多く、それが続く並木歩道は美しく、また、市内各所に湖が多く散在し、それが景観に落ち着きを加えています。
だが、眼を車道に転じますと、そこは騒音と排気ガスと埃の塊が人間を襲ってきて、多くの人は顔を覆ったマスクで、仮面ライダーのような服装をしています。更に、気がつくのは、女性のスカート姿が皆無ということです。一週間滞在しましたが、全てと言っても過言でないほどスラックス姿、それもジーンズが圧倒的でした。市内の交通手段はオートバイであるし、バスは50人乗りに100人は乗るといわれる厳しい交通事情、スカートでは難しいと思います。
スカート姿は絶無ですが、マスクを取ったハノイの女性は美しくやさしく親切です。
ベトナム料理は中華料理の影響を受けていますが、さほど脂っこさはなく、激辛味の少ないマイルドな味で、生野菜やハーブを使ったものが多いので、身体によさそうな感じがして食欲が進みます。ホテルのコンシェルジェが紹介してくれるレストラン、どこでも共通しているのが、若い女性の笑顔によるサービスで快適です。
しかし、そのサービスマナーに驚きます。例えば、薬膳料理の鍋料理で、鍋が沸騰すると走ってきて、鍋の蓋をとり、鍋の中に魚や肉を入れてくれますが、問題は、そのとった鍋の蓋をどこに置くかです。テーブル上は魚や肉や野菜の大皿が並んで、蓋を置くスペースがない場合、どういう行動をとるかです。
隣のテーブルは、フランス人とガイドらしきベトナム女性の四人、先ほどから米のご飯の上に肉や野菜を載せたものを食べていますが、まだテーブル上にはスペースがあります。そのスペースを横目で確認したかわいい笑顔の若いサービス係りは、鍋からとった蓋を隣のテーブル上に、黙って突然に置くのです。
ギョッとして隣の4人を見ると、さすがに驚いたらしく蓋とこちらの顔を、交互に見つめ合いますが、かわいい笑顔の若いサービス係りは平然と何事もなかったように、鍋の中に入れた具をかき混ぜると、隣のテーブルから再び蓋をとり、こちらの鍋に載せます。隣のテーブル上には、蓋が今まであったことを証明するかのように、鍋蓋の湿気が残した濡れた状態が残っているのに、それを拭こうとはしません。レストランの接客応対サービスに常日頃の食事マナーが顕れました。世界に通ずる普遍性ソフトウェアと違っています。
ハノイの子どもが行きたい国
ハノイの中心街に住む1971年生まれの女性を訪問しました。家族は夫と12歳の女の子と4歳の男の子がいます。
ハノイの中心部にある住居の多くは、表通りから入った路地に混在しています。この女性の家も、幅1.5メートルくらいの細い路地を、奥に右左に曲がり入り、最後は一軒の家の入り口で路地が終わる手前の左側、向かいの家のドアには、子猫が首を紐で縛られて羨ましげに歩く人間を眺めていて、その子猫が繋がれているドア前の家が、訪問した家です。家の入り口は、鉄製の開き格子で鍵がかかって閉じられています。その閉まっている鉄格子の片隅にあるベルを押すと、鉄格子ともう一つの木製ドアが開いて、中に招じ入れてくれました。
1階がキッチンと居間。敷地は狭いので5階建です。2階は長男の部屋、3階は両親ベッドルーム、4階は12歳の長女の部屋、5階は仏壇部屋だと説明受けました。細長い階段には窓がないので日当たりはなく、両隣の家も壁同士が接する建て方で、同様の5階建てです。招じ入れられた1階の居間とキッチンには、天井からテレビが吊り下がっていて、その前に食事するテーブルがあり、すぐ横には、ホンダのオートバイと自転車が置かれています。つまり、1階は車庫も兼ねているのです。
日常の家族生活は、夫婦共稼ぎですので、子供を連れて朝7時半に家を出て、男の子は保育園に預け、夕方5時に迎えにいき、夫も6時には仕事から戻ってくるので、毎日4人揃って夕食し、テレビを見て、家族団欒する生活、日本人は家族揃って食事しないそうですね、と指摘されました。
眼鏡をかけた12歳の女の子に聞きました。「一番行きたい国はどこ」「日本です」「どうして」「ドラエモンのマンガがあるから」。
アジア地区では圧倒的に「ドラエモン」が人気です。また、テレビも日本のアニメーションが圧倒的シェアですので、マンガ・アニメ等のソフトウェアパワーによって、日本のイメージが作られている実態をハノイの家庭で確認できました。
特殊性が普遍性になった
ニューヨークの子供に聞くと、好きな食べ物のベストスリーは「スシ、ピザ、スパゲッティ」と答えます。今や寿司は世界の普遍的な食べ物です。しかし、30年前、始めてヨーロッパに行ったとき「日本人は魚を生で食べるらしいね」と、フランス人から軽蔑的な言い方をされたことが思い出としてあります。
そこから、いつの間にか大変化し、世界の普遍性となりました。日本独自の伝統的であった特殊性が、世界中で受け入れられたのです。これをどのように理解したらよいのか。それは、日本人の生活スタイルが持つ背景のソフトウェアが、今の現代の文化パワーとして世界に受け入れられたのであり、そのソフトウェアの原点は、1240年を超える伊勢神宮の式年遷宮にあることを、寒気厳しい早朝の伊勢神宮で感じました。以上。
2007年01月06日
2007年1月5日 考えることのシステム化
環境×文化×経済 山本紀久雄
2007年1月5日 考えることのシステム化
新年明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
今年の経済と日本の最重要課題
今年の日本経済は景気拡大を続ける、という予測が経済調査機関の大勢見解です。一部に今年前半足踏み状態の「踊り場」に差し掛かるとの懸念見解もありますが、これも短期間で終わり、年間では順調に推移し、日経平均株価も年後半にかけて上昇基調に向うというのが大勢です。このような景気拡大は世界的な傾向で、アメリカは10年間、イギリスは15年目、オーストラリアは16年目に入る景気拡大を続け、日本も35年前の「いざなぎ景気」期間を超えました。
だが「景気はよくなっているらしいが、さっぱり実感がない」という声が巷には強いのも実態です。これは過去とのデータ比較でハッキリしています。いざなぎ景気(65.10~70.7)とバブル景気(86.11~91.2)と今回(02.1~)を比較してみますと、消費は9.7%⇒4.5%⇒1.7%増であり、賃金は17.6%⇒4.8%⇒0.3%増に見られるように、いざなぎ景気の時は「消費も増え、賃金も増えた」のですが、今回の景気では設備投資と外需が主なる牽引車なのです。つまり、企業の業績向上で全体の経済状況を好転させたのです。
この結果、国の税収が増え赤字国債の発行も少なくなってきました。日本はプライマリーバランスを単年度で黒字化することが当面の目標で、これは税収増で目標年の11年より早まりそうですが、このような目標を掲げているのは日本くらいで、プライマリーバランスが黒字なっても、バブル崩壊後に財政支出した膨大な借金が減るわけではありません。
個人でも借金漬けが続く生活では、明日に向って意欲的な計画は難しいのは国も同じで、日本国家の大借金漬けは最重要課題です。早く本格的に財政再建をすることが国家運営上最も必要なのです。ですから、まだまだ企業に頑張ってもらい、税収を増やしてもらわねばならないのが実態です。
的を絞る
日本企業の強みは製造力です。日本人が持つ「ていねいにモノをつくりあげ、少しでもよくしようとする意識」を製造現場の仕組みに活かしたトヨタを始め、多くの優良企業が世界に評価されているのはこの日本人の感性です。
トヨタのように毎年アメリカに工場を造ってきたのは、貿易摩擦対策もありますが、アメリカ人がトヨタ車を高く評価し購入するからです。キヤノンも同じで、優秀な製品づくりがアメリカ人に受け入れられ、今日の世界的企業になった要因です。
更に今後、日本の人口が減少していくことを考えれば、日本国内では販売数量は増加しないのですから、購買してくれる人が多い国に進出しなければなりません。自動車の場合、日本国内で販売できるのは軽乗用車を入れても昨年574万台で、ピークの90年(777万台)の74%、これからも増えないのですから海外に展開するしかなく、それをトヨタは実行してきたわけで、結果は納税額日本一という実績になっているのです。
素直に考えると、日本の最重要課題である財政再建を早めるには、トヨタのような世界的企業へ多くの企業が成長・躍進し、好業績をあげ、国に税収という貢献をしてもらうことが最大の対策になります。
つまり、多くの要因がかみ合って複雑になっている財政再建策を、一つの的に絞って対策を整理してみれば、それは企業の成長であり、その企業成長とは人口が増加している海外での展開にかかっているのです。これは歳出削減や個人所得格差等の問題を考慮しない、ある意味での暴論ですが、今回の景気拡大の中身を検討し、財政再建という国家問題を考えれば、様々な対策を考えることも重要ではあるかもしれませんが、的を絞った対策に特化すべきではないかと思っています。
ある世界観を持って世界を見る
今年の世界経済の伸び率予測は、経済調査機関の見込みで4%を超す成長となっています。日本、アメリカ、ユーロ圏は2%前後と予測していますが、中国をはじめとした新興国の景気拡大が大きく世界全体に貢献するので4%を超すと見ているのです。
ここでまた素直に考えてみたいと思います。例えば、自動車はアメリカ、ユーロ圏、日本では多くの家庭で所有していて、何ら珍しい存在ではありません。だが、その他の国では車は一般的に非所有物であり、貴重品であると思います。つまり、車を持つことに憧れている人たちの方が世界全体では多いのです。カメラも同じです。日本人にとってカメラは持っているのが当たり前ですが、地球の上から世界を見れば、カメラを持っていない人の方が多いと思います。世界的に見れば需要は限りなく存在するのです。
その需要があって、経済的に購入できなかった国の人々が、経済力を持ち始めた。これが世界経済を成長・躍進させる最大要因となったのです。構図が変わって来たのです。
BRICsのブラジル、ロシア、インド、中国。NEXT11ネクスト・イレブンのバングラデシュ、エジプト、インドネシア、イラン、韓国、メキシコ、ナイジェリア、パキスタン、フィリピン、トルコ、ベトナム。TIPsのタイ、インドネシア、フィリピン。
東西冷戦の終結を受けて、1990年代に始まった経済のグローバル化は、このような国の経済成長を促進し始め、地球の隅々まで経済成長という姿がいきわたっていくというのが、経済専門調査機関が予測する世界経済の伸び率4%を超す背景なのです。
ですから、経済力を持ち始めた国々対してアプローチしていくことによって、まだまだ企業は成長できる可能性が高いのです。つまり、世界経済全体が大きく成長し、日本製品に対する需要がますます増えるという世界観で、地球全体を見る必要があると思います。
人の力量とは考えること
毎月、内外各地を訪れ、多くの方とお話し、事業の成功例や失敗例を学んでいます。実例としてお話いただく内容は結果論です。この結果論はある条件で成功した事例であって、それをそのまま真似して展開したとしても、必ず成功するとは限りません。逆に失敗した事例でも、成功する場合があります。倒産寸前企業の再建を成功させた者としてよく分かります。
事業が成功するか失敗するかは、その背景にある「経営を担当した人の発想や工夫」によるのです。戦略決定と戦術展開の巧拙、つまり、事業担当する人の力量の問題に帰結します。トヨタもキヤノンも創業者から現在まで経営者の力量が優れていたからこそ、世界的企業に成長し、国家に多額の納税を行う貢献企業に成れたのです。企業は人なりです。
ですから、企業成長には人材が必要なのです。経営環境も重要な必要条件ですが、それよりも人の力量です。
では、どのような力量が必要なのか。様々な人間力要素があると思いますが、最も大事なことは「考える」ということではないでしょうか。この「考える」ことは誰でも行っていることで、人間ならば必ず行うことです。
しかし、「考える」という内容をシステム的に行っているか、ということについては如何でしょうか。「考える」ことを脳内行動のシステムにしているかどうかということです。
「考える」とは次の五つの作業ステップを踏むことだと、私の専門である脳力開発では定義します。①集める⇒②分ける⇒③比べる⇒④組み合わせる⇒⑤選ぶ、この五段階のステップを意識的に踏んで、日常行動の中にシステムとして習慣化させていく。
「①集める」とは情報を収集することであり、「②分ける」とは要件ごとファイル化することであり、「③比べる」とは戦略に基づいて集め分けたものを対比することですが、特に大事なのは「④組み合わせる」です。新しい発想・着眼・創造は組み合わせから生れ、他との違いをつける最大ポイントです。最後の「⑤選ぶ」は決定することです。
この一連の作業を常に行って、日常の中に習慣化させ、システム化して行く結果が、諸問題への対処方法を決め、行動となって、その実行結果として、成功・失敗が決まるのです。
考えることのシステム化
今年の日本経済は順調に推移するという予測と、世界経済も高い伸びを示すという予測、この両者の組み合わせによって、日本の企業力を更に強化し、税収を高めることによって、日本の最重要課題である財政状態が、早く正常状態に戻ることを期待したいと思います。
そのためには日本の企業力向上が絶対条件であり、企業経営者の「考える力」システム化が前提条件ですが、この脳力開発思考ステップは全ての人に有効であると思います。以上。
(1月20日号は海外出張のため休刊となります)
2006年12月06日
2006年12月5日 情緒と形
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年12月5日 情緒と形
戦艦大和
広島県呉市の「大和ミュージアム」を訪れました。JR呉駅を出て、多勢が歩いていく方向について行くと自然に着きます。人気があるので訪問客が多いのです。入館すると眼前に「戦艦大和」が突如として現れます。この突如という言い方は少しおかしいと思いますが、こういう表現が適切と思えるほど、始めて見る「戦艦大和」は偉容に溢れています。
実は「戦艦大和」の全形を捉えた写真は少なく、その少ない中で公試運転中、全速で大時化の中を走っている姿が写され残っています。この写真が素晴らしく、これが残っていなかったら、「戦艦大和」人気は今ほど沸騰しなかったのではないか、と言われるほどの名写真で見慣れた姿が眼前にあるのです。イメージと実物とが一体化しました。実物の10分の1の大きさであっても、日本刀のような繊細なバランスと、日本人の緻密丁寧感覚でつくった造形美が横たわっています。
昨年公開された「男たちの大和」という映画、出演者の少年達を募集しましたら、オーディションに約2000人が集まり、何度かの選抜を重ね絞っていくうちに、少年達の様子が変わっていき「同年代であつた少年が、このように戦って、みんな死んでいったかと思うと、仇やおろそかに演技ができない」という心境をもらすようになったのですが、これは「戦艦大和」で亡くなった3300人の気持が伝わったものと思います。
確かに、館内で遺された遺書を読み、テープの声を聞くと、出演者の気持ち同様、私もあの時代に生きていれば、敵艦に体当たりすることに疑問を持たなかったのではないかと思います。何故なら、日本全体が「その時代の雰囲気」になっていたのですから、死に臨む気持ちと、死に対する疑問感、それが今とは全然異なっているので、現在の感覚で評論しても意味がないのです。これは戦争賛美ではありません。その状況下では「その時に生きている感覚しかない」のです。
この日本人が持つ全体的な「情緒感」と、そのような情緒感覚になっていく「形」、これは日本人特有のものではないかと感じます。
六義園
寒い日でしたが、始めて「六義園」を訪れました。JR駒込駅近くの27,000坪もある広い日本庭園です。柳沢吉保が元禄15年(1702)に築園したものですが、明治時代は三菱財閥の岩崎弥太郎の別邸となり、昭和13年(1903)に東京都に寄付されたものです。今まで多くの人から素晴らしいとお聞きしていましたが、まだ訪れたことがなかったのです。
庭園の中心には池が配置され、そこに趣のある島と石が配置されています。池の周りを歩き、池越しに紅葉が映えている景色を見ますと、これが日本の美しさであると改めて感じ、10月に歩いたニューヨークの「セントラルパーク」との違いを感じます。「セントラルパーク」の面積は「六義園」の約35倍ありますので、規模は比較になりません。大きな樹木が並び立ち、芝生が広がり、池ではボート遊びが出来るほど、テニスコートもあり、動物園も劇場もあります。当然立派なレストランもあります。また、サイクリングで走れる道路も整備され、スピード出して走っているので危険を感じるほどです。更に、広大な貯水池もあって、この周りを亡くなったジャクリーン・ケネディ・オナシスがよく走っていたというので、彼女の名前がつけられています。
二つの庭は発想が全く異なります。「セントラルパーク」はゴミ捨て場だったところを、世界初の都市公園として造りました。「六義園」は昔の中国の詩の分類法である六義、それにならった古今集の和歌分類「かぞえ歌、なぞらえ歌など」に由来したものですから、同一基準で比較することが間違いです。
しかし、園内を人が歩いて回るという行動については同じですから、短い訪問タイミングで両方を体験しますと、独りでに比較してしまい、その結果で感じるのは日本とアメリカの差であり、その意識差を2001年9月11日以後、しばらく行かなかったニューヨークを今年訪れ、改めて感じました。
ニューヨークは異なった人種がかき混じりあって住んでいるのに、一体化していなく、多様な文化は残ったまま、つまり、「サラダボウル」という感覚で、その中で生き抜いていくには「競争に勝つ」ことしかない、と会った人たちが一様に語ります。だが、その語り口の肩越しに、勝者になれないことを予測している「孤独」さが漂い、結果として発生する超格差社会を受け入れる、ひやりとした割り切り感覚があります。
つまり、論理中心に勝ち生きる社会の現実の厳しさがアメリカにあり、そういう感覚を根底に持って造った機能美が「セントラルパーク」だと思います。ところが、「六義園」は違います。園内を歩くと内省的にならざるを得ない感傷感覚が伝わってきます。和歌の世界の「情緒感」と「形」が伝わってくるのです。
皇居
次に行ったのは皇居です。いつも皇居前広場とお堀端から皇居を眺めるだけでした。
今回は一般参観として、多くの人と一緒に桔梗門の前に整列し、それも四列に整然と
30分前から並び、外国人も同じく整列に入れられ、皇宮警察官に引率され一般参観コースを歩きましたが、少しでも列が乱れると指摘され、元の四列に直されます。誠に厳しいもので、外国人はビックリでしょう。
富士見櫓を右手に見て、上り坂を左に曲がると宮内庁があって、その奥が「宮殿」です、という案内皇宮警察官の説明に違和感を持ちました。「宮殿」というにはあまりにも質素なのです。今まで多くの国でパレス・宮殿を見てきました。ロンドンのバッキンガム宮殿が代表するように、いずれも石造りの威圧感を与える構造となっています。
それに対して皇居は平屋建ての「宮殿」で、静かにそこに佇んでいる、という感じがします。また、毎年、新年と天皇誕生日に、宮殿の長和殿東庭に面したバルコニーで両陛下が祝賀を受けられるところ、参賀する人たちからあまりにも近い距離に位置していることにもビックリし、加えて緑の多さにも驚き、最後まで四列縦列で歩いて、皇居には典型的な日本の「情緒感」と「形」が表現されていると感じました。
秩父夜祭
最後は12月3日夜の「秩父夜祭」です。秩父市は埼玉県内にありますが、そこで開かれる三百数十年の歴史を誇る「秩父夜祭」に、ようやく今回行くことができました。
今まで行かなかったのは、とにかく秩父盆地は寒く、その寒い夜中に開催され、見物客が多すぎるという評判を聞いていましたので、長いこと逡巡していたのです。
実際に「秩父夜祭」の現場に立ってみると、熱燗を何度も手にしてしまう寒さと、息が詰まるほどの人ごみ、これは前評判通りでしたが、しかし、秩父神社からお旅所といわれる場所まで、元気な若衆によって掛け声と共に、豪壮に街の中を曳きまわされる六基の屋台と笠鉾は誠に見事です。素晴らしいの一言です。よくぞこういう伝統が何百年も残っていたと感動します。また、その曳きまわしの背景に、夜空の連発スターマイン花火が彩ります。更に、昼間は街の各地で屋台芝居の歌舞伎と、屋台囃子が演奏され一日中楽しめますが、問題は祭りの終わりが深夜になりますので、戻りが明け方になるということだけです。始めて見物した「秩父夜祭」にも、日本の「情緒感」と「形」が表現されていることを確認しました。
情緒と形
今年の流行語大賞は、トリノオリンピック金メダル荒川選手の「イナバウアー」と、「品格」です。「品格」は藤原正彦氏の「国家の品格」(新潮新書)がベストセラーになったことかからですが、この本は「論理より情緒」「英語より国語」「民主主義より武士道精神」「経済大国より文化大国」「普通な国より異常な国」・・・それらが「日本が品格を取り戻す」ためのキーワードだと主張し、これが多くの人から共感を得ました。
この流行語大賞を機会に改めて「国家の品格」読み直しますと、「数年間はアメリカかぶれだったのですが、次第に論理だけでは物事は片付かない、論理的に正しいということはさほどのことでもない、と考えるようになりました。数学者のはしくれである私が、論理の力を疑うようになったのです。そして、『情緒』とか『形』というものの意義を考えるようになりました」(はじめに)と述べているところに強く共感いたしました。
そこで10月と11月は海外出張がないので、今まで訪れていない国内各地を回り、この「情緒」と「形」が、日本に確かに存在する事実を再確認してみたわけです。以上。
2006年11月21日
2006年11月20日 格差社会
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年11月20日 格差社会
米中間選挙結果
11月9日のアメリカ中間選挙について、世界中の人が高い関心を持ち見つめ、民主党の勝利とブッシュ大統領・共和党敗北を全世界で確認し合いました。
一国の選挙結果について、どうしてこのように世界中が関心を持つのでしょうか。日本の総選挙についても、このように世界中で高い関心を呼ぶでしょうか。ある程度の関心事項として取り上げられると思いますが、アメリカの選挙結果とは格段の差があります。これは日本が特殊でなく、アメリカ以外の国に共通している状況と思います。アメリカだけが特別なのです。世界中でアメリカへの関心が、異常に高いのです。
アメリカは旧ソ連との冷戦状態を勝ち抜いて、今や一国だけの超大国として世界に君臨しています。政治、軍事、経済、文化、すべての分野において抜きん出た力を世界に及ぼしています。このアメリカのブッシュ大統領が、2001年9月11日に発生した同時多発ニューヨークテロを機に「テロとの戦い」を標榜し、アフガニスタン攻撃、イラク戦争へと突き進んだ結果、アフガニスタンもイラクも治安は一向に安定せず、返ってテロ危険は世界各地に広がっています。出口の見えないアメリカの戦い方に、世界の人々の不安がつのっているのが現実の姿です。
日本やイギリス、オーストラリアのような、アメリカとの同盟国は、ブッシュ大統領の「テロとの戦い」に共同歩調を採って、イラク駐留へと行動しました。これに対し、日本では「ブッシュ大統領の言いなりだ」「アメリカべったり」だという批判的見解や、一国のみとの同盟関係を楯に戦争への全面協力はいかがなものか、という意見が多々ありますが、このような意見対立は日本独自のものではなく、世界中の国々で一様に議論され、結果的にアメリカを敵視する国もあれば、運命をともにしようとする国になっているのが現実です。それにしてもテロは9.11で、選挙は11.9というのも面白いものです。
アメリカに対する気持
そのアメリカを、2001年9月11日以後各国がどのように見ているか、その実態を毎日新聞が特集として04年4月から06年3月まで、同紙第一面に掲載した内容を、この度「脱米潮流」として出版しました。
世界の様々な国では、アメリカを好きな人もいれば、嫌いな人もいます。当然です。しかし、この「脱米潮流」を読んでみますと、アメリカへの好き嫌い感情が、その国の政府が採っている政治情勢、つまり、アメリカ敵視政策国であっても、同盟国であっても、一般国民の多くの感情は全く同様である、という現実を伝えていることに驚きます。つまり、自由なアメリカにあこがれ、アメリカに行きたいという気持で一致しているのです。
例えば、イラン。アメリカは核開発、人権、テロ支援の各問題でイランへの圧力を強めています。それに対しイラン政府は強く反発し、アメリカからの圧力が強ければ強いほど、イラン国内では反米保守派が活気づいて「アメリカは敵だ」という声が高まる一方のように感じていますし、日頃の報道からそのように理解しています。
ところが、毎日新聞記者とテヘランの若い男性との会話は次のとおりなのです。
「アメリカはイランを攻撃するのか?」とイラン人男性、「大丈夫。アメリカにイランを攻撃する余裕はない」と記者の回答、「なら、イランは当分、このままということか」と肩を落とした。今、イランの若者にはこの男性のように、状況が変わるならアメリカによる攻撃さえ「期待」するような感情さえ芽生えているという。この男性はイスラム革命(1979)の年に生まれました。イランでは革命後の世代が人口の三分の二を超え、王政を打倒した革命の熱気は過去のものとなっていて、革命後に誕生したイスラム支配は自由を制限しいたことで、国民の支持獲得に失敗し、若者や女性を中心に「変化」を求める傾向が強い、とも書かれています。また、04年の総選挙で大量の改革派議員の立候補が認められず、国民は政治の自由さえ奪われ、若者たちの絶望感は、多くが留学先にアメリカを希望するなど、「自由」を標榜する国への過度のあこがれを生み、その国からの「攻撃」を「期待」するといったゆがんだ感情につながっている、と分析しています。
隣の中国の実態についても、意外な事実が書かれています。中国では90年代から指導部が愛国教育を強化してきた結果、新しい形の民族主義が台頭するようになって、国内の政治体制や指導者への批判が禁じられた状況の中で、アメリカや日本などの外の「敵」に矛先を集中する傾向があり、「新民族主義」などと呼ばれています。この動きは「実際には政府幹部の腐敗や貧富の格差」に不満を抱く国民が「愛国」という看板を掲げて暴走するケースを生み出し、中国そのものにとって危険な存在になってきているようです。
それを証明するのが99年の北大西洋条約機構(NATO)の軍機がユーゴスラビア中国大使館誤爆事件に対し、愛国教育を受けた学生が反米感情を燃え上がらせ、各地で大規模なデモを起こし、これは官製デモとの見方がありましたが、最後は指導部が収束にてこずるほど激しいものになり、「新民族主義」の台頭として注目を集めました。
しかし、このデモで中心的な役割を果たした学生の多くはその後、アメリカに留学しているのです。最近の学生は「アメリカ覇権主義反対」を叫びながら、アメリカ留学を目指して必死で英語を勉強している。これは笑い話でなく現実の姿なのだと伝えています。
また、北京五輪(08年)や上海万博(10年)に向け、タクシー運転手から役人まで英語の勉強を半ば義務づけられていて、学習人口はアメリカの人口3億人を遥かに超す
4.5億人に達していると言い、この結果の先には「国民意識に革命的な変化」が起きるかもしれない可能性さえも指摘しています。つまり、英語を勉強するということは、アメリカ社会をより知っていくことにつながり、それは自国の「一党支配体制」という矛盾に気づくということになっていくだろうと予測されるからです。
アメリカを敵視している代表的なイランと、一定の距離を置いている中国がこのような実態ですから、他の国は当然の如く、一般の人々がアメリカに持つ感情は好意的な事実を「脱米潮流」が伝えています。そのことを意外と思いつつも、成る程と納得します。
超格差社会
もう一冊ご紹介します。「アメリカの真実・小林由美著 日経BP社」です。今のアメリカは四つの階層に明確に分かれていると分析しています。
まずトップに「特権階級」として、400世帯前後いるとされている純資産10億ドル(1200億円)以上の超金持ちと、5000世帯強と推測される純資産1億ドル
(120億円)以上の金持ちがいます。
次に「プロフッショナル層」として純資産1千万ドル(12億円)以上の富裕層と、純資産200万ドル(24,000万円)以上で、且つ年間所得20万ドル(2400万円)以上のアッパーミドル層で、この層は高級を稼ぎ出すための、高度な専門的スキルやノウハウ、メンタリティを持っている人たちです。以上の二階層500万世帯前後は、全米
11,000万世帯の5%ですが、ここに全米の富の60%が集中していて、経済的に安心して暮らしていけるのは、この5%の金持ちだけだと断定しています。
三階層目は「貧困層」ですが、ここで疑問をもつのは、かつての中産階級はどこに行ったかですが、アメリカの中産階級は70年代以降、国力が相対的に低下する過程で、徐々に二分されてきて、一部は高度な専門的スキルやノウハウを磨いて「プロフッショナル層」へステップアップしたが、しかし、大半は「貧困層」に移ってしまい、その理由は製造業の衰退で、レイオフされたがステップアップできなかったためであり、これはマイケル・ムーア監督映画「ロジャー&ミー」にあるとおりと述べています。
最下級層は「落ちこぼれ層」で、四人家族で年間世帯所得23,100ドル(280万円)以下と、スラムや南部諸州に集中している黒人やヒスパニック、インディアンと、海外からの難民と密入国した違法移民で、この層が全人口の25%から30%占めています。
ニート・フリーターへの見解
アメリカの公立小学校では、まず、話すための英語から学びだします。移民が多いので話し言葉から入るのです。日本は入学時に既に日本語を話せるから文字から入ります。ですから、アメリカの公立学校のレベルは低く、ここで学ぶ「落ちこぼれ層」は決してエリート大学には行けず、最下級層から脱皮できないというのが現実で、格差社会は解決できないのです。しかし、今日本で問題となっているニートやフリーター格差問題は、アメリカとは全く違い、自らがキャリア開発しないからその立場にいるのであって、その背景にキャリアを会社から与えられるものと考える甘さがあり、その感覚を許している日本人の他人任せ解決姿勢を、厳しく問題視しているこの本の指摘を、成る程と思います。以上。
2006年11月06日
2006年11月5日 基本を押さえる
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年11月5日 基本を押さえる
今の新聞
先日、長期信用銀行出身の経営者の方とお話をする機会がありました。話題は長銀がバブル崩壊後巨額の不良債権を抱え、経営が迷走状態となり、最終的に政府によって一時国有化された後、アメリカの企業再生ファンド、リップルウッドや外国銀行らからなる投資組合New LTCB Partners CVに売却され、これが新生銀行となった経緯になった辺りから、憤懣やるかたない表情となり、当時の政府と大蔵省を罵倒します。この気持は十分に分かります。今から6年8ヶ月前の出来事でした。
気持が少し落ち着いた頃に「長銀の出身者で有名人はどなたですか」とお聞きしますと「竹内宏さんと日下公人さん」を挙げられました。竹内宏さんは経済をやさしく絵解きすることで人気がありましたし、日下公人さんは今でも著書・講演で活躍されています。この日下公人さんが今の新聞について次のように述べています。
1. 取材力不足のまま報道する。2. 報道に迫力がないので解説に逃げる。
3. 解説も勉強不足だから道徳論に逃げる。4. 道徳論も結論を言うには勇気がいるから、単に一般的な願望を言う。
猪瀬直樹さんからも同じようなことを直接聞いたことがあります。道路公団民営化の問題で新聞記者と接し痛切に感じたと言っていました。毎日読んでいる新聞の記事内容がこのようであるとしたら、自分の足で確認することの必要性を改めて感じます。
日本の景気
東京駅、大丸デパートのコート売り場に人影がありません。気温が高くコートやセーターなどの防寒着が売れません。衣料品専門店は軒並みに売上前年割れです。
しかし、大企業の中間決算発表は好調です。日本の全体景気もいざなぎを超え、10月19日日銀支店長会議では、日本の全地域が回復・拡大基調に転じたと報告されました。データ上では景気回復が長期化しているのです。
だが、一般の人々、先日もあるセミナーで「この不況下で苦しんでいる」と発言した29歳のサラリーマンがいたように、景気回復感がない人々も大勢いるのも事実です。
これに対し、経済エコノミストの今井澂さんは次のように明解に述べています。
「要するに大企業の製造業で、世界市場にリンクしているところは、絶好調と言っていいし、この大企業と取引がある中小企業は元気だ。日本国内にしか市場がない製造業や非製造業、特にサービス業は、この好況の恵みにまったく浴していない」
これになるほどと思います。そういえば今年の5月にアメリカ・シアトルに行った際、ここにはボーイング社の本社があって、ANAが次期主力機「787」を50機まとめて注文したので、シアトルの町で大評判になっていました。この2008年に就航する「787」は、既に5年分以上の生産数に相当する650機(今年の6月末)を受注しており、この機体向けに炭素繊維を供給している東レの中間決算は過去最高の営業利益となっているのです。勿論、東レと同じくボーイング社と取引がある日本企業はすべてこの恩恵を受けて、好調な決算となっています。この内容を山本塾でお話しましたら、出席の外国航空会社の客室乗務員の方が「うちも何機か注文している」という発言もあり、今井澂さんの指摘は事実と確認できます。ですから、このような大企業と、その下請関係企業が所在している市町村は景気がよく、そうでないところはシャッター通りになっていく。グローバル化が市町村の景気を左右させているのです。
NYぬりえ展
10月21日にニューヨークのぬりえ展が終了し、開催した大西ギャラリーのオーナーは、次のコメントを述べました。
「ニューヨークの人たちは日本文化・アートに大変興味があるが、それを鑑賞できるのは美術館が多く、気軽に訪れられるギャラリーでの鑑賞は難しい。その意味で今回のぬりえ展が、現代美術の中心であるチェルシー地区の当ギャラリーで開催されたことによって、アメリカの幅広い層に、日本のポップ・カルチャーの原点としてのぬりえを紹介できたことは有意義だった。また、日本のぬりえを見るのはアメリカで初めてであったが、ぬりえは子供の遊びとして世界共通のものだから、アメリカのぬりえと比較し、その差にとても興味を持ったようだ」。
また、ジャパンタイムズには「来場者はきいちのぬりえの”かわいさ”を認め、同時にきいちの芸術性とそのディテールに感銘を受けていた」と掲載されました。
これらの評価から、ニューヨークで「きいちのぬりえ展」を行うことは、時期尚早という一抹の不安もありましたが、それは杞憂であったと感じているところです。
大人のぬりえブーム
ある方からメールをいただきました。「大人のぬりえがブームとなっているが、ブームが去った後はどうなるのか」という内容に「やはりそうなのか」と思います。ぬりえはブームだから人気が出ていると理解しているのです。
確かに河出書房新社と産経新聞社が主催した11月3日の「大人の塗り絵コンテスト」には、3千点以上の応募があり、入選作を決めるのに困るほど力作ぞろいだったと審査員が述べています。確かに大人が塗るのですから、しっかりした作品が多く、これだけの応募があるのですから、河出書房新社刊の「大人の塗り絵」シリーズが140万部を超えるベストセラーになっていることも頷けます。
ブームとなっている理由としては「脳を活性化する」「癒される」等を挙げています。しかし、脳の活性化や癒されるものは他にもたくさん存在する中で、どうして「ぬりえ」がブーム化しているのか。そのところの理由が明確でないままに、新聞やテレビがブームとなっていると報道し、それを見聞きした多くの人がブームと理解していく。そのような気がしてなりません。
つまり、ブームになっているということは、人間の中に存在している何かを捉えているということですが、その何かを明確にしていく作業を誰もしないで、ただブームという報道と、その報道によって多くの人たちがぬりえを塗っているのではないか。
そのところを指摘したのが冒頭のメールであり、この方は「ぬりえという存在の基本を押さえろ」と伝えてくれたのではないかと思っているところです。
コンテンツビジネス
明治維新を期に「和魂洋才」を基本に走ってきたのが日本の実態です。今でも諸外国から技術を買い、それに応用技術を付け加え、それを付加価値として効率よくつくろうとしている企業が多くあり、この上手さで「ジャパン・アズ・ナンバーワン」と謳われたときもありました。しかし、今は世界の工場はアジア諸国に移って、人件費高の日本が世界と競っていくには、応用技術だけでは限界が来ていると、御手洗経団連会長が指摘しています。応用技術の前提となっている基本特許を押さえないと、国際競争に負けるという主張でその通りと思います。
一方、アメリカのハリウッド映画やデイズニーは、コンテンツを磨いた結果、アメリカの重要な輸出産業になっています。日本でも宮崎駿監督によるスタジオジブリの一連の作品は、日本国家のブランド価値を上げる結果となり、ゲームと並んで輸出産業となっています。つまり、コンテンツビジネスが成立しているのです。
コンテンツとは情報の中身のそのもののことで、映画や音楽、ゲームなどの娯楽から、教育、ビジネス、百科事典、書籍まで幅広いのですが、今までこれらは業界ごとにバラバラで対応していたものを、一つの産業として育成し「知的財産立国」になろうとするのが、2002年11月に制定されている「知的財産基本法」です。
基本を押さえる
「大人のぬりえ」が日本でブームとなっている。だが、世界のどこの国でも「大人のぬりえ」は存在していないし、ブームになっていない。だから、日本のブームを世界のブームに広げること、それはマンガやアニメーション、ゲームの事例から不可能ではなく、「大人のぬりえ」がコンテンツビジネスとして成り立つ可能性がある。
そのためには何が必要か。新聞記事レベルを脱したぬりえの世界実態把握と、ぬりえが持つコンテンツと脳の相関関係と脳細胞反応データ集積等、これらの「基本を押さえる」ことが知的財産への道ではないか。そのような想いを持っているところです。以上。
2006年10月21日
分かっているが捉えない
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年10月20日 分かっているが捉えない
景気拡大は「いざなぎ」を超える
2002年2月に始まった今の景気拡大が10月で57ヶ月となり、戦後最長のいざなぎ景気(1965-70年)を追い越すことは確実となりました。民間エコノミストの予測では7-9月期の実質成長率の予測平均は年率3.6%、10-12月期は2.6%と巡航速度で成長できると見ています。
いざなぎ景気の時は、いわゆる「3C」の時代でカラーテレビ、クーラー、自家用車の購入がブームとなり、今の中国並みの高度成長期でした。それに対し、今は少子高齢化で社会・経済が成熟する中での成長であり、物価がデフレであり、サラリーマンの賃金(名目雇用者報酬)も減ったことから、回復感に乏しいデータ上の景気回復にすぎないと言う人も多くいます。しかし、世界全体も年率で5%近い成長を遂げ、長らく停滞していたドイツも回復してきた実態から考えれば、日本の景気拡大も事実として受け止めなければならないと思います。ただし、景気拡大の実感はその人が所属している立場で異なりますから、その実感が人によって異なるのは当然です。
という意味は、今回の景気拡大の特徴、それは「大企業の製造業で、世界市場にリンクしているところは絶好調で、そこと取引のある関係企業と、そこが立地している都市が好調」なのです。日本国内だけの市場を相手にしているところは苦しいのです。つまり、ここ10年くらいの世界経済のグローバル化が、今回の景気拡大を招いたのですから、グローバル化にマッチしていない場合とでは、実感差があるのは当然です。
ナイヤガラの滝
ニューヨークの「ぬりえ展」参加の合間に、ナイヤガラの滝を見に行きました。ニューヨークからバファロー市まで飛行機、空港外に出ると気温は47度華氏、ということは摂氏では8度、体感温度はそれほど寒くは感じませんが、ガイドがもうすぐに観光シーズンは終わると言います。その通りで訪れた一週間後の12日に、35センチの初積雪があり、空港閉鎖と道路通行止めになりましたから、ナイヤガラはもう冬に入っているのです。
従って、観光シーズンは5月初旬から10月中旬までの6ヵ月だけとなりますが、その期間に世界中から1400万人が訪れます。日本に来る外国人は年間700万人ですから、半年で日本に来る倍の人たちがナイヤガラの滝を見に来るのです。
世界三大滝はナイヤガラ、イグアス、ビクトリアですが、とても70歳とは思えない若さの女性ガイドが、三大瀑布とはナイヤガラ、イグアス、それと最も長いのは徳川幕府だと言うジョークに笑いながら、長さ320m高さ56mのアメリカ滝と、長さ675m高さ54mのカナダ滝で構成されるナイヤガラの滝、これは世界中が認める普遍性存在と思いました。
という意味は、一分間に150万トンの水が流れ落ちる景観を、言葉も習慣も異なる多くの民族の人が見に来て、一様に「すごい」と感動させる価値を所有しているからです。立場や所属する条件が異なっているのに、つまり、考え方が違っている人たちが、普遍性として共通に認識できるもの、それがナイヤガラの滝です。
日本の人気
日経新聞10月2日の「核心」で論説主幹の岡部直明氏が「日本はソフトパワーが強みで、日本文化へのあこがれは世界に広がっている」と述べています。「フアッション、デザイン、映像・音楽ソフトなど洗練された文化産業が、日本の新たな戦略分野として位置づけられている」とも述べています。
今回のニューヨーク「ぬりえ展」は大成功でした。この状況はぬりえ美術館のホームページhttp://www.nurie.jp/で御覧いただければと思いますが、これも背景に日本文化への人気があってのことと思っています。
さて、ニューヨークにいる間は、地下鉄やタクシーも利用しましたが、基本は歩きでした。とにかくマンハッタンのアッパーからロウアーまで自分の足で歩きとおしました。
その中で一番驚いたことは、イースト・ビレッジの居酒屋でした。一つの通りに日本の居酒屋が英語でなく日本名で何軒も並んでいます。その一軒「ビレッジ横丁」に入って、その盛況なことにビックリしました。40分ほど待たされ、ようやくテーブルに案内されたほどです。メニューは日本の居酒屋と同じで、注文したのはおにぎり、ヤキトリ、キンピラゴボウ、おひたし、焼きそば、シシャモ、ポテトサラダ、菜の花のオイスター炒め、さつま揚げ、肉じゃが、ハマグリの塩焼き、湯豆腐、これに日本の瓶ビール三本、会計合計120ドル×119円で14,280円でした。五人ですから一人当たり2856円。お腹が一杯で全部は食べられず残しましたが、日本と同じくらいの価格と思います。
隣は日本人でない人、つまり、外国人の四人連れで熱燗三本がテーブルの上にあります。ニューヨークでは日本酒が大人気なのです。加えて、寿司人気も相変わらず続いていて、とうとうフレンチレストランにも寿司バーが設置され、そこで冷やした日本酒が好まれ、牡蠣やキャビアの店もすしバーと日本酒を取り入れ、ニューヨークのリトルリーグ代表選手、
10歳から12歳の子供選手、これに好きに食べ物は何かとアンケートしたら半分がトップに寿司と答え、結婚式でもギャラリーオープンパーティでも寿司が人気で、寿司から食べだしてなくなっていく。
さらに、街角のリカーショップのショーウインドーにも、日本各地の薦被り酒樽、その数20個余が所狭しと並び、一段と一目を惹きます。中に入ってレジにいる主人と思える日本人に訊ねると「日本人は相手にしない」という言葉。確かに9月末に開催された日本酒試飲イベント「ジョイ・オブ・サケ」は、一人75ドル(当日売り90ドル)にもかかわらず、午後六時から九時の開催時間内に一千人を超す入りで、質問し熱心にメモ取るアメリカ人の実態に「日本酒が大人気」ということが分かったと、ニューヨークの週刊日系新聞「よみタイム」が掲載しています。
分かっているが捉えない
この日本のソフトパワー、果たして世界の普遍性になり得るのでしょうか。考え方が違っている人たちでも、すべての人が共通して普遍性として評価するナイヤガラの滝のような存在になり得るのでしょうか。
今回のニューヨーク滞在中に多くの日本人と会いました。長くニューヨークに暮らしていて、ニューヨークに詳しいのでいろいろと教えてくれます。例えば「あそこのレストランはどこの経営だ」「あそこはこういうトラブルが最近発生した」等、アメリカのショーウインドーであるニューヨークの実態について、実に詳しく教えてくれます。お会いした長期滞在者の方々に共通している親切さです。
しかし、ふと気づいてみると、ニューヨークの現象について伝えてくれるのですが、このような実態になっていることについての背景分析は語ってはいない、という共通項があることが分かってきました。
こちらは昨年「ぬりえ文化」を出版し、今回の「ぬりえ展」も文化として主張する一貫として開催し、12月には「ぬりえの心理」を出版する立場ですから、相手が伝えてくれる中に文化的な視点からの分析が薄いことに気づきます。
そこで「どうしてアメリカで今の日本ブームが発生したのか」と、さりげなく尋ねてみると、一瞬ビックリしたような表情となって沈黙します。こちらの質問が意外だったのでしようか。それともそのような背景分析をしていないのでしょうか。
実はそうなのです。現実の現象を「分かっているが、背景要因を捉えていない」のです。アメリカ人が何故に日本文化へのあこがれ、それを取り入れようとしてブーム化しているのか。そのことについて「捉えていない」という実態が分かりました。
この「捉えていない」理由は簡単です。現在の日本文化ブームを分析し解説した文献が少ないからです。単発的で業種的に分析したものは多くありますが、同盟関係にある日本とアメリカの文化的な歴史背景から説き起こした本格的文献が少なく、それらに接していないので解説できないと判断いたしました。
アメリカで日本ブームは確認できる範囲で過去二回ありました。最初は明治9年(1876)のアメリカ独立百年祭万国博覧会での「日本館」の成功から日本ブームが起き、第二回目は戦後で、禅に代表されるシンプルで奥行き深い日本文化に気づいたブーム。この二回と今回のブームはどのような違いがあり、どこに同質性があるのか。そのことを捉え解明して妥当に世界に主張していかないと、日本文化ブームは過去二回と同じく、いつからか静かに自然埋没の流れに向って、すべての人が世界の普遍性として共通に認識できる文化にはなれないと思います。「分かっているが捉えない」ここから脱却が課題であると思います。以上。
2006年09月22日
2006年9月20日 新時代の競争とは
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年9月20日 新時代の競争とは
ピアノコンサート
近所のカトリック教会が経営している幼稚園を卒園し、現在、イタリア・フィレンツェ在住のピアニスト、五月女慧さんをお迎えし、町内自治会主催の教会内コンサートが開かれました。
幼児よりピアニストを目指し、この町に九歳まで住み、フランスで国立高等音楽院を卒業し、その後フィレンツェで研鑽を積み、イタリアを中心にしてヨーロッパ各地で活躍している五月女慧さん。幼い頃よく見かけた、見覚えのある皇太子妃雅子様似の笑顔が、一段と落ち着き、重厚さを加え、譜面なしで一気にショパンからバッハ、モーツアルトと弾いていきます。さすがに一流のプロは違うと感じ入りました。身体から音を生み出していると感じました。
曲の合間に幼稚園時代の思い出「幼い頃に通ったこの教会、多分、大きくなって見たら小さく感じられると思っていたが、今日久し振りに来て見て、昔のイメージ通りで大きく、また、園長先生のお話が長いとき、教会天井のモザイク模様の十字星印を数えていたが、覚えていた数どおりであることを確認でき、懐かしさで感動した」と語りました。
一般的には、幼いときの印象を大人になって確認してみると、大きく異なることが多いのですが、五月女慧さんは幼いときの観察と、今回、改めて確認した内容が同じであったということ、つまり、大人になってから感じる感覚を幼児時に既に持っていたのです。
ハンマー投げの室伏選手
今年になって世界の各大会で負け知らずで、優勝が続いているハンマー投げの室伏選手が次のように語っています。「ハンマー投げはフォームで覚えるものじゃなく感覚です。感覚はつねに新しくしていかないと先がありません。結果が出たときのフォームを守る発想はハンマー投げにはないですね」と。
一般的に、多くの人は、仕事ということを決められたルール、定められた手順でするものと理解し、実行しているのではないでしょうか。マクドナルドの応対手順のようにある一定の社内基準があって、それに基づいて眼の前の仕事をこなしていく。これを仕事と思っているのではないでしょうか。
これも確かに仕事をしているということに当てはまりますし、そうすべき業務も多いと思います。しかし、このような仕事の癖をつけると、何かトラブルが発生したとき、その問題解決に当たっても、決められたルールがないかと、それらを求めていくことになりやすいと思います。手順、ルールというものは過去に発生し、過去に処理してうまく行ったものを整理したもので作成されている事例が多く、そのマニュアルどおり動くことが仕事であると思い込んでいます。また、このような姿勢で仕事するのは、大きな変化のない時代では、的確で妥当な仕事振りとして評価されたと思います。
ところが、時代はバブル崩壊があって、もはやバブル崩壊後と言えない新展開の時代環境になってきています。バブル以前とも、バブル崩壊以後と異なる時代環境になっているのです。つまり、今までの経験やルールでは適応できなくなるケースが多くなっているのです。過去の成功体験、問題体験から作り上げた手順・ルールというものが、現実に合わなくなっているのです。
とすると、今の時代と環境に合致させた手順・ルール、それを作り直さなければならないと考えるか。いや違う。新しい時代は未知の実態に踏み込むのだから、自らの感覚を磨いて、どのような事態にも対処できるようにしておくことで対応すべきか。
これに対する答えが冒頭の室伏選手の発言であると思います。即ち、感覚を磨いておくことが、新しい時代への仕事対応力であると、室伏選手は主張しているのです。
小泉政権を引き継ぐ安倍政権
今日20日、第二十一代自民党総裁に安倍晋三氏が選ばれました。安倍政権誕生です。安倍氏は小泉首相の改革路線を継承すると言明しています。ということは小泉政権が何を目指していたのか、ということを一度振り返ってみることが必要と思います。
2001年5月7日の小泉首相初の所信表明演説では、次の三つを述べました。
1. 不良債権最終処理、2.財政構造改革、3.競争的な経済システム整備でした。
このうち「不良債権最終処理」はメドがつき、「財政構造改革」は2006年の骨太方針で、2011年度でプライマリーバランスを採ると決定され、その方策として歳出のカット額配分も決められました。
そうすると三つ目の「競争的な経済システム整備」、つまり、「21世紀にふさわしい競争政策の確立」に重点配分され、そこへ主役が今後移っていくことになると思います。
その視点から最近の動きを見てみると、西武鉄道やライブドアによる証券取引法違反摘発事件、鋼鉄製橋梁工事や防衛施設庁工事をめぐる入札談合事件、水谷建設事件と村上ファンド問題、いずれも競争や透明性を追及する一連の流れが目につきます。
先日、アメリカからやってきて、日本で長いこと企業経営をしている社長が述懐していましたが、アメリカより日本のほうが順法精神で劣るというのです。新しい企業が既存業界に参入しようとすると、何々業界組合という存在が出てきて、日本は「和の国」だから仲良くやろう、そこで工事受注も皆が順番に受けられるようにしたい。つまり、談合に参加するようにと堂々と説明に来るのだそうです。アメリカではとても考えられない日本が持っている当たり前の商習慣だそうです。
つまり、既存組織が持つ利益、それを守って維持して生きていこうとする傾向、それが日本では強いのだ、ということを厳しく指摘していました。
競争という意味の理解
前号のレターで小林慶一郎氏(独立行政法人経済産業研究所)の見解「構造改革の継承とは、市場経済システムとは豊かさを得るための手段として考えるのでなく、政治が目指すべき目的と考えることである。小泉首相はおそらく戦後史上初めて、市場経済システムそのものを政治が目指すべき目的価値であると暗黙に宣言した首相だった」とご紹介しました。この市場経済システムを健全に安定させることが政治目的ならば、それは自由な競争が前提となります。自由を制限することは、市場経済ではなく、管理された市場経済となり、そこには競争原理が働かなくなります。競争が自由に行われる社会、それがあって健全な市場経済システムが成り立つのです。
では、ここでいう競争という意味とは何でしょうか。オリンピックの100メートル競走やマラソンのように、特別に鍛え上げた優れた身体を持った人間間の競争なのでしょうか。いやそうではなく、今の時代の競争とは「違いを創る」ことなのだと、東大教授の
岩井克人氏が次のように述べています。(日経新聞 経済教室 2005.8.29)
「かつての産業資本主義時代においては、農村に過剰な人口が存在したので、会社は都会に大量に流失してくる人々をいくらでも安い賃金で雇えたから、製造コストは低く抑えられ利益が上がった。しかし、20世紀の後半、先進資本主義国に異変が起こり、農村からの人口流出が止まり、都会で働く労働者の賃金があれよあれよと上がり始め、その結果、収入と費用の差が縮まり、かつての産業資本主義は終焉し、ポスト産業資本主義となった」
では、ポスト産業資本主義の現在はどうすれば利益が得られるか。岩井教授は続けます。
「利潤とは収入と費用の違いである。他社と同じ製品しか作れないなら、異なった技術を導入して費用を下げなければならない。他社と同じ技術しか使えなければ、異なった製品を作って収入を高めなければならない」と、更に続けて「会社は横並びの大量生産を止め、違いを意識的に創っていかなければ利潤を生むことが出来ない。カネ持ちであることは、違いを他より早く生み出すことの結果でしかない」と結論づけしています。
当たり前のことを説明しているようですが、ここが重要なポイントなのです。違いを創るためにはどうするか。それは「ヒト」の能力や知識を利潤の源泉にせざるを得なくなっているという事実を指摘しているのです。脳細胞からしか利益は生じないという意味です。
美しい国へ
安倍新自民党総裁の著書「美しい国へ」に「既得権益を持つ者が得するのでなく、フェアな競争がおこなわれ、それが正当に評価される社会」にするのが構造改革であると記されています。これは小泉首相初の所信表明演説の三点目「競争的な経済システム整備」を継承する宣言であり、競争とは岩井教授の「違いを創る」ことを意味し、そのためには
五月女慧さんと室伏選手が示した自らの時代感覚を磨くことが前提要件と思います。以上。
(10月5日レターは、ニューヨークぬりえ展参加のため休刊となります)
2006年09月05日
2006年9月5日 小泉政権後の改革時流
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年9月5日 小泉政権後の改革時流
新しい時流
日本は明治維新と第二次世界大戦によって大混乱を経験すると同時に、その前後でガラッと思想が変わりました。江戸時代の東洋思想が明治以降は西洋思想に変わり、第二次世界大戦までの軍国主義が戦後は民主主義に変わりました。
今の時代もこれと同じような思想変化をしていると思います。新しい時代が来ていることを分かっている人には、新しい思想が分かっている。だが、新しい時代が来ていることを認識していない人には、新しい時代思想が分からない。という思想格差が発生しています。何を想い、何を大事にするか。時流を見誤ってはいけないと思います。
ペルーへ新婚旅行
水道局から連絡があり、先日、水道メーター前後に使用されている鉛給水管を、ステンレス管に取り替える工事が行われました。朝一番の工事で、興味があったので工事を見学していたら、女性の現場監督が来て、工事担当者と雑談している中で、この女性が近々結婚するらしく、新婚旅行にペルーへ行くということが分かりました。
ペルーに新婚旅行として行く理由は「このチャンスでないと今後行けないから」というものでした。ペルーは遠く、簡単には行けないので、新婚旅行という一大セレモニーの際に思い切っていく、という意味です。
そこで、ペルーに行ったことのある体験者として、ペルー旅行の懸念事項を話しました。一つはナスカの地上絵を見るためのセスナ機は、急旋回するので大体の人が飛行機酔いをすること。もう一つは高度3000メートル以上の高地に一挙に行くので、多くの人が高山病になること。特に高山病になると、ひどい風邪を引いた状態と同じく、食事は出来ず、下痢が激しく、歩くのもつらく、観光バスの中に座ったままでツアー行程を過ごすだけ、という最悪の状況で楽しい新婚気分は吹っ飛ぶことになってしまう。
この間、女性現場監督の目と顔が徐々に変わっていき、工事中なのにその場からいなくなりました。多分、婚約者に電話するために消えたと推測しました。
ぬりえの心理
この夏は、暑い日が続く中、早朝と午前中の机に向かい「ぬりえの心理」を書き上げました。昨年出版した「ぬりえ文化」は「入門ガイド編」、今回の「ぬりえの心理」は「中級編」の位置づけとし、ぬりえに関係する各立場、子ども、親、出版社、販売者、ぬりえブックなどの立場から読みやすいエッセー風に心理分析を行いました。書き方は擬人化法を採り入れ、各章ごとに解説としてのコラムも入れ、英文にして世界にも発信するので、内容は日本だけにとらわれず、世界各地の実態から編集構成しました。
この「ぬりえの心理」を書くため、多くの心理学の研究専門書を読みました。その結果、明確に分かったことがあります。それは、人間とは潜在意識が行動を決めていくということです。大人になった人間が示す好き嫌い、わがまま、頑固さ、柔らかさなどの個人的性格は、幼少期に形成され、それが潜在意識として脳の奥底に刻み込まれていて、顕在意識が働いていないとき、つまり、無意識下のときは潜在意識によって行動していることが分かりました。
また、大人であることの特徴は「幼少期時代を忘れる」こととも分かりました。すべての人が幼少期時代を過ごしてきたのに、すべての人が幼少期時代を忘れています。忘れることが大人になる第一歩なのです。だから大人になって幼少期時代の心理を思い出そうとしても、特別で特殊なこと以外は浮かんでこないのです。つまり、自分が幼少期時代に、どのような心理で日常過ごしてきたかということ、それを大人は忘れて行動しているのです。
しかし、今生きていている行動の原点に、幼少期の体験が存在しているということは事実ですから、幼少期にどのような教育と環境で育てられたかが、大人の行動を決めている重要なファクターなのです。親の育て方が、子どもの将来の生き方適否妥当性、それに大きく影響させています。幼少期は遊びが人生ですから、親が与える遊び玩具に影響を受けます。その遊び一つとしてのぬりえが位置づけられます。高がぬりえですが、されどぬりえです。
小泉首相
小泉首相が今月で任期を終えます。政権末期でありながら「指導力がある」と支持する人が41%(直近日経新聞社調査)という実態です。
この小泉首相五年半の政治について、このところ各立場から分析し論評することが多く行われています。小泉首相は自らの政治行動を多弁に解説調で語ることは少なく、加えて、言葉のセンテンスが短いので、論評しようとする識者が取る方法は、小泉首相を観察するしかありません。小泉首相の行動結果を観察し、観察した後に小泉さんは「このような考え」ではないかと推測することになります。小泉首相も人間ですから、すべての人と同じように幼少期時代に潜在意識が形成されています。顕在意識で行動していないときは、無意識下の行動になりますから、潜在意識が表面化するのは当然です。
特に人が追い詰められ、危機に陥ったときは、その人の潜在意識が如実に出ます。小泉首相の最大の危機は郵政民営化が参議院で否決されたときでした。そのとき採った行動は「郵政解散」でした。解散という首相としての最高権限の行使、様々な異論が噴出しましたが決断しました。それを論理的に考察して採った行動と見るか、潜在意識が大きく影響して決断したと考えるか、それは意見が分かれるところですが、一般的には小泉首相の蛮勇とも言われているほどですから、通常の感覚ではなしえない政治行動だったのでしょう。ということは小泉首相が持つ人間としての基礎力、理屈でなく感性とも言える本音の人間力、そこから決断した結果と思いますが、これは潜在意識が影響したと考えたいと思います。
小泉政治の改革目的
バブル崩壊の始まりである地価の下落は15年前。1991年は土地神話が崩れた年でした。それから長いこと日本経済は低迷に喘ぎ、日本は終わりの時代を迎えたとも、衰亡化への足音が迫ってきたとも、某国のトップからは「日本はなくなる」とも発言され、悔しい思いをしたこともありましたが、今は、政府の月例経済報告で「デフレ」という表現が削除され、企業業績もバブル期を超え、銀行の不良債権の処理も進み、雇用も改善に向かい、税収も増加し、全国の公示地価が取引価格を加味した加重平均で15年ぶりに上昇に転じました。
日本経済は「もはやバブル後でない」言え、この状況をつくり出したのは小泉首相のリーダーシップであると、素直に評価すべきと思います。しかし、一方で、格差の拡大や不均衡問題を指摘する声、つまり、構造改革路線の修正を求める意見も大きくあります。
小泉首相は次の首相に「構造改革の継承」を条件として求めています。この「構造改革の継承」とは何を意味するのか。それについて小林慶一郎氏(独立行政法人経済産業研究所)の見解をご紹介したいと思います。
「結論を述べれば構造改革の継承とは、市場経済システムとは豊かさを得るための手段として考えるのでなく、政治が目指すべき目的と考えることである。小泉首相はおそらく戦後史上初めて、市場経済システムそのものを政治が目指すべき目的価値であると暗黙に宣言した首相だった。この立場に立てば、市場経済システムをよりよきものにすることに目的があるのであって、そのために解決しなければならない問題が格差の拡大や不均衡であると捉える必要がある。
多くの政治家は、市場経済システムを単に国を豊かにするため、つまり、カネもうけのための手段と考えている。小泉首相の改革なくして成長なし、というスローガンは経済成長という豊かさよりも、市場経済システムを健全に安定させるということを優先させる姿勢を示している。この姿勢は自由主義をお題目でなく、実質を伴う政治理念として真剣に追求することであり、そのところに歴代政権にない熱烈な支持を国民から受けたのだ」
見事な小泉首相への観察力と敬服します。小泉首相の脳細胞の奥底に、市場経済システムを健全に安定させるためには自由主義でなければならないという強い意識、これは潜在意識とも言うべき分野からの発想と考えますが、それを小林慶一郎氏は見抜き、国民も暗黙に理解し、その結果が「指導力がある」と41%が支持している背景と思います。
目的と手段
ペルーに行くのは目的か手段か。楽しい新婚旅行が目的ならばペルーは条件的に無理があります。小泉首相の改革を継承する次の首相が登場する目的は何か。市場経済システムを健全に安定させるということ、これを手段としてではなく、目的として次期首相も継承すると受け止めるならば、構造改革目的は変化しないという時流を理解する必要があります。以上。
2006年08月21日
2006年8月20日 基礎前提力
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年8月20日 基礎前提力
最近身近で感じたこと
最近、経験したことがあります。それは「同じチーム内で、同じ情報によって、同じタイミングで、同じ事件に接したのに、結果への見解が全く異なる」という経験です。
緊密なチームワークで、情報の共有化も図っていたのに、結果への判断が全く異なっていたのです。数人のチームですから、日頃から頻繁に接し、コミュニケーションも問題なく行えていたのに、結果への評価が全く異なったということ、これはどういう意味を持っているのだろうか、ということに強い疑問をもちました。
経団連・御手洗会長の日本経済イノベート計画
キャノン会長の御手洗冨士夫氏が経団連の会長に就任しました。その機会に「日本経済イノベート計画」提言を月刊文芸春秋八月号に掲載しました。詳しい内容は文芸春秋を見ていただくとして、その中で強調しているのは「基礎的研究開発の充実」です。
日本は世界でもっとも特許の出願数が多い国であるにもかかわらず、そのほとんどが「応用、派生技術」による特許だと言い、それに対しアメリカは「基本特許」が強く、応用特許では、すでに開発された基本特許をどう使うかという視点で研究されるため、リスクは少ないが、たとえ特許が成立しても、基本特許の使用許可を得て、ライセンス料を支払わなければならない現状になっている。だから「基礎的研究開発の充実」が必要であると強調しているのです。その通りと思います。
基礎前提力
経団連・御手洗会長の提言を、人間に当てはめて考えたらどうなるのでしょうか。
人間にとっての「基礎的研究開発の充実」とは、二つの分野に分かれるのではないかと思っています。「基礎前提力」と「基礎研究力」です。
まず、「基礎前提力」は三つの要素から構成されると思います。
その第一は個人の考え方の問題です。いつも「考え方をフレキシブル」に出来るかということです。誰でもそうですが、ある程度の年齢に至ると「考え方を変える」ことが難しくなります。歳を取れば取るほど難しくなりますので、そのことを理解して自らが「考え方をフレキシブル」にする努力を行っていくという姿勢が大事です。そのことを別の言い方にしますと「戦略・目的」分野と「戦術・対策」展開を、区別し行動できるかということになります。「戦術・対策」にこだわり執着し、「戦略・目的」を軽んじ蔑ろにする思考は「考え方をフレキシブル」に出来ない人物の特徴です。「考え方をフレキシブル」にすることが基礎前提力の第一です。
次はチームワークという問題です。チームワークをどのように組めるのかという視点です。一人の力は限界があります。他の人との組み合わせによって新しいことへの挑戦が可能になっていくのです。ですから、まず大事なのはチームメンバーとの円滑な連携・協力です。いわゆるホウレンソウ(報告・連絡・相談)を通してのコミュニケーションが程よく、適宜、適切に出来るかです。これは古くから言い伝えられていることで、日本人がもっとも大事にすることです。このホウレンソウが基礎前提力の第二です。
三つ目はグローバル化の中での改善項目です。日本人の特徴からの問題です。日本人は世界の人々との比較で、どのようなところに特徴があるのか。逆に言えば弱点を知った上で、それを補う訓練を自らに植え付けるという視点です。日本人の弱点は先般のワールドサッカーで見事に示されました。得点能力が低いのです。シュートがゴールに結びつかないのです。パス回しが多すぎるのです。ゴールを取るタイミング決断力が弱いのです。判断力はあっても、その判断から決断への結びつけが弱いから「判断はできても決断が出来ない」傾向が強い国民性です。それを知った上で自分自身をつくりあげていこうとすることが、世界と仕事するためには必要で、これが基礎前提力の第三です。
この「基礎前提力」が不十分の場合、どのように努力しても、途中か最後あたりで、この三つの不十分さが顕在化することになり、結果的に人間力の弱さとなって物事が達成できないという結果になり易いのです。これは人間としての基本的な部分の鍛えで、その意味で経団連・御手洗会長が提言した「基礎的研究開発の充実」の「基本特許」分野に当たるのではないかと思っています。人間の基礎前提がガッチリと構成できていない人は、結果的に達成度が低いということになりやすいと思います。
基礎研究力
人間にとっての「基礎的研究開発の充実」のもう一つは「未来への基礎研究力」です。
あるテーマ、ある事件、ある問題、それに向かい解決したいときに、その対象に対して行動するための推進する基礎研究力です。
テーマや問題の性格を分析整理し、どの方向に持っていくことが妥当な解決策となるか、つまり、未来に生ずる解決への方向性を定めることと、それを推進する行動力です。
これはテーマと問題によって、それへの対処が常に異なります。ですから、テーマと問題によっての応用、派生技術が問われます。その意味で、これは経団連・御手洗会長の提言で言う「応用、派生技術」に当たると思っています。テーマと問題について妥当なステップを踏んで行動していけるかどうかです。
例えばテーマでしたら「創造と開発」のステップ、問題解決で言えば「異常、不良、損失、困惑、悩みの解決」のステップですが、この推進には昔から常に変わらないセオリーが存在しています。そのステップセオリー通り努力し一生懸命に進めていくと、突発的大事件が発生しない限り、時間の経過とともに良好な状態になっていき、解決に結びついて行くことが多いのです。これは今まで多くの「創造と開発」事例と、「問題解決」事例を経験したことから断言できます。
ですから、この「未来への基礎研究力」としての「応用、派生技術」は「ある条件」さえ整っていれば、成功の道に向います。多くの成功事例はこのステップセオリーを踏んでいるからこそ成功しているのです。
実態を知る
では、成功に向うための「ある条件」とは何か。それは実態を知るということです。
当たり前だと考えられるでしょうが、この実態を知るということが、自分の「実際知識」になっていないと役立たない場合が多いのです。
俳優の児玉清氏が日経新聞のコラム(2006.7.28)で述べています。
「猛暑の中でのオリンピックとなったアテネを実際に訪ねたときに痛感したことであった。テレビ観戦していた人たちに、帰国後、いかにもの凄い炎暑であったか、女子マラソンの日など煮え滾るほどの暑さであっことを僕がいくら訴えてもわかってもらえなかったのだ。テレビの画面だけを見て、恰もすべてがわかったと思ってはならない。実際にそこに行かなければ本当のことはわからない、ということを肝に銘じたのはこのときであった」と。
テレビ画面は奇麗事になるきらいがあり、見てわかったつもりの観光ガイドブック的な知識になりやすいのです。そうではなく実務として役立てようとしたら、体験知識にしておかないと「未来への基礎研究力」としての「応用、派生技術」に発揮できないと思います。多方面の異種・異質の領域について直接体験することがベターで、その積み重ねが「創造と開発」と「問題解決」のステップセオリーに重なって効果を発揮させていくのです。
最近の事例で検証できたこと
最初に申し上げた「同じチーム内で、同じ情報によって、同じタイミングで、同じ事件に接したのに、結果への見解が全く異なる」という経験から、どうしてそうなったのかという疑問。その答えは「基礎前提力」にあったのではないかと思っています。
いくら同じチーム内に所属していても、別人格で、生れも育ちも異なるのですから、同じ考えではありません。その上に「基礎前提力」への理解レベルが異なっているとしたら、いくら「創造と開発」と、「問題解決」へのステップセオリーを踏もうとしても、また、現場の実態把握がお互いに出来ていたとしても、スタートする最初のところで齟齬がありますから、次のステップに入れないということになります。
経団連・御手洗会長提言の「日本経済イノベート計画」で触れている「基礎的研究開発の充実」は、人間行動に関して大変示唆に富んだ指摘であると痛感しています。以上。
2006年07月22日
2006年7月20日 一身にして二生を経る
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年7月20日 一身にして二生を経る
一身にして二生を経る
「一身にして二生を経る」、福沢諭吉の言葉である。明治維新という激変の中で、自分の体験を二つの人生を経たようなものとして語った言葉です。
徳川幕府時代は下級武士として、緒方洪庵の適塾で蘭学を学び、蘭学塾を江戸で開き、蘭学が時代の中で役立たないことを見抜き英学に転じ、咸臨丸で渡米し、幕府の外交文書翻訳係りとなり、幕府の外交使節に随行し、仏、英、蘭、プロシャ、露、ポルトガルの諸国を回り、慶応2年(1866)に「西洋事情」を著し、翌年には幕府の軍艦受取に一行に加わり渡米、慶応4年(1868)明治維新の年に慶応義塾を創設した。これが生れてから33年間の江戸時代の福沢です。
明治以後は、ご存知の通り教育と「学問のすすめ」等の著作を中心に多彩な啓蒙活動を展開し、時代のヒーローとして活躍しました。その期間も33年間です。
ちょんまげ時代と断髪時代を半々に生き、福沢はよいタイミングに生れたと、亡くなるときに感じたと思います。もう20年早く生れていたら、当時の稀なる海外渡航要員に選ばれず、また、度重ねる渡航をしていなければ「西洋事情」も書けなかったはずです。逆に20年遅れて生れていたら、明治維新時には少年期で、活躍は出来ず、時代の大転換に身を以って体得することは出来なかったのです。福沢は幸運だったと思います。
長寿にして二生を経る
今は福沢の生きた時代と、寿命が大きく異なる条件となっています。福沢は66歳で亡くなりましたが、今は平均80歳を超え、百歳の人も大勢いる長寿の時代です。
日本人の多くはサラリーマンで、その定年は60歳。「改正高齢者雇用安定法」が4月1日に施行され、①定年制の撤廃、②定年年齢の65歳までの引き上げ、③定年後65歳までの継続雇用、この三つの選択肢が各企業で検討されているものの、大勢は60歳で勤め人から離れることが実態です。
ということは、定年後の生活が長期間になるということで、定年前とその後の二つの「生」を生き抜くことが必然となりました。時代の変化とは無関係に、多くの人は自分の人生を二つの「生」で生きなければならないという宿命にあります。福沢は時代の大変革によって、現代のサラリーマンは宿命によって、「一身にして二生を経る」を得ました。その背景条件は異なりますが、結果は福沢と我々は同じ環境になっているのです。
生き方基準
我々が長寿という宿命によって「一身にして二生を経る」を得たわけですが、では、この環境下で、どのような生き方が求められるでしょうか。生きる基準を、どのように持つべきかということです。
基準の一つとして考えられるのは「過去基準」です。サラリーマン時代との比較からこれからの自分の生き方を決めていく、つまり、いつも過去の生き方を参考にし、過去の延長で未来を考えていくという生き方です。
第二の基準として考えられるのは「業界基準」です。同じ勤め人時代を過ごした仲間との関わりを大事にしていく、つまり、同じような環境の人の生き方を参考に、自分の生き方を構築していくものです。
もう一つ考えられるのは「可能性基準」です。つまり、自らが宿命として得た二生の後半を、自らの中に隠れている可能性を探っていく生き方です。
どの生き方を採るかはその人の人生観で決めるもので、その結果の善し悪しは、その人が亡くなるときに、自分がどう一生の感慨を述べたかで明らかになります。
二生を経ることの前提構造
長寿によって獲得した「二生を経る」という期間、その定年後に生きる期間は、それまでの時間と構造的に異なっていることを理解しなければなりません。今までの経験が役立たない、未知の分野に入っていくことになるのです。
子ども時代の明日は必ず体の成長が約束され、体が育成されていく時代でした。大人になって過ごした壮年時代は、成長は止まりましたが、安定した体が充実した仕事をさせてくれました。過去の成長線上に自らの体が存在していました。
しかし、定年後に迎える長い期間は、体は成長せずに、返って肉体の構造上衰えていく期間に当たります。死という運命の終着点に向っていくという、やむをえない実態が続くのです。
だが、多くの人はその事実を理解せずにいて、何かの怪我や病気、事故が発生したときに、はじめて自らの体の衰え変化に気づき、その時に、過去とは体の構造が異なっている、今まで同じ生き方では難しくなっている、とはじめて理解することになります。
成長から安定へ、安定から衰え、弱化していく、その折り返し点が明確ではなく、加えて、一人一人の状況が異なる、つまり、同年齢でも健康個性がそれぞれ違っているので、同年齢の人の事例もあまり参考にならない、という実態にもなってくるのです。
ということは、生き方基準として申し上げた過去基準は、過去とは異なった体構造に向っているのですから、定年後の二生には適応しにくい、また、周りの人を参考にする業界基準も、一人一人の健康個性が異なっているので、難しいということになります。
結局、消去法によって第三の「可能性基準」が浮かび上がってきますが、これについては日本人特有の大きな一つの特徴を投げかけたいと思います。
変身ロマン願望
日本人が好きな歴史上の人物は1位が織田信長で、2位は坂本竜馬で、ここ数年変わっていません。特に坂本竜馬は司馬遼太郎の小説「竜馬がゆく」によって、若い女性の支持を多く受けています。竜馬は天保6年(1836)生れですから、山岡鉄舟と同じ歳で、清河八郎が結成した尊皇攘夷党の仲間です。同じメンバーとして政治活動をしたわけですが、鉄舟と竜馬の人気度は月とすっぽんです。格段の差があります。
司馬遼太郎の「竜馬がゆく」三巻で、竜馬が勝海舟を暗殺しようと赤坂の海舟邸に行き、返って海舟の弟子になってしまう情景が書かれています。海舟が地球儀を回して大英帝国の繁栄振りを説明し、日本と同じ海に囲まれた狭い国土なのに、海洋国家として外国との商売で利益を上げている。日本も開国し、航海貿易をし、製鉄所をつくり、軍艦を建造する等の日本興国論を滔滔と海舟が展開した時に、突如、竜馬が「勝先生、わしを弟子にして仕ァされ」と大きな体を平伏させた、とあります。暗殺にいったはずが弟子入りしてしまったのです。この場面、惚れ惚れするほど見事な文章展開です。感動します。竜馬が日本国に役立つ人物になったのは、海舟に出会い、海舟から指導教育を受けたときからスタートしたのですが、その場面情景をロマン溢れた文体で司馬遼太郎が描いているのです。
それまでの竜馬は剣術使いでした。それがこの時を期して日本を変える人物に変身したのです。一介の剣術使いがある時を期して質的変身を遂げる。この変身ロマン願望が多くの人に潜在意識としてあるからこそ、竜馬は人気があるのです。
可能性基準は地道な努力しかない
竜馬は脱藩して江戸で剣術修行に入った人物です。それがある時突然、剣を捨て変身し、亀山社中をつくり、薩長同盟を成し遂げ、明治新政府構想の船中八策を起案するのです。しかし、本当にそのような大変身が可能なのか。
それはありえないことだ、と疑問を投げかけるのは歴史作家の加来耕三氏です。本当は、子ども時代から秀才で、佐久間象山に学び、西洋事情に明るかったからこそ、海舟の内容を納得できたのだ。これが真実だと言い切ります。この見解に納得したいと思います。元々世界の事情に詳しかったからこそ、海舟の内容を納得したのです。地道に勉強努力をしていたのです。「竜馬がゆく」は小説です。過去を隔絶させる変身ロマンが必要だったのです。ここが大事なところです。
人間には変身はありえないという事実に立ち、日本人に宿命として与えられた「二生を経る」への生き方対応は、可能性基準によって生きることが望ましく、また、そのための前提は、地道なことに情熱を傾けて取り組むという平凡さ、それがその人に結果として質の高い非凡な生き方を与えてくれるという、事実に戻りたいと思います。以上。
(8月5日のレターは海外出張のため休刊となります)
2006年07月07日
伝統文化を再認識する
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年7月5日 伝統文化を再認識する
ワールドサッカー
7月5日はワールドサッカーの準決勝でした。準決勝に進出したのはすべてヨーロッパの国。アジア地区の国はすべて敗退し、日本は一勝も出来ずに終わりました。予選を通過できると思っていた日本人にとっては残念でしたが、ロンドンのブックストア(公認掛け屋)の事前見込みが当たりました。
この結果は、サッカーが行われてきた過去の歴史、それが今回の準決勝国を決めたのではないでしょうか。日本は体力とか戦術面等、問題点がいろいろ論議されていますが、結果的にはサッカーというスポーツを続けてきた長い伝統力の差、それが発揮されたと考えた方がよいと思います。ですから、これからもこの較差を埋めることは相当苦しいと覚悟した方がよいし、その前提の上で日本人らしさを追求したサッカーが求められると思います。
カナダ人の温泉文化
カナダのバンクーバーから内陸に向かって約500km、カナディアン・ロッキー南部のバンフ国立公園からも約500km南西に入った中間点で、アメリカとの国境近くに一軒の温泉ホテルがあります。アインワース温泉です。洞窟風呂として著名ですが、山奥ですから遠く、飛行機と車でバンクーバーから一日かかります。
ホテルのオーナーは70歳代の夫婦、とても親切にいろいろ案内してくれます。まず、最初に連れて行ってくれたところは源泉湧水場所、洞窟風呂のすぐ上の道路端、四角い箱で覆ってあって、湯量は一日7万ガロン。リットル換算で26万リットル。湯量は豊富です。湧水温度は48.9度。この湯温では熱すぎるので洞窟風呂では42度に下げています。しかしながら、ヨーロッパでは大体25度が標準ですから、同じ白人系ですので日本並みの温度では、熱過ぎるので訊ねてみました。
答えは「今までずっと長い間経営してきて文句も出ないし、皆さん喜んで入っているから大丈夫だ」といいます。そこで、実際に42度の洞窟風呂に入っていき、一緒に入っている人たちを見回すと、真っ赤な顔してはいますが、文句を言う顔つきでなく楽しんでいる様子です。ただし、入り口の岩盤注意パネルに「10分から15分までがマキシマム」と書いてあります。この実態を確認してホッとしました。
それは、ヨーロッパの温泉との比較から、日本の温泉に欧米人を迎えるための大きな問題は、温泉温度にあると今まで考えていたのです。日本の温泉は熱すぎるので欧米人には難しいのではないかと思っていたのです。だが、このアインワースでは実際に42度の温泉に入っているわけで、温度は問題ないことになります。これは大きい体験でした。今まで日本の温泉が、欧米人を迎え入れるために湯の温度調整工夫が必要だろうと、それについて悩んでいたわけですが、カナダのアインワースでホッとしました。世界は歩いてみるものだと改めて思った次第です。
ところで、この温泉は皮膚によい効果を与えるらしく、ニキビが3日間で治った事例や、リューマチにも効果があるとオーナーは力説します。日頃温泉利用者と接しているので、治った事例はたくさん知っているのです。
しかし、妙なことにパンフレットを含め、何の病気に効くとはどこにも書いていないのです。発表していないわけです。ここがヨーロッパ大きく異なるところですので、その点をオーナーに訊ねてみると「治ると言って、治らなかったら、すぐに訴えられる」から書かないと言います。なるほど、アメリカ型社会では効果・効用は表現できないのかと納得しました。社会の原点にある文化が異なるのです。何でも訴える訴訟社会が背景にあるので、温泉も効果・効用はいえません。
ということは温泉に来る人々は、何を期待してくるのかということになります。ヨーロッパは身体の治療目的で温泉に行きます。日本では温泉宿が提供してくれる極上のサービスや、癒し感覚の素晴らしい「おもてなし」が期待できます。また、ここでは日本のような宴会が出来ません。カナダの奥深い山の中の一軒家ホテルですから、周りには山と川というカナダの大自然しかありません。
アインワース温泉では、洞窟風呂とプール風呂に入って、ただ向こうに見える山並みを眺めるだけです。身体を洗うこともしませんし、してはいけないルールです。源泉掛け流しで、レジオネラ菌の心配はない環境ですが、日本人が温泉に求める「おもてなし」は皆無です。
いくらカナダの豪快な自然の山並みでも、半日も見ていれば見飽きます。しかし、多くの人々が訪ねてきて、真っ赤な顔して洞窟風呂に入り、プール風呂で静かに首だけ水面に出して、川向こうの山並みを眺めています。それがここの入浴方法なのです。日本とは明らかに楽しみ方が違っています。温泉にジッと入っているだけが温泉の楽しみ方なのです。温泉文化が異なっていると思います。日本ともヨーロッパとも異なる温泉利用があることを、カナダのアインワース温泉で理解しました。
マッサージ設備に見るカナダ文化
オーナーから協力依頼されたことがあります。それはこのホテルのマッサージを受けてほしいということです。「笑う温泉・泣く温泉」をオーナーに進呈し、中味を少し解説したところ、ヨーロッパ各地の温泉でのマッサージと、ここの内容を比較し評価してほしいという要望なのです。
そこで、マッサージを担当する女性、いかにもスポーツで鍛え上げた感じのする中年女性から、マッサージを受けましたが、問題はなく受けた感触も悪くありません。顔からのどまで品よくマッサージしてくれます。なかなか繊細です。カナダの山奥だからマッサージもいい加減なものだと予測していましたが、全く異なりました。
そのことをオーナーに報告すると大変喜んでいましたが、一つだけ大問題があるとも伝えました。それは設備状態です。マッサージというのは気分をほぐすものでもあり、リラックスするために手当てしてもらうものでもありますから、マッサージを施術する場の雰囲気が大事なのです。
ですから、ヨーロッパではマッサージ室はセンスよく上品感覚で作られているのがあたりまえなのですが、ここは悪く言えば物置の一角という場所なのです。その酷い環境の部屋にベッドが一つ置かれてあるだけで、施術中は一応癒し系の静かな音楽テープをかけますが、設備状態は最悪です。そのことはオーナーも十分知っていて、いずれ解決したいと言っていましたが、こういうところが雑なのです。それがカナダの文化かとも思った次第ですが、マッサージからもそこの国の文化が分かります。
国の印象は文化から
オーナー夫婦と一緒のテーブルで朝食をとっていたときです。何気なく日本についての印象をオーナーに聞いてみました。すると「人がいっぱい」という一言のみです。それ以外は思い浮かばないと言います。これにはこちらが絶句しました。
日本が世界に評価されているのは「伝統文化であり」「アニメ・マンガに代表されるポップカルチャーであり」「非軍事対外協力である」と、こちらは理解していますので、オーナーからの一言にはビックリしました。
そこにちょうど会計係りがデータを持って登場しました。このアインワース温泉の利用者数とか、売上金額などを教えてくれとオーナーにお願いしましたら、それは会計係りの担当だからといい、朝食のテーブルに呼んでくれたのです。親切にデータを開示してくれた後に、日本の印象を会計係りの中年女性に聞いてみました。
すると「とても親切でビューテイフルな国で伝統がある」と最高の表現です。絶賛です。これにも一瞬絶句しました。オーナーと対極表現だったからです。
同じカナダ人で、同じホテルで普段から仕事で接し一緒に働いている仲、同じカナダの山奥に住んでいるし、生活文化も大差ない二人、しかし、日本に対する印象は対極にあるのです。その対極差の理由、それが会計係りの次の一言で分かりました。それは「中学生の息子が伊豆の修善寺でホームステイし、その息子が撮ってきた300枚の写真を見て説明を受けたから」ということなのです。
修善寺で受けた日本人の親切と、修善寺の歴史と文化を示す写真を息子から説明を受けて、日本の印象が構成されたのです。実際に身近で日本のことを体験した人から伝わって、その結果として日本の印象がつくられていく事実を目の前で確認しました。なるほどと思い、日本の実態を伝える重要性を改めて感じましたが、最も大事なことは、日本には外国に胸張って伝えられる「伝統文化」があるという事実確認です。
この事こそがすべての原点です。日本の伝統文化は世界で高く評価されている事実、そのことを我々は正しく認識し、日本文化を正しく把握する努力をしたいと思います。以上。
2006年06月22日
2006年6月20日 分からないが判断基準
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
今年の梅雨
NHKテレビニュースで中国の一人当たり水消費量は、日本の四分の一であると報じていました。その点、日本は水が豊かで、今日も梅雨の雨が降っています。これを恵みの雨と思うか、それとも昨年に比較し雨が多く、日照時間が少ないと判断するか、それはその人によって異なりますが、ある人は「今年の天候不順は、江戸時代の天保の大飢饉時に似ている」と言い「天候不順な時は農薬の使用量が増える」とも言っています。
確かに天保の大飢饉は七年間に渡って発生しています。しかし、この大飢饉で日本全国がすべて「食べられなかった」のかと言いますと、そうではなく当時は幕府領と藩領によって為政者が異なっていましたから、そこの政治によってずいぶん被害状況に格差がありました。また、江戸時代は多雨、干ばつ、冷期が多く、ある人に言わせると「江戸時代は異常気象の方が多かった」とも指摘しているほどです。
ところが、この異常気象が多かった江戸時代に、米に生産が飛躍的に伸びた事も事実なのです。江戸時代の初期には千八百万石だった生産高が、天保時代には三千万石に増えているのです。米の生産が増えたということは、この時代は平和であり、人口も増え、耕地面積も伸びたことを意味し、これは農民の働く意欲が高まっていたとも解釈できるのです。 今年の梅雨状況から天候不順と断定するかどうか、それは各人の判断によって分かれます。
ワールドサッカー
日本はオーストラリアに負け、クロアチアと引き分けました。戦前の予想では日本はオーストラリアには勝って、予選は突破する見込みでした。だが、これはかなり難しくなりました。今年の3月、ロンドンのブックメーカー(公認賭け屋)で、ワールドサッカー国別掛け率を聞きました。以前にお伝えしたと思いますが、その時点でブラジルがトップで3倍、ドイツとイングランドが6倍、イタリア・フランスが7倍、クロアチアは50倍、オーストラリアは150倍でした。では日本は何倍か。それは125倍から250倍の間で動いていました。予選F組の中では日本が一番低いのです。
しかし、今月のFIFAの世界ランキングでは、1位は勿論ブラジルですが、クロアチアは23位、オーストラリアは42位で、日本は18位なのです。F組の中でのランキングではブラジルに継ぎます。どちらの評価ランクを採るか。それは人によって異なり、日本人として日本チームを高く評価したいのですが、いまのところロンドンのブックメーカー倍率が示す結果です。
人は何を基準にして判断するか
我々は常に判断をしています。目の前に現れる出来事を判断し続けています。また、その判断は自分の中に存在する、何かの「ある基準」で決めています。その「ある基準」とは自分の原体験を基に、そこに今までの人生経験や環境条件を加味しているものではないかと思います。つまり、自分の体験と場数の積み重ねによって、一人一人が何らかの判断基準を持っているのです。
しかし、この判断基準を多くの人は明確に把握していないから厄介です。通常、目の前に出来事が現われたとき、多くの人は直感的に行動することで、物事への対応をとっています。よく考えて行動しろ、などと言われても、実際は直感で判断しています。また、直感で判断しないとスムースな行動はできなく、日常生活は支障を起こしかねません。ですから、日常生活は直感の連続行動になっています。
しかしながら、直感で行動しているのですから、その直感行動する自分の内部には、何かの基準があるはずです。何もないのに直感行動はありえません。一人一人異なった判断基準が存在しているのです。
社会の共通概念
一人一人行動する判断基準が異なっているのですが、一方、社会にはこれを規制する共通概念が広く強く存在しています。
例えば、お腹が空いたとします。しかし、自分は空いたが隣の人がお腹を空かしたとは限りません。また、お腹が空いたとしても昼食時間にならないと、自分勝手にはなかなか食べられません。文明社会では昼食は12時というある規制が世の中に習慣化され、それに基づく共通概念が染み渡っています。社会の共通性概念にしたがって行動しないと、人間関係は壊れていきますから、一人一人の判断で勝手に行動できないシステムになっています。このレターはパソコンで書いています。パソコンに向うのは一人一人異なる個性ですが、向かい合っているパソコンはある一定の基準で規制され、作られているものです。ある人独自のパソコンがあったとしますと、そのパソコンを使って多くの人とメール連絡は不可能ですし、インターネットで様々な情報を入手できません。
つまり、パソコンは世界共通に規制された概念で作られているからこそ、多くの人と情報連絡でき、そうであるからこそ多くの人から活用されるのです。あるキーを誰が叩こうとも、その打たれたキーは同じ結果を示すから、パソコンは多くの人に役立つ存在になっているのです。それが同じキーを叩いて、結果が人によって異なるとしたら、この便利なパソコン社会・IT社会の隆盛はありえません。
ですから、社会には人々が共同して生活するための、共通概念が広く強く存在していて、それにしたがって行動していくことになります。
共通性概念の問題
社会生活を送っていくためには、この共通性概念を大事にしないといけません。しかし、この共通性概念だけを意識し、大事にし、守って行動していくとどうなるでしょう。共通性概念とは多くの人に当てはまるものですから、多くの人と同じ行動となり、多くの人と異なる行動は採らないということになります。社会が決めたことという暗黙のルールに従って行動する人間となります。それはどういう人間でしょうか。それは個性のない人間ということになります。人は生れたときから個性が一人一人異なっているのですが、その個性を発揮しないで社会規範ともいえる共通概念だけで行動していくと、最後には自分という存在、他人と自分がどのように違うのかということが分からなくなり、結果的に社会不適合になりやすいといわれています。
これは自閉症の発症が始めてアメリカで報告されたのが、1943年であったということからも推察できます。アメリカの児童精神科医が「従来の報告にないユニークな状態を示す一群の子どもがいる」と発表したのが1943年でした。その12年前の1931年に、テレビが始めてアメリカ社会に登場しました。テレビとは「情報が片側からの一方通行で、こちらからはコミュニケートできない」ものです。そのテレビの前に幼児を置いたままにしておくとどうなるか。正確には解明されていませんが、このテレビの普及と自閉症はパラレルになって発生したと言われています。テレビとは何か。それは強い刺激で、繰り返しが強力に行われるものです。その代表的なものがテレビコマーシャルで、視聴者の目に印象強く残してもらうために様々な工夫をして訴えます。その結果視聴者は、このコマーシャルを受け入れていくこと、つまり、コマーシャルが与える共通した概念が視聴者に入っていって、その結果で行動することになりやすいのです。これがコマーシャルの狙いです。
同様にテレビから発する情報、それはある種の社会に共通する概念ですが、それに幼児期から慣れきっていくと、実際の社会で異なる事例問題に当面したとき、つまり、共通性でない特殊性事例に該当したときにどうなるか。それは簡単に予測できます。自分の原体験を基に、そこに個別の人生経験や環境条件を加味しているものが少なく、共通性優位で行動基準が出来上がっていますので、戸惑い、困惑する結果となります。
分からないということが大事
ある人が最近分からないことばかり発生すると言いました。その通りで、今の世の中は日本社会の共通概念だけでなく、世界の異なった共通概念と、そこに世界中の一人一人の個性が集まって動いて、その一人一人がそれぞれ噛み合わないで動いていくものですから、分からないことが変化として顕れてくるのは当たり前です。
加えて、現状の社会システムが、今後向うであろう社会に合致していないのですから、更に分からないことが続発します。ですからこれからは「分からないということを判断基準にする」ということが、変化の時代に生きる基準ではないかと思っています。
以上。
投稿者 lefthand : 07:55 | コメント (0)
2006年06月06日
2006年6月5日 自分の敵は自分
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年6月5日 自分の敵は自分
実感する景気
90年代の金融危機のとき、家庭用金庫需要が急増しました。金融危機に対する防衛対処法セミナーが大流行で、それに伴うリスク分散の一環行動としての家庭用金庫需要でした。しかし、このところ金庫の販売状況が平常に戻ったようです。ということは「家庭用金庫=タンス預金」への動きが止まり、家庭用金庫にあったゴールドが値上がりとともに現金化され始めました。これらの動きはようやく人々の気持が、おカネを「守る」から「使う」に移りかけているのではないかと感じています。
というのもアメリカ・シアトルに行こうと、JAL、このところJALは不祥事件が続き不人気ですが、予約しようとJALに電話すると満員との回答だったからです。サンフランシスコ経由も満員、仕方なくカナダのバンクーバー経由でチケットを入手しました。機内誌にJAL管理職から下克上されたトップ、その顔写真入り挨拶文が掲載されているのは気に入りませんが、実際に乗ったJAL機内客室乗務員は、親切で一生懸命対応してくれています。ゴールデンウィーク後でありながら、満員の機内を見回して景気の動向を実感しました。
オンリーワン経営
JAL機内誌でグレゴリー・クラークさん(多摩大学教授)が、外国人から見て不思議な現象として「日本人の講演好き」があると書いています。日本人は他人の意見を聞きたがる人種だと断定しています。他の国よりもこの傾向が強いと述べています。自分もよく他人の講演を聞き、時折講演する者として、この指摘は当たっていると思います。
ついこの間も、東京で有名な企業経営者団体から講演の声がかかり、テーマ決定の事前打ち合わせに参りました。事務局の方から最近の講演内容を問われましたので、先日の静岡県伊豆長岡で行った「世界から見た日本の温泉業界への期待」の内容をお話しすると、すぐに「世界から見た日本の魅力」というテーマを指示されました。このテーマの背景意図は、日本の魅力を外国から見た立場で分析し、改めて日本の素晴らしいところを確認し、ますますグローバル化が進む中で日本企業が向かうべき方向性を示してほしいというものです。
つまり、グローバル化に向かう経営時流を解説することになりますが、それは外国と日本を比較することによって、日本文化が外国から高く評価されている事実を認識し、その日本文化のよさを最大限発揮させることこそが、グローバル化の中で生き残って成長していく根源力になるという内容になります。
しかし、この日本文化のよさを再確認し得たとしても、自社経営との具体的結び付けが他の企業と同じパターンであるならば、それは差別化されないということですから、特長がないので独自成長は難しく、再び同じ分野で、大勢が揃って同じスタイルで、その中でナンバーワンを競い合う、という厳しい経営実態に陥ります。今までに繰り返してきたものと全く同じ結果となるのです。
ですから、日本のよさを再確認するとともに、次への展開は脳を使って工夫し、他社と差別化した「オンリーワン」経営を目指すことが大事なのです。ということでテーマは「世界から見た日本の魅力」ですが、内容は「ナンバーワンからオンリーワンへ」ということになります。しかし、このようなオンリーワンの必要性は新鮮味がなく、既に十分に分かっていて、知られていることなので、講演会に人が集まりません。従って別タイトルテーマとなったわけです。
しかしながら、世の中の成功セオリーは昔から変っておりません。だが、セオリーを分かっていても実際に出来ない人が多いからこそ、実は何回も同じセオリーを講演会でお伝えすることに意味があるのです。「分かっていることを、実際に出来るようにした」人が、成功への道に向かうことになります。
人の話を聞くこと
このところ続いて傾聴の勉強をしまして、改めて人の話を聞くことの大事さを認識しました。また、営業力で成功した人物のお話を伺う機会もありまして、その方が「会話の中で当方が話すのは二割ぐらいに抑え、残りの八割はお客様の話を聞くようにしている。そこで大事なのは二割を話すこちらの言葉が大事になるわけです。聞かれてもいないことをべらべら喋るのでなく、お客様の質問や相談に対して、適切な言葉で明確に答えることが大切です」と教えてくれました。また「お客様から十の質問をされて、一つや二つは答えられない方がいい。そうでないとお客様を負かしてしまうことになる。分からないことは正直に言うことです」更に「その場ですぐ調べて答えが見つかったら、お客様のおかげで勉強できました、という返事をすると、その場の雰囲気は最高になること、間違いありません」とも教えてくれました。
毎月の講演会で質問に答えられないこともありますので、なるほどと思うとともに、家庭内でいつも「聞いていない」と指摘されている現状では、反省しかないなと思いつつ「分かっていながら出来ない」ことが実際に多いのだなぁと、本当に思います。
昔からよく言われている内容であって、それを知って理解しているのに出来ない自分は、自分の中に出来ないもう一人の自分がいるということになりますが、傾聴セミナーを受講した人は、皆さん同様の感想をもらしますから、多くの人が分かっていて出来ないこと、その典型例の一つが傾聴と思います。
理念の追求=居酒屋→居食屋→有機栽培→介護施設
先日、ワタミ㈱の渡邉社長のお話を聞く機会がありました。有名人ですから大勢の聴講者がいましたが、その年齢層がいつもの講演会と異なって若いのです。まだ20歳代前半の人が大勢来ています。明らかに経営者ではありません。これから仕事を探そうとする人か、卒業予定の大学生です。それらの人が皆一生懸命にメモし、渡邉社長の一言一句を聞き逃さないぞ、という感じで身体が前乗り姿勢なのです。ちょっと感動しました。いまどきの若者は、という感覚を変えさせられました。
渡邉社長の内容は厳しいものでした。小学校五年で両親を失い、それまでの豊かな生活が一変し、貧しさということを本当に体験した。会社というものは一般に入るものだと思っているようだか、自分は会社をつくるものであると考えていたので、一度も就職活動しなかった。今は大学新卒が一年間に500人入ってくるが、最初は大卒から見向きされなかったので、店にアルバイトしている学生を口説いて就職させた。このような体験談を聞いたわけです。
最近はあまり行かなくなりましたが、以前は「和民」に行ったことがあります。そのときにここは居酒屋という認識で、ここでは酒を飲むところというイメージで利用していたところ、向こうの部屋で若い夫婦が幼い子供をつれてきていて、その子供が走り回っていたことを妙だなぁと、思った経験があります。その疑問が渡邉社長のお話を聞いていて疑問が解けました。こちらは居酒屋という理解で「和民」に行ったのですが、実は渡邉社長の理念は「居食屋」という、ファミリー対象の新しい食事業態を目指していたのです。だから当然子供がいて当然なのです。こちらは居酒屋と思っていたので、子供に違和感を持ちましたが、それはこちらの理解不足だったのです。疑問が今になってようやく分かりました。渡邉社長が目指すこれからの経営は、有機栽培と介護施設展開です。有機栽培によって害の少ない新鮮な食材を提供できるようになるのですから、それは介護施設入居者にも提供できることになります。
つまり、居食屋も介護施設も「食」という視点で考えれば同じで、当然の発想であり、日本で最大の有機栽培事業と介護施設事業展開を目指しています。その発想の原点に、自分が日本の農業を変え、自分が日本の介護を変えるのだ、という強い目的があり、そのことを本当に理解できる人材を選別して採用していると言い切ります。ですから、本社ビルの八階で開催されるエリアリーダー会議で、この理念・目的に従っていない行動の幹部には「ここから飛び降りてしまえ」、というような激しい叱咤が日常茶飯事であると真顔で語ります。激しい叱咤は、本人を憎んで嫌いで言っているのではなく、渡邉社長が目指す理念に同感して一緒に働いているはずなのに、そのことが実行できない「相手の中にある敵」に対して発声しているのです。
景気が動き出したタイミングに、改めてオンリーワン経営・傾聴・理念追求型経営が大事で、その前提としては「自分の敵は自分」をコントロールすることです。以上。
2006年05月05日
2006年5月5日 集団的催眠状態になる日本人
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年5月5日 集団的催眠状態になる日本人
財政赤字の本質
ゴールデンウイークも後半になって、各地からUターンの渋滞が始まっています。天気は快晴、気持ちよい五月五日ですが如何お過ごしですか。当方は事務所移転後の細かい後始末と、放っておいた草花の手入れと、原稿書きで過ごしております。
先日、自民党の片山さつき代議士のお話を聞く機会がありました。さすがに東京大学法学部卒で大蔵省の主税局勤務、その後フランスの最高レベルのENA(フランス国立行政学院)を修了しただけに、何でも詳しく現在の問題点を解説してくれました。その中で当然ですが、国家財政の赤字についてもふれ、解決策は行政改革と消費税の増額になるだろうとの見解でした。国と地方を合わせた2005年12月末の債務残高は800兆円で、GDP対比
150%程度、この改善策として外国からは「どこかの時点で増税してリカバリーするだろう」と見られているとも言っておりました。まだ日本の消費税が他国に比較し低いので、その分楽観的に外国から見られているという意味です。
しかし、この内容を聞きながら思ったことは、この巨額の財政赤字を発生させた張本人は、国の財布を管理している大蔵省に責任があり、その大蔵省に在籍していた片山代議士にも当然あるわけですが、その責任云々については一切言及しませんでした。バブル崩壊以後も公共投資重視の、ケインズ型経済政策を採ったのは大蔵省です。勿論、政治の力によって押し切られたとも思いますが、ヨーロッパ各国の非ケインズ経済政策に対して、日本は反対の従来政策を踏襲してきた責任、それについて何ら言及がなかったのです。経済政策の失敗が今日の巨額債務残高に拍車をかけたことへの説明、それが欠如していました。
集団的催眠
日本人は「物事を自分に都合よく動くという夜郎自大的な判断をする」というのが半藤一利氏の見解です。「例えば、第二次世界大戦のガダルカナルの戦い。最初は米軍の本格的な反攻でない、という判断で対策が後手後手に回ったが、これは起きて困ることは起きないという発想だった。ソ連の満州侵攻にしても陸軍は考えたくなかった。海軍は米艦隊を日本近海におびき寄せて撃滅できると夢をみていた。こういう発想を持つのは、小集団のエリートの弊害で、陸大や海大出の優秀な人材が集まった参謀本部や軍令部に絶対的な権力が集中していたからであった。その彼らは作戦を司る軍事学にはたけていたが、常識を教わっていない。ある種の『タコツボ社会』で、失敗してもかばい合って反省が次に生かされない。ノモンハン事件の参謀たちがそのいい事例だ。この戦争の指導者たちが陥った『根拠なき自己過信』は、何もその時代だけのものではない」(日経2006.4.20)。
この見解は巨額債務残高となったことにも重なり合います。終戦後展開してきた経済政策、高度成長時代を支えた見事なケインズ型経済政策、その効果がバブル崩壊という時代が反転した状況下でも通じると過信し、思い込み、それを声高に叫ぶ一部の政治家に圧され、集団催眠にかかったように、巨額の国債発行をくり返したのです。その事実を当時の政治家言動から振り返ってみます。
(小渕首相)世界一の借金王にとうとうなってしまった。600兆円も借金をもっているのは日本の首相しかいない(2000年度予算案提示時1999.12.12)
(宮沢大蔵大臣)大きな歴史から見ると、私は恐らく大変な借金をした大蔵大臣として歴史に残るんだろうと思います(2001年度予算編成記者会見時2000.12.20)
(亀井自民党政調会長)一家の稼ぎ頭の父ちゃんが倒れてしまったのだから、子供から借金しても栄養をつけさせないといけない(毎日新聞1999.11.14)
いずれも世界に類例のなき巨額国債発行であること、それを十分認識しているのですが、その効果を確証出来ず、しないまま、公共投資等を増額すれば経済が好転するという「思い込み」の集団的催眠状態で、国家の政治を推進していたのです。恐ろしい感覚です。
この集団的催眠状態を小泉首相がようやく覚まし、歯止めをかけましたが、残った結果は今日の財政惨状です。政治家と大蔵省の持つ世界的視野での経済認識、ベルリンの壁崩壊以後の世界経済状況激変、そのことに対する事実認識に問題があったのです。
これらの経緯について、大蔵省出身の片山代議士から何も発言がありませんでした。責任の所在を感じていないのだと思います。いずれにしても、日本人は思い込みが強く、いったん燃え上がると熱狂そのものが権威となって、多くの人々を引っ張っていき、引っ張られた人々も頑張り過ぎるということを、昔も今も続けているのです。危険な習性を持つ国民です。
熟成
ある人から連絡がありました。今日が誕生日でこのようなよい季節に生れたしあわせを噛みしめ、これからは更に熟成したいという内容でした。人は年齢とともに熟成していく。すばらしいことです。そうありたいと思っています。しかし、ここで考えなければならないことは、熟成という意味です。言葉として熟成の意味は分かりますが、人間としての熟成という意味をどのように理解するかです。ワインの熟成ならば樽に入っている年数で客観的に判断可能です。だが、人間の熟成はどうやって判断するのでしょう。例えば昨年の五月五日と、今年の同日を比べて、何がどのような変化したのか。それを比べる手段があるのでしょうか。年齢だけは生年月日が戸籍で確定していますから、明確に判定できます。
ところが、人間の内部に関する熟成はなかなか明確にはならないのですが、明らかに人は変化しているはずです。昨年と同じではありえないのが事実です。ですから、必ず人は熟成したいと願って行動していれば、その願いどおりに熟成していくはずですが、その根拠を明確し難いため、熟成度合いの判断は自分で自分を主観的に判断することになって、それは情緒的に自己評価することになります。
つまり、自分を自分で客観的に判断することが出来難いのですから、判断結果にその人の習癖が当然の如く表れることになり、自己流の熟成度合い判断になります。客観性に欠けることになります。半藤一利氏が言う「物事を自分に都合よく動くという夜郎自大的な判断」になります。ですから、自分で自分を熟成させるのはかなり困難で、特に「夜郎自大的な判断」をしたがる日本人には難しく、この習癖は国家運営の政治家にも官僚にも当然当てはまります。
山岡鉄舟の連載
このゴールデンウイークに、月刊ベルダ誌連載の山岡鉄舟六月号を書きました。この六月号でちょうど一年間掲載が過ぎ、二年目に入りました。この一年間、鉄舟の最大の業績「江戸無血開城」について展開し、現在はそのような偉大な業績を挙げ得る人物になれた、幼少年時代について書いております。鉄舟を研究すればするほど、鉄舟の偉大さに頭が下がり、このような人物が現在の日本に存在していたなら、集団的催眠状態に陥りやすい日本人に歯止めをかけてくれたと思います。
歌舞伎役者の八代目坂東三津五郎(1906〜75)も、同様のことを述べています。八代目は、歌舞伎界の故事、先達の芸風に詳しく、生き字引と言われ、随筆集「戯場戯語」でエッセイストクラブ賞を受賞していますが、何と鉄舟にも詳しいのです。
それもそのはずで「慶喜命乞い」の芝居を演じた際に鉄舟を随分研究して、次のように鉄舟を語っています。
「山岡鉄舟先生は、江戸城総攻めの時、あらゆる階級の人たちに会って『おまえたちが今、右往左往したってどうにもならない。たいへんな時なんだけれども、いちばんかんじんなことは、おまえたちが自分の稼業に励み、役者は舞台を努め、左官屋は壁を塗っていればよいのだ。あわてることはない。自分の稼業に励めばまちがいないんだ』と言うのです。このいちばん何でもないことを言ってくださったのが、山岡鉄舟先生で、これはたいへんなことだと思うんです。今度の戦争が済んだ終戦後に、われわれ芝居をやっている者は、進駐軍がやってきて、これから歌舞伎がどうなるかわからなかった。そのような時に、私たちに山岡鉄舟先生のようにそういうことを言ってくれる人は一人もおりませんでしたね」(『日本史探訪・第十巻』角川書店)
時代の混乱時に鉄舟のような偉大な人物が必要であったことを、八代目坂東三津五郎が認識しているのです。仮にバブル崩壊時の経済政策運営本部に、鉄舟がいたらどうであったか。歴史に「仮に」はないことは知っていますが、間違いなく集団的催眠状態からの政治に歯止めをかけたと思います。鉄舟の生き様を研究していると常人とは異なっています。鉄舟は自らの人間完成を戦略目的として生きた人物で、その実現を明治十三年(1880)に「大悟」、悟りの境地に達しました。日本人のような習癖には鉄舟のような熟成人物が必要です。以上。
(5月20日号レターは海外出張のため休刊となります)
2006年04月25日
2006年4月20日 脳ブーム
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年4月20日 脳ブーム
事務所の移転
4月22日に事務所を自宅に移転させました。その後片付けや整理などで毎日体力を使い、その結果このレターの発行が遅れました。
移転しようと考えたのは、ドイツからの記事が発端でした。ドイツ在住の日本女性作家がハンブルグからベルリンに引っ越したら、友人のドイツ人が揃って「新しい住まいは壁にペンキを塗るべきだ」と言い、その理由として「自分で壁を塗ればすぐに自分の家だという感じがするから」と言われ納得したとエッセーで述べていました。
これになるほどと思ったわけです。大工が造るのではなく、自分で自宅をつくりあげる、という感覚がドイツ人は強いのでしょうが、自分が手掛けて造っていくプロセス、それは自分の人生も自分で創りあげていくことにも通じることだ、それにいたく納得したのです。
と言いますのも、二年前から自宅の改装を始めていまして、外回りの屋根と外壁は専門家にお願いしましたが、内部は休みの日に予定立てて少しずつコツコツと自分で作業していたためです。特に壁紙を貼る場合は、古い壁紙を剥がし、その後は新しく貼るための準備として養生をし、一定期間をおいて壁紙を貼っていくなどの作業していくうちに、自分の家は自分で大事にするものだという感覚を強く持ち始め、このことは自分の体をメンテナンスすることと同じだと思いました。
ようやくこの4月になって、子どもが成長し空いた部屋を含め全体作業が終わり、事務所スペース部分が確保されましたので引越ししたわけです。今は、自分が造り上げた事務所という感覚に浸っていますが、引越しするに際して本や資料の整理を行いました。いかに無駄なものが多かったと反省し、大量のゴミ捨てになり環境面でご迷惑をかけたのですが、自分の贅肉がとれたようなすっきりした気分となりました。
東京MXテレビ
突然、東京MXテレビ局から電話がかかってきました。来週の木曜日(4月20日)に「脳力最前線」という番組を放送する。三社(名)の脳力開発関係専門家に登場してもらうが、その中の一人として取材させてほしい、という内容でした。
脳力開発という言葉は、師匠の城野宏先生が創始したものです。昭和60年(1985)に亡くなりましたので、既に21年経ちました。昨年、城野宏先生が関係していた「経営ゼミナール」の代表に就任しまして、すぐに「経営ゼミナールの発展」というDVDを作りましたのが今回役立ちました。
テレビの取材は前の事務所でのインタビュー形式でしたので、背景画面は殺風景な壁だけですから、DVDから経営ゼミナールの開催画面を挿入することで彩りをつけて放映してもらいました。
テレビの中でお話したことは、一つは城野宏先生の業績紹介、二つ目は「経営ゼミナール」の開催内容紹介、三つ目は「脳力開発」の向うべき方向性です。この方向性については、日本人の戦略思考の欠如をいつも痛感していますので、そのところを鍛えなおすために、いつも思い考えていることをお話ししました。
東京MXテレビであり、内容が固いので見る人もいないと思っていましたが、結構ご意見をいただきました。また、特に勉強になったのはテレビ局のプロデューサーから聞いた時代の動きです。時流です。今回の番組企画背景に時代が「脳」に高い関心を持っているから取り上げたという説明でした。
改めて振り返ってみますと、城野宏先生が最後の戦犯として、中国から帰られたのが昭和39年(1964)。それから中国の獄中で生きのびた凄まじい体験から生み出した、脳力開発・情勢判断学を世に問い、著書も数十冊出版し、多くの人から支持されたのです。
しかし、今は城野宏先生の名前も知らない人が多く、脳力開発という言葉も死語に近いと思っていたところ、実は世の中が「脳ブーム」という有様になっていたのです。
美人脳
今、書店に行くと「大人のぬりえ」が大量に並んでいます。4年前に「ぬりえ美術館」をオープンしたときには考えられませんでした。
ぬりえは子どものするもの。それが常識です。これは日本だけでなく、世界の常識です。ところが、いつの間にか書店には「大人のぬりえ」コーナーが誕生し、多くの大人がぬりえを楽しんでいるのです。介護施設でもぬりえが行われています。
「ぬりえ美術館」の「ぬりえサロン」、最初の参加者は館長の金子さんだけでした。次第に増えていったのですが、ついこの間までは四五人でした。ところが4月の参加者は会場一杯となりお断りする実態となりました。
こうなってくるとマスコミの取材は更に多くなり、いくつかの企業広報誌にも掲載されるようになって、とうとう内閣府の広報誌「CABIネット」までも取材に来ました。5月号に掲載される予定です。
また、「ぬりえ美術館」のホームページへのアクセスも一段と増えました。そのホームページに掲載された「ぬりえと脳」の関する内容を以下ご紹介します。
「脳が活性化すると認知症の予防になるだけではありません。東邦大学医学部、総合生理学の有田教授は、脳内神経の「セロトニン」の研究者として著名な方で、私(金子館長)も今週、ぬりえをしている時に脳のセロトニンはどうなるのか測定をお願いしている方です。有田先生によりますと、セロトニンには3つの働きがあり、活発になると、1.頭を目覚めさせる。2.筋肉に緊張感を働かせる。3.交感神経を適度に働かせるという動きがあるそうです。ですからセロトニンが活発化すると、眼が大きくぱっちりと見え顔の輪郭引き締まって、顔全体がリフトアップされて、背筋がピンと伸びるそうです。
素敵なことばかりですね。
更に、自律神経への働きかけにより、バランスのとれた心の状態に整うのだそうです。つまりセロトニン神経を活性化させれば、顔形、姿勢、メンタル、体調まで、すべてがベストな状態になるのです。今は、「大人のぬりえ」ということで、年配者に光があたっていますが、ぬりえをして脳を活性化するということは、年配者も、子供も、そして若者も、すべての人にとって非常に有効ということになります。
杏林大学医学部精神神経科学教室の古賀先生によりますと、脳は1日の終わりに軽く動かしたほうが脳の健康が保てるということから、寝る前にぬりえをするのが良いそうです。
ぜひ、子供と年配者だけでなく、すべての年代の方々がぬりえを、特に寝る前にぬりえをしてみてはいかがでしょうか」
加えて、とうとう女性誌の25(ヴァンサンカン)の2006年4月号では、「あなたの脳、『美人』ですか」という特集が掲載されました。そこに次のように書かれています。
「脳年齢を計るゲームや効率重視の脳力アップの本など、昨年来の脳ブームがまだまだ続いています。実は、美人になるためにも脳は大切な働きをしているのです」と述べ、「脳の美人化」計画として「美人脳促進アイテム」を7項目提案しています。その提案の第一アイテムは「大人のぬりえ」です。驚きました。
当方は城野宏先生提唱の「脳力開発」を、経営者にお役に立つよう「経営ゼミナール」でお伝えして26年間過ぎましたが、その間に世間では脳ブームを迎えていたのです。それも何と「美人脳」というところまで飛び火していました。これはちょっと安易な表現ではないかと気になりますが、脳ブームはまだまだ続くと思います。単なるブームは何時か消えていくものですが、人間にとって最も大事で重要な脳、これへの関心は失われることはあり得ないからです。改めて城野宏先生の慧眼に感心しているところです。
人口減対策に脳を
日本人の誰もが正しく事実を認識していること、それは日本が人口減に向っていることであり、高齢化になっていくことです。この事実現象に対してどのように対応していくのか。そのことの議論が各所で多くなされていますが、この議論を他人事にしてはいけないと思います。一年ごとに実態が明確に現れクリアになる人口減と高齢化という新時代、それに対応するのは我々なのです。一人一人の問題なのです。
結論と対策はハッキリしています。人口減に伴う生産力人口減に対しては生産性アップ、高齢化に対しては高齢者自らが脳を活性化させること、この二つの方向性で日本の国づくりをしていくことしかありせん。
そのことを日本人に気づかせるために、脳ブームが発生したと理解しています。以上。
2006年04月05日
2006年4月5日 劣等感と伝統力
YAMAMOTO・レター環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年4月5日 劣等感と伝統力
劣等感
今フランスは、初期雇用契約を盛った新しい雇用法「機会平等法」反対の、全国ストとデモが発生し大変な騒ぎですが、二月末から三月初めに開催された農業祭は例年通り盛り上がりをみせていました。初日にはシラク大統領も出席し、まずフランスの地ビールを試飲すると、ワイン業者から「こっちに来てワインも飲め」と声がかかって、会場内を笑顔で楽しんでいましたが、今では全土の大混乱によってシラク大統領は苦境に陥り、ドビルバン首相とともに支持率が低迷しています。
パリ農業祭では日本人女性とフランス人男性の新婚カップルと、一緒に会場内を廻りました。彼女は三年前にパリに来ました。フランス語を全く分からないまま、パリに来てブティックで働いたのです。今回の争点になっているフランスの雇用方法、まず、最初は無給で働き、そこで働いている間に自分にあった職業を決めていくスタージュ(stage)で頑張りました。その過程でこの男性と出会ったのです。
フランスに来た当時、彼女の中に「何かのフランスに対する意識」が潜在的にあったといいます。フランスというより欧米に対する認識感覚です。一言でいえば「劣等感」と表現する内容になると思いますが、自分の内部にある何か欧米人に圧倒されるような気持、それを持ったままフランスに来ました。
しかし、ブティックで働き、そこで力を発揮し、経営者から認められ始め、結婚した男性との交際も始まった頃から、自分の中で気持に変化が起きていることに気づきました。その変化の始まりは、周りのフランス人が彼女に発する「日本の伝統文化」に対する質問からです。日本という国が持つ伝統文化、それへの説明・解説を求められることが多々発生し始めたのです。つまり、フランス人は日本という国に対して「伝統文化に優れた国」というイメージを持っていて、その内容を理解したいために多くの質問を彼女に発したのです。だが、彼女は的確にすばやく相手の質問に回答はできなかったと述懐しました。フランス人の質問に対して回答し説明できる「日本に対する理解力」を有しないまま、フランスに行っていたことを相手からの質問で深く強く認識し反省したのです。
しかしながら、その反省の過程で彼女の感覚は大変化しました。全く正反対になったといってもよいと思います。それは、日本の「伝統文化」に対する自分自身の再評価をとなって、日本で生まれ育ったすばらしさに気づき認識し、そこから徐々に自然に「劣等感」というものが消えていったと言うのです。
同じことは他の在仏日本人からも聞きます。地方都市で生活している日本人女性、フランス人と結婚していますが、最近は地元企業から日本文化について講演を依頼されることがあり、日本への関心は高く、その講演と説明のために参考書籍を紹介してくれないか、という依頼がこちらに来るほどです。
私もピレネー山脈のリュション温泉、そこで市長以下幹部に同様の講演をしたことがありますから、日本に対する関心度の高さは本物であると感じますし、関心の背景は日本の「伝統文化」の豊かさから来ているのです。
日本の伝統文化発生は江戸時代
現在の日本が世界で評価されている背景には三つの要因があると言われています。第一は伝統文化であり、第二は世界の若者を惹きつけているポップカルチャーとしてのクール・ジャパン現象であり、第三は非軍事による対外協力である。(ハーバート大学ジョセフ教授)この中の第二のポップカルチャーもその源流をたどって行けば、それは伝統文化として栄え確立した江戸時代につながっています。ですから、日本の伝統文化の源は江戸時代にあるのです。
山岡鉄舟の連載をしております関係から、幕末が中心ではありますが江戸時代を分析していますと、従来、語られてきた実態とは異なる江戸時代のすばらしさが分かってきます。
これは既に多くの事実で、多くの識者によって解明されだしましたが、それとともに、今まで伝え語られてきた内容が「ある立場」からなされたということが分かってきます。
それは、明治維新政府が新しい日本をつくりたい、その目的としての方向性は「国家の西洋化」であったために、それ以前の江戸時代政治を、とかくマイナス的に評価する教育をおこなってきたことです。江戸時代は民衆を圧制し、農民に対して苛斂誅求の政策で臨んだ、というような解説が多くなされ、それを受け入れてきたのが今までの実態でしたが、実はすばらしい豊かな社会であったというのが、最近の歴史研究で明らかにされているのです。もちろん事件はたくさん発生し、異常気象によって飢饉はありました。その事例を持って徳川政治は百姓や一般庶民が食えない貧しい生活を強いた、という見解には問題があります。その大きな重要な視点は米の生産量です。江戸時代の初期は全国の米生産高は1800万石であったものが、幕末の天保期になると3000万石に増加しているという事実です。この事実を見落としてはならないのです。それは、江戸時代は基本的に平和であり、平和であったからこそ農民は米生産増に邁進し、勤勉に働けたから米の増産に向かったのです。国の政治安定なくして食料安定は図れません。
また、この食料事情の安定化がなされたからこそ、今に評価されている日本の「伝統文化」が興隆したのです。文化興隆の背景には政治・経済の安定が必要条件です。
つまり、明治維新後に展開された「西洋化」としての「近代化」が開始される以前の、江戸時代の伝統社会の最も成熟した姿、即ち「西洋化」の影響を受ける以前の伝統社会の純粋な姿が、今、日本の「伝統文化」として外国から高く評価され、世界各地から関心を持たれ、冒頭のフランスに渡った若い日本人女性が多く質問を受ける内容なのです。
劣等感はなぜ形成されたか
今年の九月にニューヨーク(NY)で「ぬりえ展」を開催します。その準備を行っていますが、最も苦労していることにアメリカの実態研究があります。NYの人々にぬりえを紹介するという仕事、そのために必要な前提は「NYの人々の感覚」の把握です。つまり、アメリカ人とはどのような思考プロセスを構成しているかという検討なのです。この検討なくして案内文書は書けません。そのため相手の立場研究が何よりにも優先するのです。
まだ十分ではありませんが、分かったことに欧米人の自己主張の強さがあります。積極性ともいえますが、自らの優位性をまず主張することを優先する思考です。その結果として生み出される行動は「可能性にたいして積極的(アグレッシブ)であること」であり、それを片時でも疎かにすれば、じっと立ち止まっていることさえ許されなく、立ち止まればたちまちおし倒され「負け組」となっていく競争の激甚さです。すごいと思います。
これが欧米人の人種優位性をも主張させ、それを彼らの頭の中に認識させ、その結果アジア人に「劣等感」ともいえるものを植え付けさせていったと思います。これは欧米人の人種優位性主張の歴史をたどってみればすぐに分かります。例えば1758年に生物分類学の創始者カール・フォン・リンネは、ホモサピエンスを四つに分け、それを受けついた一派が人種のヒエラルキーを理論構成し、ヨーロッパ人を指す「コーカサス人種(コーケイジャン)」という用語をつくり、このコーカサス人種こそが身体美の理想的な基準を示すものであり、他の人種はそこから徐々に逸脱していったものだと主張したのです。
その後も人種間の差異を説明しょうする人類学学者が多数輩出し、その結果は「コーカサス人種の頭蓋の平均的容量が最も大きい」とまで主張がなされ、白人優位説が欧米人の中に確立したのです。その差別思考を持った人たちである、ペリーに始まる欧米人たちが一挙に幕末日本に来て、日本訪問記で「日本人を専制的で小さく劣った人々して描き、アジア的で隔離された日本では進化と進歩がはるか昔に停止してしまっている」と表現し、その後も訪れた欧米人も同様の感覚で日本を判断し、その判断結果を「西洋化」ということを急いだ日本人が知らず知らずに受け入れ、認識させられていったのです。
これがパリで若い日本人女性が内在的に持っていた、劣等感といえる所在の歴史であり、もしかしたら一般の日本人が内在している傾向と思います。
伝統力
だがしかし、パリの若い女性が徐々に劣等感を解消させ、ハーバート大学教授が指摘する日本評価の理由を考えれば、日本人は世界に誇る江戸時代の「伝統文化」を持ちえているわけですから、つまらない過去世紀になされた根拠なき白人優位人類学的主張を排除すべきなのです。その試みの一つとして実は今回の「ぬりえNY展」を位置づけたいと思っています。NYという世界一の情報発信地で日本の「伝統文化」を受け継ぎ、そこから描いた世界一の「きいちのぬりえ」を積極的(アグレッシブ)に伝えるつもりです。以上。
2006年03月21日
2006年3月20日 すべて小さく考えろ
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年3月20日 すべて小さく考えろ
アイルランドの景気
アイルランドのダブリンに着き、タクシーに乗って街中に向かう道路、いたるとところで道路が掘り起こされ、両サイドの畑では建物が建築中、街中のホテル前も工事中で狭い窮屈な停車スペース状態です。
このアイルランドは空前の景気です。入国パスポートチェックで「ビジネスか」と聞かれます。経済関係の訪問が多いのでしょう。20年前とは大違いです。このアイルランドはケルト文化の色濃く残った静かな落ち着いた国でした。世界的作家を多く輩出しており、ノーベル文学賞受賞作家は四名もおり、小泉八雲はアイルランドの出身です。世界的な数学者も出ているように、薫り高い島というイメージでしたので、司馬遼太郎のアイルランド紀行を持って20年前に訪ね、ケルト文化遺跡を落ち着いた雰囲気の中で楽しみました。
しかし、今は大変化です。空港からのタクシーが妙に話しかけてきます。どこから来たのか。ビジネスか。何日滞在か。どこへ行くのか。気候はどうか。少し煩わしいので本を広げましたが、本を閉じるとまた話しかけてきます。こういうタクシーは危険です。相手を観察し隙を見つけようとしているのです。やはりそうでした。メーターがホテル到着時に23ユーロだったのが、財布からお金を取り出して改めてメーターを見ると28ユーロになっていて、30ユーロを紙幣で渡すと、すぐに30ユーロの領収書を手書きで書いてしまいます。釣りをよこさないのです。お金をとることに執着していることが分かります。帰りはホテル手配のタクシーで、空港まで23ーロでしたので、やはりこのタクシーはいかさましたのです。タブリンに着いたばかりのドサクサに稼ごうとする悪い根性が発生しています。地元の人に聞きますと、最近このようなタクシーが発生しているということで、もともとアイルランドは人柄の良さで知られていたのに残念な実態です。
お金が一番という風潮は経済成長の結果です。EUに加盟して、助成金を受け、それを教育投資に充当注入し、ハイテク産業育成を図ったことが1990年代に入って空前の好景気を招きました。ここ7年間の平均成長率は10%を超えています。政治は保守系が
安定した政権を握っていて、財政は大幅黒字です。
人口不足
ダブリンの目抜き通りの不動産も大変化です。不動産価格、それが10年間で10倍になっています。日本円で億単位の不動産、それも二桁の億単位が並んでいるのです。ということは物価が上がり、人件費も上がり人手不足となったのですが、その対策として外国からの移民、ポーランド・中国・フィリッピン・インドネシアから受け入れました。この人たちは一般的にサービス業に従事しています。全人口の25%が30歳以下という人口構成でありながら、このアイルランドでは人不足なのです。それだけ経済成長がすばらしいということです。
人口不足という意味ではオランダも同じです。ただし、不足する理由がアイルランドと異なります。こちらに来て新聞を見て知ったのですが、オランダはここ100年間で最低の増加率を示したとオランダ統計局が発表しました。理由は三つ。一つは国外移住者の増加、二つ目は移民の減少、三つ目に出生率の減少です。この中で大問題なのは国外移住者です。純粋のオランダ人が自国を捨てて他国に移住していくのです。行き先は暖かい地域、フランス南部・イタリア・スペインなどですが、昨年は12万人もの人々が移住しました。前年比10%増です。世界の国々の人口不足問題も理由がそれぞれだと思いました。日本は出生率逓減から人口が減少していくのですが、オランダでは国民自らが国を去っていくのです。因みにオランダに移民として入ってくるのは、かつてはモロッコ人やトルコ人でしたが、今はポーランド人が激増しています。こうやってみるとポーランド人がヨーロッパに進出していることが分かり、国ごとに様々な要因があり、その対策も国ごとに異なります。
アイルランドもポーランド人の移民増加が多く、それらの人はサービス業に従事しているのですから、レストランに行って注文に対応しているのはポーランド人が多いということになります。こちらにはアイルランド人かポーランド人か、その区別がつかないのですが地元の人に聞くと分かるようです。
そのポーランド人が多いウェイトレス、オーダーを受け、テーブルに皿を運び、テーブルでのカード支払い手続き、これが仕事の流れですが、店によって当然異なります。すばやく手際がよい店と、その反対のレストランがあり、その差は同じポーランド人が担当しているとは思えないほどです。勿論、人によって能力の差があり、行動に較差が発生するのですが、それではない何かを感じます。その何かとは店側の教育であると思います。最初にしっかり伝え、訓練しておくこと、それが出来ているところは客に対して好感度が高く、結果として能率が高いのです。折角移民として受け入れたのですから、生産性の高い行動をとれるような体制とシステム化が必要なのです。
仮に日本が移民を受け入れるという政策を採った場合、その際には事前に日本の生産性保持するための教育が必要条件と思いました。
本音と建前
冬季トリノオリンピックは残念でした。日本の選手は最初から不振でした。目標としていた選手一人一人の力を出し切れず、メダルには届かない結果が続きました。しかしようやく女子フィギアスケートで荒川静香選手が金メダル、これでホッとしました。冬のオリンピックの最大の華での快挙、他の種目の何倍かの効果ある金メダルでした。
荒川選手の金メダル獲得の日にパリに入りましたので、パリで会ったフランス人から祝福されまして、荒川選手金メダルの大きな効果を実感すると同時に、金メダルを獲得するには大きな何かが影響しているはずと感じました。
というのも、先日順天堂大学の沢木教授からお聞きした内容が印象的だったからです。沢木教授はご存知のとおり現役時代陸上名ランナーであり、その後順天堂大学陸上部の監督として何度も箱根駅伝に優勝し、科学的トレーニングを取り入れていることで著名な人です。その沢木教授が夏のアテネオリンピック選手結団式の後で、500項目にわたる心理テスト(TPI検査)を実施し、その結果でオリンピックを予測しました。このテストは本音と建前を探ることができるのです。自主・協働の気持ちになっているか、それともしらけや閉鎖的な気持ちなのか。順応しているのか、萎縮しているのか、反発しているのかが分かるのです。心理テストの結果、女性の場合の建前はよかった。オリンピックに向かって積極的に自主的にやりますと。ところが、本音はそうでない。ちょっとしらけがある。あるいはあの監督は嫌だなと反発している。非常にバランスの悪い結果でした。
一方、男性はどうだったか。これは単純で本音と建前があまり変わらない。ですから陸上男子は入賞者が十一名もいた。女子の陸上入賞者はマラソンの三名のみでしたが、この三名は海外で合宿中でして、心理テストを受けていなかったのです。
ものの見事に事前の心理がアテネオリンピックの成果に表れています。この結果から常識的に考えますと、何かの理由でトリノ日本選手間に建前と本音で乖離があり、それがメダルを取れない、つまり、派遣選手数に対する生産性の低さとなったのだと思います。
すべて小さく考えろ THINK SMALL
トヨタの「カイゼン」運動も、アメリカのウォルマートの創業者サム・ウォルトンが言い続けた「THINK SMALL」も「すべて小さく考えろ」ということで通じます。
強くなるということは企業に例えれば成長であり、売り上げ増で、それを増やすためには三つの方法があります。一つは品揃えを増やすこと。二つは店を増やすこと。三つは一品あたりの売り上げを増やすことです。つまり、生産性を上げることですが、一と二は「増やす」というコンセプト、それに対して三は「変える」ということです。一品あたりの売り上げを増やすのですから、品質を見直し、臨機応変に売り場を変えるなど、その商品の良さを更に追求する単品管理の状態に入っていくことです。
一方、強くなるということを、人に例えれば生産性を高めることになると思います。オリンピックの派遣選手数に対するメダル数、その効果を期待するなら選手を本音と建前が一致する状態にすること、移民政策を採ってもサービスに問題ないようにするためには事前教育が肝心です。
日本が人口減の中で世界的な競争力を持ち、成長し続けていくために必要な条件は、一人当たりの生産性を上げることが最も大事です。そのためには「変える」ことであり、自らの足元を知りつかんで「すべて小さく考えろ」で工夫し、創る変えることです。 以上。
2006年02月19日
100%理論
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年2月20日 100%理論
プロという意味
知人から「温泉文献目録」をいただきました。早速開いてみると「笑う温泉・泣く温泉」が掲載されています。専門書として書いたわけですから当然ですが、温泉プロ鑑定者から専門書として認定されていることを確認できました。
二月五日のテレビ朝日「オイスターロードの旅」で「フランスを救った日本の牡蠣」がテロップで流れました。小さな文字ですから、気をつけなければ見過ごします。放映後、ディレクターからメールが届きました。「仙台地区の視聴率は10.2%、関東地区は5.8%、一番よかった視聴率場面は16.0%で、フランス・ブルターニュのマデックさんと森公美子・きたろうが話しているところ」との内容。マデックさんを推薦した手前、このメールに嬉しくなりました。提供した情報がお役に立ったことを素直に喜んでいます。テレビ局からマデックさんにDVDを送ったともあります。近々マデックさんに会いますので、話に花が咲くでしょう。
昨年出版の「ぬりえ文化」もそうですが、専門書を書くということは、一般的にその道のプロになったことを意味し、プロとして社会から認識されるわけです。
では、プロとはどのような存在者を意味するのでしょうか。タイミングよく、日経新聞にプロの定義が掲載されていました。(2006.2.9 大機小機)
1.高度な専門技術を有していなければならない。
2.専門技術を適応するに当たって、厳格な倫理観を有していなければならない。
3.すべての能力はクライアントでなく、顧客の利益のためにささげなければならない。
これはライブドア問題から提起されたものですが、日本では本来のプロフェッシォナル観念が希薄である、とも言及しています。
この三条件に該当する専門家であるどうかについては、忸怩たるものがありますが「思考を深めない、深く物事を考えない風潮の現代」では、世の中の出来事や情報を「ある立場から分析し整理」し、その内容をお伝えするということは、何らかの存在価値があり、必要なことであると思いますので、今後も専門書を書く立場からお伝えしていきたいと、改めて覚悟しているところです。
表面の背後にあるもの
不動産の達人「さくら事務所」の長嶋修氏が次のように語っています。
「売れる住宅とよい住宅は必ずしもイコールではない」「よい住宅とは、長持ちする、自然災害に強い、断熱性が高くエネルギー過剰使用でなく、維持管理がしやすい」なるほどと思います。また、売れる住宅は「内外装やシステムキッチンなど見える部分にお金をかけたもの」であるとも主張しています。これにも納得します。
これは文章にもいえます。「街場のアメリカ論」で内田樹氏が次のように述べています。
「腐る文章と腐りにくい文章があり、腐るというのを言い換えると経時的に汎用性がないということである」「メディアがもてはやす『切れ味のよい文章』はたいていの場合、『同時代人の中でもとりわけ情報感度のよい読者』を照準している。今から二十年前の読者や今から二十年後の読者のことなんかあまり考えない」この見解にもなるほどと思います。
本も同じです。売れている本とよい本が必ずしもイコールでなく、テレビでも視聴率の高い番組とよい番組とは別であるようです。
どの業界人も、ユーザーの求めるものを提供しようと、人々が持っている希望を探っています。ですから、ユーザーの嗜好を探ることに熱心で、結果的にユーザーに媚びることになる提案になりやすいのです。
しかしながら、ユーザーは本当のところで「自分に媚びてくるもの」よりは「プロとしての提案」「プロとしての見解」を欲しいのではないでしょうか。表面的な「かっこよさ」ではないものが提供される時代になっているように思います。
松井選手の100%理論
NYヤンキースの松井選手をテレビで見ました。松井選手に大リーグで活躍している秘訣をクイズ的に尋ねる番組でした。ピシッとした背広姿の松井選手が明確に答えます。
「基本的にトーリ監督の考え方と同じです。100%理論です。自分の力を100%出すことです」この答えになるほどと思います。自分の力を120%出すのでなく、また、80%でもない100%出すことが目的だと言い切りますが、これは大変なことであると感じます。それは、自分の力がどの程度あるかということを100%把握していないといえないことであり、仮に把握していたとしても、いつも100%出し続けるのは難しいと思うからです。そのところを松井選手が解説してくれました。
「そのためにまず行っていることは、過去の経験をしっかり記憶することです」「次に試合の日は毎日同じルーチン動作を続けることで、集中力に結び付けます」「この二つのことを継続することで目標を目指しています」
会場から質問がでました。「過去の経験を記憶しているということですが、○○号のホームランは何年何月何日でどの投手から打ちましたか」ちょっと時間をおいて正しい答えを発言します。会場がどよめきます。
次の質問は「毎日同じルーチン動作とはどのようなものですか」「それは試合前にロッカー室でおにぎり二個お茶を飲んで食べること、バッターボックスに入る動作がいつも同じであること」と答え、このルーチン動作は日本でもアメリカでも同じであると強調します。特殊なルーチン動作ではないことに会場がどよめきます。
100%自分の力を発揮させるために行っている二つのこと、この二つは出来そうですが実際にはかなり難しいと思います。しかし、その難しいと思われることを淡々と実現しているからこそ、ヤンキースで大活躍できているのです。
主観的に生きる
百歳以上の方について調べてみた特徴は「依存心をもたない」生き方であることを、健康クラブの例会で教えてもらいました。「依存心をもたない」を別の表現に言い換えますと「主体的に生きる」ということになると思います。また、「主体的に生きる」とは「自らの考えに基づき行動する」ということになり、それは「主観的な考え方」に通じ、自分の主観で行動するということは、自分本位の思考につながります。こう書きますと、一見「わがままな生き方」を追及するという意味に解釈されそうです。
だが、人生百歳も生きて元気なのですから、決して「わがままな生き方」だけではないと思います。何かのセオリーがあると思います。
横尾忠則氏という69歳の今でも旺盛な制作活動をしている人物がいます。横尾忠則という人物のイメージは、グラフイックデザイナーとして世に出、その後、画家に転進し、人生というマラソンコースを全力で疾走しながら息切れしない人と思っています。その横尾忠則氏が自らの生き方を次のように語りました。
「自分の長所も短所もひっくるめて知り、活用すると生きやすい。資質が社会に向かって開かれたとき、のびのびと仕事ができるのではないか。つまり、自分の性格に従うことであり、人生にはゴールがないと思うこと」と言い切ります。
これにもなるほどと思います。仕事の成果や死を気にしないで、自分の主観で行動することが社会から受け入れられることになるというのです。つまり、自分が好きなことで、自分の思うままに行動して、それが世間から受け入れられていくという意味です。
言い方を変えるならば「わがままな生き方」ですが、その生き方が受け入れられるというのですからその生き方内容は世間的に「わがままな生き方」になっていないのです。
ということは実は「社会の動きと自分の資質の間に違和感が生じていない」という意味になり、それは横尾忠則氏が描いている目標と今の時代との間に乖離が少ないということになりますので、自分の力を100%発揮できる状態におくことが生きるコツだといっているのです。
自分の能力を100%引き出して生きることは難しい。これが普通の人の考え方です。しかし、松井選手は100%理論を実行していますし、横尾忠則氏も同様です。この世で自分の姿を100%引き出せたら幸せと思います。すべての人は何かの分野で社会のお役に立つ能力を持っています。ですから100%理論を目指したいと思います。以上。
(次の三月五日号は、海外出張のため休刊いたします)
2006年02月05日
ルールをつくれるか
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年2月5日 ルールをつくれるか
日本経済の状況
「昨年2005年は日本経済にとって、先行きの見通しが明るい、希望にみちた年であった。多くの企業が創業以来の最高収益を記録し、株式市場はバブル期以来ともいえる活況を呈し、日経平均は年間40%もの上昇を示した。失業率の低下は数字的にはそれほどではなかったものの、大学新卒への求人数がバブル期なみになるなど、雇用環境は明らかに好転した。銀行の不良債権問題は、人々の話題にも上がらなくなった。つい数年間までは、企業・銀行の決算時期のたびに3月危機、9月危機が喧伝されていたことを思い起こせば、まったくの様変わりである。日本経済に残されたのは『デフレ脱却』という課題である」。この内容は専修大学野口旭教授の見解です。
これに多くの人が頷くと思いますが、勿論、反対する論者も多数います。しかし、元企画庁次官の赤羽隆夫氏は、この反対論者に対して「十数年に及ぶ長期低迷を体験したので、人々が確信を持ちにくいのも無理はないが、拡張力は相当に強い。基本は借金、労働力、設備のデフレ3兄弟によるハラスメント(苦痛)がなくなり、バブルの後遺症がほぼ癒えたこと。もうひとつは景気対策はやらないと公言した小泉経済政策の不作為が寄与した」と語り、デフレからの脱却も間違いないと断言します。
このように日本経済の順調さを経済専門家が述べ、それらのコメントを日本国民の多くが受け入れていますが、このような短い内容で一つの国についてコメントできるということは、やはり日本は単一民族であり、分かりやすい国といえると思います。
アメリカの複雑さ
NYを訪れジョンF.ケネディ国際空港からマンハッタンまで、両サイドの道筋はビルの立ち並びと、レンガ壁に鉄階段、消火栓、下水溝から吹き出す蒸気、お馴染み「ビックアップル」風景が続きます。だが、その風景の中味は簡単には理解できません。
理解できないことは、街中で歩くとすぐに分かります。人々の顔が皆違って、国際的すぎるのです。移民の数が多く、100の国籍を持つといわれ、あらゆる言語が飛び交っている上に、住民が出身地区ごとに共同体を構成しているアイルランド人地区や、リトルイタリア、チャイナタウン、ユダヤ人、アフリカに韓国地区、更にプエルトリコ人は飛び地を構成していて、ひとつの文化で括れません。
更に、アメリカが日本ともっとも異なるところは人口です。人の数が日本の2.4倍であるという単純な意味でなく、人口が増え続けているという意味で反対なのです。アメリカ国勢調査局の推計によると、1月現在の人口は29,790万人で、毎月19万人程度増えていっています。8秒に一人の赤ちゃんが生まれ、31秒に一人のペースで移民が増えているのです。つまり、赤ちゃんの誕生と移民の流入が人口増加の要因で、今年中には3億人を超えるのは間違いありません。これが日本と根本的に異なる背景条件の違いです。
そばが受け入れられている
マンハッタンの真ん中のホテルロビー、ここで打ち合わせすべく相手を待ちながら、周りの人々を見ていると、大抵は大きな声で喋っています。特に身振り手振りで激しいのは、隣の椅子に座った中国系女性二人です。最初は白人男性を交えて書類を広げて話していましたが、その白人男性が去ってからは二人の間でケンカ腰の会話が続いています。書類を指し、手で書類を叩き、激しい言い合いは戦っているとも思える激しさです。
一方、こちらは静かなものです。NY在籍一流企業幹部との打ち合わせは、お互い穏やかな世間話から入って、こちらが提案書類を読み上げるのも静かで、スムースな質疑応答が終わると、相手が昼食に誘ってくれました。親切です。この企業へ提案するためにNYに来たのが最大の目的でしたから、友好的雰囲気で終わりホッとし、誘われた近くの日本そばレストランへ参りました。
ちょうど12時の昼食時、入ってビックリ超満員です。予約してくれていたのでテーブルが確保されていましたが、真ん中の相席専用席も埋まっています。日本人らしき人もいますが、殆どは近くのビジネスマンと見受けました。店内案内係りに聞いてみますと、昼間はいつもこの調子で満員との事です。そばを箸で巧みに食べています。違いは「そばが短く量が多い」という程度で、汁も関東で普通に出される濃さの味です。そば粉はカナダの専用畑で収穫していると、店のチラシに書いてあります。
国の運営ルール
NY州当局が推計したウォール街の金融機関が支給した、昨年ボーナス総額が発表されました。これまでの最高だった2000年を20億ドル上回る215億ドル(2兆4600億円)に達しました。ネットバブルの最盛期を上回る水準で、一人当たりも前年比10%増の12.5万ドル(1400万円)と過去最高を示しました。ですからNYの景気はよいのです。安くはないそばランチにビジネスマンが殺到するのも、このような実態からかと納得します。
しかし、同じタイミングに報道されるのは、アメリカに住む16歳以上の男女のうち
20人に1人は、英語が読めないという事実です。これはアメリカ教育省の「2003年読解力調査」から判明した事実ですが、約1100万人の国民が国語としての英語を理解できないということに驚きます。ヒスパニック系やアジア系がその該当人種との事で、対策として公立学校の改革を推し進めるとの事ですが、これは大変と思います。
言葉で伝え理解してもらうことが、お互いの前提行動です。そのお互いの理解が進まない環境では、結果は不十分な内容になります。国の政策も、人との関係も、すべてはお互いの理解度で決まっていくので、そのためには共通言語が必要ですが、それができない人たちが増えているという事、それは移民が増加しているからで、その増加で人口増が図られている国の運営は難しいと感じます。
したがって、言葉とは別の運営ルールが必要であり、それが暗黙裡に存在しているのではないかと強く感じます。言葉ではない国の運営ルールがあるのではないか、と思います。
文化を伝える
「ぬりえNY展」を開催するに当たって、最も注意しなければならないのは、この「言葉ではない国の運営ルール」の確認であると思いました。100もの人種が一緒に生活していて、それらの人々が一人一人異なった行動をとりつつも、人々の底辺にあって、アメリカとして一つの国運営している何かがあって、その何かがアメリカの底辺に共通部分として存在し、アメリカの国運営を支えているはずです。それをつかみ整理し、そこから「ぬりえNY展」を伝えていくことが絶対要件と感じました。
では、それは何か。それが実は分かり難く、そこに苦労しているところです。言葉でいえば「きいちのぬりえをアメリカ人が理解し納得する論理」という事になりますが、それをつかむためには、アメリカ人の立場に立った論理構成が必要になります。しかもそれには英語も話せない国民が20人に1人いて、ケンカ腰の打ち合わせが当たり前で、その一方では過去最高のボーナス支給を受けている、というように混在している実態の中でつくりあげる必要がありますから、ある一人の見解を聞いて、それでもって論理構成するということでは、多くの人に対応することができず、不十分な成果で終わります。
仮にそのところを割り切って、昼食に日本そばレストランを訪れるマンハッタン中心地のビジネスマンのみを対象にする、ということも考えられますが、それでは限られた層に対する理解だけで終わり、今後の展開に影響が出てきて将来に問題が残ります。
アメリカは日本と違って、多くの複雑な価値観で構成されている国家なのです。
ルールをつくれるか
村上隆というアーチストがいます。現代の日本人で最もNYで成功した一人です。その村上隆が次のように語っています。「アメリカに行ってみたら、自分が常につぶやいていた日本のアートシーンなんて誰も知らなくて、まったくの意味のない、関係のないものに過ぎなかった。そうか、アメリカのルール=ニューヨーク・アート法というのを勉強しなければ、僕はアートの世界で生き残っていけないんだ。そう身に沁みて自覚したのが起点だった」更に「アメリカ人の中に、『無意識のうちに日本のサブカルチャーを刷り込まれていた自分は実は日本人だった』という記憶を呼び覚ます形の『勝ち負け』とはまた異なる意味での記憶の継承追及が必要だ」と語っています。この村上隆が追求し成功したことを今年9月開催の「NYぬりえ展」で可能か。それが今一番の課題と考えています。以上。
2006年01月20日
2006年1月20日 時代の大きな流れに投資する
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年1月20日 時代の大きな流れに投資する
地球はFLAT
時代の最先端にいることをLeading Edge(リーディング・エッジ)といい、そのエッジ(Edge)から見える景色(世界)をEdge View(エッジ・ビュー)といいます。
人は目の前に展開する出来事、その景色状況を自分の文脈で判断・行動し、自分の未来を創っていきます。従って、妥当な文脈判断の連続ならば、未来は妥当な姿になっていきます。だが、眼前の景色は帆船で、つまり、動力は風任せですから、一般的には「景色は見えても実態は風のようにつかみ難い」状況になっています。ですから景色の意味が分からないままに、自分の文脈で解釈し行動することになります。
パリの主婦から年賀状をいただきました。フランス人と結婚した日本女性で、パリで一男二女に囲まれて子育てに忙しい日を送っていますが、ハガキに長男が「先週の土曜日に友達五人と、シャンゼリゼのシネマで『キングコング』を見て、その日はバスチーユに住んでいる友達の家に泊まってきました」とあります。もうそのような年齢になったのかと驚くとともに、このハガキにJR秋葉原駅ホームで見た「キングコング」映画ポスターを重ねました。
「キングコング」は、最初昭和29年(1954)に制作され、当時一年間で961万人の動員力を示しました。その後もシリーズ化し、全部で28作品9960万人の観客動員数ですから大成功です。今やアメリカでもフランスでも世界中で人気です。
「キングコング」の人気がなぜ続いているのか。それは人々が「キングコング」を
Edge Viewとして受け止め「キングコング」の登場を最先端感覚Leading Edgeとして見て、そのことを暗黙の了解事項としているのではないだろうかと、月刊ベルダ誌の編集長に話したところ、「世界の旅先で見る景色、その中で Edge
Viewと考えられるものを取り上げコラムにしませんか」となって、来月から「地球はFLAT(フラット)」というタイトルで連載することになりました。
フラットと題したのは、世界中の人は階級差なく生きていくべきだ、という想いからですが「景色は見えていても、その背景実態は風のようにつかみ難い」状況の解明について、少しでもお役に立てばという気持ちで、コラムを書いて参ります。山岡鉄舟と併せて連載で忙しくなりますが、何とか挑戦していきたいと思っています。
フランスを救った日本の牡蠣
2月5日(日)14時から15時25分のテレビ朝日系列全国ネットで、「遥かなるオイスターロードの旅」が放映されます。この中で著書「フランスを救った日本の牡蠣」が紹介されることになりました。
昨年の夏開催された世界牡蠣フェスティバル会場で、テレビ朝日の制作担当者が「フランスを救った日本の牡蠣」を片手に、名刺交換に来られました。用件は、宮城県牡蠣が世界に受け入れられ、世界の人々に食されていることを、ドラマ化したいので協力してほしいという内容で、この本の中に出てくる場所と人物を紹介してくれということでした。大変うれしいことで、早速情報提供いたしまして、現地ロケを終えて今回の放映になったのです。
この本は2003年9月に出版したものですから、もう3年を過ぎましたが、世界牡蠣フェスティバルの会場で名刺交換した殆どの人が、名刺交換すると「あー。あの本の著者ですか」と頷きます。牡蠣業界でこの本は知られていることが、昨年夏の世界牡蠣フェスティバル会場で分かりました。
知られている要因は、フランスの牡蠣実態について網羅していることです。一般人が牡蠣を食べる楽しみの実態から始まって、レストラン、エカイエ、市場、養殖者、研究者へのインタビュー、加えて学術的な分野まで網羅しているところに価値を認めてくれているようです。牡蠣は昔から好んで食され、特にフランス人の牡蠣好きは世界でも知られた存在なのに、それらの実態をまとめて情報提供できる資料がなかったところに、この本が登場したのです。その意味で新鮮な内容であると受けとめられ、牡蠣業界に少しはお役に立っているようで、その証明が今回のテレビ朝日放映となったと思っています。
3年前に出版したとき「誰がそんな本を読むのか」と、心配してくれた人もいましたが、今でも牡蠣関係者に参考にされている事実が分かり、専門書というものの息長さを感じています。売れる本を書くのではなく、まだ世の中に無い内容を書いていく。という方針の一環から「フランスを救った日本の牡蠣」を出版し、その姿勢が今回のテレビ放映、それも全国ネットに取り上げられたことを喜んでいます。
また、時代の流れ逆らっていなかったテーマであったこと、その確認が3年過ぎにできほっとしています。
加えて、昨年末から世界10カ国に取材を始めた「世界牡蠣事情」、その2007年出版に向けて励みになりました。
協力を得る
昨年秋ごろから新しい仕事が増え、一段と忙しくなりました。不思議なもので忙しくなると、更に依頼が続いてきます。今朝も経営者向けの雑誌社から原稿依頼が来ました。ありがたいことでご期待にお応えしたいと思いますが、そのような機会が生ずる縁は、多くの方と日ごろお会いしているからこそ生まれるものと思っています。
すでに何回かお伝えしておりますように、今年の9月にNYでぬりえ展を開催いたします。日程も場所も決まって、後はその日のために準備するだけですが、開催するためにはお金の手配が必要で、これが最大の課題です。
どのようなすばらしい企画でも、それを実行するためにはお金が必要です。まして、それがNYでの開催となると、個人的な範囲を超える多額の資金が必要になります。ですから、企業に協賛をお願いすることになります。勿論、文化活動を支援してくれる公共的組織にもお願いしますが、企業という力にご協力を受けないと開催は難しいというのが実態です。そのような背景から、今年に入ってNY展のために企業訪問いたしました。これも忙しくなった一つの理由ですが、開催を最も楽しみにしているNY展ですから、お会いいただく経営者の方にご説明とお願いに参りました。
結果は、おかげさまで多くの企業からご協力賜りまして、来週から現地NYで開催実務打ち合わせができることになりました。
企業経営者の方々にご協力をお願いするためには「なぜNY展がその企業と関係あるのか」という基本的な意味づけの説明が必要になります。誰も関係なく、意味もないところにお金は出しません。大事な資金提供をいただくわけですから、その開催趣旨が該当企業にとって「なるほど」と思う論理性が絶対要件です。
また、この論理構成に加えて、今回の開催が時代の流れに合致していること、その理解を得ることが絶対要件です。つまり、ご協力していただくための最大ポイントは、こちら側からの説明力に存在するのです。企画をつくり、お願いに行くこちら側の脳力にかかっているのです。相手に理解していただくためには、自らの工夫がまず先です。NY展の開催・成功のためには、こちらの論理性・時代性を磨くという努力にかかっています。
「主因は内因にある」。これは脳力開発の指針ですが、まさに、この指針がこのような大規模企画成功のために最も大事で必要なこと、それを今回の企業訪問で再確認いたしました。
時代の大きな流れに投資する
日本経済が最も活力に満ちていた時代に生きたはずの団塊の世代サラリーマン。その人たちが定年間近になって、総額50兆円ともいわれる退職金の動向が注目を浴びていますが、同じ世代で豊かさの二極化が進行していたと、日経新聞が発表しました(2006.1.8)。男性649人、女性102人、合計751人のアンケート結果ですが、金融資産1千万円未満が世帯のほぼ半数いるようです。だが、金融資産が2億円超える人もいて、その人の回答は「時代の大きな流れに投資してきた」という基本姿勢です。なるほどと思います。金融資産でもってすべてを判断できませんが、一つの過去の生き方目安になりますし、時代の大きな流れに逆らっていたら、資産は構成されなかったでしょう。キングコングの国際的活躍も、フランスを救った日本の牡蠣のテレビでの紹介も、ぬりえNY展開催も、すべては時代の大きな流れに沿っていないとうまくいかないと思います。 以上。
2006年01月06日
2006年1月5日 見える化
環境×文化×経済 山本紀久雄
2006年1月5日 見える化
明けましておめでとうございます。本年もよろしくお願いいたします。
NYタイムス記事の反応
前回レターでご紹介した、昨年12月21日のNYタイムス記事「アジア人ライバル達の醜いイメージが、日本でベストセラーに」に関して、いくつかご意見をいただきました。 皆さん、それぞれご見解をお持ちで、なるほどと思います。
ところで、元旦の日経新聞第一面で、今年20歳になる大学生千人に「あなたの嫌いな国はどこですか?」と聞いた結果は、1位中国43.7%、2位韓国28.7%と掲載されました。継続的データがないので確定的には言えませんが、この両国に対する感情は、最近では最も高いものではないでしようか。ある意味のナショナリズムが台頭していると思います。その要因はいろいろあり、それらの要因に頷けるのですが、あるひとつの立場に頑固にならないようにしたいと思います。
常に自己を相対化し、客観視し、時折自分を見つめなおすという作業が必要であると思います。一気に過熱する、というのは危険だと思います。
2006年の景気
日本はバブル崩壊という傷口をようやく治療し、再び日本経済は反転を示すタイミングに来た、と主張するのが三菱UFJリサーチ&コンサルティング投資調査部長の嶋中雄二氏です。嶋中氏から「日本経済の現状と今後」について、昨年12月詳しくにお聞きしましたが、そこで述べられたことが元旦の日経新聞にも掲載されました。
「2006年はゴールデン・サイクルに突入する。景気循環を示す短期の在庫循環(3―4年)、中期の設備投資循環(10年前後)、長期の建設投資循環(20年)、そしてコンドラチェフの長期波動(60年)、この波長の異なる四つの循環がすべて上昇に転じる」まさに、日本は「好況の時代」を迎えるという分析内容で、嶋中氏から頂いた諸データからは、このような動向がうかがわれます。しかし、ここで気をつけなければならないことは、すべての部門、すべての人々がこの「好況の時代」を謳歌することにはならないという事実です。日本の産業構造がかつてとは異なっている事実です。
国際収支の現実を見ればそのことがよく分かります。2005年度上期の貿易収支額
4.9兆円より、海外からの利子・配当の受け取り超過額を示す所得収支5.7兆円の方が上回っているのです。この実態が示す意味は、今や日本は他国では作れない高品質の製品輸出で稼ぐ一方、投資や金融で稼ぐ投資立国への道を歩み始めているということです。
貧乏敗戦国として再スタートした日本が、還暦を越える66年を経て、産業構造改革を行って、新しい意味での豊かな国に変わろうとしているのが今なのです。
ですから、今までの思い込み・思考を変えねばならないタイミングに、すべての人が立っていると思います。何故なら、「好況の時代」を謳歌するのは、その「好況の時代」に相応しく合致する知識体制・行動システムを、創りあげることができるところであり、それを実現できた人のみが、より高いリターンを獲得してしまうからです。
言葉を換えて言えば、「格差のある好況の時代」が到来しているのです。
人口減社会
元旦の新聞は一斉に日本の人口減を取り上げています。昨年が近代に入って初めての人口減を示した年であり、予想より早く来たことのショックから、いろいろな対策案が提案されています。しかし、諸対策を直に進めたとしても、出生率が格段に低いわけですから、それが上昇しないと人口は増加しません。竹中総務大臣がテレビ討論会で「人口減社会への突入は30年前から分かっていたが、30年間有効な手段を準備しなかった」と述べている通り、何年もいたずらな出生率予測の誤差を行ってきたことも含め、対策が後手に回って、今になって問題視しているのです。
まず、この人口減対策は簡単には解決つかない、という視点が大事です。また、対策は超長期戦になりますので、その間、別の短期対策視点が必要です。
短期に、直にできることは、今生きている我々ができることです。つまり、我々が変化することが必要なのです。では、どの方向に変化するのか。それは「生産性を上げる」ことしかありません。このようにお伝えすると、今でも忙しいのに、更にスピードアップするのか、という疑問が持たれると思いますが、そのような内容ではありません。
人口減対策として、国全体の産業構造の見直しとか、規制緩和とか、非効率な公共部門の民営化とか、海外からの優良な人々とマネーの呼び込みとか、それらの政策的なことは、政府が音頭をとって行っていき、長期的にその方向に動いていくと思います。ですから、我々一人一人が人口減対策として行うことは別のところにあります。
それは、一人一人の持てる力を、一人一人が自らの変化で、最大限に発揮させることです。人は皆すばらしい財産を持っているのです。ただ、それを発揮していない人が多すぎるのです。発揮しないようなシステム環境下に、自分で自分を置いているのです。
そこから一人一人が脱皮すること、そのために考え方を変化させること、それが人口減対策の本筋であると思います。
愛知万博の成功
昨年の最大のイベント成功は愛知万博であると思います。開幕前と開幕直後は心配されました。だが、時間が経過するにつれ集客があがってきて、結果的には2205万人、目標1500万人に対し147%もの人が入場しました。
万博には大変関心があり、日々入場者数を記録していましたので、よく分かるのですが開幕直後は1日6万人と不調で、5月から1日10万人になり、8月は13万人、とうとう9月は1日20万人と、当初の6万人に対し三倍になりました。
このように好調となった要因について、閉幕となった9月25日以降、ずっと考えていましたが、ハッキリした結論は得られませんでした。
ところが、先日、愛知県館の総合プロデューサーの山根一眞氏の発言を聞いて、ひとつ理解が進んだことがあります。一言で言えば「時代の思考が変わった」ということです。
山根氏は「今までのモノづくりは、資源もエネルギーも永遠にあるという前提でやってきた。その意味で、あらゆるモノづくりは、産業革命から全然変わっていない。電気も発電所でつくっている。それを愛知万博の政府館とNEDOパピリオンでは、会場内のゴミから発電して賄ったのであり、それは『環境革命』の実践であった」と述べたのです。
すべての基本になる動力源の電気を、自らの会場内から創出するシステムにしたのです。この万博会場内で使用する電気を、会場内で産出したということ、つまり、自らが持つ中味から基本的な動力源を作り出したということは、人に例えれば、一人一人の持てる力を最大限に発揮させることで、自らの新しい能力を生み出すことであると考えられるのです。
このことを未来の地球環境を心配する、多くの日本人に直感的に理解されたのではないでしょうか。今の環境問題の本質は自分たちにあると分かったのではないでしょうか。
それが愛知万博の成功に結びついた、真の要因ではないかと思っているところです。
自分の中に何があるかの旅をする
正月二日は近所の四家族が集まって宴会をしました。一年に数回集まって宴会します。
今回のホスト役は、昨年春、霞ヶ関のある官庁を定年退職した高級官僚だった人物です。
キャリアの上級職は、一般的に定年前に天下りするのが通例で、それが社会で問題なっているのですが、このホスト役人物は天下りを拒否し、定年を迎えたのです。四家族とも、それぞれ異なった職業経験であり、まだ定年前の人もいまして、話題が豊富で、様々な会話が交わされ楽しい一時でした。時間も過ぎてそろそろ終わりかけた時、ホスト役から質問を受けました。「山本さん。定年後の生き方について教えてください」。
先輩のこちらに尋ねてきたのです。そこで、日頃皆さんにお話していることですがと言いまして「自分の中に何があるかの旅をすることではないでしょうか」と答えました。
これに対するホスト役は「うーん。なるほど。そうか・・・」と暫く腕組して宙を見上げ「分かりました」の発言。とても嬉しい正月二日でした。
見える化
トヨタの成功にはトヨタ式経営があり、そのひとつの「見える化」は、問題発生を隠さずに見えるようにする改善運動です。これは人にも例えられます。自分の中に何があるかの旅をして「見える化」すること、それが人生という仕事ではないでしょうか。 以上。
2005年12月23日
クールジャパンの背景
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年12月20日 クールジャパンの背景
NYタイムス記事
NYタイムス一面に掲載(2005年11月21日)された記事をご存知でしょうか。英語のタイトルは、「Ugly Images of Asian Rivals Best Sellers in Japan」ですから「アジア人ライバル達の醜いイメージが、日本でベストセラーに」と訳せます。
最初の書き出しに「若い日本女性が“今の韓国をつくったのは日本だ、と言っても大げさじゃないわよ!”と声高に叫んでいる」とあり、「今の中国を見て御覧なさい。中国の根本的な本質、思想、文学、芸術、科学、制度、どれをみても魅力的なものなど何一つとしてない」と続け「日本人が中国人と韓国人を見下して、対立を扇動する内容のマンガ本二冊が日本でベストセラーになっている」という紹介記事です。
NYの知人がこの記事を翻訳して送ってくれたのですが、日本ではあまり関心高く取り上げていないようです。しかし、先週オーストラリア・シドニーで、日本人向けの週刊情報誌を見ましたら、この記事が紹介されていました。このような記事は、外国人が日本をどう見ているか、という意味で参考になる記事と思います。
ご興味ある方はご連絡いただければ、翻訳記事をご提供いたします。
日本のギャップ
日本人が外国へ行く人数は2004年実績で1683万人。これに対して外国から日本を訪れる人は614万人で、世界32位という低い実績です。
しかしながら、日本の人気は高まるばかりです。車、IT機器、アニメ、寿司、ラーメンなど「クール・ジャパン」と呼ばれる新しい「かっこよさ」で世界に広がっています。
シドニー市内の、最もロケーションのよいビル三階に紀伊国屋書店があり、そのマンガ売り場では少年・少女達が床に座って読みふけっています。紀伊国屋の前はラーメン専門店「一番星」ですが、昼時には入り口予約用紙に名前を書いて待つ人が20人はいます。同じテーブルに相席させ、レジで支払うスタイルですから、食べ方もシステムも日本式です。二階に降りると「日本屋」という看板の陶器とお茶の専門店があり、経営者は香港の若いカップルですと、日本人女性店員が教えてくれます。地下の回転寿司もシドニーっ子でいっぱいです。
これはシドニーだけでなく、NYでもパリでも同じでした。現地・現場・現認した事実です。ですから、他の都市でも同じ実態と思います。
しかしながら、このような人気が高い日本ですが、実際に日本を訪れる人は少ないのです。このギャップをどのように考えたらよいのでしょうか。
日本経済のギャップ
日本経済に対する考え方にも内外差が大きく発生しています。2005年9月14日に内閣府主催の日米経済学者会議があり、そこでの米コロンビア大のデビッド・ワインシュタイン教授発言にはビックリしました。「日本の財政赤字はそれほど深刻でなく、すでに危機は去った」と語り、日経新聞・経済教室欄(2005年11月29日)で「日本国民は竹中平蔵という経済改革のよき指導者を持てたことを幸運だと考えるべきだろう」と主張しました。
これに対し、内閣府の林伴子参事官は、出生率の低下、財政赤字の実態、介護医療費の増加要因をあげて、日本の財政は安心できないと、内閣府主催の同会議で反論しました。
2002年に米格付け会社が、日本国債を格下げし、アフリカのボツアナより下にランクしたときは、日本政府は外貨準備高や個人貯蓄高などをあげて、日本は危機に瀕していないと反論しました。ところが今は、海外の方が日本経済について楽観視しています。外国人の日本株買い越しは過去最高であり、ドイツは総選挙の結果がしめすように、国民が改革を支持しなかったのに、日本国民は小泉政権の改革を支持したと高く評価し、フランスからは日本の租税負担率が低いので、まだ上げる余地があるのだから心配ない、というように数年前とは全く攻守ところをかえた、日本経済議論が展開されている実態です。
しかしながら、日本国民の多くはまだ経済について心配しているのも事実です。
稲盛経営哲学
京セラ名誉会長の稲盛和夫氏は、次の方程式で「考え方」の大事さを強調しています。
仕事の結果=考え方×熱意×能力
この単純方程式の中に稲盛哲学が入っています。熱意と能力の前段階に「考え方」が位置づけされているのです。ですから、最初の考え方に間違いがあれば、いくら熱意と能力があっても、仕事の結果は全然ダメになるというのです。最終結果として、経営数字やお金を求めたかったら、その経営者の心理や人生観が決めるといっているのです。
この稲盛哲学方程式は何でも適用できると思います。例えば、オーストラリアでは20年前まで大腸ガンが多く、その当時、世界を見渡したところ日本は少なかったので、日本を研究したら、日本人は魚を多く食べるということが分かって、それから魚を食べることを広めだしました。結果は、今のシドニー・フイッシュマーケットが示しています。
今やシドニー・フイッシュマーケットは、日本の築地に次ぐ多種類の魚介類を扱い、近代的なIT機器による活発な競りが行われており、それらを見ると、オーストラリア人が魚を食べていると分かります。ガン予防を起点に「魚を食べるという考え方」に変わったのです。
稲盛哲学は日本車にも適用できます。米ゼネラル・モーターズ(GM)の経営危機が伝えられていますが、一方、日本車は快調で、オーストラリアでもトヨタがシェアトップです。
アメリカは車の母国なのに、どうして弱体化したかについて、ホンダのトップだった雨宮高一氏が次のように語りました。答えは単純シンプルです。「まじめさが足りなかった」の一言です。この「まじめさ」とは「継続性」と読み替えてもよいと思います。
製造業研究の第一人者である藤本隆弘東大教授は、宮本武蔵の「千日の稽古を鍛とし、万日の稽古を練とせよ」を引用して、日本の製造業の本質を語っています。地道にひたすら改善を積み重ね、自社の能力を高めること。これが大型買収や華麗なブランド戦略を上回る威力を発揮させて、結果としてジワジワとシェアをとっていく。今やトヨタ式改善活動は、オーストラリアの田舎町企業の壁に「KAIZEN」と書かせるまでの、世界標準になっているのです。「改善活動という考え方」が世界を制したのです。
クールジャパン
今、世界は日本のことを「流行を次々と生み出すかっこいい国」だと思っている。これが世界の日本を見る常識になっているといえます。確かにNYでも、パリでも、シドニーでも、日本のアニメとマンガと日本食は憧れの的です。最初にNYで、ラーメン店にアメリカ人が並んでいるのを見たときは驚きました。次にパリで同じ状況を見たときも驚きました。しかし、シドニーでラーメン店に入って、食べながら入り口に20人以上並んでいる情景を見ても、もう驚きませんでした。それは眼が慣れたのではなく、日本が持っている魅力内容を理解でき、その視点でラーメン店に集まる外国人を、見つめることができたからです。
外国人は日本商品のすばらしさを、正しく妥当に認識しているのです。日本車が何故人気あるのか、それを現地で聞いてみれば分かります。ガソリン価格が急騰して、燃費のよい、修理の少ない車を求めるのが常識となっているのです。デザインや華やかさよりも、商品の目的に合致した実質価値を選択基準とすれば、当然に日本車が評価されていき、その背景には、それらを創りあげてきた日本人を評価することにつながっていくのです。
日本人に対する考え方を変えたのです。考え方を変えたポイントは「まじめさと緻密さ」への評価であり、継続的努力を続けることのできる国民性への理解です。
だが、しかし、社会経済性本部が発表した「国民の豊かさの国際比較」2005年版を見ますと、国民一人当たりの国際観光収入は、比較対照のOECD加盟30カ国の中で最下位です。一位のルクセンブルグは約97万円、それに対し日本は1.4万円。全く話になりません。かっこいいと思われているのも事実なら、外国人が訪れてこないのも事実です。
外国人が来ない理由はいろいろ挙げられますが、その大きな一つとして「住んでいる外国人が少ない」ことを指摘できます。自宅の周りを見てください。外国人は殆どいないでしょう。先進国では珍しい実態です。何故住んでいないか。それは住めないように規制があるからです。親戚が多い国には観光に気楽に行きやすいのですが、その反対は訪問し難い国です。
日本のクールジャパンの背景は、緻密な国民性と、その緻密であるが故に排他的な国民性、その両者が存在しているのではないか。その指摘がNYタイムスの記事ではないか。このようにシドニーの街中を歩きながら考えた、今年最後のYAMAMOTOレターです。以上。
2005年11月20日
分かりやすさ
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年11月20日 分かりやすさ
小泉首相の分かりやすさ
9月11日の衆議院選挙は時代の分かれ目でした。この日まで毎日のようにマスコミを賑わしていた亀井静香氏が、選挙が終わるとパタッとマスコミに登場しなくなりました。
替わって登場してきたのは、新しい閣僚の下で進められている、日本の構造改革への話題で、国と地方の税配分見直し三位一体改革、人件費削減を目指す公務員制度改革、政府系金融機関の統廃合改革、医療制度改革などが、毎日のように新聞一面を賑わしています。
選挙前における亀井氏の考え方は「郵政民営化解散したら、自民党が分裂するし、民主党を有利にするばかりでなく、細川政権が誕生したと同じく、民主党政権となりかねない。だから解散はありえないし、小泉首相は総選挙を脅かしにして、郵政民営化を成立させようとしている」というものでした。この考え方に結構多くの政治家や政治評論家も同調していましたが、結果はご存知の通りです。
総選挙が終わり、内閣組閣直前のタイミングに、ベテラン政治評論家としてテレビでよく見かける、毎日新聞顧問の岩見隆夫氏からお聞きする機会がありました。岩見氏は「小泉さんは分かり難い政治家だ」といい、「まともに考えないほうがよい」「自分は政治記者として40年以上関わっているが、小泉さんは分からない」との発言、続いて「だから内閣の顔ぶれは予想できない」という政治評論家としての職務を放棄したような、一種の諦めに似た感じでした。つまり、過去の永田町事例からは判断できない、それが小泉首相だということです。
ところが、小泉首相の方は「最初から郵政民営化がダメならば解散すると言っていた」と明確です。方針・方向性はぶれていなかったのです。しかし、亀井さんを中心にする「自民党的なるものを」守る人たちは、これをまともに受け取らず、更に郵政民営化反対に拍車をかけてしまい、ドンドン突っ走ってしまい、読み違いもここまでくると悲劇で、無残な結果に終わりました。
悲劇の最大の要因は時代の動きへの感覚誤差です。時流を見誤りました。その上、小泉首相の「言葉の文化」に負けました。小泉首相はシンプルに明確に国民にメッセージを送りました。それは「郵政民営化を議会はどうしてもダメだと否決した。しかし、私はどうしても理解できない。だから、国民の皆さんに聞いてみたいのです」と、解散した直後の総理大臣記者会見で述べたのです。それも、思いつめた顔をし、毅然とした表情でした。
これをテレビでみた多くの人たちに、どのように受け止められたかは明らかです。テレビでは「どんな顔して話すか」がテレビ視聴者をつかむコツ・ポイントで、それを小泉首相は心得ている上に、内容が「シンプル・明確」なのですから、今から考えると、この時点で今回の勝利が決まったと思います。
ゴーン発言の分かりやすさ
日産自動車のカルロス・ゴーン社長が、日経フォーラム「世界経営者会議」(2005年10月24日)で、日本での企業経営体験を語りました。
● 日本から多くのことを学んだ。一つは単純な形で実行すること。日本人は複雑さを疑問視し、実行の質とスピードを追及する。二つ目は、プロセスを重視すること。三つ目は、ある一つの強みを他の領域でも生かす考え方。例えば、生産プロセスを販売現場に生かしてすばらしい結果を得られるようにするなどだ。
● 自動車業界は整理・統合途上にあり、有力メーカーが集中している国は、日本、韓国、ドイツ、フランス、アメリカだけだ。その中で日本には規律、プロセス、顧客志向、即応性という基本的な文化環境が存在している。
さすがにゴーン社長は状況把握力に優れ、それを分かりやすく表現できる能力を持っていると思います。特に「日本人は複雑さを疑問視する」という発言、これには納得します。
社会に発生する物事は、様々な要因が絡みあって複雑に表層化し、その表に現れた現象の背景には、多くの要因が存在しています。ですから、物事を単純に理解できないのですが、そうかといって複雑に難しく解釈していくと、それはかえって物事の本質を分かり難くさせていき、結果的に適切な行動がとれず、対応が遅れるということになりやすいのです。更に、ゴーン社長は「日本人は実行の質とスピードを追及する」と発言していますが、その背景に「単純な形で実行する」を好む国民性があるからこそ、「質とスピード」が可能であることを見抜いているのです。ゴーン社長が「シンプル・的確」に日本人を理解し、それを「分かりやすく表現した」ところ、それが日本で成功した要因と思います。
ドラッカー氏の分かりやすさ
ピーター・F・ドラッカー氏が11月11日逝去されました。ドラッカー氏の著書は随分勉強しました。「現代の経営」(1954)「経営者の条件」(1966)「断絶の時代」
(1969)などに影響を強く受けました。分権化、目標管理、知識労働者、民営化、今では当たり前に使われているこれらの言葉は、すべてドラッカー氏の造語でした。
また、日本に対して深い理解を持っていて、特に明治維新に感動し、日本人に対し分かりやすいメッセージを贈ってくれていました。
● 明治維新は人類史上例のない偉業であり、この明治維新への探求が、私のライフワークになったもの、すなわち社会のきずなとしての組織体への関心へとつながった。したがって、日本は私の恩人だ。
● 日本が「失われた10年」で悲観主義にとらわれてはいけない。日本は明治維新、更に第二次大戦後の復興・成長と、二つの奇跡を抜本的な構造改革によって達成した。そうした社会の資質、柔軟性に日本人はもっと自信を持っていいし、もってほしい。
日本人に対するこの励ましは大きかったと思います。日本経済が構造改革を進め始めた結果、踊り場を脱しようとしている現在実態を考えると、ここにもドラッカー氏の日本人に対する、分かりやすい励ましが大きく影響していると思わざるを得ません。
加えて、ドラッカー氏が認識し高く評価しているように、明治維新は偉大な構造改革でした。封建時代の姿を近代日本に生まれ変わらせ、今日の発展の基礎を創りあげたのですから、明治維新は世界に誇る日本人の革命歴史です。現在、山岡鉄舟を研究していますので、必然的に明治維新を掘り下げ分析研究し、そこに鉄舟という武士道体現者をオーバーラップさせることで、毎月の雑誌連載と講演を行っているのですが、そのような立場に至った背景にドラッカー氏の言葉の影響が少なからず存在していたと、今になって感じ感謝しているところです。ドラッカー氏の冥福を祈りたいと思います。
改革の方向性
小泉内閣が進める構造改革と亀井静香氏を代表とする主張、その差はどういうところから発しているのでしょうか。皮肉にも目的は「財政を再建しなければならない」というところでは同じでした。方法論が異なっていたのです。
● 小泉首相は、公共事業削減が国民の痛みにつながることを承知の上で「傷みに耐えてくれ」と財政を絞って、景気回復につなげようとする考え方。
● 一方の亀井静香氏は、それは間違っている。財政支出を絞ると、景気が悪くなる。景気が悪くなると税収が減る。だから、どんどん公共事業を増やすことだ。それが景気をよくするのだという考え方。
両方の主張とも分かりやすい言葉と内容です。だが、国民の判断結果は小泉首相でした。亀井静香氏には向きませんでした。亀井氏の主張方法は、既に過去の歴代内閣が実験済みで、結果は世界一の借金大国にしただけでした。そのことを国民は分かっていたのです。
このまま行ったらどうなるのか。孫子の代に日本はどうなるのか。それをひとりひとりが考え、その結果として時代が変わっていると判断したこと、それが今回の選挙の背景にあったと思います。
その背景とは時代への認識です。日本の未来は二つの大きな変化に立ち合っています。一つは少子高齢化であり、それは人口減という事実です。もう一つは財政赤字770兆円という、日本国の一世帯あたり2000万円にも及ぶ借金の額、これは誰が考えても政治の失敗でつくってきた事実です。
この二つの時代認識が、今回の選挙の背景にあり、その認識から容易に考えられるのは、もうかってのような政治、それは「日本全国すべてを均衡させた発展」と「行政に多くの支えを期待する」を望むことは困難、という事実です。
この誰にでも分かる日本国の実態が、今回の選挙で分かりやすく国民に認識されたこと、つまり、分かりやすさということが、国民に時代の方向性を決めさせたと思います。以上。
2005年11月04日
時代を読み、時代と闘う
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年11月5日 時代を読み、時代と闘う
衆議員選挙結果の論評
小泉第三次内閣がスタートしました。先の衆議員選挙結果を受けての改造ですが、その選挙について、前々回のレターでご紹介した藤原直哉氏の見解、それは大手新聞社が選挙前に「与党有利」と報じたのは、「大新聞はアメリカにいわれ情報操作している」であると言い切ったのですが、結果は大外れでした。事前の新聞予測報道が正しく、藤原直哉氏見解は全く誤りました。この件に関して「藤原氏は結果をどう釈明しているのか」という問い合わせが多くの方からありましたので、その後の藤原氏の見解をご紹介いたします。
藤原氏が述べる選挙結果は「小選挙区立候補者1131人を、民営化賛成と、反対に色分けして、その小選挙区での票数を集計した結果、民営化賛成3389万票、反対3419万票」(日刊ゲンダイ9月28日)で、30万票反対のほうが多い。だから民意は反対だったという見解です。ですから、選挙結果を見誤ったわけでなく、小選挙区という選挙のあり方・システムの結果で自民党大勝利となった、という主張です。
このように場合には、まず、藤原直哉氏の立場を検証しないと発言趣旨が分かりません。藤原氏の立場は、明らかに小泉政治に対して反対なのです。その立場から分析し、解説しますので最初から判断結果は決まっているのです。小泉政治に対する問題点、疑問点を探す作業をしてから、判断するということになります。良い悪いということではなく、自らの立場から見解を構成しているのです。
ある一つの事実を判断するのは、その人の立場です。ですから、当選者数で圧倒的多数という事実から判断すれば自民党勝利、そうではなく合計投票数でみれば反対という主張になります。人は立場から物事を判断する好事例であり、人の発言は立場からなされる、ということを改めて確認したいと思います。
景気に対する立場の転換
郵政民営化法案成立後の構造改革は、次の四つ、それは●国と地方の「税配分」を見直す三位一体改革、●「総人件費の削減・定員の純減」を目指す公務員制度改革、●政府系金融機関の「統廃合」等の政策金融改革、●「診療報酬」の見直し等の医療制度改革であり、これらの改革を進めていくに当たっては、日本経済の状況が大きな背景要因となっていきます。つまり、景気の動向如何が重要な影響力を持ちます。
その景気については、10月20日の日銀支店長会議で福井総裁が「景気は踊り場から脱却し、回復を続けている」「緩やかながらも息の長い回復を続けていく」との発言をしました。また、経営の現場からの発言として、大丸デパートの奥田会長が「百貨店の売り上げはここ数年、全国平均で年間3%前後、落ちていたが、今年は下げ止っている」(日経新聞
10月31日)と、景気の底割れの不安は遠のいた、という実感を述べています。
これらが景気の全体感を示す発言ですが、一方、地方の商店街に見られるシャッター通りの現実を見ると、景気は回復していないという指摘もなされています。確かにシャッター通りの現実から検討すると問題が多々あるのですが、この見解についても「立場の転換」をしていかないと、景気判断を見誤ることになると思います。
日本の実態感
日本の実態を把握する方法はいろいろあると思いますが、最も妥当で適切な方法は、ある期間、集中的に日本全国を自分の足で観察を続け、自らの肌体験を通じて感じた結果で判断することではないかと思います。あるテーマを持って、そのことに集中し各地を行動する。それを続けていると、次第に自らの感覚、それは意識しているテーマに対する感度ですが、それが鋭角になっていき、その結果として実態を妥当に把握できる。
これは、過去何回も、多くのテーマで調査・研究してきた経験則からいえる事実です。その好適例として『「奥の細道」を歩く』(総集編 日経10月21日)が眼に留まりました。
日経新聞・土田記者が5ヶ月間、142連泊、芭蕉が歩いた道筋を旅した結果の感想を述べた記事です。その中で地方のシャッター通りとして目立ったところとして、矢板(栃木)、白河(福島)、石巻(宮城)、尾花沢(山形)、柏崎(新潟)を上げています。
これは、土田記者が毎日歩いて感じた実感比較、そこから取り上げたのですから事実実態ですので、この目立ったシャッター通りを基準にして判断すると「景気の底割れの不安は遠のいた」(大丸デパート・奥田会長)という発言は妥当でないということになり、この視点から日本経済を問題視する識者も多くいます。
しかし、土田記者は142連泊のまとめとして、次のように述べているのです。
「山村漁村の高齢化も行く着くところまで行った感じだが、●日本は狭くない、●国土は緑一色、●地方は貧しくない――で、いずれも日本の「常識」に反している」と。
これが実際に5ヶ月歩いた現代の日本の実態感覚なのです。更に、その実感感覚から「旅で接した人の多くが、その土地で暮らしていることに強烈な自信と誇りを持っていて、その高い精神性がゆとりを生み、表情を豊かにしている」と断定しています。この土田記者の事実実感をどのように理解したらよいでしょうか。
背景条件が変わった
ついこの間のバブル崩壊前までの日本、その政治の基本は●国土の均衡ある発展、●行政が地域間格差を支える、という方針でした。しかし、これは時代の変化で出来ない相談、ということになっているのが日本の現実です。
時代変化の背景、それは●人口減、●高齢化のスピード、●国家財政超赤字であり、これらが全国一律均衡発展と、地域間格差を支える行政サービスの継続を難しくさせているのです。つまり、日本は時代変化を取り入れた「再編成」が必要不可欠で、その方向性は「選択と集中」となりますが、この時代背景を本当に理解しないと、今の時代を生きていくことは難しいと思います。
大丸デパート・奥田会長は「公共事業に依存する産業構造から抜けきれず、雇用や所得の改善が進まない地区は厳しい」とも発言していますが、この意味は「従来型政治は終わった」という事実を指摘しているのです。ですから、行政には頼らず、自らが所属する地域・地区が、自ら特長を創造・工夫して、解決策を講じていくしかないのです。
しかしながら、時代変化を取り入れないところは、従来型のままですから、当然問題点が浮き彫りになり、それが実態として各地に現出していき、その問題実態に視点を当てる「立場」からみれば「日本経済は回復途上ではない」という判断になると思います。
時代を読み、時代と闘う事例
(智頭町)
8月5日のレターでご紹介いたしましたが、鳥取県に智頭町という人口九千人の町があります。何もないと思われていたこの智頭町に、今は観光客が訪れることで知られ、マスコミにも取り上げられるようになってきました。
ここは前町長の寺谷誠一郎氏が「何もないが、空気と水は綺麗だし、昔の面影が残っている」という素直な街づくりコンセプトからスタートしました。その代表が「石谷家住宅」であり「板井原集落」です。「石谷家住宅」は8月5日のレターでご紹介しましたので、今回は「板井原集落」をご紹介します。智頭駅から4キロ、車で10分、バスはありません。不便です。しかし、ここに行くと「日本の山村集落の原風景を残し、昭和初期から三十年代のたたずまいが色濃く」、スローライフを求める都会の中高年層が「故郷に帰ってきたような安らぎを覚える」と足しげく訪れるようになりました。こうなると、この土地で暮らしていることに強烈な自信と誇りを持ち、訪れる人をゆとりある表情で迎えるようになりました。自らの地域を価値再編成し、時代を読み、時代と闘って成功した好事例が智頭町です。
(ぬりえ美術館)
都営地下鉄三田線に乗って、頭の向こうに目線をおくと、見慣れた画面が入ってきました。
ぬりえ美術館の車内吊り広告です。それも東京国立博物館、東京国立近代美術館等が展開する「今日は、アートでゆっくり」というキャンペーン交通広告です。ビックリしました。小さなプライベート美術館が、天下の国立博物館・美術館と同一に扱われているのです。勿論、東京都交通局の展開ですから、広告費は無料です。10月までの累計に入館者数は前年比177%、この実績は「ぬりえ文化」出版も影響していると思いますが、ぬりえが確実に時代の感覚をとらえ始め、それを外部機関が認識し始めたと理解しています。
時代の変化によって、自らを変えなければならない。これが時代のセオリーです。以上。
2005年10月20日
現地・現場・現認とタイミング
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
現地・現場・現認とタイ ミング 2005年10月20日
出迎え犯罪被害
パリのモンパルナス駅から、TGVでボルドー駅に着きました。乗車三時間ですから大阪に行くのと同じですが、一駅も停車しません。駅近くになると出迎えの人から携帯に、駅のミーティングポイントで待っているという電話です。大きな駅には出迎えや、待ち合わせ場所としてのミーティングポイントがあり、それが四隅から矢印が中心に向かっているデザイン標識で表示されています。到着後のミーティングポイントでは、ネクタイをしたビジネスマンらしき男性が二人握手を求めてきました。
通訳をお願いした女性がフランス語で挨拶し、こちらも握手で対応し、案内されるままに地下の駐車場へ階段を降り、割合新しいルノー車に案内され、後部座席に座ると出発です。車が走り出して改めて出迎えのお礼と、これから行くところまでの所要時間を尋ねると、妙な返事です。お互いの会話がかみ合いません。地下の駐車場から地上に出るころになって、人違いということがわかりました。
お互いに、慌てて再び駅のミーティングポイントに戻り、本来の出迎え者を探しだし「よい旅を」などと手を振りあい別れましたが、ちょっとした出迎え事件でした。
これがフランスでよかったと思います。昔から中国などアジア地域の空港では「出迎えを装った犯罪被害」が発生しています。偽の出迎え者に連れ去られて、金品を奪われるなどの被害が結構あります。企業名・氏名などを事前に調べて、プラカードなどに書いて待ち受け、連れ去るのです。フランスですから人違いですみましたが、国によっては危ない結果となった可能性があります。注意したいと再認識しました。
NYを訪れる
ここ数年、外国への入国セキュリティーチェックは厳しくなっています。特にアメリカは9.11事件以後、安全チェックが格段に厳しくなって、あの早口のまくし立てる聞き取れない米英語で、細かく尋問されるのかと思うと、ついアメリカを敬遠し、そのアメリカでもNYだけは行かないと決めていましたが、5年ぶりにフランスに行く前に三日間だけ滞在してきました。ケネディ空港に到着し、果たしてどの程度の厳しさか。緊張して入国審査官の前に立ったところ「目的は」という思わぬ日本語で気楽になり、その後の質問も短くやわらかで、両手の人差し指指紋と顔写真は撮られましたが、予想外の簡単さでした。ホッとしました。また、ケネディ空港からマンハッタンに入り、道を歩き、交差点で周りを見回して感じるのは、以前のような緊迫感がなく、危険を前提にした防衛行動で動き回らないですむことです。街の中に安全感が漂っているのです。その安全感は地下鉄に証明されています。地元の人に聞きますと、今やNYの地下鉄は「早い・安い・安全」という代名詞だといいます。24時間走っていて、夜中の一人乗車も怖くない、と言い切ります。すごいことです。昔と全く逆の姿を実現しているのです。今のNYは殺人も少なく安全な街となって、人口70万人以上のアメリカ大都市安全度ランキングで第四位になりました。参考までに地下鉄料金は「5回プラス1回サービス計6回で10ドル。一回乗車に換算すると1.7ドルですから、1ドル112円換算で約190円。定期券は一日乗車券7ドルで、7日間の場合は24ドルですから一日換算すると3.4ドル、同換算率で一日中何回乗っても380円のバカ安」です。安全な上安く、NYの変化を象徴しています。
素直で勉強好き・プラス発想
クールジャパン、かっこよい日本。国民総生産GDPでは世界第二位ですが、GNC
(Gross National Cool)ではダントツの第一位日本。それを証明するのが日本アニメの人気です。マンハッタンの中心に所在する紀伊国屋の店頭、そこの一階の真ん中あたりにアニメ売り場が大きく占めています。紀伊国屋の店長に確認してもよく売れているとニコニコ顔でうなずきます。日本食の人気は世界的ですが、最近は日本式ラーメン店にアメリカ人が並んでいるという状況です。ラーメンはパリでも同様で、いわゆる西洋人が店の前に立ち並んで待っているほどですから、ラーメン人気も世界的な傾向と思います。
日本食ブームに加えて、今回訪問した日本企業、いずれも元気でした。お会いした現地日本企業トップの方々、皆さんゆったり落ち着いて自信に満ちています。バブル崩壊後の傷が癒えて、日本企業はアメリカ経済順調の中で、業績を伸ばしていることを確認できたこと、これが最もうれしいことでした。
その企業トップにお会いして気づいたことがあります。皆さんに共通していることです。
それは経営コンサルタントの船井幸雄先生が常日頃述べている「成功するトップは、素直で勉強好き、そしてプラス発想の三条件だ」、これを備えていると感じました。「勉強好き」とは「知らないことを知ることが好き」ということ、「素直」とは「知らないこと、確証のないことは、どんなことも否定しないこと」と、船井先生が定義しています。プラス発想は今更説明する必要がないと思います。
NYでお会いした経営トップの方々、その語られる言葉の背景に「素直で勉強好き・プラス発想」があり、それが業績順調の理由であると再認識いたしました。
ぬりえ・剪画展
来年9月から10月にかけて「ぬりえと剪画(せんが)展」をNYで開催するための下準備、それが今回の目的でした。加えて、日本企業の元気さを確認でき、好業績の確保は現地企業のご努力もありますが、共通した背景には日本文化への再評価・再認識があり、その代表的な証明としてのアニメのすごい広がりがあること、それについて各企業理解しておりました。そこで、このアニメの原点に実はぬりえが存在していることを説明いたしますと、皆さん大きく頷いてくれます。
このようなぬりえが持つアニメへの関わり、それは今年9月に出版した「ぬりえ文化」を書くに当たって研究したからいえることで、本が役立ち、助かりました。
なお、一緒に展開する剪画展、この剪画という文字、一般の人は難しくて読めず書けずですが、植木を刈り込む「剪定」とパソコンに打ち込みますと出てきます。なかなか知られていないのですが、簡単にいえば「きり絵」の芸術性を高めたものなのです。剪画展が昨年NYで開催され、反響よく来年も開催するというので、ぬりえ展も一緒に展開させてもらおうと企画し、NYの現地・現場・現認をするために今回行ってきたたわけです。
現地・現場・現認
知らないことや確証ないことは、現地に行き現場の状況を現認すること。これが大事で欠かしてはならないポイントです。しかしもっと大事なことがあると思います。それは全ての人は明日以降の未来に向かって行動しているのですから、現地・現場・現認したことを未来に活かしていかねばならないということです。折角に現地・現場・現認したことでも未来に活かさないと行動した意味がなくなります。ところが、現地・現場・現認したとしても、そのタイミングがずれ、遅れてしまい、折角の行動が活かせないということになることが多々あります。タイミングを計った現地・現場・現認が隠れた重要ポイントなのです。ここを疎かにしてはいけません。現地でコーディネートしてくれた人が、一年後の展開のためにNYを訪れる、という行動に驚いたと発言していましたが、こちらは当たり前で当然のことで、それより今行っていることがタイミング的にみて妥当なのか。というところにポイントをおいて考え行動してきました。
人は考える動物であり、考えることとは、未来へ向かう自分の行動を作るための前提作業です。また、過去には戻れず、過去は未来に使うしかないのですから、過去を思い出だけにしてはいけないと思います。過去に経験した様々な成功・失敗、その分かれ目ポイントは何か。その多くは未来に対する予測誤差から発生しています。未来は不確定ですから誤差が発生するのが当たり前ですが、しかし、未来に結果を出し、物事を成し遂げたかったら、未来予測誤差をなるべく少なくするための、未来への投資を心がけた方がよく、その投資とは未来計画つくりにつきます。その未来計画の精度で決まります。
ですから計画つくりために現場・現地・現認をするタイミングが最も大事です。現場・現地・現認するタイミングの決め方で、未来予測の内容妥当性が決まるからです。
NYに行きませんか
2001年9月11日以後のNY、安全度の確認ができました。来年の9月27日から「ぬりえと剪画展」と山岡鉄舟講演を行います。NYマンハッタンを楽しみながら、来年秋の「オータムインNY」へ一緒に参りませんか。詳細は来年ご案内いたします。以上。
2005年09月22日
One To One
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年9月20日 One To One
選挙が終わって
衆議院総選挙が終わりました。小泉首相の大勝利でした。ほとんどの人の予想を超える記録的大勝利です。
前回のレターでご案内した藤原直哉氏の「自民党大敗」という予測、藤原氏は事前に発表された新聞の予測内容が自民党有利と報道したことに対し「大新聞はアメリカにいわれ情報操作している」とまでいいきっていました。そこまで断言するには相当の根拠があったものと推察し、結果がはっきり現れた現在、本人の見解を聞きたいところです。
まだ藤原直哉氏から次のワールドレポートが届かないので、どういう論理構成で自民党大勝利を分析してくるのか、それを待っているところです。
まだ藤原直哉氏から次のワールドレポートが届かないので、どういう論理構成で自民党大勝利を分析してくるのか、それを待っているところです。
しかし、今回の選挙は投票率が高く、久しぶりに多くの国民が、関心高く迎えた9月11日でした。どうして関心が高かったのか。その要因分析も様々なされていますが、高くした一つの事例を紹介したいと思います。
それは熊本から届きました。熊本の田中貴子さんという大学生が「選挙実行委員会」をつくって、若い世代の選挙に対する関心を高める行動を展開したのです。
今まで20歳代の人は選挙投票率が低く、無関心で、その理由を聞きますと「誰に投票しても政治の結果は変わらないから」というような返事が多く聞かれました。
今回、このような若い人たちに関心を持ってもらい、選挙投票に行動を変化させようと、田中さんらの大学生が自主的に「選挙実行委員会」を立ち上げ、候補者を集め、各会場で討論会を始めたのです。選挙終盤戦には東京からフジテレビが熊本に取材に来て、人気番組の「とくダネ!!」で、この熊本の若い力の結集が紹介されました。素晴らしい若い人たちの行動力です。
小泉首相大勝利の裏に、高投票率という実態があり、それを実現させた背景に熊本に代表される若い世代の活躍があったこと、その事実を知り、その動きは若い世代が未来の日本の方向性を考えはじめた変化の一環であると思います。素晴らしいことです。
足立美術館
足立美術館は有名になりました。昔は東京都足立区にある美術館ではないかと誤解するほど知名度はありませんでした。しかし、今は「足立美術館」と聞いただけで「ああ、あの有名な横山大観の絵で」とうなづく人がほとんどです。
その上、ここ三年間、日本庭園ランキングで第一位ということで、さらに有名になりました。ランキング審査はアメリカの日本庭園専門誌が行ったもので、日米豪の専門家が全国693ヵ所の寺社、美術館、旅館などから選考しています。単に庭の内容だけでなく、庭の管理状況、建物との調和、接客サービスなどを総合的に評価したものです。二位は京都の桂離宮で、ここを抑えての第一位というのですから立派です。
前から一度行ってみたかったのですが、ようやく先日訪問することができました。JR西日本の島根県安来駅からシャトルバスが無料で送り迎えしてくれますし、安来駅で足立美術館の入場券を購入すれば手荷物を無料で預かってくれます。安来駅前は何もないのですが、食べ物なら何でもありという食堂とコンビニがあるだけの田舎駅ですが、駅前片隅のシャトルバス停には、発車時間間近となるとどこからか大勢集まってきます。
その安来駅近くのコンビニに入って、ふとレジ前のPOPを見てびっくりしました。どこかで見た顔写真がカウンターを飾っています。渋い外国人の上半身です。それは調理人の姿、パリのギ・サヴォア、三ツ星レストランのオーナーシェフです。何回か取材で会い、ギ・サヴォアレストランはバカ高いので一回しか食事をしたことはありませんが、その一回食事したときに、挨拶に出てきて、スープをサービスしてくれたことを憶えています。そのパリで最も有名なギ・サヴォアの笑顔写真が「ボジォレー ヌーヴォーご予約承り中」と書いてあるPOPの中にあります。ギ・サヴォアがコンビニチェーンと提携したのです。三ツ星レストランのオーナーシェフ、それもギ・サヴォアですから、コンビニとの提携には何かの理由があるのでしょうが、「フランスを救った日本の牡蠣」に登場してもらった人物と、足立美術館に行く前に安来駅前で会えるとは意外でした。今度、ギ・サヴォアに理由を聞いてみたいと思いますが、驚きました。
さて、足立美術館は噂どおりの立派さでした。しかし、その概要をお伝えすることはやめたいと思います。十分なる解説ができないと思いますので・・・。
しかしながら、足立美術館を今日の評価にしたのは、オーナーであった足立全康氏の情熱です。貧しい家から身を起こし、71歳のときに美術館を開館したのです。幼少期は引っ込み思案で、学校の成績も丙と乙だらけ。尋常小学校を卒業した12歳から働き始め、農業の傍ら木炭の販売、鉱山経営で失敗、兵役後大阪に出て仕出屋、たどん屋、再び郷里に帰って米の仲買い、荒物屋、繊維ブローカー、刀剣製造会社、戦後は大阪で綿布問屋、外車販売、金融業、不動産業など、とにかく生涯で30を超える事業を興し、数々の成功と失敗を繰り返しました。
大儲けしたのは不動産会社です。戦後の混乱期に戦災焼け跡バラック建ての心斎橋骨董店、その店先にあった横山大観の絵、それに「胸がすうっとするような荘厳な気持ちにされ」、それ以来、大観に惚れ込み儲けたお金で買い集めだしました。集めてみると蔵に納めておくだけではもったいないと、郷里の自宅があった辺りの場所に昭和43年(1968)に美術館を設立し、それから37年、今や島根県安来市の道路端畑の真ん中に、突如として立地する足立美術館、美術館としては立地がよくない場所に、国内外から集まって、今や国内トップクラスの入館者数を誇るまでになったのです。
足立全康氏の成功は、横山大観という時代が変わっても、多くの人に価値が認められる絵画、それ一筋に情熱を傾けたところに、今日の成功があると思います。
TABOO
今は変化のときです。衆議院選挙も郵政民営化という変化を求めた自民党が勝ちました。対する民主党は、変化は必要であると意識しながらも、変化ということに対して曖昧さを残したスローガンでしたので、大敗したと思います。
知に完成形がないように、時代にも完成形がなく、過去を創り変え再生していかないと、制度も組織も腐っていきます。ですから、その時代に合致したシステムを創り、それが創り終えたら、更に次の時代へのシステム創りをする。そのような弾力的思考を持たないと、今の時代を乗り越えて行くのは苦しいと思います。
変化は英語でCHANGEです。この中からGをとってCにするとCHANCEですから、変化はチャンスであるといえ、このような比喩がよく巷間いわれています。変化に対して常に前向きに取り組んでいけば、必ずチャンスが訪れるともいわれています。
その通りと思いますが、そのようにチャンスにするためには一つ大事な条件があります。それはGとCの違いを知ることです。GとCとでは何が違うか。Gをみれば分かりますように、GとはCに小文字のTを加えたものです。ジャイアンツからタイガースのTをとるとCになって、そのCで書き直すとCHANCEチャンスとなるのです。つまり、Tという意味を変化から取り去るとチャンスになります。
ではTとは何でしょう。それはTABOO・タブーです。意味は禁止された、禁制という意味ですが、人は必ずこのTABOOを持っています。固定観念や既成概念とも思い込みともいいますが、すべての人は自分の考えとしてTABOOを持っています。
だが、時代は自分に関係なくドンドン変化していき、それに背を向けていると時代に取り残されていきます。ということはTABOOという意味も変わっていきます。TABOOとして変えてはならないと思う自分の気持ち、その固定観念、既成観念、思い込み、それらを時代感覚でチェックする必要が出てきたと思います。
One To One
日本の姿を創るのに、大きな役目を果してきた郵便局のお金、その運用を時代と共に変化させていく。その必要性を小泉首相が選挙の争点にしたことは、我々にTABOOを見直すことを教えてくれ、加えて、マーケティングの大事さも教えてくれました。
代議士が反対し流された改正案、それを国民に尋ねなおしてみようという今回の選挙、それはOne To Oneマーケティング手法です。一人ひとりに聞いてみて、それから総論を構築していく。正に店頭で一人ひとりに個対応し、その結果で全体売上を獲得していく。そのマーケティングセオリーを採り入れたのです。政治的にはいろいろな見解はあるでしょうが、一人ひとりに対応したマーケティングの勝利と思います。以上。
2005年09月06日
近代戦のあり方
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年9月5日 近代戦のあり方
国会解散
国会図書館に行くたびに、国会議事堂の前を通ります。今年の夏は小中学生がたくさん並んでいました。国会議事堂の見学に来ているのです。何のために国会見学に来るのか。それは子どもたちの間に、今回の解散・選挙が関心もたれているからです。
その解散について大人たちの間で見解が分かれます。参議院で否決されたのに、何故に衆議院が解散するのか。筋が異なる。小泉首相の暴挙だ。また、森前総理の「衆議院で郵政民営化に努力してくれた人たちを路頭に迷わせてよいのか」発言は、政治家を失業させるのは困るから解散させたくない、という稚拙な小泉首相への口説もありました。
一方、解散によって国民の前に問題を明らかにし、差し出し、真の決定権者に決定させるということは、日本の民主主義を確実に進化させることにつながる、という見解もあります。いずれにしても小泉首相権限で衆議院が解散し、9月11日に総選挙が行われます。
選挙結果予測
選挙の一週間前になってくると、各新聞が選挙結果の予測記事を掲載し始めます。4日の日経新聞は「与党安定多数の勢い」と全国世論調査の結果を一面に発表しました。5日の読売新聞も同じく全国世論調査の結果で「自公過半数超す勢い」と掲載、同日の共同通信も「与党優勢」と報道しております。政治評論家の三宅久之氏に直接伺いましたが「今の情勢ではよほどのことがない限り自民党が圧勝」という見解です。
しかし、経済評論家として著名な藤原直哉氏の発行するワールドレポート(2005年8月31日)では、以下の内容が指摘されています。
1. フランスのルモンド紙は自民党苦戦
2. イギリスのフィナンシャルタイムス紙は自公過半数割れ
3. 高知新聞の独自の世論調査で小泉支持が41%、不支持が48%という結果で、東京の大新聞とは異なり、地方はアンチ小泉
4. 経団連が自民党支持を打ち出しているが、これは大企業が小泉政権と海外勢力とつながって、国内で弱肉強食政治を推進する証左である
5. 結論として与党は過半数取れずに小泉政権退陣、同時に民主党も過半数を取れない
6. その結果、自民党は小泉政権の退陣と同時に党が瓦解するのではないか
つまり、総選挙一週間前の全国世論調査で示した大新聞の予測と、著名な論客である藤原直哉氏の見解は真っ向から対立しています。
どちらが当たるのか、それは11日の夜に分かりますが、今から事前に皆さんも自らの見込みで予測しておくこと、それが今回著名人の出馬や新党結成が出た「劇場型」といわれる衆議院へ関心を高めることになるのではないでしょうか。とにかく、小中学生にも高い関心がある今回の選挙ですから、自らの事前見解と、結果との分析は必要と思います。
近代戦のあり方
白川静氏は字統・字訓・字通の3部作で知られています。その白川静氏が次のように述べました。(「日本の進む道」2005年8月19日日経)
「日本の近代化は明治時代に開花し、大正期になってようやく世界に目が開くようになりました。大正デモクラシーに代表されるように、それは成長しつつあったが、軍部の台頭によって未成熟なままに終わってしまいました。台頭を許した裏には農村の疲弊、国全体の貧困があった。要するに日本は近代社会になりそこねたのです。『戦争』と言わず、『事変』と称して宣戦布告もせずに既成事実を重ねる。政治の前面に出てくるのは『近代戦のあり方』も知らない軍人ばかり。日本人は人材が不足していたのです」
なるほどと思いますが、ここで指摘していることは明治時代に日本の近代化が開花したということです。では、どうして明治時代に開花したのでしょうか。明治時代に開花するには、その前の時代に何かの要因がなければなりません。それは江戸時代です。
江戸末期に日本の近代化を開花させる最大要因はペリーの来航でした。嘉永6年(1853)7月8日、アメリカ・ペリー艦隊は4隻で浦賀の沖合いに停泊。だが、これはオランダを通じて一年前に幕府に伝わっていましたので、幕府はペリー一行が来た場合の予行演習も行って準備していました。その予行演習内容は『日本は人口3000万人で需給のバランスが国内だけで十分とれているので、外国と貿易する必要がない。長い航海生活で不足する生鮮野菜や水・薪などは提供する』。つまり、今まで通りという交渉方針でしたが、これは世界という視点から来航したアメリカには、とうてい理解できない理由でした。
当時、日本近海では、乱獲ともいえるほどの捕鯨活動が行われていました。鯨油は欧米の必需品で、それは灯りとして、石鹸をつくものとして、印刷機の潤滑油として、鉄鋼の高炉釜入れ用として、多くの使用価値がありましたので、鯨を追って日本近海にまではるばる航海してきたのです。それらを理解できない日本人を、かえって欧米人は不思議がって、通訳だったヒュースケンは次のように述べています。「日本近海にたくさんの外国船が国旗を翻し鯨をとりにきている。なぜ、勇気もあり、活動力にも欠けていない日本人が、同じように遠く外国の岸まで船を送り、自国の旗を進めようとしないのか」(ヒュースケン日本日記)つまり、日本も世界貿易体制に入って活躍すればよいのではないか、という世界常識からの見解、これは現在、日本が世界貿易で成り立っている実態で分かりますが、ペリー来航はその事実を暗示し、近代戦のあり方を教えようとしていたのです。
鳥羽伏見の戦い
慶応4年(1868)1月3日、京都の南郊、鳥羽・伏見で幕府軍と薩長中心軍とが戦い、幕府軍が敗れて将軍慶喜は江戸城に逃げ帰りました。これが明治維新・戊辰戦争の始まりです。鳥羽・伏見の戦いでは幕府軍は圧倒的な軍勢で陣地を構築していました。対する薩長軍は人数少なく、当初、必勝の算はなかったのですが、結果的に幕府軍の大敗となって、一気に情勢が変わったのです。この勝敗の帰趨について様々な分析がなされていますが、最も大きな要因は「時代との接点体験」をしていたかどうか、これで決まったのです。というのも、薩長はいずれも当時の欧米先進強国と戦争したという体験を持っていました。薩摩は文久3年(1863)の薩英戦争で、当時世界最強のイギリス艦隊と戦い、長州は元治元年(1864)に下関を英米仏蘭四国艦隊によって攻撃を受け完敗し、いずれも欧米科学力のすごさを熟知して、その体験から軍の近代化を図ってきたのでした。
ところが、幕府側の欧米に対する理解は、外交交渉のみからでしたので、頭では分かっても実態はついていかず、薩長の犠牲を払った実践経験とは格段の差があったのです。
ですから、鳥羽・伏見の戦いに出陣した幕府軍の諸藩軍の中には、戦国時代の感覚で参戦した藩も多く、「近代戦のあり方」を知らずに戦ったのです。いくら軍勢が多数でも、薩長の欧米先進国との戦争によって体験し、軍備強化した軍隊と、そうではない幕府軍とでは勝敗は当初から明らかでした。時代との接点体験の有無が大きな差でした。
アハ!体験
ニュートンが、リンゴが木から落ちるのを見て万有引力の法則を発見したエピソードはあまりにも有名ですが、このような天才達のひらめきが人類の歴史を創ってきました。英語では「ああ、そうか!」と気づいたときのひらめき感覚を「アハ!」という言葉で表し、この「アハ!」と気づくと、神経細胞の間の結合が強められ、一瞬にして脳の学習が完結するのだと、脳科学者の茂木健一郎氏が解説しています。(2005年8月25日日経)
明治維新の成立には、もう一つ薩長側に大きな課題が横たわっていました。それは京都に居住する公卿たちの保守性です。公卿衆は武家政治が始まって以来、700年もの間、政治の実務から遠ざかって、日頃は風流韻事と学問だけであったので、保守の殻に閉じこもったその感覚を、時代の厳しい現実に変化させねばならなかったのです。
この改革を行うに当たって、中心となった薩摩の西郷も大久保も非常に苦労したのですが、何とか結果的に公卿衆に「世界の情勢と、その中にいる日本の境遇情勢」について「アハ!体験」させる攻め方をしたことが、明治維新成功のもう一つの要因でした。
時代には完成形はない
知に完成形がなく、何が正しいかどうかも分からないことが多い。同様に時代にも完成形はなく、時代がどの方向に向かうのが正しく妥当なのか実は分からない。しかし、過去を創り変え再生していかないと、制度も組織もしがらみで腐っていく。白川静氏が指摘する「近代戦のあり方」が、国民の民意として9月11日にどう表れるのでしょうか。以上。
2005年08月21日
歴史は人が残す
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年8月20日 歴史は人が残す
最近の情勢判断
年に数回同じ居住区の人たちと食事会、ハイキング、旅行などをします。先日は暑気払という名目で、近くに新規オープンした焼肉店に行きました。安くてうまいと評判の店です。参加者は10名。女性が8名で皆さん中高年です。
最初の乾杯が終わって、差し障りのない雑談の後、市長・知事の評価、地元選出代議士の評価、次に郵政民営化について盛り上がってきました。皆さんテレビで問題点を把握していますので指摘はなかなか鋭く、なるほどと思うことが多々あります。それに対する見解を求められましたので、こちらの見解を述べましたら、真面目に聞いてくれたようです。
小泉首相による衆議院の解散によって、あっという間に事態が動き展開し、郵政民営化反対者は窮地に陥って国民新党ができたように、物事が極まってくると、結論がでるのが極めて迅速で、変化して行き、もはや元には戻らなくなります。しっかり時代を見たいと思います。世の中の出来事の背景を知ろうとしなかったり、無関心でいたり、目の前のことにしか気を配っていないと、遠くで起きている巨大な変化に気づくことができず、それがいつの間にか目前に関係してくることがわからず、明日も今日と同じだろうと漠然としていると、結局、後で後悔することになる。これが最近の情勢判断です。
官僚の嘘
日本道路公団の内田道雄副総裁と金子恒夫理事が、談合全般に関与した「正犯」に当たると東京高検に逮捕されました。この逮捕に至るプロセスはテレビでご存知の通りで、内田副総裁が談合組織「かづら会」なぞは知らない、新聞報道ではじめて知った、という鉄面皮な迷答弁に、質問者の猪瀬直樹氏が呆れた顔をし「嘘でしよう」と発言したのがきっかけで、とうとう今回の逮捕につながりました。一民間人の作家が官僚の嘘を引き出して逮捕につなげたのです。時代は変わったと思います。テレビという公開画面の中で、民間人の質問に官僚トップが平然と嘘をついている実態が放映されたのです。多くの人に官僚とはあういう人間なのかという、新たな恐ろしさを感じさせ、その官僚の収入が税金から支出されている、という事実に憤りを感じます。東京新聞の7月31日に、千葉商科大学学長の加藤寛氏が「悪臭は元から断て」と次のように寄稿しています。
「道路公団の民営化のために七人委員会がつくられたのはよかったが、途中で内部分裂のため改革案がつくれなかった。そのとき、ジャーナリズムの論理は辞任した委員を高く評価したが、改革とはそんな格好よさを褒め称えることではない。泥にまみれても改革委員会を死守することである。今残っている猪瀬、大宅氏に非難の声はあるが、彼らの頑張りがついに内田副総裁逮捕を実現したではないか。公団及びそのファミリーの影を暴かなければ、改革の一撃を加えることは難しい。国鉄の場合もその暗部を国民の前にさらけ出したから世論の支持が得られた。単なる改革プランは夢として描くだけで解決にはならない。レントシーキング、たかり社会の元を断たなければ、表向きの改革の姿だけを幾ら提言しても改革案にはならない。その元とは財源の根拠を提供していた郵貯、簡保、年金の元を断つことである」と。
海舟の直感
月刊誌ベルダに山岡鉄舟を連載していますので、幕末の状況分析を通じ、江戸無血開城こそが日本を独立国家として発展させたスタートであったと理解しています。
その江戸無血開城は慶応四年(1868)3月14日、田町の薩摩邸における西郷隆盛と勝海舟の間で正式に決定しましたが、実際には鉄舟が駿府にて西郷と会見交渉し、事前に事実上決めていたのです。
ということは鉄舟こそが独立日本を創りあげた功績者です。だが、この鉄舟も官軍が充満している東海道筋を突破して、駿府に辿りつくためには独りでは無理で、官軍の中を通り抜けられる武器が必要でした。それが薩摩藩・益満休之助でした。薩人の益満が鉄舟に同行してくれたからこそ、官軍の中を走破でき西郷と会見・交渉できたのです。
では、誰の指示で益満を鉄舟に同行させたのか。それは海舟です。海舟邸に前年末の薩摩藩焼き討ちの折幕府に捕らえられ、死罪となるはずの益満がいたのです。鉄舟が将軍慶喜の指示を受け、海舟邸を訪れる3日前に牢屋から引き取った、という図ったようなタイミングでした。海舟と鉄舟はそのときまで面識がありませんでしたし、鉄舟が慶喜の指示を受けたことも海舟は知りませんでした。しかし、益満を対官軍工作員として準備しておいたことが、鉄舟の功績を引き出し、これが江戸無血開城を成し遂げさせたのです。益満を牢屋から引き取ったタイミング、その海舟の直感力が歴史を創り上げました。
直木三十五
この益満休之助という人物を、主人公に取り上げて書いた作家が直木三十五です。
直木賞として冠を称せられている作家です。殆どの人は芥川賞が芥川龍之介であることは知っていますが、直木賞が直木三十五の業績を称える趣旨から設けられた賞であることを知りません。
直木三十五は明治24年(1891)大阪生まれ、早稲田大学に進むものの、関東大震災後に関西に戻り、雑誌「苦楽」の編集などに従事。再上京後は次々と著述をあらわし、昭和5年(1930)に新聞連載がスタートした「南国太平記」で一躍人気作家になったが、昭和9年(1934)結核性脳膜炎のため43歳で没しました。
このときの直木三十五の死に対して、多くの追悼が寄せられましたが、その多さでいえば、空前とも絶後ともいえるほどで、新聞は勿論総合誌、文芸誌など、かなりのページをさいて追悼特集を組み、「衆文」のように全誌をあげて追悼号とした雑誌もありました。
そのなかで菊池寛は「直木は大衆文学者といわれたが、彼の本領は一個の大歴史小説家である。彼出でて初めて日本に歴史小説が存在したといってよい。彼は荒唐無稽な筋書きによって舞文するのではなくして、歴史的事実に立脚して、その事件と人物とを、彼の豊富なる想像と精鋭な描写とによって、生かしているのである」と激賞しています。
確かに、図書館から「南国太平記」を借りて、夏休みに読んでみましたが、お由良騒動といわれる島津家のお家騒動を素材に、薩摩藩の幕末回天史を描いた長編であって、内容のポイントとなる場面は史実に基づいていることが分かり、益満休之助も登場し「鳥羽伏見の戦いの後、江戸に潜入した益満は、幕兵に正体を見破られ捕らえられ、勝海舟に助けられ、西郷との下交渉に働く」と、その姿が描かれています。
司馬遼太郎など名だたる作家が受賞している、大衆文学の登竜門としての「直木賞」は、直木三十五の業績を称えることから制定され、文壇歴史にその名を刻んでいます。
絵本の歴史
今月末に「ぬりえ文化」を出版します。ぬりえについては専門研究書がありませんので、日本でも、多分、世界でもはじめての専門書として各分野で活用される存在になると思います。といいますのも、2003年に出版した「フランスを救った日本の牡蠣」が牡蠣業界では専門書として活用されている事実を、先般の「国際牡蠣フェスティバル」で確認できたからです。今回の「ぬりえ文化」も関係する人々から受け入れられると期待します。
ところで、ぬりえを研究する過程で絵本の成り立ち・歴史についても分かりました。
「絵本の歴史は1844年にフランクフルトのお医者さん、ハインリッヒ・ホフマンによってつくられました。一人息子のクリスマスの贈りものとして、ホフマン先生が息子のいたずらや失敗を、自分で描いて、詩をつけて、一冊にとじて息子に贈りました。それを友だちや、その親たちが愉快がり、知り合いの出版社が乗り気になって石版技術で出版しました。それまでのかた苦しいお説教調で宗教画の安本を圧倒して、ぞくぞく版を重ねました。これが絵本のはじまりだったのです。この結果、ホフマン先生は医者ということは忘れ去られましたが、絵本の著者として人名辞典に残り、この絵本は絵本の古典となりました」と瀬田貞二氏の絵本論にありますように、ホフマンさんから始まったのです。
道路民営化委員会での猪瀬直樹氏の働きは、作家としてよりも道路公団民営化の歴史に名を残すでしよう。幕末、海舟が時の誰よりも国際情勢を的確に分析し、日本が分断されないように動いた一環として益満の手配があり、それによって鉄舟が働いたことで歴史を創りました。直木三十五も菊池寛によって直木賞として文壇の歴史を創りました。ホフマン先生も絵本の歴史を創りました。衆議院解散による9月11日の選挙結果で、郵政民営化を成し遂げるかどうか。小泉純一郎の名が歴史として残るかどうかが決まります。以上。
2005年08月08日
感性と論理性と実現性
YAMAMOO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年8月5日 感性と論理性と実現性
内閣府セミナー
7月20日に内閣府と高齢社会NGO連携協議会主催のセミナーがあり、その分科会のパネラーとして出席しました。基調講演はさわやか福祉財団理事長の堀田力氏と、一橋大学名誉教授の江見康一氏です。堀田氏はロッキード事件の検事として著名であり、江見氏は81歳のときに東京から兵庫県赤穂市まで、約680キロを自転車で走破した人物で現在84歳、お二人とも洒脱な話し振りと、ハッとさせる含蓄に富んだ内容で勉強になりました。お二人の主張で共通していたのは、自分の人生は自分でつくるものであって、それは一人一人のオリジナルなものであるということ、これに同感いたしました。パネラーとしての分科会テーマは「自己実現の夢、健康で、明るく、楽しく、生涯学習」で、最初にパネラーとしてテーマについて見解を要望され、次のように申し上げました。
「国際会議や海外企業訪問時に経験することですが、日本人が発する質問に一つのパターンがあります。それは『平均ではどのくらいか』というもので、これに対する欧米人の回答は『多い人は多いです』といたって簡単です。つまり、平均ということにあまり関心がないのです。人は人、自分は自分ですから、多少は人を気にしますが、日本人のようにあまりにも気にすることはありません。この傾向は『欧米人は一人一人が違う生き方をしているという意味』に通じます」また「分科会のテーマは五つの内容から構成されていますが、自己実現していれば、その人は楽しく、明るいですから、身体も健康になり、自己実現を目指すための研究も進み、結果的に生涯学習になります。この五つの内容はつながっているのです」と。
他人から知る自分の個性
突然、若い男性から連絡が来ました。ある会社に勤めていたのですが、退社し独立したいという連絡です。早い時期に独立したほうがよい、という主張を持っていながら、なかなか独立できなかった経験者として、このような若い人の決断に賛成しますが、課題はその独立する内容です。条件整備がどの程度整っているかというところです。
概略の経緯をお聞きしてみますと、まだ十分に条件整備を整えていない実態でした。これは当たり前のことと思います。十分なる条件整備が整ってから独立するというのは、希望としては成り立ちますが、実際には「十分という意味」が抽象的ですので、それが完全に整備されるということはありえないと思います。
しかし問題は、安定した収入がなくなるのですから、独立するという意味、つまり、プロとして世間が認める力がないとお金は入ってきません。そのプロとして世間が認める内容を保有しているのか、というところが最大の課題となります。
また、一般的には若い時代は、自らの力の内容、それは潜在能力を含めてまだまだ自らの力の中味を知らないのが実態です。加えて、素晴らしい素材としての魅力があったとしても、それを発揮する場がないと、独立したとしても仕事にはつながらないのです。
そこで自らの存在価値を判定する方法の一つとして、今まで経験したことのない新しいテーマに挑戦することを勧めました。自分がどのような分野で活躍できるかという検討・トライのためです。
ちょうどよいタイミングで、ある企業からご依頼のテーマがあり、直感的にこのテーマが若い人に向いているのではないかと思い、企業に企画提案してもらいましたら、幸いに受け入れられましてスタートしたところです。
結果は分かりませんが、仮に今回のテーマが成功しますと、新しく経験する内容であって、成果を他者である企業が評価してくれるのですから、他者がプロとして通じる素材を見つけ、人に役立つ若い人の個性を探してくれる、ということになっていきます。
つまり、自分の個性は他者との関係性で開発され、磨かれるものであると考えていることの実証、それがこの若い人にも適応できることになりました。
鳥取県智頭町
何か困ったときに打開策を見つける作業は、一瞬の感覚・感性からが多いと思います。考えて、考え抜いて決めたとしても、その最初の発想と入り口は一つのある気づきから発生して行くことが多いのです。ですから、問題に当面したときに感じる最初の感覚・感性は大事です。
しかし、この感覚・感性のままで問題解決策を続けていくと、いつの間にか問題解決にならず、更に傷口を広げていくことも多々あります。それは、最初の感覚・感性は妥当であったとしても、その後に展開する方法に問題があるからです。
物事の印象を敏感に嗅ぎとって直感的に方向性をみつける感性と、物事の順序を組み立てていく能力としての論理性、その論理的に組み立てたものを本質を失わずに実際に処理して行く実現性が必要になります。つまり、物事を成し遂げていくには「感性」と「論理性」と「実現性」という三つの能力要素が必要なのです。
今、殆どの地方都市が集客力に悩んでいます。駅前にあった何とか銀座商店街はシャッター通りになっていますが、これは人が集まらないから売れず、売れないから営業不振となり、廃業していくからです。ですから、町に人が集まってくれれば、この問題は根本的に解決するのです。このようなロジックは当然分かっているのですが、その方策を考えられずに、一日一日無駄な時間を費やして、役場の地方公務員は給料を税金から受取っているのが実態です。しかし、この根本的問題を解決させかけている町もあり、その実例を鳥取県の端っこにある智頭(ちづ)町の実態からみてみたいと思います。
観光カリスマということをご存知でしょうか。国土交通省が認定した観光業に貢献した人におくられた名称です。智頭町の前町長の寺谷誠一郎氏も観光カリスマで、寺谷氏が行った実績は全国に知れ渡っています。今回、その現場をみて参りましたので実態をご報告いたします。
智頭町はJRで大阪から2時間、京都から2時間半、岡山からも1時間半、鳥取市からは約50分かかる山間僻地に所在します。トンネルを抜けて岡山方面に向かえば、剣豪宮本武蔵の生誕地がありますが、ここ智頭町には記念すべき歴史的な謂れや昔からの名所・旧跡は何もありません。何もない人口9000人の町に、今や年間5万人の観光客が訪れるようになっているのです。

寺谷氏は素直な感性の持ち主です。小さな町が大都市に勝てる何かの武器は何か。これが発想の原点で、その原点から町を見回してみると「空気と水なら十分あるし、昔は宿場町だったからその名残は残っている」と気づいたのです。
次に考えたのは、町に中心ポイントをつくることでした。論理的に考えてみて、中心になる存在物は「大きくて目立つもの」が必要だと判断し、それなら町の中心地にある「大きな個人住宅」が適任だと、町長に当選したばかりの平成9年7月にこの住宅を訪ねたのです。訪ね伝えた言葉は「町のためにこの家を出て行って欲しい」という行動でした。これに対し当然のことながら、「大きな個人住宅」の当主は屋敷を町に譲る理由はなく、今まで住んでいたのだからこれからも住みつづけるという回答をしたわけです。
この町長の行動はあっという間に町全体に広まって「町長は頭がおかしい」と酷評されました。しかし、寺谷町長は日参を重ね、智頭町が観光で立ち上がるには中心ポイントがどうしても必要だということと、この「大きな個人住宅」を訪ねる度にその建物造作構造の素晴らしさにとりつかれていったのです。
この「大きな個人住宅」が、現在一般公開されている「石谷家住宅」です。石谷家は鳥取藩の、大名参勤交代宿泊地が智頭宿と定められた時代から、宿場町の中央に位置する庄屋をつとめ、その後も地域社会に大きな役割を果していたので、当然住宅も規模大きく立派なのです。ここに目をつけ説得し、今では智頭町の観光中心ポイントにし、ここを基点に宿場町の風情を残す杉玉を、各家の軒先に飾るなどの諸対策を講じた結果、観光客が急増したのです。詳しく知りたい方は、現地・現場・現認がセオリーですから、行かれると皆さんのお住みになっている街づくりへご参考になること請け合いです。
物事を成功させるには、直感的な感性、組み立てる論理性、実際に処していく実現性、この三要素が自己実現にも、プロを目指す独立にも、町活性化にも必要なのです。以上。
2005年07月21日
都市は養育するもの
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年7月20日 都市は養育するもの
国際かきフェスティバル
7月13日、14日の二日間、第一回国際かきフェスティバルが開催され、参加いたしました。会場はゆりかもめ国際展示場、東京ビックサイト会議室です。
世界のかき専門家の集まりで、講演発表は基本的に英語のため苦労しましたが、世界で始めてのかき研究者会議は満員盛況でした。
会議の合間や懇親会で名刺交換したのですが、ここでビックリしたことがありました。
それは名刺交換すると、相手の多くの方が「フランスを救った日本の牡蠣」の著者ですね、とこちらに確認します。中には、この本を持ってフランスまで調査に行ったオイスターバーのコンサルタントや、テレビ局の人からはこの本を部内で回覧して読んだ、というようなお礼とも報告ともいえる内容を聞くことができました。
当初は、フランスのかき事情、それを知ろうと調べ始めたのですが、日本には断片的なエッセー風なものしかないということが分かり、それならばかき全体を網羅し、関係する現場からの実態内容にしたいと、かき養殖場・販売チャネル・かき専門レストラン、それと一般人へのアンケート取材まで行って、2003年に出版したのが「フランスを救った日本の牡蠣」です。
今回、国際かきフェスティバルに出席することで、かきに関係する人たちにお役に立っているということが分かり、この本を書いたことの意義を改めて感じると共に、日本には、あるテーマで統一構成した資料が少ないという事実を再認識し、その統一したものの一つとして評価されているという事実、これに満足した第一回国際かきフェスティバルでした。
7月5日のレター
前回のレターについては、随分ご見解と感想をいただきました。熊野古道の石畳、トヨタと二宮尊徳との関係性、これらについてメールや電話、それと直接にお話をいただき、皆さんのご関心が高いテーマであったと改めて認識した次第です。
また、二宮尊徳に対するイメージが一般的に「徳の人」と受け取られているような雰囲気があるようでしたが、そうではなく「再建請負人」というのが実態だという説明を新鮮受けとめられたようです。
いつの時代でも再建が必要ですが、特に幕末という時期は、江戸幕府及び各藩の経済状態が最悪で、その解決のために尊徳が活躍し実績を残したのであって、ちょうど今の日本の政府と各県市町村財政悪化問題と通じるところがあるのです。
そのような財政悪化状態の中にあって、トヨタ自動車という一企業がますます隆盛し、世界中の国々から工場をつくって欲しいと要望される実態、それを尊徳の「仕法」という改革手段とトヨタの「カイゼン運動」と重ね合わせて解説いたしました。
尊徳の改革手段「仕法」については、山岡鉄舟を研究している過程で幕末の政治・経済状態の分析から当然に関心事として浮かび上がってきました。更に、トヨタについてもトヨタ出身者が多くの機関から引く手数多の状態であることから、トヨタの実態を時流として分析するのは当然です。ですから、前回のレターでも触れ、現在、各地でお話しているのですが、この見解については同様な方が多いようで、尊徳とトヨタを結びつけて論及する傾向が広まっています。両者に共通するのは昔から変わらない日本の良習慣といえるものを取り入れていることですが、これは熊野古道を世界遺産として遺してくれた先人の知恵にも共通しています。
都市を養育する
本には「まえがき」があり「あとがき」もあります。忙しい人は「まえがき」を読み、すべてを理解したように本を閉じます。もう少し余裕がある人は「あとがき」を読みますが、これで本の中味は終わったと、あとは書店の書棚に戻します。
これが一般の傾向と思いますし、自分もそうしているのですから多くの方も同様と思います。これだけ書籍が数多く出版されるのですら当然と思います。
ですから、本を書く立場としては「まえがき」に全精力を傾ける必要があります。「まえがき」の出来が悪いと「あとがき」にも行かずに、それでおしまいですので、「まえがき」は重要です。「まえがき」を的確に印象付ける内容にすることがすべてに優先します。
という考え方をもって8月末出版予定の「ぬりえ文化」の「まえがき」では、この本の「志」を強調しております。
最近読んだ「まえがき」で強烈な印象を受けたものに「持続可能な都市」(岩波書店)があります。この本では「まえがき」を「序章」に替えていますが、その出だし文章、
「和歌山市の歴史的ランドマークとなっている紀州和歌山城は、緑豊かな虎伏山に建つ。天守閣にのぼると、眼下に紀の川がゆったりと流れ、紀州海峡に注ぐ風景を眺めることができる。和歌山城は秀吉が弟の秀長に築城を命じたことにはじまり、その後、紀州徳川家55万5000石の城となった。・・・・・ところがその和歌山城に隣接した場所で、和歌山城の景観を台無しにしかねない大規模都市再開発プロジェクトが2005年春、終わった」に目が釘づけになりました。
またもや日本の景観が壊されたという残念さと、それを鋭く明確に指摘する論客がいるという事実、その両方から、本としては高い3400円をレジに持っていったのです。
和歌山城の天守閣の高さは67メートル、都市再開発プロジェクトのホテル建物は80メートル、ホテルが城よりも10メートル以上も高い。
この都市再開発プロジェクトは和歌山県が率先して再開発に奔走し、デベロッパーが計画を立案したのですが、この立案基本コンセプトは「和歌山城に相対する、都市の新たなシンボルを建設することによって、過去と現在の二つのランドマークからなる古都和歌山にふさわしい美しい都市景観を創出します」としたのです。
しかし「和歌山城は和歌山市の歴史的シンボルである。公共空間の最上位に位置することが望まれる和歌山城を見下ろす位置に、城とツインをなすどのような優雅なランドマークタワーホテルの建設が可能だというのだろうか」と指摘し「都市空間の占有、特に建築物の高さ制限に関しては、それぞれの社会の構成員が不文律の約束事として遵守してきた」ものがあると続けます。
加えて、「都市は養育する」のであり、その基本原則は「ゆるやかで自然な、過激でない変化、ほんとうの社会的、経済的要求にこたえるような変化である」とし、和歌山市のランドマークタワーホテル計画は「都市は養育する」精神を踏み外していると、鋭く厳しく痛烈に批判しています。
更に、「都市空間とは『精神的ルーツ』や『過去とのきずな』につながる建物、あるいは聖地・聖域、政治的空間の重要性に従って序列化しながら形成されることが重要である」ので「和歌山城を足下に見下ろす超高層ホテルの建設は、明らかにこの原則にも違反している」と結論づけしています。その通りと本当に思いますし、その実例を愛宕山から見た江戸景観と、現代の東京景観によっても強く感じます。
ベアトのパノラマ写真
手許に幕末の慶応元年(1865)から2年(1866)頃に、イギリス人写真家「フェリックス・ベアト」が愛宕山から撮影した江戸景観写真コピーがあります。恵比寿ガーデンプレイスの東京都写真美術館でコピーしてきたものです。当時世界一の人口100万人を誇った江戸、ベアト写真でみる大都市江戸は整然と落ち着いて上品な景観で、140年後の東京を、ベアトが撮ったと同じアングルから撮影し比較してみますと、つくづく貧しさと哀れさを東京景観に感じます。
近代化という日本人が走ってきた過去の実態、それは、日本人がつくりあげてきた素晴らしい景観をなくす行動だったと思わざるを得ません。都市空間の魅力を失わせること、それが、経済成長という意味であったのかと思い、悲しい思いになります。
国際かきフェスティバルの懇親会は台場の日航ホテルでした。宴会場からみる夜景は、日本開国の歴史を証明する台場と、その向こうに広がるレインボウブリッジと林立する高層ビルの明かりです。それは無秩序に乱立して結果的に輝いているのであって、日本が持ちつづけた良習慣としての「精神的ルーツ」や「過去とのきずな」とつながっているとはとうてい思えず、和歌山市の事例や愛宕山からみた東京と同じでした。「都市を養育する」という精神を大事に復活させること、それが日本の大きな課題であると思いました。以上。
2005年07月05日
熊野と尊徳とトヨタ
YAMAMOTO・レター 環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年7月5日 熊野と尊徳とトヨタ
熊野古道
紀伊半島南東部の熊野地域。連なる山々と深い森。ここが昨年7月世界遺産「紀伊山地と霊場と参詣道」に認定されましたので、梅雨時期の晴れ間の数日、この熊野古道を歩いてまいりました。今は車という便利な交通手段がありますが、中世、ここが日本最大の霊場であった時代は、困難な道筋でありながらも、熊野詣は「蟻の熊野詣」と表されるほど多くの人々をこの地に向かわせ、様々な人々が、様々な思いを抱いて、様々な願いを込めて、途中で行き倒れになる危険を承知で歩いたのです。祈りの道、蘇りの道、それが熊野古道です。また、この道は辺境の山岳地帯にあるため、道案内が必要であったことから、その道案内を修験者がつとめ、この道案内の人を先達(せんだつ)と呼称しました。
今回の熊野古道歩きでも先達をお願いしましたが、今では様々な職業の方が先達をつとめています。今回お願いした先達は熊野古道の宿泊施設のご主人でして、苔むし、木の根が張り出した、昼なお暗い杉林の険しく狭く、いまだ鶯が鳴いている祈りの道、その古道を一緒に歩きながら道の成り立ちについて説明してくれましたが、その中でも「石畳」については成る程と思いました。
道に石畳を敷くことは、この地が多雨地帯であることから、豪雨によって土砂が流され、道が壊されるのを防ぐためであり、また、温暖な気候からすぐに草が茂ってしまい道としての機能を果たさなくなる可能性があるからだ、という先達の説明に納得しました。
つまり、この道が日本人の心を癒す道として役立ち、整備し残していくためには、石を使って人々の歩きを安全にしたいという、古人の創意工夫がつくりだした知恵によって石畳が存在しているのです。このような隠し味ともいうべき古人の多くの知恵が、熊野古道を世界文化遺産にしたこと、それを再認識させてくれた熊野古道歩きでした。
二宮尊徳
二宮尊徳という先人も我々に多くの教えをもたらしています。二宮尊徳は黒船が来て国内の物情騒然たる安政三年(1856)に亡くなくなりましたが、死後149年、今なおその業績を語られること多き人物です。一時は小中学校の校庭に必ず「薪を背負って本を読む二宮尊徳銅像」がある程でした。
尊徳は、幕末時の疲弊した封建農村社会にあって、郷里小田原藩栢山にはじまり、栃木の桜町の三カ村を復興させ、天明の再度にわたる大飢饉を楽々と乗り切る農村に変身させる業績を残し、さらに、奥州相馬十万石、人口10万人の藩を生食溢れる領地に変貌させたのです。これをみた幕府は「日光御神領」改革を尊徳に指示依頼したのです。しかし、すでに病に冒されていた尊徳は改革途中68歳で倒れたですが、今の時代でいえば県市町村行政財政健全化の再建請負人ともいうべき人物でした。
尊徳の改革方法は「仕法」であり、その原点は「分度」の確立でした。
「分度」とは一家の分度、一村の分度、一藩の分度、全国の分度を確立することです。つまり、収入と支出を確然たらしめた予算を確立することでした。
しかし、分度の目的は、入るを量って出を制するという緊縮政策でなく、入るものを出来るだけ多くし、それを社会生活の根源である土地と農民に投入することによって、土地と農民を豊かにすること、それを分度の目的においたことが成功の秘訣でした。
つまり、生産された財貨を、できるだけ消費生活で消費させずに、生産の場へ積極的に再投入し、これによって拡大再生産を封建社会の枠の中で実現させる、という方法が分度であり、その一連の改革方法を仕法と表したのです。
分度を原点とした仕法の第一は、まず該当地を徹底的に統計データで調べることでした。データが無きために尊徳から断られる町村も多々あった程です。第二は、学問だけに頼らず、自然に対する実体験知識の活用を主体とし、第三は尊徳が保有した優れた土木技術力と土地開発力であり、第四は複雑な損益計算と複利計算の手法を取り入れて、元利償還計画をつくり上げる計算力でした。特に第五としてあげられるのは、種金または仕法金、報徳金ともいう最初に必要で投入される元金、それを無利息で貸付できる財力が尊徳にあったことです。それは無類の勤勉家で、天才的な利殖家でもあった尊徳しかでき得ないことであったのですが、尊徳の仕法を受けようとするもの達は、無利息のお金を貸してくれる奇特な人がいるという噂を聞きつけ、それを目当てに尊徳の仕法を受けたいと交渉がはじまり、その交渉過程で仕法という改革方法を理解することにつながっていったのです。
この「仕法」とは、領主の財政再建の当然の方策でもありました。ある期間を区切って領主の分度を設定し、土地の収穫から領主に取り上げられる量を、いわば「括弧」の中に入れてしまうのですから、領主はその期間収入は増えず、一定の分度という予算の範囲で経営していかねばならないのです。ということは、仕法によって増収が図られたとしても、その増収分を土地の拡大再生産に再投入し、そのことに全力を集中できるような仕組み、それをまず固めていくことになります。
次に、農民に対しては、かっては耕地であったが、農村の衰亡により荒地化した土地を元に戻すという作業に取り掛からせます。また、その作業を農民一人ひとりの努力だけによって問題が解決できるという理解をさせること、つまり、本来の荒地を開墾するほど困難でないという「易き」から着手し、本来目的の「難事」へと進むという理解をさせて、その「易き」に全力を結集させる仕組みとしているのです。
これは、考えてみれば、生産する原場人間のやる気を起こすという人間心理をついた巧妙な方法ですが、それと共に一方の為政者には、一定の予算範囲内で経営するという自律を求めているのですから、現在の国県市町村が見習うべき当然の改革方法であったのです。
改革として、まず人のやる気を引き出し、その上で為政者に自律を求める、それを実践的に展開したところに二宮尊徳の偉大さの根源があります。
トヨタ自動車
6月末は株主総会のシーズンでした。いくつかの総会に出席してみましたが、各企業ごとの社風によって運営方法が異なり、それなりに面白い体験をしましたが、変わらないのは企業は社長が運営するものである、という事実です。社長によって企業は良くも悪くも、成長もするし、停滞もするのです。
世界のトヨタ自動車も社長が変わりました。その渡辺新社長へのインタビューが日経新聞に掲載され(2005.7.2)、その中で次のように述べています。
「開発や調達、生産、販売など各部門が抱えている兆候を『見える化』し、何が足りず何を補強すべきなのか明確にする」
この中の「見える化」発言に、トヨタは社長以下一つの仕組みでつながっていると思いました。なぜなら、社長の口から「見える化」という具体的なカイゼン手段方式が自然に表現されているからです。
トヨタのカイゼン運動は世界中で有名になりました。カイゼンという日本語がそのまま通用する言葉になっているほどです。カイゼンについては、トヨタの関係者の何人からお話しを伺ったこともあり、実際にトヨタに見学に行ったこともありますので、以下に少し補足してみます。
● トヨタは当たり前のことを根気よくする集団だ。
● 何に対しても疑問を持つことからはじめ、このために何故を五回繰り返す。
● 現状をそのままルール化し、次にそのルールを直すことからはじめる。
● 改善は小さな積み重ねだ。
● 全ての答えは現場にある。現地、現物、現実、現認。
トヨタの宣伝係ではありませんが、このような内容は世間に流布されていますし、その内容は別に事新しいものではありません。特に秘訣があるわけでなさそうです。渡辺新社長の「見える化」発言も、問題点を明らかにすることですから、経営者にとって当たり前のことです。これが世界一のトヨタ自動車経営のすすめ方なのです。
昔も今も変わらないセオリー
熊野古道を世界遺産にしたのは、古道石畳を整備した古人の気持ちが原点にあったからです。二宮尊徳が財政改革として行ったことは事新しい方法ではなく、農業生産現場の人たちのやる気を引き出す仕組つくりでした。トヨタの経営も新しいことではなく、当たり前のことを熱心にあきらめずに継続追求した結果、それが世界一にしたと思います。
2005年06月21日
情報社会の中で
2005年6月20日 情報社会の中で
「森は海の恋人」運動の提唱者である畠山重篤さんの会社、今は宮城県唐桑町ですが、市町村合併で、もうすぐ気仙沼市唐桑町になる事務所にお伺いしました。
畠山重篤さんとは拙書「フランスを救った日本の牡蠣」に、推薦文を書いていただいた関係で、その後も親しくしております。
今回も壁にぎっしり本が詰まっている応接室、といっても牡蠣と帆立の養殖漁業ですから、海に面した木造二階建て事務所、その入り口あたりには箱に入ったまま、無造作に牡蠣や帆立が置いてある環境下の応接室ですので、小さな机と椅子があるだけで、別に装飾的な華美なものはありません。そこで畠山重篤さんとお互い近況報告しあったのですが、今回は衝撃的な発言が畠山重篤さんからありました。
それは、京都大学の教授になったという内容です。一瞬ビックリしましたが、しかし、建築家の安藤忠雄氏も東京大学教授になったのですから、畠山重篤さんが京都大学教授になってもおかしくないと考え直し、それでは京都に行く回数が増えるのですね、と尋ねますと、「いや、新しくできた『京都大学フィールド科学教育センター』のシンポジウムで講演するとか、三陸の海に来てもらってセミナーを開くことが中心です」との回答です。
日本の大学は学部ごとに独立していて、お互いの連携が薄いのが特徴です。京都大学もそのような実態で、林学の研究林は80年の歴史があり、水産実験所は50年歴史があるのに、林学と水産学の学者が交流したことが殆どないという実態でした。
ところが、2003年3月に開催された「世界水フォーラム」で、畠山重篤さんが発表した「森は海の恋人」運動を知った京都大学は、これをヒントに林学の演習林、理学の臨海実験所、水産の水産実験所を統合し、京都大学フィールド科学教育センターを設置したのです。
加えて、人と自然の共存の在り方を提示しうる「森里海連環学」という全く新しい学問を起こし、ここの社会連携教授として畠山重篤さんが就任したのです。
素晴らしいことです。リアスの海で、毎日長靴を履いて船で作業している人物が、京都大学の教授になったのです。それも、自分から売り込んだわけでなく、京都大学からこの雑然とした事務所に訪ねて来て、この小さな机の前で依頼されたのです。日本の大学が時代の感覚を取り入れ、柔軟性に満ちた改革をし始めた証拠です。嬉しくなりました。
ぬりえ学会に来た若い男性
ぬりえ美術館で主催している「ぬりえ研究会」、もう一年以上続けているのですが、ここでの成果が今年8月末に「ぬりえ文化」として発刊されることになりました。
その原稿を書き上げたタイミングに、ぬりえを文化として確立するためには、更に深める作業をする必要があるとの視点から、「ぬりえ学」を目指そうということになり、今月から「ぬりえ学会」をスタートさせ、その紹介をぬりえ美術館のホームページに掲載したところ、ぬりえメーカーの入社2年目の若い男性社員から参加申し込みがありました。
「ぬりえ学会」初回の6月16日、長身細身・長髪の若い男性が颯爽と時間どおりに参りましたので、早速、どうしてこの会に関心を持ったのか聞いてみました。答えは「高齢化社会が進むので、痴呆防止のために大人にぬりえを広めたい。すでに一部の介護施設で始めているが、それを一般層に広げたい」という理由です。ということは、自分が勤めている会社の仕事としての延長から、この「ぬりえ学会」に興味を持ち、そこから業務の拡大を図りたいという意味です。
そこで、こちらからは「単に大人のぬりえをつくって売りたい」という意図だけでは、商品は出来ても期待するほどの成果は得られないだろう。成果を求めたいのなら、自分がぬりえというものについて、専門的な知識と体験をしっかり持ち、ぬりえに関して一応のプロになることが必要だ、と伝えますと「そのとおりと思います」という素直な回答です。
真面目な気持ちで参加したことが分かりましたので、ぬりえが持つ背景状況、それは、これから向かっていくであろう世界人口の推移について、まず解説しました。
1972年にローマクラブから「人口増と環境悪化、資源浪費で100年以内に地球上の成長は限界に達する」という発表があった。しかし、この中の人口問題については、21世紀に入って「世界人口は一定の静止状態になり、中先進国では高齢化が著しく進む」という予測に変わっている。そのような状況であるから「痴呆防止のために大人にぬりえを広めたい」という希望は世界的な需要として期待できる。従って、ターゲットを日本国内だけでなく中先進国に広げる、という発想に立つことが重要だ。
また、そのような実例としてアニメーションの世界があって、日本が圧倒的に世界標準となっている、という実態を伝えると「アニメーションはぬりえが原点ではないでしょうか」という返事です。そのとおりなのです。アニメーションは静止絵が重なり動き、それによって映像化していくのですから、最初は線画に色を塗ることから始まっているのですからぬりえが原点といえるのです。やはり若い人は素晴らしい感覚だと、嬉しくなりました。
愛知万博の好調さをどう意味づけるか
愛知万博がますます好調になってきました。6月18日(土)は今までの中で最高の17.2万人という入場者でした。最低が3月オープン初日の4.3万人でしたから、最低と最高の差は12.9万人で4倍です。また、開幕以来10日毎の入場者数をウオッチングしてみますと、最初の10日間の一日平均が6.1万人に対し、6月11日から20日までの10日間は13万人となっていて、これまた2倍の増加を示しているのです。出足は確かに不調でしたが、徐々に日を追うごとに好調になってきて、これで目標1500万人を大きく超過し、1800万人にも達するのではないかと予測されます。
通常のイベントでは初日が好調で、その動きを引きずってその後も順調に伸ばしていくという状況推移が多いのですが、今回の愛知万博はこの動きと全く異なります。
出足が絶不調で、これは大失敗でまたもや国の赤字を増やすのかと心配しましたが、5月の連休辺りから調子が出てきて、夏休み前の梅雨時で季節的には難しい6月18日に最高入場者数を示したのです。
この好調要因をどのように判断するのか。どう意味づけるのか。それが各地で話題になっています。それについて日経新聞(2005.6.18)は次のように分析しました。
1.入場者数を押し上げているのは「団体客」と「リピーター」。開幕当初に一日一万数千人だった団体客はゴールデンウイーク後、約三万人に増加。
2.特に修学旅行など学校行事の入場は全国の2800校約七十万人を超えた。
3.期間中に何度も入場できる全期間入場券の平均入場回数は3.7回で、最高は60回以上に達する。
4.入場者の居住地調査結果では、愛知、岐阜、三重の3県が53%、関東地方は15%、関西は14%と過去の国際博と比べ、国内入場者は地元色が濃いようにみえる。
5.海外からの入場者はいまひとつ。協会は「7月にかけて海外メディアへの広告や旅行展への出展など積極的なPRに務めたい」という。
この日経新聞分析で特筆すべきことは、地元圏の貢献です。地元の名古屋人は日頃から「お値打ち」と何度も口にし「価格と価値のバランスを重視する。名古屋人には価格帯は問題ではない」といわれ「普段の財布のひもは固いが結婚式は盛大で、高級ブランドも大好き」との特徴であるといわれています。
そのシビアな「お値打ち」感覚の地元の人たちが、入場者の半数を占めていることが分かった愛知万博、今まで、中部経済が全体的に好調であることや、万博の方向性の妥当性や、環境に対する感覚の高まりなどについて、このレターでいろいろ分析してきましたが、今回は新しい地元圏が要因であると、また発見できたのです。好調要因はいろいろ絡んでいます。
情報社会の中で
現代は情報化社会で、身の回りにあらゆる分野の情報が溢れています。この状況が意味するところは、情報が各種メディアによって大衆化されていき、情報そのものは相対的に希少価値が減っていくということになります。つまり、情報はIT技術によって簡単に入手可能となり、その結果、情報そのものの価値よりは、むしろその情報がどのような意味合いを持つか、ということが重要になってきています。
畠山重篤さんは「森は海の恋人」という短い言葉に時代の意味づけを持たしたことで教授になり、ぬりえをアニメの原点だと素早く意味づけできる若い感覚が大人に広げたいという希望につながり、万博に「お値打ち」感覚を見いだした地元中部地区人たちによって好調万博は支えられている。これからは情報を意味づけすること、それが大事と思います。
2005年06月06日
はじめてなのに懐かしい
2005年6月5日 はじめてなのに懐かしい
各地に出かけると
名古屋駅の地下鉄東山線ホームに立ち、線路の向うをみると「このホームから転落した時は、ホーム下の奥へ避難してください」と書いてあります。このような表示は他の駅ではみたことがありません。地下鉄東山線名古屋駅は、ホームから転落する事故が多いのか、それとも単なる危険防止の注意事項か。
それにしても転落した時は、多分、慌てているだろうから、すぐにホームに登ろうとするはずです。しかし、この表示の意味するところは、線路からホーム上に戻ることが実際には難しいのか。一瞬ドキッと緊張感を与える掲示文字でした。
浜松町から羽田空港に行くモノレールに乗って、ドア上に表示されている終点駅をみると「羽田空港第2ビル駅」とあり、その前駅は「第1ビル駅」となっています。いつの間にか空港駅が二つになっているのです。昨年の12月に終点駅が変わっているのです。
「第1ビル駅」で降り、荷物検査を受けてJALのラウンジに入り、少しゆっくりしようとお茶・ジュースのサービスカウンターに行ってみて気づきます。明らかにサービスメニューが減っています。何が減っているのか。冷蔵提供していた水・お茶のペットボトル類がなくなっています。この実態でJALの経営状況が分かります。
各地に出かけますといろいろ変化に気づきます。
持続的成長・サステイナビリティ
万博に行くため、名古屋城に近い旅館に宿泊申し込みしたところ「朝食はどうしますか」との質問に「お願いします」といいますと「皆さん、朝食とらずに万博に行きますよ」という回答です。万博に行くなら、早く行って人気のパビリオンに並んだほうがよい、という親切な気持があらわれている電話応対です。
万博が一段と元気になってきました。6月5日現在で662万人となり、目標1500万人達成に必要な一日8.1万人に対して、1.1万人多い9.2万人となりました。
名古屋大学で開催された「愛・地球会議」でも、万博事務局長が胸張って入場者数を元気に報告しました。この会は「持続可能な社会の創造」をテーマに、世界の有識者や専門家が参加するシンポジウムで、万博開催の3月から9月まで毎月開催されているのです。6月2日は「21世紀の産業基盤~循環社会へのメッセージ」がテーマで、雨降る中、多くの人が名古屋大学に集まりました。
会場内で気づいたことがあります。発表者から「持続的成長・サステイナビリティ」という言葉が多発され、これからは「ゆっくりと熟成した成長」が必要であるという主張がなされていることです。環境重視の視点からは当然で、会議のコーディネーターである茅陽一博士(地球環境産業技術研究機構副理事長)から、前提背景条件として
1. 世界人口は21世紀にゼロ成長になるだろう
2. しかし、経済は何らかの成長を遂げなければならない
3. そのためには、資源の循環化、エネルギーの脱炭素化が必要
の3項目が提示され、時代は「持続的成長・サステイナビリティ」の方向に向かっていることを確認いたしました。
マンモス絶滅ストーリー
愛知万博の8人乗りのゴンドラ、何処か地方訛りの中年女性が7人、その中に1人加えてもらって瀬戸会場に向かいました。女性は親切です。すぐに飴やお菓子を差し出してくれながら「朝一番にマンモスをみてよかったよ」と語りかけてきます。
ゴンドラは途中2分間、一切外がみえない窓ガラス状態に瞬間にして変化します。これは何だ、と一瞬女性たちはガヤガヤしますが、窓外の住宅透視プライバシー保護のためと分かって、成る程ね、とその技術に感嘆するため息に変わります。
さて、「マンモス」がどうして万博のメイン展示場のグローバル・ハウスに存在するのか。当然、マンモスを展示するには意味があります。名古屋大学のパネラーで登場したグローバル・ハウスの福川館長、この人物は元通産省事務次官ですが、マンモス絶滅は食糧危機からなのか、それとも環境変化によるものなのか、いずれ学者によって明らかになるだろうと発言していましたが、マンモス絶滅のストーリーを宇野正美氏は次のように推測しています。
「ツンドラ凍土から殆ど完全な形でマンモスが掘り出されたことがあり、そのマンモスの胃腸には食べた植物がそのまま残っていた。これはゆっくりとした変化ではなく、急に大変化が起きたことを示している。予測がつかないスピードでマンモスの身体全体が凍結していったのである」(国際時事情報誌エノク2005年6月号)と。
つまり、宇野正美氏の主張は、気象条件の劇的変化によって、一瞬にしてマンモスは滅びたというのです。これを事実として受け止めれば、シベリアの奥地凍土からわざわざマンモスを掘り出し、名古屋まで運んできたのは、地球環境の悪化によって、再び過去と同様の劇的変化が未来に発生する可能性があり得るし、今度はマンモスの替わりに人間が凍結するかも知れないという恐れ、その情報を伝えるためにグローバル・ハウスのマンモス展示があると理解できます。
多くの人がマンモスをみたいという背景、それは勿論、興味本位でしょうが、その興味の奥底を推測すれば「どうしてマンモスが絶滅し、それが万博のメイン展示物となっているのか」ということに、漠然とした疑問を持ちつつ、マンモス絶滅と地球環境と人間の未来、それらを結びつけて考えられる人々、それらの人たちによってマンモスが人気となっているのではないかと、と思っています。但し、「朝一番にマンモスをみてよかったよ」と語りかけてきた中年女性グループが、そのような感覚であるかどうかは分かりませんが。
なつかしの風景
愛知万博の人気パビリオンは大変な状況です。会場前に並ばずに入れる、事前予約を済ませた会場入場券が、インターネットのオークションに大量に流出し、高値で売買されています。(日経新聞2005年6月3日) 一番人気のトヨタ館と日立館は、日曜日の予約済み入場券が一万四千円という高値、実際にインターネットで事前予約システムに応募しても、予約済みを確保するのは至難の状況ですので、オークション購入に向かうのも分かります。
この人気はハイテクの企業だけでなく、アニメの「サツキとメイの家」も大人気です。「サツキとメイの家」は昭和30年代の生活を描いた、宮崎駿監督の長編アニメ「となりのトトロ」(1988年)に登場する家を復元したものです。この入館引換券も競売サイトに出回ってしまい、今はハガキによる予約方法に変更になり、先日ハガキで応募したところですが、とにかく人気があります。
その人気の背景に「昭和時代を懐かしむ」傾向があげられ、日本各地の昭和時代を復元した施設にも多くの人が訪れて、正に昭和時代が時流で、そこを訪れる人たちは二つに区分けできます。昭和時代を体験している人たちと、そうではなく「昭和時代を未体験の若者たち」ですが、「未体験の若者」の多くが、訪れて「はじめてなのに懐かしい」と発言します。
しかし、昭和時代には生まれていなかったのですから、若者の「懐かしい」という表現は矛盾し、論理的にはあり得ないことですが、実際にそのように発言するのですから、若い人たちの奥底人間感覚に触れる何か、それが「昭和時代」にあると思います。
レッサーパンダが立ち上がった
千葉県で一頭のレッサーパンダが立ち上がって、二本足で歩いたと思ったら、他のところのレッサーパンダも同様に二本足で歩いて、それが大人気です。飼育係りが差し出す手に向かって二足歩行する姿、それをテレビでみて「かわいい」と思いつつ、一瞬何かが脳内を走ります。それは人類の歴史をみた、と思ったからです。400万年以上前、直立二足歩行を始めた猿人は、まず、両手があいたため、手で道具をつくるようになり、それまで顔の両側についていた眼が顔の前面に並んでつくことになり、両眼視という遠近自由焦点操作が可能になり、頭部の肥大化から脳の発達へと結びついたのです。この歴史事実をレッサーパンダが再現したのではないかと思い、そこに一瞬「懐かしい」という感覚に襲われたのです。「かわいい」と発言する奥底に、人間の遠い古い原点過去という「懐かしさ」を感じました。
はじめてなのに懐かしい
どうも愛知万博には妙な感覚が備わっているような気がしてなりません。各地に出かけてみつける新しい変化ではなく、「はじめてなのに懐かしい」というような人間の奥底に存在し、引っかかるもの、その部分が万博会場にあるような気がしてなりません。それが何であるか。具体的に指摘することは難しいのですが、人間の奥底に存在する何かの感覚、未来の世界が向かわなければいけない時代感覚、それが愛知万博会場にあるように感じます。以上。
2005年05月22日
武士道と愛知万博
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年5月20日 武士道と愛知万博
イラクで働いていた
前回レターでお伝えしたハローワークでの「イラク求人広告」、その際に「イラクに行けば金になると世界から様々な人が危険を承知で、傭兵とか、土木関係の作業員として集まっていている」ともお伝えしました。それが5月5日のレターで、その4日後の5月9日にイラクの武装組織「アンサール・スンナ軍」が斉藤昭彦さんを拘束していることを伝え、イラクに日本人がいることが判明しました。
斉藤さんはイラクで英国系警備会社ハート・セキュリティ社に勤めていて、それまでの経歴は自衛隊と、フランス外国人部隊に傭兵として長く所属していた「プロの軍人」です。今でもフランス外国人部隊には40人の日本人がいるそうです。
世界で最も危険な地域のイラクに世界中から人が集っていて、その一連の動きとして長崎ハローワーク「イラク求人広告」もあったのだ、と改めて理解しているところです。
新渡戸稲造の武士道
新渡戸稲造の「武士道—日本の魂」が出版されたのは1900年で、この本を書いた動機を、同書の中で以下のように説明しています。
「約十年前、ベルギーの高名な法学者、故ド・ラヴレー氏から『日本の学校には宗教教育はないと言うことなんですか』と、尋ねられた。私が『ありません』と答えると、すかさず、教授は『宗教なしとは! 道徳教育はどうしてほどこされるのですか?』私は即座に返答できなかった」と。
しかし、武士道を書くに至った本当の「動機」は、別のところにあったのではないかと推測します。当時の日本の状況から考えたいのです。明治維新後わずか二十数年で大国清国に勝利した日本、世界から「野蛮で好戦的な民族」とみられ誤解されていたと思います。外国にいた新渡戸稲造にはそれを直接肌身で感じ、心配し、正しく日本人の姿を伝えなければいけないと思ったはずです。
といいますのも、新渡戸稲造の武士道は、江戸時代に明確化された武士道ではないのです。武士道というタイトルですが、武家社会だった江戸時代の武士道ではなく、日本人の精神基盤にある「普遍的な倫理観」、それを武士道として表現し、それを世界に日本人の精神構造として知らしめたのです。
更に、また、同書の最後に次のように書いてあります。
「<武士道>は独立した倫理の掟としては、消え去るかもしれぬ。しかし、その力はこの地から滅び去ることはないであろう。武人の勇気や公民の名誉を教えるその学院は、破壊されるかもしれぬ。しかし、その光とその栄光は、その廃墟のあとまで長く生きのびるであろう。・・・(中略)・・・幾世をも経たのち、その慣例は埋め去られ、その名さえ忘れ去られても、その香りは、『道ばたに彼方を見つめれば』、はるか彼方に目に見えぬ丘からのように、空をただよって来るであろう」と。
つまり、日本人のDNAには、武士道精神が奥底に基盤として存在しているので、決して忘れ去ることがないモノである、と最後に書き残しています。
武士道の二つの側面
武士道研究家の第一人者である笠谷和比古教授(国際日本文化研究センター)は、著書(武士道その名誉と掟)で武士道の二つの側面を述べています。
「武士道の一つの側面は『忠義』の観念で、それは『主君−家臣』というタテの関係である。もう一つの側面は『名誉』の観念で、これは個々の武士の『武士としての自我意識・矜持』としてのヨコの関係として存在する」と。
この二つの側面を今の時代に当てはめ、会社組織に例えていえば「忠義」は社長・上司との関係、会社の組織一員として働く立場からは「名誉」を「人間としての規範・矜持」として理解できます。
新渡戸稲造の武士道は、この二つの側面の「名誉」を中心ポイントに取り上げているのですが、それは、書いたときが封建時代が終わった明治時代ですから当然で、このヨコ関係としての「名誉」、現代風にいえば自らが持つ「志・大義・理念・良心」等の、自己の内部に存在する「人間としての規範・矜持」が最も大事と考え書いたのです。
「愛・地球博」愛知万博に行こう
3月25日に開幕した愛知万博は当初不振でした。入場者目標1500万人、これを開催日数で割りますと、一日平均8.1万人の入場者が必要です。
開幕して最初の土曜日は4.6万人、日曜日は好天でしたが5.7万人、万博事務局の計画は15万人でしたから、三分の一の達成率でした。これで先行きを心配していたのですが、5月19日現在で462万人、一日平均8.4万人となりました。
イベント等にみられる一般的な動員傾向は、立ち上がり当初が好調ですと、それを引きずって後半も順調に行くので、愛知万博当初の不振は今後に懸念を生じさせました。
ところが、ここに来て、ジワッと集客力が高まってきました。爆発的な人気、すごい目玉的な存在、それが見当たらないのに会場に人が集まりだしたのです。
その要因として、既に何回も万博に行き、会場の状況に詳しい人からお聞きしますと、「従来の万博とは異なっている」と明確に発言します。
多くの人は大阪の万博、1970年ですが、この高度経済成長途上の万博残像を持っていて「何か面白くて目立つもの」があると思い、実際に愛知万博に行ってみると、結果は「従来の万博とは異なっている」と一様に発言するのです。
愛知万博は「環境がテーマ」であることは誰でも知っています。ですから「環境にやさしい万博だろう」程度で行くと、そこには「ポスト環境」ともいうべき技術やビジネスモデルが並んでいて、そこで時代は新しい21世紀に入っていることを感じ取るのです。1958年のブリュッセル万博は「核技術」がテーマでした。原発によってエネルギー問題が解決されれば、世界はハッピーになるという発想だったのです。その当時はそれが最先端時代感覚だったのです。今では誰もそう思わない、考えられないテーマだったのです。前回のハノーバー万博テーマは「人・自然・技術」という三者の集大成、つまり、20世紀最後のハノーバー万博は環境技術の総まとめでした。
しかし、21世紀最初の愛知万博は「自然の叡智」がテーマとなり、ハノーバー万博テーマから「人」と「技術」が消え、残ったのは自然であり、その叡智だというのです。
この叡智とは何か。それは具体的に明確には分からないまでも、現在の環境問題への対応状況では、地球世界が危ないという意識と共に、次の新しい「安全な世界物語」の創造が必要である、という感覚が日本人には分かっていて、その内面下意識の顕れ、それがこのところジワッと集客が増えてきた理由ではないかと推察しているところです。
都電が懐かしい
ぬりえ美術館に取材で来るマスコミ、その人たちが一様に語るのは、都電とぬりえのミックスが時代感覚に合っているということです。走る車の邪魔になるからと、都電を廃線にしてきた日本の各都市、今になってみれば都電が残っている街並みを高く評価するのです。香港からも都電とぬりえの視察に来るほどです。路面電車は車の邪魔で「もはや時代遅れ」だと、渋谷の玉川通りの坂道を上っていた「玉電」と、御徒町昭和通りの都電を消した発想は、1958年のブリュッセル万博の「核技術」をテーマにしたことと同じです。市電を残し、郊外まで延伸活用しているドイツ・カールスルーエに世界中から視察に行くのは、当時の考え方が問題であったと分かり、昔がよかったと懐かしむ気持ちからです。人が本来持っている「自然感覚」が戻ってきつつあると思います。
万博は世界の方向性を示している
日本人は、その精神基盤に存在した武士道精神を忘れ、経済優先で走ってきました。だが、「その名さえ忘れ去られても、はるか彼方に目に見えぬ丘からのように、空をただよって来るであろう」と最後に新渡戸稲造が書き残した武士道精神は、我々のDNAに残っているはずです。愛知万博は20世紀に破壊し苛め抜いた地球環境、それを人間の持つ「志・大義・理念・良心」から発した「自然感覚」による「叡智」で組み立てなおすことがテーマです。忘れ去られた武士道精神が「はるか彼方からただよってくる」のと同じく、「彼方に見え始めた安全な世界物語」を求め始めだした日本人を愛知万博へ向かわせ、その人達によりジワッと集客力を高めてきているのではないでしょうか。以上。
2005年05月06日
時代の中での判断基準
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年5月5日 時代の中での判断基準
イラクで働かないか
イラクで働かないかという求人広告が、ハローワークに出たと赤旗新聞(2005.3.28)が報道しました。長崎のハローワークで、地元の会社が求人票を出したのですが、元請がどこかは分かりません。給料は二週間で50万円で、渡航費用は全額支給です。二週間経って求人票は消えましたが、応募した人がいたそうです。
朝のNHKラジオに時折登場する経済評論家の藤原直哉氏によると、イラクに行けば金になると世界から様々な人が危険を承知で、傭兵とか、土木関係の作業員として集まっていているそうです。今回応募した日本人はお金が目的か、それとも別のものがあったのでしょうか。
東京駅前郵便局
郵政民営化が大詰めを迎え、もうすぐに決着がつくと思いますが、いつも不思議に思っていることがあります。東京駅前の中央郵便局のことです。
先般、ドイツのカールスルーエに行き、街中を歩いていて疲れたのでカフェで一休みしようと、店がたくさん集まっているビルの中に入りました。入り口を入るとすぐの左側片隅に郵便局がありましたので、地元の人に「ショッピング街の中に郵便局があるのですね」と尋ねますと「ここはもともと中央郵便局でしたが今はショッピング街に変身したのです」という答えです。郵便局は片隅で全体の10分の一にも満たないスペースになり、内部改装し、郵便局がビル所有者でテナントとして多くの店が入ったのです。場所は街中の一等地ですから、市民が大勢立ち寄って買い物・飲食を楽しんでいます。
同様なことが東京駅前の中央郵便局でも、できないかということです。東京駅前に中央郵便局をおいた発想は鉄道で配達する時代のものでした。
今は状況が変わっていますし、東京駅前は車が多く、一流企業が集積する一等地ですからいつも渋滞しています。また、回りを見れば東京駅丸の内界隈は再開発で大変化しているのですから、中央郵便局敷地評価額1600億円を効果的に活用してもらいたいと思っています。同様に全国各地の一等地に所在している郵便局が、民営化されれば素晴らしい改革変化ができるはずで、民営化後に期待したいと思います。
尼崎脱線事故
JR西日本の尼崎脱線事故は悲惨でした。通勤列車でしたから多くの被害が発生し、改めて交通機関の怖さを感じました。
その加害当事者であるJR西日本の幹部の対応が厳しく問われています。事故後の記者会見での迷走や、被害者・家族への対応、社員の事故当日親睦ボーリング大会の開催と飲み会、全く常識を欠いた行動です。幹部への批判として代表的な事例は「用意された文章を読み上げて謝罪した垣内社長」です。このずれ込んだ感覚差はどうしようもありませんが、問題なのはこのような感覚の人がトップになっているという事実です。
企業幹部となっている人たちとは、ある目的をもった一つの組織の中で、多数の人と競争し生き残って階段を上がることができた、という人種です。ですから、ある意味での企業論理・常識を十分持ち、それを駆使した行動をしてきたからこそ、幹部になれたのです。
企業にはその会社の社風を含め、ある基準が存在します。一般社会とは異なった基準と考えてよいと思います。その社風・基準にうまく合格した人たちが幹部であり、それが企業内部では成功といわれる人たちなのです。ですから、企業感覚には優れているが、そこで上手に適応することで生きてきたために、普遍的な感覚を失いやすいというデメリットがあります。これがJR西日本の幹部に見事に発揮されているのです。
生活環境と生活習慣
「諸法無我」という言葉があります。広辞苑によると「いかなる存在も永遠不変の実体を有しない」とあります。この意味を「物事の実体と本質は、その物事の回りに存在する関係で決まる」と解釈しますと、我々が現在持っている常識感覚の内容は「自分の回りを取り囲む生活環境と生活習慣によって決まる」と理解できます。
イラクへ働きに行くことに応募した人、それはその人が持っている生活環境と生活習慣によつて、つくり上げられた考えから判断したと思います。
東京駅前の中央郵便局、前をみればオアゾという新しいエキサイティングなビル、左側をみれば再開発された丸ビル、その隣は現在再開発中の新丸ビルがあり、東京駅周辺はすごいスピードで変化しているのです。変わらないのは中央郵便局だけで、変わらない理由は郵便局に存在している生活環境と生活習慣からです。
事例としてあげるのも嫌なのですが、悲惨な事故に対する対応感覚のずれたJR西日本幹部達、これもJR西日本の中に存在する生活環境と生活習慣からです。
山岡鉄舟
この連休は月刊ベルダ誌に、山岡鉄舟の連載第一号を書くために費やしました。雑誌の連載ですから各号ごとの字数は制限されていますので、実際に書上げる時間はそれほどかかりません。しかしながら、改めて山岡鉄舟物語を書くという意味を考え、その考えをどのように組み立てるかというところに精力を費やしたのですが、結局、それは山岡鉄舟という稀有な人材を自分の常識で判断し、書き著すしかないと気づいたのです。
ということは、山岡鉄舟という人物を語るということを通じて、自分がいつも何を想い、どのような生き方をイメージし描いているか、そのことを幕末明治維新史という歴史舞台を通じて表現することになるのです。これはとても怖いことです。自分の考えと常識を、世間という広い一般社会に、雑誌という公共的媒体で発表するということ、つまり、自分の生活環境と生活習慣を発表することになるのです。
ぬりえ文化
山岡鉄舟を書く直前まで「ぬりえ文化」を書いていました。一応書上げ秋に出版となりますが、これも苦労しました。理由は「ぬりえ」ということを描いた経験、少しはあったとしてももうかなり昔の幼いときの思い出しかない、そのぬりえを「文化論」と論じていく。これは難しいことだと感じていたからです。
「ぬりえ文化」を書こうと思ったのは数年前からです。東京都荒川区に「ぬりえ美術館」が設立されたのが三年前、その設立構想段階から参画していましたので、ぬりえを「文化」にする必要性は感じていました。そこで、いずれ取り上げたいと思っていましたが、そのキッカケ・切り口が見つからなく数年過ごしたのです。
書くキッカケ・切り口が見いだしえなかったのは、自分の中にぬりえに対する感覚と常識が欠けていると認識していたからです。しかし、常識が欠けているのならそれをつくりあげればよいのだ、と思い直したときから楽になりました。
様々なところから資料を集め始め、整理し分析しているうちに、ようやく頭の中に構想が浮かぶと共に、金子マサ館長という共著者の協力もあり、ようやく連休前に書上げられたのです。ずい分時間がかかりましたが、終わってみれば子どもの遊びであり、子どもが楽しみに描くものですから、そのところを素直に捉えて、自分の常識からぬりえを捉えればよいとおもったときから書き出せたのです。よい経験になりました。
時代の中での判断基準
連休中にも「ぬりえ美術館」にマスコミ取材が多くありました。マスコミの関心は「ぬりえ美術館」の近くを通る都電、それが今人気なので、都電とぬりえを結びつける企画で取材にくるのです。昔は路面電車が多くありました。渋谷の玉川通りを走っていた「玉電」、御徒町を走っていた「都電」、これらを消したのは日本の戦後の「もはや路面電車は時代遅れ」という交通政策で、消した後を首都高速道路の高架で覆ったのです。
ところが、すでに紹介したカールスルーエの目抜きカイザー通りは、人と電車しか入れないショッピングモールとなって、人と電車の共存が実現しているのです。日本は電車を消し、ドイツは残しました。同じ敗戦国でも判断基準が異なりましたが、今になってみれば日本人の多くは都電を懐かしく求め始めたのです。この感覚のずれが怖いのです。そのときの政策推進者の常識感覚と判断基準が社会をつくりかえていくのです。
山岡鉄舟は誰も見通しのつけられなかった巨大な歴史的課題に、徒手空拳で立ち向かい、結果的に時代を見通した判断基準で、新しい明治維新という姿を実現させたのです。以上。
2005年04月21日
万博に行く意味
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年4月20日 万博に行く意味
愛知万博に行こう
愛知万博の入場者数は4月20日現在179万人です。期間中の動員目標は1500万人、これを開催日数で単純に割れば、一日8.1万人。これが平均一日あたりの目標入場者数です。20日までの人数を開催済み日数26日間で割れば、一日あたり6.6万人ですから、目標8.1万人に対して81%の達成率です。
一般的にイベントは、立ち上がり当初の動員状況が、その後の推移に大きく影響します。
万博事務局は、当初開催日と翌日の入場者数を15万人と予測していました。だが、雨という条件があったとはいえ、実績は4万人台と大きく予測を下回り、これで目標への道のりが黄色信号となりました。
実際に万博会場を経験してきた人に聞きますと、会場で目玉となるものが少ないという意見が聞かれます。その目玉が欲しいという意見、そこに万博の開催目的と入場者とのズレがあります。テーマは「環境博」で、今の世界の最先端環境情報を伝えるべく編集してあり、1970年大阪万博のように、面白く・楽しく・驚きがあって楽しいというイベントとは異なるのです。ところが、訪れる人たちは、環境博という言葉を知って、その意義の理解をしていても、会場を訪れて「もう一つ何かが欲しいなぁ」という感想をもらします。どうもこれは従来の大阪万博イメージを引きずっているのではないか、という感がします。
この感覚のズレをどうやって解消し、入場者増加につなげることができるのか、そのところに対する万博事務局手腕が問われますが、現状のままでは、多分、達成目標に届かず、結果として赤字を発生させ、補填として税金が投入され国民負担になります。ですから、ここは愛国心で「愛知万博」に多くの人が訪れることが必要ではないでしょうか。中国反日デモの「愛国無罪」でなく、日本人は「愛国参加」で愛知万博に行こうではありませんか。
大学の現状
少子化が最初に経営に対して影響を与えてきたのが大学です。大学希望者は全員大学に入れるという「全入時代」が訪れました。しかし、実際には人気大学に受験生が殺到しますから、定員割れの大学が続出することになります。
その結果、生徒が集まらない大学は経営危機を迎えますし、もうすでに何校かは倒産し、大学閉鎖していて、この動きは加速化されていきます。
卒業生にとって「母校が消える」という結果が常識だ、という時代になってきたのです。
これに対する対応策、それを、今、最も大学実態に詳しい、クイック教育システム社の
矢澤昌敏氏を経営ゼミナールにお呼びし、レクチャーを受けました。
といいますのも、少子化が招く経営危機は、すぐに一般企業に押し寄せ、大学と同じ現象が発生しますから、各大学が知恵を絞っている内容を検討しておくことは、近未来の企業経営にとって重要情報収集になるからです。
しかし、今回の矢澤氏のお話で改めて明らかになったことは、少子化問題も然ることながら、大学生の質の劣化も大問題として存在することでした。従来のイメージとは異なった学生に変化しているのです。学生は勉強するものだ。これはもう古い実態なのです。ということは学力がないまま卒業し、新入社員として各企業に「お勤め」することになるのです。
企業はどう対応するか
かっての大学生とは異なった質の若者、その人たちを新入社員として受け入れる企業側は、自社が持つ既存の「企業体質」に早く馴染ませ、慣らせないと大変です。
学校時代のままで会社内で行動されたら、社会生活・企業活動とは馴染まない「勝手で自由な行動」をすることになりますから、企業目的である「売上・利益」獲得への最適行動には結びつかず、結果は「新入社員は問題要因」ということになりかねないのです。
対策はいろいろあります。大学側に学生の教育をしっかりしてもらうということ、それは当然の要求ですが、これは不可能に近いと思います。大学の先生も、生徒の親も放任主義できましたから、それを一気に改善することはできず、改革には10年スパンのロング対策が必要です。その間も毎年大学卒業生はドンドン社会に編入されていきます。
ですから、大学と家庭に改善を期待できず、結局は受け入れる企業側で努力し、新入社員の再教育をする必要があるのです。そのためにはどうするのか。それは企業という性格から考えた上での手段を講じることだと思います。
企業力とは集団力
企業とは所属している人たちの協力関係で仕事を進めていくところです。規模の大小があっても基本的なシステムは同じです。バラバラ勝手な行動では企業目的は達せられません。
当たり前のことですが、この基本的な理解が最も重要です。ここを間違えると大変です。
毎日出社するが、企業目的とは異なった「勝手連行動」となる企業の先行きは明らかです。
新入社員が来たら「直ちに企業目的に馴染ませる習慣づくり」をすること、これしかありません。入社した瞬間から始めることです。時間をおくと、時間の経過と共にやり難くなります。「鉄は熱いうちに打て」です。
具体的にどうするか。それは上司の言うことを、そのまま行動させる体制にすることです。上司に対する忠誠心をつけさせるしかありません。上司が指示することを実行する人間に作り変えることです。
なぜなら、上司が企業集団のリーダーなのですから、リーダーの指示に従わない行動は、企業目的に合致しないからです。リーダーの指示が的確でない場合はどうするのか、という反論がありそうですが、それはそのようなリーダーを上司として配置しておく企業が問題なのであって、新入社員の教育の問題ではありません。現状の上司を指導したのはその企業の上部幹部であるのですから、問題の最終責任は社長にあるのです。
ですから、上司の指示は社長の方針であるので、直属上司の指示に素直に従って行動してもらわないと困るのです。
このところの仕組みをしっかり理解してもらうこと、つまり、上司の指示は企業の方針であり、それは社長の方針であるということ、この当たり前の考え方を徹底するしかないのです。これを徹底するということは、新入社員に「企業への忠誠心」という「愛社精神」を植えつけるという作業になり、その愛社心の強弱が企業の強弱になる、という当たり前の真理を新入社員が来たら徹底的に教育すべきです。これが集団力の強さの源泉なのです。
ドラッカーも認めた日本人の家族的集団力
今年の二月の日経新聞「私の履歴書」はP.Fドラッカーで、そのエッセンス主張は「強みの上にすべてを築け」でしたが、その視点から今回の連載で日本人の強みに関して指摘してくれたことがありました。それは日本人は職業を問われると「○○会社に勤めています」ということが多いが、それは所属する組織に対する構成員として、一種の「家族意識」を持っていることの証拠であって、それは集団で仕事をする場合の強みであると強調したのです。
つまり、日本人は企業に家族意識というような、集団力的な強みを発揮させていると、世界一の経営学者が認定したのです。その通りと思います。
集団力はどこで養われるのか
幼稚園に入った子どもは、最初一人一人バラバラ好き勝手な行動をしていますが、すぐに先生の指導で、お互いの仲間という存在を認識していくことになって、集団行動できるようになって行き、子供にとって幼稚園は楽しい自分の居場所になります。
これと同じです。新入社員にとって最初の職場は幼稚園です。放っておくとバラバラな勝手連行動となります。幼稚園の先生と同じように、新入社員を指導しなければ、新入社員は団体行動をとれずに楽しい職場になれないのです。このコツを教えるのは上司しかいません。
上司の指示に従わせるということが、新入社員に「企業への忠誠心」という「愛社精神」を植えつけるコツなのです。そうするとドラッカーが認めた、日本人の強みとしての「家族意識」が発揮され、自社の強みとなるのです。
愛知万博にはやはり行こう
時代は環境破壊経済成長から持続的成長になっています。愛知万博は面白く・楽しく・驚きがあって楽しいというイベントではなく、時代の最先端環境万博であるという認識が必要であり、日本人の意識感覚構造改革の場が愛知万博です。一人一人が時代感覚を変化させれば、日本人は集団的に変化する強みがあります。だから愛知万博にはやはり行こう!!以上。
(経営ゼミナールの万博ツアーは7月25日です。詳細http://www.keiei-semi.jp)
2005年04月06日
仕事は思考回路の構築のこと
YAMAMOTO・レター
環境×文化×経済 山本紀久雄
■2005年4月5日 仕事とは思考回路の構築のこと
■大地震はくる
4月から新年度に入りましたが、相変わらずマスコミを賑わしているのは、ライブドアであり、地震報道です。日経新聞(2005.2.23)で出久根達郎氏が「大地震の
69年周期説」を紹介しています。地震博士といわれた河角宏氏が唱えた説で、関東大震災は1923年、それより68年前の1855年に安政の江戸大地震、その73年前天明2年の1782年に江戸・三河・越中・加賀など広い範囲の大地震があったことから、河角博士が統計上計算して唱えたものです。内容は「69年プラス・マイナス13年で大地震が発生する」ですから、「関東大震災の1923年にプラス69と13で2005年」となり、ちょうど今年が該当します。
そのタイミングを見計らったように、政府の地震調査委員会は3月23日「30年以内に震度6弱以上の揺れが起こる確率図」として、日本列島を色分け分布図とした予測を発表しました。政府としての最高機能は「国民の安全確保」ですが、その政府から地震予告ともいえる発表がなされたという意味、それは近々M6以上の大地震がくる覚悟をしておくように、という警戒情報連絡と受け止めたほうがよいと思います。
■地震への準備対応
3月20日に「福岡西方沖地震」が発生しました。震度6弱、M7、震源の深さ約9キロでしたが、九州北部でM7の地震が起きたのは、1700年以来300年ぶりです。
このところ連続している大地震、95年の阪神・淡路大地震、2000年の鳥取県西部地震、2004年の新潟中越地震、スマトラ沖地震、そして今回の福岡西方沖地震など、共通しているのは、大地震の発生が想定外で、無警戒であった空白域でおき始めているのです。このような想定外の地震が大規模で発生しているのは、日本列島が新たな地殻変動の活動期に突入した証拠である、と主張するのは(株)アクトンの鈴木三郎社長です。
鈴木氏によると、地球は新たな地殻変動期に入っている。過去100年の地球は稀に安定していた期間だったのであり、加えて、昨年2月から3月にかけて地球の公転軌道がずれて、磁場に狂いが生じたことが異変の原因であるとも解説しています。
いずれにしても、地震は地域一帯に公平に襲ってくるものですが、それへの救援対応は不公平になることを覚悟しておくべきです。道路寸断、架橋崩壊、道路歩道橋の倒壊等が重なって、地域への救援は不公平にならざるを得ません。
地震が発生してから、政府に文句をいってもダメなのです。救援に来るのが遅れるという覚悟の基に自己責任で準備対応しておくことが必要なのです。
言い古されている地震対策の数々、それを真面目に思い出して準備しておくこと、それが政府の地震調査委員会から予告された、地震に対する一人一人の対応と思います。
■家のリフォーム
社宅に住んでいる息子に「マンションでも買ったらどうか」と問いかけましたら、「地震が来るので買わない」という答えが戻ってきましたが、問いかけたこちらは現在リフォームの真っ最中です。
一昨年に屋根葺きと外壁塗装を専門家にお願いし、昨年は襖の張替えを自分で行い、今年に入ってからは内部の壁を張替えしています。全部完了するのはまだまだ先です。
もう建ててから26年も過ぎまして、向こう三軒両隣はすべて建替え新築していますが、こちらはお金をかけずに自分でリフォームする方針で、時間をかけてジックリ進めています。ついでに家具類の置き場も検討し、地震対策ツールを設置したりしています。
家のリフォームを行って分かったことがあります。分かってみれば当たり前のことなのですが、やはり実際に体験してみないと実感として納得できないことがありました。
それは「リフォーム作業のためには事前準備が重要」なことです。日曜大工DIY店からリフォーム用品を購入してきても、すぐに作業できるわけではないのです。実際に作業するまでには、当然のことながら、事前に襖等の構造を勉強しないと進みません。襖を張り替えるには、襖を一度解体する必要があり、その解体には襖の組み立て構造を知らないと、無駄な力を入れたり、時には壊してしまうこともあるのです。襖の構造を始めて知って、改めて「なるほどこれが先人の知恵か」と思うところが多々あります。
リフォームするには、リフォームする対象の構造、それをまず把握すること、それが全てに優先するのです。
■トラバンドとバレーボール
先般のドイツで、ホテルロビーにあった雑誌をめくったら、懐かしい写真をみました。共産圏時代に東ドイツで走っていたトラバンドという自動車、それを修理工場で直しているいるおじさんの姿です。共産圏時代にこのトラバンドに乗れる人は模範市民でした。しかし、共産主義の時代が終わって、まだこのトラバンドに乗っている人は落伍者の部類に入ると思います。雑誌のトラバンド写真の後ろには、メルセデスとかBMWが並んでいるのです。ということは、昔の模範市民が乗るべき車も、時代が変われば底辺のところにいる人しか乗らない車になったということです。時代は昔の常識を変えていくのです。
しかし、昔の常識を変えてはいけないこともあります。
2008年の北京オリンピックを目指す、女子バレーボールの日本代表トレーニング担当アドバイザーに、順天堂大学スポーツ健康科学部長の沢木啓祐氏が就任しました。かって「東洋の魔女」と恐れられた女子バレー、昨年のアテネオリンピックで五位にようやく入賞したものの、長く低迷を続けています。
沢木啓祐氏が就任してみて分かったこと、それは「代表チームがデータを継続的に取っていない」という情けない事実でした。30年前にあった素晴らしいトレーニング方法を継続化していなかったのです。継続していたのは、技術と戦術偏重の作戦ばかりでした。
東京オリンピック金メダルの、女子バレーボールチームの大松監督が「為せば成る」と、必死に考えつくりあげた世界で勝つためのトレーニングとデータ、その基本が忘れ去られていたという事実が沢木啓祐氏によって明らかになったのです。バレーボールがなぜ弱いのか、ようやく分かった気がしました。変えてはいけない常識があるのです。
■仕事とは思考回路の構築のこと
3月の日経マガジンで、NYヤンキースの松井選手が次のように語っていました。
「僕から見て『ああ、自分より野球のセンスあるな』という選手はたくさんいます。でも、逆に『もったいないな』とも思うんですよ。大事なのは思考回路です。どういう風に打とうかなとか、イメージを膨らまして、自分で『深く考える』ことです」と。
「足りない素質」を補うのは深い「思考」であるという松井選手に、改めて驚き、頷きます。開幕戦でレッドソックスと対戦し、立派な仕事をした背景には深く考えた「思考回路」構築があって、それがしっかり仕事をやり遂げる基盤となっているのです。
ところが、仕事と作業の区別もつかない人もいます。作業とは「あらかじめ正しい答えがある」場合であり、仕事は「自分で問題解決に乗り出さねばならない」場合の行動であると思います。
「笑う温泉・泣く温泉」が紀伊国屋のBOOKWEVで、温泉専門書分野で売れ筋トップとなりましたが、この中で提案した「温泉地成功6通りの戦略」を日本の観光業は参考にしてもらいたいと思い、銀行会館で開催した3月の「丸の内時流塾」では、南仏アベンヌ温泉を取り上げました。結果は、温泉関係者に好評でしたので、4月も同じくアベンヌ温泉を再び取り上げますが、今回も温泉関係者から申し込みが結構あります。
(丸の内時流塾の内容は、経営ゼミナール http://www.keiei-semi.jp/ に掲載)
アベンヌ温泉の成功は、山奥の寒村に「行ってみたい」と思わせたこと、逆にいえば「誰も訪ねないという問題を解決したこと」であり、そのための「思考回路」を深く構築した結果なのです。松井選手もアベンヌも成功の理由は同じなのです。
■地震対策は体験のもとに思考すること
大地震がくるという政府からの予告、これに対する我々の最大弱点は、経験したことなく突発発生する一瞬のM7大地震に「思考力」で対応しようとしている現実です。これが最大の弱点です。思考に体験を加えなければならなく、その為には実際のM7恐怖体験をすることが最も必要なことです。至急に本所消防署内にある「防災館」(03−3621−0119)に行って、大地震の恐怖体験をすることが思考回路の前提条件です。 以上。
2005年03月21日
本籍地と現住所
YAMAMOTO・レター
環境・文化・経済 山本紀久雄
2005年3月20日 本籍地と現住所
温泉治療に携わりたい
「笑う温泉・泣く温泉」の読者から、長文の手紙が出版社経由で届きました。内容は「一気に読んだ。この本の中に探していたものがあった。自分の心の中を整理させてくれ、求めていたものを明確にしてくれた。今は学生だが、将来は温泉治療に携わり、自然の治癒力による力で社会に貢献したい」というものです。
書店の旅行コーナーに並んでいる、一般の温泉本には共通性があります。それは温泉水の効能効果よりも、「温泉の楽しさ」を伝えること、つまり、景観とか、旅館の施設、料理の豪華さ等の特徴に主点がおかれていることです。しかし、「笑う温泉・泣く温泉」は専門書の分野に入ります。日本図書館協会推薦図書になったのも、内容が専門的だからです。
手紙を書いた若い女性は、幼いときからニキビ・アトピー等で苦労してきて、その治療として温泉が有効であると聞いていたが、その治療が現実にヨーロッパで行われている実態を「笑う温泉・泣く温泉」で初めて詳しく知り、日本でも同様の温泉治療を普及させたいので、その方向に向かうための勉強をしたい。ついてはその勉強機関を教えてほしい。との希望も書いてあり、温泉治療に詳しい専門家を紹介いたしました。
出版した本が若い人の未来に影響を与えたということ、著者として望外の喜びです。
目の前の情報
民営化と共に「新東京」という冠名前が消えた、「成田国際空港」からパリに向かいました。パリのド・ゴール空港に飛行機が着陸し、ボーディングブリッジへたどり着くと、「客室乗務員はドアモードをディスアームド・ポジションに変更してください」と機内アナウンスが流れます。これはどの航空会社でも必ず流すアナウンスです。
このアナウンスが流れると、乗務員がドアに何か作業するのですが、今までこの作業は、多分「ドアにかかっている鍵を外しているんだろう」と思っていましたが、山本塾に出席するスチュアーデスの方からお聞きし、初めてこのアナウンスの意味が分かりました。
それは「ドアに取り付けられた緊急脱出用の装置を解除するため」だったのです。ドアの内部には「緊急脱出用の滑り台が収納されている」ので、ドアを開けると同時にガスが充填され、自動的に滑り台ができるようになっているのです。ですから、緊急時でないとき、つまり、空港のボーディングブリッジへたどり着いたときには、この緊急脱出用の装置を解除することが必要なのです。そうしないと高圧ガスによって、10秒で膨らむようになっているので、ドアの近くにいる人はとても危険なのです。
飛行機に乗るたびに目の前で行われる光景、その意味を分からないまま長いこと過ごしてきました。分かってみれば成る程と思うことでも、漠然と事実ではないまま勝手に認識していることが多いと、今回、改めてド・ゴール空港で感じた次第です。
サン・ジェルマン・デ・プレの書道塾
パリの中心、サン・ジェルマン・デ・プレの交差点はいつも喧騒に満ちていますが、そのすぐ裏手にある「カリグラフィス」という書道教室は静かです。ここでフランス人が書道を習っているのです。一昨年、フランス人からもらった一冊の本、それはフランスで最も美しい本として表彰されたもので、書道の本でした。書道が人気なのです。
フランス人が書道をする理由、それは「書かれたものが言葉として何を意味しているかは分からないが、スピードの対極にある書道は癒しになる」という理由が多いのです。
確かに、日常の生活とかけ離れたこと、それが大きな魅力であって、「カリグラフィス」は人気なのですが、今回、その書道教室をやめたフランス人の声を聞くことが出来ました。
なぜやめたのか。それは「熱心に書き、上手く書けていたが、結局書いている字の意味が分からない、ということに改めて気づいた。分からないものを書いても空しい」というのです。何となく実感として分かり、行動の意味づけの大事さを再認識しました。
ゲランドの塩
昨年に続きパリの農業祭を視察し、加えてブルターニュのゲランドに向かいました。
目的は世界に冠たるブランドとして確立しているゲランドの塩田視察です。
モンパルナス駅からTGVで約3時間、冬のゲランドは塩田の補修作業の毎日です。塩の生産は6月中旬から9月中旬までの3か月間、その生産方法をサイエ村の「塩職人の家」で、塩職人の「イヴォン・モランドー」氏から説明を受け、塩生産の塩田模様をモデルルームで見学しました。
その生産方法を一言でいえば「完全なる自然」です。海水をゆっくりと勾配五千分の一で、水を通す穴は鉛筆の太さという、異なった五つの池を回遊させていくうちに、海水が天日で蒸発し、最後にたどり着くオイエ(採塩池)では塩だけが残り、それを掬い取るのです。ですから、海水の蒸発を天日だけで行うのですから「天日塩」というのです。
この「天日塩」というネーミング、それを単なる品名に近いものだろうと理解していましたが、ゲランドの現場で初めて「天日塩」という意味を理解しました。現代の科学社会の中にあって、ゲランドは完全なる自然有機生産であるという意味、それが「天日塩」というネーミングの背景にあること、それを、初めて現地で知り深く頷いたのです。
宮古島の塩
日本に戻りましたら、近所の方が宮古島に行かれて、そのお土産に塩をいただきました。
説明を読んでみますと「ミネラル成分の含有量18種類は世界一でギネスブックに認められた」とあります。早速、電話して成分表をFAXしていただき、ゲランドの成分表と比較してみました。確かに宮古島のほうがミネラル成分が多く、ギネスブック掲載は嘘ではありません。
次にパンフレットに図示してある生産方法をみますと、そこには「海水を熱し塩分の濃度を高めて、水分を瞬時に蒸発させる」とあります。人間の科学力によって塩を採り、それも一年中安定した塩生産を可能なシステムにしているのです。
また、その塩は細かにパウダー状になっていて、手にとると粉のようなやわらかく、食感もよく、使いやすさという点ですばらしく、各成分がどのような効能効果があるのかという説明も明確です。その上、容器もしっかりした瓶ですので、そのまま食卓におけます。
成る程、宮古島の塩はさすがに工業国日本製で、工業的安定生産によって品質管理状態も瓶詰めで問題ないと納得したところに、宮古島から電話がありまして「FAXは届きましたでしょうか」という親切さです。さすがに日本の客対応は見事です。感心しました。
一方、ゲランドはどうか。ゲランドの「フルール・ド・セル 塩の花」という最もよい塩は、密封したビニールに入れ、その上から布袋包装しています。密封ビニール袋を開けますと、再び密封出来ませんので、全部ビニールから取り出せる大きさの瓶に詰め替えなければいけません。また、自然のままですからパウダー状ではなく粒状です。
本籍地と現住所
困ったことが生じると、人は何かに頼りたくなります。苦境に陥った経営者の多くが採る行動パターンがあります。まず、最初は仏壇に手を合わせ出します。いままで仏壇に線香もあげなかったのに仏壇を拝み、次に座禅に挑戦し、幹部に厳しいはっぱをかけ始め、寝酒を飲みだし、夜中に悪夢にうなされるようになっていきます。ホッとするのは、同業経営者との飲み会で、その経営者の方が自社よりも悪い経営状況だと知ったときだけですが、このような現住所状態では本質的な経営改善は出来ません。
苦境を乗り切るためには、自らの仕事の原点から考え直さねばならないと思います。自分の仕事の原点としての本籍地、その自らの本籍地を強く認識しながら、今の「現住所としての仕事に献身」する姿勢が大事なのです。これは人の生き方にも通じることです。
そのためには、飛行機客室乗務員が行う目前の行動意味を、よく分からないまま漠然と認識したままにすることや、意味不明の字を書にして空しくなるフランス人の事例のようなことは、なるべく行わないことが大事であると思います。
ゲランドと宮古島の塩生産方法は、自然と科学という両極に位置しています。どちらの塩を好み、食するか、その判断のための情報は、ゲランドも宮古島も、つくり方からミネラル成分量まで明確に表現しています。原点からの本籍地情報を公開しています。
若い女性からの手紙、いろいろ探してようやく「笑う温泉・泣く温泉」に出合ったとあり、読み終えて未来への方向性が定まったということの意味、それは今まで漠然と想い探し求めていたこの読者の原点・本籍地、それを暗示できたのではないかと思っています。以上。
2005年02月21日
好感度第一位国家ビジョンに参加する
YAMAMOTO・レタ-
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年2月20日 好感度第一位国家ビジョンに参加する
財政健全化へイタリアとカナダが採った方法
さいたま新都心の関東財務局ビルには立派な講堂があって、そこの活用を図るため「さいたま新都心大学」という企画が昨年から行われています。授業料を支払って出席するのは地元の人達です。2月9日は財務省主計局課長からの「日本の財政状況」の実態説明でした。霞ヶ関で政策立案に直接携わっている担当課長からの説明ですので、分かりやすく出席者から好評です。説明が終わり質問時間となり、質問のトップバッタ-は主婦でした。
「1991年の時に財政収支が最悪だったイタリア・カナダが、2005年時点で先進国の上位という立派な改善を示しているが、そのためにどのような政策を採ったのか」
この質問の裏には、日本が1991年時点で先進国トップの健全財政であったが、現在では最も悪化しているという実態からの質問であり、「日本を改善したい」という気持からの発言です。
回答は「イタリアは年金給付の削減、公共事業の抑制、増税と財務警察による厳しい脱税摘発実行であり、カナダは国から各州に対する独立採算財政の徹底化、つまり、補助金政策の見直しを行って、各州に自己責任で州財政の責任をもたせたことだ」というものでした。説明を聞いてみれば最もなことばかりの健全財政化への方法です。
日刊ゲンダイ特集記事
日刊ゲンダイというタブロイド版新聞が、1月17日から五回にわたって「大増税の時代が襲い来る」という記事を連載しました。その内容が参考になりますのでご紹介します。
第一回 2004年は配偶者控除の一部廃止、消費税免税点の1000万への引き下げ、酒・タバコ増税、2005年は年金課税の強化、低所得者層への人頭税としての住民税均等割増税、定率減税の縮小・見直し、所得控除の縮小・見直し、法人への外形標準課税(法人への人頭税)の検討、2007年には消費税の二桁化実施(財界案では15%前後、財政制度審議会試算では21%)
第二回 老年者控除の廃止(年間所得1000万円以下の高齢者の50万円控除の廃止)、公的年金控除の縮小(年金夫婦生活の課税最低限が285万円から205万円に引き下げ)、介護保険利用者の自己負担部分の拡大、在職老齢年金制度の年金カット(65歳以上の厚生年金需給者の年金カット)
第三回 欧州並みの高い消費税率となり、欧州で実施されている食料品などの日用品「軽減税率」は当面導入しない方針(所得の低い人ほど税負担が重くなる逆進性が強まる)、消費税率が21%になると、10年後の潜在的国民負担率(国民所得に占める税、社会保険料、財政赤字の割合)は50.6%に上昇(今年度は45.1%)
第4回・五回は省略しますが、最後に次のように結論化しています。
「国家公務員96万人、地方公務員350万人、準公務員も500万人いる。合計1000万人、家族を合わせると3000万人、実に国民の4分の1が公務員で食べているのだ。だから公務員を半分にし、福祉も半分にし、税金も半分にすべきだ」と。
日刊ゲンダイの特集、読んでみれば増税路線に向かっていくことがよく分かりますが、どうしてこのような増税路線を採らねばならないのか、それは国家の財政赤字が膨大であるからです。では、その赤字はどうして発生したのか。それは1991年以降のマクロ政策の失敗にあったといわざるを得ません。政治家の採った政策の失敗と、それを許してきた国民のつけが廻ってきたのです。
かってイタリアは世界最大の財政赤字国でした。そのときのイタリアに対する外国からの評価はどうだったのでしょう。その時のイタリアの評判は最低でした。イタリア人はだらしないから国家財政もダメなのだ。という評価だったのです。
今のイタリアは改善しましたが、イタリアに変わって先進国第一の財政悪化国はどこなのか。日本です。ということは外国人からみた日本の評価は、かってのイタリアと同じようにみられ、考えられているとしたら、日本は「好感度が高い国」とはいえないのです。
自殺者とその要因
警察庁が発表した自殺者数は2003年度34,427人、前年対比107%です。この数字は主要国と比較して、異常に高いことはすでにご承知と思います。アメリカが
31,655人(2002年)で、人口が2倍以上ですから、自殺死亡率は日本がアメリカの倍以上であり、イギリス・イタリアの3倍前後、ドイツの1.5倍以上、フランスの1.3倍程度に相当します。また、2004年以降は集団自殺が頻発しています。
動機別で最も自殺者が多いのは「健康問題」で15,416人、次に「経済問題」で
8,897人となっていますが、この「経済問題」が最も高い増加率12%となっています。しかし、ここでよく考えてみれば、日本は世界の中で豊かな国として認識されているのに、その豊かな国でどうして経済問題という「生活苦」で死ななければならないのか、ということです。また、世界中には貧困から教育を受けられない多くの若者がいるが、日本はこの面でも恵まれた環境にあって何の不足もないのに、どうして人生に夢がないと訴え、ある者はキレて他者を傷つけ、ある者は閉じこもりとなり、ある者はリストカットをくりかえしているのか、ということです。
生きる意味
今年の1月20日に出版された「生きる意味」(東京工業大学院助教授 上田紀行著 岩波新書)は自殺の要因について鋭く分析し、参考になりますのでご紹介します。
「自殺の増加原因を単に不況のせいにする言動が目立つ。「経済力」の不振が全ての原因だというのだ。景気が悪いから、人々の生きる力が弱まっている。だからもっと『強い』日本にしなければならないという言動は一見魅力的だ。確かに不況の克服は重要かつ、危急の課題である。しかし、経済が好調なときは人々の元気がよくて、不況になると一気に顔色が悪くなるような社会を、真に『強い』社会と呼べるだろうか。不況でもしぶとく生きていく、そこにも生きる楽しみと人生の確かさを実感できるような人間こそが、今こそ求められているのではないだろうか。
現代の日本が直面している最大の問題は、経済不況ではなく『生きる意味の不況』だ。それがこの本の出発点である。どんな金持ちでも、いい家に住もうとも、生きる意味がないと感じ、生きる意欲が湧いてこなければ、人間は輝かない。この地球上で、不況とはいえ大変な豊かさを享受している私たちが直面しているのは、『生きる意味』が分からないという、意味の病なのである。
今求められているのは、私たちが自分自身のかけがえのなさを取り戻すこと、既製服のようなお仕着せの『生きる意味』ではなく、自分自身のオ-ダ-メイドの『生きる意味』を創り出すことである。一人ひとりの多様な『生きる意味』へ熱い思いを持つ時代、そこにこそ真に豊かな成熟した社会への道が開かれている」
成る程と思います。一人ひとりが「生きる意味」を持って「輝く自分人生」を創るところに、自殺者が少ない「好感度高い国家」が存在するのだと思います。
身の回りの環境整備
ヨ-ロッパの著名な地方都市、例えば環境都市として知られている南ドイツのフライブルグの街を歩き、あえて裏通りを歩いてみると分かります。どこにもゴミがありません。
温泉で有名なバ-デン・バ-デンのホテル、その裏口辺りをチェックしてみてもゴミは見かけません。ところが、日本の著名温泉地の調理場の出口辺り、そこには前夜お客に高額で提供したビ-ルやお酒の空き瓶が放置されている、それが一般的に多いのです。
フライブルグもバ-デン・バ-デンも、世界中から観光客を多く迎えている都市です。それらの都市の常識はゴミ処理の巧みさです。人には見せない場所で管理し整備し処理しているのです。これが世界から優良観光客を集めるための最低前提条件です。
国家ビジョンに一人ひとりが参加する
先進国一位の財政赤字の改善、主要国第一位の自殺率の改善、欧米一流基準から劣る都市美観感覚の改善、この三項目が「好感度第一位国家」ビジョン達成への最低必達条件であり、これが2030年に世界中から観光客を4000万人迎える前提要件と思います。
またこの最低必達条件をクリアするのは国民一人ひとりの意識改善が前提条件です。以上。
(次回3月5日は海外出張のため休刊となります)
2005年02月09日
好感度第一位国家とは
YAMAMOTO・レタ-
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年2月5日 好感度第一位国家とは
2030年の国家ビジョン
政府の経済財政諮問会議が今春まとめる「日本21世紀ビジョン」の中間報告案が明らかになりました。25年後の2030年、日本が目指すべき三つの将来像です。
●「好感度第一位国家」=世界中の人々が「訪れたい、働きたい、住みたい」と思う国
●「健康寿命80歳社会」=高齢期も生涯現役で自立・充実した生活を過ごせる社会
●「等身大公共革命」=小さく効率的な政府を実現。民間が広範囲で公共サ-ビスを担う
この中で筆頭に上げられたのが「好感度第一位国家」で、内容は世界のアニメ産業の拠点や、製造業の各業種で最低一社が上位十社に入る、という目標を明示し、訪日外国人旅行者を4000万人に拡大するというものです。
国家ビジョン策定の裏背景
昨年10月に実施した内閣府による国民へのアンケ-トで、最も多かったのは「2030年の生活が悪くなる」という回答でした。その具体的イメ-ジは次の四つです。
● 人口減で経済が停滞し悪循環に陥る
● 財政再建が進まず、国債価格が急落し増税が民間の足かせとなる
● 東アジア経済統合が中国中心に進み、グロ-バル化に乗り遅れる
● 経済格差が拡大し、将来に希望を持てない層が滞留する希望格差社会が到来する
これらの暗く悪いイメ-ジを持っている人が63%もいる、それが今回の国家ビジョン策定の背景にあります。この表面に現れた悪いイメ-ジ、それを反対の姿に変化させるという基本戦略が「2030年国家三つのビジョン」であり、これら国家ビジョンの実現を通じ、生産性を大幅に引き上げ、人口減少下でも国力低下を回避させ、未来を明るい希望の持てる社会にしていこうとするものです。
好感度第一位国家とは
てはビジョンの中でトップに挙げられた「好感度第一位国家」とは、具体的にどのような姿を意味するのでしょうか。それは世界中の人が憧れる魅力ある国家になって、現在の訪日外国人600万人を、約七倍の4000万人にするということです。ですから、魅力は今の七倍になっていなければなりません。
政府の観光立国推進戦略会議(座長 ウシオ電機会長)が、先般55の具体的な提言を行いました。提言の一つひとつすべて重要なものであり、該当する観光関係者が率先して実行して貰いたいものばかりですが、我々一般住民としても参画すべきものがあります。
それは自分が住んでいる「地域」「場所」の魅力とは何かを考えることであり、その魅力を高め、もてなしの心を持って来訪者に接し、自分が観光する際には、休暇時期を分散させて、快適な旅を最大限楽しむなどの「観光するこころ」を育てることが必要、という提言に成る程と思います。まず、自分が住む「地域」「場所」が魅力的になること、その実現があって、はじめて他地域・世界の人々が訪れると言っているのです。
ダイエ-の基本戦略の選択
ダイエ-が産業再生機構に入り今後の再建方向性が検討されています。ダイエ-が現状の姿になったこと、それに対する見解が多く語られています。その一つひとつが参考になりますが、結局「消費者からの支持」が多く得られなくなって、消費者がダイエ-に買い物に行く回数が少なくなったこと、つまり、お客から「他社に比較して好感度が低い店舗場所」と評価されたことが不振の要因なのです。
この不振要因背景には、ダイエ-が採った基本戦略の誤りがあった、と指摘するのはダイエ-創業者中内功氏の弟による自伝、中内力著「選択」(神戸新聞社)です。
その指摘内容は「ダイエ-創業期において意見対立があった。その対立とは小売業に人材と資金を集中するか、それとも卸・メ-カ-を傘下に収め、さらに周辺事業も取り込むか。この基本戦略の違いだった」と振り返っています。前者が著者、後者が功氏だったのです。基本戦略の方向性が妥当で的確であると、未来は時間軸と共に明るい姿に変化していくが、反対の場合は暗く厳しい現実となっていく。これが戦略選択決定の怖さであり、反面、魅力なのです。表を採るか、裏を採るか。その意思決定が未来を決めるのです。
子どもへの思いを伝えているか
閉塞間が漂う育児環境、陰湿化するいじめ、引きこもり・・・。子育ての場で問題が山積しています。育児における父親の存在が問われている時代です。
すでに子育てを終えた環境下ではありますが、重要な社会問題ですから関心を持っています。先日、家族の「今」を見つめ続けている、作家の重松清さんからお伺い機会がありました。また、2月1日のNHKラジオで「ガンバレ!主夫」という長時間番組を聞きましたが、ここで家事・育児をしている父親の奮闘振りに驚きました。
この主夫という新しい言葉とその背景には、家族のあり方が変化する中で、父親はどんな役割を見出せばよいのか、というテ-マの追求があったのです。重松さんも、NHKで語った二人の主夫も同じことをいいました。「結局、問われているのは自分の人生観だ。俺はこういう父親なのだという存在を自分の主語で語ることだ」といいました。これには感動しました。家族崩壊とか、子育て環境が悪すぎるという一般的な意見が多い中で、そのような一般論では自らの家庭は何ら問題を解決できない。そんなことはどうでもよいのだ。自分の家族の問題なのだから、自分の流儀で進めていく。そのためには重要な判断基準がある。それは何か。その何かについて重松さんは「日本中のすべての家族に共通する幸せはもはやない。だが、わが家にとっての幸せを見出すことはできる。わが家にとっての輝きは何か。それを探し、子に伝えるのが父親の役目だ」と語り「皆はこうだ、社会はこうだ、マスコミはこうだというのはずるいし、怠けていると思う」とも加えたのです。
ヨ-ロッパ人の都市再生思想
都市再生としての開発が盛んです。六本木ヒルズや汐留・東京駅周辺、都心に超高層のハイテクビルが建設されています。
日本社会はこのところ階級差がついてきたという見解もありますが、世界中からみればまだまだ格差の少ない社会です。ところが、ビルの形態だけをみると、大金をかけた超高層ビルと、庶民の雑居とが混在している景観となっていて、その格差は都心で目立ち、老朽化した空きビルは見捨てられつつあるのが実態です。
ヨ-ロッパの優れた地域環境都市、例えば南ドイツのフライブルグが典型ですが、それらに行って感じるのは高層ビルが少ないことです。街並の上に飛び出しているのは、教会のド-ムであって、民間のオフィスやマンションビルではありません。特別な理由がない限り、新築は中心市街地では禁止されているところが多いのです。伝統的文化を壊したくないから、規制が非常に多いのです。個人的には迷惑すぎると思う規制でも、町全体が守れば街並としての全体統一感が保たれるのです。
経済と機能を追及したのが日本の街並で、個人主義のヨ-ロッパ人の方が、実は全体主義で自由を規制していることが建物から分かります。これらの背景に「中心市街地は昔のままにしたい」という思想があり、そのために厳しい規制と保護を設けています。つまり、地域の建物を残して、さほど巨大化せずに中身を変える工夫して、人が集まる建物をつくる。これを「本当の価値ある都市再生」と考えているのです。ですから当然この思想で、外国の都市を評価し判断していくことになります。
好感度を高めるのは自分
ヨ-ロッパに世界中から多くの人が訪れる最大の理由の一つは、市街地の見事な整備状況にあります。落ち着いた美しい街並が魅力となって、観光客の目を楽しませるのです。
この事例から考えれば、2030年に4000万人の訪日観光客を迎えるためには、自らが住む地域への基本的な戦略的思想の変換が必要です。
ダイエ-の失敗は、人の支持を得られる戦略から離脱したところにあったという見解、家庭内問題の主因は、父親の輝き不足にあるという重松氏の主張、同じことは地域の好感度を高める役割を担う我々にも当てはまります。自分が住む家の内外の整備なくして、地域の整備はありえないく、それを行うのは自分という一人、その一人がそれぞれ担うことなのです。「本当に価値ある都市再生」へ向かうためには、まず、自ら住む地域に自分が何をし、何ができるか、という思想への変換が最も必要です。このテ-マ次回続く。以上。
2005年01月21日
非適応文化を修正する
YAMAMOTO・レタ−
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年1月20日 非適応文化を修正する
(景気は踊り場)
日本の景気は踊り場にいる。これが1月7日の日経新聞社主催、新春景気討論会での結論でした。これから先の見通しについてはパネラ−の立場でそれぞれ見解が分かれます。年内に上昇する、夏ごろになる、否横ばいだ、と意見は異なりますが、マイナスにはならないだろうというのが統一見解でした。
パネラ−の一人、ヨ−カ堂鈴木会長は低成長を予測しましたが、その根拠は「人の気持」です。人々の気持を明るくしないと消費は増えない、と強調します。人の気持が揺れ動いていることは、今年の正月三が日神社仏閣への初詣の人数が示しています。1974年から統計が記録されて以来最も多い8966万人が全国の神社仏閣に出かけました。これには新潟中越地震、インドネシア・スマトラ沖地震等が影響していることは間違いありませんが、多くの人が今の時代に不安感を持っているのです。
(おけさ踊り)
日経新春景気討論会を終えて東京駅北口に入りますと、広くて高いホ−ルに何かが輪になって動いています。何だろう、と思って近くに寄ろうとしたときに「にいがたキャンペ−ンです」と、薄い透明ビニ−ル袋を手渡されました。中にはポケットティッシュが一つ、それとパンフレットが数枚入っています。
成る程、中越地震で被害を受けたので元気を出そうとキャンペ−ンをしていて、そのために佐渡のおけさ踊りを披露しているのか、と思いましたが、それにしてはラジカセの音が低くて聞こえず、踊っている人が寒々しく見え迫力がありません。北口ホ−ルは高くて広いので通常のラジカセ程度では音響効果が出ないのです。
(クロ−ズアップ現代)
その日のNHK7時ニュ−ス後は、クロ−ズアップ現代が続きます。テ−マは何と「にいがたがんばれ」でした。東京駅で見たおけさ踊りと連動しているのか、とテレビを見ながら手許のビニ−ル袋に入っているパンフレットを取り出すと、それは新潟観光誘致内容が網羅されています。JRの割引運賃、温泉も大歓待でお待ちしますとの表現です。
クロ−ズアップ現代に温泉の支配人が登場しました。「宿泊客が激減して何千万円の売上源です。対策としてお客さんに手紙を書いて、その中に餅を一個入れて送っています。この旅館を思い出して欲しいという気持からです。先日一人の男性が来てくれました。嬉しかったです。しかし、もっともっと来てくれることを祈っています」と語ります。
大変だなあと思います。地震で危険なので人は行かないのです。地震の影響から当たり前ですが、結果は地元の経済に大打撃を与え、それを回復したいと新潟県はキャンペ−ンを展開したのです。気持はとてもよく分かります。同情します。
(人が観光地に行く意味)
景気は踊り場だというように表現する「景気」という言葉、それは「景色」の景と「気持」の気から構成されています。
景色はどこでもあります。日本中、山あり川あり海ありですから、全て景色だらけです。だが、その景色の中でも人が多く訪ねる特別なところがあります。昔から「名所」といわれるところです。多くの景色の中から人々が自然に選んできた場所が名所となって、今でも多くの人を引き寄せているのです。
その特定の名所が人を引き寄せる要因は何でしょうか。それぞれ名所の特長によって要因内容は分かれますが、共通していることは「その場に人をひきつける何かがある」ということです。普通の景色とは異なる何かを感じさせ「人に行きたい気持にさせる」ものがあるのです。それはその場に固有の「気」が存在するからです。その場に立つと「いいなあ、気持いいなあ」を感じさせるもの、その「気」を持っているのが名所になるのです。ですから、古来昔から「景色に気がある」名所に多くの人々が訪ねるのです。
また、その場の気の強弱によって、集客人数の強弱が決まります。それがそれぞれの神社仏閣への初詣人数にも、一人一人の人間力にもあらわれます。
(時とタイミング)
新潟中越地震によって被害を受けられた方々は、この正月仮設住宅で過ごされた方が多いと報道されています。自宅が一番よいのは分かっていますので、大変だと本当に同情しお見舞い申し上げる気持で一杯です。自分の立場に置き換えればよく分かりますから。
このような気持になっている人が、日本中の多くの人の現実の気持ではないでしょうか。とすると、正直に申し上げて新潟地区に行って、被災者の方々がおられる場所近くに行ったとしても、通常の観光気分になれないのではと思います。例えどんな名所があって、その場の「気」を感じたいと思っても、日本中が新潟中越地震状況を熟知しているのですら、ちょっと観光気分で訪れることは憚れる、それが多くの人の気持の中にあると思います。
このような気持ちのところに「にいがたキャンペ−ン」が行われたのです。展開する新潟の人の気持はよく分かりますが、果してこのキャンペ−ンの効果が十分発揮出来るでしょうか。疑問です。時とタイミングで非適応と思います。新潟にお見舞いに行こう、というキャンペ−ンであるならば別の気持になれますが、観光には申しわけなくて行けない、というのが正直な気持でしょう。気持がそうならないのです。では、経済的打撃はどうするのか、と反論されるかもしれませんが、それは別途の対策で講じるしかないと思います。
(時代は反対に向かう)
今年は戦後60年になります。その間一貫して日本の政治は自民党一党が支配してきました。途中で細川・羽田内閣がありましたが、その他は連立政権としてもずっと自民党が政権を担ってきたのです。
先日、田原総一郎氏が次のように言っていました。「戦後政治は三本の柱で成り立っていた。第一は国際外交で全方位・世界中と仲良くする。第二は国民生活を豊にする。第三は国民生活を便利にする。しかし時代は変わった。第一の国際外交はイラク派兵で米国側についた。第二の国民生活はここ3年給料が下がり、年金支給・医療給付も悪くなり苦しくなった。第三は高速道路・新幹線の延伸・新設に国民多くから疑問が出されているが、これは不便でよいという主張だ」と。
つまり、戦後60年間の方針が逆の方向になったといっているのです。そのとおりと思いますが、そこに更に人口減という事実問題が迫ってきました。
人口が増えつづけるという前提で全てのシステムが出来上がっているのです。しかしその前提条件が反対になるのですから、当然に国家運営システムは今までと反対思考で行っていかねばならないはずです。ところが、今までの体制システムを変えることに抵抗があるのが人間ですから、なかなかうまく改革が進まないのです。
(真面目さが非適応を生む)
自分の体験で分かりますが、多くの勤め人は真面目に一生懸命仕事をします。きちんと決められたこと、それは上司の指示を受けて、それに対応すべく努力しつづけています。また、管理職は部下からの報告とトップからの指示を受け、その両者の間で必死に真面目に取り組んでいます。このような共通姿勢の他に、もう一つは「仕事の枠組み以外に興味を持たない」という共通性があり、この感覚で行動しマネジメントしていくのが一番と思っているのが日本の多くの勤め人です。
しかしながら時代は反対方向に向かっているのですから、「仕事の枠組み以外に興味を持たず」、「時代の動き」に関心をはらわずに、ただ一途にきちんと真面目に従来姿勢で仕事しているだけでは、あっと思う間に、真面目に必死に取り組んでいる「その仕事そのもの」が時代に非適応となっていく、という恐れが大きいのです。
つまり、世の中の変化に対応できないという結果を招くのは「あまりにも真面目だから」ということなのです。一生懸命に真面目にすることが「非適応文化」になる時代だ、という事実を知り、ある種の不真面目さ、それを自らに取り込んでほしいと思います。
(どうするか)
時代の踊り場でどの方向に向かうか不安・不明な現在、その今に適応するためには、自らの中にある「非適応文化」ポイントを、探し見つけ修正していく生き方が必要です。 以上。
2005年01月14日
ミクロを変えてマクロを変える
YAMAMOTO・レタ−
環境×文化×経済 山本紀久雄
2005年1月5日 ミクロを変えてマクロを変える
新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願い申し上げます。
(日本の進むべき道)
昨年最後の日経新聞「やさしい経済学」は、野村総合研究所研究理事の富田俊基氏の「日本が進むべき道」の最終回で、日本政府が抱える膨大な財政赤字の解決方法として次のように述べています。
「歴史的にみて、国債が著しく巨額に達したときは次の三つの解があった。第一は財政再建である。第二にインフレを起こして国債残高の実質価値を減じようとする政策であるが、これを実行しようとすると市場はそれを察知し、資金は海外に流出する。これに伴い金利が急上昇して経済活動が打撃を受け、結果としてインフレは抑え込まれるだろう。第三はデフオルト(債務不履行)という国債の元利払いをしない等の支払条件を強制的に変更する政策を採ることであるが、この場合は国の信用が国内外で低下し、その後は国債発行がほぼ不可能になるほど高い金利を求められよう。したがって、国の信用の歴史は、今日の日本には財政健全化の道しか残されていないことを物語っている」
つまり、日本の財政赤字解決は、地道に進める財政再建という方法しかないのです。
(蔵王温泉)
「笑う温泉・泣く温泉」に対して温泉旅館の方からご連絡をもらいました。「世界の温泉利用観光客を誘致していくところに、未来の温泉業界発展の鍵があることを承知しているので、今回の本はとても参考になった」という内容です。このご連絡は宮城県の東鳴子温泉の「旅館大沼」の大沼伸治氏で、温泉業界では知られた若手改革者です。このような改革者によって、日本の温泉地がヨ−ロッパに負けない環境となって、世界中から観光客が訪れることで、日本が観光立国大国になり、人口減少社会日本の経済に大きな効果をあげることが出来るよう、関係各部門へ今後も研究し提案していくつもりです。
その温泉研究の一環として、年末に山形県蔵王温泉に行ってまいりました。蔵王温泉を訪れたのは40年ぶりでしたが、相変わらず雪景色の美しい温泉量の豊富なすばらしい温泉地です。宿泊したところは著名なリゾ−ト施設企業が経営しているチェ−ンホテルです。ですからフロントの応対から食事の内容を含め納得のいくサ−ビスであり満足しました。
ところが、一つだけ不審に思ったことがありました。夕方到着して直ぐに向かった一階の大浴場、その脱衣場に掲示されている「温泉分析書」を読みビックリしました。山形衛生試験所による分析で、その分析内容は大きく詳細に書かれていますのでよく分かりますが、その分析年月をみて驚いたのです。何と分析したのは昭和33年(1958年)なのです。今から47年前の分析結果が堂々と壁に表示され、その昭和33年4月の分析日が「天気晴れ」と書かかれているのが白々しく感じます。
この情報化の時代、新鮮な情報が常識の時代、毎日、大勢の客が利用している温泉水の分析が47年前のままでよいのか、という素直な疑問が生じます。世の中の変化と共に地下の変化もあり、温泉水の成分変化も当然生じているのですから、今の実態を正しく利用者に提示することが温泉施設の情報提供義務です。しかし、この一流ホテルの大浴場は設備とサ−ビスは立派ですが、肝心要の温泉水が現在の姿ではない47年前の分析結果をそのまま表示しているのです。温泉偽装問題が大きく取り上げられ、温泉水情報の正しい表示の重要性は知っていても、実際の現場ではまだまだ問題への意識が薄く対応出来ないのです。残念です。
(喜多方と高山)
蔵王に行く途中、福島県の喜多方に寄りました。これで昨年は喜多方に二回訪れたのですが、この喜多方は蔵とラ−メンの町として有名です。
また、昨年は岐阜県の高山にも参りました。高山は山岡鉄舟が子供時代を過ごしたところですので、鉄舟研究会の仲間と行き、地元の仲間にご案内いただき、じっくり街並みを楽しみました。高山も喜多方も古い町として人気がありますが、両方を比較して気がついたことがあります。それはミクロな視点です。
ご存知の通り、高山は「訪れてみたい町のナンバ−ワン」として高い人気があります。その人気の一つに江戸時代からの古い町並みがあります。四百年前の町割が変わることなく残っていることに加えて、二階建ての木造切妻造り、ゆるやかな屋根勾配、深い軒と格子や柱の調和が美しく、また、そこに設置されている看板や暖簾などの形や色調も規制し、電灯は白熱灯にする等の街づくりがおこなわれ、旅人を惹きつけているのです。
一方、喜多方は蔵が多く、その蔵では酒造りがいまでも行われて、蔵の中に古い美術品も多く展示されていて、それを見ていると時間の経つのを忘れるほどです。更に、ラ−メンの味に惹きつけられ多くの観光客が訪れる人気の町です。
お互いそれぞれ特徴があり、魅力があるのですが、明らかに異なっている個所は店舗の回りではないかと気づきました。お互い家並みや店舗・蔵は同じように魅力がありますが、違っているのは店舗や蔵を一歩出たところの整頓度、つまり、街並みの清潔さです。
喜多方の中心街の路地を一歩入ってみると小さな神社がありましたが、その鳥居の回りにゴミが散らばっていて、その近くの店舗出入口回りも同様状態でした。勿論、大量に散乱しているのではなく、少しのゴミなのですが、それは高山ではみかけないのです。
気にしなければ気にならない程度のゴミです。しかし、その程度のゴミであっても、それがある状態と、そうでない状態では、住民の環境美観に対する現実の認識度を示していて、そのようなミクロな感覚意識差が両街の集客力の差となっていると思いました。
(日本の競争力ランキング)
今日の財政悪化の最大要因は、バブル崩壊後のマクロ経済政策として、毎年多額の赤字国債を発行し、需要の創出を狙ったのですが、結果は経済活動は活性化せずに膨大な財政赤字だけが残ったのです。特に橋本内閣の後を受けた小渕内閣のときには、財政が一気に悪化し「大借金を残した首相だ」と小渕首相が自ら述懐しました。時代は「非ケインズ効果」の経済環境に変わっていたのに、過去成功したケインズ経済政策の踏襲で対応したこと、それが失敗の一大要因でした。時代の変化を気づかなかったのです。
その日本経済がよくなったのはつい最近です。長いこと苦しみました。よくなった要因の第一は企業の利益向上です。大企業中心にリストラを行って、自らの経営体質を強化し、利益が確保できるようになり、その結果として設備投資が活発化し、日本経済全体に好影響を与えたのです。勿論、米中への輸出増加という効果があったことも大きい要因ですが、基本的には企業自らの経営努力で経営改善し、その結果としてGDP成長に貢献したのです。
更に、日本企業が強くなった背景には情報収集力と調査企画力の向上もあります。輸出企業が外国との競争で弱いところを克服していったのです。80年代、日本企業の強さは何であったか。それは品質と納期の正確さでしたが、弱かったのは情報収集力と調査企画力でした。それを克服したことも日本の企業が変化し全体の国際競争力を上げた理由です。
その変化実態は外国調査機関の評価が示しています。毎年開催されているダボス会議での、国際競争力ランキングがその変化を物語っています。日本は80年代の好調により、93年までは競争力ランキング第一位でした。ところが94年は第三位、95年は第四位、2000年には一気に第二十一位と没落しました。2001年も二十一位でした。このときは世界から日本はもう沈んだともいわれたのですが、しかし、2004年には第九位に上昇しました。主な理由は企業利益向上によるものです。企業の努力改善というミクロの変化で、国全体のマクロの競争力ランキングを上げ得ることができたのです。
(ミクロの変化でマクロを変える)
インタ−ネットのおかげで必要な情報の殆どは机の上で入手できます。それも質的に揃った内容を無料で受け取れるのです。ということは世界中の人が求めようとするならば、同じ内容と質の情報が一斉に同時に手に入れられるのです。多くの人が瞬時に平等に獲得できるのが現代の情報です。ですから、問題は簡単に認識できる状態にあります。ところが、人の行動の結果には大きな差が生じているのです。
温泉偽装表示問題を認識していても、蔵王のホテルのように47年前の温泉分析書のままでは観光立国は難しいと思います。喜多方が高山を上回る観光客を受け入れるには、住民の身近な清潔度意識を高めないと難しいと思います。日本の膨大な財政赤字改善には奇策ではない真っ当な財政再建政策を採ることしかありません。2005年にこれらの改革大変化を求めるためには、いずれも現場におけるミクロ視点の一歩から改善することが前提条件です。
これは2005年に大変化を求めようとする個人にも、当然、当てはまることです。以上。
2004年03月25日
ブランド力
YAMAMOTO・レタ−
環境×文化×経済 山本紀久雄
2004年3月20日 ブランド力
パリ出張のため3月5日レタ−は休刊いたしました。
地下鉄から地上に出て、凱旋門を背にシャンゼリゼ大通りをコンコルド広場方向に眼を向けると、ちょっと違和感を感じ、改めて周りをウオッチングしてみると、右側の最も凱旋門に近い場所に、今までシャンゼリゼでは見かけなかった新業態店らしき店があります。
入り口に立ってみると「publicis drugstore」(ピュヴリウシス ドラックストア)と看板にあります。publicisは広告代理店名ですが、この企業がドラックストアを経営しているのです。ドラックストアという名前から薬や化粧品を含め、日本でみるマツモトキヨシのような業態店を想像すると大違いです。
シャンゼリゼ大通りに、マツモトキヨシのような店が出現するようではイメ−ジが壊れます。といってもシャンゼリゼ大通りにもス−パ−がありますので、日本のドラックストアが進出してもおかしなことはないわけですが、凱旋門の前にオ−プンしたドラックストアは日本とは大きく異なっていました。
道路に面したスペ−スは軽食・喫茶サロンとなっています。座ると背景に凱旋門が映って、観光客が喜ぶ撮影シ−ンが現実化しています。サロンの向かい側、そこは入り口の右側ですが、そこのガラス壁一杯に今日の新聞が貼ってあります。世界中の新聞です。日経と朝日もありますので、そこで一面を読むことができます。新聞のガラス越しの向こう側は書籍・雑誌の売り場です。
真ん中を通っている通路はなだらかな上り坂曲線で、その緩やかな山道感覚の通路の奥には、左側にワインがあり、その向かい側に薬と化粧品があって、一番奥にコンビニともいえる軽食・飲物売り場が広がっていて、コンビニの向うはシャンゼリゼの裏通りに通り抜けできるようになっています。各売り場はそれぞれが区分けされた部屋別コ−ナ−売り場となって、異なった別の店が集まっている雰囲気を漂わせていて、さすがにフランスらしいと思う前に、この店が24時間営業であること、これには本当にビックリしました。
このドラックストアからもう少しシャンゼリゼ大通りを降りていくと、世界に冠たるブランドであるルイ・ヴィトンの直営店があります。外側の壁に「150周年」と大きくPR看板が派手に掲げられ、入り口に相変わらず東洋系の人が並んで、店内に入る順番を待っています。今時、入り口に並ぶ店はルイ・ヴィトンだけでしょう。それだけブランドの力を評価されているのですが、日本のオリジナル製品でルイ・ヴィトンに匹敵する世界的ブランドとなっている事例はあるでしょうか。どういう理由でルイ・ヴィトンが世界のブランドとして評価されているのか。その明確な理由を解説できるほど分析しておりませんが、確かにブランド力という摩訶不思議な存在は絶大な力を持っている事実を、ルイ・ヴィトンが証明しています。
パリでは2月28日から農業祭が始まりました。初日はシラク大統領も会場に訪れ、午前中の3時間を会場で過ごし「シラクは朝食をとらずに農業祭に来た」とTVニュ−スでシラク大統領が試食・試飲している姿、それが報道されるほどに農業祭は人気があります。
19世紀からずっと続いていて、今回は113回目ですが、とにかく会場は人で埋まります。外は零下の寒さですが、会場内はコ−トも上着も脱ぎたくなるほどの人出です。普通の一般の人が、各産業の生産者が直接商品展示をするコ−ナ−を回って歩くのです。
農業祭という名前から想像するのは、農産物だけと思いますが、実は魚介類からトラクタ−類の機械、衣服、ワイン、菓子、フアッション製品、外国からの特産品参加、それと最大の見世物は動物です。牛、馬、豚、羊、アヒル、ダチョウ、犬までいます。牛や豚は日本ではみたことがない巨大なボディで、それが会場内を移動するため人間と同じところを歩くので、その臭いと人間の体臭とが重なって、異常な熱気となります。
日本でも展示会が盛んに行なわれていますが、それは各業種別のものが多く、全産業が揃う展示会はないと思います。パリの農業祭は生産者が中間業者である店を通さずに直接に消費者と会うという展示会なのです。そのような生産者と消費者がダイレクトに触れ合い、意見交換が行われるということか毎年開催され、すでに113年間続いているという事実、それをどのように解釈したらよいのか。そのところを会場内の熱気と、ワインの試飲酔いでフラフラになって、巨大牛のショウをみながら考えてしまいました。
先日、日本海に浮かぶある島を訪ねました。美しい景観で穏やかな人たちがゆったりと住んでいて、このような環境で生活したら安全・安心感がある生活ができると思いました。
この島の行政の方からいろいろうかがうことができた機会に「この島の産業は何でしょうか」とお聞きしますと「漁業が一番で次は土木建築業です」という答えに、一瞬戸惑いを感じました。狭い島の産業、その第二が土木建築であり、その土木建築の発注元は公共事業なのだという補足説明に、ますます困惑の気持ちとなりました。
日本が成長してきた仕組み、それにはいろいろあるでしょうが、その重要な政策の一つとして明治時代から採られてきたのは「政府が税金などの資源を集中的に管理し、それを全国に再配分する経済政策をとることにより、全国を格差なく平等に国民生活の向上を図る」というものであったと思います。この経済政策は見事に成功し、1980年代には日本中をバブル経済に浮かれさすまでにし、世界第二の経済大国に成長させました。
しかし、この仕組みは国家全体の税金収入が順調に入ってきて、インフレが持続する時代には有効でしたが、税収が減り、デフレとなり、官の体制はバブル期と同じ膨れたままでは、必然的に膨大な借金国債発行による国家経営となって、今までどおりの全国再配分政策は難しくなってきているところに、人口減という直近未来現実が訪れているのですから、穏やかな島でも当然公共事業は減少していくことになります。
したがって、今まで政府財政政策に頼って経営していた土木建築業界は、当然、受注が減って、経営が厳しくなっているのです。これは、この島だけの問題だけでなく、日本全体に共通したことで、今までの経営のやり方を変えていかねばならない、ということを示唆しています。
では、どうするか。それは政府という発注元からの需要が少なくなるのですから、年々減少する受注額に対応できるようにリストラをするか、政府に変わる得意先を探すかという二つの手段しかありえません。つまり、厳しいリストラをするか、新しい得意先を獲得するかということになりますが、仮にリストラという方法を選び、一時的な経営対応をとったとしても、長期的に政府支出は減少していく国家財政の現状から、公共工事に頼る経営は年々難しくなっていくことになるので、必然的に新しい得意先を開拓するという方法を取らざるを得なくなって行くと思います。ところが、この新しい得意先の獲得という方法は簡単にはできないので、経営状態が厳しい企業が多くなっているのです。
このことは日本という国の問題として考えてみても分かります。現在、政府は「外国人観光客増加」ということを方針にし、それを受けて東京都は観光案内所を100ヵ所新設するという計画を打ち出しています。東京都に観光案内所が3ヵ所しかないというのですから当然の対策ですが、この程度では大きく観光客増加は難しいと思います。何故なら、根本的な視点が欠けているからです。
外国人に日本にきて貰うということは、新しい顧客の開拓と同じなのです。今までは政府が国家財政の再配分という政策で成長してきた仕組みを、リストラも絡めながら新しい顧客の獲得という仕組みにつくりかえなければならないのです。
そのためには根本的な視点の検討が必要です。それは、日本という国のブランド内容、それがどうなっているのか、という視点です。多くの外国人が「日本に行きたい」という意思が弱いから、結果的に観光客が少ないのです。「行きたい」と思わせるような「日本ブランド力」をつけること、これが何よりも先行する課題です。
フランスを訪れる外国人は日本の10倍以上です。その差が何故生れたか。それは、過去とってきた政策の差、例えば生産者と消費者が一堂に会する接点を100年以上続けた仕組みと、1ヵ所にお金を集め上から効率的に流していくことを100年以上続けた仕組み、つまり、多くの異なった分野の人と擦り合せできる場を持っていたか、という差が大きいのではないか。それが農業祭のワイン試飲で酔い過ぎて辿りついた結論でした。以上。
2004年03月07日
日本人は不安民族
YAMAMOTO・レタ-
環境×文化×経済 山本紀久雄
2004年2月20日 日本人は不安感民族
「鉄舟・21・サロン」のホ-ムペ-ジを2月15日オ-プンしました。一昨年の夏、荒川区町屋に世界で始めてのぬりえ専門美術館として「ぬりえ美術館」が開館されたのを機会に、同美術館のサロン活動の一環として、山岡鉄舟を研究する会を「鉄舟・21・サロン」として毎月開催してまいりましたが、ようやくホ-ムペ-ジをオ-プンできるところまで辿り着くことができました。(http://www.tessyuu.jp)
ホ-ムペ-ジは誰でもプロに依頼すれば出来ますが、そのためには資金が必要です。その資金が「鉄舟・21・サロン」にはありませんでした。ゼロ預金から始めたのです。サロン参加者は当初数人でした。そのうち真面目な内容が評価され、口コミで広がりまして、最近はぬりえ美術館の1階ホ-ルが満員盛況になるほどの参加人数となってきました。
ホ-ムペ-ジの作成資金は、毎月の参加者からいただく会費を積み立ててまいりまして、時間はかかりましたが今回のオ-プンとなったわけです。1年6か月かかりました。
山岡鉄舟研究の専門家で著書もある佐藤寛氏からは、現在、日本で鉄舟研究会を毎月開催しているところは、この「鉄舟・21・サロン」しかないだろうといわれ、その言葉も励みになりました。鉄舟に関心あるファンは、男女・年齢・地域を超えて全国各地におられます。
今後は鉄舟にご関心ある方にホ-ムペ-ジでご連絡でき、とても楽しみにしております。
その鉄舟は、多くの偉人・先達とともに明治維新という大革命を成し遂げ、大混乱状態から日本を現代の近代国家にするための基礎を構築して来たのですが、その大混乱の明治維新時代と同じように大変革期にあるのが、現在の日本です。
日本経済の回復について、政府は中期的経済財政見通しを「改革と展望-2003年度改定」として目標を明示し閣議決定しています。それによりますと2006年度に名目2%成長を達成し、国と地方の基礎的な財政収支(プライマリ-バランス)を2013年度に黒字化する、という内容です。また、それに向かう年度としての2003年10月から12月の実質成長率実績は1.7%になったと2月18日に発表されましたが、これは13年半ぶりの高い成長率であり、年率換算では7.0%となりますから、これで2003年度の政府見通しはほぼ確実になったといえる状況にあります。
この政府見通しと今年の実績を信用すれば、日本はバブル崩壊後の後処理で失敗した政策の、その後始末としての改革を着実に行っていくことによって、日本経済は心配ない状態に持っていくというスト-リ-になります。しかし、多くの経済専門家はこの政府見通しについて懐疑的にみて、異なった見解を発表しています。
その懐疑的見解として、近いうちに「預金封鎖」が実施されるだろうという一方の主張、もう一方として「ハイパ-インフレ」が日本を襲うという主張があります。いずれもそれなりに検討した根拠があり成るほどと思いますし、そうなれば日本経済は大混乱状態に陥ることになりますので、それを心配する多くの人が「大いなる不安」を持っているのが事実です。
いったい「不安」とはどういう心理状態を指すのでしょうか。広辞苑では「安心できないこと。気がかりなさま」とあります。そのとおりですが、心理学的にもうちょっと定義づけしますと「不安とは、未来に直面する課題があるのだが、その課題がどちらかというと明確でなく、しっかりとした対処をできないでいる感情」となります。
恐怖とは異なります。恐怖とは「対象がハッキリしていて、外的要因が強い」のですが、不安は「対象が恐怖に比べてボンヤリしていて、内的要因が強い」ことで、日本人はこの不安感情を強く持ちやすい国民性ではないかと、改めて最近感じたことがあります。
現在「日欧温泉文化本」を、フランス語で出版するために翻訳をしている翻訳者から、内容確認・問い合わせ・指摘がある中で、はっと気づいたことがあります。
それは、フランス語に翻訳する過程で「この文章の主語は何ですか」という指摘を受けたことからです。この指摘は一回ではなく、その後も同様の「主語問題」が何回も続いています。つまり、普通に書いている日本語の文章に、フランス人から見ると主語が抜けている、という指摘を継続的に受けているという事実、それを新しい経験として新鮮に受け止めたのです。新しい気づきです。
主語の問題を指摘された当初は「それは文章全体から推察でき、十分に分かるだろう」と思い、そのような回答をしたのですが、よく考え直し、指摘受けた個所を再度見直してみると、確かに主語が明確でなく欠けていることに気づくのです。
主語が抜けている日本語文章、それは私だけでなく日本人が共通している事例であるということを確認してみたいと思います。そこで、日本人なら誰でも知っている著名人作家で、ノ-ベル文学賞を受賞した川端康成氏の名作「雪国」で事例検討してみます。
同氏の名作「雪国」は「国境の長いトンネルを抜けると雪国だった」で始まります。この文節は日本人ならば殆どの人が暗記しているほど知られています。ということは、この雪国の始まり文節を何ら疑問に持たず受け入れ、名文として評価しているのが、日本人の共通した考えと思います。また、この文節が日本人の好きな文体として、いろいろな場面で引用される事例が多く、これは日本人好みの文章であるということを証明していると思います。
しかしながら、この文章をよく分析してみますと何かが欠けているのです。それが「主語」なのです。それを端的に指摘したのが、この文章を英文に翻訳したものです。
著名な翻訳家が英文化し、世界に紹介され、その結果として川端康成氏はノ-ベル文学賞を受賞したのですが、その英文の「雪国」の始まり文節には、「BY TRAIN」という言葉が付け加わっています。
つまり、「列車で、国境の長いトンネルを抜けると雪国だった」と、翻訳では「列車で」が加わっているのです。日本人にとっては、「列車で」といわなくても、文脈から当たり前の理解がなされるという前提から、「列車で」という主語は省かれていて、その省かれたことによって「名文」と評価されていると思います。
仮に、この「雪国」の始まりを「列車で」という文章をいれてから、川端康成氏が書いたとすると、「雪国」は同氏の代表作になりえたかどうか、その疑問さえ生じる個所と思われるほど、「雪国」の出だし文章は重要ですが、その重要な始まり部分を英文に翻訳するためには、主語としての「BY TRAIN」がどうしても必要だったのです。
文体を構成する中に主語が抜けている、という指摘は重要です。主語がない文章を読むということはどのような結果となるのでしょうか。
それは文章を読む人の解釈に任せるということになり、読み手によってどうにでもとれるということになり、読む人の主観で理解内容が変化させられます。これは一見、弾力的ともいえなくありませんが、内容解釈が多様ということは明確さに欠け、曖昧さが多いことになって、主語として主張するものがボンヤリしやすいのです。したがって、主語がない文章は「課題が明確でないことから、しっかりした対処ができない」という、前述した心理学的にいうと「不安定」な感覚の多い文章となりやすいのです。
文章を書くということは、その人の考え方を表現することですので、主語がない文章を書き慣れている日本人とは、物事を曖昧にしやすく、曖昧さは不安感を醸成することに結びつきやすく、日本人は不安感を持ちやすい民族といえます。
その不安感を持ちやすい日本人に、バブル崩壊以後の長期経済低迷時代が訪れたのですから、本当に不安感に満ちた国民になってしまったのです。1965年(昭和40年)自殺者は1.5万人でした。今はここ五年間ずっと二倍以上の3万人を超えている自殺者数は、この不安感という曲者が大きく影響していると思います。
しかし、よく考えてみれば、不安は不安です。不安とは「課題が明確でないことから、しっかりした対処ができない」ことから発生した感情ですから、まだ問題が具体化していない前の感情なのです。まだ具体的な恐怖になっていないのですから、不安と思う感情が生じたら「それは、まだ現実問題ではない」という事実に立ち戻ってみる、という思考が必要で、その思考習慣をつけることが大事です。が、もっと不安感を無くすために必要不可欠なことは、日頃から「主語を明確にする文章を書く習慣」をつけることであると思います。
「鉄舟・21・サロン」のホ-ムペ-ジを、ゼロから18か月かけて開設できましたので、次のステップに入ります。「鉄舟・21・サロン」は研究会・勉強会ですから、その主語としての目的は「研究内容の深さ追求」が絶対必要条件です。そのためには、山岡鉄舟の何を研究し、その結果を何に反映するのか、という目的を明確にすること、つまり、主語を曖昧にしないことが大事であると、フランスからの指摘で改めて考えているところです。以上。


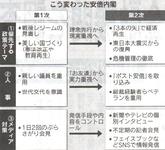

-thumb.jpg)